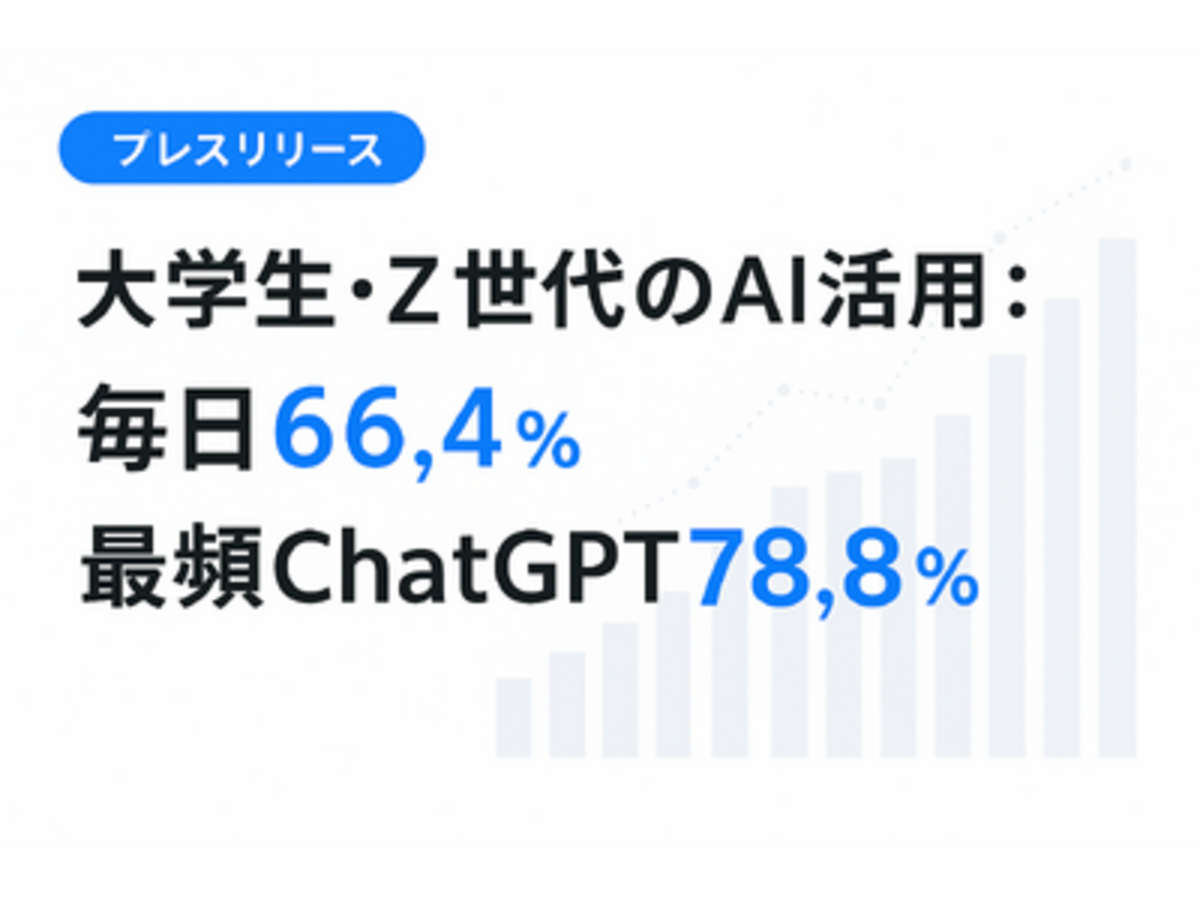マイカー広告は、熱いうちに打て。街中の「運転席」をナラティブ発生装置に変える新メディアの威力とは
スマホやテレビなど、スクリーンからの情報摂取が大幅に増えている昨今、改めて街中など「リアル」な場でのコミュニケーションを可能にするOOH(Out Of Home=屋外広告メディア)の存在感が高まっています。
その背景には、デジタル化の進展で新聞・雑誌などの「紙媒体」が減少し、メディアミックスの候補としてOOHが際立ってきていることがあります。スクリーンで見た情報に、オフラインのリアル空間で改めて接触し直すことでブランドの存在感・臨場感を一気に高める効果が期待されています。
エレベーター広告やタクシー広告など、今改めて注目されるOOHには新たな広告チャネルも続々と台頭しており、屋外における「視線」の奪い合い戦争が加熱しています。
そんな中、今最も注目を集めている新メディアの一つが、マイカーのリアウィンドウを広告枠とする「マイカー広告」です。

街中の「運転席」をナラティブの発生装置にするマイカー広告
今話題のマイカー広告の領域を開拓し、力強く牽引しているのが「マイカー広告 CheerDrive(チアドライブ)」です。2021年3月にリリースされたばかりでまだ珍しいこともあり、後続車両はもちろん道行く歩行者も「ナニコレ?」と注目し、話題を集めています。
現在の屋外での「視線」の争奪戦で重視されているのは、リーチ人数などの「量」よりも、注視せざるを得ない状況で注目させることによる接触の「質」のほう。一日の生活動線のなかで、人々が視線を持て余すタイミングを捉えて「思わず見入ってしまう」広告メッセージを送れるメディアが求められています。
やり場のない視線のやり場となるエレベータ―広告は、この意味でまさに絶妙の広告スポットといえますが、すし詰め状態なので会話が生まれづらいという弱点もあります。
一方、マイカー広告は接触したら即会話のネタになります。そもそもドライブの一番の楽しみは景色を見ながらの「会話」なので、搭乗者は常に街をキョロキョロと見渡して話題を探しています。だから必然、マイカー広告を見た後続車両の運転席はその話題でもちきりになります。
ブランドから生活者に一方的に語りかける「ブランドストーリー」ではなく、日常会話のなかで生活者の口の端に自然とのぼる「ナラティブ」が今後は重要だといわれています。マイカー広告は、街中の運転席をナラティブの発生装置に変える画期的なメディアといえます。
街の「視線」をひとりじめ

車社会の日本においては、都市でも地方でも街の中心は「道路」。チアドライブでクルマに広告を出すことは、街のど真ん中のスペースに広告を掲出するということです。
また、新しい広告枠はそれだけで注目を集めやすいので、今は街の視線を一手に浴びるチャンスです。今やすっかり「バナーブラインドネス」状態で無視されるWebのバナー広告も、登場した頃は皆が注目し、クリック率が1%を超えるケースも珍しくありませんでした。
街の視線が集まるのはもちろん、マイカー広告の一番のオーディエンスは「後続車両の運転席」です。走行中も目に入りますし、信号待ちの度に至近距離で1分前後、アテンションをひとりじめできます。
応援してくれるファンを「推し返す」

マイカー広告の効果は、実は「2階建て」になっています。道行く人への露出効果はもちろんですが、それに加えて広告を背負って走るドライバー自身のファン化効果も見逃せません。
ドライバーは広告したいブランドを自ら選び、立候補して愛車に掲出する仕組みになっています。つまり「チアドライブ」という名の通り、ドライバー自身がブランドの応援団長になる広告メディアなのです。
広告を貼って駐車場に停めていると、他のドライバー達から広告ステッカーについて尋ねられることも多数。協力ドライバーに調査したところ、30日間のキャンペーン期間中に約6割のドライバーが5人以上に広告について聞かれ、多い人は20人以上に聞かれることも。

広告を背負って走るドライバー自身が最強のスポークスマンとなり、他人に熱く語るうちにさらにファン度を高めていきます。一方で通行人や周囲の人々は、他者(=ドライバー)を介して認知することで、行動経済学でいうところの「ウィンザー効果」が働き、信頼感や確信がさらに増すという構造です。
また、広告収益の一部は協力費としてドライバーにポイント還元されます。概ね走行したガソリン代の半額程度をポイントで賄うことができるため、ガソリン代が高騰して家計を圧迫する今の世相にも合った仕組み。応援してくれるファンを、燃料費支援で「推し返す」ことができるメディアであるともいえるでしょう。
「おでかけ」といえば、お買い物

一般的な広告のパーチェスファネルで考えると、認知から購買までには長いプロセスがあります。しかしマイカー広告の場合、広告接触者=ドライバーや歩行者は既に「家から出ている」状態。おでかけといえばショッピングなので、そのまま「購買行動」につながりやすい構造を持っています。
また、購買行動直前に接触することで選好度を上げる「リーセンシー効果」も狙えます。たとえば飲食店のフランチャイズであれば、お腹がすいてきたタイミングで前のクルマの美味しそうなハンバーガーを見て、たまらずドライブスルーへ、といった流れを作れます。
さらに、上記画像のラーメン屋・どうとんぼり神座の事例のように、クーポンを背負って街を走らせることも可能。新しいメディアなので、自社ならではのコミュニケーションアイデアを考えるのも面白そうです。
マイカー広告は、熱いうちに打て。
質・量ともに高いリーチがとれるマイカー広告「チアドライブ」ですが、2021年にリリースされたばかりのHOTなサービス。2023年にリアウィンドウの広告を見かけた前澤友作氏が自身のファンドを通しての出資を行うなど、まさに今大きく育ちつつある新メディアです。
街角の接触者からのアテンションが高いのはもちろん、リアウィンドウの広告を写真に撮ってのSNSバズの拡散が起こりやすいタイミングでもあります。また現在はニュースバリューも非常に高く、地上波テレビ局をはじめ様々なメディアで取り上げられているため、思わぬ露出効果も期待できます。

マイカー広告「チアドライブ」の実力
ドライバーの登録者数は2023年の4月の段階では2万人超でしたが、前澤ファンドの出資やメディア/クチコミの話題化などで一気に拡大し、現在は約10万人規模に。今後も大きな伸びが期待できます。
チアドライブを支えるドライバーは、都区部だけでなく全国で募集しています。ドライバーの居住地ベースで【都道府県・市区町村単位】で指定できるため精緻なエリアターゲティングも可能。

認知効果についても確かなものがあります。東京都内で30日間、500台の車両に広告を掲出した上でターゲットである20-60歳男女10,000人にアンケート調査を実施したところ、その広告主のステッカー広告を見たと答えた人の割合は12%に。1ヶ月で実に90万人以上の認知を獲得しました。
実施費用は税別30万円からで、この金額で30台の自動車に30日間の掲出が可能。1台ごとに1万円追加すれば自由に出稿規模が調整可能になっています。もちろん費用の中に印刷・配送費やドライバーへのお礼も含まれています。1台あたり平均、都市部で800km・地方郊外で1,000km走行するので、15,000-20,000人の目に触れることになります。
ドライバーが実走したかどうかの成果確認はどうするのか?途中でステッカーを剥がされないか?ドライバーは後方確認はできるのか?など、新しいメディアだからこそ様々な疑問が湧いてきますが、詳細が気になる方は「チアドライブ」のサイトで詳細をチェック。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- バナー
- バナーとは、ホームページ上で他のホームページを紹介する役割を持つ画像ファイルです。画像にリンクを貼り、クリックするとジャンプできるような仕組みになっています。画像サイズの規定はありませんが、88×31ピクセルや234×60ピクセルが一般的です。また、静止画像だけでなく、アニメーションを用いたバナーもあります。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他