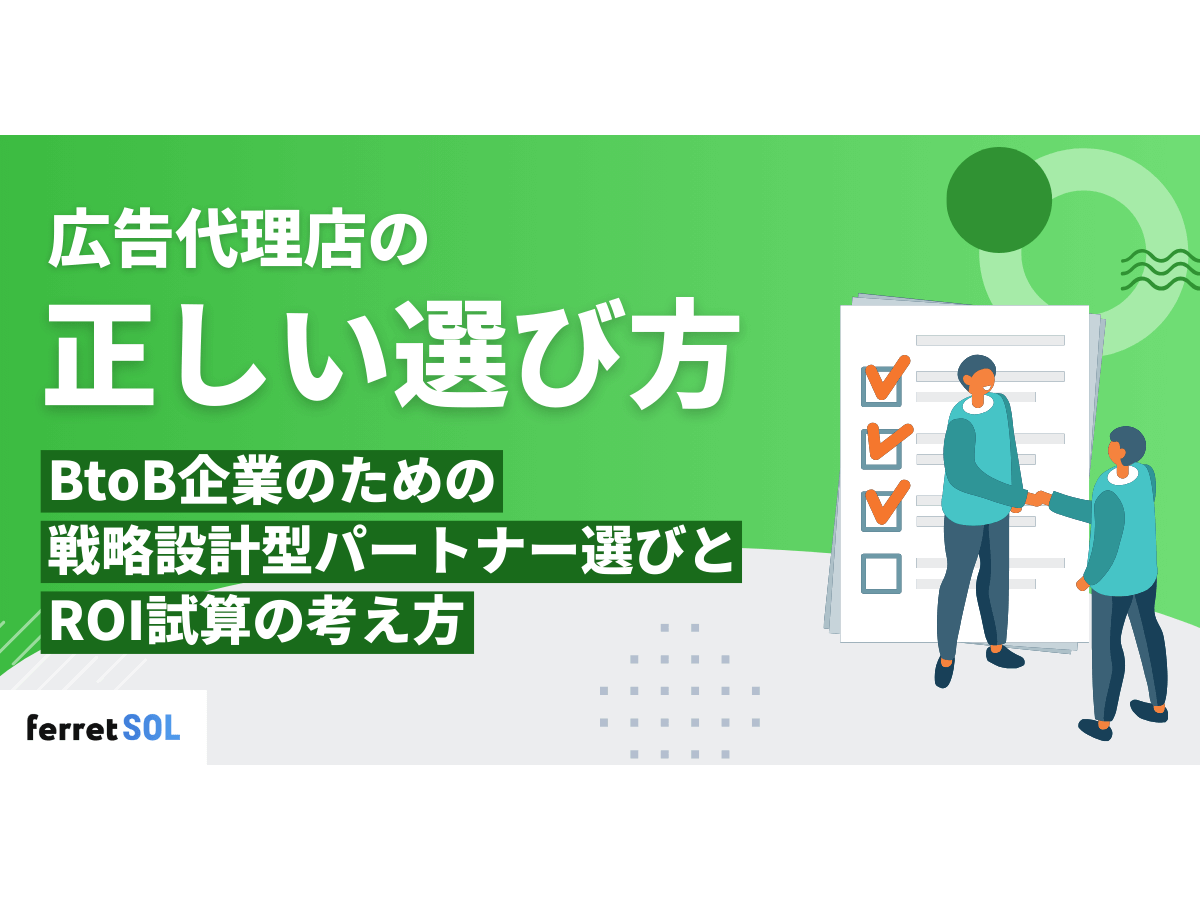田原総一郎氏・土屋敏夫氏・夏野剛氏がテレビとネットメディアの未来を語る-INNOVATION WORLD FESTA 2016-
5月14日、国際サミットG7の前夜祭として筑波大学で開催された「INNOVATION WORLD FESTA 2016」内で、ジャーナリスト田原総一郎氏、電波少年など多くのヒット番組を生み出したTVプロデューサー土屋敏夫氏、imodeの生みの親であり、現在多数のIT企業の取締役を務める夏野剛氏らによるトークセッションが行われました。
今回は、「メディアの革命」をテーマに交わされた議論の様子をお届けします。
昔に比べてテレビはつまらなくなった?
田原氏:なんで、電波少年みたいなアポなしでロケをする番組が今はないの?
土屋氏:なんででしょうね。
もともとテレビってアポイントとってロケに行くものなんですが、アポなしでやったら面白いんじゃないかと思いつきでやったら受けたんですよね。
猿岩石のヒッチハイクの時とか、視聴者は感動したいと思ってゴールシーンを見るんですよね。
で、ゴールした時に「次はアメリカ横断です」って発表した瞬間、局に抗議電話が1,000本きました。
この記録はテレビ業界で抜かれてないんじゃないですかね(笑)
田原氏:今抗議電話が1,000本きたらすぐ放送中止になって、最悪クビですよ。なぜ電波少年は放送中止にならなかったんですか?
土屋氏:僕は確信犯でやってたし、視聴率もよかったですしね。
その時は抗議くるだろうと思って、普段は電話対応10人のところ100人用意してましたからね。
テレビって、想像をこえるから面白いんですよ。観てないと何をするかわからないのがテレビの面白さ。それが今ないのはやばいかなと思います。
田原氏:夏野さんは?今のテレビどう見てる?
夏野氏:「問題起こらないように問題起こらないように」と言う意識は感じますね。
僕が出ている番組で、「こういうこと言わないでください」って言われたこと今までなかったんですよね。
でもそれが最近言われたことがあって。某アイドルグループの解散騒動の時に、「事務所の名前は出すな」と。「出したら私の首が飛ぶ」とみんな言うんですよね。
それは、面白い番組を作りたくないんじゃなくて、自分の職が危ないということを優先的に考えてるんだなと。
土屋氏:まあテレビって視聴率ですから。視聴率を取るビジネスモデルに貢献していればいろんなことができるんですよね。
テレビの面白いところが、作ってる人間と見てる人間がすごく近いから、視聴者の反応が良ければ続けていけるんですよね。
夏野氏:見る方にも問題があると思いますけどね。
熊本地震の時に、バラエティ流すのは問題だとか、楽しそうな写真あげてるんじゃないとか騒ぐ人もいました。
不謹慎だということを追求することに喜びを感じるんでしょうね。
土屋氏:そうですね、絶対正義というか、誰も文句を言えない正義を振りかざすことを良しとする人は多いですよね。
テレビの信頼度は高い?低い?
田原氏:テレビは今偏向報道していると言われているけど、このまま続くとなると電波停止しなきゃいけないかも。
夏野氏:ニコニコ動画で、この前中国の全人代(http://jp.reuters.com/article/china-parliament-idJPKCN0W804I) を生中継したんですよね。史上初で。
ネットって右寄りと言われてますよね。実際は右寄りじゃないんですけど、右の主張の声が大きくて。
ただ、我々は特に右も左もない。中国の全人代を中継したからといって、我々が中国に共鳴してるわけじゃないんです。チャンスがあったからやっただけなんですよね。
僕が1つ思うのは、テレビ用に作ったコンテンツはテレビに、ネットはネットにっていう考え方はもう古いんじゃないかと。
面白いコンテンツを作って、それに最適なメディアを選べばいい。
ニュースとジャーナリズムの境界線
田原氏:夏野さんはネットとテレビで話し方変えますか?
夏野氏:変えますね。ネットは尺が長いから、きちんと説明できる。
逆にテレビはワンセンテンスしか言えないから誤解されやすい。
こちらが偏ったことを言ってなくても、意図通り伝わらない場合が多い。
ただ、僕が出てるバラエティ番組は政治経済ネタはほとんどやらないです。
視聴者が関心がないから。安倍さんの話もしばらくやってないですね。
土屋氏:この場だからこそ是非お聞きしたかったんですが、「テレビジャーナリズム」と「ニュース」は分けて考えなきゃいけないのかなと。
テレビジャーナリズムは権力の監視などやらなきゃいけないことがある。
一方でニュースは、例えばベッキーの不倫問題がトップにあるわけじゃないですか。
ニュースは、みんな関心があるであろうことをテレビ側がチョイスしている。
それとテレビジャーナリズムは別だと思うんですよね。
田原氏:その2つって分けられるかな?
土屋氏:区分をどうするかという問題はあるけど、例えばジャーナリズムはこの番組、ニュースはこの番組というようにどうにかして分けた方が、テレビジャーナリズムとしてやるべきことが見えてくるんじゃないかなと思います。
ニュースでいうと、例えばSNSとかで、彼氏が今日何を食べたとかも個人にとってはニュースになりますよね。
そういうことを踏まえた上で、テレビ、ネット、雑誌それぞれのジャーナリズムを考えるべきです。
夏野氏:僕はジャーナリズムはジャーナリズムとして、テレビだろうがネットだろうが関係なく1つで扱った方がいいと思いますけどね。
メディアによって特性はありますよ、映像の有無とかね。でも日本の場合、新聞とテレビが対になっていますし、そういう意味ではメディアごとに分ける必要はないと思いますけどね。
田原氏:でもセットになっているテレビ局と新聞社が同じ意見とは限らない。
例えば、安保関連法についての報道を見ると、テレビは90%反対している。これは偏向しているんじゃないかという見方がある。新聞はおおよそ半々に分かれてバランスが取れている。
土屋氏:読売新聞と日本テレビも意見分かれてますしね。
夏野氏:その反対意見って、テレビ局としての意見ですか?
田原氏:いや、出演しているキャスターですね。
土屋氏:それはキャスターの世代というのもあると思いますけどね。キャスターとしての個性を出すように教育された年代がそういうモードになっているだけで、テレビ局としての意見とは思わない。
夏野氏:メディアは、皆が考えてるであろうことをなるべく鏡のように返すってことを・・・
田原氏:いや返せない。
土屋氏:何が本当の鏡なのかってことですよね。編集して発信するのであれば必ず主観が入るから、鏡のようにそのまま写すということは実はできない。
政治とテレビの関係
夏野氏:政治家は基本的に浮世離れしていますよね。
いまだに国民全員がテレビを見ていると勘違いしています。
田原氏:テレビは、安保関連法に90%反対している。でも、安倍内閣は選挙3回やって全部勝っている。テレビが安保法を批判しても批判しても安倍内閣が勝つというのはテレビが軽んじられているということかな。
夏野氏:日本は昔から、政策によって選択するアジェンダ選挙じゃなくて、昔から知っている政治家に入れるような流れになってる。特に投票率の高い年代の方がそういう傾向にある。だから、政策に対する世論調査の結果が選挙に反映されない。
土屋氏:いまでも、世論調査やると安保反対の方が多いと思いますね。
夏野氏:テレビの番組に対して意見が出てくるというのは、まだ信頼感がある証拠なんですよね。
テレビに、間違ったことを言う人が出るはずがないという。そこは守んなきゃいけないですよね。
土屋氏:対論として、ネットは全く根拠のないことをもっともらしく言う言説が出てきてしまう。そういう意味ではネットよりテレビの方が信頼できると。
田原氏:夏野さんはテレビは短いからちゃんとしたことが言えないけど、ネットはちゃんと言える。それならネットの方が信頼高いことになるのでは?
土屋氏:夏野さんウォッチャーからすると、ネットではあんなに過激なのにテレビではおとなしい。絶対にテレビ局から何か言われているに違いないと思っちゃうんですよね。
夏野氏:実際はそうじゃないんですけどね。朝生なら長いから説明できるけど、他の番組は尺が短いからできないというだけで。
地上波とネットの融合
田原氏:土屋さんは、現役時代と管理職になってからは考え方変わった?
土屋氏:全く変わってないです。
実は日テレラボという研究メディアを作ることになりまして。
これからネットメディやVR、AIをテレビに直結するための研究セクションを立ち上げたんですよ。
田原氏:実はこの前私と夏野さんでテレビ朝日とCAで組んでabemaTV出ました。
夏野氏:あの番組はセット含めて朝生(朝まで生討論)そのままでしたよね。
あの番組に関しては、ネットと地上波の境目がなかった。
あれはテレ朝とCAの合弁事業なので、半分テレビの血が入っていて、ああいうことができていけばいいなと。
土屋氏:僕はabemaTVが出たとき、これからテレビが変わるんだなと思いましたね。
テレビのコンテンツがインターネットで配信されるということが自然になっていくなと。
TBSもNHKも日本テレビもやればいいじゃないかと思いますね。
夏野氏:この際ドラマとかも1話だけ先にネットに流して、評判見て続けるか決めるのでもいいんじゃないかなと。これは評判良いから月9に持ってこよう!とかね。
テレビで流したものをネットで流すなんてものでもなくなってきてるんじゃないですかね。
土屋氏:ただ、低いと言われている視聴率10%でも、観ている人は600万人はいるんですよ。
そういうトライアルはいいと思うんですけど・・・
ネットが繋がって、スマホ持ってて当たり前みたいな環境は今後ますます進んでくるからTV局はコンテンツメーカーとしてどうしていくか考えなきゃいけない。
田原氏:せっかくだから、会場の方に聞いてみますか。今のテレビは面白くないと思う人?
(会場の8割挙手)
土屋氏:しまった・・・(笑)
ただ、20年前ぐらいの田原さんがやってたテレビで、今のテレビはつまらない人って会場に聞いたらみんな手を挙げていました(笑)だから、昔はよかった症候群はあまりアテにならないんですよね。
でもテレビの下降は実際あると思うし、そこは真摯に受け止めなきゃいけないなと思います。
- セッション
- Googleアナリティクスは、ホームページに適切に組み込めばアクセス状況を把握できる便利なサービスです。Googleが無料で提供しており、日本でも大手企業や金融機関、政府など、その利用のシェアを広げています。そこで、もっとも基本的な単位がセッションです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他