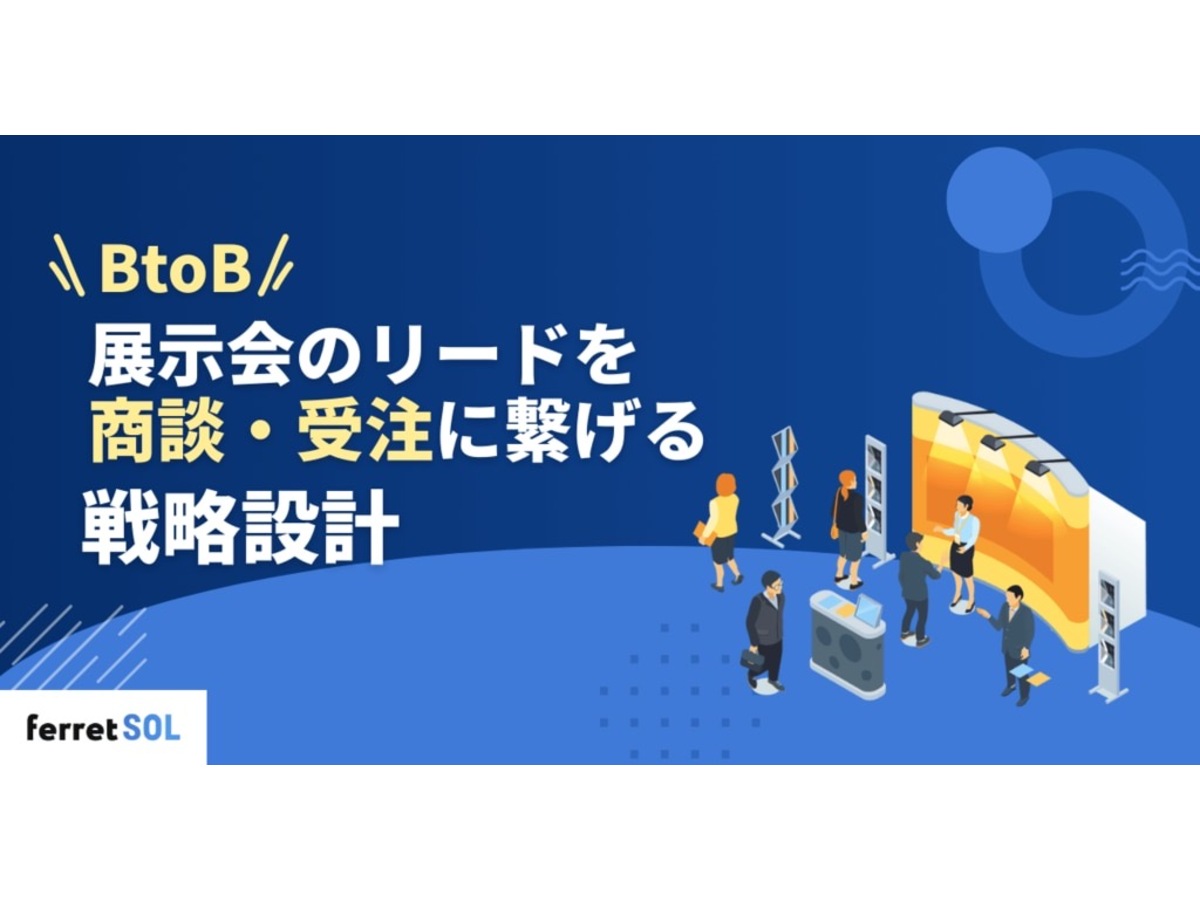競合他社より魅力的に!展示会出展の6つのポイントを解説
自社サービスの営業手段の1つとして、展示会への出展があります。展示会は、来場者にとっても出展者にとっても、あるテーマについて情報収集ができる貴重な場です。来場者と直接顔を合わせ、顧客の生の声を聞くこともできます。
しかし、初めて出展する場合、どのような準備・運営・フォローが必要かわからない方もいらっしゃるのではないでしょうか。しっかりした準備ができていないと、せっかくの機会を最大限活用できない可能性もあります。
今回は、展示会に出展する際の事前準備から事後フォローまでを詳しく解説します。
各企業における展示会出展の目的
巷では、様々な展示会が開催されています。しかし、「上司からの指示で出展することになった」「とりあえずたくさん名刺交換をしよう」など、明確な目的が定まっていない場合も少なくありません。
展示会の出展には、大きくわけて2つの目的があります。
1. 商品やサービスの販売
2. リード(見込み顧客)の獲得
せっかくの貴重な機会を最大限活用するためにも、展示会には目的を明確化して臨みましょう。
下記では、目的に応じて効果的に出展するためのポイントを順番に解説していきます。
展示会の種類
先述で、展示会出展の大枠の目的を理解できたところで、続いて展示会の種類を把握しましょう。
展示会は、複数の企業が出展する「合同展示会」と、1社のみが主催する「主催展示会」にわけられます。その上で、目的に応じて以下の種類に分類できます。
● 展示会の主な種類
1. ビジネス系:販売促進が目的の場合
2. 催事・セール系:展示即売が目的の場合
3. プライベート系:自社の技術や商品のアピールが目的の場合
4. パブリック系:展示販売+会場での情報発信が目的の場合
参考:
展示会にはどんな種類がある?目的で分けよう|サンシャインシティ
1. ビジネス系
主にBtoB向けの販売促進が目的の展示会です。企業担当者は、情報収集や商談を行うために来場します。「商談型」とも呼ばれます。
●事例
・メッセナゴヤ2017
2. 催事・セール系
主にBtoC向けの展示即売が目的の展示会です。顧客と直接その場で商品を売買し、自社商品に対する認知度の向上を図ります。競合他社の商品や売り方も見れるため、リサーチにも使えます。
●事例
・家具インテリアプレミアムバーゲン
・TOKYO OUTLET WEEK
3. プライベート系
主にBtoB向けの1つの企業が主催する展示会です。一般的には大手企業が、自社の技術や商品をアピールするために行います。自社のみの開催なので、テーマや内容を統一できます。
●事例
・Hitachi Social Innovation Forum 2017 TOKYO
・Cybozu Days 2017
4. パブリック系
BtoBもしくはBtoC向けの比較的大規模な展示会です。商品の展示や販売に加え、会場での最新の情報発信が目的です。顧客に対して新商品や最新情報をアピールし、その後のビジネスにつなげます。
●事例
・第45回東京モーターショー2017
・東京ゲームショウ2017
展示会出展のポイント
今回は、前述した種類の中でも「合同」での「ビジネス系」の展示会に出展する場合について解説します。
まずは、展示会出展を決めてから終了後までの流れをまとめました。以下の手順を辿っていきます。それぞれの段階でのコツを掴み、効果的な出展につなげましょう。
● 展示会への出展決定から終了後までの流れ
1. 展示会の目的と戦略を決める
2. 具体的なKPIとKGIを決める
3. 展示会の詳細を決める
4. 集客を行う
5. 当日対応
6. 会期後のフォロー
1. 展示会の目的と戦略を決める
展示会の目的
まず、展示会に出店する目的を明確にしましょう。詳しくは後述しますが、目的が自社の認知度向上なのか、新しい見込み客数なのかによって、打つ施策も変わります。
大まかな予算や投資対効果もある程度予測しておきましょう。
ほかの展示会や競合他社の出展をリサーチ
出展前に、ほかの展示会を見学したり、同じ展示会に出展する競合他社の状況を調べたりすることもオススメです。特に初めて展示会に出展する場合は、テーマや規模が似ている展示会をいくつか見学し、雰囲気や特徴を掴みましょう。
来場者の目線から、訪れたくなるブースや商品のPR方法などをリサーチします。良いブースと悪いブースを比較し、考察すると自社の運営に役立ちます。
2. 具体的なKPI(目標)とKGI(目的)を決める
展示会の目的は、契約(受注)までの流れの中で大きく5つにわけることができます。

1. 企業・ブランド認知
2. サービス認知
3. 顧客情報取得
4. 商談
5. 契約
上記の段階のうち、どこに展示会の目的(KGI)を置くかで、そのための目標(KPI)も変わってきます。例えば「3.顧客情報取得」にKGIを置くのであれば “交換した名刺の枚数”、「4.商談」であれば “着席数・商談数”をKPIとします。
展示会の来場者を予測して決める
展示会の種類や内容によって来場者の属性や目的も異なります。出展予定の展示会にどのような来場者が集まるのか、過去のレポートやほかの出展予定企業などを調べて予測しましょう。
来場者リストがもらえる場合は、個社ごとに戦略やアプローチ方法を考えてもよいでしょう。
3. 展示会の詳細を決める
自社のブースのレイアウトや紹介するサービスの詳細を決めます。
社内で共通したイメージを持てるように、文章化したりデザイン化したりするのがオススメです。詳細を決める過程では、予算や納期なども考慮に入れ、計画的に進めましょう。
展示会で使用する資料の制作も行います。当日は来場者の荷物も増えるため、負担を減らす目的でできるだけデジタル化するのもオススメです。
4. 集客を行う
来場者、もしくは来場予定者に対して、集客のための事前広報を行います。当日のスケジュールや辞任配置、役割分担も決めておきましょう。
5. 当日
笑顔で呼び込み
合同展示会には、競合他社も含め、多くの企業が出展しています。その中で印象付けるためにも、運営メンバーは笑顔で呼び込みを行いましょう。
ブースの入り口で引き止め過ぎたり、同じ来場者と長く話し込んだりするのは避けます。新しい来場者が立ち寄りやすい雰囲気を心掛けます。
客層を掴む
呼び込みを行いながら、来場客を観察して見込み客を見付けます。来場者の流れや属性に応じて、臨機応変に対応することができます。
例えば、人気セミナーの前後は来場者数が増える傾向があるなど、流れをつかめば集客にも活かせます。
会場を回る
ブース前だけではなく、会場を周りながら観察と呼び込みを行うことも有効です。他社のブース前で呼び込むのはマナー違反ですが、資料置き場などで手持ち無沙汰にしている来場者にアプローチできる可能性もあります。
ただ、展示会によって集客や呼び込みのルールが決まっている場合もあるため、事前によく確認しておきましょう。
6. フォロー
展示会終了後は、自社のブースに訪れた来場者のデータを分析します。資料送付やその後のプロモーションなど、見込み顧客に対するフォロー施策を実施します。
当初設定していたKGIとKPIの達成度も測りましょう。上手くいかなかった点がある場合は、出展の記憶が新しいうちに改善点を共有します。
展示会では見込みの高い顧客だけではなく、潜在化している顧客へのフォローと育成も重要です。展示会当日から長期的に期間をとり、見込み客からの受注率を測っておくと、次回の展示会出展の戦略に活かすことができます。
まとめ
展示会は、ニーズの有無にかかわらず、特定のテーマに関心のある多くの顧客と接触できる貴重な機会です。
見込み化していないからこそ、自社のサービスへの忌憚のない意見を聞くこともできます。
出展する際は、目的を明確にして万全の状態で臨みましょう。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoC
- BtoCとは、Business to Consumerの略で、企業と消費者間の取引のことを言います。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoC
- BtoCとは、Business to Consumerの略で、企業と消費者間の取引のことを言います。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- レイアウト
- レイアウトとは、もともと「配置」や「配列」を指す語です。ここでは、「ホームページレイアウト(ウェブレイアウト)」と呼ばれる、ホームページにおけるレイアウトについて説明します。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他