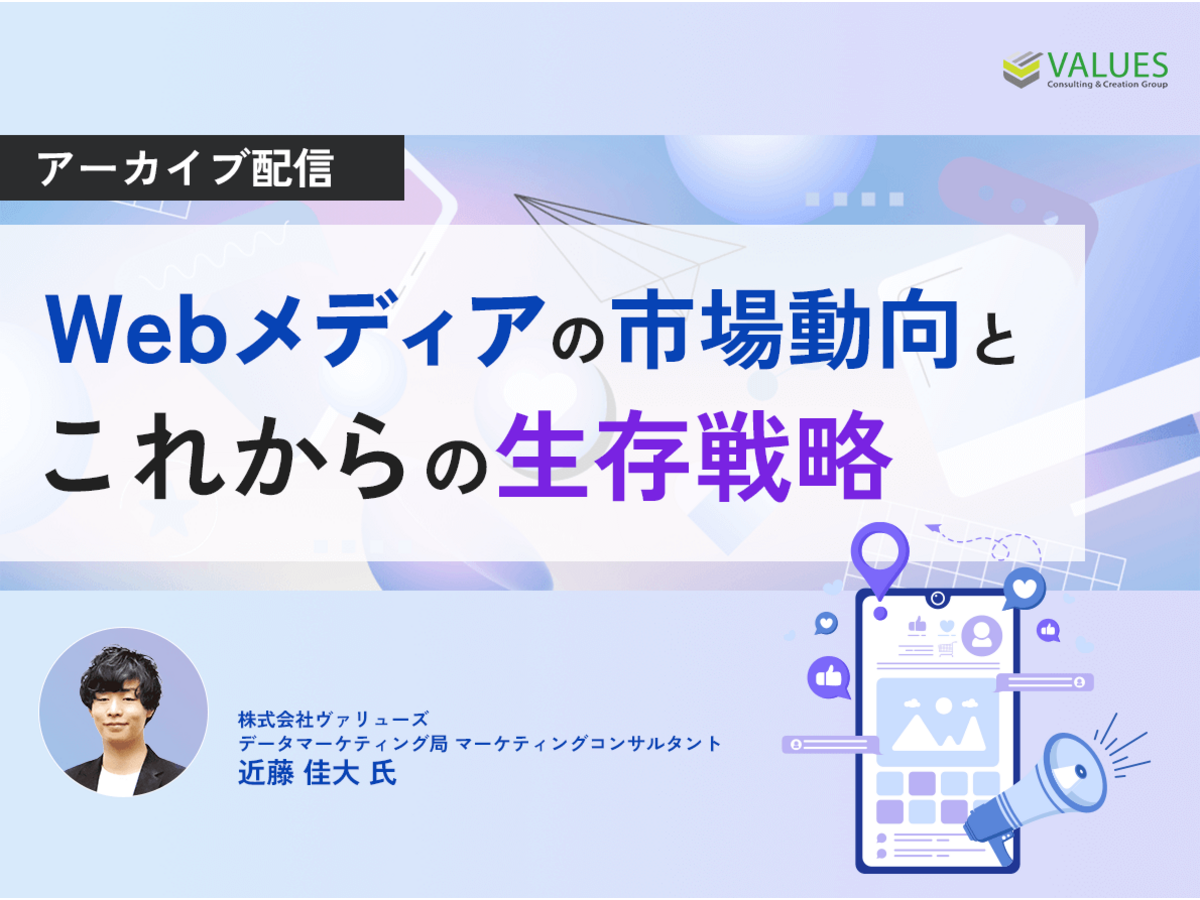【POOL inc. × 老舗革メーカー】旗振り役の「言葉」たちが生む、プロダクトの新しい可能性

「SHARE CHATS」をコンセプトに磁器や革、真鍮などそれぞれ違った質感を持った素材がぴったりとひとつになったコップや、「SHARE GOOD NIGHT」をコンセプトに「おやすみ」を言い合える相手がいる幸せを毎日思い出せる革製のスイッチカバー。
原宿の「WeWork Iceberg (アイスバーグ)」エントランスのカフェスペースにて期間限定で開催された展示会『WHOSE LEATHER_SHARER』会場には、忙しい打ち合わせの合間に足を止め、しばし作品に見入るビジネスパーソンやユニークな革アイテムの数々を物珍しそうに見つめる海外渡航客でにぎわっていました。
姫路の老舗革メーカーの「株式会社 山陽」と、クリエイティブエージェンシー「POOL inc.」による『WHOSE LEATHER』は、革の新しい可能性を切り拓く共同プロジェクト。2018年に続き二回目の展示会開催となった今回は「SHARE」という言葉をキーに、建築家やクラフト職人、アートディレクターなど様々な領域で活躍するクリエイターが「革」という素材を「使い手」の発想で捉えなおした作品が集結しました。

「言葉」を軸に、企画を研ぎ澄ませていく
「SHAREという言葉には、畜産物としての革の恵みをシェアするという意味と、様々な領域のクリエイターの発想をシェアするという二つの意味が込められています」と語るのは、『WHOSE LEATHER』プロジェクト立ち上げから一貫して関わるコピーライターの川見航太氏。畜産に伴って出る牛革は、タンナーと呼ばれる革職人が「価値化」することで新しい命が吹き込まれる。「皮を革にする」適切な処置がなされないと、無駄になるばかりか環境に悪影響を及ぼしてしまうケースもあるのだという。
『WHOSE LEATHER』プロジェクトは毎回、まず「言葉」の設定から始まる。今の世の中の問題意識や空気感と革の接点を突き詰めて、ここしかないという一点の「言葉」に集約できた時、はじめてプロジェクトは動き出す。その言葉を受けて、次はアートディレクターが世界観を立体的に拡張していく。この「言葉と画」のキャッチボールで企画を洗練させていくのが、広告クリエイターならではのプレースタイルだ。
「言葉が出たときには、それを説明するデザインだけはやらないようにしています」と話すのはPOOL inc.のアートディレクター宮内賢治氏。軸となる言葉が定まっているからこそ、発想を振り切ることができる。革といえば高価で、伝統的で、職人的というのは誰でも分かっている。普通はクラフト感あるデザインをやりがちだが、今回はあえて革を革らしく見せないようにツートンの世界観に統一したという。

SHAREの最小単位は『2』。ツートンというフォーマット自体で分かち合うということを表現しながら、色合いによって状況を感じられるようにした。「たとえば革の端切れで秋の落ち葉を表現した『SHARE SEASONS』のピンク色は秋の空を。『SHARE CAMPFIRE』ではアウトドアの気持ちいい空と緑の色です」

メンバーの旗振り役としての「言葉」
「ビジョンクリエイティブを掲げるPOOL inc.では、コンシューマー向けではなくチームメンバーが共通理解を持つために、旗振り役の言葉を立てることはよくあります」と宮内氏。その言葉を指針とすることで、メンバーから多様なアイデアが出た際も判断がブレない。広告では必ず達成しなければならない目的があるので、あえて言葉で枠組みを作ることで「なぜやるのか。それによってクライアントは顧客からどういう存在になれるのか」という視点を持ったまま自由に発想を振り切れる。
「たとえばサントリーオールドの『恋は、遠い日の花火ではない。』というキャンペーンでいえば、ビジョンとなる言葉は『remind』です。僕は"ワンダーワード"と呼んでいるのですが、英単語一語くらいでみんながわくわくドキドキする"言葉の種"を見つけるのがまず最初の仕事です」と川見氏。
当初のアイデアとしては、革のプレゼントボックスをイメージした「GIVER(与える人)」というキーワードも検討していたが、二人にPOOL inc.プロデューサーの内島氏も交えた会話の中で、イメージを限定しすぎず、現代性とつなげられる「SHARER」を導き出した。
宮内氏によると「うまく肉付けができる言葉と、そうでない言葉」があるという。「SHARE」はみんなが語り合いたくなるテーマで、尽きることなく話せる。「限定しすぎずに、発想を広げられる」言葉だ。逆に発想の足かせになってしまうような言葉を軸にしてしまえば、革のベルトや財布というようにいかにも「革」っぽいアイデアの集合になってしまう。
言葉によって軸が決まると、関連する様々な要素が自然と定まってくる。「たとえば会場はWeWorkしかないだろうと。シェアオフィスということはもちろんですが、そこに集まる人はシェアエコノミーやエコロジーを大切にする人が多い」そういう人たちからコンセプチュアルな共感を得ることで、『WHOSE LEATHER』の活動に巻き込んでいく。
広告発想が切り拓く、プロダクトの新たな可能性

「一昔前は伝えるための手段も媒体も限られていましたが、今は目的達成の方法が増えてきており、まず何を選択するかから突き詰めて考える必要があります」と宮内氏。広告主の感度も上がってきており、常に提案に発見が必要になってきている。「でも、どんなにメディアが変わろうと『1コピー=1ビジュアル』でアイデアを研ぎ澄ませる、という下地を共有しているのは広告クリエイターの変わらぬ強み」だという。

WHOSE LEATHER_SHARER
姫路の老舗革メーカーの「株式会社 山陽」と、クリエイティブエージェンシー「POOL inc.」による『WHOSE LEATHER』は、革の新しい可能性を切り拓く共同プロジェクト。2018年に続き二回目の展示会開催となった今回は「SHARE」という言葉をキーに、建築家やクラフト職人、アートディレクターなど様々な領域で活躍するクリエイターが「革」という素材を「使い手」の発想で捉えなおした作品が集結しました。
編集後記
メディア環境やビジネス構造の変化から、近年広告会社に求められる役割も大きく転換してきている。これまでは宣伝部のみに向き合っていれば充分だったが、事業部や商品開発部との直接のやりとりが当たり前になった。広告クリエイターの発想はモノの売り方を考えることではなく、売れるモノを考えるところから求められるようになってきている。言葉の概念集約のチカラを使って、アイデアの集約・拡散を繰り返し、プロダクトの既成概念をアップデートする。「一つの言葉で事業を動かすことができる」という信念によって生み出された「旗振り役の言葉たち」が、新しい世の中の方向性を指し示している。
取材・執筆/神保康介
この記事を読んだ方におすすめ

コミュニケーション能力より、編集力!? 本田哲也氏に今改めて聞くこれからの「戦略PR」とは?
日本を代表する戦略PR専門家である本田哲也氏が、日本初となるPR戦略立案に特化したブティック「株式会社本田事務所」(東京都港区)を立ち上げました。「Powered By PR~日本のPRには「戦略」が足りない。~」というキャッチフレーズを冠した、同社の狙いとは。そしてこのタイミングで新たな道を切り拓くこととなった、本田氏の想いとは?「世界でもっとも影響力のあるPRプロフェッショナル300人」(PRWeek誌)に選ばれたPRの専門家本田氏にPRに対する想いや、今後の展望について話を伺いました。
- コンセプト
- コンセプトとは、作品やサービスなどに一貫して貫かれている考え方をいいます。デザインと機能がバラバラだったり、使い勝手がちぐはぐだったりすると「コンセプトが一貫してないね」などと酷評されてしまいます。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- ASO
- ASOとは、App Store Optimizationの略称であり、アップストア最適化を指します。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他