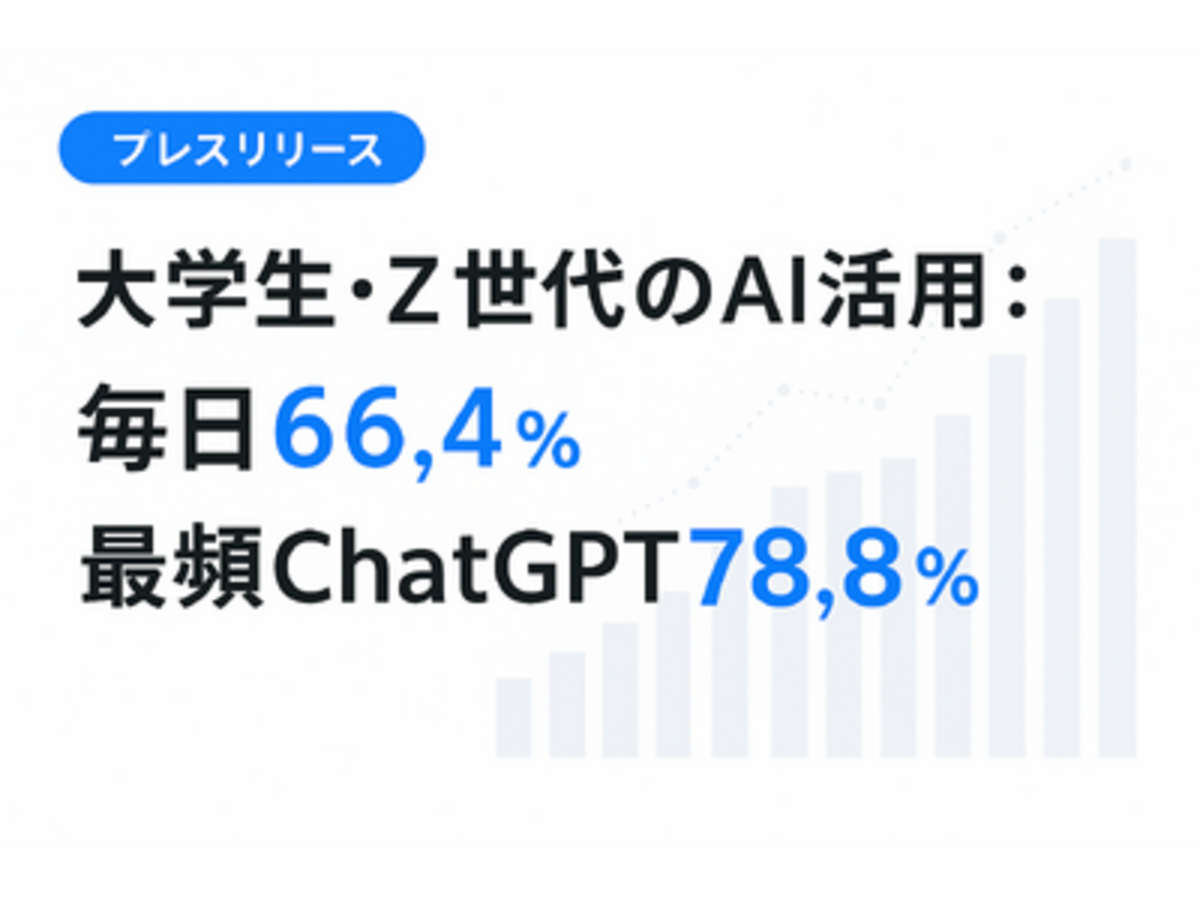ワーケーションとは?新しい働き方のメリット・デメリットと定着への課題を読み解く
「ワーケーション」とは、「Work(仕事)」と「Vacation(休暇)」を組み合わせた造語で、「休暇を取りながら柔軟に働く」といった、新たな働き方を指す言葉です。昨今のコロナ禍によるリモートワークの進展、そして、国が推進する「働き方改革」の観点からも、この「ワーケーション」という言葉が注目され始めています。この記事では、ワーケーションのメリット、デメリットや、今後の日本社会における普及に向けた課題などについて読み解いていきます。
ワーケーションとは
「ワーケーション」とは、普段の勤務地を離れ、自然に囲まれたリゾート地・保養地などで休暇を取りながら、リモートで仕事をすることを指します。
「Work(仕事」と「vacation(休暇)」を組み合わせた造語で、もともとは2000年代のアメリカにおいて、このような働き方が提唱され始めました。
日本では2017年からJAL(日本航空株式会社)グループが働き方改革の一環として、この「ワーケーション」への取り組みを推進する、と発表して注目を集めました。
JALでは、引き続き2020年秋にも「ワーケーション」の取り組みを推進し、新しい働き方の効果を検証する、としています。
具体的には、岩手、兵庫、石川、愛媛、宮崎の5県を「ワーケーション」対象地域とし、JAL社員が各地を訪れてワーケーションを実施し、現地でのさまざまな社会貢献活動にも参加するとのこと。
たとえば愛媛県では、柑橘類の果樹園で草刈りや水やりなど農園整備に参加し、さらには収穫された果実を活用した地域の新商品レシピ作りに取り組む、といったプログラムも想定しているそうです。JALは、対象としたこの5県を「労働力や関係人口などの課題を抱え、他地域や他業種との共創ニーズのある地域」としています。
地域外の人が地域に入ることで活性化につなげる、という点まで「ワーケーション」のビジョンに掲げていることが伺えます。
参考:
休暇中に働く? ワーケーションのメリット・デメリット|株式会社日立ソリューションズクリエイト
JAL、地域と共創する働き方検証 ワーケーションで社会貢献|Aviation Wire
ワーケーションのメリット
それでは、ここからはワーケーションのメリットを具体的に見ていきましょう。
①長期休暇を取得しやすくなる
ヨーロッパなどでは約1ヶ月間もの「バカンス休暇」を取ることが当たり前だといいます。その一方、日本のビジネスパーソンにとっては「有給休暇を取りづらい」「長期休暇を取りづらい」といった休暇に対する課題がまだまだ根強いもの。
しかし、「ワーケーション」で旅先などから会社にリモートアクセスできる環境が整えば、必要最低限の業務をこなしつつ、並行して休暇も楽しむといった柔軟な対応ができます。「1ヶ月も会社から離れると、毎日の現場のことが気がかりだ」という役職に就いている人でも、会社との接点を最低限に保っていることで安心感が得られる側面もあるはずです。
このような観点から、「ワーケーション」が普及すれば、多くのビジネスパーソンが長期休暇を取りやすくなる、という期待がされています。
②リフレッシュ期間を取り入れることで、日常へのモチベーション向上
日頃のオフィス環境から離れた、リゾート地・保養地などの環境がもたらすリフレッシュ効果もポイントとなるでしょう。
パソコンを開いてリモートワークをしている時間以外は、森林浴やマリンスポーツ、温泉などでリフレッシュ。日頃の心身の疲れを癒やしたり、家族と同行すればコミュニケーションを深める良い機会にもなったりもします。
いわゆる「ワークライフバランス」を図り、毎日の仕事や生活に対するモチベーションを再確認する時間にもなり得るでしょう。
③仕事は短時間集中で効率アップ、環境の変化による新たな着想にも期待
「ワーケーション」においてパソコンを開いて仕事に向かう時間には、「短時間に限定的して仕事をする」というスタイルになります。また、毎日オフィスに篭もっている状況と比較すると、自然に囲まれ、きれいな空気が吹き込むリゾート地・保養地などまったく異なる環境で仕事をすることになります。
環境の変化から、普段は湧かないような新しい発想やアイデアが得られる可能性も生まれ、かえって効率的に業務をこなせるという効果も期待できます。実際のところ、「ワーケーションでは集中力が途切れず生産性が上がる」という側面は、これまでの実践事例からも多々、指摘されているとのことです。
④訪問地域で新たな人々との交流や社会貢献活動を持てる
「Vacation(休暇)」の過ごしに方は各人、さまざまな楽しみがあることでしょう。
保養地での散策、森林浴、登山、マリンスポーツや温泉、グルメだけに留まらず、前述したJALグループの取り組みのように、「農作業を手伝って地域の人と新たな交流を育てる」「訪問地での社会貢献活動に参加する」といったことに楽しみを見出す人もいるはずです。
普段暮らしている地域とは離れた他地域に、新たな人脈を育てることは、ビジネスパーソン個人にとっても新たな財産となり、プラス要素となります。
また、企業側にとっても「◯◯社の人はワーケーションで保養地を訪れるたびに、地域活動に参加してくれる」といった、社会貢献活動に関する新たなアピールポイントや信頼醸成も期待できます。
⑤「働き方改革」に取り組んでいる先進的な企業だとアピールできる
「ワーケーション」の取り組みを導入することで、企業にとっては「働き方改革にいち早く取り組む、先進的な企業である」とアピールすることにつながります。
既に在籍している社員にとっては長期休暇が取りやすくなり、日々の働き方に改善をもたらし離職者を減らす効果も期待できます。
また、求人・採用の際にも「ワーケーションの制度がある」とアピールできれば、応募者から見ても新たな魅力の一つになることでしょう。
参考:休暇中に働く? ワーケーションのメリット・デメリット|株式会社日立ソリューションズクリエイト
実は五輪対策だった
実はこの「ワーケーション」が盛んに提唱されるようになった背景には、行政サイドの2020東京五輪対策だった、という側面もあります。「五輪期間における首都圏人口の分散策」という狙いがあり、2019年11月に、複数の自治体が「ワーケーション・アライアンス・ジャパン」を設立。ワーケーションに関する情報発信などを始めました。
そこには、「首都圏人口の分散策」に付随し、行政や地方自治体によるさまざまな思惑も隠されていました。
首都圏のビジネスパーソンの間でワーケーション参加が普及すれば、従来以上に、地方の観光地に長期滞在する人口増につながります。
宿泊施設にとっては、客室を埋めることが難しかった平日やオフシーズンの稼働率向上につながり、さらにはショッピングなど、観光以外の事業者たちにも恩恵がもたらされます。また、地方が抱える「空き家」や「空きオフィス」の問題解決への期待もありました。
早期から「ワーケーション」の普及に期待を抱いてきたのは、個々のビジネスパーソンや企業側というよりは、むしろ、行政サイドであった、という背景も浮かび上がってくるのです。
参考:官邸発「ワーケーション」は働き方を変えるのか|東洋経済オンライン
ワーケーションのデメリット
[図1]

出典:【ワーケーション】約4割の方が、今後普及していくと「思う」|日本トレンドリサーチ
[図1]は、「ワーケーションは普及していくと思うか?」という問いに対する回答を示したものです。
これは、「日本トレンドリサーチ」による調査結果で、2020年7月31日~8月4日の期間に男女総計1200人から回答を得たものです。
グラフを見ると、「普及していくとは思わない」と回答した人が60.5%と過半数に上っており、普及にはいくつかの課題や、デメリットを感じている人のほうが多いことが伺えます。
それでは、一般のビジネスパーソンや企業サイドが感じている「デメリット」「課題」とは何なのでしょうか?
①導入・運用コストがかかる
リモートで円滑に仕事を行うには有線インターネット、あるいはWi-Fiが使える環境を整えることが大前提です。それに加えて、ビデオ会議やビジネスチャットなどソフトウェア、パソコンなどのハードウェアを用意する必要もあります。
いずれにせよ、導入・運用にはある程度のコストがかかります。
これらの社内共通システムやハードウェアの整備は、日頃からテレワーク実施が進んでいる企業にとってはそれほど障壁にはなりませんが、まずはテレワーク環境から整えなければならない、という企業にとっては決して小さくはない負担となります。
加えて、ワーケーションを実施する場合の旅費交通費は会社が負担するのか、個人が負担するのかといった点も、改めて検討・議論が必要でしょう。
②情報セキュリティ面での懸念
業務上、取り扱っている情報のセキュリティへの懸念も生じます。
「個人情報を扱う場面ではどのように運用するのか?」「個人個人に付与した端末をどのように管理するのか?」「パソコンやタブレット端末、スマホの盗難・紛失が起きてしまったら?」といった問題への対策を予め講じておく必要があります。
③社員の稼働時間の管理をどうするか
これはリモートワーク全般に言えることですが、遠隔地に居て姿が見えない状況で仕事を進める際、社員の稼働時間把握・管理をどうするか?という問題が生じます。
この課題解決には、「テレワーク用の勤怠管理ツールを使う」「バーチャルオフィスシステムを取り入れる」などいくつかの方法が考えられます。
企業側にとって、「稼働時間管理」の対策を事前に講じておく必要があります。
ワーケーション普及をめぐる今後の課題
①日本におけるリモートワーク普及率の低さ
新型コロナウイルス感染拡大により、2020年4月7日に政府が緊急事態宣言を出しました。パーソル総合研究所の調査によると、その後テレワークに移行した企業は従来の2倍強に増えたとのことですが、それでも全体の30%を切っています。
つまり、7割の人はリモートワークがどうしてもできない状況に置かれていた、と言えます。
医療従事者、介護従事者、小売業の販売員など、エッセンシャルワーカーとして従事しており、そもそも、現場から離れては仕事が全く成立しない、という人も居ます。
「ワーケーション」提唱と同時に、日本においてどうすればリモートワークがもっと普及するか、という課題も見つめ直す必要があるでしょう。
②コロナ禍における企業業績の悪化、雇用環境の悪化
昨今、「コロナ倒産」「雇い止め」といった言葉をよく聞くように、コロナ禍で全国各地の企業が業績悪化、労働者は雇用環境の悪化に直面しています。
そんな中、「ワーケーション」という取り組みは、どこか遠い世界の、一部の人だけが享受できる仕組みのように感じられ、決して自分ごと化できない労働者・企業も多いのではないでしょうか?前述したように「ワーケーション」は、労働者・企業サイドが期待を抱いていた働き方というよりは、どちらかといえば行政サイドが熱心に推進しようとしている側面があるとも言えます。
よって行政や地方自治体は、今まさにこの、コロナ禍の中での労働者・企業目線に立って、「ワーケーション」の位置づけを改めて考える必要があるでしょう。
③地方のWi-Fi整備率の低さ
「ワーケーション」推進への取り組みにおいては、地方の国立公園などもターゲット地域になっていますが、地方の山間部などではWi-Fi整備率がまだまだ低い、ということも現実です。
行政・地方自治体サイドが「ワーケーション」を推進するならば、都市部と同等のWi-Fi環境を整備してから受け入れをしなければ、ユーザーの満足は得られず、「ワーケーション」の取り組みは定着しないでしょう。
参考:
休暇中に働く? ワーケーションのメリット・デメリット|株式会社日立ソリューションズクリエイト
休暇中に仕事? 「ワーケーション」が支持されぬ6つの理由|YAHOO!ニュース
ワーケーションの未来とは?
日本における「ワーケーション」普及に向けては、行政や地方自治体、ビジネスパーソン、企業のそれぞれが足並みを揃えていくことが肝要です。
また、「働き方改革」「新しい、柔軟なワークスタイル」「首都圏の人口密集対策」「過疎地の活性化」といった表層的な目論見に留まっているだけでは、決して一般のビジネスパーソンや企業サイドの理解は進まないでしょう。
また、「リゾート地でパソコン越しに上司の顔を見たくない!」といった、ビジネスパーソン側の意識の問題もあります。
これらの課題を乗り越えるためには、例えば「ワーケーションを通じて新たな人脈を他地域に広げ、築いていく」「新たな社会貢献の場を持ち、楽しみを見出す」といったように、ビジネスパーソン一人ひとりが今後のライフスタイルへの「投資」にできるような希望を持てることがキーポイントとなりそうです。
今後日本の社会において「ワーケーション」が定着していくためには、行政・地方自治体本位や、企業本位の目線よりも、何よりビジネスパーソン本位での訴求が必要だと言えるのではないでしょうか。
関連記事

WFH(ワークフロムホーム)とは?仕事に通勤は不要!?テレワークとの違いも解説!
コロナウイルスの感染を予防する目的で、企業が導入し始めた在宅勤務。自宅での仕事が通例化することからWFHという言葉が使われ始めました。在宅で勤務することを指す言葉ですが、急遽取り入れることが増えた形態のため、上手に付き合うのが難しいと考える人もいることでしょう。そこで本項では在宅勤務をより効率的に進めるためのコツなどを伝えつつ、WFHという考え方についてさらなる理解を深めていきます。ぜひ参考にしてもらえれば幸いです。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- タブレット
- タブレットとは、元々「板状のもの」「銘板」といった意味の単語です。パソコンの分野で単にタブレットといえば、「ペンタブレット」や「タブレット型端末」などの板状のデバイス全般を指します。ここでは主にタブレット型端末について説明していきます。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他