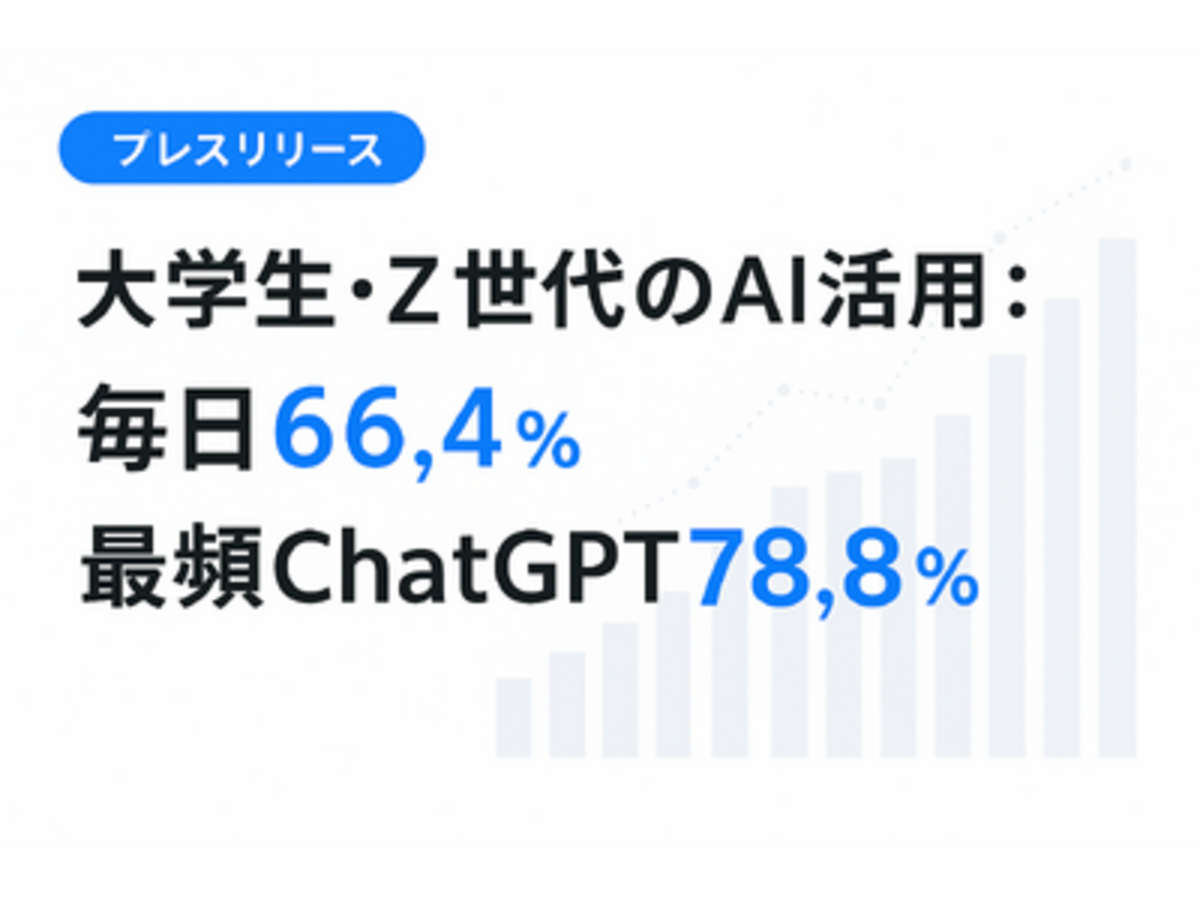オープンイノベーションとは?定義やメリット・事例を解説!
「オープンイノベーション」
ここ数年、テレビや雑誌などでもよく取り上げられる言葉です。
しかし、オープンイノベーションという言葉に、あまり馴染みが無い方も多いのではないでしょうか。
それもそのはず、グローバルな視点から見ると日本は遅れを取っており、大企業を中心に今まさに取り組んでいる最中なのです。
そこで今回は、この* 「オープンイノベーション」* の概要やメリット・実際の企業で行われた事例を紹介していきます。
オープンイノベーションとは
まず、オープンイノベーションとは、ハーバード大学経営大学院のヘンリー・チェスブロウ教授が提唱した考え方です。
2003年には書籍を出版しそのタイトルに「オープンイノベーション」が使われたことから世界で広く知られるようになりました。
ヘンリー・チェスブロウ教授は、オープンイノベーションを次のように定義しています。
「企業内部と外部のアイデアを有機的に結合させ価値を創造すること」
つまり、日本国内で既に行われている企業間の連携や、グループ企業内の連携などもオープンイノベーションのひとつ。
言い換えれば、オープンイノベーションは「企業のプロジェクトで社外組織を活用する」イノベーションの方法と言えるでしょう。
欧米をはじめとする、多くの先進企業は積極的にオープンイノベーションを行っており、事業化や利益の追求を実現しているのです。
しかし、まだまだ日本は世界的な視点から見れば、まだまだ遅れをとっているのが現状。
これからの企業の成長の鍵となるオープンイノベーションを、日本も積極的に取り入れていく必要があります。
次は、オープンイノベーションのメリットを説明していきたいと思います。
オープンイノベーションのメリット
オープンイノベーションのメリットは以下の三つです
・新しい技術や考え方を吸収できる
・多様化する消費者ニーズの把握が可能
・製品開発の効率化
ひとつずつ詳しく解説していきます。
新しい技術や考え方を吸収できる
オープンイノベーションは、外部資源の活用することで今までになかった新しい考えが生まれます。これにより客観的視点を事業に活かすこともでき、各々の企業のそれぞれの視点だけに基づいた製品やサービスの提供を防ぐこともできます。
また、新しい技術や考え方を吸収することによって、自社の強みと弱みを整理することも可能です。これによって強みを伸ばしていくのか、弱みを改善するのか、といった点を戦略的に判断することもできるようになるでしょう。
多様化する消費者ニーズの把握が可能
オープンイノベーションは、外部からあらゆる情報を取得できます。これは、多様化する消費者ニーズを的確に捉えることになり、同時にビジネスの最適化にも繋がることです。
消費者のニーズが今後も多用会していく中で、常に変化する消費者ニーズを捉えた最適な製品やサービスをリリースしていく必要があるのです。それにはやはり外部からの様々な方向性からの情報を得て活用していく必要があるでしょう。
製品開発の効率化
オープンイノベーションは外部からの情報をもとに製品開発をする際にも効率化が期待できます。
従来では、新しい技術や知識を得るために長年にわたる様々な調査や研究が必要でした。
社外からそれらを取り入れれば、その調査や研究に費やしたコスト時間を削減でき、それを積み重ねることによって、より早いサイクルで製品やサービスを作ることも可能になるのです。新開発の効率化ができれば、結果として事業全体のスピードも早めることにもなります。
クローズドイノベーションとは
では、ここからは従来から日本で取り入れられている、クローズドイノベーションについて説明します。
クローズドイノベーションはその名の通りオープンイノベーションの対義語で、日本経済を成長させる要因でした。
クローズドイノベーションには、競争優位性や利益の還元性が高いといったメリットがあります。
しかしそれは言い換えれば、商品の開発から提供まで全て自社で行わなければならないため、時間と人的コストもかかるというデメリットも。現在では、競争環境が激しさを増しているため、このクローズドイノベーションは経営戦略としてベストではなくなってきています。
このようなことから、徐々にクローズドイノベーションからオープンイノベーションに切り替える企業が年々増えてきているのです。
次に、そのオープンイノベーションに切り替えた企業の具体的な事例を確認してみましょう。
オープンイノベーションの具体的な事例
では、ここからは具体的な事例を企業ごとに解説していきます。
自社のノウハウの流出リスクやオープンイノベーションの経験不足などの要因を抱えながらも、オープンイノベーションに成功した事例です。
東京ガス
東京ガスでは「リビングサービス改革プロジェクト部」という組織を設立しました。
これは、2017年4月より質の高いサービスの提供を目指したオープンイノベーションへの取り組みです。
住宅やセキュリティといった領域でスタートアップ企業との検討したり、有識者と共にプロジェクトを行ったりといった積極的な活動を行っています。
三菱UFJフィナンシャルグループ
三菱UFJフィナンシャルグループでは、もともとあった三菱UFJ銀行のIT事業部をデジタルイノベーション推進部に変更。
デジタルイノベーション推進部によって、グループ全体のイノベーションに関する取り組みを行っています。
この取り組みによって、日本の銀行では初めてとなるスタートアップのアクセラレーターとして様々な支援を行い実績を残しています。
富士ゼロックス
富士ゼロックスは、ご存知の通りプリンターや複合機製造の大手企業です。
オープンイノベーション事業を展開し「四次元ポケットプロジェクト」として中小企業6社を参加させ新製品の開発を行いました。
このプロジェクトでは、室内旅行機や望遠メガホンといった従来の富士ゼロックスの技術だけでは難しかった製品の発表にも繋がっています。
まさに、オープンイノベーションに成功した事例の一つといえるでしょう。
ソフトバンク
ソフトバンクでは「SoftBankInnovationProgram」をスタートしました。
これは、国内外問わず共同で事業化や商品化をするパートナーを募集するものです。
中小企業やベンチャー企業にとっては、大手ソフトバンクと手を組み事業の拡大につなげるチャンスにもなっています。
レゴ
レゴでは、そのブランド力と一般人からのリソースを融合させたオープンイノベーションを行なっています。
ファンサイトでもある「LEGOIDEAS」で一般人が作ったオリジナルモデルを公開しており、同時にファン投票を実施し、ここで多くの票を集めたモデルを実際に商品化するといった、斬新なオープンイノベーションを実施しています。
P&G
P&Gは、日本の外資系企業の中でも長い歴史を持つ会社です。
主に洗剤や家庭用品を扱う企業らしく、消費者の「こんなものが欲しかった」への商品開発にオープンイノベーションを採用しています。
外部から研究員を募集したり社内外から積極的にアイデアを集めたりと、従来よりも消費者に寄り添うような商品開発を行っています。
まとめ
このように、オープンイノベーションは企業の成長にとって今や必須の方法です。
積極的なリソースの取り入れにより、さらに消費者に求められるような製品やサービスの開発につながった事例が多くあります。
まずはこの記事を参考に、オープンイノベーションへの理解と活用を深めてみてはいかがでしょうか。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- サイクル
- サイクルとは、スタートしてゴール、そしてまたスタートと、グルグルと循環して機能する状態のことを言います。まわりまわって巡っていく、といった循環機構をさすことが多いです。水の循環サイクルというように、実は繰り返しになってしまう使われ方もすることもしばし。また、自転車に関する事柄として、サイクルスポーツなどという使われ方をされることもあります。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他