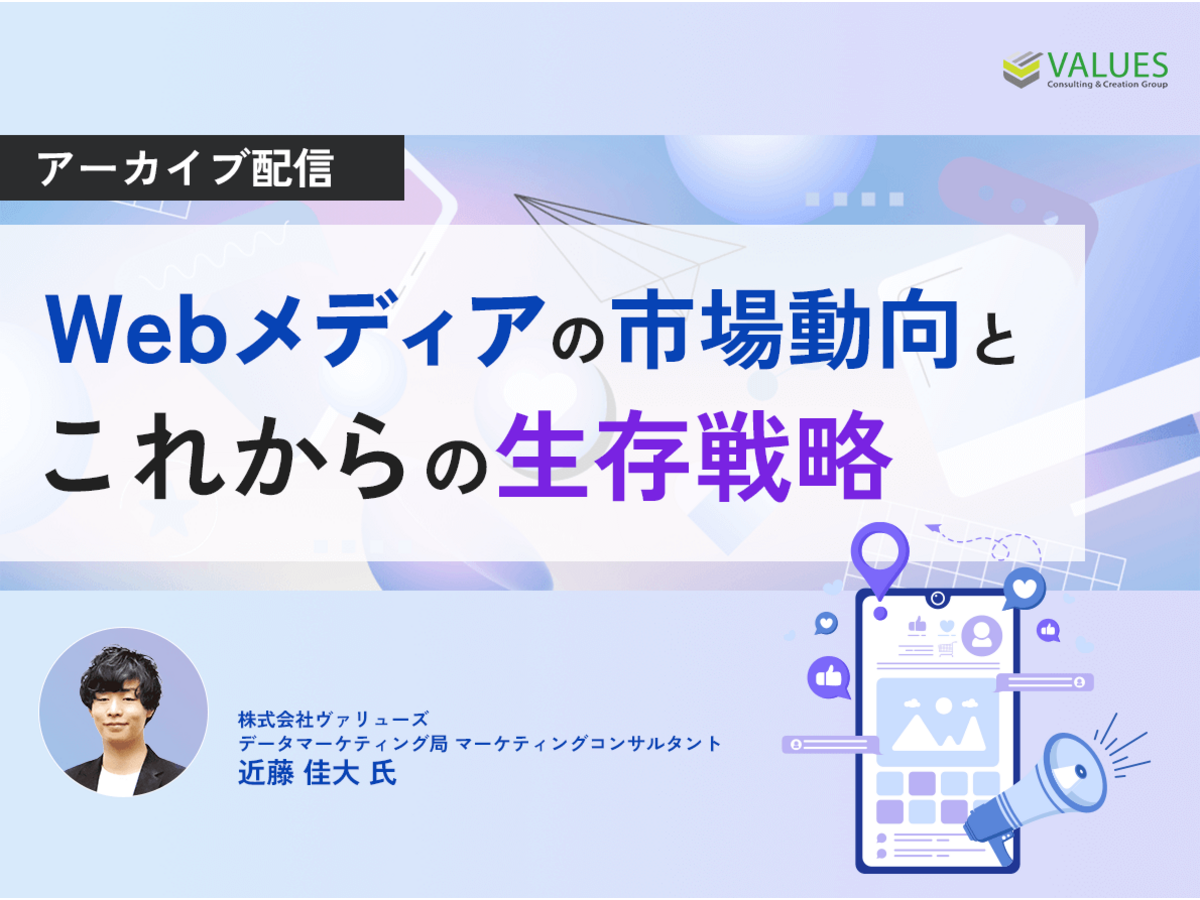デジタルシフトに成功する組織づくりの秘訣とは
※この記事はアドビ株式会社祖谷考克(そたに たかよし)様からの寄稿記事となります。

筆者プロフィール
- 祖谷考克(そたに・たかよし)
- アドビ株式会社DXマーケティング&セールスデベロップメント本部執行役員・本部長。広告会社を経て、2013年にアドビ入社。ビジネス・コンサルタントとして顧客のデジタル・ビジネスを推進。2018年に新組織デジタル・ストラテジー・グループを立ち上げ、経営視点からの中期的なデジタル変革の戦略策定を支援。2019年11月より現職。
筆者は、アドビ株式会社にてDXマーケティング&セールスデベロップメント本部の組織を立ち上げ、現在本部長としてチームを率いています。本連載では、3回にわたって、企業のDX推進に必要な組織づくりや、B2Bマーケティングの視点から見る顧客体験の最前線などについて解説していきます。
1回目となる今回は、デジタルトランスフォーメーション(以下、DX)を推進するにあたっての組織づくりや進め方などについて取り上げます。
目次
DXとは何か
ここで改めてDXとは何かについて考えてみましょう。多くの企業がDX推進することを表明していますが、その目指すところが必ずしも一致しているわけではありません。よく聞くのが、新しいツールを導入すればDXになると考えている例です。新しい営業管理ツールを導入することはDXではなく、手段でしかありません。
DXとは、デジタルが浸透した世界を前提として、それにあわせてビジネスを変革し、社会や顧客に新しい体験価値を提供することだと筆者は考えています。
ポイントは、企業が企業のために変革するのではなく、社会や顧客のために新しい体験価値を提供するために変革することにあります。その変革を実現するために、新しいツールを導入することもありますが、それは目的ではなく、あくまで手段なのです。
本連載では、本来の意味でのDXを推進するための考え方を筆者の体験や知識を通して紹介していきます。
DXの推進が失敗する背景にあるもの
DX推進を掲げる企業は多いですが、その一方で現場が苦労しているという相談もよくいただきます。苦労している最も大きな理由は経営層が正しくDXを理解していない、そして全社的にDXの考えが浸透していないということです。
DX推進は、ビジネスの変革を伴うので、一事業部や担当者のレベルでやり遂げられるものではありません。DX推進の方針を打ち出し、旗を振るのは経営層の役割で、デジタルを前提とした体験価値の設計はどうあるべきなのかを考えた上で実行する部署に予算を割り当てていく必要があります。
しかし、その戦略なしに、DX推進をうたい、予算だけを情報システム部など特定の部署に割り当てているような例も見受けられます。
この状態でDX推進を経営層から命じられた部署は、その予算を真新しいツール導入に費やしてしまいがちです。その場合、業務の効率化など社内向けの業務改善だけを目的にしがちで、これからの時代に求められる新しい価値提供を見据えているとはいいがたい状況になってしまいます。
漠然とDX推進と言われても、自社の何を変革し、どんなことを目指すのかというゴールがないので、ものさしがないままにプロジェクトを推進することになります。予算の一部を使って、スモールスタートで始めて、スモールな成果しかでないまま、正しく評価されずにいつの間にかプロジェクトがたち消えになってしまったという話も耳にします。
限られた予算であっても、戦略があれば「現時点でこの部分だけを実施して、これだけの成果が出たので、拡大すれば将来的にここまでできる」とロードマップを示すことができます。しかし戦略がないと、スモールな成果のみで判断することになり、将来的な価値を不当に低く評価することにもなりかねません。
経営層が世の中の変化に気づいているか
しかし、DXを丸投げされた部署でもやり方によっては、経営層を動かすことができます。欧米はトップダウンで組織が動くことが多いのですが、日本はボトムアップで、現場の働きが推進力になって組織を動かすということもあるからです。
ただ、この時に複数の部署がそれぞれ個別に動き出すのはあまり得策とはいえません。例えば、事業部ごとに異なるツールを導入してしまうと、データが分かれてしまって連携が困難となり、全社的なデータとして使えないため、経営判断に活かせません。
部署最適化によるボトムアップではなく、全社最適のためのボトムアップで経営層に成果を示していく方法が望ましいと考えます。
経営層を動かすには、わかりやすいデータが有効ですが、組織や経営者の考え方によっても“ツボ”が違うので、なかなかこうすれば成功するというパターンがないのが、推進を難しくしています。
例えば、経営者がスマートフォンを通じたデジタルサービスを日常の様々なシーンで活用しているようであれば、デジタルを介した体験がどんなものなのかを知っているので、年齢を問わず理解してもらいやすい傾向があります。
一方でスマートフォンは持っているものの、電話やメール、チャットなどしか使っていない場合、その先の未来まで見据えた体験の可能性をイメージしにくい傾向があります。
新聞やラジオしかなかった時代にテレビが登場した時以上に、スマートフォンの登場は非常に大きなインパクトを社会にもたらしました。経営層にはそれくらいの大きな変化がすでに起こっていて、顧客体験が以前とは大きく変わっていることを実感してもらう必要があります。
経営層を動かすためのボトムアップの動き方
世の中に新しい価値を提供して、その報酬として利益を生む、その方針を示して全社を動かせるのは経営層だけです。その経営判断のためには、事業部など現場からの適切な情報提供が必要になります。
この時も特定の部門だけで情報提供するのではなく、複数の部門からプロジェクトの参加者を募って、クロスファンクショナルチームを作り、それぞれの部門からのニーズや顧客の変化を経営層向けのインプットとして用意します。経営層はその情報を参考に、これから自社がどういう方向を目指して、何に力を入れていくのか、方針を示すことができます。
経営層から方針が打ち出されたあとは、現場はその実現を目指して動き始めればよいのですが、ここでも各部門で独自のことをやり始めないように注意してください。つい自分たちの部門のことを考えがちですが、それぞれの部門最適ではなく部門横断・横串で動けるように連携していく必要があります。
大きな組織になるほど共通認識のもと横串で動いて行くのは難しくなるので、クロスファンクショナルチームで集まって足並みを揃えていくことになります。トップの示す方向性にあわせて、現場目線の横連携のマネジメントが必要です。
しかし、このクロスファンクショナルチームのプロジェクトを引っ張っていける人がいないという場合もあるでしょう。通常業務との兼任の場合は、多くのリソースを避けずに後回しになってしまうこともありがちです。専任でプロジェクトを担当できればよいのですが、専任になったその後のキャリアを不安に感じることもあります。
そのため、外部の助けを借りる選択肢も検討してみる必要があります。DX推進のプロジェクトマネージャーというロールのプロフェッショナルを1から育てるよりも、外部から必要なスキルを持つ人を呼んだほうが、短期間で効率的なプロジェクト推進ができることがあるからです。
外部リソースを活用する一番のメリットは、多くの企業が陥りがちな失敗を知っているので、先回りして避けられることです。また、外部の人間であるからこそ、社内のしがらみなく物事を進められます。
変革をするには、時に痛みを伴います。社内のメンバーだとやりにくいこともありますが、第三者視点だからこそ、決断できることもあります。
アドビのコンサルティングチームにも、DX推進のために、プロフェッショナルな知見とノウハウを提供して欲しいというご依頼をいただいています。
DXを推進し続けるために必要なこと
大きな方向性を示すのは、経営層の役割ですが、実際のプロジェクトの推進は権限を移譲された現場が動いていくべきです。DXは終わりがないプロジェクトでもあります。環境が変われば、顧客の期待値も変わり、その変化は終わることがないので、私たちは挑戦し続けないといけません。
新しい変化に対して、次の一手を考えて意思決定をする、実施してフィードバックを得て、次の改善策を考える、このサイクルは早いほうがよいので、現場への意思決定の権限移譲が必要なのです。
しかし、権限移譲があっても何を基準に行動していいかわからないというお悩みを聞くこともあります。迷ったときは、経営層の示す方向に立ち返ってみる必要がありますが、加えて顧客が何をしてほしいと思っているのか、顧客にとって正しいことは何かということからもう一度考えることが重要です。
自分たちが世の中に提供したい価値と、顧客にとって正しいことをかけ合わせて、判断基準ができていきます。世の中や顧客の変化を敏感に感じ取り、いち早く決断して、顧客が求める新しい体験を提供できれば、顧客はその企業を支持します。
こうした早く決断する土壌がベースにあって、その上に手段としてツールがのってくることで、DXが推進されていくでしょう。
さて、次回は「コロナ禍においての営業やマーケティングの仕事の変化」について取り上げます。
連載一覧
デジタルシフトに成功する組織づくりの秘訣とは(当記事)
よりよい顧客体験を提供するための組織連携
良質な体験を提供するための組織のあり方
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- サイクル
- サイクルとは、スタートしてゴール、そしてまたスタートと、グルグルと循環して機能する状態のことを言います。まわりまわって巡っていく、といった循環機構をさすことが多いです。水の循環サイクルというように、実は繰り返しになってしまう使われ方もすることもしばし。また、自転車に関する事柄として、サイクルスポーツなどという使われ方をされることもあります。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他