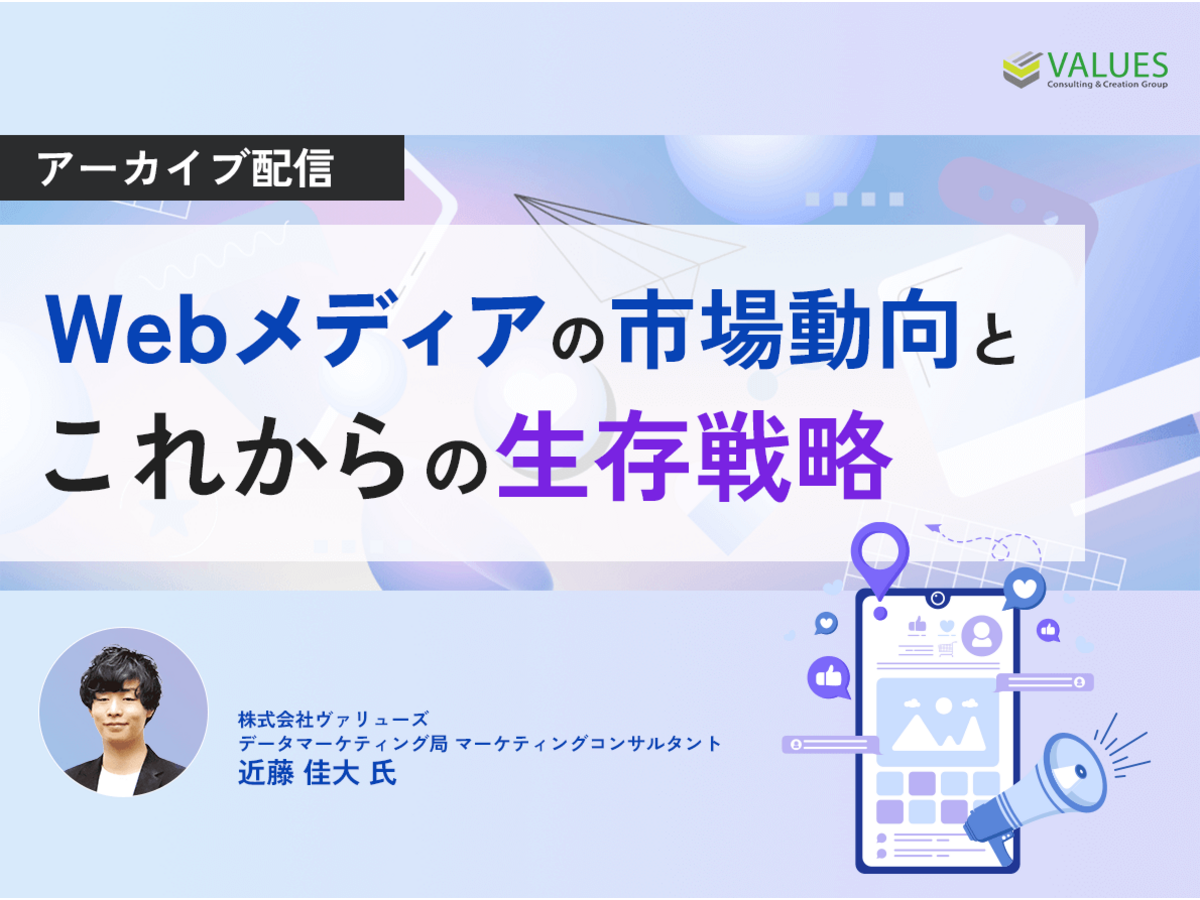よりよい顧客体験を提供するための組織連携
※この記事はアドビ株式会社祖谷考克(そたに たかよし)様からの寄稿記事となります。

筆者プロフィール
- 祖谷考克(そたに・たかよし)
- アドビ株式会社DXマーケティング&セールスデベロップメント本部執行役員・本部長。広告会社を経て、2013年にアドビ入社。ビジネス・コンサルタントとして顧客のデジタル・ビジネスを推進。2018年に新組織デジタル・ストラテジー・グループを立ち上げ、経営視点からの中期的なデジタル変革の戦略策定を支援。2019年11月より現職。
筆者は、アドビ株式会社にてDXマーケティング&セールスデベロップメント本部の組織を立ち上げ、現在本部長としてチームを率いています。本連載では、3回にわたって、企業のDX推進に必要な組織づくりや、B2Bマーケティングの視点から見る顧客体験の最前線などについて解説していきます。
2回目となる今回は、顧客接点を最大化するために、営業、マーケティングがやるべきことについて解説します。
目次
- 急激に変化した働き方。営業スタイルも変化
- オンオフを自在に行き来する顧客。それを踏まえたバイヤージャーニーマップが必要
- 顧客と接するすべての部署で接点を整理する
- 最初のハードルはとにかく低く設定しよう
急激に変化した働き方。営業スタイルも変化
コロナ禍、特に緊急事態宣言中は、リモートワークが急速に普及し、オフィスから離れた場所で仕事をすることが定着してきました。通常の業務はオンラインで処理して、会議や打ち合わせ、面談などもオンライン会議で行われるようになりました。
営業活動も同様で、対面での営業は避けざるを得ず、多くの企業で営業活動をオンライン会議、メールなどで行うことになりました。
ただ、新型コロナウイルスが収束したあとも、この流れが進んでいくかというと、そうとも限らないと思っています。以前から働き方改革の一環としてリモートワークが推進されてきましたが、リモートワークが浸透したことで、逆に直接会って働くことの価値も改めて評価された点もあるかと思います。
そのためこれからは働き方の選択肢が広がる形で、目的や内容に応じてリモートワーク、出社して働くスタイルの両方が並存していくと予想します。これは営業も同様です。オンラインなのか、オフラインなのか、顧客のニーズにあわせて営業は対応していくことになるでしょう。
B2Bにおいてはデジタル浸透とともに顧客自らが情報収集をする傾向が強まってきていますが、さらに弊社調査によると日本は世界と比べて、対面での情報提供よりも、PCからの情報提供を好む傾向があるようです。

お客さんと面と向かって話したほうが効果が高いと感じている営業担当者にとっては、難しい状況になっていると言えます。
対面営業のほうが成果が出やすいのにはいくつか理由があります。一つは感情に訴えられること。「次回は上司を連れてきます」と組織として対応していることをアピールする、「近くに来たので寄りました」と接触頻度を上げる、あるいは「今期の売上が厳しくて」と泣き落としにかかるなど、あらゆる手段で、顧客が断りにくい状況にして売上につなげるのも一つの営業テクニックです。
しかし、リモート商談ではこうした「空気」を使ったテクニックはほぼ意味がありません。オンラインの場合、顧客が対面のときと同じように集中して話を聞いているとは限りません。
時間はとったものの、営業担当者の話にあまり興味がなければ、他の仕事をしながら聞いている、早めに打ち切るということが容易だからです。顧客にとっては、断りにくくて発注するような状況を防げる分、リモート商談のほうがありがたいのです。
こうした状況から、営業担当者の中にはリモート商談を繰り返す中で、これまで以上にコミュニケーションスキルが磨かれてきている人もいます。
紋切り型のセールストークでは、顧客の注意をひけないので、画面越しの数少ない情報を拾い、そこから顧客がより興味を持ちそうな話、顧客が必要な情報をわかりやすく伝えられるように工夫し続けた結果、本人も驚くほどコミュニケーションスキルが上がったそうです。
営業が顧客のニーズに合わせた情報提供をしていくには、顧客が何に興味を持っているのか、どんな課題を感じているのかという顧客理解が必要で、そのためにはマーケティング部門との連携が求められます。
この連携がうまくいき、顧客のニーズにあわせた情報提供ができるようになれば、リモート商談の特性を生かして、これまでは対応が難しかった離れた地域の企業にもアプローチできるようになり、商圏の拡大も可能です。
オンオフを自在に行き来する顧客。それを踏まえたバイヤージャーニーマップが必要
オンライン、オフラインを使い分ける行動は、B2Cでも顕著です。あるメーカーの社長から伺ったお話では、緊急事態宣言中に店舗を閉めてECサイトに誘導した結果、緊急事態宣言明け以降は、オンライン、オフラインを上手に使い分けるハイブリッド型の購入体験をする方が増えているそうです。
例えば、初めて購入する商品であれば、店頭で見て店員の説明を聞いて購入します。その後、リピート購入する場合は、すでに商品の特徴や使い心地はわかっているので、ECサイトから購入します。
他にも、店員さんと話がしたいから店舗で購入する日もあれば、荷物が多ければECサイトで購入するなど、その時々の状況や気分で使い分けをされている方が増えているとのこと。もちろんその前提として店舗での接客は、ECサイトではできないようなコミュニケーションや体験を提供することで、店舗ならではの価値を高める必要があります。
B2Bの場合は、基本的な情報収集はオンラインで可能です。マーケティング施策として、Webサイトに掲載する情報を充実させたり、オウンドメディアで様々な視点から情報を発信するようになり、顧客は検討段階で豊富な情報を得ており、おおよそ発注する企業も絞り込んでいます。
裏を返せば、オンライン上で十分な情報を提供できていない場合は、検討の段階で候補から外れてしまうリスクがあるということです。また、候補にリストアップされた後、問い合わせを受ける際には、顧客はすでにある程度の製品/サービス知識を得ており、自社の状況に特化した具体的な情報を求めていることになります。
よって、マーケティングと営業で、どんな情報をどのタイミングで届けられるのか、情報を整理していかなければなりません。そのために有効な取り組みが、マーケティングと営業で一緒にバイヤージャーニーマップを描くことです。顧客が製品検討、意思決定などの各ステップで、どの情報が必要なのか、情報ソースは何か、その時の期待は、といったことを整理します。
マーケティングと営業がそれぞれ別のバイヤージャーニーマップを作ってしまうと、顧客から見ると情報提供が一貫していないように見えたり、マーケティングからすでに提供している情報と同じ情報をわざわざ商談で披露するような事になりかねません。
ある調査でも、営業とマーケティングが連携していると商談の成約率が上がるというデータもあります。

出典:MarketingProfs、IDC、Accenture
顧客と接するすべての部署で接点を整理する
バイヤージャーニーマップを作っても、顧客がジャーニー通りに動かない場合も多くあります。バイヤージャーニーは、顧客の認知から購入決定までのプロセスの全体像を捉えて、情報を求めるタイミングを整理し、マーケティング、営業それぞれで共通の理解を深めるために活用します。その上で個別にこのタイミングでは、どういう情報が必要なのか、ということを考えて対応していきます。
顧客自身が、今知りたいと思っている情報ではなくても、そのタイミングで提供することで、ソリューション選定の中でその情報が活きてくることもあります。Webサイトだけでは見極められない、個別のケースや要件に対しての情報提供ができるのは、リード獲得後の1to1コミュニケーションのタイミングになります。そのための接点の設計をしていくことになります。
顧客接点を最大化していくには、まず顧客と直接接するすべての部署での接点を整理していきます。マーケティング、営業はもちろん、購入したあとのカスタマーサクセスも、重要な顧客接点であり、顧客情報を共有していくことになります。
丁寧に情報を共有できるほど、部門をまたいでも、顧客のニーズを抑えてコミュニケーションができるので、顧客体験をよりよくすることができます。
さらに、上記ほど詳細な情報を共有する必要はありませんが、間接的に接する部門、例えば製品開発部門、管理部門などにも、情報の共有ができることが理想です。顧客情報1件1件を都度都度インプットする必要はありませんが、定期的に顧客情報として提供できるとよいでしょう。
彼らは顧客の対応ではなく、顧客体験を形作るあらゆるもの、例えば契約書のフォーマットや取り交わし方(紙なのか、電子サインなのか)に対して、顧客の声を反映させていくことができます。
最初のハードルはとにかく低く設定しよう
全社で顧客情報を連携するには、やはり手段としてのツールが必要です。CRM、SFA、MAなどのツールで、顧客の情報を登録しながら部門間で共有していきます。なお、ツールの導入の失敗例としてよくあるのが、最初の運用設計時に、顧客のあらゆる情報のインプットを求めることです。
入力項目が多くて、しかもその入力内容がなかなか活用できていないと、入力するモチベーションが下がります。普段の業務が忙しくなると、入力の優先度が下がりがちで、運用開始後数ヶ月経ったのに、全く情報が蓄積できていない、という失敗も少なくありません。
そこで、入力項目の優先度をつけて、最初は実行できる範囲で運用していくのがおすすめです。会社名、部門、担当者名、連絡先、導入タイミングなど、必要最低限の項目のみに絞ってまずはオペレーションをまわせるようにします。
それでも、情報が蓄積されていけば、そのデータを活用した新たなアプローチができるようになります。少し活用できるようになったタイミングで、ROIを判断して、継続する価値があるのかどうかを判断します。
継続する価値がないという判断であればそこで止めて別の方法を模索してもよいでしょう。継続する価値があるのであれば、次のステップとして、入力項目を増やすなどの対応をしていきます。
とにかく最初は何でもできるスーパーマンを基準にするのではなく、標準的な能力の人ができるレベルでルールを作ることです。実行可能性を優先して、まずはプロセスとして定着させる、成果が生まれてくれば、その価値が伝わり、業務としての優先度も上がっていきます。
さて、「次回は、顧客データ活用と組織マネジメント」を取り上げます。
連載一覧
デジタルシフトに成功する組織づくりの秘訣とは
よりよい顧客体験を提供するための組織連携(当記事)
良質な体験を提供するための組織のあり方
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- CRM
- CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、直訳すると顧客関係管理となります。
- ROI
- ROIとは、Return On Investmentの略で、投資利益率のことを指します。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他