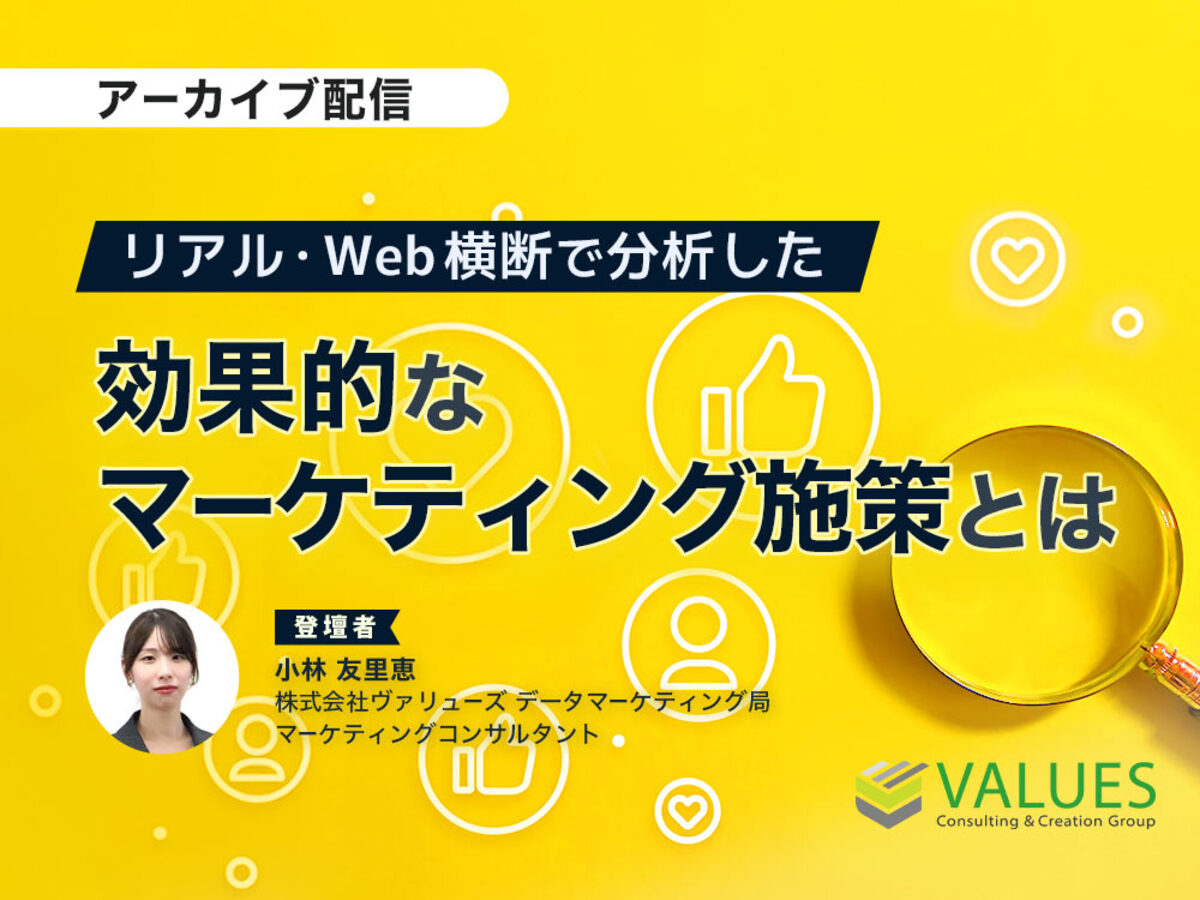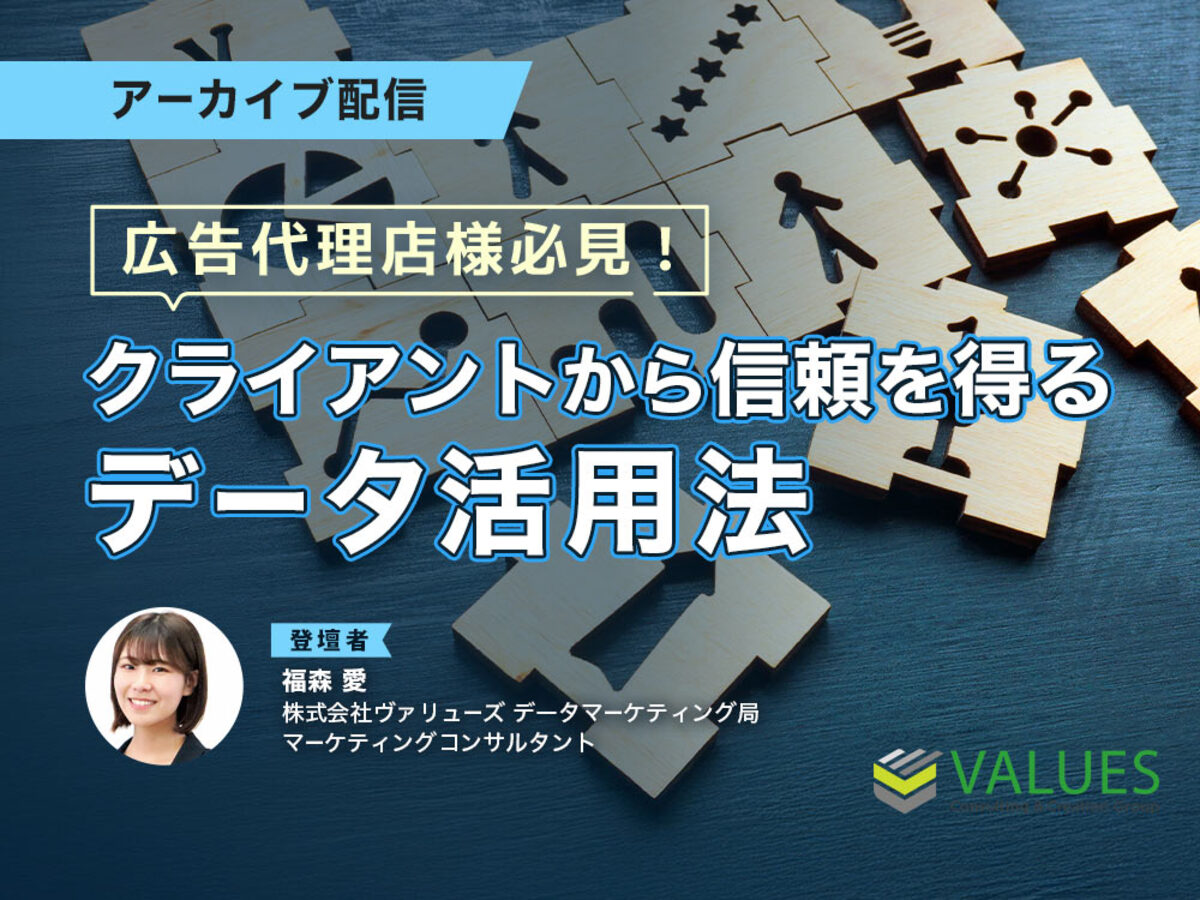「相関関係」「因果関係」の違いとは?見分けるポイントと事例をわかりやすく解説!
「近年の犯罪者はみんなゲームをやっている。だから犯罪の原因はゲームにある」
こんな論説をニュースや新聞で見たことはありませんか?一見矛盾がないように見えるこの主張ですが、「ゲームをやる人の割合が社会的に増えている」という現象を見逃しているため、正しい主張だとは言い切れません。
こういったデータの読み間違いは「相関関係」と「因果関係」を混同してしまっていることが原因です。今回は、相関関係と因果関係の違いに加え、これらを混同しがちな事例を解説します。
目次
▼資料作りにおすすめ
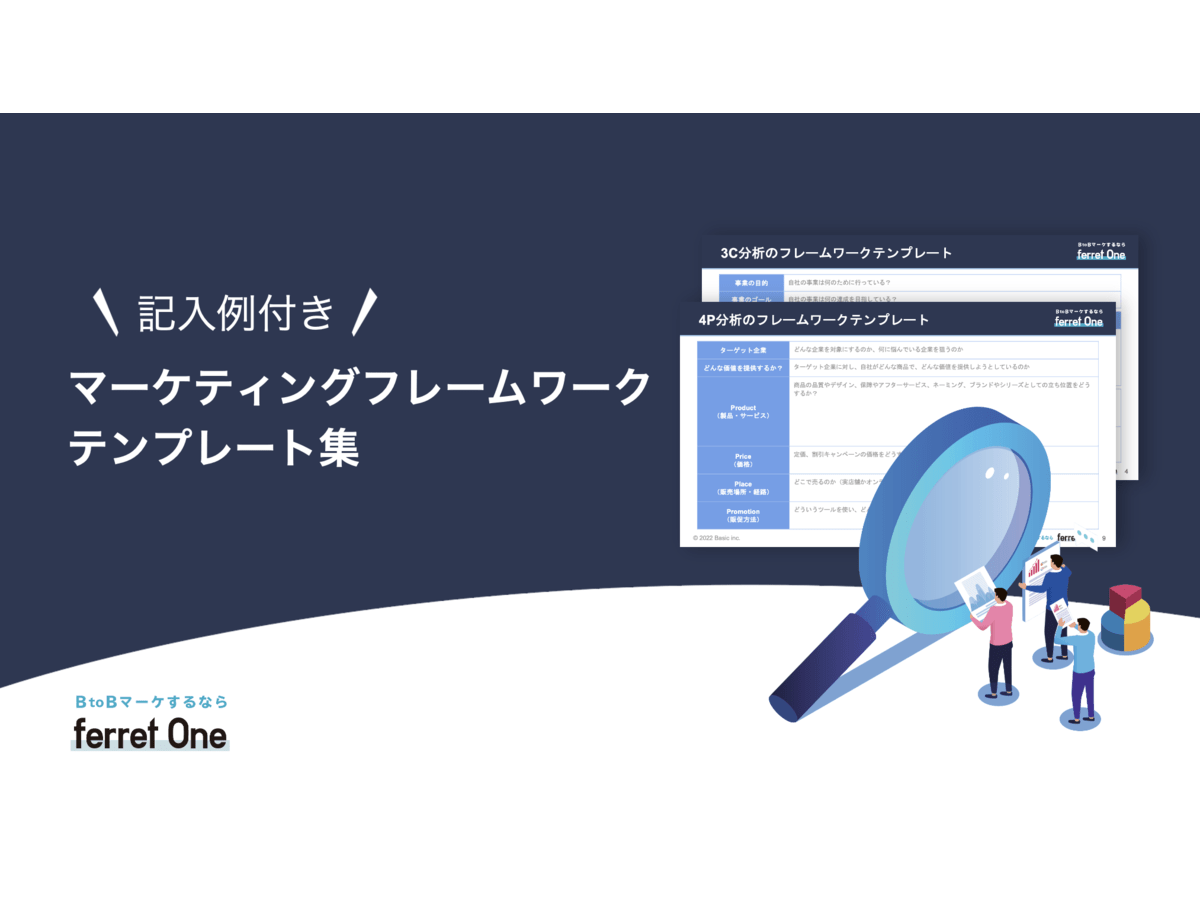
【記入例付き】マーケティングフレームワーク テンプレート集
各フレームワークごとに、BtoBの記入例を3種類ずつ添付しました。
相関関係とは
相関関係の意味は、広辞苑では、「一方が他方との関係を離れては意味をなさないようなものの間の関係。」と説明されています。
例えば「父と子」「右と左」「上と下」は片方を軸として説明されている概念であり、相関関係があるでしょう。また、数学の世界では*相関関係とは「一方が増加する時、他方が増加もしくは現象する傾向が認められるという二つの量の関係」*とされています。
つまり相関関係とは、AとBの事柄になんらかの関連性があるものを表しているでしょう。
例えば「時間の経過」と「空に浮かぶ太陽の位置」には相関関係があります。朝には東の低い空にあった太陽は、時間の経過と共に南から西へと移動していくでしょう。しかし、この2つの事柄に因果関係はありません。
因果関係とは
では、因果関係とはなんでしょうか。広辞苑において因果関係とは「原因とそれによって生ずる結果との関係」とされています。わかりやすいものでいうと、仏教の教えにある「因果応報」という言葉があるでしょう。これは、過去に行った所業によって現在の身にあらゆる事柄が起こるという考え方です。
つまり、因果関係とは、Aを原因としてBが変動することを指します。先ほどの例を出して言うと「時間の経過」と「空に浮かぶ太陽の位置」に因果関係はありません。時間を原因として太陽が動いているわけではないからです。もし地球が自転を止めて、時間がいくら経過しても空に浮かぶ太陽の位置が変わることはありません。
相関関係と因果関係の関係

整理すると
相関関係:AとBの事柄になんらかの関連性があるもの
因果関係:Aを原因としてBが変動すること
です。
「相関関係」の中でも、原因と結果を表しているものだけが「因果関係」として表記されます。つまり、因果関係のあるものには相関関係がありますが、相関関係は必ずしも因果関係とはならないことを頭に入れておきましょう。
参考:
「相関関係」と「因果関係」の違いを理解すれば根拠のない通説にだまされなくなる!
小学館『精選版日本国語大辞典』
岩波書店『広辞苑第六版』
因果関係の把握がビジネスにおいて必要な理由
ビジネスにおいて、因果関係を把握することはどのように役立つのでしょうか。マーケティングに限らず、ビジネスの場ではデータ分析を用いて新規の企画をしたり、次の戦略を決めたりすることが多いでしょう。
例えば商品の売上や来客が減った原因、客単価が減った原因など、せっかくデータを分析し考えられる原因を改善したとしても、そもそもその事象との因果関係がなければ意味がありません。データ分析において、因果関係を正確に把握することは、次の計画を立てる上でとても重要なことだと言えるでしょう。
相関関係と因果関係を誤読してしまう理由
相関関係と因果関係を誤読してしまうのは、データ上では同様のものとして表示されてしまうからです。ビジネスでも同様のことはしばしば起こります。
例えば、ネットショップの利用回数と利用額の関係性を例に考えてみましょう。
ネットショップの利用回数と利用額に因果関係はある?

上記は、ネットショップで商品を購入した顧客それぞれの「利用回数」と「利用額」をグラフにしたものです。このグラフをみると*「利用回数が多い顧客ほど、利用額が多い」という相関関係が見えます。ならばこの結果から「利用回数が多くなるほど、利用額が高くなっていく」*という因果関係を導き出していいのでしょうか。
その考察には検討の余地がありそうです。なぜなら*「利用額が高い=そのネットショップで気に入った商品が多い」顧客が、何度も利用している可能性*があるからです。つまり、最初から利用額の少ない=気に入った商品が少ない顧客は1、2回で利用をやめてしまい、最初から利用額が高い顧客だけが何度も利用しているだけかもしれません。
「利用回数が多いほど利用額が多くなるんだったら、利用回数を増やす施策を打てば利用額を増やせるだろう」と考えるのは誤りです。利用金額が少ない顧客に対してクーポンを発券して再度の利用を促しても、2回目にやってきた時に気にいる商品がなければ利用額は上がりません。
このように、一見原因と結果に見えるようなことであっても、因果関係があるとは限りません。
参考:
「相関関係」と「因果関係」の違いを理解すれば根拠のない通説にだまされなくなる!
散布図|なるほど統計学園高等部
正しい因果関係を見つけるためのポイントは?
正しい因果関係を見つけ出すには、どういった点がポイントとなるのでしょうか。それには大きく分けて4つのポイントがあります。
1.データの裏にある背景を考える
例えば、渋谷駅前のスクランブル交差点で交通量と年齢層の調査を行ったとします。その時「交通量が増加するのに伴って、交差点を通過する人の平均年齢が下がった」としましょう。そのことから*「交通量が増えるから、交差点を通る人の平均年齢が下がる」*と言っていいのでしょうか。
こんな時はデータのもとであるサンプルにはどんな背景があるのかを考えるようにしましょう。渋谷駅前のスクランブル交差点は、昼頃には周辺にあるオフィス街のサラリーマンも利用します。しかし、夜には高校生や大学生など多くの若者が繁華街であるセンター街に向かうでしょう。
その結果*「交通量の少ない昼の平均年齢は高くなり、交通量の増える夜には平均年齢が低くなる」*ことになります。交通量そのものが平均年齢を引きげているわけではないことがわかるでしょう。
2.相関関係にある2つの要素以外にも関わる要素がないか考える。
例えば、100人に対して血圧と所得額の調査を行ったとします。その時「血圧が高い人ほど、給与が高かった」という相関関係が生じた場合、「血圧が高い人ほど給与が高くなる」という因果関係を導くことはできません。
それは、年齢という3つめの要素を見逃しているからです。通常、年齢が高い人ほど血圧が高くなり、年齢が高い人は給与が高くなる傾向にあります。そのため、データ上では年齢が高い人ほど血圧が高くなるように見えてしまうのです。
*このように2つの要素以外に根本的な原因がある場合があります。*何か因果関係があると思ったら、他にも関わる要素がないかどうか考えてみるようにしましょう。
3.周辺のデータも合わせて確認する
因果関係を見つけ出した時には、もとにしたデータ以外にも根拠を強化する別データも探すようにしましょう。
例えば、複数の地域に対して電灯の数と犯罪発生件数の調査を行ったとき「電灯の数が多いほど、犯罪の発生件数は少なかった」とします。この時、他の地域・国での調査結果や、犯罪を行っている人のヒアリング調査など周辺にあるデータをもとにして、根拠の裏付けを行うようにしましょう。
4.十分なサンプルを用意する
どのような調査であっても、十分な数のサンプルを用意しなければ因果関係があるとは言えません。また、サンプルの属性が偏っている場合も、正しい因果関係が見つけられないことがあるでしょう。調査に見合ったサンプルを用意するように注意してください。
「本当に因果関係があるのか」をよく考えてみよう
AとBの事柄に関係があるものを「相関関係」と言い、その中でも、Aを原因としてBが変動するものを「因果関係」と言います。相関関係があるからと言って、必ずしも因果関係があるわけではありません。
しかし、データだけをみると関係性があるので「因果関係がある」と判断してしまうこともあるでしょう。大切なのは、「本当にこの2つの事柄に関係性はあるのか?」と疑って見ることです。複数のデータを検証するだけでなく、データの裏にある人間心理や環境を考えるようにしましょう。
資料作りに役立つ資料ご紹介
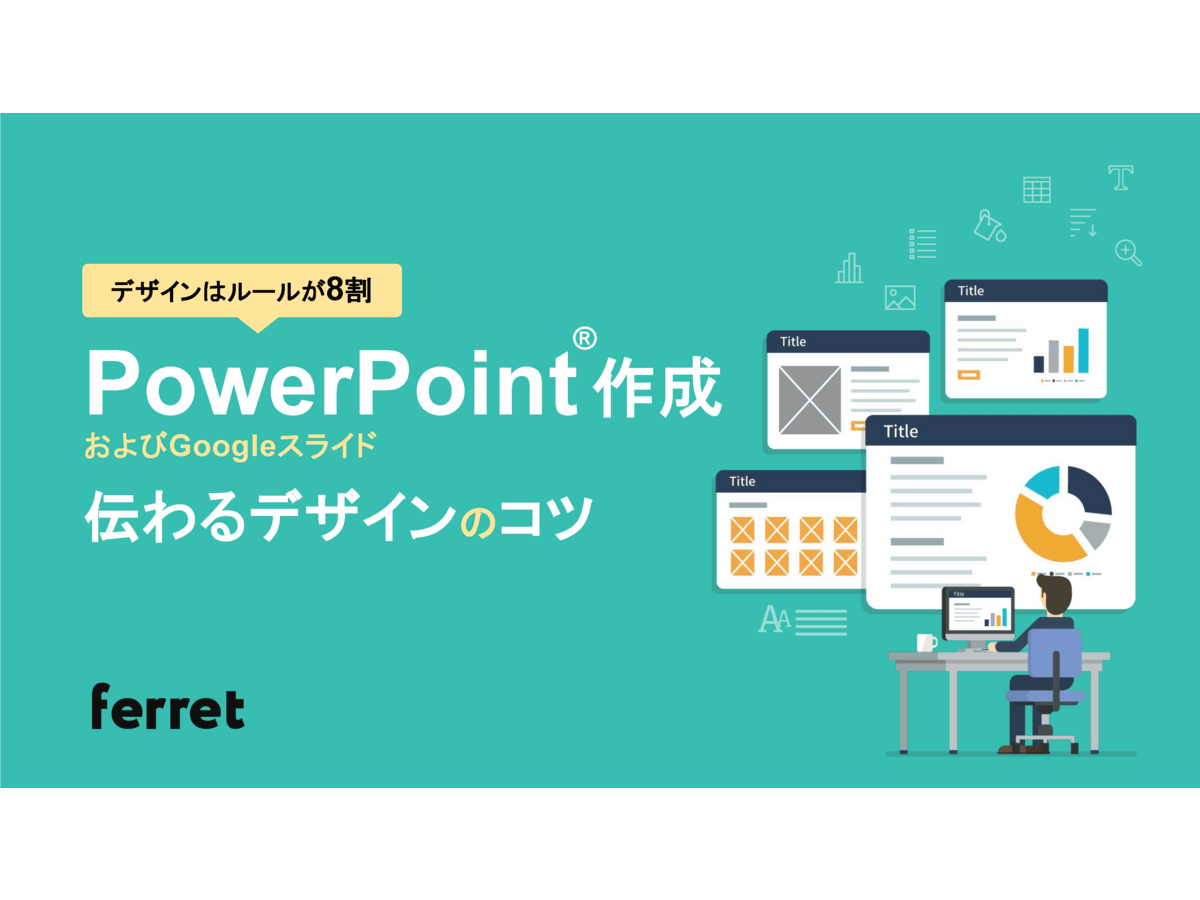
【パワーポイント作成】伝わるデザインのコツ
ほんの一手間で驚くほど見やすく変わる!パワーポイントやGoogleスライドなど資料のデザインを見やすく仕上げるコツを解説します。
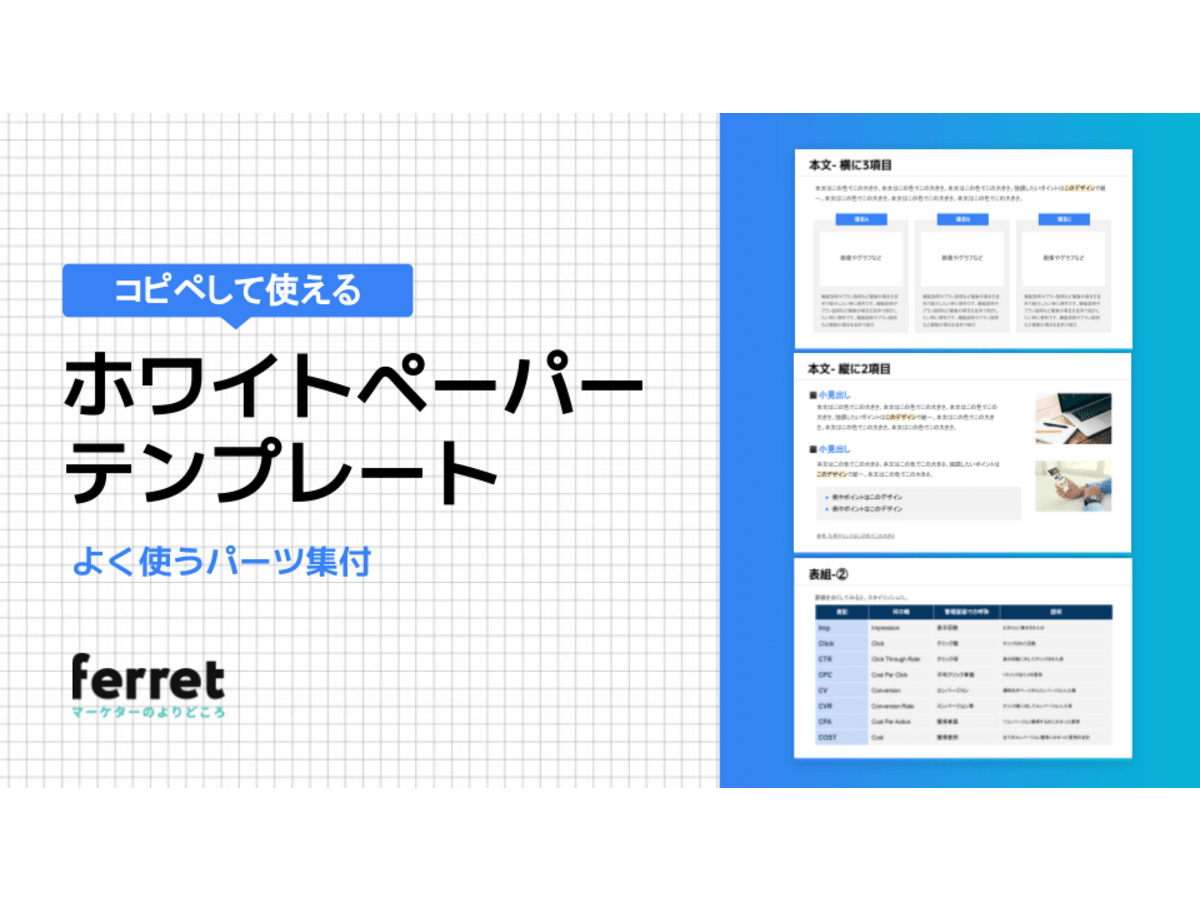
コピペして使える!ホワイトペーパー テンプレート(ppt形式)
ferretのホワイトペーパーなどでよく使うページレイアウトやパーツをまとめました。デザイナー視点での一言アドバイス付き。コピーして色を変更するなどして是非ご活用ください。
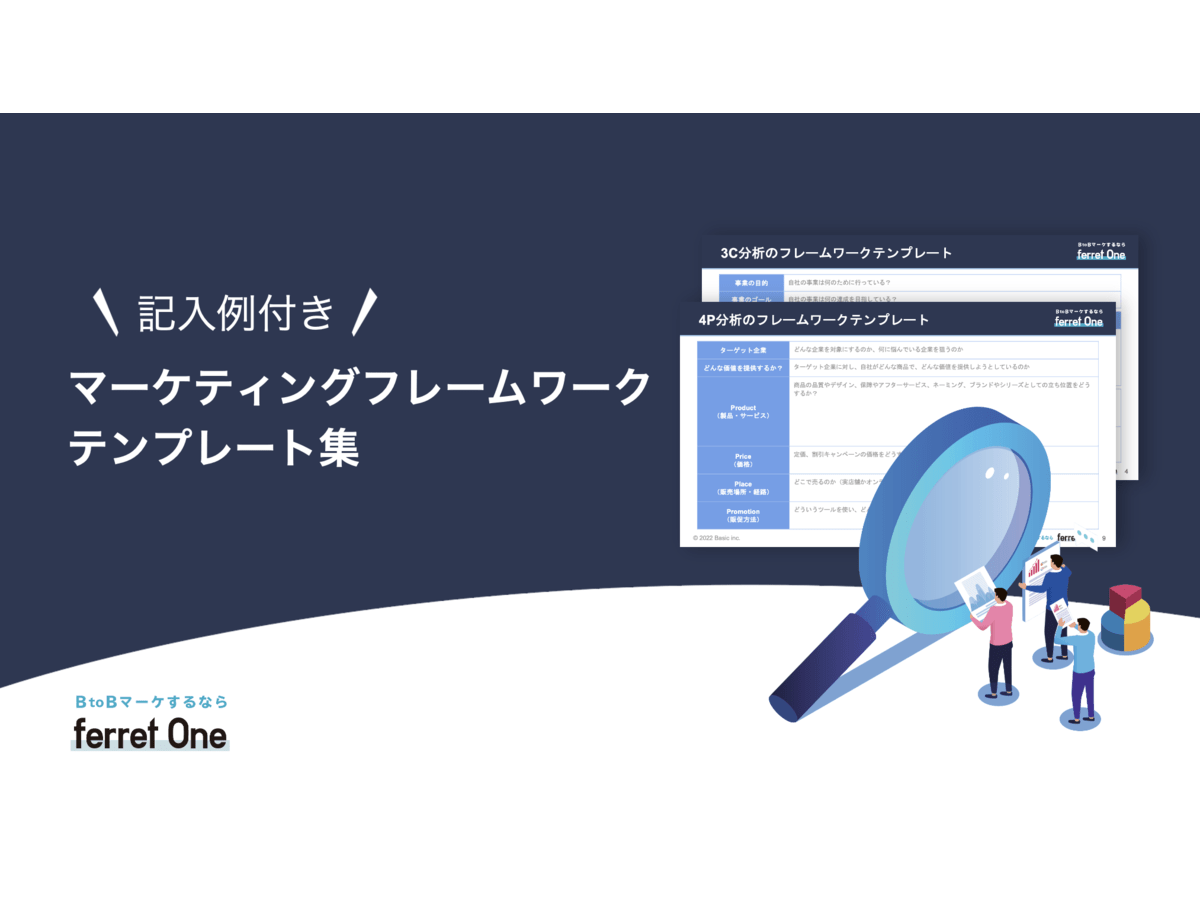
【記入例付き】マーケティングフレームワーク テンプレート集
各フレームワークごとに、BtoBの記入例を3種類ずつ添付しました。
こちらも合わせてチェック

無料でデータを可視化して効率化できる!Google Data Studioとは
日々多くの情報に触れるマーケターにとって、データの一元管理や視覚化は、情報の取捨選択と同じくらいに重要な手続きです。そんなマーケターの手間を省略し、データドリブンな改善、施策の手助けをしてくれるのが「Google Data Studio」。この記事ではGoogle Data Studioについて、基本的な情報や特徴、メリット、簡単な操作方法を解説しています。

論理的思考とは?〜基礎知識からトレーニング方法まで解説
ビジネスを行う上では、論理的に考える力が求められます。論理的思考ができれば、会議やプレゼンで、筋道を立ててわかりやすく相手に説明することができます。今回は論理的思考の概要を解説し、オススメ書籍も併せて紹介します。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 単価
- 商品1つ、あるサービス1回あたり、それらの最低単位での商品やサービスの値段のことを単価といいます。「このカフェではコーヒー一杯の単価を350円に設定しています」などと使います。現在、一般的には消費税を含めた税込み単価を表示しているお店も少なくありません。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他