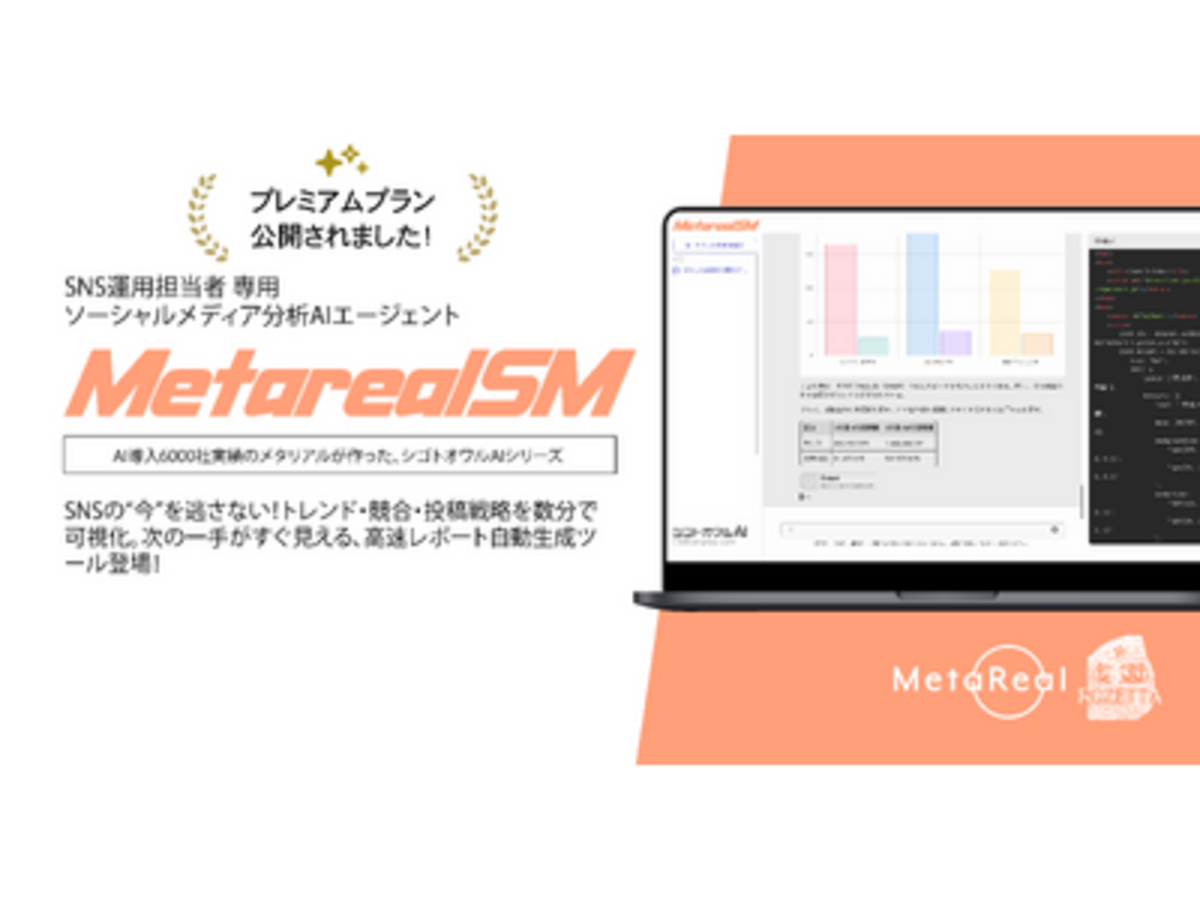Twitterだけでは不十分?ソーシャルリスニングをWeb全般の炎上対策に活用しよう
炎上という言葉もかなり一般的になり、ソーシャルメディアの持っている怖い側面を多くの人が理解するようになりました。ソーシャルメディアの普及からしばらく経ちがリテラシーも向上してきてはいます。
しかし、自分がWeb担当者となって矢面に立ちネガティブな投稿と向き合わなければいけなくなった時、冷静に対処できる人はまだまだ少ないのではないでしょうか。
今回は、ソーシャルリスニングを活用したリスクモニタリングについて解説していきます。
ソーシャルリスニングを使ってリスクモニタリングをしよう
ソーシャルリスニングのツールを利用すれば、あらかじめ設定されたキーワード群を元にさまざまなソーシャルメディアの投稿を収集することが可能です。ソーシャルリスニングはブランドの反響を調査するだけではなく、ネガティブな投稿、リスクとなりうる投稿も検知します。このソーシャルリスニングを活用すれば、ソーシャルメディアに日々投稿される炎上の種や素早く拾い上げ、拡散する前の対応ができるのです。またお客さんの不満などを出来る限りリアルタイムにキャッチできれば、より素早いサービス改善に役立ちます。
炎上リスクはTwitterだけに潜んでいるわけではない
ソーシャルリスニングで検知できるのはTwitterなどの一般的にSNSとして認知されているものだけではありません。Yahoo!知恵袋などのQ&Aフォーラムサイトや2ちゃんねるといった匿名掲示板、Amebaブログなどのブログサービスに書き込まれる記事やコメントなど、さまざまなメディアで日々発信される情報をキャッチします。ツールによって取得できるメディアの幅は異なりますが、リスクモニタリングに活用したい場合、できるだけ多くのメディアに対応していると良いでしょう。
その理由の一つは、お客さんの不満や炎上の火種が投稿されるのはTwitterに限定されるものではないからです。扱われている製品やサービスの特性によって、どのメディアに投稿されやすいかの傾向は変わってきます。また、お客さんと製品、サービスとの関わり方によって、リスクとなる情報が流出しやすいメディアは変わってきます。
例えば、ちょっとした接客対応の悪さや製品の不良などは、Twitterに投稿されやすい傾向にあります。友人に対して「ちょっと聞いてよ!」といった感覚で、愚痴を聞いてもらって発散したいといった心理が影響いると考えられます。また、自社内での不平不満といった個人が特定されてしまっては困る内容は2ちゃんねるのような匿名掲示板に投稿が集まります。
このように、単にソーシャルリスクモニタリングといってもTwitterだけでなくさまざまなメディアを網羅的に監視していく必要があります。
メディアの特性によって書き込まれるリスクが違う
単純な小売や接客サービスなどに関する不満はTwitterなどでインスタントに書き込まれる傾向がありますが、購入の検討に時間がかかる製品やサービスなどの場合、モニタリングしなくてはいけないメディアが変わってきます。
住宅メーカーを例に挙げてみましょう。住宅メーカーの場合、購入を決定するまでに結構な時間を要します。そのプロセスは、住宅展示場に行って営業担当との話をして、見積もりを出して何度も打ち合わせをして、やっと契約。その後も引き渡しまでの間にかなりの時間、顧客と密に関わることになります。
住宅の工法やお金のことに詳しいお客さんは中々おらず、長期間不慣れなことの判断を迫られ不安に思います。決断次第で何千万ものお金が関わってくるため、できる限り有識者の意見を聞きたいと考えます。そのため、住宅メーカーを検討しているお客さんは、Yahoo!知恵袋など専門的な情報が得られるメディアに質問を投稿する人が多くいるのです。Yahoo!知恵袋に寄せられる質問は、困っているユーザーの生の声が集まっており、何に困っているのかが事細かに記載されています。営業の対応の質向上のためのフィードバックとして活用でき、トラブルの種の早期発見につながることもあり、重点的にモニタリングする価値があります。
営業担当の対応が良くないなどの単純な不満などはTwitterに投稿されることもありますが、住宅に関する法務的なトラブルなどがあった場合はブログなどしっかりと長文で説明できる場所に投稿されることが多いです。意志を持って抗議しようと考えるお客さんは、しっかりとした証拠をブログにまとめ、場合によっては工事の瑕疵があった場所を動画に撮ってYouTubeにアップロードされるなどのリスクもあります。
メディア毎に適切な対応は異なる
では実際にリスクとなりうる投稿を検知した場合、どのように対処すると良いのでしょうか?
Q&Aフォーラムサイト
Yahoo!知恵袋などQ&Aフォーラムサイトの場合、現在進行形で悩んでいるお客さんであることが多いです。本当に知見のある人の回答を必要とされているため、担当者が実際に回答しても問題ありません。その際に、業界関係者である旨を記載すると信頼感が増します。自社に対する質問の場合、社名を出して回答するかは慎重に検討してください。誠実な対応として好感度が上がる場合もあれば、監視されている、自社に都合のいいことを言って誘導しようとしているなどと嫌悪感を抱かれる場合もあります。
Twitterはサービスの特性上情報拡散にとても適しており、炎上のリスクが最も大きいメディアです。特に細心の注意を払って対応する必要があります。メディアの特性上、投稿者に対して直接リプライを送ってコミュニケーションすることも可能です。ただ、ほぼ確実に誰かにスクリーンショットを撮って保存されてしまうものと考え、迂闊な回答をしないよう徹底的に心がけましょう。
緊急の対応を要する場合、まず状況を整理し事実関係を確認しましょう。もし、自社に非がないことを証明できるのであれば、証拠を出しながら誤解のないよう説明することで、ユーザーに納得してもらえる場合もあります。
参考:賞賛と炎上を分けるもの
(2013年、チロルチョコに虫が混入したというツイートに対し、工場出荷後に混入した根拠を説明した例)
また、ユーザーのちょっとした困りごとや疑問などに対しては、公式がリプライで説明してあげることで、丁寧な対応をしてもらえたとして好感度が上がるというケースも多くあります。
2ちゃんねる
2ちゃんねるは匿名掲示板であるため、内部告発など機密性の高い情報漏洩のリスクが考えられます。ただ、発信する側も匿名であり、信憑性という面では低く相手にされないというケースも多くあるようです。また1スレッドに対して1000投稿までという制限もあり、メディアの特性上拡散のリスクは低いことが一般的です。投稿者に対してコメントするなど中途半端に介入してしまうと、揚げ足を取られる可能性もあり避けた方が無難。内部の人間から発言の可能性もあるため、内容をしっかり把握した上で調査するといいでしょう。炎上するほど盛り上がってしまった場合には、スレッド場で釈明するのではなく、公式リリースなどで対応しましょう。
ブログ
ブログに掲載される要注意投稿は、140文字の制限があるTwitterとは違い、筋道を立てて状況を説明している場合が多いです。詳しい情報が載っていることが多く、モニタリングする側にとっても問題点を理解し対応を検討できます。
しかし、ブログ上で投稿者と直接コミュニケーションすることは難しいです。コメント欄が設置されていることが多いですが、もし意志を持って抗議しようと投稿している場合は火に油を注ぐだけです。また、ブログの場合検索エンジンにも残りやすいため内容によっては長期的なリスクにもなり得ます。状況をしっかり理解し、根本的な解決に向けた対策を検討しましょう。
まとめ
各メディアの特性によって検知されやすいリスクの傾向などはありますが、ベストの対策というのはやはりケースバイケースです。あくまでガイドラインとして考えてください。いずれにせよ、あらゆる対策も早期発見が1番のアドバンテージです。ソーシャルリスニングをうまく使いこなし、被害を最小限に抑えるよう日々モニタリングしていきましょう。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他