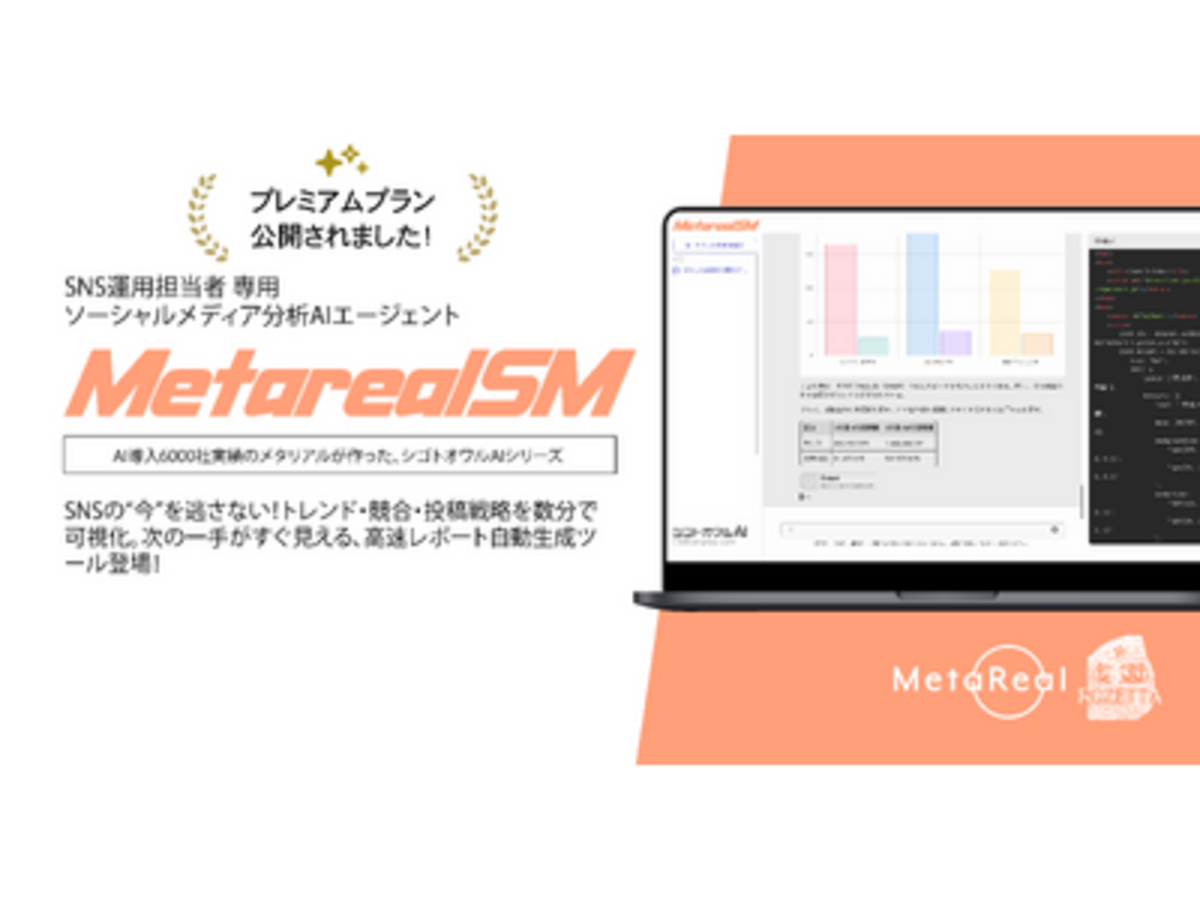これからソーシャルメディア運用を始める方は要チェック!担当者がやりがちな「失敗」ポイント
せっかく自分がWeb担当者になったからには、ソーシャルメディアを活用して効果的なマーケティングをしたいと考える方は多いのではないでしょうか。今の時代、ソーシャルメディア運用くらい最低限やっておかないといけないといった危機感を持っている方もいるかもしれません。
しかし、ソーシャルメディアの運用というのは面倒なことがたくさんあり、一筋縄ではいかないものです。対社内、対社外それぞれに、失敗に陥りやすいポイントというのが、いくつかあります。
今回は、ソーシャルメディア運用で陥りがちな失敗と対策をまとめました。
起こる可能性のあるミスは、事前に把握しておくことで防止策を講じることができます。
これからソーシャルメディアマーケティングを始めたいという方も、運用しているけど行き詰まっているという方もぜひチェックしてみましょう。
そもそも、ソーシャルメディア運用は手間がかかるもの
Twitterやfacebookといったソーシャルメディアは個人単位で気軽に活用されており、かつ無料のツールとしてとても身近です。時代に合った手法として、ソーシャルメディアの運用は最低限やっておかないといけないいと考える人も多位でしょう。
個人で何の気なしに使っているサービスであるため、とても簡単に活用出来ると勘違いしがちですが、企業の顔となり業務の一環として投稿する以上、考慮しなくてはいけないことがたくさんあります。考慮しなくてはならないことが多ければ多いほど、検討に時間がかかるのです。
自分に決定権がない場合は、上長との相談や稟議の手間もあります。ソーシャルメディア運用を考えるのであれば、まず「片手間でできるから」という考えは捨てた方がいいでしょう。
対社内で陥りやすい失敗ポイント
ソーシャルメディアを導入しようと意気込んでも、アカウントを開設する前に社内でのやりとりつまずく場合もあります。
そもそも社内でソーシャルメディアに対する理解がない
幅広い年齢層がソーシャルメディアを利用するようになってはいますが、ソーシャルメディアに触れたことがない方が社内にもいらっしゃるのではないでしょうか。決定権を持っている上司の方が、ソーシャルメディアに慣れていないという場合もあり、なかなか理解を得られないというケースも多くあります。
また、ソーシャルメディア運用はすぐにわかりやすい効果が出るわけではありません。0から始めようと思うと、運用を開始する必要性を説得するのに他社事例を調べたり、資料を作って稟議に上げたりと色々と手間がかかってしまいます。
社内ポリシー、情報セキュリティ面で承認がおりづらい
会社の規模が大きくなればなるほど、情報セキュリティの監査などが厳しくなってきます。企業名やブランド名を出すか出さないか、営業活動が目的かなど、情報セキュリティやコンプライアンス、ブランド管理の部門などに細かくチェックを受ける可能性もあります。
現場担当者レベルで盛り上がって企画をしても、社内でたらい回しにされ、どこかの部署が首を縦に振らないため運用を開始できないというパターンも少なくありません。
現場単位で陥りやすい失敗ポイント
社内での承認が降りいざアカウントを開設した後でも、陥りやすい失敗ポイントは多く存在します。実際に運用をする現場単位でも時間や人的リソースといった課題があります。
意外に時間が取れない
運用を開始したとしても多くの場合はソーシャルメディアの対応に専門の担当者を立てられず、どうしても業務の片手間になってしまいます。日々色々な業務を回す中で、コンテンツの案を考え、慣れていないうちは効果が出る方法について勉強する時間も必要です。
上長とのコンテンツ確認に手間がかかる
社内の体制にもよりますが、投稿内容は事前に一度上長が目を通すというルールになることも多いです。現場担当者の一存で投稿し、誤った情報を流してしまうなどの、コンプライアンス面で問題になるリスクを回避しようとすると、やはりそれ相応の手間がかかってくるものです。
また代理店に運用をお願いする場合にも、確認が遅れて投稿スケジュールがずれてトラブルになるというケースもあります。
担当者不足に陥る
ソーシャルメディアを使った大々的なキャンペーンをやるようなことがない限り、大抵の場合は担当者が2、3人で運用しているケースが多いでしょう。会社の規模が小さければ、担当者が1人しかいないことも少なくありません。
担当者が退職してしまったり、人事異動などで部署から離れてしまうなどのタイミングで、全然活用されなくなることも考えられます。特定の社員のリソースに依存してしまうと、その人が動けなくなった途端に運用できなくなってしまい、勿体無い状況になります。
運用上で陥りやすい失敗ポイント
実際に運用をしていく中で、どう進めていいかわからなくなるという方は多いでしょう。また、時には炎上というリスクもつきまとってきます。
そもそも目的がはっきりしていないまま運用している
案外やりがちなのが、運用の目的やゴールがはっきりしないまま、なんとなく運用してしまっているパターンです。
運用の目的が広報なのか、ブランディングなのか、サイトへの誘導なのかなど曖昧なまま形骸化してしまうケースは多いです。
すぐネタ切れになってしまい、アイデア出しに追われる
目的がはっきりしていない場合に特に多いですが、何を投稿すればいいのかが思いつかずすぐネタ切れになってしまいます。かといって1ヶ月に1回程度しか投稿しないのであれば、当然フォロワーもつかず、運用している意義がなくなってしまいます。また、アイデア出しに追われると、他の業務の時間を圧迫することになってしまいます。
フォロワーがつかずに迷走する
ソーシャルメディア運用をする上で、やはりフォロワーの数は気になるものです。フォロワーがいなければ、せっかく投稿内容を練ってもあまり意味がないと感じてしまいモチベーションを保つことは難しいです。
フォロワー数はわかりやすい数値なため、社内から評価を受けるときに見られることも多いでしょう。フォロワーが増えるのには時間がかかりますが、数値だけで判断されてしまうと全然効果が出てないのではないかと判断されてしまいがちです。
また、フォロワーを急激に増やしたいからといって、相互フォローを謳っているアカウントを無作為にフォローしていくという手法もやりがちです。そもそもしっかりとタイムラインを見ているアカウント、自分に興味がありそうなアカウントからフォローされないとあまり意味がありません。また一度に大量にフォローしすぎるとアカウントが凍結されたり、すぐフォロー数上限に達すること考えられます。
ただニュースを流すだけのアカウントになる
ネタがなくなってきて工夫をしなくなると、ニュースやお知らせを投稿するだけになりがちです。定期的にお知らせが欲しい自社のファンであれば問題ありませんが、それ以外の人はお知らせbot化してしまっているアカウントをフォローし続ける理由はありません。
炎上の火種を作ってしまう
ソーシャルメディアの失敗談で1番取り上げられるのは、やはり炎上です。SNSと炎上についてはニュースに取り上げられることも多く、ソーシャルメディアを活用することはリスクというイメージがついてしまい、社内の承認が降りにくくなる要因の一つにもなります。担当者が個人的なアカウントと混同して投稿をしてしまったり、意図せず特定の人の反感を買ったり、コンプライアンスに抵触していることに気がつかないなどが原因となる場合が多いです。投稿する前に複数人でチェックするフローは徹底するといいでしょう。
まとめ
個人で使う分には気軽というイメージがありますが、ソーシャルメディアを活用したマーケティングはしっかりとした業務です。始めるからには、愛情と根気を持ってアカウントを育てていかないといけません。一度見直してみる機会になればと思います。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ソーシャルメディアマーケティング
- ソーシャルメディアマーケティングとは、マーケティングにソーシャルメディアを用いる手法のことです。たとえば、TwitterやFacebook、Google+やLINEなどのソーシャルメディアに定期的に投稿し積極的にユーザーと交流することで、自社のホームページのPVアップや商品の宣伝効果を狙います。なお、ターゲットとなるユーザーがソーシャルメディアを使用していない場合、ソーシャルメディアマーケティングを行うと効果が期待できないので注意が必要です。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他