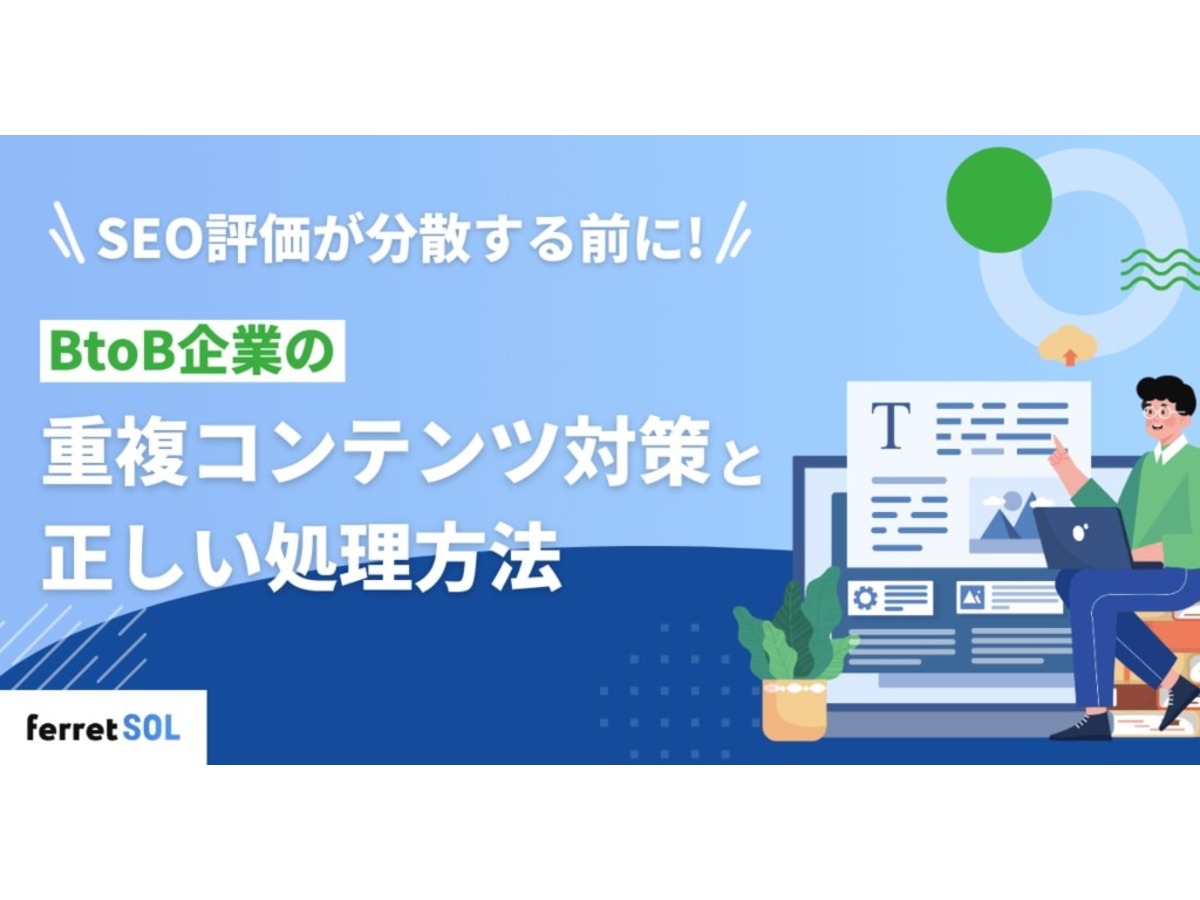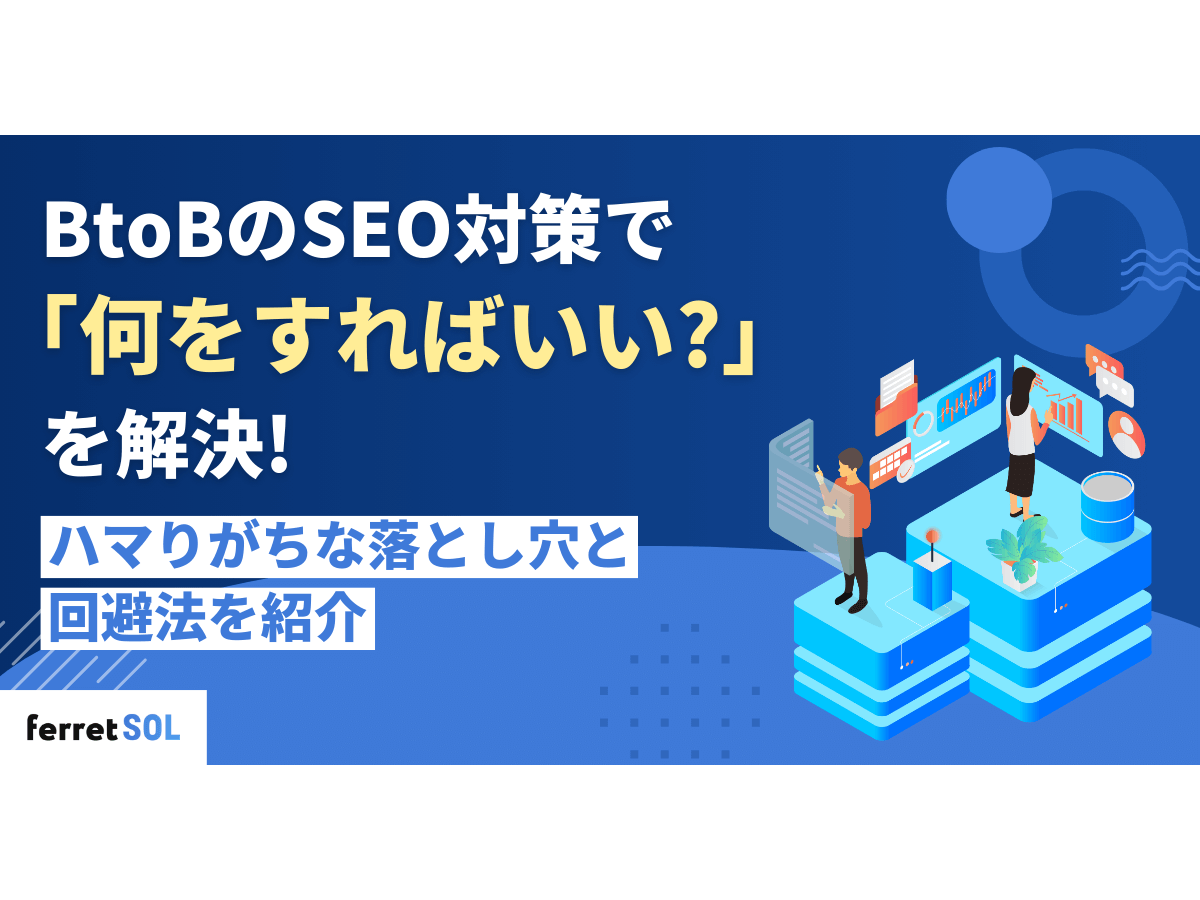ホームページに必要不可欠!重要項目「検索ボックス」の位置パターン7選
ユーザー体験を追求する専門家「UXデザイナー」は、Webマーケティングにおいては今でも非常に重要な役割を担っており、Amazonの求人でも300種類以上の求人情報が掲載されています。
"ユーザー体験の向上" にフォーカスを当てた時、様々な項目が列挙されていますが、大抵の場合検索ボックスをどこに置くかは後回しにされがちです。しかし、検索ボックスの場所を(ホームページ内の)どこにするかは、そのサイト自体の生命線を握るといっても過言ではないほど重要な項目の1つです。
そこで今回は、検索ボックスの位置パターン7選を紹介します。
本記事を参考に、皆さん「どこに検索ボックスを置くべきか」を考えてみてください。
検索ボックスの「場所」が売り上げにつながる?

検索窓の大きさや位置などを最適化させる手法のことを、SEO(Search Engine Optimization)になぞらえて、SBO(Search Box Optimization / 検索窓最適化)と言うことがあります。
昨今のサイトの情報量は以前と比較しても圧倒的に多くなっており、ユーザーが求めている情報を瞬間的に提示することが非常に重要です。検索ボックスはユーザーが欲しい情報へと導く重要な役割を果たしていることは言うまでもありませんが、それにもかかわらずサイト全体のUXに比べ、検索ボックスのユーザビリティ改善が後回しになってケースがあとを絶ちません。
2004年からAmazonのサイト内で使われているA9という検索エンジンは、日々改善が行われており、同社がどれほど検索エンジンを重要視しているかが垣間見られます。また、Yahoo!Japanのトップページでも、検索窓の高さを6ピクセル変えただけで、広告収入を4億円以上変えたというデータも存在します。
そうした検索ボックスのベストプラクティスを考える上で、デザインを再考したり自動検索機能などのユーザビリティ改善にかかわる機能を実装したりするのは、もちろん重要です。しかし、どんなに素晴らしい検索ボックスだとしても、そもそも認知されなければ「存在しないのと同じ」です。
つまり、SBOにおいて最優先すべき事項は「どこに検索ボックスを置くか」ということです。
パッと見て検索ボックスが認知されると、ユーザーがサイトを利用する際の利便性は大きく向上します。ここでは、検索ボックスの7つの位置パターンをご紹介します。
検索ボックスの位置パターン7選
1. 上部右側

昔から**「検索ボックスといえばこの位置」**としてよく置かれている場所が、上部右側のエリアです。はてなブックマークのトップページや日経新聞のホームページ、Wikipediaなど、トラディショナルなWebサイトの多くがこの位置に検索ボックスを置いています。
ferretのデスクトップ版もこの位置に検索ボックスを置いています。
ホームページのロゴを左上に置くのは長い時間Webデザインの「テンプレート」にもなっており、ロゴとのバランスを保つためにこの位置に検索ボックスを置くことが多いようです。この位置の検索ボックスは「目立つ」とまではいかなくとも、ユーザーもある程度この場所に検索ボックスがあることを「予知」することができるため、ユーザビリティの観点からも理にかなっていると言えます。
しかし、トラディショナルなWebサイトの多くは、検索ボックスが*「小さめ」になってしまいがち*です。場所としては問題なくとも、検索ボックスのサイズを再考したほうがいいケースがあるのは留意しておくべきでしょう。
2. 上部中央

ページの中央部に堂々と検索窓を配置するサービスも増えています。

Amazonのホームページでは若干右寄りではありますが、中央部に大きな検索窓を置いて、誰が見てもわかるようにしています。また、この例を何年も続けているのがYahoo! JAPANで、ページ上部に置かれている検索窓が存在感を放ちます。楽天もこの位置に大きめの検索ボックスを置いています。
ページ上部の中央部に検索窓を置いているサービスは、比較的検索が生命線を握っているサービスです。パッと見た時に検索エリアが目に飛び込んでくるので、よく考えられたポジショニングであると言えます。
3. 上部左側

以前はあまりスタンダードではありませんでしたが、最近よく見られるようになったのが上部左側に検索ボックスを置くパターンです。

このパターンで確認すべきは、Airbnbのホームページでしょう。以前のAirbnbのページはヒーローヘッダーを置いて、そこに検索ボックスを配置するパターンでしたが、現在では小さなロゴの隣にシンプルでわかりやすい検索ボックスを配置しています。
この位置は、デジタルコンサルティングファームのニールセンが提唱しているF字パターンの**「視点のはじまり」**とされる場所で、ほぼ全てのユーザーが目にする場所でもあります。この場所には大きくて目立つロゴを配置したいと考えているデザイナーも多くいるでしょうが、ロゴデザインをシンプルにしてその隣に検索ボックスを置くことで、ユーザビリティが大きく向上します。
コンサルタントのグラハム・カールトン氏による調査によれば、この位置に検索ボックスを置いているのは、イギリスの著名な50サイトのうちでたったの1サイトだけだったそうです。
先例がまだ少ないですが、逆に言えば検索ボックスの位置を変えるだけでもユーザーの検索率が向上する可能性もある場所なので、検索ボックスの移動を検討してみてはいかがでしょうか。
4. サイドバー

Webサイトの中でもブログ系のサイトの中に多いのが*「サイドバー」*に設置された検索ボックスです。
ブログサイトの多くは2カラムか3カラムになっており、そのほとんどが右側のカラムに検索ボックスを置いています。
ブログサイトの運営者にとって、サイドバーを右カラムに設置するのはサイトの構成上都合がいいことですが、ユーザビリティを考えるとこの位置がベストポジションかどうかは考える必要があるでしょう。なぜなら、スクロールしてしまうと見えなくなってしまうからです。サイトによっては、スクロールしてもサイドバーがくっついてくるような、ユーザビリティを考慮したケースが見られます。
しかし、トップヘッダーを固定する場合と違って、サイドバーの固定はより多くの面積を必要とするため、本当にこの場所が妥当かどうかを検討してみたほうがいいでしょう。
5. インライン

旅行サイトや飛行機のチケットサイトなどは検索ボックスを上部ではなく、*インライン(つまりページの内部)*に堂々と配置するケースがあります。これは旅行サイトや飛行機チケットサイトの特性と関係しており、すでにユーザーは検索前提でサイトを訪問するからです。
ユーザーが検索前提でやってくるのであれば、検索エリアを目立たせていくのは当然の流れです。

例えば、Booking.comでは検索ボックスをちょうどページの真ん中に表示しています。スクロールをすることでこの部分の検索ボックスは隠れてしまいますが、その代わりに上方から別の検索ボックスが登場します。
6. ど真ん中

Googleのホームページや百度(Baidu)のホームページなど、検索が前提のホームページはページの上下左右で*「ど真ん中」*に配置しています。
検索行動を行う前には余計な情報を一切表示しない潔さによって、ユーザビリティを極限まで高めることに成功しています。
7. 隠れた位置

AppleのホームページやAdobeのホームページのように、検索よりもカタログのような役割を果たしているサイトの多くは、いわゆる*「虫眼鏡アイコン」*だけを残して、検索ボックスを隠すことをしています。

検索ボックスを隠すことでデザイン上の違和感を払拭することができる反面、ユーザビリティの上では2つの点でリスクも孕んでいます。
まず、ユーザーが検索ボックスをそもそも認識できないという問題が発生する可能性があります。ユーザーは横長の四角形を認識することで検索ボックスであるということを認識しますが、虫眼鏡だけがあってボックスがないということに戸惑うユーザーがいるかもしれません。また、仮にユーザーが虫眼鏡を認識したとしても、クリックして初めて検索ボックスが登場するので、「クリックする」という余計な動作が発生してしまうということです。
虫眼鏡アイコンだけを表示するのはユーザビリティ上大きなリスクがあることを認識しておくべきです。製作者側の都合でどうしても虫眼鏡アイコンだけにしなければならない場合にも、右上に配置するなどして誰にでも予知できる場所に置いたほうがよさそうです。
まとめ
検索ボックスの位置はサイトの特性や分野によっても大きく変わりますが、基本的な検索ボックスの位置パターンを知ることで、今置かれている検索ボックスの位置を変えるきっかけにもなるでしょう。
A/Bテストやアナリティクスといった客観的な指標によって、検索ボックスの位置による効果を知ることもできます。ユーザーが使いやすいサイト設計を、今一度考えてみるのはいかがでしょうか。
- UX
- UXとは、ユーザーエクスペリエンス(User Experience)の略で、ユーザーが製品・サービスを通じて得られる体験を意味します。似たような言葉に、UI(ユーザーインターフェイス、User Interface)がありますが、こちらはユーザーと製品・サービスの接触面を指した言葉です。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- UX
- UXとは、ユーザーエクスペリエンス(User Experience)の略で、ユーザーが製品・サービスを通じて得られる体験を意味します。似たような言葉に、UI(ユーザーインターフェイス、User Interface)がありますが、こちらはユーザーと製品・サービスの接触面を指した言葉です。
- ユーザビリティ
- ユーザビリティとは、ホームページの使いやすさのことです。万人にとって使いやすいホームページは存在しませんが、運営者はターゲットとするユーザーに便利に使ってもらうために、優先させることや割り切ることを検討し改善する必要があります。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- トップページ
- インターネットのWebサイトの入り口にあたるページのことをトップページといいます。 一般的には、階層構造を持つWebサイトの最上位のWebページをさします。サイト全体の顔としての役割も果たすため、デザインなどで印象を残すことも考えたサイト作りも有効となります。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- ユーザビリティ
- ユーザビリティとは、ホームページの使いやすさのことです。万人にとって使いやすいホームページは存在しませんが、運営者はターゲットとするユーザーに便利に使ってもらうために、優先させることや割り切ることを検討し改善する必要があります。
- トップページ
- インターネットのWebサイトの入り口にあたるページのことをトップページといいます。 一般的には、階層構造を持つWebサイトの最上位のWebページをさします。サイト全体の顔としての役割も果たすため、デザインなどで印象を残すことも考えたサイト作りも有効となります。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ユーザビリティ
- ユーザビリティとは、ホームページの使いやすさのことです。万人にとって使いやすいホームページは存在しませんが、運営者はターゲットとするユーザーに便利に使ってもらうために、優先させることや割り切ることを検討し改善する必要があります。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ヘッダー
- WEBページの上部スペースに位置し、どのページが開かれても常に共通して表示される部分です。ヘッダーの役割は、まずWEBページを目立たせ、ブランドイメージを訴求することにあります。会社のロゴなども通常はここに置きます。また目次となるメニューを表示し、自分が今どのページにいるかを分からせることもあります。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- ユーザビリティ
- ユーザビリティとは、ホームページの使いやすさのことです。万人にとって使いやすいホームページは存在しませんが、運営者はターゲットとするユーザーに便利に使ってもらうために、優先させることや割り切ることを検討し改善する必要があります。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ユーザビリティ
- ユーザビリティとは、ホームページの使いやすさのことです。万人にとって使いやすいホームページは存在しませんが、運営者はターゲットとするユーザーに便利に使ってもらうために、優先させることや割り切ることを検討し改善する必要があります。
- クロール
- クロールとは、検索エンジン内のシステムであるクローラ(ロボット)が一つ一つのサイトを巡回し、サイトの情報を収集することを指します。
- ヘッダー
- WEBページの上部スペースに位置し、どのページが開かれても常に共通して表示される部分です。ヘッダーの役割は、まずWEBページを目立たせ、ブランドイメージを訴求することにあります。会社のロゴなども通常はここに置きます。また目次となるメニューを表示し、自分が今どのページにいるかを分からせることもあります。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- クロール
- クロールとは、検索エンジン内のシステムであるクローラ(ロボット)が一つ一つのサイトを巡回し、サイトの情報を収集することを指します。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ユーザビリティ
- ユーザビリティとは、ホームページの使いやすさのことです。万人にとって使いやすいホームページは存在しませんが、運営者はターゲットとするユーザーに便利に使ってもらうために、優先させることや割り切ることを検討し改善する必要があります。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ユーザビリティ
- ユーザビリティとは、ホームページの使いやすさのことです。万人にとって使いやすいホームページは存在しませんが、運営者はターゲットとするユーザーに便利に使ってもらうために、優先させることや割り切ることを検討し改善する必要があります。
- ユーザビリティ
- ユーザビリティとは、ホームページの使いやすさのことです。万人にとって使いやすいホームページは存在しませんが、運営者はターゲットとするユーザーに便利に使ってもらうために、優先させることや割り切ることを検討し改善する必要があります。
- A/Bテスト
- ホームページを作るときや何か商品を売りたいときに掲載する写真、あるいはデザインで迷ったときに、不規則ででたらめな順番でホームページや画像のデザインを変えて表示し、利用者がどちらをより多くクリックしたのか、より多く購入につながったのか、ということを試験できる技術やサービスまたは行為自体をA/Bテストといいます。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他