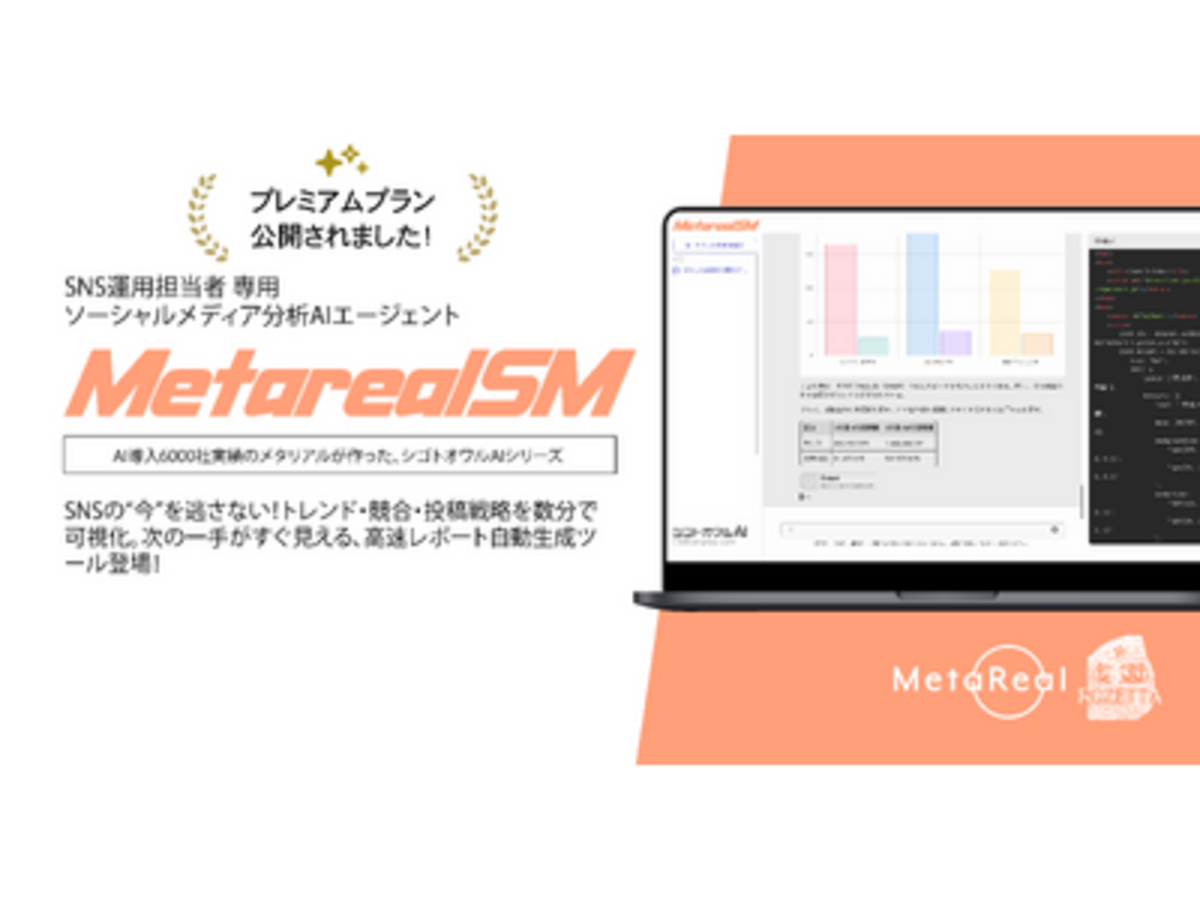すぐにシェアしたくなる!Facebookでインフォグラフィックを投稿するメリットと5つのポイント
短い時間で多くのことを伝えなければいけないCMや、たった1回で印象に残るプレゼンテーションを行わなければいけないような発表の場では、情報量をコンパクトにまとめたインフォグラフィックが大活躍します。
文字で情報を伝えようとしても、情報量が多くなればなるほど冗長的になって、結局何を伝えたいのか分からなくなってしまいますが、インフォグラフィックを使うことで、複雑なデータも視覚で直感的に理解することができるからです。
そして、インフォグラフィックの大きなメリットに気づいたWebマーケターたちは、インフォグラフィックをSNSにまで活用しはじめています。
しかしながら、インフォグラフィックは縦長のものが多く、Facebookのフィードでフルサイズのインフォグラフィックが流れてきてもそれほどカッコよく映らないので、実際のところエンゲージメントを上げるのに苦労しているという声もよく耳にします。
ただし、ヤングジェネレーションの間でYouTubeやInstagramが流行しているように、ダラダラと読むよりもパッと見て分かるものが好かれているのは確かです。
Facebookでインフォグラフィックを活用したマーケティングを展開するには、どのようにすればいいのでしょうか。
今回は、インフォグラフィックをFacebookで投稿するメリットと、上手に投稿するための5つのポイントをご紹介します。
インフォグラフィックをFacebook投稿で活用するメリット

Facebookでどのような投稿をすればクリックされやすいのか、悩んでいるひとも多いのではないでしょうか。
実際、Facebookでつながる友達の数が多くなれば多くなるほど、毎日流れてくるフィードの数も比例して多くなってくるので、いかに注目してもらえる投稿にするかが非常に重要になってきます。
その一つとして、インフォグラフィックを活用する動きがあるのですが、その背景には次のようなメリットが存在しています。
1. パッと見ただけで伝わる
複雑な情報もコンパクトにまとめることができるのは、インフォグラフィックを使う大きなメリットと言えます。
先述したように、ジェネレーション層が下に行けば行くほど、読むよりも観たり聞いたりして楽しむ人々が多くなるので、インフォグラフィックは若い世代にも受け入れられる傾向にあります。
「2011年はチョコレートの消費量が200kgだったのが、2012年には240kgに増えました」という情報も、文章では分かりにくいですが、棒グラフや折れ線グラフで推移を視覚的に見せたほうが分かりやすく伝わります。
2. 説得力がある
インフォグラフィックのほとんどが数値を扱っています。
数値はたんなる言説に比べて客観性があるので、説得力が増し、もし自分にも該当することであれば、気になってクリックしたくなるものです。
ただし、比較する数値が多くなってしまうとごちゃごちゃしてしまうので、注意が必要です。
3. 親しみや好感が持てる
文字だけで説明されてしまうと理屈っぽいと感じますが、インフォグラフィックではイラストやアイコンを使って説明することが多いので、好感を持って受け入れることができます。
その意味では、数値を使いながらも分かりやすく視覚化しているので、右脳型の人も左脳型の人も上手に取り込むことができるよい方法だと言えます。
Facebookでインフォグラフィックを活用するための5つのポイント

ここまで読めば、インフォグラフィックを活用しない手はないぞとばかりに意気込んでしまうのもよく分かります。
しかし、ちょっと待ってください。
Facebookでインフォグラフィックを使う場合、いくつかのポイントがあります。
ただ単に通常の画像のように投稿するだけでは、エンゲージメントは上がりません。
それでは、どのようにすれば上手く活用できるのでしょうか。
1. 画像の縦横比を決めよう
Facebookページで画像を投稿する際には、通常の画像投稿の他にもカルーセル投稿やスライドショー投稿を行うことができます。
しかし、いずれの投稿タイプを選択しても、Facebook上で共有できる部分には限りがあるので、巨大なインフォグラフィックを用意しても一部しか表示できないことを覚えておいてください。
インフォグラフィックの一部を投稿して誘導のきっかけにすることで、興味がある人にホームページやブログでインフォグラフィックの全体像を見せることができれば、ユーザーも安心します。
Facebookでインフォグラフィックのスライスを何枚か見せるときには、適切なサイズに切り抜きをすることを忘れないようにしましょう。
画像のサイズには、*横長(Horizontal)・縦長(Vertical)・正方形(Square)がありますが、Facebook上に投稿するときにはできるだけ「横長」か「正方形」*を使うようにしてください。
● 正方形|Square
正方形の画像をアップロードする場合は、Facebookの最大許容サイズである470pxが各辺に適用されることを覚えておいてください。
基本的にはどのようなサイズでも自動調整されますが、470px未満であれば、無理矢理引き延ばされるので、ドット画のようになってしまったりピンボケしているように見えてしまいます。
● 横長|Horizontal
横長の画像をアップロードした場合も、横幅は470pxに自動調整され、横幅に応じて縦幅も自動的に変動します。
横幅が470px未満の場合はそのまま右寄せで表示され、左側に空白が空いているように見えてしまいます。
● 縦長|Vertical
縦長の場合は、さらに注意が必要です。
Facebookにアップロードされた縦長の画像は、高さが最大で394pxに自動調整され、高さに応じて横幅も調整され、左右に余白が空いてしまいます。
例えば、500 x 700pxの画像をアップロードした場合は、Facebookは281 x 394pxに自動的にリサイズします。
一番画面を広く使うことができるのは、470px以上の正方形の画像ということになります。
2. インフォグラフィック全体のリンクを貼ろう
写真の大きさや向き、枚数にかかわらず、投稿したインフォグラフィックの全体像を閲覧できるリンクを添付しておきましょう。
繰り返しになりますが、インフォグラフィックのすべてを掲載することはできないので、リンク先に飛んでインフォグラフィックを楽しんでもらい、面白ければシェアしてもらうようにしましょう。
3. カルーセルを使ってみよう
インフォグラフィックの画像を1枚ずつ投稿するのではなく、一度に複数枚見てほしい場合にはカルーセルを活用するのが便利です。
カルーセルの場合はどの画像をタップやクリックをしても、同じフルサイズのインフォグラフィックに飛ぶように設定することができます。
それぞれの画像にキャプションをつけたり編集したりすることもできます。
カルーセルで使用する画像は正方形を使うので、600 x 600pxで画像を作成しましょう。

▲ Lemonlyの投稿したカルーセルタイプの投稿が非常に参考になります。
4. リンク画像をカスタマイズしよう
Facebookの投稿編集画面でリンクを入力すると、リンク先で使われている画像をもとに自動的にサムネイルを作成しますが、このサムネイル画像はいろんな画像にカスタマイズすることができます。
画像の横に表示された*「+」マーク*をクリックすることで、画像を追加することが可能です。
このサムネイル画像は、最大で1200 x 628pxで表示することができます。
サムネイルをカスタマイズしてリンクを共有する場合、インフォグラフィックの一部やタイトルに差し替えておけば、そこをクリックした場合にインフォグラフィック全体を表示するように誘導することができます。
5. キャンバスを使ってもっと自由に投稿しよう
2016年、Facebookに新しい投稿タイプとして*「キャンバス」が登場しました。
この最もカスタマイズ可能な投稿タイプの注意すべきところは、現在モバイルアプリ上でしか閲覧できない*点です。
したがって、デスクトップではキャンバスを見ることはできません。
モバイル上では、インフォグラフィックをより長く表示することができるので、とんでもなく長くうんざりするものでなければキャンバスを使ってみると、縦長の画像であってもうまく表示することができます。
また、キャンバスでは、サムネイル画像自体に全体のインフォグラフィックを表示するリンクを付加できるほか、同じリンク先のCTAボタンをつけることもできます。
これだけでも面白いですが、キャンバス形式で投稿できるのは、これだけの種類があります。
- 写真
- クリックボタン
- カルーセル
- カスタマイズした背景・フォントカラーのテキストブロック
- ビデオ
- ヘッダー
キャンバスで投稿された画像は最初折りたたんで表示されますが、設定で横幅に合わせた表示を行うことができます。

ユーザーはモバイルアプリ上ではピンチしてズームすることができないので、モバイル端末上でも見やすいように十分にパーツを大きく表示しておきましょう。
まとめ
さまざまな投稿タイプがあるので、それぞれの強みを理解し、それらを活かして投稿すると、エンゲージメントの高い投稿を実現することができます。
いろんなタイプの投稿を何回かに分けて投稿し、ユーザーの反応の高いパターンを見つけることが大切です。
インフォグラフィック自体の作成の仕方のポイントは以下の記事でまとめています。
もしインフォグラフィックの作成に戸惑ってしまったら、ぜひ参考にしてみてください。
参考:
分かりやすさが肝心!印象に残るインフォグラフィックを作る5つのコツ
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- サムネイル
- サムネイルとは、多数の画像や動画など、読み込みに時間のかかる情報の概要をおおまかに把握するために作られた縮小画像のことです。 一般的にはサイズ・画質が落とされた画像が採用され、該当の画像や動画を読み込むかどうかを判断するための「見本」として使われます。 元々は親指の爪(thumb nail)という意味を持つ言葉で「サムネ」と略して呼ばれることもあります。
- サムネイル
- サムネイルとは、多数の画像や動画など、読み込みに時間のかかる情報の概要をおおまかに把握するために作られた縮小画像のことです。 一般的にはサイズ・画質が落とされた画像が採用され、該当の画像や動画を読み込むかどうかを判断するための「見本」として使われます。 元々は親指の爪(thumb nail)という意味を持つ言葉で「サムネ」と略して呼ばれることもあります。
- サムネイル
- サムネイルとは、多数の画像や動画など、読み込みに時間のかかる情報の概要をおおまかに把握するために作られた縮小画像のことです。 一般的にはサイズ・画質が落とされた画像が採用され、該当の画像や動画を読み込むかどうかを判断するための「見本」として使われます。 元々は親指の爪(thumb nail)という意味を持つ言葉で「サムネ」と略して呼ばれることもあります。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- サムネイル
- サムネイルとは、多数の画像や動画など、読み込みに時間のかかる情報の概要をおおまかに把握するために作られた縮小画像のことです。 一般的にはサイズ・画質が落とされた画像が採用され、該当の画像や動画を読み込むかどうかを判断するための「見本」として使われます。 元々は親指の爪(thumb nail)という意味を持つ言葉で「サムネ」と略して呼ばれることもあります。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- フォント
- フォントとは、同一の特徴を持った文字の形状を一揃いでデザインしたものです。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- ヘッダー
- WEBページの上部スペースに位置し、どのページが開かれても常に共通して表示される部分です。ヘッダーの役割は、まずWEBページを目立たせ、ブランドイメージを訴求することにあります。会社のロゴなども通常はここに置きます。また目次となるメニューを表示し、自分が今どのページにいるかを分からせることもあります。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他