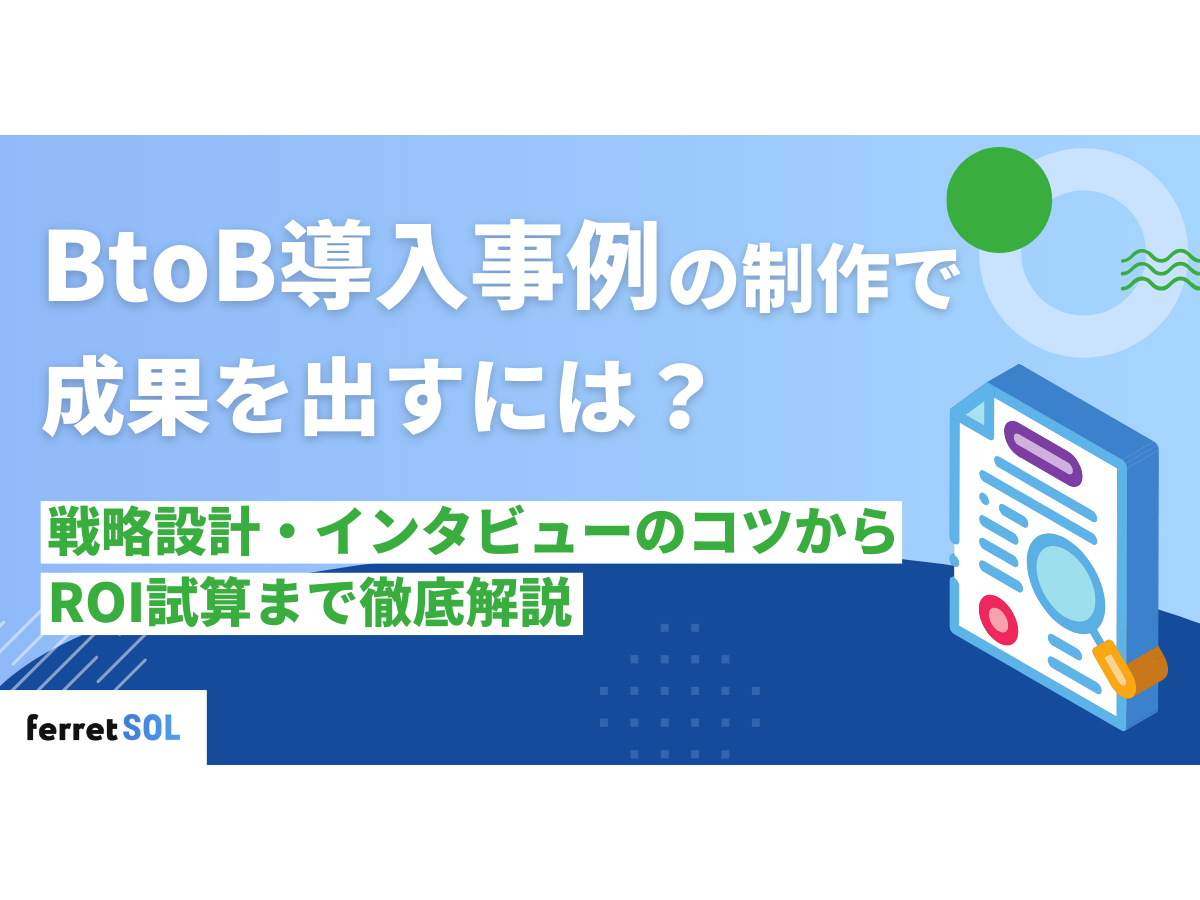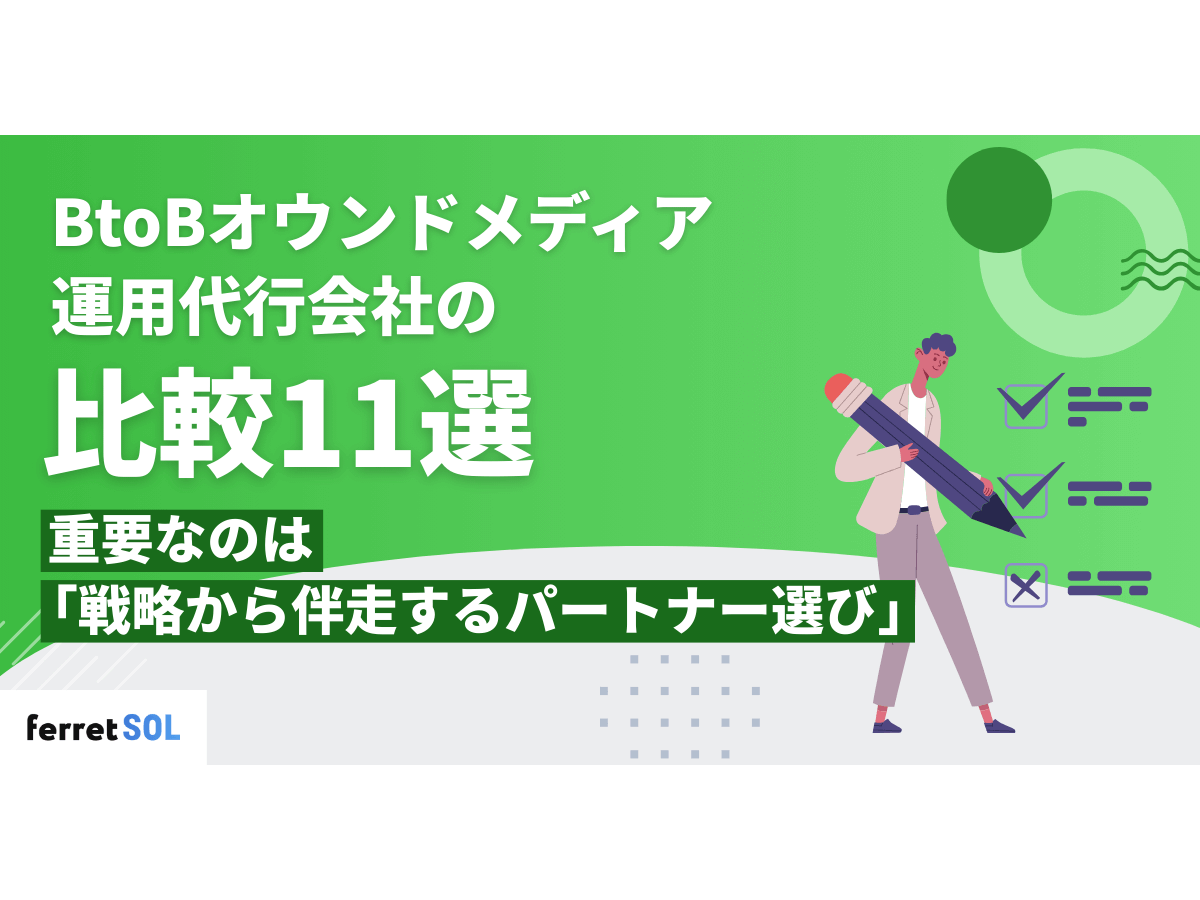【インタビュー】いきなり編集長に任命されたらどうする?メディア運営者が持つべきマインドセットを『LITALICO発達ナビ』編集長に聞く
情報発信に取り組みたいけれど、社内にメディア運営の経験者がいない。
オウンドメディアやコンテンツマーケティングを進めていく上で、適任者不在という悩みを抱える企業は多いようです。
これまでやってこなかったことを新しく始めるのですから、社内に適任者がいないのも仕方のないこと。情報発信に取り組もうとする企業は、未経験ながらも可能性のある人に”編集長”を任せます。
任された人も、いきなり“編集長“に抜擢されて、右も左もわからない中、手探りでメディアの運営に取り組んでいるはず。一体、企業内で編集長に抜擢された人に、求められるスキルやマインドセットとは何でしょうか。
事業会社でメディアを立ち上げ、運営している編集長は、日々どのようにして仕事をしているのか。事業会社で編集長として苦悩しながら活動してきた人たちに、ヒントを聞いてみたいと思います。
今回は、株式会社LITALICOにて、発達障害のポータルサイト『LITALICO発達ナビ』編集長を務めている傍ら『編集長ことはじめ』という編集長について学ぶコミュニティを運営している鈴木悠平さんに話をうかがいました。
●鈴木悠平
編集者・文筆家。東日本大震災後の宮城県石巻市におけるコミュニティ事業の立ち上げ、コロンビア大学大学院での地域保健政策の研究を経験した後、株式会社LITALICO入社。発達支援教室「LITALICOジュニア」での指導員、「LITALICO研究所」の立ち上げ・運営業務等を経験したのち、発達障害に関するポータルサイト「LITALICO発達ナビ」の編集長に就任。
足りないところは助けてもらって運営するのがメディア

鈴木悠平さんが編集長を務める『LITALICO発達ナビ』は、 発達が気になる子どもを育てる保護者に必要な情報を発信したり、会員同士で支え、相談し合えるコミュニティを運営する発達障害ポータルサイトです。
発達障害や子育てに関するコラム、様々な分野で活躍する人のインタビュー記事などを掲載しています。記事コンテンツを配信するほかに、発達が気になる子どもが通うことができる福祉事業所の施設情報やクチコミ、子育てに関するQ&Aを投稿できるコーナーなどが用意されているサイトです。
鈴木さんが編集長という役割に就いて、最初から全てが順風満帆ではなかったものの、『LITALICO発達ナビ』は右肩上がりで成長し、2017年3月現在で月間180万UU/540万PVという規模まで拡大しています。
鈴木さんは編集長に就任するより前から、『greenz.jp』などの媒体でライター経験がありました。全く何も経験がないよりはマシではあったものの、1人だけでは立ち上げることが難しかったのでは、と当時を振り返ります。
鈴木さん「ライターと編集長では、求められる職能は異なります。ですが、偶然にも僕はコンテンツを作る経験があり、同期にコンテンツを届けるためのSEOやマーケティングの知識のある人間が部内にいたため、足りないところを補うことで、メディアの立ち上げを比較的スムーズに行うことができました」。
編集長は「コンテンツの質」を保つ最後の砦

スタート時はかかわる人数も限られていた『LITALICO発達ナビ』も、成長とともに関わる人数も増えていきました。
鈴木さん「『LITALICO発達ナビ』の運営には、事業部全体で約30名の社員(常勤・非常勤含む)がいます。事業部長以下、マネージャー、企業営業、カスタマーサポート、エンジニアなどメディアの運営を支える様々な職種で構成されており、僕が管掌する編集部は、コンテンツの制作・配信、ユーザーコミュニティの活性化、カスタマーサポートなどを担うチームです。編集部には、編集長の僕と4名の常勤編集スタッフ、約10名の非常勤ライターが所属しています。また、社外にも寄稿してくださる外部のライターさん(発達障害のある子どもの保護者、成人当事者や専門家の先生など)が約20名ほどおられます」。
人が増えると、編集長が手を動かすことは減りますが、これだけ多様なメンバーのマネジメントをしなければなりません。マネジメントを行いながら、編集長として日々の業務の中で大切にしているのは、「コンテンツの質を追求すること」だと鈴木さんは語ります。
鈴木さん「『このコンテンツは、胸を張って世に出せるか』を毎日考えながら、記事の企画・編集をしています。編集長がコンテンツの質にこだわれなければ、そのメディアのクオリティは決して高くなりません。編集長は、メディアの質を保つ最後の砦なんです」。
時には、編集者やライターが指針とできるように編集長自らが記事を執筆し、事例を作っていくこともあるそうです。
鈴木さん「チームができたばかりの頃は、まだ執筆・編集マニュアルや制作フローなども体系化されていません。編集部のメンバーも『自分たちはどんな記事を作るべきで、良い記事とは何なのか』という基準やイメージを持てていない状態でした。そんな立ち上げ期に編集長に求められるのは、自ら行動して『基準』を打ち立てること。例えば、検索順位で1位になるSEO記事を書く、ソーシャルメディア上で数千シェアされる記事を書く。色々なことに編集長は挑戦するべきです。自身が成功体験を積み重ね、それを体系化してマニュアルに落とし込んでいくことで、再現性が生まれます。自ずと、チームとして質の高いコンテンツを出せる打率が上がっていくはずです」。
コンテンツの質が落ちないようにチェックを厳しくし、時には自ら参考となるコンテンツを作る。メディアの要であるコンテンツの質が落ちないよう、配慮するのが編集長の役割です、と鈴木さんは語ります。
「全体の舵取り」が編集長の役割

ただ、編集長はコンテンツの面倒だけを見ていればいいわけではありません。さらに、「編集長」と一括りにしても、メディアによって編集長の役割や担当する業務は異なります。鈴木さんの場合は、コンテンツづくり以外にも様々な業務を担当しています。どんな業務を担当しているのかうかがってみると、下記のような内容が出てきました。
・記事の企画や執筆、編集
・ライターの採用や育成、マネジメント
・ソーシャルメディア運用やSEO対策などのチャネル構築
・WebサイトのUI/UXの改善のための企画提案と進行管理
・広告出稿やイベント協賛のための企業営業
・イベント開催等を通じた読者コミュニティづくり
・カスタマーサポートやサイトパトロール業務
鈴木さんは、コンテンツの質を追い求めることに加えて、これだけ多くの業務をどう担当されているんでしょうか。
鈴木さん「ユーザーが増えてきたり、機能を拡充したり、発達ナビというサービスが成長するにつれて、新たな課題やそれに対応するための施策が増えていきます。こうなると、自分1人ではとても全てを見切れないので、各業務ラインごとにリーダーが立っていくことが必要です。サービスができて半年から1年ほどが経つ頃に、次第に自分のマネジメントスタイルも変わっていったように思います。1人ひとりに手取り足取り基準や「答え」を教えていくのではなく、「問い」を投げかけていく。スタッフそれぞれが、サービスの成長に向けて何をすべきか、どう進めていくかを考えて提案して、自ら推進してくれるようなチーム作りを意識しました。細かな実務はその業務ラインを担当する編集者がリードしていき、僕は全体を把握しながら必要な時だけ相談やサポートに入る。そのための会議体やレポートラインも整理していきました」。
様々な業務を担当している鈴木さんですが、その中でも編集長としての大切な役割を次のように語ります。
鈴木さん「『LITALICO発達ナビ』のユーザーに対して、メディアがどのような価値を提供できるのかを考え抜くことが、編集長が担うべき役割です。編集長として「どのようなメディア、どのようなコミュニティをつくっていくのか」の方針を定め、その舵取りをすることが大切な役割だと考えています」。
編集長として、人を惹きつけるビジョンを語る力を身に付けたい

試行錯誤を重ねながら、媒体を成長させてきた鈴木さんは2017年2月に個人として『編集長ことはじめ』という活動を立ち上げます。
「編集長ことはじめ」では、様々なメディアの編集長経験者の寄稿や、メディアづくりのケースやノウハウを学ぶ記事を発信しています。
鈴木さん「手探りの状態で、『LITALICO発達ナビ』の編集長を務めてきました。日々、新たな課題に向き合いながら、こう思ったんです。『ライティングや編集の技術を教える書籍や講座はあるのに、編集長の職能について教えてくれる場所がない』。自身の編集長としての知見を共有することで、これから編集長になる人をサポートしたい。すでに編集長として活躍している人に寄稿してもらうことで、自分自身も編集長として成長したい。そんな想いから『編集長ことはじめ』を立ち上げました」。
メディアによって編集長の役割や仕事が異なるからこそ、編集長同士が知見を共有し、スキルの体系化を目指すことで、新しく編集長になる人の悩みを解消できる。鈴木悠平さんはそんなコミュニティを目指して、情報発信やイベント運営に取り組んでいます。

「編集長ことはじめ」イベントの様子
鈴木さん「自分1人ではできることに限界があります。掲げたビジョンを実現するためには、仲間を集め、組織をつくることが必要です。そのためには、多くの人に『このメディアに関わりたい』と思ってもらえるような、ビジョンを語る力を身に付けるべきだ、と考えています」。
まとめ - とにかく、「ユーザーと向き合うこと」を大切に -
鈴木さんは、自身の編集長としての経験や、様々な編集長との交流から学んだことを振り返りながら、新たな“編集長“に対するアドバイスをこう語ります。
鈴木さん「ユーザーと向き合い、メディアを通じてユーザーに提供できる価値は何かを日々考えること。そのためには、イベントやオフ会などに足を運んで、ユーザーと交流する。その交流の中からユーザーの声を拾い、コンテンツに反映していくことで、メディアは成長していきます」。
編集長は、情報発信における要です。だからこそ、情報発信を始める際は編集長としてのマインドセットを作っていくことが求められます。まだまだ、情報が整理されていない領域ではありますが、鈴木さんが語るように、ユーザーと向き合い、ビジョンを語ることで仲間を集めていくことが共通して必要なことではないでしょうか。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ポータルサイト
- ポータルサイトとは、インターネットの玄関口となる巨大なWEBサイトのことを言います。 サイトが独自の情報を発信するのではなく、検索エンジンやリンク集を核として、ニュースや株価などの情報や、メールやチャットなどのユーザーがインターネット上で必要とする機能を提供しています。
- ポータルサイト
- ポータルサイトとは、インターネットの玄関口となる巨大なWEBサイトのことを言います。 サイトが独自の情報を発信するのではなく、検索エンジンやリンク集を核として、ニュースや株価などの情報や、メールやチャットなどのユーザーがインターネット上で必要とする機能を提供しています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他