
【テンプレートあり】6Rとは〜STP分析を正しく行うために欠かせないフレームワーク
マーケティングを行う際、様々なフレームワークを駆使して自社に適した戦略を練る必要があります。
そのうちのひとつ、コトラーの提唱した「セグメンテーション」「ターゲティング」「ポジショニング」の頭文字をつなげた「STP分析」も、市場を見極めてターゲットを明確にして市場での自社の立ち位置を理解する際に有効です。
3つの各要素を正しく進めるためには、指標を持って検討しなければなりません。
今回は、「STP分析」を正しく行うために有効な6つの指標「6R」を解説します。
6つのチェックポイントを確認した上でSTP分析を行えば自社が目指すマーケティング戦略の軸をブレさせずに進められますので、特にマーケティング初心者の方は参考にしてみてはいかがでしょうか。
6Rとは

6Rとは、STP分析を行う際に利用する6つの指標のことを意味します。
- Realistic scale(有効な規模)
- Rank(優先順位)
- Rate of growth(成長率)
- Rival(競合)
- Reach(到達可能性)
- Response(測定可能性)
上記の6つの頭文字をとって「6R」と名付けられました。
セグメンテーションとは、分析を通して不特定多数に人々を共通の性質やニーズを持つ人に分けていく作業のことを指します。
ターゲット層を細かく分けて分類していくことで、自社がターゲットとするべき層をはっきりさせることが目的です。
6Rを使用して分析を行う際は、個々の指標に注目しすぎるのではなく、6つの指標を総合的に見ることがポイントとなります。
例えば、Realistic scale(有効な規模)の指標では優れていても、Rate of growth(成長率)では劣っているケースの場合、短期的な利益は得られても、長期的な利益はあまり望めません。なぜなら、市場が大きくても成長率が悪いため、マーケットが先細りしていくことが予想されるからです。
Realistic scale(有効な規模)が小さく、Rival(競合)も少ない場合では、一般的にマーケットの規模は大きい方がよいためRealistic scale(有効な規模)が小さいことは問題となりがちです。
しかしこの場合、ライバルとなる企業も少ないため安定したシェアを獲得できる可能性もありますので、会社やサービスの安定を考えればチャンスにもなり得ます。
6つの指標
1.Realistic scale:マーケット(市場規模)は適切か
マーケットの規模を示す指標です。
すでに多くのユーザー・ファンを抱えている商品やサービス、1人あたりの消費量・消費額が大きい商品やサービスなどは企業により多くの利益をもたらす可能性が大きいため、基本的にはマーケットは大きい方が良いといえます。
ただし、マーケットが大きければ良いというわけでもないため、市場の成長率や、ライバルの数、大きさも考慮しましょう。
ある時期は大きかった市場規模が時代とともに衰退していったという事例もあるため、この指標だけで判断することは望ましくありません。
一方で、小規模市場でもある一定層の人々をターゲットに安定したサービス供給を行うという考え方もあります。
ニッチ産業とも言われ、ターゲットを絞ることで競合を避け、安定した収益をあげることが可能です。
2. Rank(優先順位):ユーザーにとって優先度が高いものか
ユーザーにとっての優先度を判断する指標です。
ターゲット層の関心度が高い商品やサービスを提供すれば、ユーザーに自社を発見してもらいやすくなります。
ただ関心度の高い商品やサービスを提供するだけではなく、例えばメディアを利用して情報を拡散してもらうなどの施策を行うことで、ターゲット層に一気にアプローチをかけられます。
6つの指標の中で最もイメージが湧きにくい指標ですが、この指標でポイントとなるのは「ターゲットに関心を持ってもらえる物・サービスかどうか」ということです。
3. Rate of growth(成長率):成長する市場か
市場の成長率を示す指標で、競合の売上高や対象となるジャンルの商品、サービスの消費額などを参考に判断します。
Realistic scale(有効な規模)やRival(競合)と共に比較することで、マーケットの全体像を把握することができます。
市場の規模は小さくてもこれからの成長率が高いと見込める分野である場合も、市場の規模は大きいものの成長率に欠ける、という場合もありますので、長期的な視点を持って判断することがポイントです。
4. Rival(競合):競争が激化していないか
ライバルとなる企業や商品、サービスなどがどのくらいあるかを判断する指標です。
もちろんライバルは少ないことに越したことはありませんが、この指標だけで判断するとビジネスチャンスを逃してしまうかもしれません。
例えば、競合の数は多いけれどマーケットの規模も大きい場合であれば、新規参入がまだ間に合う可能性があります。
強い大手がいるもののある地域にのみシェアが偏っている場合は、該当地域以外で商品やサービスを提供をを行うことでシェアを確保できることもあるでしょう。
このように、ライバルの数だけでなく、地理的な環境、他の指標も参考にしつつ見極めることがポイントです。
5. Reach(到達可能性):ユーザーに到達はできるのか
ターゲットにアプローチできるかどうかを判断する指標です。企業側がさまざまなプロモーションを仕掛けても、ユーザーに届かなければ意味がありません。
例えば、新しくダイビングショップをオープンしたい場合、内陸部と海沿いではどちらが望ましいと考えられるでしょうか?
ダイビングショップのターゲット層はマリンアクティビティを好むユーザーだと考えられるため、立地の面では海沿いの方が望ましいと言えます。
このように物理的に距離が離れている、ターゲット層にプロモーションが届く導線が確保できていないなどの場合は、ビジネスプランを見直すことをオススメします。
6. Response(測定可能性):反応を測定できるか
アプローチの効果を測定できるかを判断する指標です。
商品やサービスを広める施策を多く実行してもその施策にどの程度効果があったのか判断することができなければ、ビジネスの目標達成に致命的な影響を与えるだけでなく、チームのモチベーションやメンバーの評価にも関わります。
施策の効果を測定する指標は、1つに限定せず複数持つことが理想です。
例えば「今回はリピート率を改善するためにAというプロモーションを行う。その効果を測定する指標はB、C、Dの3つとする」というように、ビジネス全体の効果を測る指標だけでなく施策1つずつの効果を測る指標を持っておくことで、ビジネスのPDCAを素早く回すことができるでしょう。
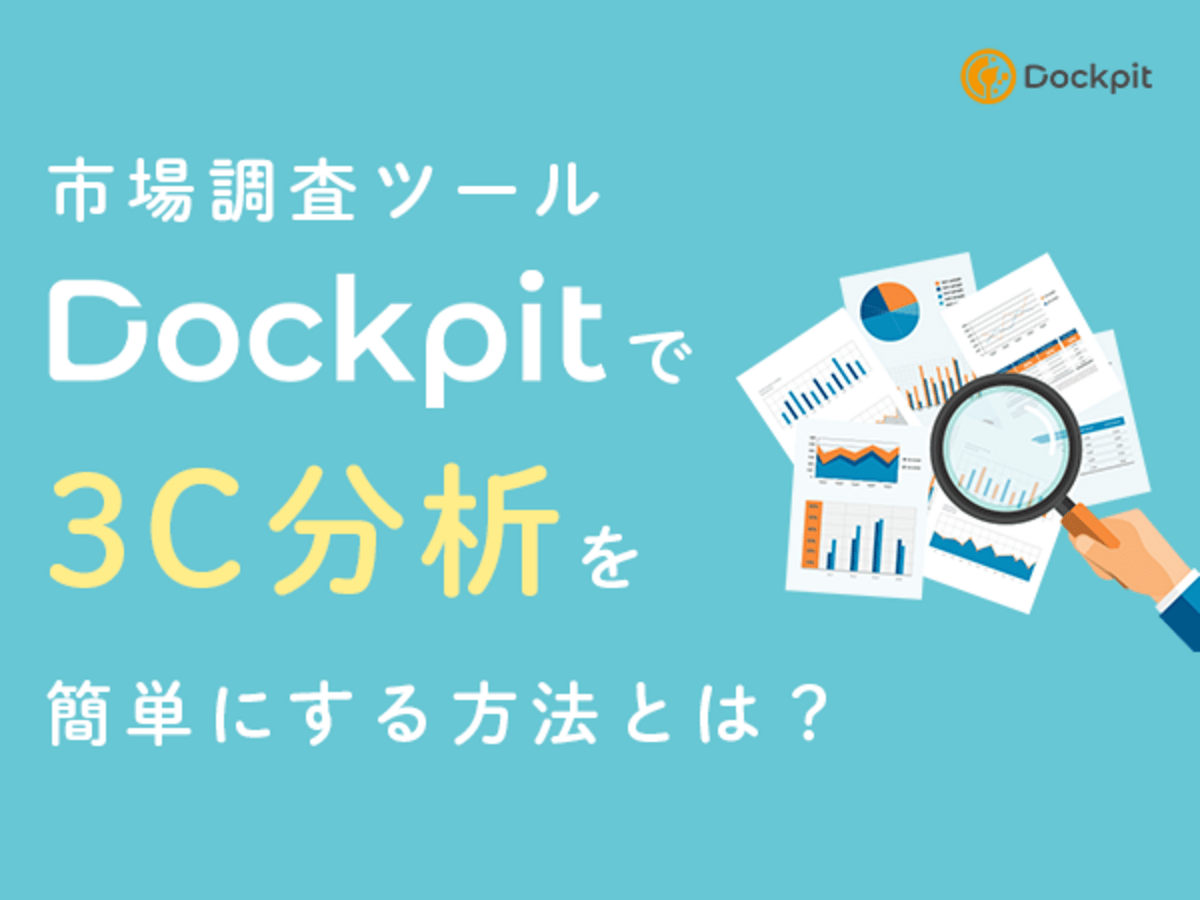
ferretも使ってみた競合分析ができるツールって?
簡単に3C分析・競合分析ができるDockpitでできることを資料で見てみる
まとめ
上記で解説した6つの指標は、STP分析を行う中でも特にターゲティングを行う際に有効です。
どのようなユーザーをターゲットとするのかを検討する際、闇雲に市場分析などを行っても高い効果を期待することができません。それに加えて、企業が「理想とするターゲット層」と実際に「商品やサービスを利用するターゲットが違った」ということも起こりえます。
今回紹介した6つの指標を、自社が提供する商品やサービスがどのターゲット層に適しているのか、現在検討しているターゲットは正しいのかどうかなどを判断する基準として活用してみることをオススメします。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- セグメンテーション
- セグメンテーションとは、ビジネスを進める上で顧客をグループ分けしたり、市場や見込み客を属性ごとに分類したりなどする行為を言います。そのグループ自体をセグメントといい、ビジネスにおいてセグメントをしっかり意識することが重要と言われています。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- セグメンテーション
- セグメンテーションとは、ビジネスを進める上で顧客をグループ分けしたり、市場や見込み客を属性ごとに分類したりなどする行為を言います。そのグループ自体をセグメントといい、ビジネスにおいてセグメントをしっかり意識することが重要と言われています。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- 導線
- 導線とは、買い物客が店内を見てまわる道順のことです。ホームページにおいては、ページ内での利用者の動きを指します。 ホームページの制作にあたっては、人間行動科学や心理学の視点を取り入れ、顧客のページ内での動きを把握した上でサイト設計を行い、レイアウトや演出等を決めることが重要になります。
- PDCA
- PDCAとは、事業活動などを継続して改善していくためのマネジメントサイクルの一種で、Plan,Do,Check,Actionの頭文字をとったものです。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他













