
わかりやすい文章を作成するなら注意したい!記号の意味と使い方
メールや資料、ブログなど、人の目に触れる文章を書く際には文章の意味だけではなく、読む人にとってわかりやすく書かれているかどうかが大切です。
わかりやすい文章を書くためには、「※」「→」「:」などの記号を利用すると便利です。
普段書いているメールや提案書の中でも、何気なく記号を利用している方も多いでしょう。
今回は、文章表現の中で使う記号について、意味と使い方を解説します。
意味を知らずに見たり使っていた記号に改めて向き合ってみましょう。
目次
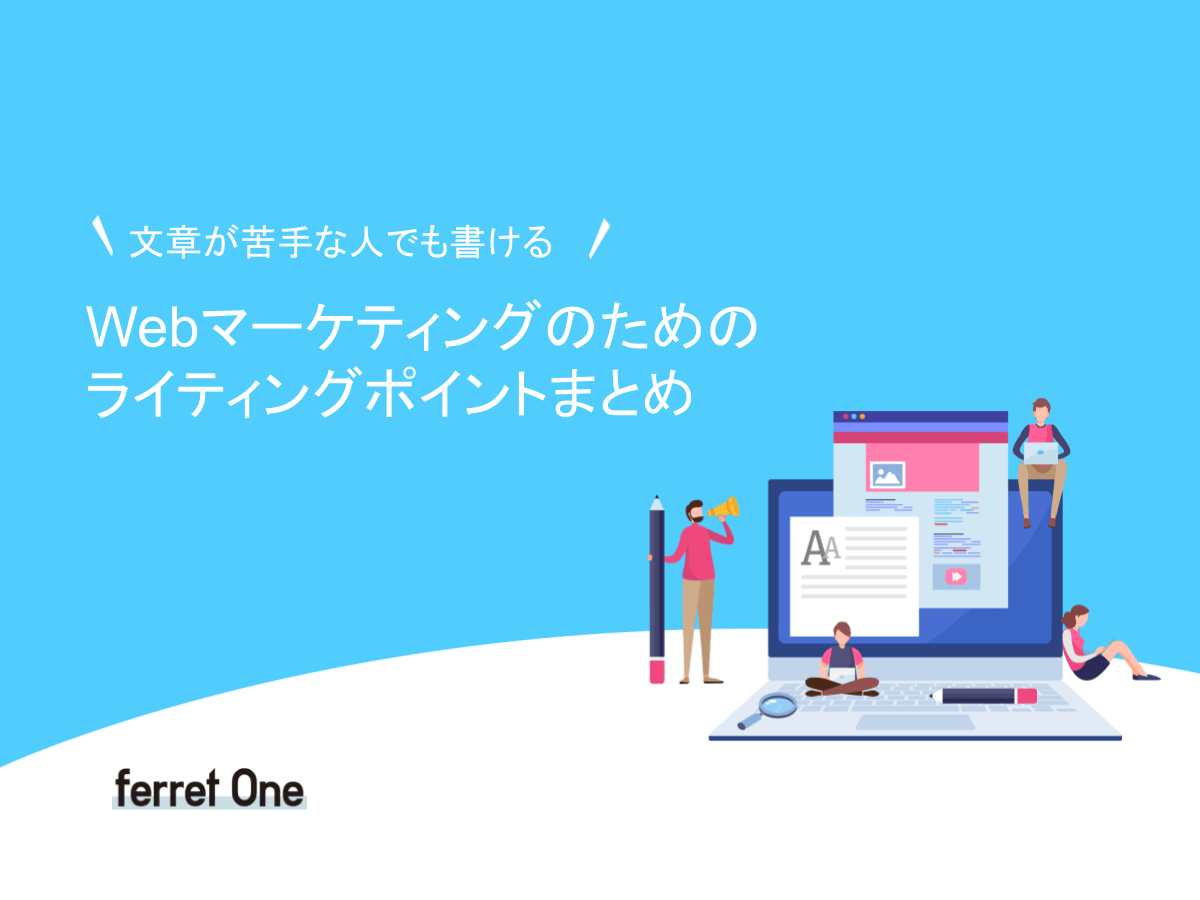
文章が苦手な人でも書ける Webマーケティングのためのライティングポイントまとめ
初めてWeb上で文章を書く方に対して、テキストコンテンツのネタの集め方と、実際に書く際の手順までを公開しています。
記号の読み方・意味
記号文字の中でも、特に日本語の文章で使われるものを印刷業界では約物(やくもの)と呼ばれています。
今回は約物の中から、特に使用することの多いものをご紹介します。
参考:
約物の種類
目印として使用するもの
※(米印)
「米」の字に似た形で、文中の注釈を行う際に利用することが多い記号です。
*(アスタリスク)
星印。注を添える時などに使う記号です。
#(ナンバー)
ハッシュマーク、番号記号、井桁(いげた)とも呼ばれています。
情報処理分野でも使われる記号です。
→(矢印)
矢の形をした記号です。方向、順路などを示すために使用します。
§(セクション)
節記号とも呼ばれる記号です。文章の区切りを表し、章立てされた論文の中で見かけることもあるかと思います。
¶(パラグラフ)
段落の始まりを示す記号です。
このような記号は「しるしもの」と呼ばれます。
箇条書きに利用する際にも使いやすく、紙面でも目立ちやすいものが多く存在します。
日本語の表現に関わる記号
「」(かぎかっこ)
会話文や引用、書名をくくる際に利用し、欧文では‘’(コーテーション)が該当します。
『』(二重かぎかっこ)
「私は昨日『お腹が空いた』と言いました」のように会話文の中にさらに会話文を用いたい時など、「」の中に「」を重ねる際に利用します。
書名をくくる際にも利用し、欧文では“”(ダブルコーテーション)が該当します。
:(コロン)
欧文で使用する句読点の一つです。特に対照、説明、引用などの前につけられます。
日本語の文で読点→句点となるように、欧文ではコンマ→セミコロン→コロン→ピリオドの順で文章を区切ります。
…(3点リーダー)
リーダーとは印刷業界で点線、破線を意味し、3点リーダーは3つの点で構成された記号です。言い切らない文章などに利用し、二回続けて使用するのが一般的です。
インターネットでよく使われる記号
@(アットマーク)
もともとは単価を意味する記号で、「かぼちゃ@100円」のように利用します。インターネットのメールアドレスにも使用されます。
現在では本来の意味から離れ、英語のatの意味と捉えて「お客様感謝祭@横浜」や「ミーティング@10:00」のように場所や時間を表現する際に用いる場合もあります。
©(コピーライト)
著作権を意味するcopyrightの略記の記号です。「©2016 samplename」のように使用します。
参考:
こんなに細かい!著作権の種類を徹底解説【著作者人格権・著作財産権・著作隣接権】
記号を用いる時の注意点
機種(環境)依存文字に注意しよう
記号を用いる際には、機種によって表示できるかどうかわからない「機種(環境)依存文字」が存在することを意識しましょう。
具体的には下記のような記号です。

このような文字は見ている人の環境によって表示できなかったり、意図しない形で表示されてしまいます。ホームページなど、多くの人が見る場所での利用は控えましょう。
記号を使用するルールを立てよう
記号を利用する際は、その記号をどのように使用するのかというルール付けが必要です。
■や・など、目印にする記号を使う際には特に注意が必要です。
■ 山の名前
・富士山
・浅間山
・御嶽山
■ 海の名前
・太平洋
・日本海
このように、同じ項目の箇条書きは用いる記号を揃えるなど、文書内では統一した基準を持ちましょう。
記号だけではなく、太字や斜字のルールも決めておくと、より統一感のある文章になります。
多用し過ぎないようにしよう
記号は文章をわかりやすくするためには便利ですが、むやみに使うと読者が混乱してしまいます。
1) ご飯を食べる → ラーメン(ラーメンは味噌味が好き)
2) ご飯を食べる → 満腹になる
1)のように関連性のないものをつないだり、余分な情報を()で付け足したり、記号を多用することは逆にわかりづらい文章になってしまいます。
2)のように、矢印は関連性のあるものをつなぐようにしましょう。
1)の内容でも下記のように整理することができます。
ラーメンを食べる。
※余談ですが、ラーメンは味噌味が好きです。
このように、記号を用いることのなく文章で表現した方がわかりやすくなる場合もあります。「なんとなく表示が綺麗になるから」と安易に記号を使う前に、文章でわかりやすい表現ができないかどうかを考えてみましょう。
参考:
製本豆知識
広辞苑第六版(岩波書店)
精選版日本国語大辞典(小学館)
明鏡国語辞典(大修館書店)
日経パソコン用語辞典(日経BP社)
まとめ
今回ご紹介したような文章をサポートする記号を約物といい、その歴史は明治期にまでさかのぼります。手書きからワープロ、そしてパソコンへと、文章を書くためのツールは進化を遂げ、それに合わせて文中で用いる記号も形を変えて役割を果たしてきました。
今回ご紹介した以外にも「()」のように文字をくくるものや、「※」のように目印になるものなど、数多くの記号が存在します。
普段何気なく利用することの多い記号ですが、ぜひ一度その意味を見返してみてみましょう。
また、むやみやたらに記号を使ってしまうと読者の混乱を招くこともあります。文中で使用する際はルールを立てて、統一感のある文章を心がけましょう。
文章作成におすすめのツール・資料
Webマーケティングに関する文章作成をする方向けに便利なツールや資料をご紹介します。
▼ AIが記事やメールの下書き提案や文章を添削してくれるツール
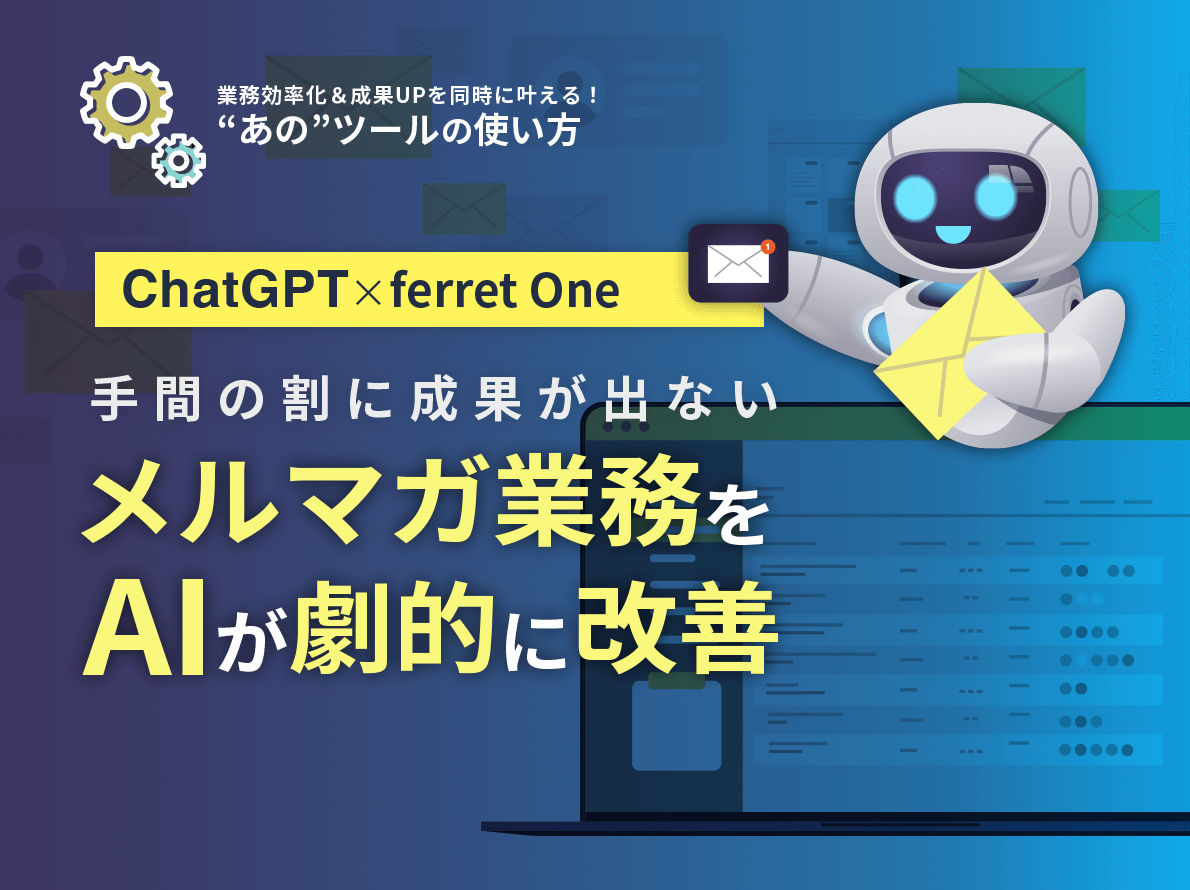
手間の割に成果が出ない。メルマガ業務をAIが劇的に改善
ChatGTPの機能をより親しみやすく、業務に活かしやすい形に落とし込んだ「AIアシスタント」のメール作成支援機能ついてご紹介します。

コンテンツ作成の生産性をAI技術で向上|ferret One
WebマーケティングのノウハウとAI技術を組み合わせて、マーケターの業務負荷を減らし、生産性を向上させます!
▼ SEO施策などでWeb記事のライティングをされる方へ
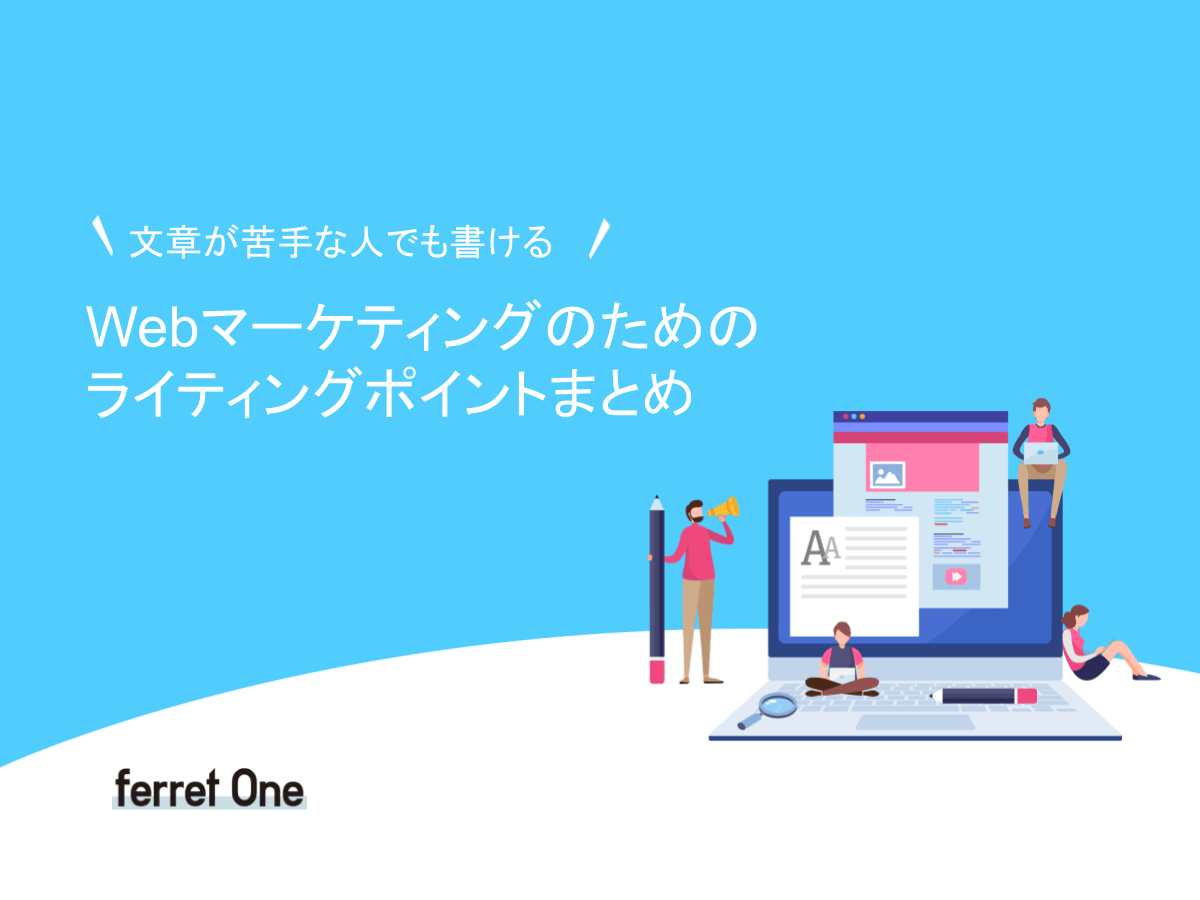
文章が苦手な人でも書ける Webマーケティングのためのライティングポイントまとめ
初めてWeb上で文章を書く方に対して、テキストコンテンツのネタの集め方と、実際に書く際の手順までを公開しています。
文章関連おすすめ記事

初心者ライター必見!ライティング効率UPにつながるChrome拡張機能10選
今回は、特にライターになったばかりの方にオススメしたい、ライティング効率をアップしたいならオススメの便利なChrome拡張機能10選をご紹介します。 どれもちょっとした作業を助けてくれるものばかりですので、業務内容に合わせて適したものをインストールしてみてはいかがでしょうか。

まとめるのが難しい・・・インタビュー記事の基本的な書き方を解説
インタビューした内容をいざ記事にしようとしても、上手くまとめられずに悩んでしまう方は多いのではないでしょうか。インタビュー記事は、インタビュイー(インタビューを受ける人)の伝えたいことを明確に、かつ熱量を残したまま読みやすく執筆したいものです。今回は、インタビュー記事執筆のコツを解説します。

【手順別】記事を作成するときに参考になる記事まとめ
記事を作成するときの方法を、準備編、取材編、執筆編、画像編に分けてご紹介します。記事作成にお悩みの方はぜひ一度ご一読ください。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- 単価
- 商品1つ、あるサービス1回あたり、それらの最低単位での商品やサービスの値段のことを単価といいます。「このカフェではコーヒー一杯の単価を350円に設定しています」などと使います。現在、一般的には消費税を含めた税込み単価を表示しているお店も少なくありません。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他









