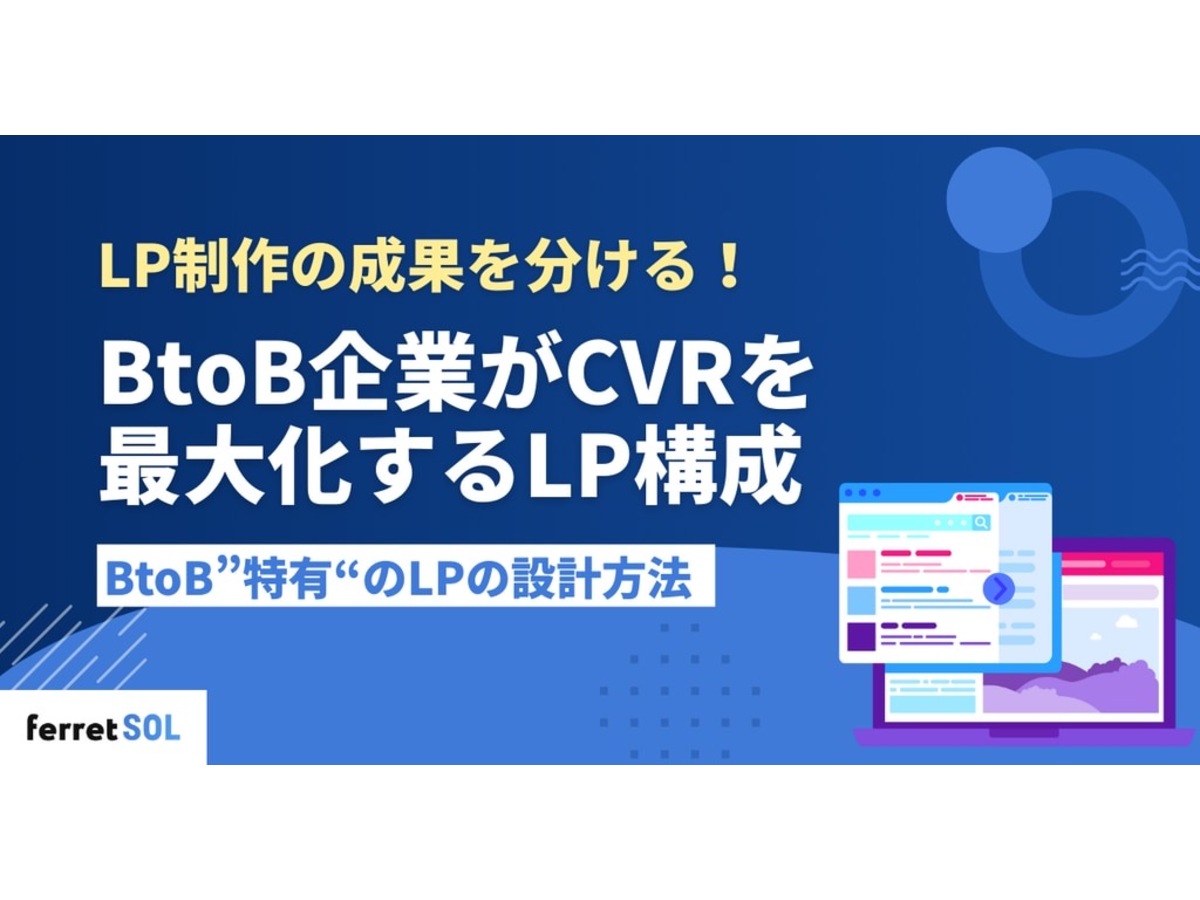CTAとは?クリック率を上げる7つの改善策と基礎知識を紹介
サイトを運営する上で重要な指標のひとつが、「コンバージョン率」です。ネットショップや商品紹介ページを運営している場合、コンバージョン率の向上が目標となっていることも多いでしょう。
コンバージョン率向上のための施策として重要視されているのが、CTA(Call To Action)です。自社のWebサイトを訪れたユーザーに購入や資料請求など、何かしらの行動を起こしてもらうための要素です。CTAを工夫することで、より高いコンバージョン率を狙うことができます。今回は、効果的なCTAを設置するためのポイントを7つ解説します。
この記事を動画で見る
目次
▼リード獲得を増やしたい方はこちらをチェック

リード獲得を増やす “サービスサイト”立ち上げの4つの手順
新たにサービスサイトを立ち上げたいという方の「何からやればいいか分からない」というお悩みを解消できるよう作成しました。
CTAとは

CTAとは「Call To Action」の略であり、日本語では「行動喚起」と訳されます。多くがWeb上でユーザーに行動を起こさせるために設置したテキストや画像のことです。上記画像の赤枠部分を指します。
ページ上で、「資料請求はこちら」や「問い合わせる」といったボタンが配置されていることがよくあります。このような、ユーザーに行動を促すボタンもCTAの一種であり、サイトで資料請求や問い合わせを獲得するには欠かせない要素です。
CTAを設置するとよい例
CTAは、以下のような行動を起こさせる場合によく設置されます。
- 購入
- 資料請求
- お問い合わせ
- 会員登録
- メルマガ登録
- 定期購読登録
- コメント記入
上記のような目的がある場合は、CTAを設置すべきでしょう。
CTAの設置場所
CTAは設置する場所を工夫することで、コンバージョン率向上に繋げることができます。一般的に下記のような場所に設置します。
- Webページのヘッダー・フッター
- サイドバー
- コンテンツ(記事)の途中や直後
- LPのファーストビュー、コンテンツとコンテンツの間
- ページ遷移時にモーダルやポップアップで表示


CTAの設置後も改善が必要
CTAはいわば、コンバージョンまでの道のりをガイドする役割を果たします。コンバージョン獲得を向上させるためには、CTAを目立たせ行動を起こさせる工夫が必要です。
また、ユーザーはさまざまな目的でサイトを訪れるため、その目的に応じたCTAを設置することが大切です。ユーザーのニーズの変化でサイト内容も変化する可能性があります。
CTAは一回設置すればそれで終わりではありません。サイト内容の変化・改修にすばやく対応し、定期的にCTAの見直しや改善を行う必要があります。
▼CV率アップにつながる改善のコツはこちらでもチェック

Webサイトの“もったいない”を無くす!BtoBサイトのCVRを改善する15のチェックリスト
弊社とその導入企業のサイト改善事例から、CVRの改善ポイントを15個リストアップ。改善点と取るべきアクションを、チェックリスト形式でまとめました。
コンバージョン率UPに向けた7つのCTA改善ポイント
1. リンク先をイメージできる文言を使用する
CTAは、Webサイトに訪れたユーザーをコンバージョンに導くためのものです。いかにユーザーに「この行動を取ることで、自分にとってメリットのあるもの(商品や資料、情報など)が手に入る」と思ってもらえるかが重要です。
まずはどのようなユーザーにコンバージョンして欲しいのかを設定し、そのユーザーに響くCTAは何かを考えましょう。
例えば、はじめてSNSに触れる担当者に、SNS運用のコツを伝える資料をダウンロードして欲しいときは、「Instagram」より「インスタグラム」とカタカナ表記した方がひと目でサービス名を認識しやすいかもしれません。分かりやすい表記は重要な要素です。
また、コンテンツの中では答えや結論を明かさず、CTAで「続きはこちら」と誘導することで、ユーザーの関心を惹きつけることができます。

2. 選択肢はできるだけ減らす
資料ダウンロードボタンが5個あるときと1個あるときでは、ユーザーはどちらが行動に移しやすいでしょうか。
一見、選択肢が多いほうが便利に感じるかもしれません。しかし、人は選択肢が多すぎると、その選択肢の多さから選ぶことを諦めてしまう心理が働きます。これを「決定回避の法則」と呼びます。
また、CTAボタンがいくつもあるとユーザーは選択に迷ってしまいます。できるだけ選択肢を減らす工夫をしてみましょう。

関連記事:心理操作でコンバージョン率向上が目指せるかも!?知っておきたい行動心理学7選
但し、BtoB向けや高額商品など、と意思決定に長期間かかるサービスや、段階的に検討していくサービスの場合は複数のCTAを用意するのが主流です。
その場合は、メインとなるCTAが目立つようなデザイン・レイアウトの工夫をすると良いでしょう。

3. 設置場所を意識する
人の視線は、一般的に「左上から右下に向かって移動」や「アルファベットのZやFのように移動」などと言われるように、視線の動きに特徴があります。この視点の動きは、グーテンベルクダイアグラムと呼ばれています。
Z型は横書きの紙媒体の場合、F型は左にメニューのある古い形のWeb媒体などをみる時の視点ですが、近年のWebサイトの構成から、基本的には左上から右下に向かって見ているケースが多いと考えて良いでしょう。
CTAはユーザーの目につきやすい場所に設置することが重要であるため、視線の流れを踏まえて右下や中央など、ページの性質に合わせてに設置場所を工夫しましょう。
また、視線の流れだけでなく、自然に目につく場所に設置するのも有効です。例えば、WebサイトのファーストビューでCTAが目に入るような場所への設置です。

4. 視覚的に強調したデザインにする
色やイラスト、写真などのデザインは、ユーザーの視覚を通して直観的に何らかのイメージを与える効果があります。CTAも、デザインを強調したり変化を加えることでコンバージョン率向上に繋げることができるでしょう。
サイトの全体的なデザインや表現方法を揃える必要はありますが、揃えた結果、CTAがあまりに目立たなくなってしまうこともあるため、普段使わない配色を用いて目立たせることも一つの手段です。
CTAの色やデザインを変更するといっても、どのようなデザインが効果的かは自社Webサイトのターゲットや商品によって異なるため、A/Bテストなどで実際に検証してより効果的なものへ改善していくといいでしょう。

5. ユーザーに起こして欲しい行動を明確にする
CTAでは、ユーザーに「何をして欲しいのか」を明確にしましょう。例えば、「ここをクリック」ではなく、矢印を加えて「↓ここをクリックして購入」「続きを読むにはこちらをクリック▶︎」のように表記を変えるだけでも、ユーザーに起こして欲しい行動が明確になります。
クリックした後どうなるのかが不明確だと、ユーザーは不安になり行動を躊躇してしまいます。積極的な行動を後押しする意味でも、CTAの表現は明確にする必要があります。

ユーザーに何をして欲しいのか明確にし、迷わず行動を起こしてもらいましょう。
6. 緊急性を感じさせる
例えば自社のWebサイトで、「A」という商品を購入してもらいたい場合を考えてみましょう。そのAを今日購入するのか、あるいは来週購入するのかはユーザーに任せられています。
Aに興味をもったユーザーが「来週購入しよう」と、その日は断念し、他社のWebサイトでAを見かけ、他社で購入されてしまうというケースも起こりえます。
このようなケースを避けるためにも、できるだけ今行動を起こしてもらえるようなCTAを設置することが重要です。例えば「期間限定」「数量限定」のような文言を用いたり、ストレートに「今すぐ」といったキーワードを含めたりすることも有効です。

人が期間限定であるもの、数が少ないものなどに価値を感じる心理を、「希少性の原理」といいます。海外のWebサイトで、CTAに「今すぐ」というキーワードを含めたところ、コンバージョン率が147%も向上したという事例があります。
ただ、今すぐと煽るだけでは不安を助長するだけなので、今すぐ必要である理由を示すことが大切です。
参考:How Creating a Sense of Urgency Helped Me Increase Sales By 332%|ConversionXL
なお、この手法は、個人が瞬間的に購入の意思決定をするECサイトなどBtoCサービスには有効です。
BtoBサービスの場合は、「数は獲れるが質が下がる」というこの手法のデメリットがあるので、「まずはリードを増やして分析をしたい」というフェーズや、デモ体験などでサービスのメリットを実感してもらいたい場合には良いかもしれません。
7. ユーザーの心理的な負担を低減させる
人は新しいものには警戒感を抱き、簡単には行動してくれないことも少なくありません。それは「損失回避の傾向」とも呼ばれ、「得をしたい」気持ちより「損をしたくない」気持ちの方が強い心理傾向からきています。
関連記事:マーケティングする上で知っておきたい!行動経済学用語7選
特に「購入」や「資料請求」など、ユーザーの個人情報を入力する必要のあるものは難易度が上がります。ユーザーの不安を低減するには、例えば「会員登録不要」「たった3STEPで完了」など、心理的ハードルを下げるような表記も効果的です。

これまでに説明したコンバージョンを増やすための7つのポイントを踏まえて、クリックしたくなるCTAボタンの作り方についてさらに踏み込んで紹介します。
▼サイト全体のCV率アップを考えるなら

Webサイトの“もったいない”を無くす!BtoBサイトのCVRを改善する15のチェックリスト
弊社とその導入企業のサイト改善事例から、CVRの改善ポイントを15個リストアップ。改善点と取るべきアクションを、チェックリスト形式でまとめました。
クリックしたくなるCTAボタンの「文言」
Webサイトへ訪問してきたユーザーを、最終アクションまで誘導するのがCTAボタンの役割です。 Webサイト制作の最終目的でもあるコンバージョン獲得を左右するため、営業活動のクロージングにあたる重要なボタンです。
ですが、Webサイトの特性上、じっくり検討してクリック、というより、ユーザーが反射神経で「つい」「思わず」クリックしてしまうように設計することが求められます。
①「あ、お得!」「お、イイね!」と思わせる具体性とバリュー感
思わずクリックしてしまうCTAボタンを作るためには、なんといっても文言が最重要です。 ボタンの形状や配色などデザイン性も大事ですが、最終的には、ボタンに示された文言をユーザーが読んで、ユーザーの気持ちに「!」=感嘆符がつくかどうかにかかっています。
例えば、同じアクションを求めるコピーでも、以下の左と右とを比べてどう感じるでしょうか?

反射的にクリックしてみたくなるのは、いずれも右側ではないでしょうか。
- 「ダウンロード」→「無料eBookを手に入れよう」
- 「送信する」→「無料見積もりしてみよう」
- 「今すぐ購入」→「25%オフで購入する」
反射的にクリックしてみたくなるのは、いずれも右側ではないでしょうか。
ためらいなくクリックしてもらうためには、「どのように」「どうすれば」「どのくらい」、ユーザーの利益となるものが得られるのか、シンプルかつ具体的なコピーで明示することが重要です。
② 文字数は視認性に注意
ただし、1つのボタンに全部を詰め込むと、文字数が多くなって一瞬で内容を判断することができなくなります。人が1箇所で瞬時に理解できる文字数は13文字までと言われています。
文言を考える際は、文字数や漢字とカタカナのバランスなど「字面」にもこだわるとより効果的です。

行動を促す動機付けのコツ
マーケティングに多用される心理学テクニックを学び、伝えたい言葉をさまざまな角度からリフレーミングしてみるのも1つの方法です。 ターゲット別に、何が1番効果的に響くのかを探ることで、マーケティングの方向性を決定する判断材料にもなるでしょう。
ここでは、心理の傾向やニーズへのマッチングといった、動機付けについて説明します。
人の心を動かす「チャルディーニの6つの原理」
人を動かすと話題になった「チャルディーニの6つの原理」について解説します。
● 返報性の原理
他人に何かしてもらったら、自分もお返ししなければという心理
例:「無料サンプル」など (無料でもらったら、「買わなきゃ!」と思う)
● 一貫性の原理
一度とった自身の言動を一貫したものとしたいという心理
例:「お試しセット」など (「お試し」で使ったものは、「使い続けなきゃ!」と思う)
● 社会的証明の原理
多くの人間がとる行動は正しいことだという心理
例:「ご愛用者○○人突破!」「○○部門でシェア1位」など
● 好意の原理
好意をもってもらった人のことを信用しやすくなる心理
例:「お得意さまだけに贈る」「日頃のご愛顧に感謝」など
● 権威の原理
権威のある人に従ってしまう心理
例:「○○氏も絶賛!」「○○TVでも紹介されました」など
● 希少性の原理
希少性のあるものほど、価値が高いと思う心理
例:「○個限定発売」「今だけ大特価」
なお、事実と異なる誇大表現やユーザーが誤認してしまうような表現などは、景品表示法で規制されています。CTAやサイト内に行きすぎた表現がないか、法令順守に努め制作しましょう。
「そう、コレ!」「あ、あった!」と思わせるニーズのマッチング

コピーの中に、ユーザーが最も求めている“ニーズを示す”ことができれば、訴求効果は飛躍的に高くなります。
例えば、スカンジナビアにあるスポーツジムチェーンでは、多くの潜在顧客が、ジムのロケーションを重要視していることに気づきました。そこで、「メンバーシップをゲット」というコピーを変更し、「Find your gym(ジムを探そう!)」の一言を加えたところ、コンバージョンが68%もアップしました。
こうしたユーザーのニーズを探る方法として、Googleサジェストを利用するのもひとつです。GoogleサジェストはGoogle のWeb検索の補助機能で、検索欄にキーワードを入力すると、その単語に関連する検索候補を検索頻度順に表示する機能です。
例えば、「ヨガ教室」と入力し、1つスペーシングしてみます。

こちらも、さきほどのスポーツジムの例と同様に、東京、大田区、練馬などロケーションに関する候補が上位に表示されました。
この結果から、東京に店舗があるヨガ教室の場合、「ヨガをはじめよう!」というコピーを「東京でヨガをはじめよう!」と変更することによって、より潜在顧客の注目を浴びやすいCTAボタンになる可能性があります。
適切な改善でCTAの効果を最大限に
CTAはコンバージョンを獲得するために重要な要素であるとともに、ユーザーにとってはニーズに直接アクセスできるガイドにもなります。ユーザーの視点に立ち適切な位置に効果的なCTAボタンを設置する必要があるため、サイト制作においてもCTA設置を考えた構築が必要です。
特にCTAボタンの制作はデザイン性もさることながら、ユーザーの心を動かす文言を掲載することに十分配慮し、定期的に改善を繰り返しましょう。ユーザーのアクションをストレスなく導くことができるCTAを設置することが、コンバージョン向上のカギとなります。
▼これからサービスサイトの立ち上げを考えている方はこちら

リード獲得を増やす “サービスサイト”立ち上げの4つの手順
新たにサービスサイトを立ち上げたいという方の「何からやればいいか分からない」というお悩みを解消できるよう作成しました。
▼本質的で継続的なCV率アップの施策を考えている方はこちら

Webサイトの“もったいない”を無くす!BtoBサイトのCVRを改善する15のチェックリスト
弊社とその導入企業のサイト改善事例から、CVRの改善ポイントを15個リストアップ。改善点と取るべきアクションを、チェックリスト形式でまとめました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ヘッダー
- WEBページの上部スペースに位置し、どのページが開かれても常に共通して表示される部分です。ヘッダーの役割は、まずWEBページを目立たせ、ブランドイメージを訴求することにあります。会社のロゴなども通常はここに置きます。また目次となるメニューを表示し、自分が今どのページにいるかを分からせることもあります。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ファーストビュー
- ファーストビューとは、ユーザーがホームページを訪問した際、スクロールせずに表示される範囲のことです。ディスプレイのサイズや解像度によって、ファーストビューは異なります。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ポップアップ
- ホームページにおいてポップアップとは、現在見ているホームページの上に、重なるような状態で、新たな画面が開き、その最前面面に表示されることを言います。より目立つ、注目を集めることが出来る反面、見ている画面を遮るように表示されるので、不快に受け取られる傾向があります。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- レイアウト
- レイアウトとは、もともと「配置」や「配列」を指す語です。ここでは、「ホームページレイアウト(ウェブレイアウト)」と呼ばれる、ホームページにおけるレイアウトについて説明します。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ファーストビュー
- ファーストビューとは、ユーザーがホームページを訪問した際、スクロールせずに表示される範囲のことです。ディスプレイのサイズや解像度によって、ファーストビューは異なります。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- A/Bテスト
- ホームページを作るときや何か商品を売りたいときに掲載する写真、あるいはデザインで迷ったときに、不規則ででたらめな順番でホームページや画像のデザインを変えて表示し、利用者がどちらをより多くクリックしたのか、より多く購入につながったのか、ということを試験できる技術やサービスまたは行為自体をA/Bテストといいます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- BtoC
- BtoCとは、Business to Consumerの略で、企業と消費者間の取引のことを言います。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他