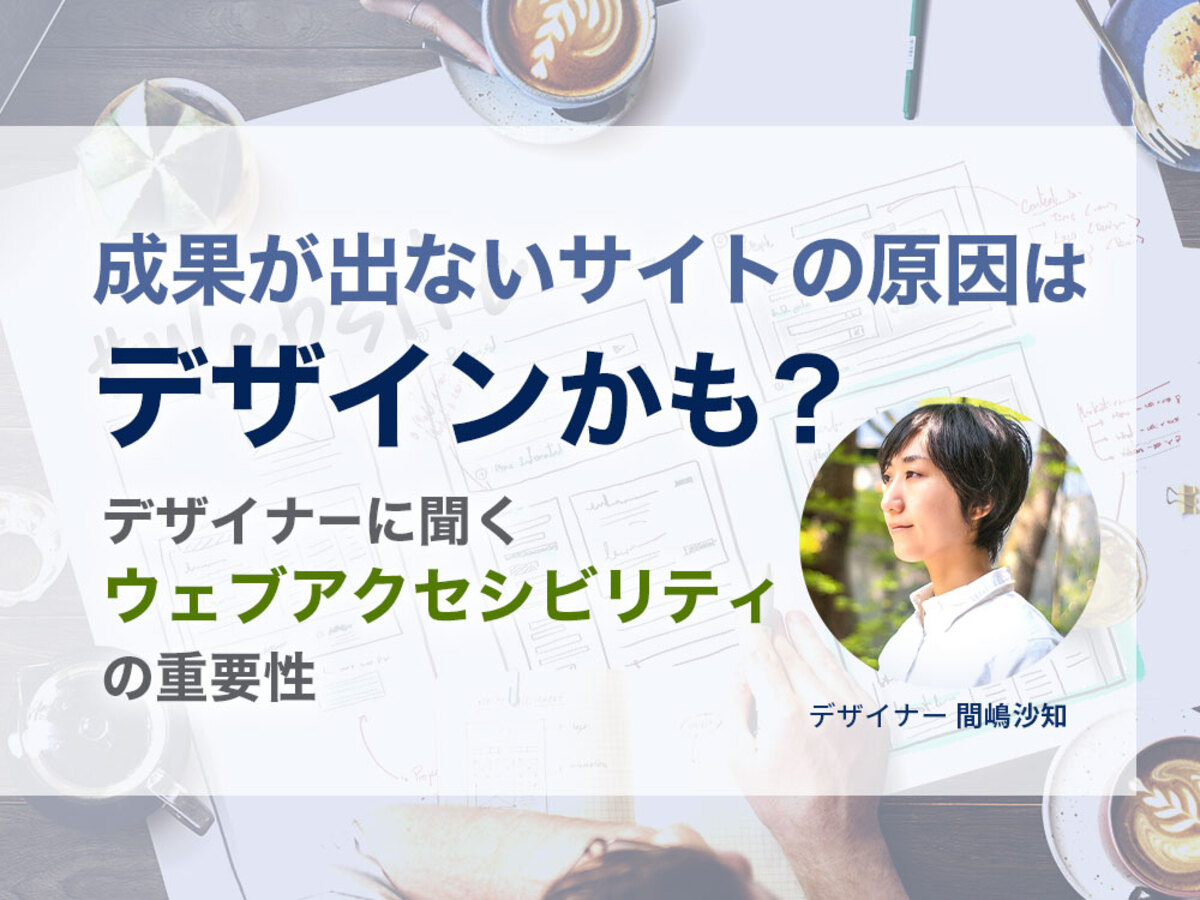RFP(提案依頼書)を作成する上で事前に理解しておきたい4つのメリット
ホームページの制作会社やデザイン・開発会社などに仕事を依頼する際、発注社側が「どのような条件で(制作会社に)作ってもらいたいのか」という内容をまとめた依頼書を作成します。それが、RFP(提案依頼書)です。皆さんも普段の業務でよく聞くワードなのではないでしょうか。
依頼された側は、それをもとに提案書を作り込んでいきます。そして、実際にプロジェクトを立ち上げる前のコンペの段階で企業選定をする際はRFPを各社に配布し、それをもとにプレゼンテーションを実施します。
各社のWeb担当者の方であれば、RFP自体がどのような役割をもっており、そもそも作成することで得られるメリットというものをきちんと理解しておく必要があります。
そこで今回は、Web担当者ならびにホームページやアプリケーション開発などに絡む方であれば必ず押さえておきたい「RFP作成における4つのメリット」をご紹介します。
▼ サイトリニューアルのRFPテンプレートはこちら

サイトリニューアルの【RFP】提案依頼書テンプレート。パワーポイント形式です。
RFP(提案依頼書)とは?

RFPは「Request For Proposal」の略で、提案依頼書のことを指します。つまりは、ホームページ制作やシステム、アプリケーション開発を依頼する際に作成するドキュメントのことです。
提案依頼書によって、発注者はプロジェクトの要件を伝え、制作会社または代理店はこれらをもとに提案を作成します。制作や開発を外注する際に、意思疎通のために作成する重要なドキュメントになります。
参考:
提案依頼書(RFP)とは?作成方法とテンプレートサイト5選を紹介|ferret
RFPを作成する上で知っておきたい4つのメリット
発注する側、お金を払う側がわざわざ資料を作る手間がかかるとなると、後回しにしたり、避けたいと思う方もいらっしゃるでしょう。
しかし、ホームページ制作やアプリケーション開発において、非常に重要なドキュメントであり、発注する側にも大きなメリットがあります。
1. 提案内容の基準になる
ホームページの制作やアプリケーションの開発の発注は、SaaSといったクラウドサービスを利用するのとは違い、基本的にオーダーメイドです。何のためにどん制作物が必要なのかを伝えない限り、制作する会社も何を制作すればいいのかわかりません。
また、制作会社は何でも屋さんではない場合がほとんどであり、この手の開発は得意だけどこれはできないなど、得意不得意があります。必須要件がその会社で実現可能かなど、事前に確認しておく必要があります。
2. イメージどおり、要件どおりの成果物を作るため
RFPは「トラブルを防ぐために握っておかなければいけないことリスト」といったイメージもありますが、前提としてより良い成果物を制作するために重要なドキュメントです。
しっかりと発注者側と提案者側の意思疎通を図り、最終的にイメージ通りの制作物を一緒に作り上げるための基準になります。また、必須要件などの漏れや、後から改修が必要になるのを未然に防ぐ事にもつながります。
3. 言った言わないを未然に防ぐ
ビジネスを進める上で往々にして起こりうることですが、ミーティング中口頭で話していたことから認識のズレは生じることが多々あります。伝えたつもりになっていただけで共通認識になっていないという多く場合もあり、RFPは「言った言わない」のトラブルを未然に防ぐ事にもつながります。
ミーティングにはディレクターのみが参加し、自社に戻ってエンジニアとの話し合いを経て提案が作成されるというケースも多く、この時点でエンジニアは要件を又聞きしている事になります。
考慮してなくてはいけない内容や、利用可能なシステム用件などはRFPを作成し明記する事で、プロジェクトメンバー全員にしっかりと共有でき、トラブルを防ぎ、より良い提案を引き出せます。
4. 提案の評価基準になる
制作会社や代理店など数社でのコンペ提案になる場合、RFPは特に重要になってきます。
各社に対し同一の情報を提供するという意味でもRFPは非常に重要です。発注者側のメリットとして、ドキュメントを1つ作ってしまえば、複数社に何度も1から説明する手間を短縮できます。また、各社ごとに認識のバラつきが出るのを防ぐことができます。
提出されてきた提案書やプレゼンテーションの評価基準にも活用できます。提案の良し悪しは、RFPに書かれている内容にしっかり則していたかを基準に評価することができ、不公平性を排除する事にもつながります。選定する際の基準にもなるため、選定にかかる時間を短縮するができます。
▼ サイトリニューアルのRFPテンプレートはこちら

サイトリニューアルの【RFP】提案依頼書テンプレート。パワーポイント形式です。
RFPに記載する内容

それでは、RFPにはどのような内容を記載すれば良いのでしょうか。
まず、RFPにはこれといった決まった型やルールがあるわけではありません。テンプレートを提供しているサイトも数多くあるので、実際に作成する際には参考にしてみると良いでしょう。
参考:
提案依頼書(RFP)とは?作成方法とテンプレートサイト5選を紹介|ferret
作成にあたり、抑えておかないといけないポイントがあります。実際に盛り込んだ方がいい項目を紹介していきます。
プロジェクト名
まず、制作にあたりプロジェクト名をつけ共通認識としておきましょう。
名称の微妙な言い回しなど、会社のレギュレーションで規定されている場合などにも誤表記を未然に防ぐ事につながります。
目的
提案を依頼するにあたり、プロジェクトの目的を共有しておく必要があります。何のために制作を行うのか?開発をして何をしたいのか?といった大前提をまず記載しましょう。
ホームページ制作といっても、単なるブランディングサイトなのか?サイト上で売上を立てたいのか?などの活用目的によって、大きく様変わりします。また、必要な機能も変わってくるため開発規模や費用感も変わります。
課題の整理/提案の背景
新たな開発を行うにあたり、自社の現状の課題を洗い出し、サイトやシステムでどのように解決していきたいかを明確化しましょう。
もしどのように解決すればいいかが自社内で明確でない場合、制作・開発のプロの目線での提案を期待する旨を記載しておくと、より良い提案を引き出せるかもしれません。
提案の背景を理解してもらう事で、より自社の状況に則した最適な提案につながります。業界独特の習慣なども他業種である制作会社に説明し汲み取ってもらう必要があります。
また、サイトリニューアルの提案の場合、現状のサイトで不便な部分など課題を明記する事で、より良い改善提案を引き出すことができます。
例えば、「サイトの更新に手間やお金がかかってしまっている」といった運用上の課題がある場合は、最適なCMSを選定し提案に盛り込んでもらえるでしょう。
目標
サイトを制作し達成したい目標があれば明記しておきましょう。
ECサイトなど実際に売上を立てるためのサイトであれば、初年度から3年後程度までの売上目標を記載しておくといいでしょう。
予算規模
予算を明記することができれば記載しておきましょう。
制作会社サイドからしてみたら、作業はこだわりだすと際限なくなってしまうこともあり、予算がないと提案が組みづらくなります。また、複数社でコンペにする場合は、予算内で各社がどこまで出来るのかを比べることが可能です。
また、記載する予算が制作に関わるものだけなのか?ドメイン取得やサーバー設定費用などランニングコストを含むかも記載しておくと良いでしょう。
デメリットとして、予算を記載することによって提案内容に制限がかかってしまい、満足のいく提案が受けられないといったことも考えられます。
スケジュール
RFPに記載するスケジュールは、制作・開発に着手する期間やリリースのデッドラインなどだけではありません。提案書提出の期限や各社プレゼンの期間、選定期日なども合わせて記載します。
提案する制作会社側によっては、別の案件との兼ね合いで十分に提案書作成に取り組めないなどの場合があるため、提案スケジュールの作成はお互いにとって重要になってきます。
提案の範囲
RFPにおいて、この提案の範囲を明確化することが最も重要です。プロジェクトの背景を共有した上で、実際に何を提案して欲しいのかを明確にします。
サイト制作・開発においても、デザイン、コーディング、システム開発、保守、運用などさまざまな工程に分かれており、どの範囲まで求めているかを明記しましょう。
また、制作する側は作業する範囲によって工数を見積もり、金額を算出するため、範囲が明確でない場合は見積もりの作成ができません。
システムの要件
開発におけるシステムの要件があれば記載しておきましょう。
サーバーの仕様などによって、利用できないシステムなどもあるため、開発する側にとっては非常に重要な情報になります。
▼ サイトリニューアルのRFPテンプレートはこちら

サイトリニューアルの【RFP】提案依頼書テンプレート。パワーポイント形式です。
まとめ
RFPを作成することはプロジェクトを進める上で非常に重要ですが、やはり担当者の範囲でわからないことは多いでしょう。RFPを作成する目的は前提としてコミュニケーションの円滑化です。
わからないことは制作会社とできる限り密にコミュニケーションを取ることを忘れず、正確でわかりやすいRFP作成を目指しましょう。
参考:
提案依頼書(RFP)の基本的な構成と作成するためのポイント|ferret
RFP(提案依頼書)とは|ホームページ制作時における役割と活用方法|ferret
サイトリニューアルのRFP(提案依頼書)のテンプレートです。
編集しやすいパワーポイント形式(.pptx)
記入例はあくまで参考に、実際の案件に応じて項目を編集してご活用ください。

- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- SaaS
- SaaSとは、Software as a Serviceの略で、ユーザーにソフトウェアの「機能」をインターネット経由で提供することを言います。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- ドメイン
- ドメインとは、インターネット上で利用可能なホームページやメールなどを識別するときの絶対唯一の綴りを言います。電話番号や自動車ナンバーが同一のものがないのと同様に、インタネットにおいても、2つとして同じドメインは存在できない、といった唯一無二の綴りです。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他