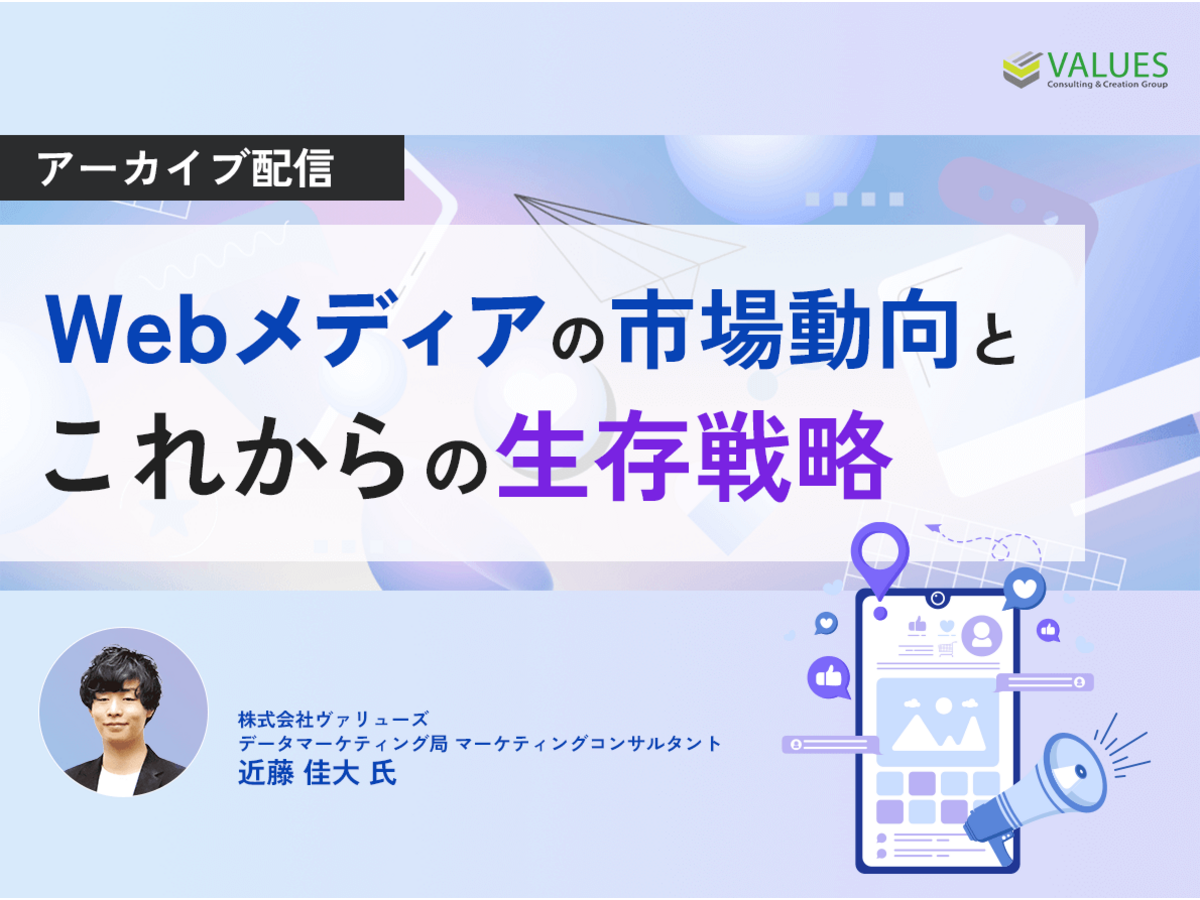データに基づく客観的な意思決定を実現するための“数字との付き合い方”
インターネットやPC、スマートフォンなどの多様な技術の普及は、私たちの生活を大きく変えましたが、マーケティングの世界においてもそれは例外ではありません。
従来では不可能だった生活者のデータが入手できるようになっているとともに、ビッグデータを駆使した調査手法が次々と生み出されており、「データ・ドリブン・マーケティング」や「高速PDCA」などという言葉に注目が集まっています。
しかし、これほどデータの測定が容易になったにもかかわらず、企業のマーケティング活動は順調とは言えません。その理由は、データに基づいた意思決定が困難な場合が多いからです。
今回はマーケティングデータ(数字)との付き合い方について、株式会社インテージの長崎貴裕が解説します。
◆Profile
長崎 貴裕(ながさき・たかひろ)
株式会社インテージ 執行役員 開発本部長
株式会社インテージホールディングス R&Dセンター長
株式会社IXT(イクスト) 代表取締役社長
データ(数字)活用の大前提は変わらず
数字は入口であり、ひとつの基準です。
マーケティングリサーチは、商品開発やブランドを市場に定着させるために欠かせないものですが、現実的に使いこなすためには、恣意的な要素が入り込む隙を与えず客観的な根拠として機能させていくことが肝心です。
例えば、「好感度が何ポイント以上でなければ、次のステップ(商品化)には進まない」といった明確なルール作りが求められます。加えて、数字を読み解くためには、“経験の蓄積”が不可欠です。これがなければ、何を調査しても得られるものはだだの数字に過ぎません。
企業のマーケティングを取り巻く環境は大きく変化していますが、大前提としてのデータとの付き合い方は変わっていないのです。
数字に基づいた意思決定・・・具体的な手順は?
仮に、発売予定の「ブランドB」についてアンケート調査を実施したところ、「買いたい」という回答が3.8ポイントあったとします。
"この3.8という数字は何を意味するのか?"これを読み解くために、蓄積した経験が大きな意味を持ちます。
例えば、過去に立ち上げた類似ブランドのケースとして、「3.5の時は失敗したが、3.7ある時はうまくいった」という数字の蓄積があれば、「今回は3.8だから大丈夫」という決断に結び付けることができます。
ただなんとなく、「3.8もあるんだからちょっといい感じじゃない?」という評価では、客観的な判断とは言えません。
当然ながらマーケティングリサーチにも限界はあります。どんなに大規模な調査を実施して、「買いたい」と回答するモニターの声をたくさん集めたとしても、確実に全員が購入するわけではありません。
だからこそ、
「過去にアンケート調査を実施した際、商品Aには“やや買いたい”と“買いたい”が合計で●%あった。そこで新しい商品コンセプトを投入したら×××という結果になった。」
「●%のモニターが“また買いたい”と答えていたが、実際には他社の新製品が出るとすぐに乗り換えられた。」
こうした経験の蓄積は重要な意味を持ってきます。
一回だけの調査で良し悪しを判断するのは無理です。「調査などあてにならない」という人ほどそういうことを意識していないのではないでしょうか。
また調査は、常に同じ基準で実施することが肝心です。
例えば、ある商品を調査するにあたり、「前回はお金があったから3,000サンプルで実施したが、今回は予算を削られたため1,000サンプルで」……と、これでは比較ができないので意味がありません。
市場競争で勝ち残るための原則
客観的な意思決定は、市場競争で勝ち残るために欠かせない原則です。誤解を恐れずに言うと、きちんとした企業はみなデータ(数字)に基づいて意思決定や将来予測をしています。
マーケティングの世界は大きく進歩しており、取れるデータも多様化しています。しかしその一方で、商品の寿命はどんどん短くなっています。
例えば、清涼飲料水の新製品の数はここ20年で2~3倍に増えましたが、同時に商品の短命化も進み、2年後にその製品が生き残っている割合は3割以下となっています。競争は確実に厳しくなっています。
モノを売ることがますます複雑化する中で、多くの企業がマーケティングを積極的に活用しようとしています。とはいえ「DMP」にしろ「マーケティングオートメーション」にしろ、流行りのマーケティング手法だからという理由だけで飛びついても、満足な結果を得ることは難しいでしょう。
マーケターとしても、消費者インサイトを理解したいという企業の求めに答えられるよう、常に新しい調査手法を考え続けていく必要があります。
インターネットリサーチ番外編

広告の正しいターゲティングとは
「DMP(データ・マネジメント・プラットフォーム)」は、Web広告の新たな施策として広まっていますが、実際に見ていると、まだきちんとターゲットに広告が届いていないと思うことが多々あります。
例えば、20代に向けて広告を配信したつもりが、40代にも表示されていたケース。父親が娘へのプレゼントを探して商品を1、2度検索したら、それ以来ずっとリターゲティングされていたようです。
とはいえ、ネット上の行動を見るだけでは属性を誤認しても仕方がないような人が増えているのも事実です。
代表的なのは女性を演じている男性でしょうが、逆の見方をすると、商品を買ってくれていれば、別に女性としてターゲティングしてもいいという見方もあります。
現実的に考えるなら、こちらの方が属性でセグメントするよりも正しいターゲティングかもしれません。
「ポイントはいらない」という善意の回答者
インターネット調査では、アンケート答えてくれた方にポイントをお支払いします。しかし、ポイント目当てで回答するモニターは質が良くないといわれることがあります。
では、ポイントを目当てにしていない回答者とは、一体どんな人なのでしょう?私個人としてはこういう人の方がずっと不思議でなりません。
ポイント目当てでも多くの方は真剣に答えてくれていますし、稀にいい加減な回答をする人がいても、そういう回答はリサーチ会社それぞれが様々な工夫で除外しています。
以前、グループインタビューで40代のモニターにポイントをお支払いすると言ったらびっくりされたことがありました。「この世界に貢献したい」という善意から、無償でご参加いただいていたようです。色々な方がいるのがインターネットリサーチの世界と考えさせられました。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ビッグデータ
- ビッグデータとは、一般に、インターネットの普及とITの進化によって生まれた、事業に役立つ知見を導くためのデータのことを指します。「データの多量性」だけでなく、「多様性」があるデータを指します。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- PDCA
- PDCAとは、事業活動などを継続して改善していくためのマネジメントサイクルの一種で、Plan,Do,Check,Actionの頭文字をとったものです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他