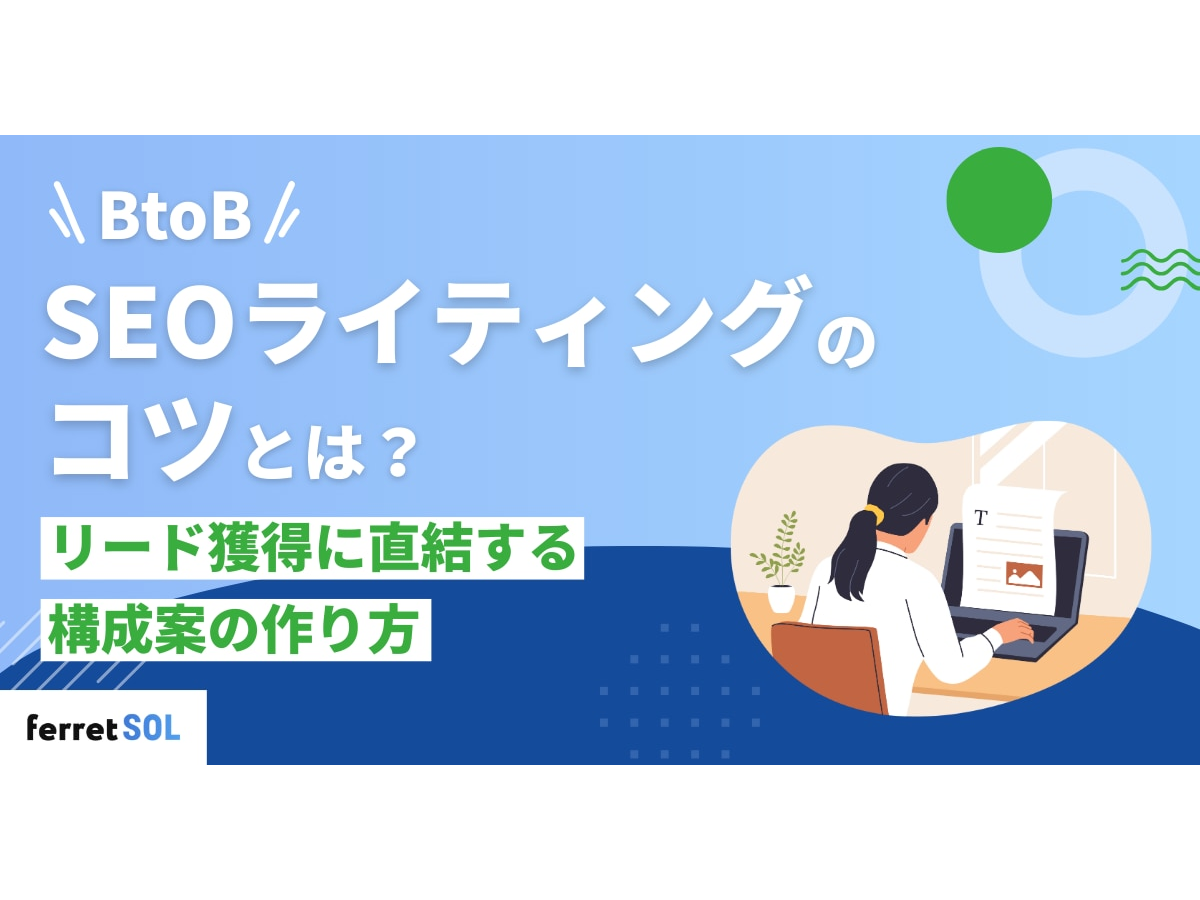「文脈効果」をマーケティング活用して商品価値を高めよう
映画を映画館に見に行くと空腹でもないのにポップコーンが食べたくなったり、仕事が終わって家に帰るとビールを飲みたくなったりと、意識していないけれど「〇〇という状況では〜〜する」ということはないでしょうか。
これは「文脈効果」という心理学で説明される現象で、周辺の状況、つまり「文脈」で人間の認知や行動が変わるというものです。この文脈効果は、商品をより魅力的に見せるキャッチコピー作りやサービスの価値を高める環境作りにも活用されています。
今回は、マーケティングで有効活用できる「文脈効果」について紹介します。
文脈効果とは
文脈効果とは、周囲の情報・状況によって対象の認識が変わることがある現象を指します。
例えば、「おなかが痛い」と言われたときに、それが「笑いすぎておなかが痛い」のか「体調が悪くておなかが痛い」のか、その言葉だけではわかりません。けれども、相手の表情やその場の状況を見るとどちらの意味なのか判断できるでしょう。これが文脈効果です。
マーケティング用語としても使用される文脈効果は、アメリカの認知心理学者ジェローム・シーモア・ブルーナー氏によって1955年に提唱されたものです。

実験では、上の図のような「崩れたB」の文字がどのように読まれるのかを検証しました。
その結果、「L・M・Y・A」をはじめに見たグループは「B」と読む人が多く、「16・17・10・12」をはじめに見たグループは「13」と読む人が多いという結果になりました。
このことから、人はあるものを認識するとき、対象そのものだけでなく周囲の情報を踏まえて判別していることが立証されました。
文脈効果との関連が深いカスタマーエクスペリエンス(CX)
文脈効果とセットで考えたい要素に、カスタマーエクスペリエンス(CX)があります。カスタマーエクスペリエンスとは、商品やサービスそのものだけではなく、それらを利用する際に得られる価値を含めた「顧客体験」です。
例えば、「おしゃれなカフェでコーヒーを飲む」シーンを想像してください。
お金を払って入手する品物はコーヒーですので、品物そのものの価値はコーヒーにのみ与えられます。しかし実際には、カフェの雰囲気、インテリア、BGMなど、周囲の環境も商品の購入に付随してきます。
このプラスアルファとなる要素が、カスタマーエクスペリエンスを高めるうえで重要です。
これを文脈効果と照らし合わせると、「カフェでコーヒーを飲むという体験」が商品である1杯のコーヒーの価値を高めていると考えられます。同じ1杯のコーヒーであっても、周囲の環境をリッチに整えることで、商品そのもの以上の価値をユーザーに感じてもらえるようになるのです。文脈効果を活用しカスタマーエクスペリエンスを高めると、顧客や売上の増加が期待できるでしょう。
参考:
カスタマーエクスペリエンス(CX)とは?“体験への価値”を高めるために知っておきたいこと|ferret [フェレット]
文脈効果に関連する心理効果3つ
1.ハロー効果
ハロー効果とは、対象の外部要因の影響を受けて評価が変化する効果のことです。
権威ある人からの推薦や、科学的な効果の証明などを宣伝文句に織り込むことで、ユーザーに「これは良い商品・サービスである」というイメージを持ってもらうことができます。ユーザーから信頼を得るための手段として活用できるでしょう。
ハロー効果の詳細については、以下の記事を参考にしてください。
参考:
ハロー効果とは〜あらゆる行動に影響のある心理効果を理解しよう|ferret [フェレット]
2.プライミング効果
プライミング効果とは、直前に示された情報に人の認識が影響されやすくなるという効果です。
商品やサービスに触れる前のタイミングで、その商品の印象がよくなるような情報を提供すると、ユーザーの購買意欲を高められる可能性があります。
プライミング効果については、以下の記事を参考にしてください。
参考:
人は自分が思っている以上に先行情報に引っ張られる!「プライミング効果」についての解説|ferret [フェレット]
3.カクテルパーティー効果
カクテルパーティー効果とは、人は自身の興味がある情報を無意識に集める傾向にあるという効果です。
自社のターゲットを明確にして、ターゲットの興味がある情報を想定し発信していれば、ユーザーから積極的に自社情報を集めてくれるようになるでしょう。
カクテルパーティー効果については、以下の記事を参考にしてください。
参考:
カクテルパーティー効果とは?興味のある情報はよく聞こえる心理作用を利用しよう|ferret [フェレット]
文脈効果を利用した例
文脈効果は、マーケティングでも活用ができます。
周辺環境や前後の状況、時間軸などを総合的に含めた「文脈」を整えることは、商品やサービスの販売促進に繋がるでしょう。
文脈効果をマーケティング活用するためのポイントを紹介します。
1.商品を取り囲むレイアウトを工夫する
同じ商品でも、販売する環境でユーザーから見た商品の価値は変化します。
例えば、同じコーヒーを販売する場合、スーパーで販売するか、おしゃれなカフェで販売するかで商品の印象は変わります。
実店舗の場合は内装を、ECサイトの場合はホームページのデザインを工夫すると、同じ商品をより魅力的に見せられるようになるでしょう。
身近な例
・ジュースのパッケージに水滴のついたフルーツの写真を使用して鮮度の高さを演出している
・銭湯に行くと、売られている牛乳やフルーツ牛乳がのみたくなる
・同じ缶ビールでも、そのまま飲むよりグラスに入れて泡を立てて飲むとおいしく感じる
2.「定番」の流れをつくる
文脈効果を活用するときは、「AといえばB」というような定番の流れを作るように意識をしてください。
例えば、長期間に渡り同じキャッチコピーで宣伝をしたり、商品の用途をそのまま商品名にしてみたりすると、ユーザーが特定のシーンに遭遇した時に企業や商品を思い浮かべてくれる確率が高くなるでしょう。
身近な例
・「やっぱりイナバ。100人乗っても大丈夫」(株式会社稲葉製作所(イナバ物置))
→丈夫な物置といえばイナバという連想
・「一目で義理とわかるチョコ」(有楽製菓(ブラックサンダー))
→義理チョコと言えばブラックサンダーという意識形成
・「がんばる人の、がんばらない時間。」(ドトールコーヒー)
→ゆっくり休む場所としてのポジションの確立
まとめ:文脈効果を活用して商品価値を高めよう
文脈効果をマーケティングに活用するためには、商品だけに目を向けず、周辺の情報にも気を配ることが重要です。
商品名やコピーを考える際は、商品を使用する前後のイメージが浮かぶような表現を用いたり、関連するほかのよいイメージのものと組み合わせて商品イメージをアップしたりなど、商品の価値を高める工夫をしましょう。
ただし、「周辺環境を整えても商品の価値そのものは変わらない」ということを忘れてはいけません。不自然に表現を盛りすぎてしまうと、ユーザーに商品の魅力が伝わらないだけでなく、不信感を抱かせてしまうこともあるので注意してください。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他