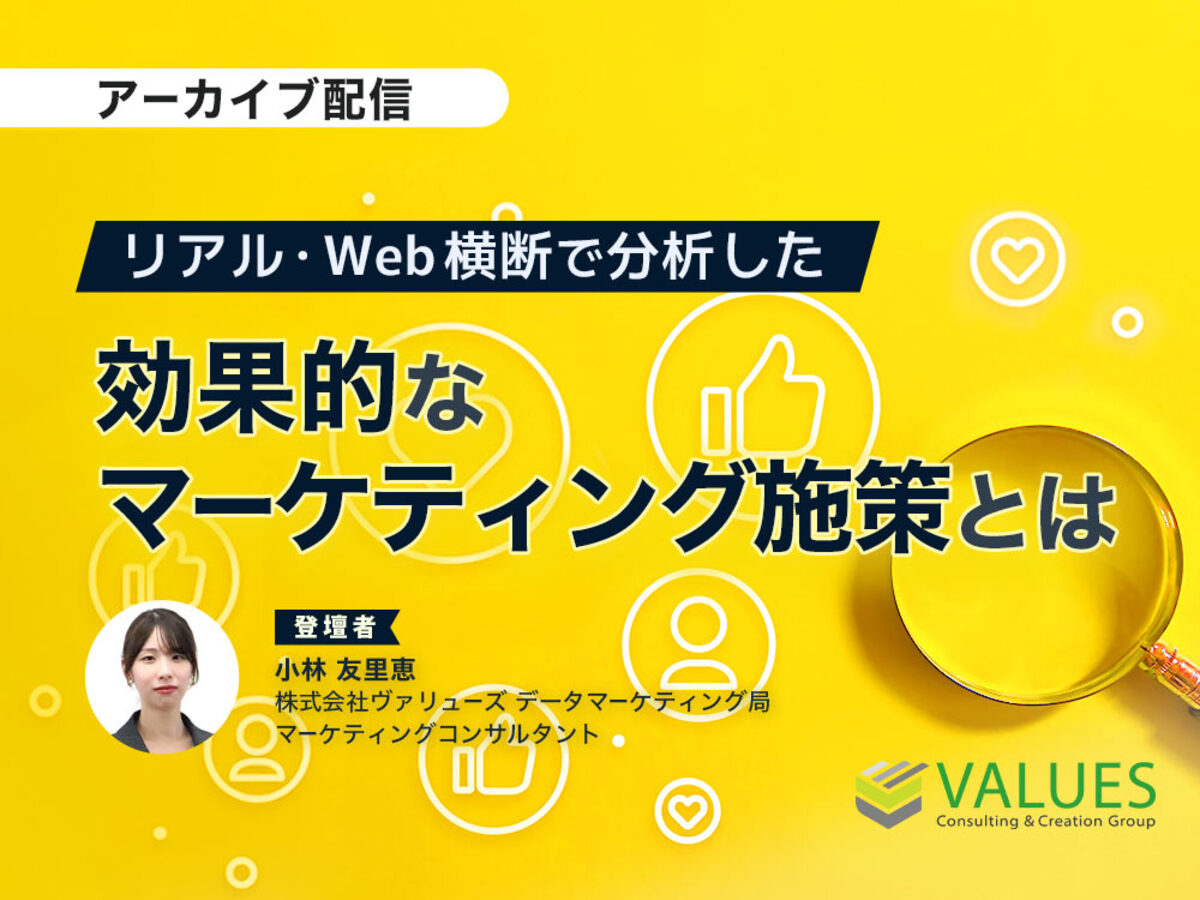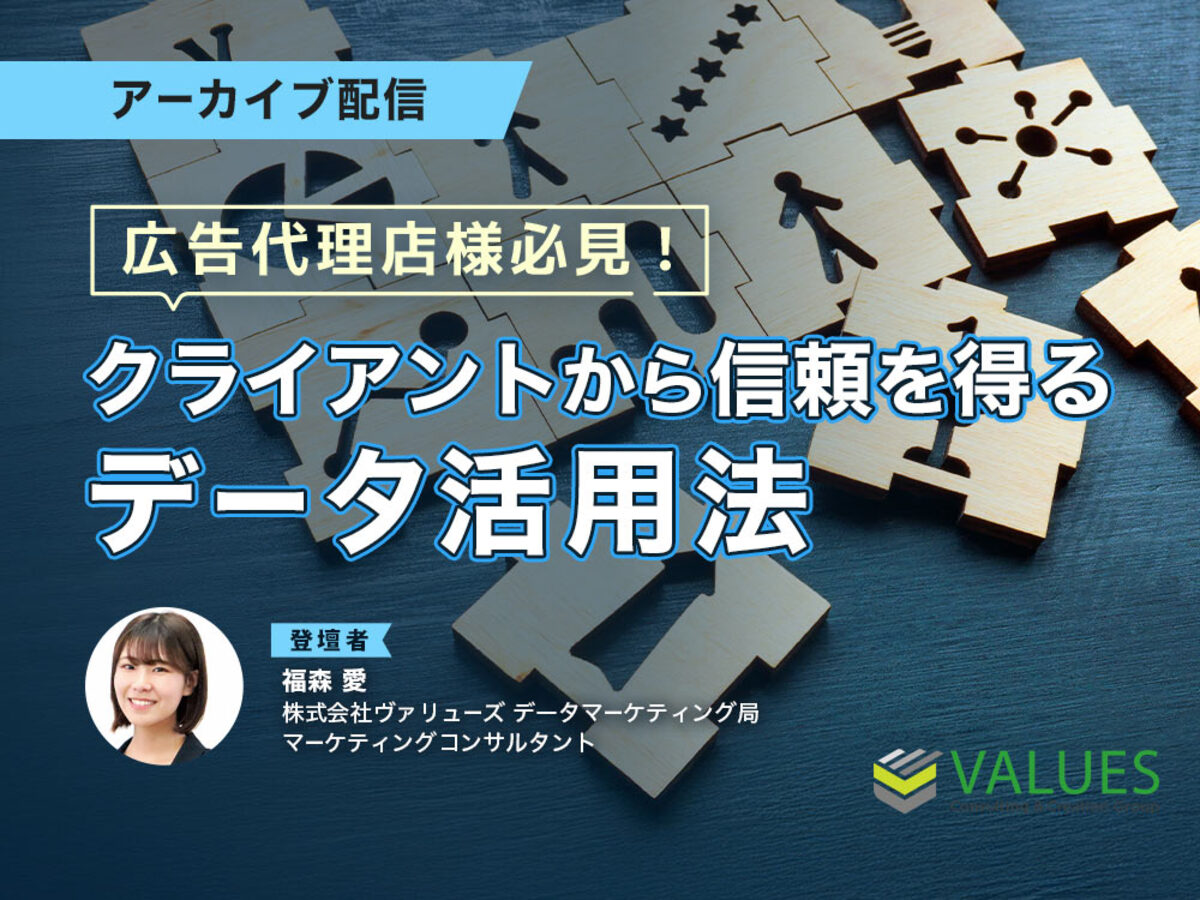【テンプレートあり】マーケティングミックス「4P分析」「4C分析」の意味と検討ポイント
どのようなビジネスを行うにしろ、確実に必要なのが「戦略」です。
どのような内容の企画や施策であっても、戦略なくしての成功は期待できません。
無数の戦略フレームワークがありますので、すべてを把握することは難しいものの、少しずつでも理解していく必要があります。
今回は、その中でもマーケティングミックスと呼ばれる「4P」「4C」についてご紹介します。
それぞれの意味するところと検討ポイント、検討する際に有効なフレームワークなどをご紹介していますので、企画や施策などを始める前の知識として参考にしてみてください。
マーケティングミックスとは
マーケティングミックスとは、「企業のマーケティング戦略において期待している効果を引き出すために、様々なマーケティングツールを組み合わせた施策」を指します。
有名なものでは「4P分析」「4C分析」の2つのフレームワークが該当します。
4P分析とは

4P分析とは、1960年代前半にアメリカのジェローム・マッカーシーという経済学者が提唱したフレームワークです。
売り手側の視点からみたフレームワークで、商品やサービスを開発する際に検討しなければならない4つの要素(「Product」「Price」「Place」「Promotion」)の頭文字をとったものです。
Product:製品
これから販売しようとしている「製品」の本質的な価値を明確にします。
合わせて、その商品・サービスの付加価値も考えてみましょう。
Price:価格
モノが売れるかどうかを大きく左右する「価格」を検討します。
商品やサービスを提供する際に必要なコストや、市場での価格(市場浸透価格、またはペネトレーションプライシング)、商品のライフサイクル(PLU、時間の推移に伴う売上高の変化)などから総合的にみた価格戦略施策を立てるようにしましょう。
Place:流通
商品やサービスを「流通」させるための最適解(流通経路や販売経路、陳列方法、店舗の立地など)を検討します。
実店舗なのかネットショップなのか、自社販売なのか代理店販売なのかなどによって、必要となるコストや流通経路は異なります。
どのような販売経路が最適なのかは商品・サービスによって異なりますので、ターゲットとしているユーザーに最適な販売経路などを模索しましょう。
Promotion:宣伝
商品やサービスの「宣伝」方法について検討します。
すぐれた商品・サービスであっても、ユーザーに認知してもらわなければその存在を知ってもらうことはできません。
予算などを検討しつつ、テレビでのコマーシャル・雑誌などのマスメディアでの広告や、各SNS上や検索エンジン上に表示されるネット広告などを駆使する必要があります。
ここでは、AIDMAやAISASといったユーザーが商品やサービスを購入する際のプロセスをモデル化したフレームワークを活用することもオススメします。
ユーザーの行動を理解することで、やみくもに宣伝するよりも戦略的な宣伝を行うことができます。
AIDMA・AISASについては、ferret内の以下の記事で詳しくご紹介していますので、ぜひ参考にしてください。
参考
ちゃんと区別できてる?AIDMAとAISASの違い|ferret

4P分析のテンプレート
マーケティング戦略の立案に役立つ!4C分析のテンプレートをダウンロードできます
4C分析とは

4C分析とは、1993年にロバート・ローターボーンが提唱したフレームワークです。
買い手側の視点からみたフレームワークで、自社の商品やサービスから消費者であるユーザーが得られるメリットのうち最も重要な4つの要素(「Customer value」「Customer cost」「Convenience」「Communication」)の頭文字をとったものです。
Customer value:顧客価値
商品やサービスが、ユーザーに対してどのようなメリットを提供できるのかを検討します。
あくまで、ユーザーが感じる価値に焦点を当てることが重要です。
商品やサービスで楽しい気持ちになれるか、優越感を味わえるか、生活が便利になったと感じるのかなど、ユーザー目線で感じる価値を明確にしましょう。
Customer cost:顧客コスト
商品やサービスを購入する際に、ユーザーが負担しなければならないコストについて検討します。
ユーザーが商品やサービスを購入する際に、高すぎる/安すぎると感じない、最適な価格帯を探ります。
似たような商品やサービスの市場価格から、どの価格帯の売れ行きがよいのかを分析してみるとよいでしょう。
Convenience:利便性
商品・サービスを使用することで得られる便利さや、購入の際の利便性などについて検討します。
最近では、インターネットの普及により24時間どこにいても商品やサービスを購入することができます。
似たような商品・サービスが市場に多く出回っている場合は、利便性に焦点を当てることをオススメします。
逆に、高級品の場合は入手困難なものへ人気が集中する場合もあります。
一概に、入手しやすい方がよいとも言えませんので、扱う商品・サービスの価値に合った利便性を構築しましょう。
Communication:コミュニケーション
売り手・買い手双方のコミュニケーションを円滑に行う仕組みについて検討します。
例えば、専用のお問い合わせフォームを作成する、TwitterやFacebookの企業アカウントでコミュニケーションをとるなどの方法が考えられます。
売り手側が発信したメッセージ(宣伝で発信した情報)が、ユーザーに届いているのか、またはユーザーからの声が企業側に届いているのかという2つの観点を持つことがポイントです。
コミュニケーションが円滑に行える仕組みを作成しておくと、商品・サービスそのものだけではなく、企業のエンゲージメントも向上します。
ファンが増えれば増えるだけ利用するユーザーも増えますので、コミュニケーション面も疎かしないように注意しましょう。

4C分析のテンプレート
マーケティング戦略の立案に役立つ!4C分析のテンプレートをダウンロードできます
共生的4C
企業と企業、企業とユーザー、国と国、というように共に生きて利益だけではなく信頼を最優先事項とする自由市場経済でのマーケティングのことを「共生マーケティング」と言います。
共生マーケティングの4つの要素は、1972年に早稲田大学商学部研究科の修士論文で紹介されたことが始まりです。
先にご紹介した「4P」「4C」をより包括的に、売り手・買い手の双方の視点からマーケティングを考えるフレームワークです。
共生的4Cについても検討すると、先にご紹介した4P・4Cの双方の視点から商品やサービスについて検討できているかチェックすることができますので、こちらも合わせて理解しておきましょう。
Commodity:商品
売り手である企業側と買い手であるユーザー側が、共に商品やサービスを作り上げていくことを意味します。
Cost:価格
「constare(共に立ち上がって犠牲を払う)」という言葉が、もともとの意味です。
商品やサービスの価格や生産・販売などのコストだけではなく、社会的なコストや環境的なコストなども含めて、商品やサービスによって課されるすべてのコストを意味しています。
Communication:コミュニケーション
企業側のプロモーションだけではなく、ユーザーもSNSなどで商品やサービスに関する情報を拡散し、企業とユーザーが共に商品やサービスに「価値」を持たせることを意味します。
Channel:流通経路
流通経路としては、企業側・ユーザー側のどちらから見ても、簡単で低コストな流れを作ることが重要です。
そのためにも、実店舗とインターネットの融合が大きなポイントとなります。
それぞれの特性を活かしつつ、より最適な経路を検討しましょう。
合わせて行いたい「STP分析」
STP分析とは、商品やサービスのマーケティング手法の選択を、以下の3つの視点から検討するフレームワークです。
- Segmentation:セグメント
- Targeting:ターゲットユーザーの設定
- Positioning:ポジション取り
マーケティング手法について検討する前に、STP分析を実施して市場価値が高く、自社の独自性や優位性を活用できる場所を検討しましょう。
ここで熟考することで、やみくもに商品やサービスの開発をするのではなく自社がより「勝てる」ものを検討することができます。
セグメント
ここでは、市場全体を4つの変数を軸にしてセグメントします。
- 1.地理学変数:気候、文化、行動範囲、人口密度など
- 2.人口動態変数:年齢、性別、家族構成、職業など
- 3.行動変数:購買タイミング、購買目的、購買心理など
- 4.心理的変数:ライフスタイル、価値観、趣味、パーソナリティーなど
この4つの軸を中心にセグメントを行うことで、今まで気がつかなかった市場の存在や将来ターゲットとなりうるセグメントに気がつくことがあります。
ターゲットユーザーの設定
自社のブランドイメージや価格帯などがカバーしている、ユーザーのグループを分析します。
ターゲットとなるグループは、必ずしも1つである必要はありません。
自社の商品やサービスでニーズを満たすことができ、長期的にユーザーとなりうるグループを選択しましょう。
ポジション取り
自社の消費やサービスが持つ強みや、独自性などを追及します。
ここを明確かつ具体的にできていればいるほど、長期的に市場におけるポジションを確立しやすくなります。
より強固なポジショニングのためにも、SWOT分析を活用して検討することをオススメします。
なお、SWOT分析については、ferret内の以下のページにて解説していますので、せひ参考にしてください。
参考
考えを整理するならこれ!SWOT分析をマスターしよう!
4P・4Cについて理解し活用してみよう
ビジネスを行う上では、企業側の利益を考えることはもちろん、ユーザー視点の利益も考慮することが重要です。
どちらの視点が欠けても、よい商品やサービスを提供することはできません。
よりよい商品・サービスを提供するためにも、今回ご紹介した4P・4Cについて理解し活用することは必須です。
どのような点に注意すればいいのか、ぜひ本記事を参考に分析を行ってみてください。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 4C
- 4Cとは、購買者視点で商品やサービスを考えるマーケティングのフレームワークで、Consumer value(顧客にとっての価値)、Cost(顧客の負担)、Convenience(入手の容易性)、Communication(コミュニケーション)の頭文字をとったもののことを言います。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- サイクル
- サイクルとは、スタートしてゴール、そしてまたスタートと、グルグルと循環して機能する状態のことを言います。まわりまわって巡っていく、といった循環機構をさすことが多いです。水の循環サイクルというように、実は繰り返しになってしまう使われ方もすることもしばし。また、自転車に関する事柄として、サイクルスポーツなどという使われ方をされることもあります。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- AIDMA
- AIDMAとは、顧客が購買に至るまでを5つの段階でわけた、購買プロセスモデルのひとつです。
- AISAS
- AISASとは、顧客が購買に至るまでを5つの段階にわけた購買プロセスの一つで、株式会社電通によって提唱されました。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- AIDMA
- AIDMAとは、顧客が購買に至るまでを5つの段階でわけた、購買プロセスモデルのひとつです。
- AISAS
- AISASとは、顧客が購買に至るまでを5つの段階にわけた購買プロセスの一つで、株式会社電通によって提唱されました。
- 4C
- 4Cとは、購買者視点で商品やサービスを考えるマーケティングのフレームワークで、Consumer value(顧客にとっての価値)、Cost(顧客の負担)、Convenience(入手の容易性)、Communication(コミュニケーション)の頭文字をとったもののことを言います。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 4C
- 4Cとは、購買者視点で商品やサービスを考えるマーケティングのフレームワークで、Consumer value(顧客にとっての価値)、Cost(顧客の負担)、Convenience(入手の容易性)、Communication(コミュニケーション)の頭文字をとったもののことを言います。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- 4C
- 4Cとは、購買者視点で商品やサービスを考えるマーケティングのフレームワークで、Consumer value(顧客にとっての価値)、Cost(顧客の負担)、Convenience(入手の容易性)、Communication(コミュニケーション)の頭文字をとったもののことを言います。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- フレームワーク
- フレームワークとは、アプリケーションソフトを開発する際によく必要をされる汎用的な機能をまとめて提供し、アプリケーションの土台として機能するソフトウェアのことです。 元々は枠組み、下部構想、構造、組織という意味の英単語です。アプリケーションのひな形であり、これを開発に利用することで、大幅な効率の向上が見込めます。
- ターゲットユーザー
- ターゲットユーザーとは、自社の商品やサービスを利用するユーザー、または、運営するホームページの閲覧を増やしたいユーザーを、性別、年代、職業など、様々な観点から具体的に定めることを指します。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- SWOT分析
- SWOT分析とは、ある目標を達成する際に企業が自社の内部環境と外部環境を整理するためのフレームワークのひとつです。
- SWOT分析
- SWOT分析とは、ある目標を達成する際に企業が自社の内部環境と外部環境を整理するためのフレームワークのひとつです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- 4C
- 4Cとは、購買者視点で商品やサービスを考えるマーケティングのフレームワークで、Consumer value(顧客にとっての価値)、Cost(顧客の負担)、Convenience(入手の容易性)、Communication(コミュニケーション)の頭文字をとったもののことを言います。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他