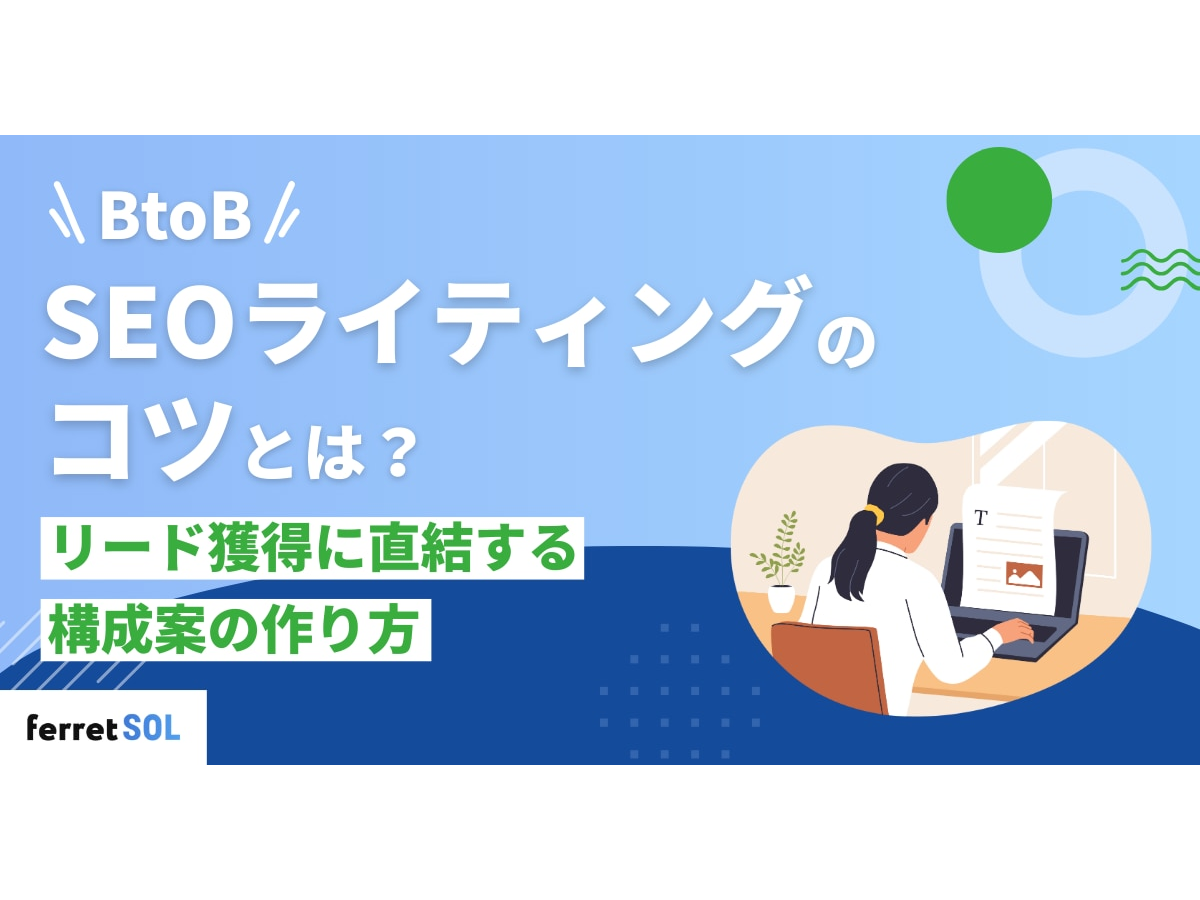これから行政との取引を考えている企業必見!BtoGマーケティングの基本を解説
自社の商品・サービスは企業だけでなく、地方自治体を対象にしても展開できるのではと考えたことはありませんか?
例えば、文書管理サービスや受付システムなどBtoB向けの商品やサービスの中には行政に適したものもあるでしょう。
ですが、今までBtoBで展開してきた企業にとっては、行政との取引がどういうものなのか想像もつかないかもしれません。
行政との取引はBtoBやBtoCに対して*「BtoG」*と呼ばれ、入札制度などの独自の取引形態が特徴です。
今回は、入札制度の解説も含めBtoGマーケティングの基本知識を解説します。
行政機関であっても、利用しているサービスの切り替えや新しいサービスの導入は発生します。切り替えや導入のタイミングを正しく掴むことができれば、新規受注も可能かもしれません。
ぜひこの機会にBtoGの基本を学んで、自社の販路を広げられるようになりましょう。
BtoGとは
企業から提供する商品・サービスは販売する対象によって内容や取引の方法が異なります。
企業を対象にした取引はBtoB(Business to Business)や、消費者を対象にしたBtoC(Business to Consumer)という言葉を聞いた事がある方も多いでしょう。
なかでも、企業と行政機関の商取引は*BtoG(Business to Government)*といい、BtoB・BtoCとは異なる特徴を持ちます。
参考:
情報処理実施調査Q&A|経済産業省
違いをはっきり説明できますか?BtoB、BtoC、CtoCの定義を解説
BtoGとBtoBの取引上の違いとは
BtoGの対象となる行政機関には、経済産業省や総務省といった官公庁だけでなく、地方自治体や独立行政法人などがあります。
それらの行政機関が商品を買い付けたり、サービスを新たに取り入れる場合、企業とは異なる法律が関わってくるのが特徴でしょう。
例えば、地方自治体であれば、トイレで利用するトイレットペーパーから庁舎の建て替えまで取引する企業の条件や契約に関わる手順は地方自治法で定められています。行政機関と企業との癒着を防ぐための規定も存在しているので、新しい自治体と契約を結ぶ際には注意が必要でしょう。
なお、行政の契約方法には、大きく分けて「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」の3つの形態があります。
1.一般競争入札
一般競争入札とは公に取引する企業の募集を行い、同じ条件のもと企業ごとの見積もりを付き合わせて取引する企業を決める方法です。
見積もりの付き合わせである「入札」に参加するのに必要な資格や入札の場所・日時などの必要事項が事前に明かされ、企業はそれに合わせた仕様書や見積もり書を作成します。
入札してきた企業のうち最低価格の見積もりを提出した企業を採用する「最低価格落札方式」と、提案してきた内容をもとに総合的に見てもっとも優れた企業を採用する「総合評価方式」の二種類があるので注意しましょう。
【一般競争入札の特徴】
・透明性、競争性、公正性、経済性が高い。
・行政の契約担当者の事務上の負担が大きい。
・参加条件に合わない不適格業者が混入する可能性が大きい。
参考:
一般競争入札について|経済産業省
2.指名競争入札
指名競争入札とは業務を請け負うのに適切だと思われる複数の企業に対して、行政から入札への参加通知を出し、入札に参加した企業の見積もりを付き合わせて取引する企業を決める方法です。
【指名競争入札の特徴】
・一般競争入札よりも参加条件に合わない不適格業者を排除しやすい。
・指名される企業が固定化する傾向がある。
・企業間の談合が比較的容易である。
3.随意契約
随意契約とは、行政機関が特定の企業を選定して契約を結ぶ方法です。
基本的に契約する企業と行政間でやり取りが行われるため、他の企業が入りづらいのが特徴でしょう。
【随意契約の特徴】
・特定の資産、信用、能力等のある企業を容易に選定できる。
・契約担当者の事務上の負担が少ない。
・契約される価格が不適切になる可能性がある。
参考:
[地方公共団体の入札・契約制度|総務省]
(http://www.soumu.go.jp/main_sosiki/jichi_gyousei/bunken/14569.html)
BtoGで新規案件を受注するためのポイント
行政が行う市場調査や庁内で利用する労務管理システム、職員の利用する机、市内のゴミ回収など、行政機関が外部に委託している業務は多岐にわたります。
公式ホームページや施設内の掲示物として業務ごとの取引方法が開示されているので、自社に関連した業務の取引方法は事前に調べておきましょう。
取引方法によって、新規案件を受注するためのポイントは異なります。
特定の企業に限って契約を行う随意契約を除いた、一般競争入札と指名競争入札におけるポイントを紹介しましょう。
1.一般競争入札:募集情報をいち早くキャッチする
一般競争入札は公に募集が行われている分、新規の企業でも比較的ハードルが低い方法です。狙っている行政機関の入札情報をいち早くキャッチして、申し込み忘れてしまわないようにしましょう。
機関によってはメルマガを配信したり、ホームページの更新情報をRSSで提供していたりといった情報提供を行っています。
電子入札と呼ばれる特定のシステムを利用して公募している行政機関もあるので、注意してください。
参考:
入札情報|経済産業省
[ちば電子調達システム支援情報|千葉県]
(https://www.pref.chiba.lg.jp/kenfudou/kensetsukouji/system/denshichoutatsu/)
2.指名競争入札:ネットでも情報を発信し、行政から選ばれるのを待つ
指名競争入札は基本的に行政機関から選ばれるのを待つ必要があります。
行政の窓口で直接働きかけるだけでなく、ホームページでも企業の情報や商品・サービス情報を発信し、担当者の目に止まるようにしましょう。
まとめ
BtoGの契約には大きく分けて3つ「一般競争入札」「指名競争入札」「随意契約」があります。業者の切り替えを行わず、そのまま延長する「随意契約」を結んでいる業務については新規の企業は入り込めません。
また、「指名競争入札」では、ホームページで情報発信を行ったり、行政機関の担当者に指名してもらえるよう働きかけることはできますが、指名がかかるかは行政の判断によります。
まずは公に広く開示され、募集条件を満たしている企業であれば参加できる「一般競争入札」に参加するのが取引の第一歩となるでしょう。
一般競争入札の情報は基本的に機関ごとの公式ホームページ上で公開されています。
事前にいつ頃公表されるのかを把握しておくだけでなく、RSSやメルマガを活用して、新規の募集は見逃さないようにしましょう。
一般競争入札では新規企業も過去に取引があった企業も、同じ土俵で争うこととなります。業務ごとの内容をよく確認して、適正な価格を提案しましょう。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoC
- BtoCとは、Business to Consumerの略で、企業と消費者間の取引のことを言います。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoC
- BtoCとは、Business to Consumerの略で、企業と消費者間の取引のことを言います。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoC
- BtoCとは、Business to Consumerの略で、企業と消費者間の取引のことを言います。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- RSS
- RSSとは、ブログやホームページが更新された際に、更新情報(コンテンツ)の要約を直接訪れることなく受け取れるソフトウェアを指します。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- RSS
- RSSとは、ブログやホームページが更新された際に、更新情報(コンテンツ)の要約を直接訪れることなく受け取れるソフトウェアを指します。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他