
ユーザーの声を聞こう!Facebookのアンケート機能を使いこなす方法
Facebookと言えば、世界的に使用されているSNSの1つです。もちろん日本のユーザー数も多く、2017年9月時点で日本におけるMAU(月間アクティブユーザー)数は約2,800万人と発表されています。
ビジネス活用する企業も多く、Facebookページの管理・運用に日々邁進されている方もいらっしゃるのではないでしょうか。そんなFacebookで、特にビジネスの場においてユーザーの声をより聞き取りやすくなる「アンケート機能」が利用可能になっています。

Twitter広告ならこの資料をチェック!
広告のプロが解説する『Twitter広告はじめてガイド』をダウンロード
今回は、Facebookで利用できるアンケート機能の使用方法についてご紹介します。
個人アカウントではもちろん、FacebookページやFacebookグループでも作成可能でビジネス活用しやすい仕様になっているので、ユーザーアンケート調査の手段の1つとして利用してみてはいかがでしょうか。
参照:
【最新版】2017年11月更新! 11のソーシャルメディア最新動向データまとめ|SNSマーケティングの情報ならソーシャルメディアラボ【Gaiax】
Facebookアンケート機能とは
Facebookグループで利用できるアンケート機能とは、指定したテーマに対して2択のアンケート投稿を行うことができる機能です。
2013年頃、アンケート機能と類似した「クエスチョン機能」が利用停止となっていましたが、2017年11月頃からより使いやすい機能として復活しました。なお、これまではアンケート機能の利用はFacebookグループ内でのみ可能でしたが、現在はFacebookグループ、Facebookページ・個人アカウントでも利用可能になっています。
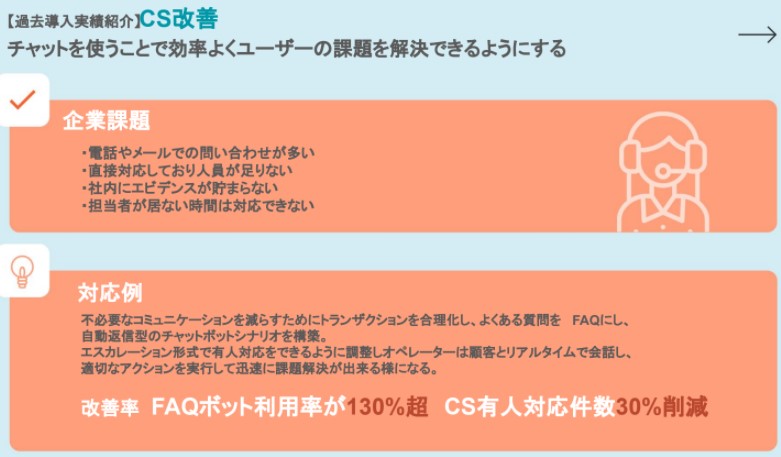
チャットボット運用で押さえておきたいポイントは?
業界別導入事例に学ぶ成功のポイントを資料でチェック
アンケート項目としてテキストはもちろん、写真画像やGIF画像も設定可能ですので、ビジネスシーンで活用するなら、新しい商品やサービスなどのデザインやネーミングについてのユーザーアンケート調査などが考えられます。
2013年頃に利用停止となった「クエスチョン機能」では、設定しだいでは投票社が回答の選択肢を追加することやFacebookページそのものを回答の選択肢として設定できるなど、回答者が行うことができる範囲が幅広く設定されていました。
特に回答の選択肢数が非常に多く設定できたため「決定回避の法則」の観点から見ても、ユーザーアンケート調査には不向きな場面も多々ありました。
現在のアンケート機能では設定できる回答の選択肢は2択と一見少なく感じますが、行動心理学の「決定回避の法則」に則ると妥当と言えます。「決定回避の法則」とは、多くの選択肢があるとかえって選択・決定が困難になるというものです。
2択だからこそ気軽に投票できるためより多くのユーザーの声を集められる可能性が高まるほか、アンケートで決まった結果を反映した商品やサービスはユーザーに愛されやすくなる、インサイトやA/Bテストなどを行うよりもより短期間で直接ユーザーの声を聞くことができるというメリットもあるためオススメです。
Facebookでアンケートを作成する方法
Step1.

アンケートを行いたいページやアカウント(Facebookページ / Facebookグループ / 個人アカウントのいずれか)を開きます。
FacebookページやFacebookグループの場合は、投稿画面下のメニューの中に「アンケートを作成」というアイコンが表示されていますので、クリックしてください。
Step2.

個人アカウントの場合は、投稿ボックス下の「……」をクリックします。
Step3.

するとそのまま下にメニューが表示されますので「アンケート」をクリックします。
Step4.

アンケート作成画面が表示されます。この画面は、Facebookページ / Facebookグループ / 個人アカウントのいずれも共通です。
まず「質問する」にアンケート内容を記入します。続いて「オプション1」「オプション2」に選択肢を記入してください。
選択肢として記入できる文字数は、かな字・英字問わず25文字までです。ここでは先にご紹介したように、写真画像またはGIF画像を選択肢として設定することも可能です。
写真画像を設定する場合は上画像のオレンジ枠アイコンを、GIF画像を設定する場合は上画像の青枠アイコンをクリックしてください。写真画像選択アイコンをクリックするとPC内に保存されている写真画像から、GIF画像アイコンをクリックするとFacebookが配布しているGIF画像から選択することができます。
次に「1週間」と記載されているボタンをクリックして集計期間の設定を行います。「カスタム」を選択すれば、自由に期間を設定することも可能です。
そのほか、通常の投稿のように場所を示す「チェックイン」や「友だちをタグ付け」などの機能も利用可能です。
アンケートを作成したら公開範囲を設定し「公開」ボタンをクリックして投稿完了です。なお、作成したアンケートに対して投票が行われた後はアンケート内容や集計期間などを編集することができませんので、公開前に今一度内容に相違ないか必ず確認してください。
Step5.

こちらはスマートフォンアプリ上でのアンケート作成画面です。基本的にPCでの画面を変わりありませんが、写真画像・GIF画像を選択するメニューアイコンが1つにまとめられています。
Step6.

上画像は、アンケート投稿後の画面です。アンケート作成者は投票があった直後から結果の閲覧が可能で、アンケート回答者は投票前は総得票数のみ、投票後は結果を閲覧することができます。
エンゲージメントの高いユーザーと考えられるためアンケートを実施しよう
企業のFacebookページやFacebookグループを定期的に閲覧するためには「いいね」をしておく必要があるため、比較的エンゲージメントの高いユーザーであると考えられます。
そのため、彼らに対してアンケート調査を行って得られた結果を反映した商品やサービスなどの展開は効果が出やすいとも考えられます。
これから新商品や新サービスの展開を検討している場合は、パッケージデザインやネーミングなど社内やチームで選りすぐった2つを提示し、最終判断をユーザーに委ねてみるのもいいでしょう。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- A/Bテスト
- ホームページを作るときや何か商品を売りたいときに掲載する写真、あるいはデザインで迷ったときに、不規則ででたらめな順番でホームページや画像のデザインを変えて表示し、利用者がどちらをより多くクリックしたのか、より多く購入につながったのか、ということを試験できる技術やサービスまたは行為自体をA/Bテストといいます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他










