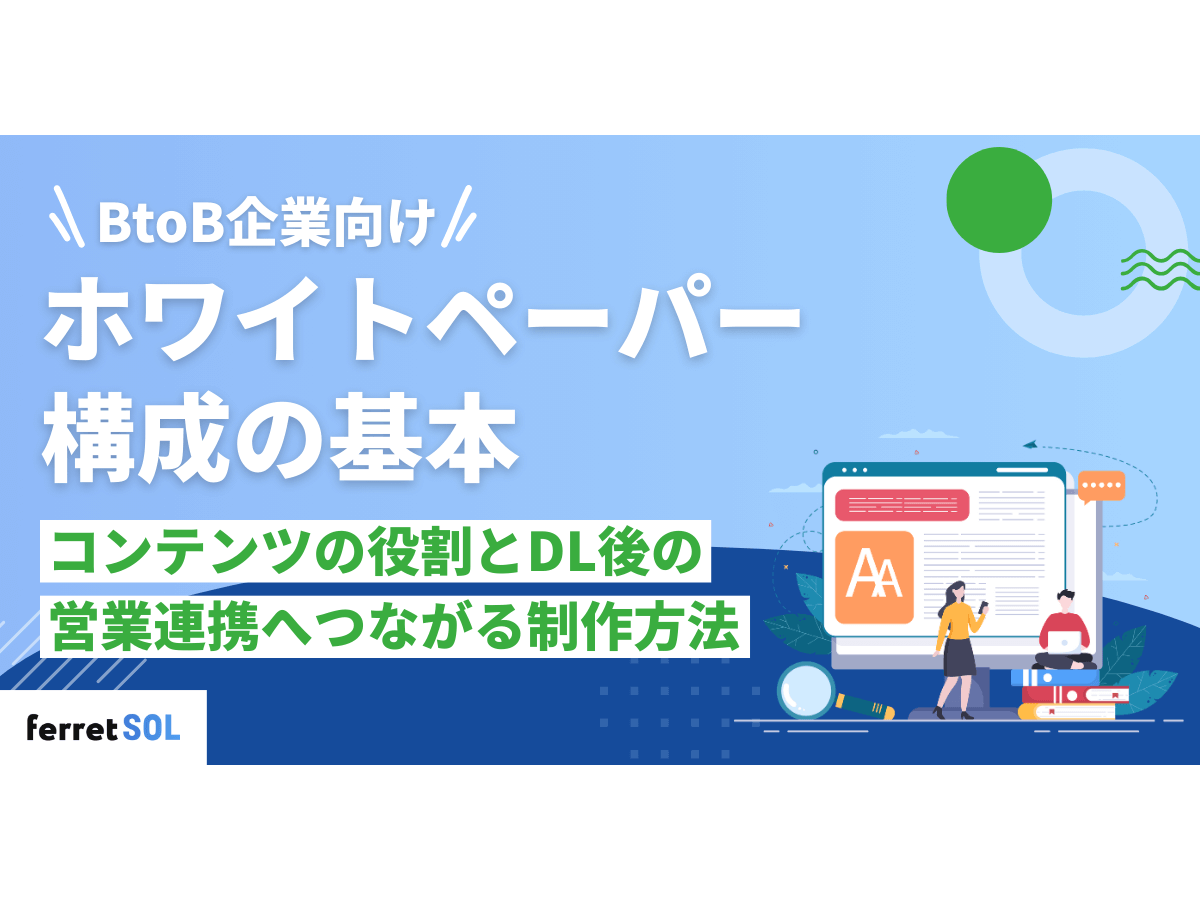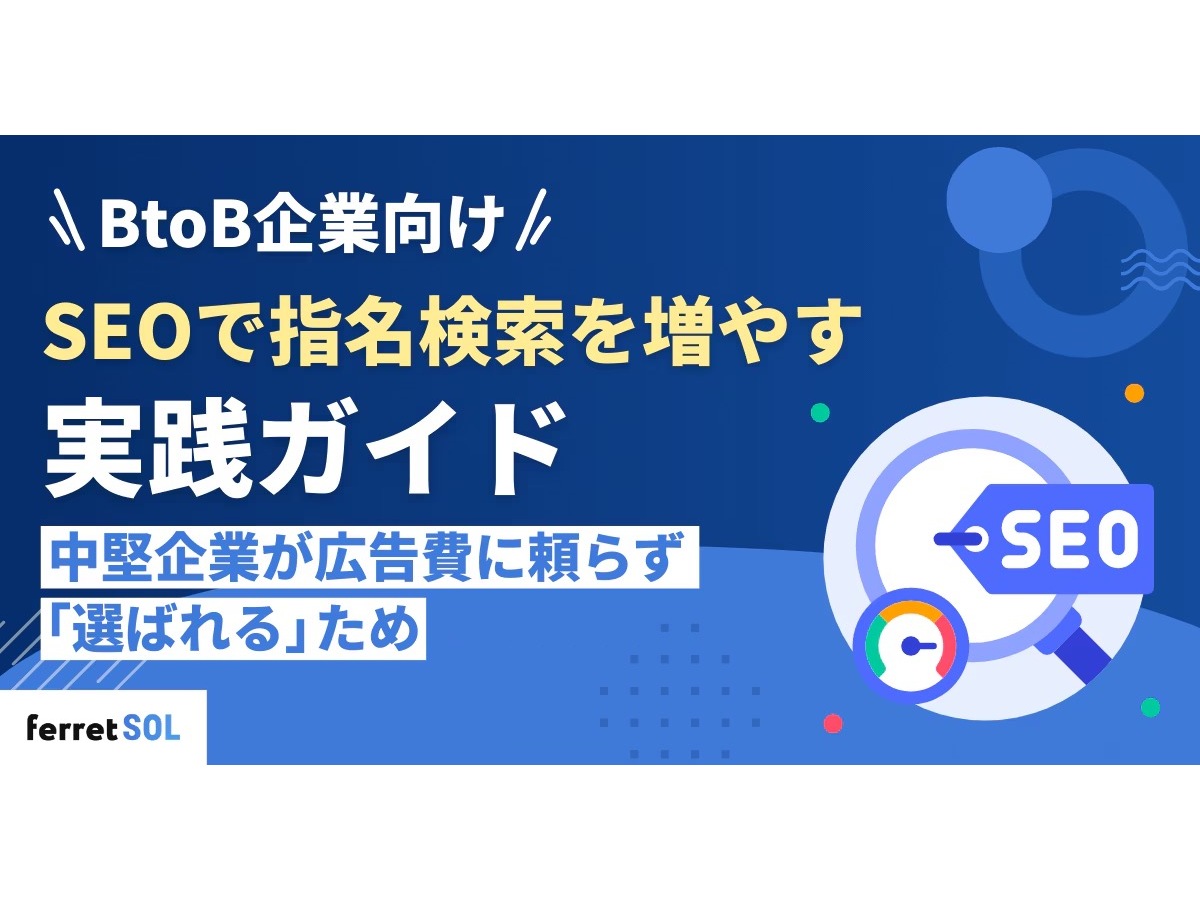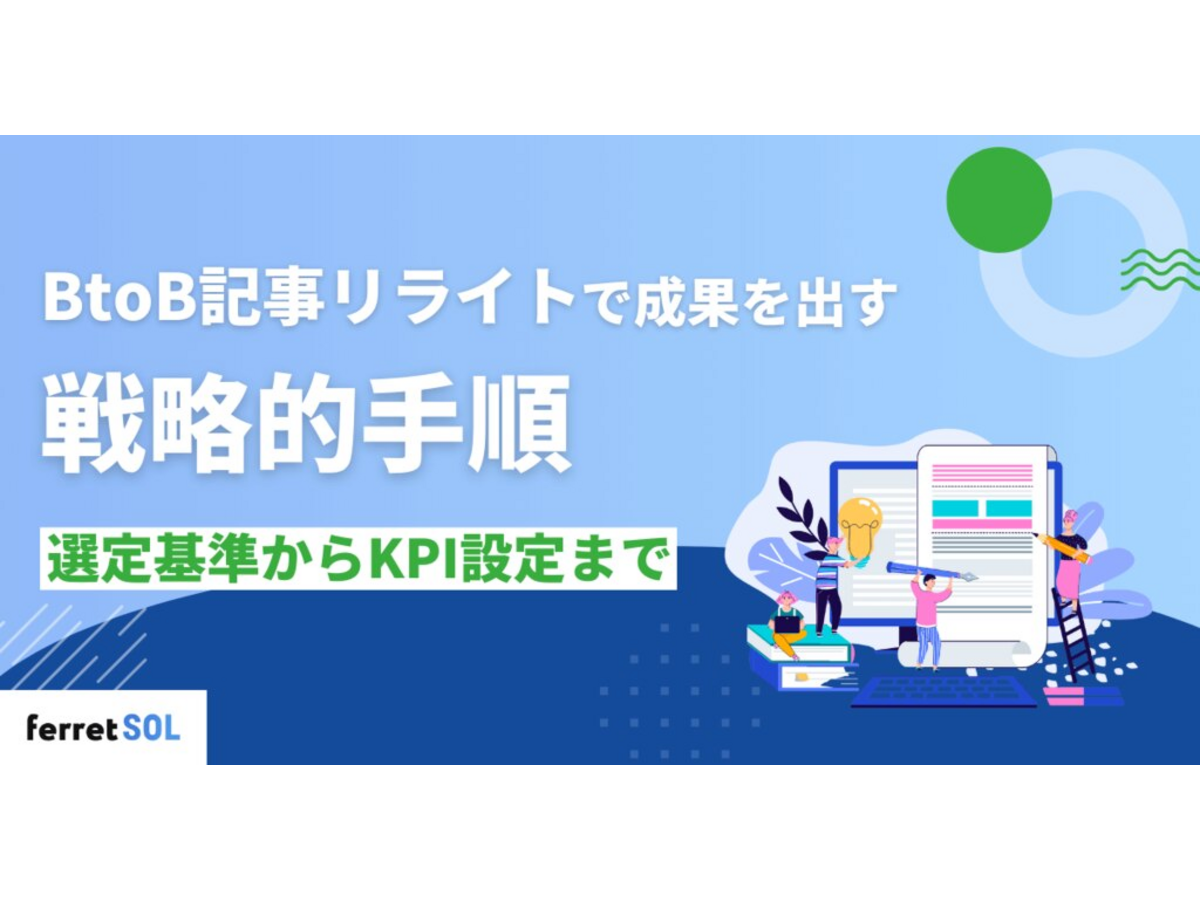ウェブライダー松尾氏が考える文章の「分かりやすさ」「コンテンツの質」とは
SEOライティングで有名な「沈黙のWebライティング」を執筆したウェブライダー社の松尾茂起氏。前編では文賢が目指す未来のコミュニケーションの形について聞きました。
今回は変化が許容された先にある「文章の分かりやすさ」とはどのように定義されるのかを伺いました。
▼前回の記事はこちら▼
ウェブライダー松尾氏が目指す「文賢」によるコミュニケーションの形
アートとデザインの視点から見る「分かりやすさ」
ferret:
前回のお話を受けて、この先「分かりやすさ」というのがどうなるのか気になります。

松尾氏:
結局、「分かりやすい」というのはアートとデザインの視点にすごく近いと思っています。アートは理解されることが目的ではなく、好きに感じてもらうことが大事です。しかしデザインは理解されることが目的であって、好きに見てもらうわけではない。「こう動いてもらいたい」という導線をつくることがデザインなんです。
例えば、Twitterはアートだと思っています。「理解してくれる人だけ来たらいい」という世界です。個を押し出して、「自分のフォロワー以外の人はわからなくてもいいよ」という。世の中の風潮としてもその傾向が強まっていて、私は完全にSNSの弊害だと考えています。
今はどんどん偏ってきています。アートだけの視点が強くなりすぎているのです。しかし、社会というのは集団行動が重要になってくるので、個を押し出した視点ではなく、全体を俯瞰できる視点が大切ではないでしょうか。
Webには中立的空間があまりなく、殺伐としています。それは多分、画面の外にいる人たちに会えていないからではないでしょうか。ネット弁慶になればなるほど、どんどん画面しか見なくなるので。人の表情や考えていることは、やはり目を見ないと分からない。理解しようとすること、されることが大切なのです。
ferret:
読み手にどう読んでもらうかを考えることが重要ですね。
分かりやすさに文字数は関係ない

松尾氏:
僕が「分かりやすさ」の議論でもうひとつおかしいなと感じているのが、文字数の議論です。
1,000文字のコンテンツと5,000文字のコンテンツがあった場合、読解スピードではなくて、理解スピードで考えたほうがいいからです。
例えば、1,000文字の文章で理解するのに10分かかるとします。私の経験ですが、同じ文章を5,000文字にしたことによって理解スピードが5分で終わるケースもあると思うのです。決して文字数の長さと理解スピードは比例しません。短ければ短いほど、それだけ理解するのが大変になることもあります。こういうことを考えてコンテンツをつくるべきであって、文字数に関する議論は不毛ですね。
重要なのは「理解できるか」です。「1,000文字のコンテンツでどこまで理解できるの?」と問われたときに、なかなかそこに説得力のある回答ができる人って少ないと思います。むしろ、文字数が少なくなればなるほど、理解は難しくなるのではないでしょうか。
例えば、もののけ姫の「生きろ。」というコピーがあります。
もののけ姫を観たことがある人であれば、この短いコピーの中にいろいろなことを考えることができます。短いコピーだからこそ、余白がたくさんあるんですね。
一方で読み手に優しい文章と考えた時に、文字数は短いほうがいいというのは、理解スピードに関する議論が置いてきぼりになっています。「短ければ短いほどいい」とか、反対に「長ければ長いほうがいい」とか、浅い議論です。重要なのは理解スピードなんです。
ferret:
なるほど。文字数以外に文章の理解スピードを上げる方法はあるのでしょうか?
松尾氏:
一つには「頭を使いながら読んでもらう」というのがあります。
そのためには色々なアプローチがあるんですが、例えば「問いを上手く与える」ということがあります。記事の中に疑問文を入れてしまうとかですね。
例えば弊社が作成したワインの記事では「何となくワイングラスを回しているんだけど、何の意味があるんだろうと思っていないですか?」と「何でだろう」と読み手に問う文章を作成しました。
「何でだろう」と考えると、脳に適度な負担が入るので、脳がウォーミングアップを始める。このようにちょっとした問いを入れて自分の頭を働かせないと、読み手は飽きたり、理解することをやめてしまいます。ある程度の苦労がないと絶対に記憶に残らないのです。

私が執筆した『沈黙のWebライティング』でも、あえて読者に考えさせる構成にしています。本の登場人物は読者の分身なので、一緒に考えます。だから、この本を読み終えた際、ある種の達成感があります。
でも、考えさせる場面が長すぎたり多すぎたりすると飽きるし、疲れます。飽きさせないための工夫が必要です。有名な歴史を紹介する番組でも、歴史の紹介だけをすればいいのに、あえてクイズを挟んで飽きさせないようにするし、視聴者に考えさせて「ああ、あれってそうだったんだ」と、記憶を定着させることに成功していますよね。
一人では考えることができない
ferret:
*ティーチングとコーチングみたいな感じですね。*授業だと一方的に知識だけ教えられるけど、問いがないので生徒側はアウトプットが上手くできない。問いを得られると自分なりに解釈し始めるじゃないですか。アウトプットのほうが実は身につきますよね。
松尾氏:
ティーチングとコーチングはすごくいい言葉ですね。僕がコンテンツを通して人に行動してもらおうとする際に「コーチを置く」という考え方があります。コーチはイコール24時間テレビの100キロマラソンの伴走者です。人って絶対に1人だと行動を完遂しない。飽きてしまうし、怠けてしまうんです。
怠けそうなときに「もうちょっと頑張ろうよ」みたいな人が必要なんですね。
これはコンテンツを読む場合も同じことが言えます。例えばワインの話になってくると難しい言葉が多く出てきます。カベルネ・ソーヴィニヨン、メルローとか、省略できないブドウの名前が出てくるときに、今まで平易な言葉が続いていたのにいきなり横文字が来ると「うわ、難しいな」とユーザーは思ってしまいます。
そうなったときに弊社がするアプローチはユーザーと同じように「うわ、難しいよね」と伴走をするということ。サポートする一文を入れるのです。これを入れずにただ単に情報を並べると、ユーザーは疲れてしまうんです。「コーチ、ちょっと待って。そこ分からないんだけど」「いいから私の話を聞きなさい」となっちゃうみたいな。
そうなると、ミスコミュニケーションが生まれてしまいます。
この場面で「サポートする一文を入れるべきかどうか」を考えられるか。文章を読むのは疲れるので、絶対どこかで緩急を意識してあげないといけません。良いコーチは、相手が理解しているかどうかを置き去りにして勝手に話を進めませんよね?
相手が本当に理解できたかどうかを確認するために、一緒に振り返りをしたり、より分かりやすく説明したりしてくれます。
コミュニケーションをとるために流行を知ることは必須
ferret:
松尾さんがコンテンツのプランニングをされるときって、どんな方々が自分たちのユーザーになり得るのかしっかり定義してから始める、というようなイメージですかね。

松尾氏:
そうです。ただ、うちはペルソナは絶対立てない。なぜかと言うと、検索集客になってくると一人ひとりを深堀した場合に当初立てたペルソナとずれてしまうからです。それこそ最大公約数的なところで決めています。ぼんやりとしたデモグラフィックと言うか、「女性が多いよね」とか「この女性って多分こういうもの好きそうだよね」とか、割と大きな枠でやります。
ただ、「全人類に共通している感覚は何だろう」というのは考えます。たとえばカラールールを決めるときは、皆が1番親しんでいるカラールールから入っていくので。
皆がよく親しんでいるカラールールの1つに信号機があります。赤色は警告色で、基本的には注意文とか警告文とか、ちょっとネガティブなイメージです。逆に、緑とか青は「進め」なので、肯定的な表現のときに使うと定義してやっていきます。
多くの人が日頃から目にするものは何だろうというのをかなり気にします。テレビも流行っている番組をよく見るようにしています。流行っているものには既視感があると思うので、「AAA(トリプル・エー)ってめっちゃ人気だよね」「安室ちゃんかわいいな」とか。そういうことは多くの人とのコミュニケーションを考える上で大切です。
ferret:
ペルソナを細かく設定すればするほど、ただでさえ少ない母数がより少なくなってしまいますし、アプローチの方法も限定されてしまいますよね。
文賢を使っている今の企業さんは、誤字脱字というよりは、コミュニケーションの方法をサポートしてほしいと思って使っているのですか?
松尾氏:
いろいろなお客さまがいますが、弊社が考えている文賢の未来についてはまだしっかりと周知できていないので、文賢が第2フェーズを迎える際に強く打ち出そうとしています。
今の推敲や校閲といった基本機能をベースにして、文賢ならではの視点で、世の中の人たちのコミュニケーション支援につながるような機能を追加していくつもりです。
例えば、文章表現機能の充実などはそのひとつです。
人間味を許容することで優しくなれる
ferret:
誤字脱字はない方がもちろんいいですが、誤字脱字があることによって人間味が出るというお話が前編でありましたよね。また、作業をする編集者にも限界があります。
松尾氏:
おっしゃる通りです。確かに誤字脱字はなくすことは良いことですが、あえて残すのも人間味があります。「誤字脱字はあるけど、それより伝えたい想いのほうが強かったんだろうな」と感じてもらえるならば、寬容になってもらえるかもしれない。
その視点が全くないと、怖くて何も書けないじゃないですか。相手にそれを期待する。だから自分もそうありたいと思う。
ferret:
松尾さんが監修されたワインのメディアも書き手を立たせていますよね。読者がその人とコミュニケーションを取るような仕組みになっている。やはりその方がコミュニケーションが取りやすいということなんですか。
松尾氏:
そうです。
ferret:
コミュニケーションという言葉と、先ほど話していた「分かりやすさ」という言葉を掛け合わせれば、あのワインのメディアは、まさにたくさんの人とコミュニケーションをとろうとしているように感じます。
松尾氏:
はい、まさにそうなんです。弊社が理想とするコンテンツは、たくさんの人が「これは読みやすい」「これは分かりやすい」と感じるコンテンツです。それはつまり、先ほど言われたように、たくさんの人と良好なコミュニケーションをとれるコンテンツでもあります。
10万人が来ていることを実感すべき

ferret:
今多くの企業がオウンドメディアを立ち上げていますが、うまく行っていないところもあるかと思います。松尾さんの経験から運営を円滑に進めるための方法などありますでしょうか。
松尾氏:
メディアをうまく成功させるポイントとしては、「なぜそのメディアをやるのか」ということを明確にすることです。「何となく」ページビューを稼いで、「何となく」来た人に対して広告を出して、「何となく」コンバージョンさせる。「何となく」が多ければ多いほど失敗しますね。その「何となく」をなくしておくことが重要です。
ただ、一番問題なのはメディアの運営者に、多くの人が見に来てくれているという「実感がないこと」ではないでしょうか。
私がメディア運営についてアドバイスする際によくすることのひとつに、大勢の観客が集まっているコンサートの写真をクライアントに見せることがあります。
その写真に10万人の観客が集まっているとします。10万人ってすごい人数ですよね。すると、主催者側の立場では、10万人の観客が何も買わず、帰ってしまうのもったいないとなる。では、この人たちにどうすればいいでしょうか。「会場でTシャツ販売します」とか「次のライブに来てもらうためにチラシを配る」とかという発想をもてば、オウンドメディアで発信する情報が自ずと変わっていきます。
またこの観客が帰っていったときに皆「今日のコンサートよかったよね」と口コミしてもらうためには、読後感がよくないといけません。

メディアを運営している人は多くの人が見に来ているという実感が分かっていない人が多い。Webの弱みは、ユーザーの顔が想像しにくいことです。一人ひとりの訪問がただの数字に見えてしまう。
10万人って、超人気アーティストのコンサートを毎日しているようなものです。
なので、例えば「その人たちが仮に1日1,000円払ったらいくらになるんだ」みたいな考えもできますよね。
ferret:
良い記事だったらまた読んでくれますし。コンサートに通うファンのように、熱烈な読者になってくれる可能性もありますね。
松尾氏:
僕は記事を曲や音楽によく例えるんですが、5分読んでもらうということは5分の曲を丸々聞いてもらうことと同じなのです。「では、曲ってどんなふうにつくられているかを考えると、最初にサビがあって、AメロBメロがあって、途中にゲストミュージシャンが来たとかで構成されます。イメージしにくいものをイメージしやすくすると、考えがクリアになって、成果物が全く違ってくることがあるんですね。
記事をなんのために書いて、どうしたいのかをしっかり考えられると読者と良いコミュニケーションがとれ、わかりやすい文章にも繋がっていくと思います。
まとめ
松尾氏に「分かりやすさ」「コンテンツの質」について伺いました。
コンテンツとはコミュニケーションであり、そのきっかけを文脈の余白といった仕掛けを通して混ぜていく。また文章を読み進めてもらうために、伴奏者のように応援したり、手助けしてくれる情報を入れておく。その情報を置くことを意識することで、わかりやすい文章になってゆく。
「分かりやすさ」は人それぞれのため、多くの人に「分かりやすい」コンテンツを伝えるのは簡単ではありません。しかし、松尾氏へのインタビューにあるとおり、人とのコミュニケーションを第一に考えることで、そのヒントを掴めるのではないでしょうか?
Photo by 青木勇太
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- 導線
- 導線とは、買い物客が店内を見てまわる道順のことです。ホームページにおいては、ページ内での利用者の動きを指します。 ホームページの制作にあたっては、人間行動科学や心理学の視点を取り入れ、顧客のページ内での動きを把握した上でサイト設計を行い、レイアウトや演出等を決めることが重要になります。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 口コミ
- 「口頭でのコミュニケーション」の略で、消費者の間で製品やサービスの評価が伝達されることです。 一方で、不特定多数の人々に情報が伝達されることをマスコミと使われます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他