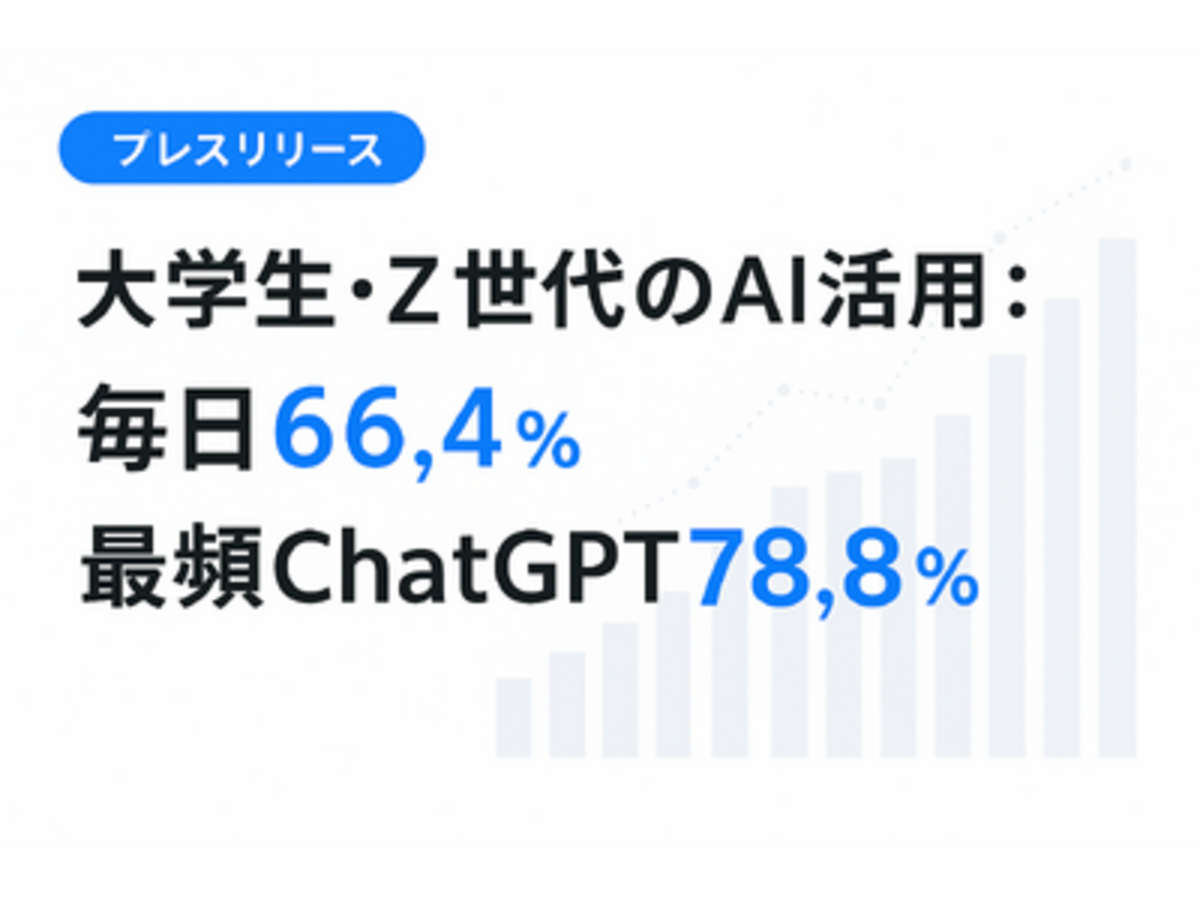ラグビー日本代表が史上初の8強入りに。2015年のブームから注力したマーケ施策とは?
2015年、イングランドで行われたラグビーワールドカップ。日本代表は強豪・南アフリカを下し、日本中に空前のラグビーブームが押し寄せました。そして2019年9月20日にはアジア初開催となる「ラグビーワールドカップ2019日本大会」が開幕します。2015年の盛り上がりから4年、ファンや競技人口は増えているのでしょうか? ラグビー界のマーケティング施策はどのように行われているのか伺いました。
プロフィール
公益財団法人 日本ラグビーフットボール協会(JRFU)
マーケティング部長 竹内 哲也氏
1970年大分県生まれ。大分県立大分舞鶴高校-立命館大学産業社会学部を経て、1994年(株)電通入社。関西支社新聞局からテレビ局、東京本社営業局、スポーツ局を経て、2015年7月より公益財団法人日本ラグビーフットボール協会マーケティング部長に就任。
父親の影響で小学校から大分ラグビースクールで楕円球を追い始め、大分舞鶴高校時には全国大会出場、立命館大学体育会ラグビー部の在籍中には一年休学し、オーストラリア・シドニーのRANDWICK CLUBに所属。卒業後は勤務先(株)電通のラグビー部や神奈川不惑クラブに所属し、現在は世田谷区ラグビースクールのコーチを務める。
3つのマーケティング施策で収益を拡大
ferret:竹内さんはずっとラグビーをやられてきたんですか?
竹内氏:はい。小学校からラグビーをしていて、現在は世田谷区のラグビースクールのコーチも務めています。
ferret:日本ラグビーフットボール協会にはいつからいらっしゃるんですか?
竹内氏:2015年の7月からです。(株)電通からの出向で日本ラグビーフットボール協会のマーケティング部の部長を務めています。
ferret:ラグビーワールドカップ2015では、日本が南アフリカに勝利し、日本中にラグビーブームが起こりましたが、その後、ラグビーを普及させるためにどんな施策を行いましたか?
竹内氏:私が所属しているマーケティング部は、コマーシャル(スポンサー)収入の最大化をミッションに、放送権の拡大やマーチャンダイジング施策の展開が主な業務です。 2015年以降の施策でいうと、日本代表のブランディング、視聴機会の創出と拡大、ライトファンへのアプローチの3つを積極的に行いました。
日本代表の代名詞「桜のエンブレム/ロゴ」のブランディング
ferret:日本代表のブランディングについては何をされましたか?
竹内氏:*ラグビーワールドカップ2015の後、最初に着手したのが、日本代表のジャージにも使用されている桜のエンブレム/ロゴのブランディングです。*2003年にオーストラリアで開催された第5回ラグビーワールドカップ初戦で、日本代表はスコットランド代表と対戦しました。それまで弱小チームとして世界から認識されていた日本代表は、スコットランド代表に低く突き刺さる攻撃的なタックルを徹底しました。*試合は負けてしまいましたが、その勇敢な戦いぶりを現地の新聞が賞賛し、「BRAVE BLOSSOMS(ブレイブブロッサムズ):勇敢な桜たち」という呼称で掲載したんです。そこから海外メディアが日本代表を記事化するときに敬意を込め「BRAVE BLOSSOMS」を使い始めました。*このありがたい愛称を、ブランディング観点で活用できるのでは、と提案し、まずは「BRAVE BLOSSOMS」の商標をとったんです。
その様な中で、2016年秋のアルゼンチン戦から「BRAVE」を全面的にコミュニケーションのキーワードで活用していこうとなり、2017年のルーマニア戦、アイルランド戦を経て、2017年秋のオーストラリア戦から、「WE ARE BRAVE BLOSSOMS」と称するようにしました。そこからマーチャンダイジングでも積極的に派生させ、様々なグッズで展開しています。また日本代表に特化したプラットフォームとして、「WE ARE BRAVE BLOSSOMS」という特設サイトを開設し、試合の結果や選手の紹介、会場情報、動画などを観られるようにしました。但し他のNF(競技団体)の代表チームと比較すると認知度はまだまだなのですが、「BRAVE BLOSSOMS」の由来を知って頂くと、好印象度が大きく増加するデータも御座いますので、今後のブランディングにおけるキーファクターになってくると思ってます。

視聴機会と放送収入の拡大に向けて
ferret:視聴機会の創出と拡大についてはどのような施策がなされたのでしょうか?
竹内氏:視聴機会については、日本協会の主催試合を(男女、15人制、7人制を問わず)いずれかのデバイスを利用すれば、ライブ視聴できる環境整備に重点を置いています。*その中でも、従来の地上波放送と昨今主流になってきたデジタル配信の施策を両輪として推進してきました。*
地上波は、先ずは最もコンテンツ力のある日本代表戦が、ラグビーワールドカップ2015のサモア戦で高視聴率が取れた(19.3%・関東地区)ことにより、翌年の「リポビタンDチャレンジカップ2016 日本代表 対 スコットランド戦」を、日本テレビが全国ネットのゴールデンタイムで放送枠を確保してくれました。それまで日本代表戦がGP帯(ゴールデン/プライム)の全国ネットで生中継されたことはありませんでしたので、日本ラグビーの歴史にとって画期的だったと思います。但し残念ながら視聴率がふるわず、その後ゴールデンタイムでの放送は、今回のラグビーワールドカップ2019の壮行試合となった9/6(金)の南アフリカ戦までありませんでした。
今後もラグビーワールドカップ2019でのホスト局である日本テレビを起点に、NHKや衛星放送のJ SPORTSを含め、日本代表戦を中心にサンウルブズやトップリーグ等も継続的に視聴してもらえるよう、各放送局との関係構築にも力を入れていきます。
一方で*デジタル配信に関しては、2016年からジャパンラグビートップリーグ(社会人ラグビーの全国リーグ)での中継をDAZN(ダゾーン)と締結。ホストブロードキャスターであるJ SPORTSと連携し、トップリーグ全試合をライブ/オンデマンド配信にて視聴可能にしました。*また、例年年末年始に行われる冬の高校スポーツの風物詩「全国高校ラグビー大会(通称:花園大会)」を、ホスト局である毎日放送との協業にて大会全50試合を無料配信できるプラットフォーム「花園ライブ」をつくりました。
*現在の国内ラグビーの競技者数で最大のボリュームゾーンは高校生です。*ラグビーで高みを目指す人にとって、高校の全国大会、特に全国高等学校ラグビーフットボール大会は、重要な通過点でもあり、同時に大きな目標設定にもなります。普及育成カテゴリー(小中高)の最高峰となるこの大会を、野球の全国高等学校野球選手権大会と同じように、如何にブランディングし価値のあるものにするかに重点を置いています。
2001年までは全国高等学校ラグビーフットボール大会は、東京キー局のTBS含めた全国の系列ネットワーク局を中心に全国ネット放送でした。1回戦から3回戦まではハイライトを含めて深夜に放送し、準々決勝以降は生放送で編成。ところが時代の流れと共に番組スポンサーが変わると、放送枠が減り、今では決勝戦しか全国ネットで放送されておりません。地方大会の予選決勝は、系列の各地方局が中継をして頂いているものの、放送が無いエリアもあったり、全国大会のハイライトもエリアによってバラつきある歯抜け状態で、高校ラグビーの放送環境は極めて危うい状態だったんです。
そして高校ラグビーの課題のひとつがエリア格差です。部員数が100人超える都市部の強豪校に集中する一方、部員数確保に走る地方の学校は沢山あります。このエリア格差の是正なくして、高校ラグビーの発展はない。その為にも個々のライフスタイルやメディア環境の変化に則した視聴スタイルの創出が重要で、誰でも手軽に視聴出来る環境をつくることによって、決してラグビーが盛んでないエリアでも関係者が応援してもらえるよう環境を整えてきました。
ただこれは完成形でなく、各地方大会の予選決勝や各種全国大会など、あらゆる高校ラグビー情報を包含し発信出来るプラットフォームを目指して協議中です。
ferret:近い将来、高校生の大会を網羅したプラットフォームになるのですね。
竹内氏:そうですね。但しネット配信の環境を整える一方で、地上波での放送枠の維持拡大には拘っています。ご存知の通り、都心部と地方とではメディアの接し方が違います。都心部はSNSを含めたネットに対するリテラシーが高い人が多いのですが、地方はいわゆるオールドメディアの地上波や新聞を軸に情報流通しますので、ローカルメディアを上手く活用し、そのエリアの放送が絶えないように高体連や地方局との連携は必要です。先ほども言ったように高校生の大会はあくまでも通過点なので、この世代を充実させないと、日本ラグビー全体の底上げに繋がらないので最善を尽くしています。
ライトファンを楽しませるマーチャンダイジングとユニークな動画
ferret:ライトファンへのアプローチはどんな施策をされたのですか?
竹内氏:ラグビーワールドカップ2015を機に、ライトファンがたくさん増えました。ありがたいことですが、ライトファンはブームが去れば潮が引くように去っていく。*但し、新規流入のファンの方々には、従来のファンよりも熱心で、向学欲旺盛な方がいることもわかった。そんな皆さんが、リピーターとして周囲に拡散して貰えるための施策を行いました。その1つが、マーチャンダイジング(商品計画)の拡充です。*
マーチャンダイジングのテコ入れは2016年からです。大変ありがたいことに、キャラクタービジネスとしてのコラボレーションや、多方面からの売り込みが多々あった中で、日本代表のマーチャンダイズを取り扱う事務局を立ち上げようという結論になり、オフィシャルライセンス兼オフィシャルストアを展開してみてはどうかとなりました。そこで電通とソニー・クリエイティブプロダクツと契約し、オフィシャルライセンス事務局を立ち上げました。結果として年々アイテム数が増え、ラグビーワールドカップ2019イヤーの今年は、スポンサーと一緒につくったドリンクや時計、ライセンス事務局だと、日本酒やパン、ガリガリ君、歌舞伎など、様々なコラボ商品を展開し現段階でも増え続けています。

またマーチャンダイジングを拡大していく上で行なったのが、ピーナッツやキン肉マンなどのキャラクターとのコラボレーションです。人気キャラクターとのコラボは、先ずはキャラクターの特性と役割をしっかりと見極めた上での実施ですが、わかり易いライトファンには喜んでもらえていると思います。2019年の7月、8月からは、オフィシャルストアを、西武池袋本店や柏髙島屋ステーションモールに出店しています。直近では羽田空港の第一旅客ターミナルに専門ショップがオープンしました。なかなか目立つので見栄えがいいですね。
あと、ライトファンの皆さんが必ず言うのは、ラグビーはルールが分からないということ。そこで制作したのが、わかり易くルールを覚えて貰うための観戦動画です。
ライトファンに対しては彼らの目線に合わせ、とにかく分かりやすく、興味を抱いてもらうことが重要なので、きもかわいいキシボーイというキャラクターを使用して、ルール解説を何パターンもつくりました。観戦マナー編も含めて6タイプつくっているんですよ。2019年の7月には、『ラグビーのルール 超・初級編』という書籍も出ています。
さらに「トップリーグの逆襲」という動画をつくりました。2015年のシーズンは、ラグビーワールドカップ2015後のブームを受けて、トップリーグを中心にお客さまが増えました。2014年の集客数が約39.6万人だったのに対し2015年は約49.2万人で、約10万人増ですね。但し、その翌年の2016年シーズンは、これは一概には言えませんが施策のアプローチが甘かった影響もあったのでしょう、トップリーグのお客さまは少し減って約46万人になったんです。
これを挽回するために、ラグビーは何となく知ってはいるものの、そもそもラグビーに対して距離があると思っているライトファンにもう一度、丁寧にアプローチをしなければならない。そうなったとき、ラグビーっていかついし、でかくて黒くてごつい超人がやっていて、とにかく何か怖くて近寄りがたい(笑)。彼等にとっては極めて非日常で、まったく他人事で関係ない存在。そんな印象を受ける方が多いと思います。
けど、実はラグビーやってる人は、体は大きいけど、サービス精神旺盛で、話してみると人懐っこくて親しみやすい。自虐的な要素もあり、宴会芸にも長けているような人が多いんですよ。*そんなラグビー選手のギャップを活かしコミカルな要素を前面に出し、ターゲットに対して寄り添うように描くことによって、もう一度ラグビー(トップリーグ)への興味喚起を促し、話題を醸成、観戦意向アップを目指したコミュニケーション施策として、SNSを中心に展開する動画です。*会場やYouTubeなどで流したりしていて大変好評です。
インタビュー後編を読む

インタビュー後編:開幕迫るラグビーW杯。2015年のブームを受けて行なったマーケ施策とは?
前編では、日本ラグビーフットボール協会が「ラグビーワールドカップ2015」のあとに行なった、日本代表のブランディングと視聴機会の創出、ライトファンへのアプローチの3つの施策について紹介しました。後編では、マーケティング施策を行なってからの効果や今後の課題についてお聞きしました。
スポーツに関する記事を読む

インタビュー前編:KPIは会場をお客様で埋め尽くすこと。新日本プロレスのSNS運用が目指すもの
私ごとで恐縮だが、1年ほど前に体調を崩して自宅療養をしていたとき、YouTubeで新日本プロレスの公式チャネルで動画を見る機会があった。7分ほどの動画であっただろうか。その短い動画を見て、私は完全にプロレスの虜になってしまった。繰り出される美しい技、レスラー一人ひとりの個性など、その魅力は語りつくせないほどだ。プロレスに完全に魅せられた私は、こう思うようになった。「なんとかプロレスと仕事を結びつけたい……。」「なんとかferret読者にプロレスの魅力を伝えたい……。」本インタビューはそんな想いから実現した企画である。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- リピーター
- リピーターとは、商品やサービスに愛着を持ち、繰り返し利用してくれるお客様のことです。 リピーターを獲得することは、ホームページを使って売上を上げるためにも重要な指標の一つと言えます。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他