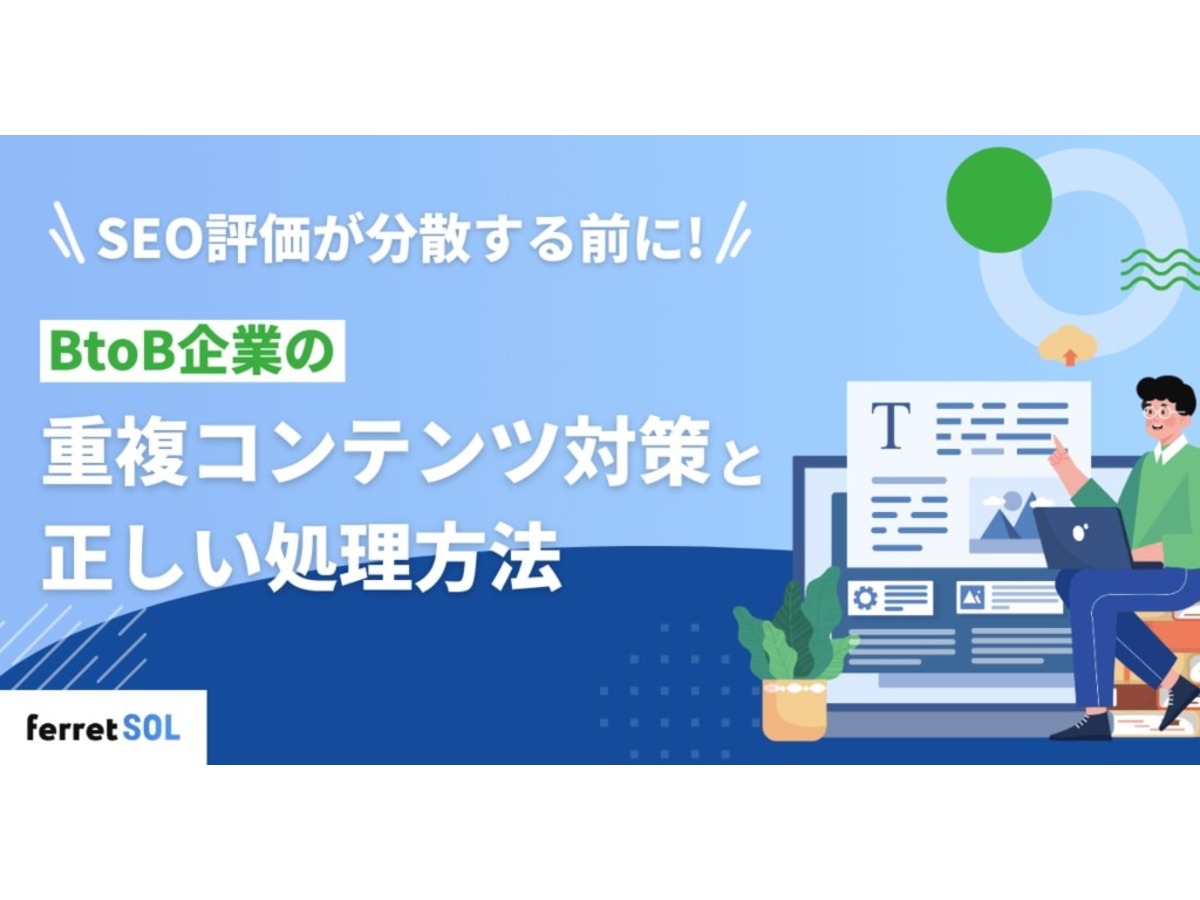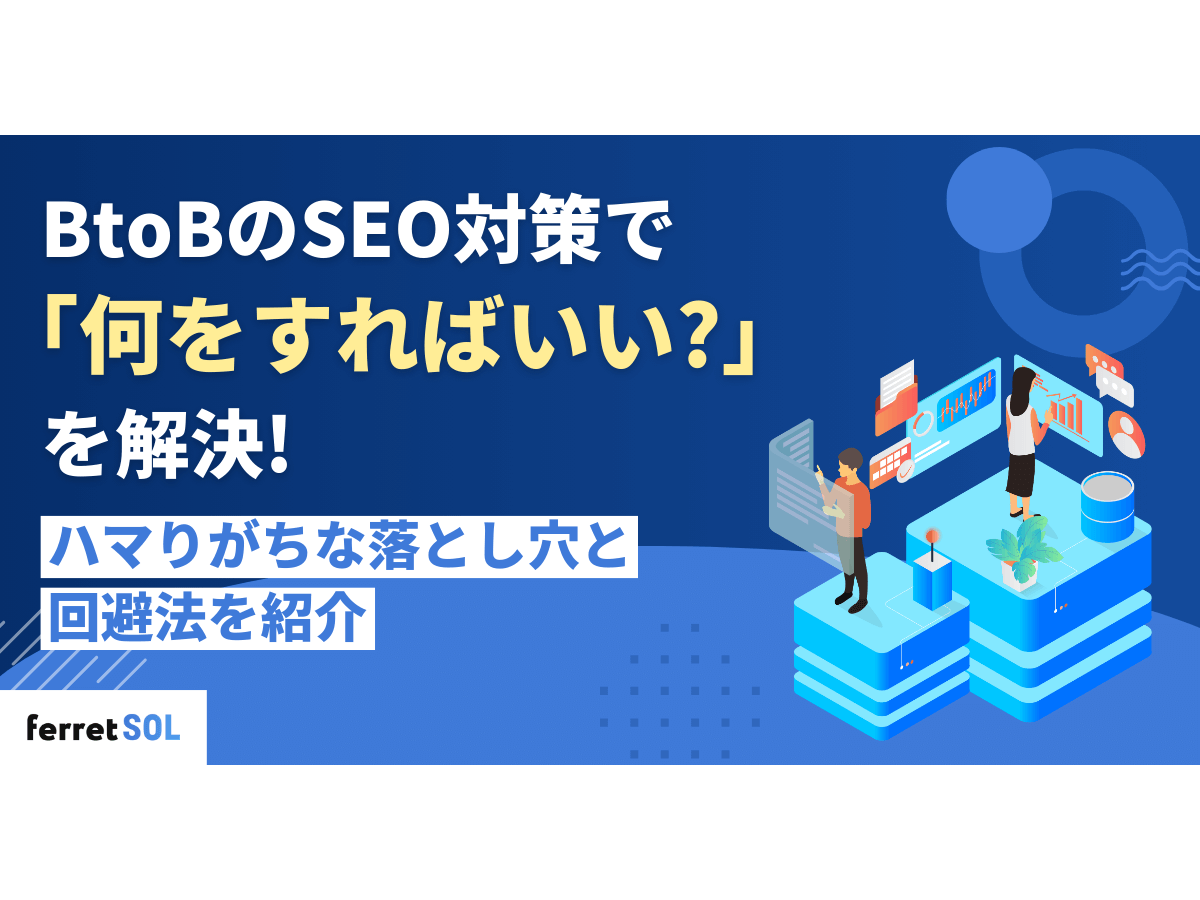アクセス増のために記事だけを増やし続けるのは大きな間違い
ferret編集部:2014年12月18日に公開された記事を再編集しています。
アクセスアップのために*ページ追加(コンテンツ追加)*をしている人は多いのではないでしょうか。現実的に、それでは十分ではないのです。実は3ページ追加して1ページが見られるくらいが現実的というデータがあり、編集部のまわりでも話題になっています。
本記事では、アクセス増のために理解しておくべき集客の構造と、その対策について解説します。
集客のために記事を書こう!は幻想
よくホームページやブログを運営していますと、「更新しろ!」「更新しないと検索にヒットしない」と言われることはありませんか?もしくはお客様やスタッフに強いていませんか?強いられていませんか?
もちろん更新するにこしたことはありませんが、残念ながらそれだけでは劇的なアクセス増にはなりません。
以下の表をご覧ください。記事本数が約1619本あるブログのGoogleアナリティクス画面です。アクセスされたページをデイリーで見ると、その閲覧されたページ種類数は455ページです。
<Googleアナリティクスでの操作>
行動>サイトコンテンツ>すべてのページ
総記事数1619ページに対し455ページがその日閲覧されています。つまり、**サイト全体のページ閲覧率は28.1%**となります。
455 ÷ 1619 x 100 ≒ 28.1%

この28.1%という数字はそれでも良いほうです。ブログによっては閲覧率10%台のところも少なくありません。また逆に多くても、編集部の知る範囲では34%でした。
つまり、いくらページ数を増やしても、すべてが見られるわけでないのです。その積み上げに比例はするかもしれませんが、3分の1、つまり3本のうち2本は見られないというのが現実なのです。
コンテンツ・マーケティングを実践する方々は、この数字は知っておいて損はないかと思います。
私たちはすべてのページを見るわけではない
ホームページの8割は見られない。これは私たちの生活行動に照らしあわせても、納得がいきます。

たとえば、あるショッピングモールに買い物に行きます。それでもすべてのお店をみるわけではありません。また、ある素敵なデザインのホームページを見つけます。それでも全ページを見るわけではありません。
これが現実であり、頭ごなしに「更新しろ!」と言う人が、忘れてしまっている大切なことといえます。
ただ、リアル店舗で、見ないにしろ、その規模からくる信頼感で来店する、というのはあるかもしれません。ホームページでも、定期更新しているからこそGoogleの評価が上がり(適切にSEO対策をしていれば)検索エンジンにヒットする、というのはあるかもしれません。ただ、「コンテンツ追加を過大評価するのは危険」ということです。
全てがロングテールに当てはまるわけではない。
ちまたではロングテールと言われているだろう、と思われる方もいるでしょう。いわゆるニーズの少ないページも、わずかながら読まれている(買われている)はずだ、と。

ロングテールとは、アクセスの多くは2割のページが売り上げの8割を占めている、しかし、残りの8割も総数で見ると多い、という集客の考え方です。残りの8割はたいていは少しのニーズしかないものを取り上げた記事や商品をさします。
しかしそれは検索からのアクセスが前提なのです。
<Googleアナリティクスでの操作>
集客>チャネル・・・表の右上「円グラフ」マークをクリック
あまり更新していないようなホームページだと、以下のように検索からのアクセス(Organic Search)が多いと思います。

ほら、やっぱりそうだろ!と思われるかもしれません、しかしこれは割合の話であって、実際の閲覧ページの種類は、やはり前述のように多くても3割なのです。自然検索流入が、すべてのページに届いているわけではないのです。
インデックス数は単なる登録にすぎない
Googleで調べるともっと多くのページが、うちはインデックスされている、と言われる方も多いと思います。

Googleで「site:ドメイン名」と検索すると、登録数がわかります。検索エンジンの検索対象となるページ数の目安といえます。ページ数よりも通常は多いはずです(カテゴリーページや自動で生成されます検索結果ページやタグページなど)。
実際、前述の28.1%のホームページでデイリーである日を見てみると、ウェブマスターツール(Google Search Console)での平均掲載順位は11位、ウェブマスターツール(Google Search Console)上での表示ページは1041件です。全記事に対して64.2%、やはり全部のページが活躍してくれるわけではなさそうです。
<Googleアナリティクスでの操作>
集客>検索エンジン最適化>検索クエリ
表示されたとしても、そこでクリックされるかどうかは未知数です。そもそも検索で見つけてもらえるほどの内容なのかということもあるでしょう。すべてのページに過度な期待はしないほうが良いでしょう。
ページあたりの集客数という指標
ですから、1ページあたり何人連れてきてくれるのか、という指標を運営に役立てている動きもあります。
たとえば前述のホームページであれば、デイリーでユーザー数1024という数字だそうです(厳密にはGoogleアナリティクスのユーザー数はCookie数ですがここではわかりやすさを重視してユーザー数と表記しています)。

<Googleアナリティクスでの操作>
ユーザー>サマリー
1024ユーザー ÷ 1619ページ ≒ 0.63
こうしてみると、人気ページの貢献度も加味されますので、指標としても使えそうです。Googleアナリティクスはアクセスされないページは記録されないのです。ですから、常にページリストを照らし合わせながら確認することになりますが、把握しておきますと、コンテンツの費用対効果の目安になるかもしれません。
いずれにせよ、追加したページ(コンテンツ)の効果は、つねにチェックしておくことが必要でしょう。
コンテンツを有効活用するために
では、その精度を上げる方法はないのでしょうか。せっかく追加したページ(コンテンツ)をいかせないのは勿体ありません。
それには、こちらの事例が参考になります。以下の図は、総ページ数が515ページあるホームページですが、アクセスされているページの種類数がなんと500ページに近い状態です。

1ページあたりの集客数としてみますと 25.6という脅威の集客力を誇っています。
これは一体どういうことなのでしょうか。Googleアナリティクスで、集客の内訳を見てみましょう。
<Googleアナリティクスでの操作>
集客>チャネル

ソーシャルやメールなど、バランスよく集客しています。つまり、検索で届かないユーザーには、Twitterやfacebookなどのソーシャルやメルマガなどで告知をし、接点を増やす工夫をしているということなのです。
アクセス増のためにできること
以上のことから、ホームページへのアクセスを増やすためには、以下のような流入すべてに配慮することが重要といえます。

これからコンテンツ・マーケティング=ページの大量追加が盛んになってくると、競合もどんどんページを追加し、相対的に自社ページが検索で順位をさげて、さらに誘導力が下がってくる可能性は高いと言えるでしょう。少なくとも好転するとは言いづらいでしょう。
ソーシャル、メルマガ、リンクを増やす(被リンク)、広告、URLを直接入力してもらう・ブックマークをしてもらうなどのブランディング(具体的にはメディアなどの露出して名前を覚えてもらうなど)といった集客の基本を徹底することが重要と言えます。
検索にヒットしないけれどニーズがありそうなページはTwitterで宣伝する、検索にはヒットしないけれどこのチームが優勝した今この瞬間は売れる!という商品ページだけは広告を配信する、などです。
それぞれコストや手間がかかることですが、これらを粘り強く対策していくことは、検索エンジンのアルゴリズムが変わったときにリスクマネジメントにもなり(検索エンジンからの流入が減ってもメルマガやソーシャルで集客が可能など)、資産となります。
参考リンク:SEOを行う上で覚えておきたいGoogleの主なアルゴリズムまとめ
それでも更新を止めてはいけない理由
アクセスにそれほど影響していない!としても、更新は大切です。
Webマーケティングのブログで有名なLIGでは、毎月アクセス解析の結果を公開しています。そこで11月は祝日が多かったながらも1日3本記事を追加していながらも、PVを減らしたことを吐露しています。※11月は10月に比べ祝日も多く平日が少なかったことを言及しています。
10月度に過去最高をマークした340万PVと比較して、月次PVは減少し、約320万PVになりました。
参考リンク:LIGブログの11月度アクセス解析と広告収入の結果 | 株式会社LIG

しかし、セッション(訪問数)は向上しており、どちらかというと更新はGoogleに「更新してるサイトだよ」とシグナルを送ることで、SEOにより有利に影響させるための必要条件とも言えそうです。
大切なのはその更新の精度をしっかり把握して、試行錯誤しながら更新する、ということなのではないでしょうか。
まとめ
・ページは更新しても3分の1しか見られない。
・ページ追加の効果はGoogleアナリティクスでわかる。
・検索エンジン頼みではない導線の構築を粘り強く行う。
ホームページのアクセスアップで、ページの追加や更新が重要なことは間違いありません。しかし、その効果を決して過大評価してはいけないでしょう。ページを更新しているといってユーザーの求める内容があるわけではないからです。
大切なことはユーザーのニーズにあった内容があること、そしてそれを検索エンジンだけに頼らず、ソーシャルやメルマガなどあらゆる手段で届ける工夫をすること。これらすべてにバランスよく気配りできるウェブマスターが求められています。
ぜひみなさんもまず、全体におけるページ閲覧率、ページあたりの集客数を算出してみてください。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- インデックス
- インデックスとは、目次あるいは目次として登録されている状態のことをいいます。また、ホームページのトップページや、製品ページの最上層ページなど、ほかのページへアクセスするための起点となるページを指すこともあります。会話や文脈によって意味が異なるので、注意が必要です。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- ドメイン
- ドメインとは、インターネット上で利用可能なホームページやメールなどを識別するときの絶対唯一の綴りを言います。電話番号や自動車ナンバーが同一のものがないのと同様に、インタネットにおいても、2つとして同じドメインは存在できない、といった唯一無二の綴りです。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- 検索結果
- 検索結果とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで検索したときに表示される情報のことです。「Search Engine Result Page」の頭文字から「SERP」と呼ばれることもあります。 検索結果には、検索エンジンの機能に関する情報と、検索キーワードに関連する情報を持つページが表示されます。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ウェブマスター
- WEBマスターとは、ホームページの管理者のことを指します。ホームページの規模に関わらず、ホームページの運営者であればWEBマスターと呼ばれます。 個人のホームページでは運営者自身がWEBマスターであり、企業による大規模なホームページでは統括する人がWEBマスターとして業務にあたります。
- Google Search Console
- Google Search Consoleとは、Googleが無料で提供しているツールの1つで、ホームページを運営する上で重要な情報を把握できます。 自分が作成したホームページの集客・管理を効果的に行うために利用するもので、訪問者の属性や検索キーワードなどを詳しく調べることができます。
- ウェブマスター
- WEBマスターとは、ホームページの管理者のことを指します。ホームページの規模に関わらず、ホームページの運営者であればWEBマスターと呼ばれます。 個人のホームページでは運営者自身がWEBマスターであり、企業による大規模なホームページでは統括する人がWEBマスターとして業務にあたります。
- Google Search Console
- Google Search Consoleとは、Googleが無料で提供しているツールの1つで、ホームページを運営する上で重要な情報を把握できます。 自分が作成したホームページの集客・管理を効果的に行うために利用するもので、訪問者の属性や検索キーワードなどを詳しく調べることができます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- URL
- URLとは、「Uniform Resource Locator」の略称です。情報がどこにあるのかを示すインターネット上の住所のようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。各ページのURLは、インターネットブラウザの上部に文字列として表示されています。日本語では「統一資源位置指定子」という名称がついていますが、実際には日本でもURLという語が使われています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- セッション
- Googleアナリティクスは、ホームページに適切に組み込めばアクセス状況を把握できる便利なサービスです。Googleが無料で提供しており、日本でも大手企業や金融機関、政府など、その利用のシェアを広げています。そこで、もっとも基本的な単位がセッションです。
- 訪問数
- 訪問数とは、 「訪問数」とは、ある利用者が特定のホームページでページを開く、サイト内で閲覧するなどの活動をした回数のことです。1回の訪問で、ホームページ内のページを何度開いても、一定時間内ならば訪問数は増えません。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- ウェブマスター
- WEBマスターとは、ホームページの管理者のことを指します。ホームページの規模に関わらず、ホームページの運営者であればWEBマスターと呼ばれます。 個人のホームページでは運営者自身がWEBマスターであり、企業による大規模なホームページでは統括する人がWEBマスターとして業務にあたります。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他