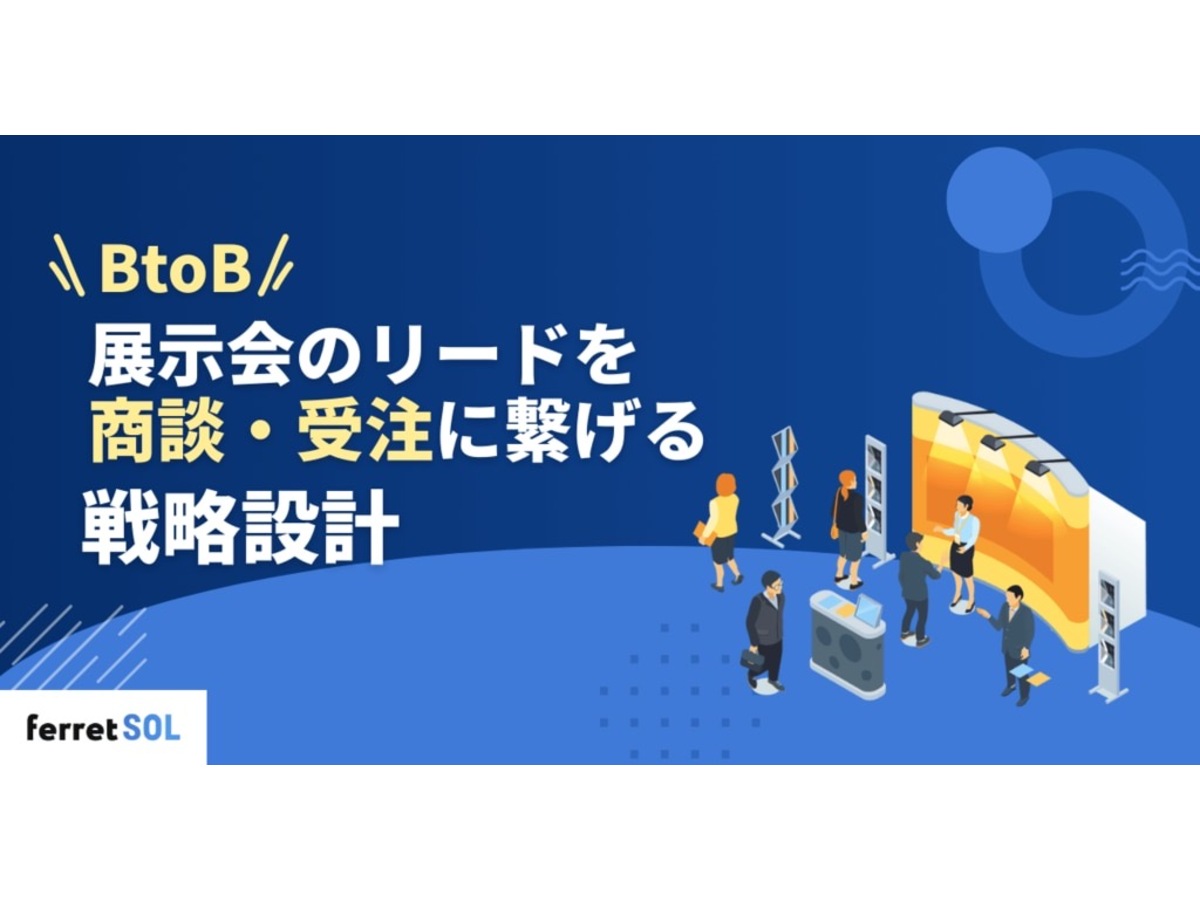受注獲得につながるウェビナーとは?効果的な開催方法を徹底解説!
収益化や既存顧客のフォローなど様々な効果を期待できるウェビナー。特に、見込み顧客の集客・育成したい企業にとっては、ウェビナーを効果的に実施することで、リード獲得やリードナーチャリングにつながるので、成果拡大を目指せます。
しかし、ウェビナーの開催方法が分からない方も多いのではないでしょうか。まずはウェビナーを開催するメリット・デメリットなどの基本的な知識を身につけることが大切です。
本記事では、ウェビナーの基本概要から開催までの流れを解説します。効果的なウェビナーを開催し、成果につなげるために重要な情報を記載しているので、ぜひ参考にしてください。
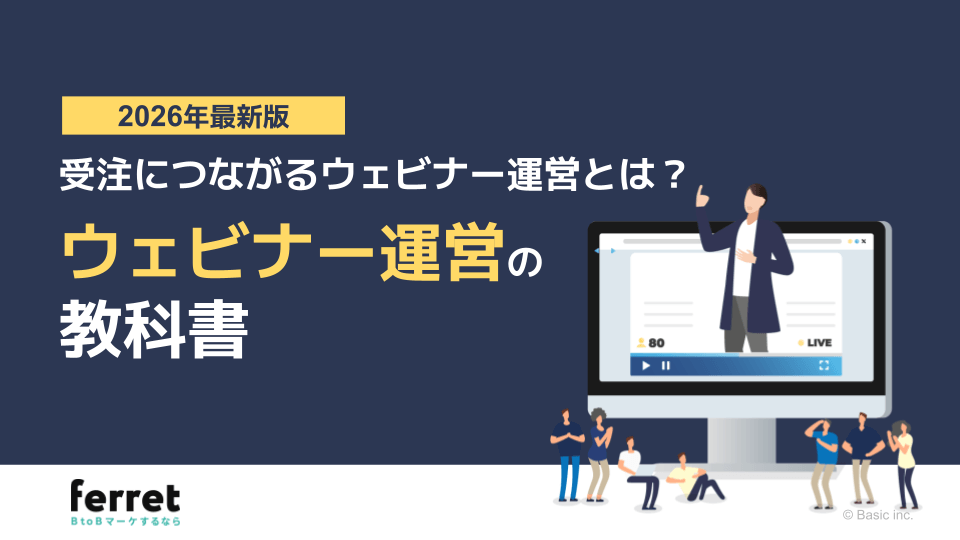
受注に繋がるウェビナー運営とは? ウェビナー運営の教科書
本書では、ウェビナーの企画から準備・集客・開催後のフォローまでの一連の流れと、ウェビナーで受注などの成果を上げるためのポイントについてお伝えします。
目次
ウェビナーとは
ウェビナーとは、ウェブ(Web)とセミナー(Seminar)を合わせた造語です。オンラインで開催されるセミナーのことを意味します。
デジタル化が加速する現在、ウェビナーに対するニーズが高まっており、多くの企業がウェビナーをマーケティング施策の一つとして導入しています。ウェビナーを開催する目的は主に以下の通りです。
- 収益化の手段(有料ウェビナー)
- 既存顧客のフォロー
- 見込み顧客の集客・育成
特に見込み顧客の集客やリードナーチャリングに関して、ウェビナーは重要な役割を担います。
ウェビナーのメリット

ウェビナー施策にはどのようなメリットがあるのでしょうか。ここでは、他のマーケティング施策と比較したウェビナーを開催するメリットを紹介します。
開催者側のメリット
❶ 低コストでリード獲得できる
インターネット環境さえ整っていれば始められる施策なので、Web広告などに比べて安価で新規リード獲得することが可能です。
❷ 認知を取りやすい
ターゲットの課題に沿ったテーマのウェビナーを段階的に設計し、複数回参加してもらうことで、「◯◯といえばA社」のように第一想起されやすくなります。
❸ 二次利用しやすい
アーカイブ配信や開催レポートなどコンテンツに二次利用することで資産として積み上げていくことができるため、新たなリード獲得に活用する好循環が生まれます。
❹ 参加者の反応が直にわかる
質疑応答の時間を設けたり、クイズ形式を盛り込むなど、内容を工夫することで参加者の反応を直に聞くことができるので、顧客理解が深まります。
参加者側のメリット
ウェビナーにおける参加者側のメリットは以下の通りです。
- どこからでも参加できる
- 移動時間が不要なため、参加時間を作りやすい
- 途中からの入室・退室が気軽にできる
- チャット機能で、主催者へ気軽に質問ができる
先述した通り、インターネット環境さえあればどこからでもウェビナーに参加できるので、参加者は会場まで移動する必要がありません。参加時間を作りやすいだけでなく、交通費や移動時間を節約できます。
また、途中からの入室・退室が気軽にできるので、自分の都合にあわせて参加できます。さらに、チャット機能があるので発言をしなくても主催者へ気軽に質問ができる点もメリットといえるでしょう。
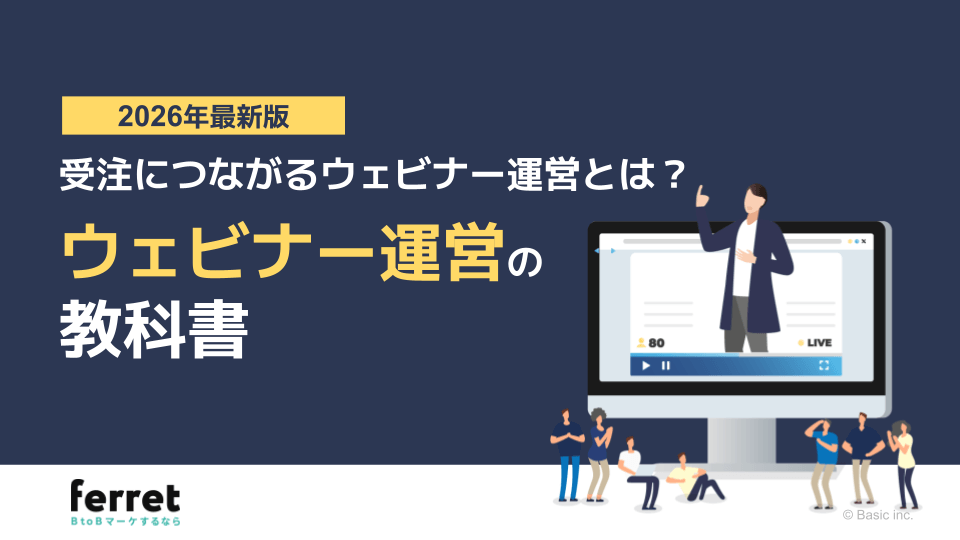
受注に繋がるウェビナー運営とは? ウェビナー運営の教科書
本書では、ウェビナーの企画から準備・集客・開催後のフォローまでの一連の流れと、ウェビナーで受注などの成果を上げるためのポイントについてお伝えします。
ウェビナーを開催する流れ
ウェビナーの準備はどのように進めればいいのでしょうか。ここでは、ウェビナーを開催する流れを紹介します。
- ウェビナーを企画する
- 資料などを準備する
- 集客する
- 開催する
- アフターフォローを行う
今回は、企画段階の流れについて確認していきましょう。
関連記事:ウェビナーマーケティング成功の秘訣とは?失敗する理由や配信のポイントを解説
ウェビナーを企画する
まず目的や目標、ターゲット像、ゴール、タイトルなど、企画において基礎となる部分を決定します。最初に設定したことは、どのように準備を進めていくか、この後の流れに大きく影響するので、しっかりとプランニングをすることが大切です。
❶ウェビナーの目的を確認する

最初にウェビナーを実施する目的を明確にすることが重要です。
まずは大枠として、認知拡大を広め潜在層を幅広く獲得したいのか、顕在層を育成していきたいのか、検討している顧客の後押しをしたいのかなど、どの段階にあたるウェビナーが必要なのか明確にしましょう。
❷ 目標(KPI)を設定する

目的が定まったら、具体的な目標を設定します。目的や目標を設定することで、ウェビナーの方向性が定まります。
例えば、目的が新規会員を増やすことと明確になっていれば、いつまでにどれくらいの申込者が必要なのかなどの目標を考えやすくなります。
ただし、最終的な申込・来場者数を決めるだけでなく、1週間前や2週間前などの途中目標を設定することも大切です。目標より数値が下回っている場合、SNSや広告などで追加施策を行うなどのアクションを起こすようにしましょう。
❸ ターゲット像を明確にする

ターゲットを設定しているかどうかは、ウェビナーの結果を左右します。明確なターゲット像が定まっていないと、ウェビナーのテーマや内容、集客方法を決められず、思うような成果を得られません。
ターゲットを設定する際は、ユーザーの悩みや関心、役職や立場、年齢など、なるべく具体的に想定することが大切です。
ウェビナーのコンテンツを制作する際も、ターゲットのニーズにあわせることで、ユーザーにとって満足感のあるウェビナーを目指せます。
❹ テーマ・タイトルを決める

ウェビナーのターゲットや方向性が大体定まったら、詳細を決めていきます。特に、ウェビナーのタイトルは、どのようなスキル・ノウハウを得られるかを伝える必要があるため、慎重に決めましょう。
一般的にウェビナーのタイトルは「メインタイトル+サブタイトル」の構成となっています。サブタイトルでは補足説明を行いますが、数字などの具体的な情報を入れると効果的です。
また、誰のためのウェビナーか、どのようなメリットが得られるかがわかるようにすると良いでしょう。限定性やニュース性のある表現もユーザーの興味を高めやすいです。
❺ ウェビナーの概要文を作る

まずはどんなウェビナーなのかをまとめた概要文を作ってみましょう。
概要文に含めるべき情報は、ウェビナーで学べる内容や対象者、視聴することで解決できる悩み・課題などです。
概要文を作っておくと関わるメンバーにも説明しやすく、様々な準備を進める上で立ち返ることができるため、趣旨からブレずに詳細を詰めていくことができるのでおすすめです。
概要文は、集客のためのLPにそのまま記載できる形で作成しましょう。参加者側がどのようなメリットを得られるかという視点を意識すると、セミナーに参加したくなる魅力的な概要文が作成できます。
❻ ウェビナーの骨子を決める
ここまでの工程で決めたテーマ・概要に沿ってウェビナー内容の流れを決めます。
60分間など決めた時間内に収まる内容に組み立てていきます。
図は下記のようなケースでのウェビナー骨子の例です。
| 具体例 | |
|---|---|
| 自社サービス | LP制作ツール |
| ウェビナー目的 | 自社サービスへの興味の醸成 |
| 対象者 | これからリスティング広告施策を始めるマーケティング担当者 |

❼ 開催日時を決める
ウェビナーをいつ開催するか決めましょう。ターゲットによってウェビナーの適切な開催日時が異なります。
例えば、一般的な会社員が対象のウェビナーは週始めと終わりを避けて、平日火曜日〜木曜日の10〜11時台、もしくは14〜15時台に設定すると良いです。
忙しい時期や時間帯にウェビナーを開催しても、思うように集客できない可能性があります。そのため、ターゲットにあわせてウェビナーの開催日時を決定するようにしましょう。
資料などを準備する
ウェビナーを開催するにあたって、集客用のLP、資料やスライド、アンケート等を準備しましょう。
❶ 集客用のLPを作成する
様々な集客方法の受け皿となる集客用のLPを用意しておくと便利です。
図はLPの構成例です。企画した内容を元にすればスムーズに考えられます。

申し込みフォームは、ページ遷移せずにLP上にあった方が離脱率が抑えられる傾向があります。
後々分析・集計しやすいフォームを使うと尚良いでしょう。
弊社ではウェビナー集客用のLPをテンプレートで簡単に作成でき、申込者の管理や便利なツールがありますので、是非ご活用ください。
▼ ウェビナーLP簡単に作れるツール

【月額9,800〜】LPを自分でサクサク作り放題|ferret One for LP
LPの改善と量産を外部業者やエンジニアに依頼せずに自分で完了。マーケティング機能も充実。PDCAが高速に回せます。
❷ 資料を作成する

まずはスライド等のウェビナー資料を作成しましょう。大きな流れを把握するために構成を作成してから作業に取り掛かることをおすすめします。
構成がない状態で資料づくりを進めてしまうと、「必要な内容が欠けていた」などの事態に陥ってしまいます。
また、スライドはワンスライド・ワンメッセージで、見やすさを心がけることが重要です。1枚のスライドに複数のメッセージがあると、参加者は何が重要であるかを判断しにくくなります。
❸ アンケートを作成する

ウェビナーの実施後に、参加者に回答してもらうアンケートを作成しておきましょう。アンケート結果を分析して、次のウェビナーの改善につなげることが大切です。
例えば、ウェビナーの内容に関する満足度や商品購入への関心度、購入する場合の予算感などを把握することで、効果的な次のアクションにつなげられます。
さらに、優先的に営業すべき参加者の絞り込みを行えるので、ウェビナーの後はアンケートを実施するようにしましょう。
集客する

ウェビナーの参加者を集めるために、様々な方法で集客を行う必要があります。一般的なウェビナーの主な集客方法には、下記のようなものがあります。
- 自社サイトへ掲載
- メール配信
- ブログやSNSでの告知
- SNS広告の配信
- イベント告知サイトへ掲載
- 営業担当から案内する
ハウスリストが豊富にある場合はメール配信、SNS活動が活発な企業はSNSの活用など、ターゲットや自社の状況に合った集客方法を検討しましょう。
関連記事:【BtoBウェビナー】集客の効果を最大化させる方法を解説
手順を知って効果的なウェビナーを開催しよう
ウェビナーを開催することで、収益化、既存顧客との関係構築だけでなく、見込み顧客の集客・育成を行えます。
ウェビナーの基本的な流れを踏まえた上で、ターゲットにとって有益なウェビナーを企画することが大切です。また、反響の良いウェビナーを目指すために、目的や目標、ターゲット像、ゴールなどの企画から資料準備、集客など開催に向けて準備を徹底しましょう。
さらに、ウェビナー開催後もアンケートの分析等を行なって改善していくのがポイントです。
下記の資料ではウェビナーの効果を最大化する方法を解説しています。今回は企画までの流れを説明しましたが、こちらの資料では全体の流れを把握できるようになるだけでなく、成果につなげるためのポイントを理解できます。
また、共催セミナーの進め方についても記載していますので、ぜひ、ウェビナー開催時にご活用ください。
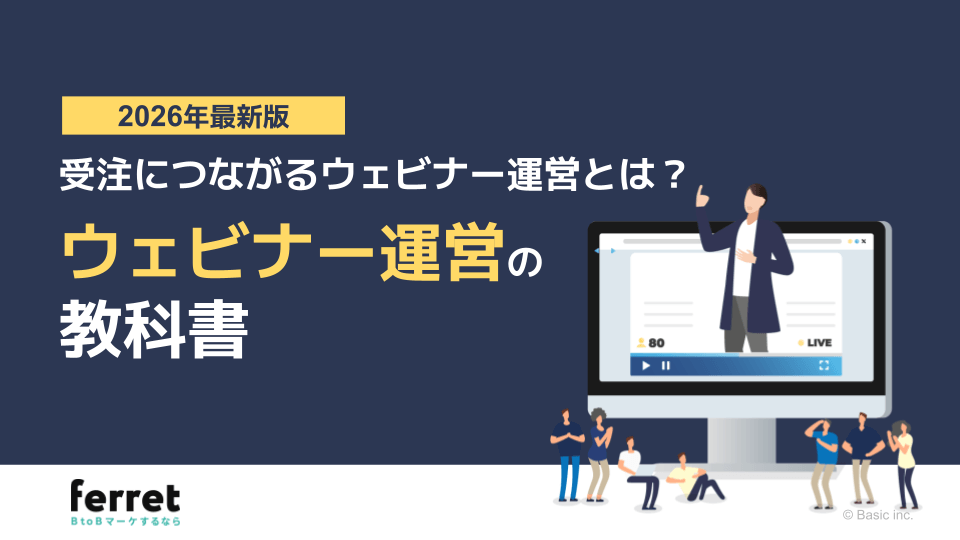
受注に繋がるウェビナー運営とは? ウェビナー運営の教科書
本書では、ウェビナーの企画から準備・集客・開催後のフォローまでの一連の流れと、ウェビナーで受注などの成果を上げるためのポイントについてお伝えします。
ウェビナー集客にもferretをご活用いただけます
ferretではセミナー集客のお手伝いをする掲載プランもご用意しております。
サポート内容など具体的な事例はこちらをご覧ください。

【事例】イベント集客をするならferret|スマートキャンプに聞くBOXIL EXPO集客の成果とは
スマートキャンプ株式会社の堤直樹氏にferretの「イベント集客メニュー」の成果を伺いました。イベント集客でお悩みの方におすすめの記事です。3分ほどで読めます。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- リスティング広告
- リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を、有料で表示するサービスのことです。ユーザーの検索結果に連動した形で広告が表示されるため「キーワード連動型広告」「検索連動型広告」とも呼ばれます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- 離脱率
- 離脱率とはホームページを見ている人が、そのホームページから去り、アクセスの記録などを取れなくなる状態の割合のことを言います。ホームページ運営者はどのページでユーザーが離脱(去った)のかをチェックし、改善に役立てることが多いです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他