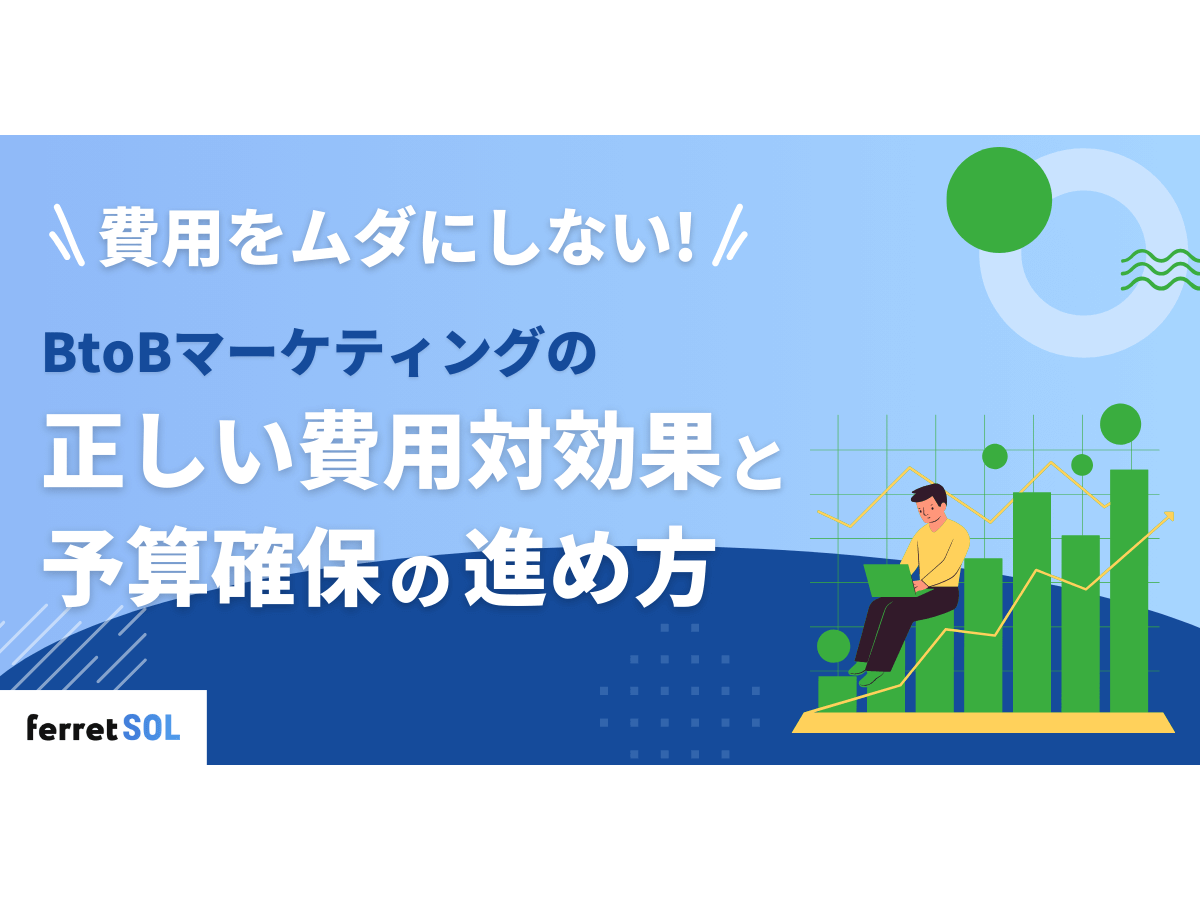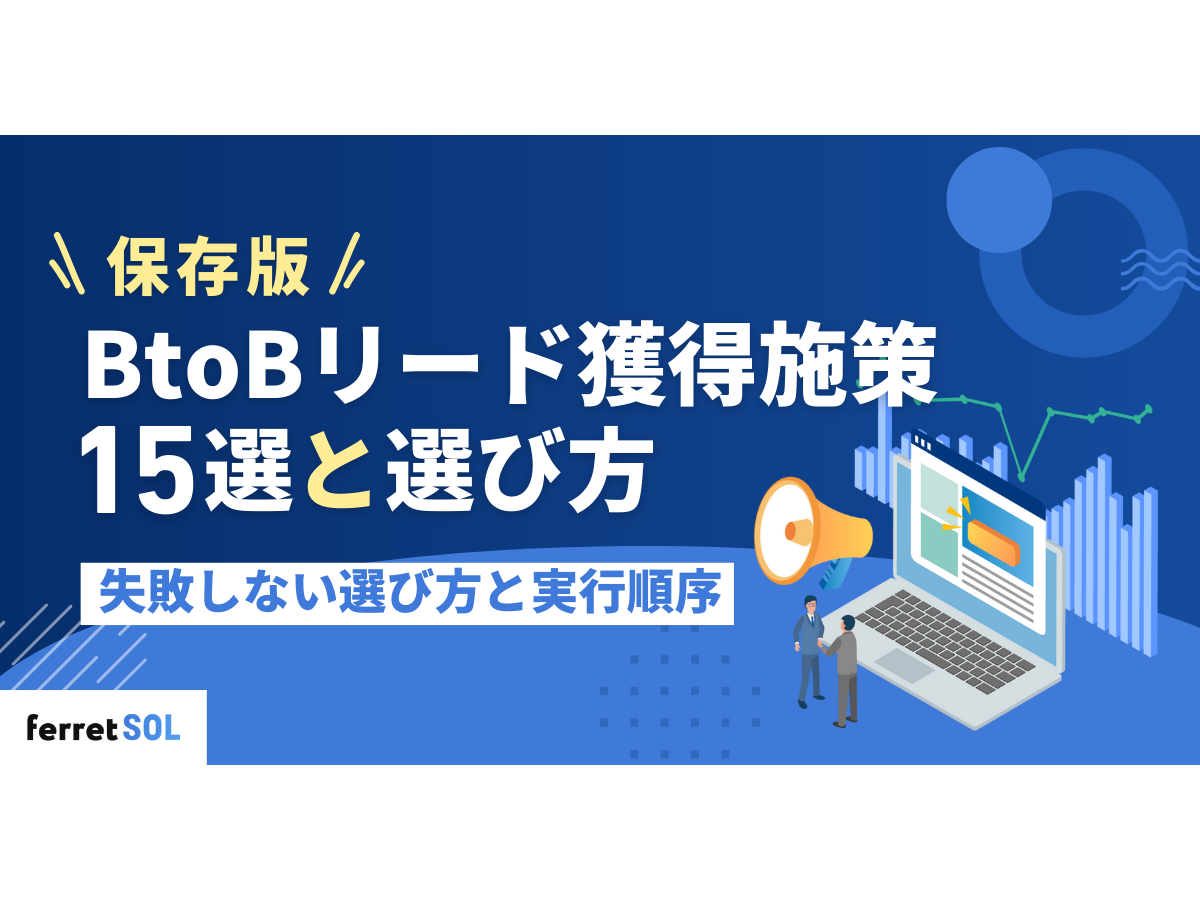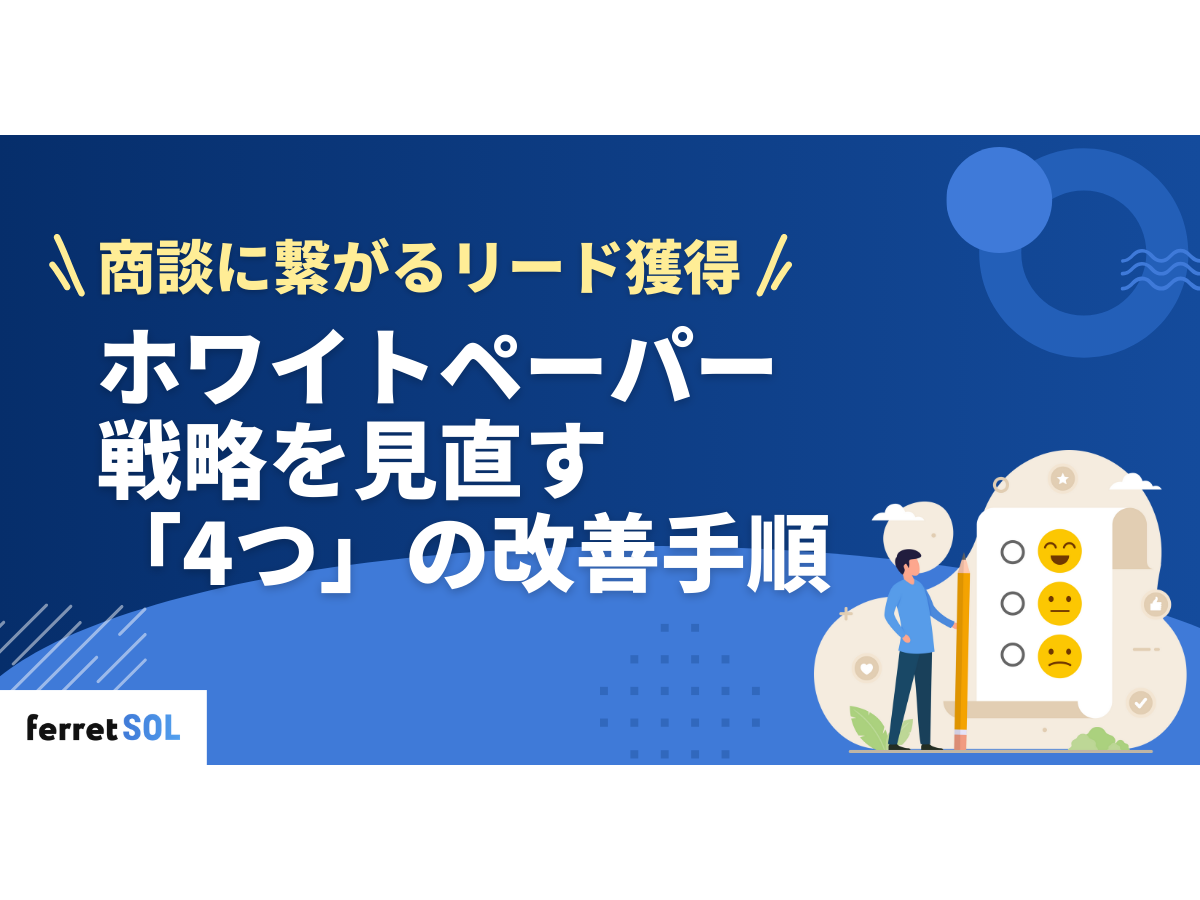ウェビナーで集客する方法13選【BtoB】成功させるためのコツや注意点を徹底解説
新型コロナウイルスの影響により、ニーズが急増したウェビナー。近年はBtoB分野でもウェビナーを活用する企業が多く出現しました。テレワークの普及により、オンライン上での面接や説明会、商談などが定着したため、将来的にもウェビナーを含むオンラインでのやり取りは継続的に活用されることが予想されます。
実際にウェビナーをマーケティング戦略として新たに導入したいけれど、何から始めればいいかわからないという方に向けて、BtoBウェビナーの基礎概要を解説します。
目次
- BtoBマーケティングでウェビナーが活用される4つの理由
- ウェビナーを実施するまでの流れ【5ステップ】
- BtoBウェビナーの集客方法7選【オンライン】
- BtoBウェビナーの集客方法6選【オフライン】
- BtoBウェビナー集客の代行会社5選
- BtoBウェビナーの企画の立て方
- BtoBウェビナーの集客率を向上させる6つのコツ
- BtoBウェビナーの集客率をさらに向上させるための2つの施策
- コロナ禍におけるウェビナーへの需要
- BtoBウェビナーの集客におすすめのセミナーポータルサイト3選
- BtoBウェビナーの効果を最大化させよう
BtoBマーケティングでウェビナーが活用される4つの理由

BtoBマーケティングでウェビナーを活用することでさまざまなメリットを得られます。ここでは、ウェビナーが活用される理由を解説します。
BtoBマーケティングの施策としてウェビナーの活用が広がっている理由は、以下のとおりです。
- 幅広い情報を入手できる
- 多くの人員を必要としない
- コンテンツとして活用可能
- 場所にとらわれない
それぞれ詳しくみていきましょう。
幅広い情報を入手できる
ウェビナーを実施することで、視聴者のデータを幅広く収集することができます。
参加申し込みの際に入力してもらう基本情報のほか、視聴者が興味を持っているコンテンツや、ウェビナーに対するリアクションなど、あらゆるデータを取得することが可能です。
例えば、ウェビナー開催後にアンケートを実施すれば視聴者の感想を把握でき、次に向けた改善策を考えることができます。また、アンケートを通じて商品・サービスの検討状況も調査できるので、その後のアプローチにつなげられます。
他にも、申込率や参加率などの数値を分析することで、視聴者にとってニーズの高いコンテンツを目指すこともできます。
このように、ウェビナーを通じてマーケティングにおいて重要な情報を集められます。
多くの人員を必要としない
ウェビナーが活用される理由として、多くの人員を必要としないことが挙げられるでしょう。
対面でのイベントは会場の確保や設営、参加者の誘導、開催後の片付けなど、様々な作業が発生するため、多くの人員を配置する必要があります。
一方、オンライン上で開催するウェビナーは会場の準備の手間を省けるので、運営に多くの人員を要しません。
配置できる人数に制限がある場合でも、ウェビナーを活用することで施策を実行できます。
コンテンツとして活用可能
ウェビナー配信後に様々な方法でコンテンツを活用できる点も魅力の一つです。ウェビナーを有効活用することで、費用対効果を高められますし、より多くのユーザーにコンテンツを届けることができます。
例えば、ウェビナーの内容を記事にすることで、自社メディアで公開することが可能です。さらに、オンデマンド配信用のコンテンツとして公開すれば、場所や時間にとらわれずにユーザーに視聴してもらえます。
このようにウェビナーの活用方法は幅広く、認知拡大やリードナーチャリング、商品・サービス購入などを目指せます。
場所にとらわれない
対面によるセミナーは会場まで足を運ぶ必要があるため、参加者が限定されてしまいます。
しかし、場所に制限のないウェビナーであれば、より多くのユーザーに参加してもらうことが可能です。
例えば、都市部で開催するイベントをオンラインに切り替えることで、地方や海外からの参加も見込めます。
さらに、移動する手間やコストを省くこともできるので、より効率的にマーケティング施策を実行できます。
ウェビナーを実施するまでの流れ【5ステップ】

ウェビナーを実施するまでの主なフローは以下のとおりです。
- 企画を立案する
2.台本・資料を作成する
3.集客する
4.ウェビナーを実施する
5.アフターセールスをする
それぞれ順番にみていきましょう。
ステップ1.企画を立案する
まず、企画を立案します。
ウェビナーの企画段階では、主に以下の2点に注意して集客する必要があります。
- ペルソナの設定する
- ウェビナーを開催する目的を決める
ペルソナとはターゲットの具体的な人物像のことです。ウェビナーへの参加者のペルソナを明確化して、そのニーズにあったウェビナーを考えることによって、ウェビナー参加者の興味・関心や購買意欲を向上させることにつながります。
また、ウェビナーの目的を明らかにすることも大切です。
ウェビナーを開催する目的には、認知やナーチャリング、商談化などがあります。このような目的を明確化することで、ターゲットが求めるウェビナーの企画内容を考えるきっかけになります。
ステップ2.台本・資料を作成する
企画を立案したら、ウェビナー本番で使用する台本・資料の作成です。
ウェビナーで画面共有などで映し出す資料も、ウェビナーで伝えたい内容を参加者に理解してもらうための大切な1つの要素です。資料は画面に映して説明しながら進行するため、台本の役割も果たします。
また、台本や資料作成が完了したら、内容に漏れや不備がないか確認したうえで、時間配分なども意識しながら一通り練習しておきましょう。
ステップ3.集客する
次に、ウェビナーに集客します。
ウェビナーを開催しても参加者がいなければ開催する効果がありません。ウェビナーはあくまでも集客するための手段のひとつです。
そのため、できるだけ多くの参加者を集めるための集客の工夫が必要です。
オンラインとオフラインどちらでも集客ができるため、ウェビナーの参加者層や内容にあわせて集客方法を選択しましょう。
ステップ4.ウェビナーを実施する
集客が完了したら、いよいよウェビナーの実施です。
ウェビナーが成功するために本番までにいくつかしておくといいことがあります。
- リハーサルで全体の流れを確認する
- 配信機材や配信場所に問題がないか確認する
- 参加者が抱きそうな質問や疑問を用意する
ウェビナー本番では、セールストークよりも、参加者との信頼関係を構築することを優先事項として進行しましょう。
また、ウェビナーの本番終了後に見返せるように、録画もしておくことをおすすめします。
ステップ5.アフターセールスをする
ウェビナー実施後すぐにすべきなのは、アフターセールスです。
アフターセールスとは具体的には、参加者へのメールの送信やアンケートへの回答依頼などが挙げられます。
アフターセールスでは、次回のウェビナーへの勧誘や最終的に購入してもらいたい商品・サービスの勧誘ができます。
*ただし、ウェビナー実施後なるべく早くすることが重要です。*それは、時間が経過してしまうと参加者の熱量や記憶の低下を招いてしまうため、リアクションの数が減ってしまいます。
参加者の熱量が下がらないうちにアプローチするためにも、すぐにメールを送信することやアンケートの回答を丁寧に確認することが求められるでしょう。
BtoBウェビナーの集客方法7選【オンライン】

ウェビナーを開催しても人が集まらなければ意味がありません。ここでは、ウェビナーの集客方法を紹介します。
オンラインでの主要なBtoBウェビナーの集客方法は、以下の7つです。
- 自社サイトでの告知
- SNSへの投稿
- Web広告への出稿
- 見込み客や過去の参加者へのメール
- ウェビナー集客サイト(ポータルサイト)の利用
- メールマガジン(メルマガ)の配信
- プレスリリースの発信
それぞれの特徴を詳しくみていきましょう。
1. 自社サイトでの告知
まずは自社が管理するWebサイトやオウンドメディアでウェビナーの告知を行いましょう。
自社サイトやオウンドメディアを閲覧している人は、もともと提供しているサービスや商品に高い関心を持っていると考えられるため、効果的な集客が期待できます。
2. SNSへの投稿
TwitterやFacebook、Instagramなど自社のSNSアカウントを作成してウェビナーの告知を行う方法です。
投稿が多くの人にシェアされれば情報は広く拡散し、これまでアプローチできなかった層にもウェビナーを告知することができます。投稿は無料でできるため、その手軽さから多くの企業が情報発信ツールとして利用しています。
ただ、その手軽さゆえ他の投稿に埋もれてしまう可能性もあるため、投稿内容には工夫が必要です。
3. Web広告への出稿
Web広告はさまざまなWebサイトに広告を掲載する方法です。具体的には以下のような広告を指します。
- 動画広告
- バナー広告
- リスティング広告
- SNS広告
広告費のコストがかかる反面、性別・年齢・職業・興味・関心などの細かいターゲティングや配信エリアの調整が可能になります。
この集客方法においてはどのようなターゲットに配信するか、ペルソナの設定が重要となるでしょう。また、広告内容もペルソナにマッチするものでなくてはいけません。
4. 見込み客や過去の参加者へのメール
見込み客や過去のウェビナー・イベント参加者のリストから、メール配信で告知をするのも方法のひとつです。
こうしたリストに掲載されているのは、自社と過去に接点を持っていた顧客や自社と取引する可能性の高い会社です。ウェビナーの内容にも興味を持つ確率は高いでしょう。
ただ、メールで告知する場合、件名で興味を惹けなければ開封されずそのまま削除されてしまいます。メールの件名には目を引くワードを入れるか、興味を持ってもらえるようなタイトルにしなくてはいけません。
5. ウェビナー集客サイト(ポータルサイト)の利用
ウェビナー集客サイトとは、さまざまなウェビナーの情報を掲載しているサイトのことで、「ウェビナー(セミナー)ポータルサイト」とも呼ばれます。
こうしたサイトは日頃からウェビナーの情報を探している人が閲覧しているため、参加に意欲的なユーザーにアプローチできる可能性が高いです。また、このような外部サイトでセミナー情報を告知することで、これまで接点を作れなかった顧客にもリーチできます。
ウェビナー集客サイトには、さまざまなジャンルのウェビナー情報が掲載されているもの、マーケティング、テクノロジー、ビジネス領域に特化したものがあるため、自社のウェビナー内容に合わせて選びましょう。
メールマガジン(メルマガ)の配信
メールマガジン(メルマガ)もウェビナーへの集客には便利な手段のひとつです。
メルマガは、発信者が告知したい情報をすでにメルマガに登録している見込み客に対して、メールを一斉送信できるオンライン集客方法です。
配信する時間やタイミングも柔軟に選べることから、メールでの案内よりも時間も手間もかかりません。
ただし、メルマガはすでに商品・サービスに興味がある見込み客にしかメール送信できないことや開封されない可能性が高いことなどのデメリットもあります。
メルマガの開封率を少しでも向上させるためにもメールのタイトルや構成を工夫することが必要でしょう。
プレスリリースの発信
プレスリリースとは、企業や組織が各メディアなどの報道機関に対して、新商品・新サービスなど最新情報を発信する公式文書のことです。
メディアとは具体的に、テレビ局や新聞・雑誌社、ニュースサイト運営社などがあります。
プレスリリースでウェビナー情報をメディアを通じて発信してもらえると、大きな集客効果が期待できます。特に、著名人や企業の重役などの影響力のある人物が登壇する場合には話題性もあって効果的です。
ただし、プレスリリースの配信費用は1〜5万円が相場となっているため、費用対効果も考慮に入れて検討したうえで活用しましょう。
BtoBウェビナーの集客方法6選【オフライン】

BtoBウェビナーは、オンラインだけでなく、オフラインでも集客できます。オフラインでの主要な集客方法は以下の6つです。
- ダイレクトメール(DM)やはがきの送信
- チラシ広告・ポスターの作成
- 新聞・雑誌広告の利用
- 過去の参加者からの紹介
- 顧客リストへのテレアポ
- ウェビナー集客の代行会社へ依頼
それぞれのオフライン集客方法をチェックしていきましょう。
ダイレクトメール(DM)の送信
ダイレクトメール(DM)は、住所を知っている見込み客に対して、商品・サービスに関することを郵送物を送って伝える集客方法です。
郵便物の具体例としては、はがきやカタログ、小冊子などがあります。
ダイレクトメール(DM)を利用することで得られるメリットは、以下のとおりです。
- 県外に住む人にも集客できる
- デザインや文章を顧客によって変更できる
- URLやQRコードも記載できる
- 顧客へ確実に届けられる
URLやQRコードを記載することやクーポンコードや割引特典などのキャンペーン情報を添付することでより効果が得られます。
ただし、印刷や郵送にコストがかかることや開封されない可能性があることを考えると、郵送先を厳選することをおすすめします。
チラシ広告・ポスターの作成
チラシ広告・ポスターは、チラシやカタログをオフラインで顧客に手渡しや郵送をする場合に活用できる集客方法です。
チラシ広告やポスターが顧客の目に触れることで、興味を喚起して集客につながるメリットがあります。
これらを利用する際には、チラシ広告の場合は顧客の目に止まるようなデザインにすること、ポスターの場合は多くの顧客が集まりそうな場所に設置することが必要です。
ただし、コストがかかってしまう点や情報の変更や更新がすぐに対応できない点がデメリットとして挙げられるでしょう。
新聞・雑誌広告の利用
新聞・雑誌広告の利用は、テレビと並ぶ代表的なマス広告のひとつです。
新聞や雑誌を定期購読している顧客に対して1回で大人数に訴求できることや新聞の信頼性や権威性の高さの影響で広告の信頼性も高まることなどが大きなメリットです。
ただし、広告宣伝費用が高いことや顧客属性を限定しにくいことなどがデメリットとして挙げられます。
過去の参加者からの紹介
過去の参加者からの紹介には、口コミと知人からの紹介があります。
口コミや紹介は、他の集客方法よりも高い効果をもたらすことがよくあります。その理由は、第三者からの意見や感想はユーザーにとって優良な参考情報であり、信頼感や安心感につながるからです。
見込み客の獲得につながるために、クーポンなどの割引特典をつけることやSNS経由で拡散してもらうことなどがおすすめです。
ただし、長期間にわたって継続的な効果は見込めないので注意しましょう。
顧客リストへのテレアポ
テレアポとは、企業や個人に直接電話をかけて、ウェビナーの案件・告知をするオフラインの集客方法です。電話番号さえ知っていれば、電話をかけて直接宣伝ができます。
短時間で多くの顧客にアプローチできることや直接顧客のリアクションを感じられることなどのメリットがあります。
その一方で、想定されるデメリットは以下のとおりです。
- 時間と手間がかかってしまう
- 迷惑電話と瞬時に判断される
- 営業部署がないと業務フローに苦労する
これらのデメリットに対応するため、顧客のウェビナーへの関心度を見極めることや顧客リストを作成することが求められます。
ウェビナー集客の代行会社へ依頼
ウェビナーの集客を代行してくれる会社へ依頼する方法も選択肢のひとつです。
ウェビナーへ集客する方法は、時間の長短はあっても、時間と手間がかかってしまいます。
そこで、ウェビナー集客の代行会社へ外注することで、時間と手間をかけなくても効率的に集客ができます。
そのため、リソースや専門の営業部署がない場合や、なるべく早く集客の成果を出したい場合にはおすすめの集客方法です。
BtoBウェビナー集客の代行会社5選

先述のとおり、ウェビナーへの集客方法として代行会社へ外注することは選択肢のひとつです。
ここでは、BtoBウェビナーへの集客をサポートしてくれるおすすめ代行会社5選をご紹介します。
- 株式会社ナツメスタジオワークス
- 株式会社グローバルリンクジャパン
- 株式会社ガイアックス
- 株式会社ティーケーピー
- 株式会社パソナ
- マジセミ株式会社
それぞれの会社の特徴をみていきましょう。
株式会社ナツメスタジオワークス

引用元:株式会社ナツメスタジオワークス
株式会社ナツメスタジオワークスは、動画マーケティング・動画制作・映像制作・動画配信など動画マーケティングをサポートする会社です。
動画を中心とする事業のひとつとして、ウェビナー動画制作や運用の代行を行っています。
また、Web動画制作専用スタジオも完備していることも大きな特徴です。
このように、ウェビナーの配信だけでなく、広告プロモーション動画やストリーミング配信など動画関連業務を幅広く支援しています。
株式会社グローバルリンクジャパン

引用元:株式会社グローバルリンクジャパン
株式会社グローバルリンクジャパンは、SNSコンサルティングやSNS運用代行などSNS事業を中心に展開している会社です。
また、ウェビナー事業も展開しています。ウェビナーだけでなく、ハイブリットセミナー・ハイブリットイベント配信や運営代行サービスなどが、個人・法人に関係なく利用されています。
ニーズにあわせたサービス内容や予算などのプランを柔軟に組めることが特徴です。
株式会社ガイアックス

引用元:株式会社ガイアックス
株式会社ガイアックスは、ソーシャルメディアとシェアリングエコノミー領域、Web3・DAOを用いた事業に注力する会社です。
SNSを中心にしたマーケティング支援事業以外にも、ウェビナー専用のLP制作や広告出稿による集客代行なども行っています。
集客だけでなく、ウェビナーの企画から撮影、アフターフォローまで支援している点が特徴的です。
株式会社ティーケーピー

引用元:株式会社ティーケーピー
株式会社ティーケーピーは、ホテル宴会場・貸会議室運営事業やホテル・リゾート事業、イベント空間プロデュース事業など幅広く事業を展開する会社です。
そのうちのイベントプロデュース事業として、ウェビナー・ライブ配信・Web会議のプロデュースを行っています。
配信方法の企画から会場や回線・機材の手配、現地でのオペレーションまですべてワンストップで対応可能です。
年間2,000件以上のウェビナー開催実績を誇る実績豊富な専門スタッフが、集客サイトの制作や広告による宣伝を代行してくれます。
株式会社パソナ

引用元:株式会社パソナ
株式会社パソナは、主に人材派遣事業などを幅広く事業を展開している会社です。
人材派遣事業以外にも、企業の経営課題や人事戦略などのコンサルティングや教育・研修も行っています。
小規模から大規模配信まで、ウェビナーを活用したオンラインセミナーをサポートしてくれます。
告知文面の作成や参加者リストの管理など専門スタッフによるトータルサポートが特徴的です。
マジセミ株式会社

引用元:マジセミ株式会社
マジセミ株式会社は、セミナーマーケティングを展開する会社です。
情報システム部門・セキュリティ部門・DX部門・IT・製造業などの幅広い分野の集客に強みがあります。
年間500回以上のウェビナー開催とデータ分析を通して培ったノウハウで、強い集客力・企画力・運営力が特徴的です。
それぞれの課題やニーズにあわせた企画提案から集客、フォローまでウェビナー運営に必要な業務をワンストップで支援します。
BtoBウェビナーの企画の立て方

ウェビナーの集客力を高めるためには、ウェビナー自体の企画も重要になります。ここでは、企画の立て方を解説します。
主なBtoBウェビナーの企画の立て方の流れ、以下のとおりです。
- 目的を設定する
- 最適な配信パターンを考える
それぞれのステップを確認していきましょう。
目的を設定する
BtoBウェビナーを実施する際は、まずは目的を設定しましょう。目的によって最適な配信方法が異なり、目標として設定すべき数値が変わってきます。
- 新規顧客へのリーチ
- エンゲージメントの強化と顧客理解
- 行動を促す
大きく分けると上記のような分類ができます。さらに、新規顧客へのリーチ拡大や、接点頻度の強化、顧客のフォローアップ活動など、BtoBウェビナーを開催する目的はそれぞれ挙げられます。
目的を明確にしたあとに目標となる数値を設定するとよいでしょう。申込数や参加率、SNS拡散数などをKPIとして定めます。この数値をベースにしながら分析を行い、改善を目指します。
最適な配信パターンを考える
設定した目的に沿って、最適な配信方法を考えます。ウェビナーの配信パターンは大きく以下の3つに分けられます。それぞれ特徴が異なるので、自社がどの形態でウェビナーを実施すべきか考えることが大切です。
1.プレゼンテーション型
プレゼンテーション型は、その名の通り視聴者の希望に沿った情報をプレゼンテーションで伝達するリアルタイム配信です。資料を共有しながら視聴者の理解を促進します。
配信したウェビナーはアーカイブとして公開できるだけでなく、著名人をアサインしやすい点などがメリットに挙げられます。
ただ、情報伝達が目的であるため、視聴者とリアルタイムでコミュニケーションを取るのは難しく、次のアクションへつながりにくいことが懸念されます。
▼メリット
- オンラインでのセミナー実施が難しい際の代わりとなる
- 配信済みのウェビナーはアーカイブとして公開できる
- 視聴者側に知識やスキルが必要とされない
- 準備や開催までの手間が少ない
- 著名講師を招きやすい(集客に繋がる)
▼デメリット
- 情報伝達が目的となるため、視聴者との双方向コミュニケーションは希薄になりやすい
- 外部講師を招く場合、ウェビナーの完成度が講師によって左右されやすい
- 知識の吸収や理解度の向上が目的となるため、次のアクションへ繋がりにくい
- フォローアップの際の会話はYes/Noクエスチョンにとどまりやすい
2.トークショー型
トークショー型は、配信者と視聴者が同じテーマに沿って話し合うリアルタイム配信です。
双方向のコミュニケーションができるので、疑問があったらその場で質問できます。この形式での開催は視聴者の参加意識を高めやすいといった特徴があり、平均85%が完全視聴しているとの調査も。また、フォローアップの会話も発展させやすく、視聴者の理解を深めやすいです。
また、問題意識を醸成しやすいため参加者に次のアクションを誘発しやすい点もメリットといえるでしょう。
しかし、議論の自由度が高いため、最終的な発言をコントロールしにくく時間通りに終了しない可能性があることが大きなリスクとして挙げられます
▼メリット
- 視聴者が集中しやすく、ウェビナーが盛り上がりやすい
- リアルタイムで双方向のコミュニケーションが可能
- 配信企業へのエンゲージメントが高まりやすい
- 問題意識が醸成しやすく次のアクションに繋がりやすい
- フォローアップの際の会話が弾みやすい
▼デメリット
- 議論の自由度が高いため、参加者や講師の発言のコントロールがしにくい
- 視聴者からの意見・質問に対し、司会者や登壇者が適切にレスポンスできる能力が必要
- 時間通りに終了しない可能性がある
- 予想外のハプニングが起きた場合でも撮り直しができない
3.アーカイブ配信
アーカイブ配信は、リアルタイムで配信するのではなく、あらかじめ撮影した動画を視聴者の好きなタイミングで視聴してもらう配信パターンです。
デモ動画など失敗が予想されるイベントであっても、事前に録画しておけば動画を編集することができます。また、配信前に動画を客観的に確認できるので、配信側の伝えたいことが伝わっているかチェックすることも可能です。
ただ、リアルタイムの配信とは異なり、視聴者の反応がわかりづらく、時間をかけて視聴してもらいにくいなどのデメリットも存在します。
▼メリット
- 視聴者の都合のよい時間帯で視聴可能
- 繰り返し何度でも、視聴者の好きなペースで視聴できる
- 取り直しや動画の編集が何度でもできるので、失敗が予想されるイベントも安心して行える
- 一度動画を作成すれば何度でも再配信ができるためコスト削減に
▼デメリット
- 時間を欠けて視聴する参加者は少ない
- 情報発信が一方通行のため、視聴者の反応が分からない
- 双方向のコミュニケーションを重視するトークショー形式とは相性が悪い
- オープンコンテンツにした場合、競合他社に研究されやすくなる
BtoBウェビナーの集客率を向上させる6つのコツ

ウェビナーの集客率を向上させるために抑えておきたいコツを紹介します。
BtoBウェビナーの集客率を向上させるコツは、以下の6つです。
- 参加メリットを具体的に
- タイトルが参加率を左右する
- 告知は開催日の1ヵ月前
- 参加しやすい日時を選んで開催する
- 参加したくなるような告知ページを作る
- リマインドメールで確実な参加を促す
それぞれのコツやポイントをチェックしていきましょう。
参加メリットを具体的に
ウェビナーの告知では、参加するメリットを具体的に示しましょう。
「どのような課題解決に繋がるのか」「どのような専門知識やスキルが得られるのか」「どのような気づきや学びがあるのか」など、ウェビナーのメリットを具体的に感じられるような告知ができれば、参加者は自然と増えるはずです。
タイトルが参加率を左右する
ウェビナーの集客率を向上させるために最も重要すべきポイントはタイトルです。
ウェビナータイトルは告知ページやメール、広告などどこからアクセスした場合でも最初に目にします。見た人に「魅力的」「参加する意義がある」と思わせるためにも、以下の要素を盛り込み、タイトルを作りましょう。
ウェビナーの具体的なメリット
- パワーワード
- トレンドワード
- 具体的な数字
上に挙げた要素を盛り込むのはもちろんのこと、どのようなウェビナーなのかをタイトルからイメージしやすくしておくことも重要です。
告知は開催日の1ヵ月前
ウェビナー告知のタイミングは概ね開催日の1ヶ月前が最適と言われています。
告知のタイミングは集客数にも大きく影響します。告知からウェビナーまでの期間が短すぎると、参加者のスケジュール確保が難しくなりますし、反対に告知が早すぎてもウェビナーそのものや、ウェビナーの申込みを忘れてしまう可能性があります。
そのため、ウェビナー告知時期の見極めが重要なのです。
参加しやすい日時を選んで開催する
ウェビナーの開催日時は集客数に大きな影響を与えます。できるだけ参加率の高い曜日や時間帯を選んで開催しましょう。
業種やウェビナーのターゲットにより異なりますが、最も集客しやすいのは「火・水・木曜日」の「10〜11時台」という調査もあります。
また、開催回数が少ないと「興味はあるのに日程が合わない」という人がいる場合があるため、ニーズを取りこぼさないためにもウェビナーは別日程で複数回開催することをおすすめします。
リアルタイム開催が難しければ録画配信でも構いません。
参加したくなるような告知ページを作る
集客効果の高いウェビナーの告知ページを作るためにはどのような点に注意すべきでしょうか?以下の項より説明します。
●内容の告知は簡潔に
ウェビナーの告知では、簡潔に内容を伝えましょう。
特にWebページ上では長い文章は読まれにくい傾向にあります。一目で内容を理解できるよう、端的な文章に収めることが大事です。
ただ、最低限必要な以下のような情報は必ず入れておくようにします。
- 開催日時
- 参加方法
- 内容
- 講師
- 視聴に必要な環境
このほか「ウェビナー視聴URLの送付日」「資料送付の条件」など質問が予想される項目についても記載しておくとなお良いですね。
●イメージ写真や参加者の声を載せる
これまでに開催したことのあるウェビナーなら、参加者の声や開催時の様子を撮影した写真を告知ページに載せることで、参加者の信頼感が高まります。
また、過去のウェビナー参加者の生の感想が参加を検討している人の背中を押すこともあるでしょう。ウェビナーの魅力やメリットが具体的に伝わるようなアンケートを選んでおくことが大事です。
●申し込み時の入力項目は最小限に
ウェビナー申込に必要な入力作業が最小限で済むよう、入力項目は極力減らしておきましょう。入力内容が多すぎたり複雑だったりすると、申込のハードルが高まり応募前に申込ページから離脱されてしまう恐れがあります。
申込フォームに入力するのは以下に挙げる限られた項目に留めておきましょう。
- 氏名
- 会社名
- 電話
- メールアドレス
- 自由記入欄(質問など)
また、申込フォームは告知ページと同じページに設置しておき、申込をしたい人がすぐに見つけられるようにしておきます。スムーズな申込がウェビナー参加のハードルを下げ、集客率を高めることにもつながります。
リマインドメールで確実な参加を促す
ウェビナーは申込や参加が手軽な反面、開催日や応募したことそのものが忘れられやすいデメリットがあります。
集客の努力を無駄にしないためにも、ウェビナー開催日までに難度かリマインドメールを配信し、開催日を再確認してもらいましょう。ウェビナーの前日・当日・1時間前などにメールを送っておくことで、参加率を向上させることができます。
BtoBウェビナーの集客率をさらに向上させるための2つの施策

先に紹介したコツに加えて、集客率をさらに向上させるために実践したい+αの施策を2つ紹介します。
定期開催で長期的な集客率アップを狙う
同じテーマのセミナーを複数回、定期的に開催することでトータルでの集客数や集客率をアップできます。人気の高いテーマやセミナーなら、毎週・毎月開催することで「興味はあったが日程が合わず参加できなかった人」も参加できるようになります。
また、開催ごとに参加者の声や質疑応答を集め、それを参考に内容をブラッシュアップしてさらに質の高いウェビナーにしていくことも可能でしょう。
新たなウェビナーの企画は会社にとっても負担のかかる業務ですから、同じセミナーの定期開催は負荷をかけずに集客率を向上させる効率的な方法です。
共催セミナーや外部講師で新規顧客を集客する
他社との共催セミナーや外部講師の招待で自社ではアプローチできなかった新規顧客の集客が可能になります。
共催セミナーでは自社単独で開催する場合よりも広く深い内容のセミナーを行えます。また、著名な講師を招けば話題性が高まるため、幅広い客層から多くの参加が期待できるでしょう。
コロナ禍におけるウェビナーへの需要

ウェビナーは従来から活用されていましたが、上図のように新型コロナウイルスの影響を契機にニーズが急増しました。外出を控える人が増加したことにより、自宅でも参加できるウェビナーが重宝されるようになりました。
最近は、ウェビナーで使用したコンテンツをオウンドメディアやSNS、メルマガなどで再利用する企業も見受けられるようになり、活用の幅が拡大しています。
BtoBマーケティングにおいてもウェビナーは広く活用されており、多くの企業がそのメリットを実感しています。
BtoBウェビナーの集客におすすめのセミナーポータルサイト3選

BtoBウェビナーの集客におすすめのセミナーポータルサイトは、主に以下の3つです。
- こくちーずプロ
- セミナー情報.COM
- TECH PLAY
それぞれの特徴をみていきましょう。
こくちーずプロ|無料で使えるイベント・セミナーの告知・集客サービス

引用元:こくちーずプロ|無料で使えるイベント・セミナーの告知・集客サービス
こくちーずプロは、簡単で安全なイベントの告知・集客ができるイベント集客プラットフォームです。
イベント主催者7万人以上でチケット販売490万枚以上(2024年5月時点)など豊富な実績があり、70万人以上の利用者数を誇るため、個人から法人まで幅広い主催者にウェビナーの宣伝ができます。
有料ウェビナーを開催する場合はチケット販売手数料がかかりますが、登録や掲載には料金はかかりません。
SEO対策も対応しており、検索キーワードのニーズにマッチした新規ユーザーにもアプローチできます。
また、バナー広告やメール配信などの集客方法やチャットツールやホワイトボード機能などのオンラインイベント対応機能など豊富に用意されています。
セミナー情報.COM|人気のセミナーを検索できるサイト

引用元:セミナー情報.COM|人気のセミナーを検索できるサイト
セミナー情報.COMは、ビジネス・マネー・情報技術・生活・文化・健康などの幅広いジャンルのセミナー・ウェビナーの宣伝がされているセミナーポータルサイトです。
利用者が口コミや評価からセミナーを検索できる便利な検索システムがあります。
予算に余裕がある場合は、セミナーに申込みがあった件数だけ費用を支払う成果報酬型プランがおすすめです。
ウェビナーの掲載だけの場合は料金はかからず、無料で利用できます。
TECH PLAY|IT勉強会・イベントなどの情報検索サービス

引用元:TECH PLAY|IT勉強会・イベントなどの情報検索サービス
TECH PLAYは、主にITやテクノロジー関連の勉強会・イベント情報などの宣伝に利用されているセミナーポータルサイトです。
利用者層がテクノロジー関連にニーズがあるため、オンライン開催のイベントが多くなっています。
イベント情報だけでなく、スキルアップやキャリアアップの目的でITに関連するブログも掲載しています。
セミナー・ウェビナー情報の掲載やイベント管理機能、グループ機能、メール・アンケート配信などは無料で利用可能です。
BtoBウェビナーの効果を最大化させよう
今回の記事では、BtoB企業のマーケティング担当者に向けて、ウェビナーの集客について紹介しました。
対面で開催されるセミナーと同様にウェビナーにおいても、集客力が重要です。WebサイトやSNSでの告知以外にも、必要であれば広告出稿も検討しましょう。また、集客力を高めるためには魅力的な内容にしなければなりません。ウェビナーの開催目的を設定し、その目的に沿った配信方法を選択するとよいでしょう。
場所や時間に制限のないウェビナーは、イベント開催後もコンテンツとして活用できるほか、視聴者の情報を取得できるなど、様々な利点をもたらす施策です。オンライン上での顧客接点は、今後益々必要性が高まることが予想されます。視聴者のニーズに合わせたウェビナーを実施し、効果最大化を狙いましょう。
ウェビナー集客にもferretをご活用いただけます
ferretではセミナー集客のお手伝いをする掲載プランもご用意しております。
サポート内容など具体的な事例はこちらをご覧ください。

【事例】イベント集客をするならferret|スマートキャンプに聞くBOXIL EXPO集客の成果とは
スマートキャンプ株式会社の堤直樹氏にferretの「イベント集客メニュー」の成果を伺いました。イベント集客でお悩みの方におすすめの記事です。3分ほどで読めます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- ポータルサイト
- ポータルサイトとは、インターネットの玄関口となる巨大なWEBサイトのことを言います。 サイトが独自の情報を発信するのではなく、検索エンジンやリンク集を核として、ニュースや株価などの情報や、メールやチャットなどのユーザーがインターネット上で必要とする機能を提供しています。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- バナー
- バナーとは、ホームページ上で他のホームページを紹介する役割を持つ画像ファイルです。画像にリンクを貼り、クリックするとジャンプできるような仕組みになっています。画像サイズの規定はありませんが、88×31ピクセルや234×60ピクセルが一般的です。また、静止画像だけでなく、アニメーションを用いたバナーもあります。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- リスティング広告
- リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を、有料で表示するサービスのことです。ユーザーの検索結果に連動した形で広告が表示されるため「キーワード連動型広告」「検索連動型広告」とも呼ばれます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- ポータルサイト
- ポータルサイトとは、インターネットの玄関口となる巨大なWEBサイトのことを言います。 サイトが独自の情報を発信するのではなく、検索エンジンやリンク集を核として、ニュースや株価などの情報や、メールやチャットなどのユーザーがインターネット上で必要とする機能を提供しています。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- 開封率
- 開封率とは、ユーザーに対して一斉配信したメルマガを、どの程度の割合のユーザーが開封しているのかを表した指標です。主にメールマーケティングシステムに標準で搭載されている機能で、開封率を知ることで、過去のメールの開封率と比較し、メールのタイトルや配信する時間帯の改善点を見つける事が出来ます。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- URL
- URLとは、「Uniform Resource Locator」の略称です。情報がどこにあるのかを示すインターネット上の住所のようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。各ページのURLは、インターネットブラウザの上部に文字列として表示されています。日本語では「統一資源位置指定子」という名称がついていますが、実際には日本でもURLという語が使われています。
- URL
- URLとは、「Uniform Resource Locator」の略称です。情報がどこにあるのかを示すインターネット上の住所のようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。各ページのURLは、インターネットブラウザの上部に文字列として表示されています。日本語では「統一資源位置指定子」という名称がついていますが、実際には日本でもURLという語が使われています。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 口コミ
- 「口頭でのコミュニケーション」の略で、消費者の間で製品やサービスの評価が伝達されることです。 一方で、不特定多数の人々に情報が伝達されることをマスコミと使われます。
- 口コミ
- 「口頭でのコミュニケーション」の略で、消費者の間で製品やサービスの評価が伝達されることです。 一方で、不特定多数の人々に情報が伝達されることをマスコミと使われます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- URL
- URLとは、「Uniform Resource Locator」の略称です。情報がどこにあるのかを示すインターネット上の住所のようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。各ページのURLは、インターネットブラウザの上部に文字列として表示されています。日本語では「統一資源位置指定子」という名称がついていますが、実際には日本でもURLという語が使われています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- ポータルサイト
- ポータルサイトとは、インターネットの玄関口となる巨大なWEBサイトのことを言います。 サイトが独自の情報を発信するのではなく、検索エンジンやリンク集を核として、ニュースや株価などの情報や、メールやチャットなどのユーザーがインターネット上で必要とする機能を提供しています。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- バナー
- バナーとは、ホームページ上で他のホームページを紹介する役割を持つ画像ファイルです。画像にリンクを貼り、クリックするとジャンプできるような仕組みになっています。画像サイズの規定はありませんが、88×31ピクセルや234×60ピクセルが一般的です。また、静止画像だけでなく、アニメーションを用いたバナーもあります。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- ポータルサイト
- ポータルサイトとは、インターネットの玄関口となる巨大なWEBサイトのことを言います。 サイトが独自の情報を発信するのではなく、検索エンジンやリンク集を核として、ニュースや株価などの情報や、メールやチャットなどのユーザーがインターネット上で必要とする機能を提供しています。
- 口コミ
- 「口頭でのコミュニケーション」の略で、消費者の間で製品やサービスの評価が伝達されることです。 一方で、不特定多数の人々に情報が伝達されることをマスコミと使われます。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- ポータルサイト
- ポータルサイトとは、インターネットの玄関口となる巨大なWEBサイトのことを言います。 サイトが独自の情報を発信するのではなく、検索エンジンやリンク集を核として、ニュースや株価などの情報や、メールやチャットなどのユーザーがインターネット上で必要とする機能を提供しています。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他