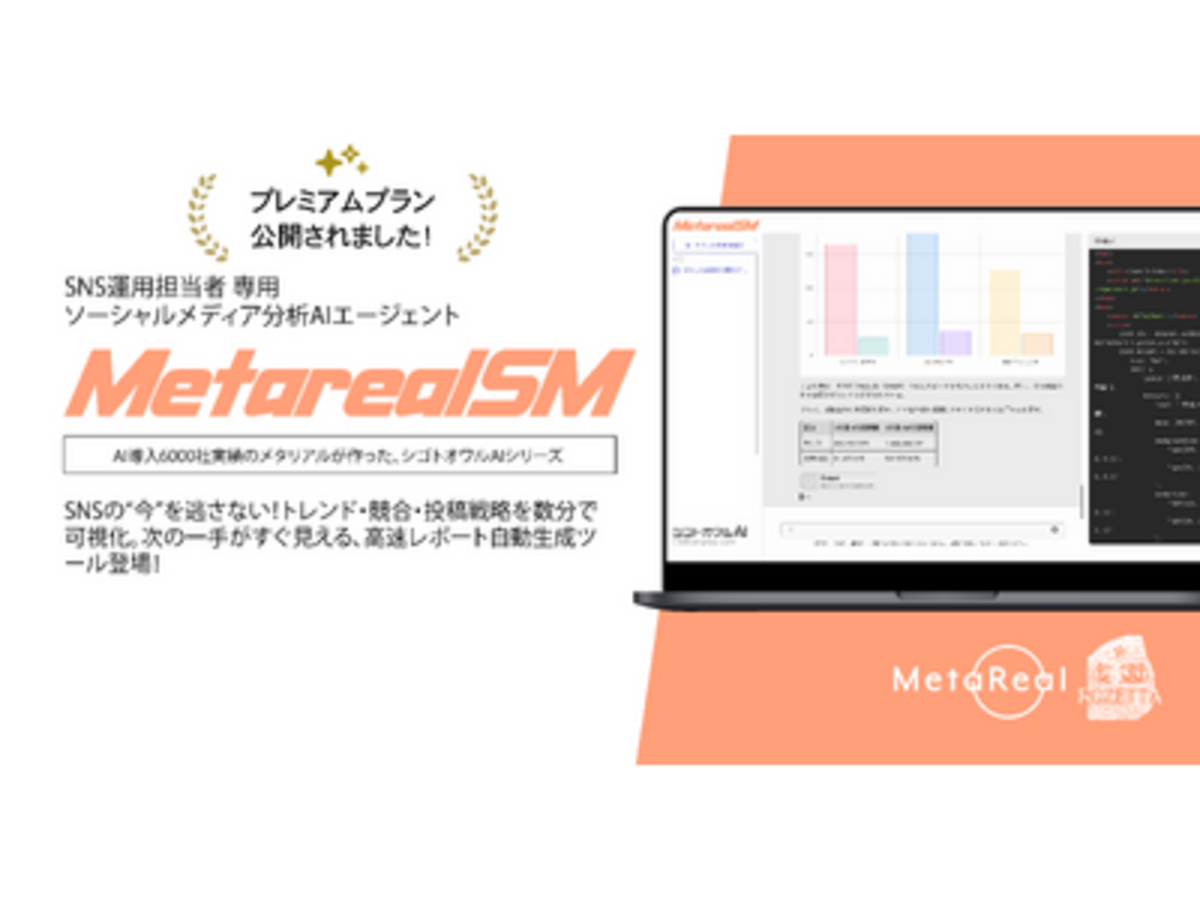企業とカスタマーの架け橋となる「ソーシャルエディター」という役割
海外では、ソーシャルメディアを通じて読者とコミュニケーションをとり、「ソーシャルエンゲージメントの達人」と呼ばれる「ソーシャルエディター」という職種が生まれています。
国内でも、Facebookの月間アクティブユーザー数は2,800万人、Twitterの月間アクティブユーザー数は4,000万人、LINEの月間アクティブユーザー数は7,000万人など、人々と交流していく上でソーシャルメディアを活用することは欠かせません。
ソーシャルメディアで情報発信する上で必要になるのが「コンテンツ」。どうコンテンツを作ってマーケティングを行い、ソーシャルメディア上でエンゲージメントを高めていくのかが企業にとって重要なテーマとなっています。
今回、ライター、エディター、ソーシャルエディターとして活動した後、コンテンツマーケティングに従事した山崎礼さんのこれまでの活動に触れながら、コンテンツを通じて情報発信する上での大事な視点について紹介していきます。
山崎礼さんプロフィール

Amazon Japan エディター。WIREDでライター、Medium Japanではエディターとして参加。転職後、AKQAでソーシャルエディターとしてNIKE担当。Workdayでコンテンツマーケティングに従事後、現職。
ソーシャルエディターによる「コンテンツ作り」とは?

山崎さんは、テクノロジーメディア「WIRED」の日本版でライターとして活動する傍ら、コンテンツプラットフォーム「Medium Japan」のエディターとしてプラットフォームの拡大に尽力されていました。
「日本人は自分で書くよりも読む方を好むのか、残念なことに初期のMedium Japanでも同様で書き手はそれ程多くいませんでした。しかし、Mediumは書き手のためのプラットフォームであるため、書き手にとって居心地の良い"場"、すなわち"エンゲージメント"の高まるプラットフォームとは何かを意識してコンテンツ作りを繰り返しました(山崎さん)」
コンテンツ作りを繰り返し行っていく中で、山崎さんが気付いたのが「物語」の大切さでした。
「人は"人の物語"に心動かされます。1つひとつの記事の数字を眺めるうちにそのことに気付かされます。例えば、あるスタートアップのファウンダーのストーリーでも、経営のトピックだけではなく、ヒューマンストーリーを交えた記事の反応がいい。View数だけではなくエンゲージメントも数字として意識するうちに、徐々にユーザーの皆さんが自分自身のストーリーやTipsを投稿するようになりました(山崎さん)」
山崎さんは、1つひとつの記事の数字を分析し、人々が共感し、自分も投稿したくなるストーリーとは何か仮説を立てて、それに該当するUS記事をローカライズし、Medium Japanの日本における拡大を模索したそうです。
その後、山崎さんはクリエイティブエージェンシーのAKQAでソーシャルエディターとしてNIKEを担当し、新製品のソーシャルポスト、アナリティクスの業務を担当します。
「ソーシャルエディターの仕事は、文章を書く仕事が40%。残りの60%はツールを使った投稿のセッティングと、数の分析です。投稿ごとのクリック数や購買率を見て、投稿によって数字に違いが出ていることに対して仮説を立て、検証を重ねていきました(山崎さん)」
HR Tech企業Workdayからコンテンツマーケティングのポジションのオファーを受けて移籍したのも、数字からコンテンツ作成をする面白さに惹かれたからだそうです。
山崎さんはコンテンツマーケターの仕事について、*「ブログ記事やFacebookポスト等を通じて、従来の広告ではリーチできなかった潜在層に企業の信念やミッションを伝えて、ファンを増やすのがミッション」*と語ります。
カスタマーをファンに変える仕事

ソーシャルエディターとして活動するにあたり、ソーシャルメディアに投稿するテキストをどう作成していたのでしょうか。山崎さんは*「言葉のプライオリティーが大事なんです」*と語ります。
「ソーシャルポストを作成する際、私は一番伝えたい単語をできるだけ前に持ってくるようにしています。始めたばかりの頃は、ストーリーを作ろうとするあまり、時に言葉が後ろに押されてしまった。それでは、ユーザーに届けたいはずの大切な言葉の力が弱まってしまいます。一番大切な言葉は何かを考え、その言葉のイメージを大切にする。そして、そこからどう文章を続けるのかが我々の腕の見せ所です(山崎さん)」
では、大事な言葉はどう選ぶのか。そのためには、プロダクトや会社自体への理解を深めること、そしてプロダクトや会社のファンへの理解を深めることが重要だと山崎さんは説明します。
会社の「中の人」として外部に向けて伝えていくのと、「外の人」として関わるのでは当然軸が変化します。
「ライターの仕事をしていた時は、自分の目線で書いていました。メディアの立ち位置を理解した上で客観的な立場で書くわけです。一方、企業の中でエディターとして活動する場合、その企業に誰よりも強い関心を持って惹かれなければいい仕事はできません。ほぼ一心同体になるようなつもりでいましたね(山崎さん)」
企業に寄り添い、その企業への理解を深めた上で、カスタマーにも寄り添うわけです。
「ソーシャルエディターは、カスタマーが何を知りたいのかを推測しなければなりません。それを教わった出来事があります。ある日、AKQAで"スニーカーヘッズ"と呼ばれるスニーカーのコアファンユーザーの取材に行った時のことです。そこで、熱心に商品への思い入れや、ストーリーを語るファンとふれあう機会がありました。自分のスニーカーへの情熱と愛を滔々と語る様子を直接目の当たりにしたことで初めて、コアなファンの感覚を知ることができ、自分もファンになることができたのです(山崎さん)」
熱心なファンの気持ちに寄り添うこと、情報を調べる際に企業や商品の良いところを着目し、ファンになるつもりで見ていくこと。そうすることで、ファンの視点を獲得していきます。
エモーショナルな側面を大事にする一方で、数字的に物事を見ていくことももちろん必要です。限られたコアなファンだけではなく、より多くのファンの動向を知るためには数字をチェックしなければなりません。
*「企業に入って数字を追いかけ始めると、数字しか見えなくなってしまいます。誰のために発信しているのか、というファンの人たちの顔を忘れないことが大切なんです」*−−そう山崎さんは語ります。
市場を牽引 "ソートリーダーシップ(Thought Leadership)"という考え方
「Workdayで、コンテンツマーケティングをしていた時は、"ソートリーダーシップ(Thought Leadership)"に基づいて、会社のミッションや先進性を発信し、潜在的なユーザーに広めていきました(山崎さん)」
山崎さんが語るソートリーダーシップとは、特定のセグメントや分野において将来を先取りしたテーマやソリューションを示して、オピニオンリーダーとして業界を牽引していく活動のことを指します。
市場の伸びが鈍化しているケースや、新たな市場を切り開く必要がある場合に、このソートリーダーシップを戦略として採用するケースがあります。米国の企業ではこの考え方でコンテンツマーケティングを行うところが少なくないようです。
「Workdayでは、CEO、CFO、COOなど、経営に関わる"C-suite"と呼ばれる人々に向けて情報を発信していきました。それ以外の人たちには、プロダクトの最終的な購入権限がない場合が多いからです。ターゲットをきっちりと絞って、そこに刺さるコンテンツをつくる。ただ、ターゲットと言っても流石にC-suiteなので、その人達を説得するためにはコンテンツも作り込まなければないりません。そのため、コンテンツを作る際の文体や執筆ルールなどのガイドラインや海外のカウンターパートとのディスカッションももちろんありました(山崎さん)」
市場そのものを牽引するような情報発信を行い、潜在的なユーザーにリーチさせる、ターゲットを絞り、そこに届くようにコンテンツのガイドラインを作成する。コンテンツマーケティングを行う上でのヒントとなりそうです。
試行錯誤しながら止めないこと
山崎さんはこれまでの経験を振り返って、ソーシャルエディターやコンテンツマーケターにとって大切な考え方を次のように語ってくれました。
「人や企業に届くコンテンツの作りかたに正解やルールはない、だから試行錯誤しながら、地道な繰り返しを続けることが大事。自分で確かめていくしかありません(山崎さん)」
インハウスエディターもそうですが、ソーシャルエディターやコンテンツマーケターも、まだまだ実践者が少なく、情報が蓄積されていない領域です。そこで成果を出していくために必要なのは、山崎さんが言うとおり、試行錯誤しながら、継続することなのかもしれません。
山崎さんの経験が、1人のプレイヤーとして企業の情報発信に携わる人にとってのヒントになれば幸いです。
参考:
いきなり編集長に任命されたらどうする?メディア運営者が持つべきマインドセットを「LITALICO発達ナビ」編集長に聞く|ferret
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- オファー
- オファーとは、一般的には条件を提案する行為をさします。さらに、ビジネス上では、ある条件を受け入れると、その見返りとして何かが得られる、優遇されるなどの商行為をさすこともあります。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他