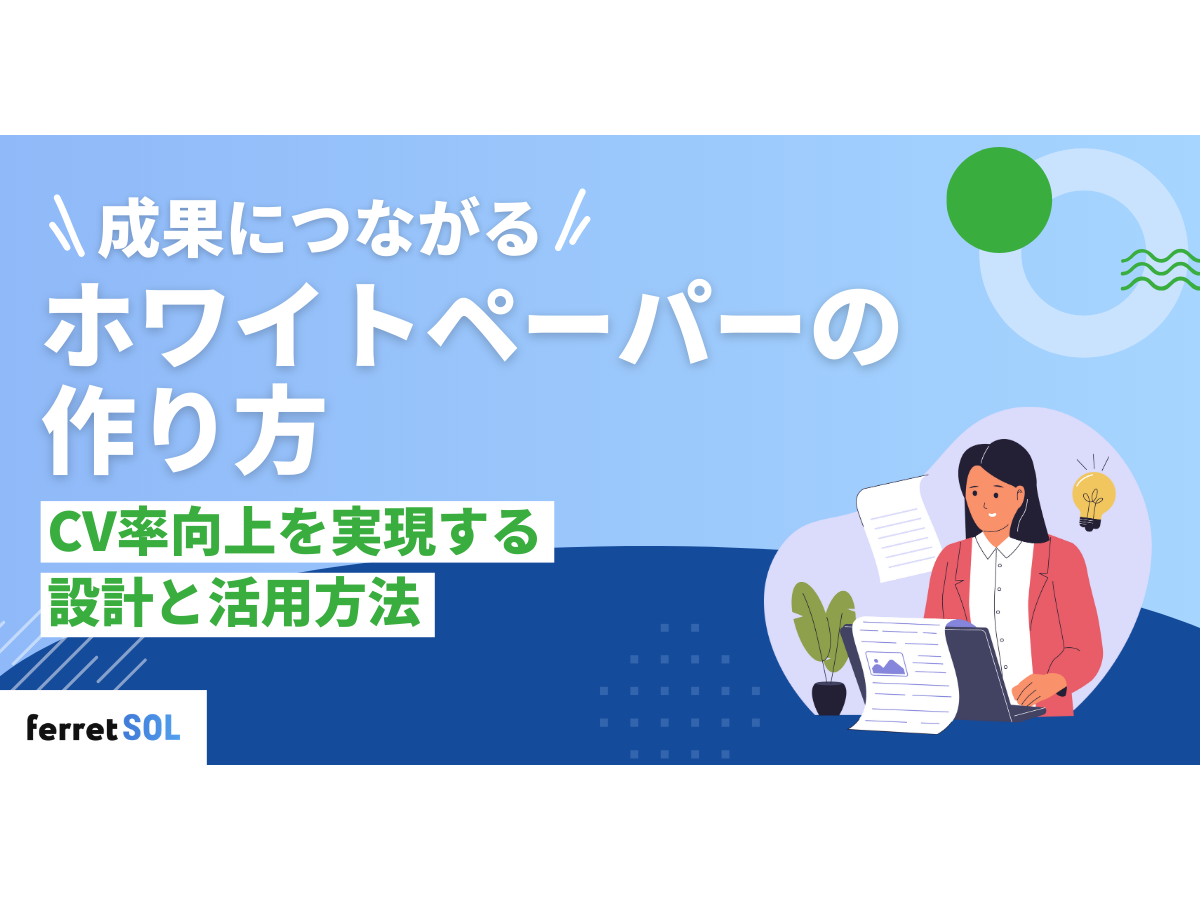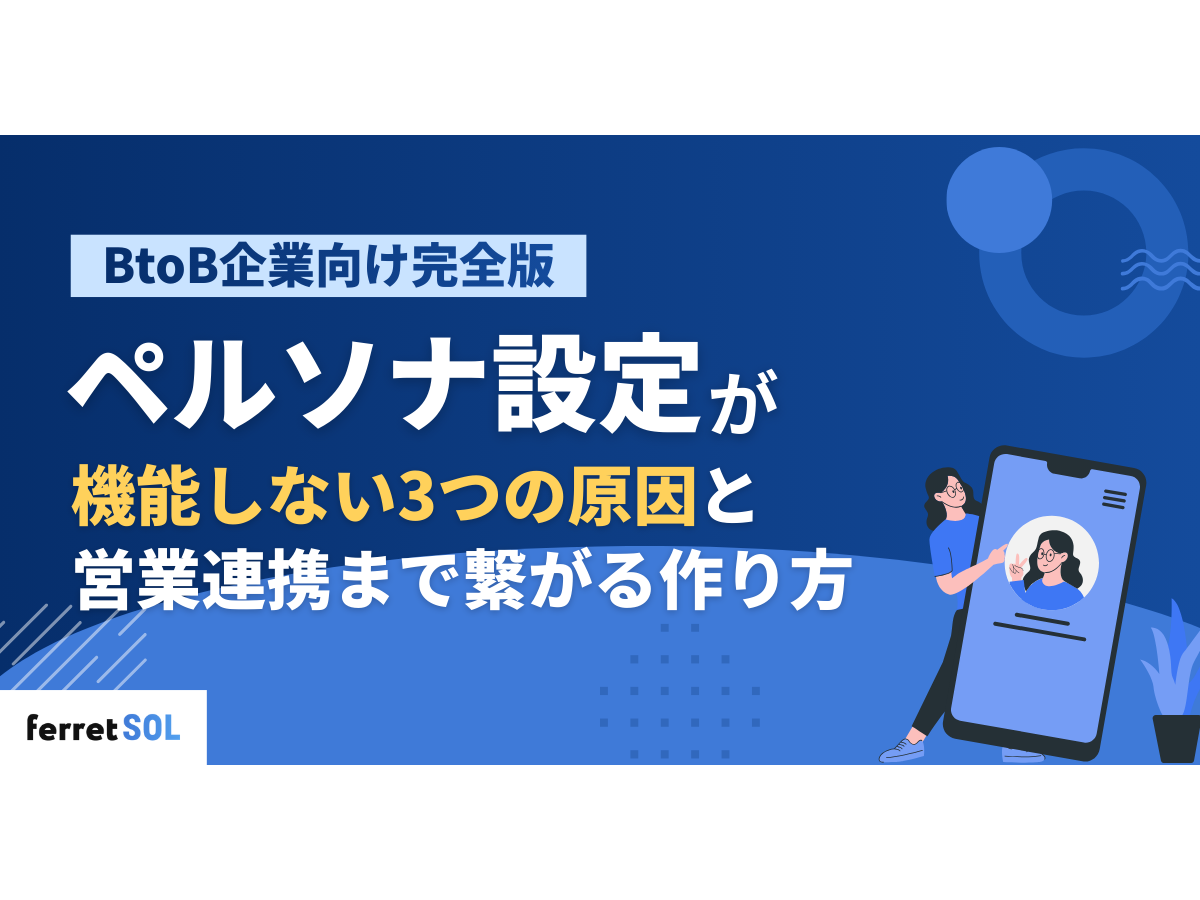【BtoB向け】サービス紹介資料の作り方を解説!成果につながる改善ポイントも紹介
「サービス紹介資料とは、どのようなものですか?」
「サービス紹介資料は、どのように作成したらいいですか?」
このように、サービス紹介資料に関して疑問を持っている方は少なくないでしょう。
近年はデジタル技術の発展により、買い手が自らの手で商品について知り、意思決定を進めることが容易になりました。そのため、サービス紹介資料を用意することの重要性が高まっています。
そこで、サービス紹介資料を作成する上での基本的な考え方やしておくべき準備、サービス紹介資料に必要な8つの要素、効果的な作り方などについて詳しく説明します。
サービス紹介資料の作成を考えている方は、「サービス紹介資料の作り方」を活用してみてはどうでしょうか。こちらでは、盛り込むべき8つの要素・見込み顧客への展開要素などを解説しているため、活用してみてください。

webからのリード獲得に欠かせない「サービス紹介資料」の作り方
本書では、見込み顧客に自ら検討を進めてもらうために欠かせない、サービス紹介資料の「重要な理由・盛り込むべき8つの要素・見込み顧客への展開方法」について解説しております。
目次
- サービス紹介資料とは?
- 効果的なサービス紹介資料を作るための基本的な考え方
- サービス紹介資料の作り方を3ステップで解説
- サービス紹介資料に必要な8つの要素
- サービス紹介資料の効果的な作り方・デザインのコツ
- サービス紹介資料の改善ポイント
- 英語版サービス紹介資料の作り方
- サービス紹介資料を作成してみよう
サービス紹介資料とは?
サービス紹介資料とは、見込み顧客が営業担当者の説明を介さずサービスの比較検討を進められるよう、サービスの詳細や提供価値を記述したコンテンツ、いわゆるパンフレット・カタログのことを指します。
サービス紹介資料を作成する目的は、ターゲット層への理解度を深耕し、意思決定を促すことです。顧客の多くはWebを活用して面談前に事前に資料を集め、比較検討しています。従って、顧客の課題解決につながると思わせる内容であればあるほど、サービス紹介資料の効果が高くなるでしょう。
近年ではWeb上に情報が溢れているため、営業担当が営業を行う前に顧客が十分な情報・知識を備えているケースが多く見受けられます。
Web上にサービス紹介資料を用意しておくことで、比較・検討段階にある見込み顧客に適切な情報を提供でき、商談時の意思疎通を図りやすくなります。顧客が同じ方向を向いているので、クロージングの確率が上がるのです。
営業資料との違い
営業資料は、導入するサービスを1つに絞り、意思決定の後押しをする見込み顧客のために作られます。相手の課題・企業規模・予算などによって、提案メニューや紹介する事例などをカスタマイズするのが特徴です。
それに対してサービス紹介資料は、営業資料の一歩手前であるサービスの候補を洗い出し、比較・検討段階にある見込み顧客のために作られた資料です。顧客が比較検討に必要とする情報を網羅的に・簡潔にまとめる文章力・表現力が求められます。
効果的なサービス紹介資料を作るための基本的な考え方
続いて、サービス紹介資料を作成する際の基本となる考え方を解説します。
営業担当との接触前から意思決定は始まっている
見込み顧客に対して十分な情報を提供できなければ、商品やサービスを検討する選択肢にすら入りません。サービス紹介資料は見込み顧客への比較・検討材料を提供し、差別化のポイントなどを訴求できます。
顧客は課題解決に向けた情報を常に収集している
顧客は課題解決に向けた情報を収集していることを、常に念頭に置いておきましょう。BtoB向けの商品の情報源として、多くのクライアントはカタログやパンフレットを活用しています。つまり、サービス紹介資料による適切な情報提供が、担当者の意思決定に影響を及ぼすということです。
今までは商談時に初めて見せていた情報を、それより前の段階からサービス紹介資料としてオープンにし、見込み顧客がアクセスできるようにしておけばリード獲得が見込めます。
こちらの「BtoBマーケティング実践ガイド」では、マーケティングの戦略設計・ノウハウを解説しています。BtoBマーケティングを行う際の参考になるため、活用してみてください。
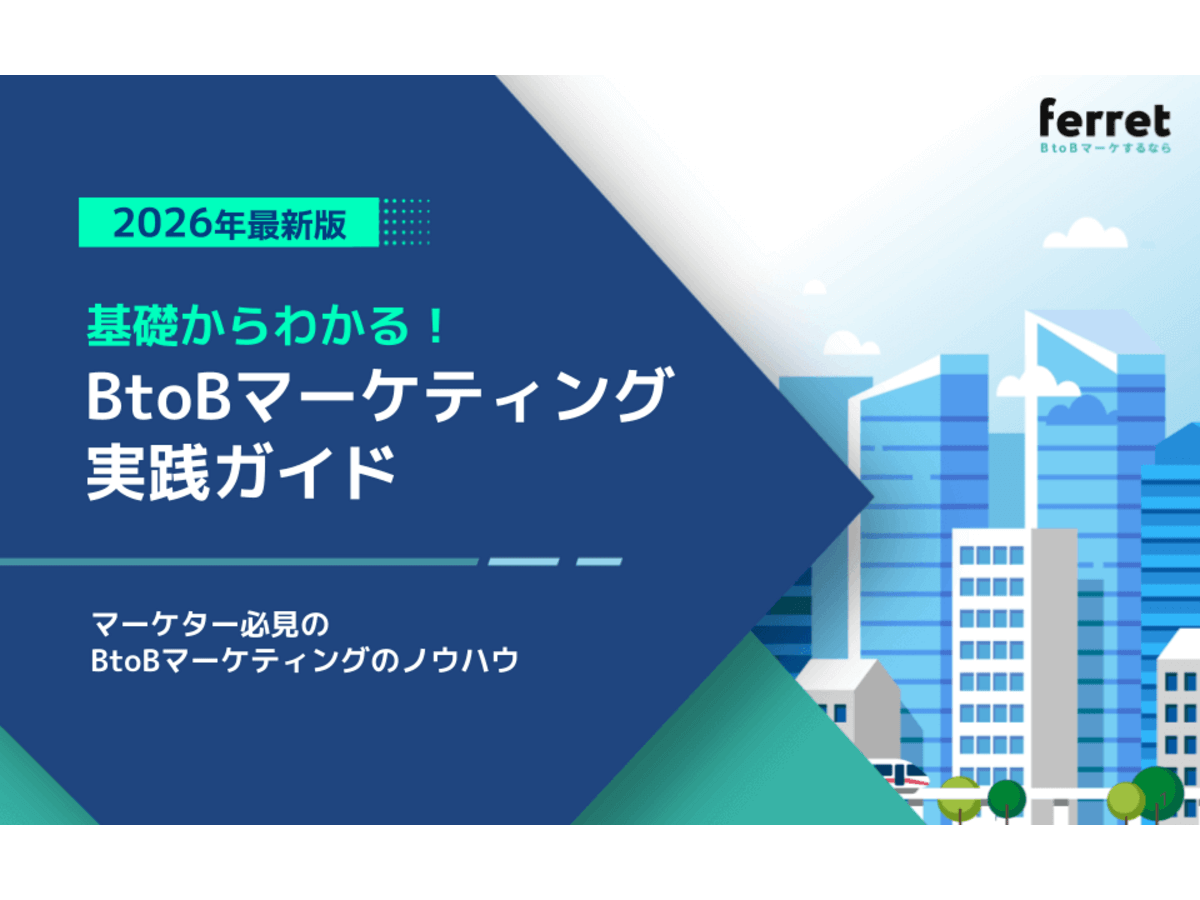
基礎からわかる BtoBマーケティング実践ガイド【2026年最新版】
本書は、これから“BtoBマーケティング”を本格的に行いたいという方向けに、マーケティングの戦略設計や各種施策のノウハウを網羅した資料です。
サービス紹介資料の作り方を3ステップで解説

ここでは、サービス紹介資料を作る前にしておくべき準備について解説します。
ターゲットを明確にする
まずは、ターゲットを明確にしましょう。ターゲットを明確にすることで、見込み顧客が置かれている状況や抱えている課題に合った、魅力的な資料を作成できます。
例えば、BtoBサービスの紹介資料を作る際は、以下のような項目をもとにターゲットを決めるとよいでしょう。
- 業種
- 企業規模
- 抱えている課題
- 意思決定者や担当者の属性(年齢、部署、役職など)
上記の項目は、自社が保有している顧客情報などをもとに検討するのがおすすめです。
伝えたいことを明確にする
サービス紹介資料を作成する前には、伝えたいことを明確にしておきましょう。伝えたいことを明確にすることで、冗長な情報を省きつつ、必要な情報を簡潔にまとめられます。
競合他社との差別化を図りつつ自社サービスに興味を持ってもらうには、具体的なサービス内容や特徴、自社サービスならではの強みなどをアピールするのがよいでしょう。
また、「問い合わせをして欲しい」「お試し版を使ってみて欲しい」など、見込み顧客にしてもらいたい具体的なアクションを伝えるのも効果的です。
実際にスライドを作成する
必要な情報がまとめられたら、実際にスライドを作成していきましょう。サービス紹介資料を構成する際のスライドは、できるだけ簡潔にまとめることがポイントです。スライドの情報量が多いと、要点が伝わりにくくなるため、注意が必要です。
また、図・表・イラストなどを利用することで、より分かりやすくなるでしょう。
▼ サービス資料の制作をプロに依頼したい方はこちら
サービス紹介資料に必要な8つの要素

サービス紹介資料には、以下8つの要素が必要です。
- 表紙と目次
- サービスの概要説明
- 機能・サービスの詳細
- 事例
- 料金・プラン
- よくある質問と回答
- 会社概要
- CTA(Call to Action)
それぞれ詳しく解説していきます。
表紙と目次

表紙には多くの情報を盛り込まず、できるだけシンプルな構成にしましょう。最初に目にする部分の情報量が多すぎると、読む前に気持ちが下がってしまいます。
表紙には「サービス紹介資料であること」と「どんなサービスなのか」を端的に表したコピーを記述します。加えて、サービスや会社を連想できるイメージ・ロゴがあれば、載せる程度で留めておきましょう。
また、トップには目次も必要です。電子データの場合は、各目次をクリックするとそのページにジャンプできるように、リンクを埋め込んでおくとより読みやすくなります。
サービスの概要説明

いきなりサービスの詳細を羅列するのではなく、まずは概要を説明します。ツールや有形商材であれば、搭載されている機能をイラストを用いて一覧で紹介すると、読み手の理解を進められます。
コンサルティングなどの無形商材であれば、具体的にどのようなアドバイス・施策実行を行うかを箇条書きでまとめましょう。
また、自社の商品をおすすめする理由について述べる際は、少子高齢化やテレワークの加速といった社会情勢を踏まえた背景を記述してみるのも1つの方法です。サービスの必要性を自分ごととして感じてもらえると、自ずと興味を高められます。
機能・サービスの詳細

機能・サービスの詳しい特徴を、イラスト・写真・表などを用いて分かりやすく説明しましょう。その際「〜することができる」といった顧客が得られるメリットを中心に記載する場合もあれば、「〜という技術が使われている」といったプロダクトの詳細を中心に記載する場合もあります。
多機能な商品の場合、機能とメリットの対応関係を示すと商品の良さが伝わりやすくなります。また、コンサルティングを伴うサービスであれば、その専門領域の有資格者がどれだけいるか記載するのもよいでしょう。
さらに、ソフトウェアであれば外部ツールとの連携・対応ブラウザ・対応デバイスなども記載しておくと親切です。
事例

商品のアピール材料として、実際に商品やサービスを使用している会社の「事例」も欠かせません。事例を記載することで「この商品を買う必要があるのか?」「この会社から商品を買うべきか?」の両方の疑問を解消できます。
特に有名企業の実績は意思決定の後押しになりやすいので、もし実績がある場合は積極的に記載しましょう。
さらに、特定会社の導入後の成果・プロセスを記述すれば「この商品を買う必要があるのか?」への答えとなります。
また「この会社から商品を買うべきか?」という疑問の解決方法は、掲載されたメディア・導入企業のロゴをまとめて掲載するとよいでしょう。サービスとしての実績を示せば、確かな実力の裏付けとして機能します。
料金・プラン

料金・プランは、サービス紹介資料では出し惜しみをせず、Webサイト以上に詳細を記載するようにしましょう。「何をすれば、どれだけ料金が発生するか」が分かるようになっていることが理想です。
提案するプランのカスタマイズができ受注単価が変わる場合は、まず需要が高い組み合わせを例とした「参考価格」を掲載するのがおすすめです。
複数のプランがある場合は、比較しやすいようプランごとにできること・できないことの違いを明記した表を作成するとよいでしょう。
また、クラウドツールを使用する場合は、決済手段が明記してあると親切です。加えて、価格表記の税込・税抜も分かるようにしておきましょう。
よくある質問と回答
提供するサービスのアピールポイントと弱点部分を、「よくある質問と回答」で提示します。そうすることで、包み隠さず情報を教えてくれる会社であると、ターゲットからの信頼を高めることができます。
よくある質問と回答をどのような内容にするかは、見込み顧客の生の声を知る営業担当に聞いてみましょう。
また、ここまでの項目で紹介しきれなかったサービスの魅力を、質問回答のなかで補うという使い方もおすすめです。商品でできないことや弱みに関しては、ネガティブな印象にならないような表現の工夫が必要になります。
会社概要

商品を提供している会社の情報を、見込み顧客は意外と見ているものです。
商品自体に魅力を持ってもらえるか否かと、「本当にこの会社に発注してよいのか」は別の話であり、資本力・ミッションなどをもとに検討する慎重な担当者・決裁者も少なくありません。企業としての信頼を得るために載せておきたい会社情報は、以下の通りです。
・商号
・代表者名
・事業内容
・資本金
・従業員数
・設立年
・企業のミッション
・拠点
・所属する業界団体
・コーポレートサイトのURL
・会社のイメージを表す写真
CTA(Call to Action)

サービスに興味を持ってもらえた方に、次のアクションを促しましょう。CTAの代表例は「お問い合わせ」のためのページと電話番号です。これ以外にも複数の選択肢を提示することで、見込みのあるユーザーのアクションを漏れなくCVにつなげられます。
誘導先には、サービスサイトのトップページやブログなどが当たります。また事業によっては、自動見積もりや無料体験、セミナー (ウェビナー)なども有効なCTAとなり得るので、検討してみてください。
こちらの「BtoBマーケティング実践ガイド」では、マーケティングの戦略設計・ノウハウを解説しています。BtoBマーケティングを行う際の参考になるため、活用してみてください。
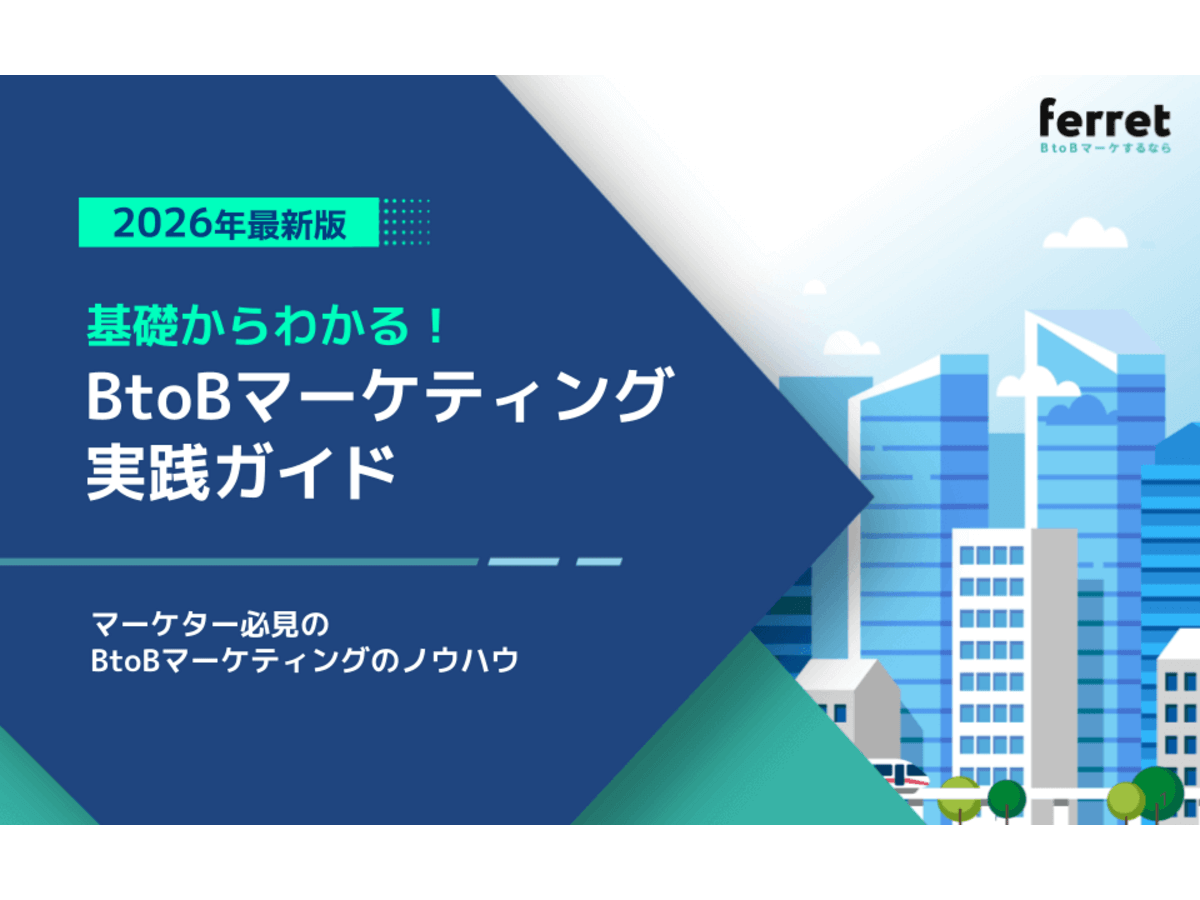
基礎からわかる BtoBマーケティング実践ガイド【2026年最新版】
本書は、これから“BtoBマーケティング”を本格的に行いたいという方向けに、マーケティングの戦略設計や各種施策のノウハウを網羅した資料です。
サービス紹介資料の効果的な作り方・デザインのコツ

ここでは、効果的なサービス紹介資料を作るために注意すべき点を8つ紹介します。資料を作る際は、これらのポイントを押さえられているかをチェックしながら作成しましょう。
1スライド1メッセージを心掛ける
サービス紹介資料を作る際は、1スライド1メッセージを意識しましょう。
1枚のスライドに多くの情報を詰め込むと、読み手は情報を理解することが難しくなり、サービスの魅力が十分に伝わらなくなる可能性があります。
例えば、1つのページに「価格が安いこと」と「アフターサービスが充実していること」を記載するのではなく、それぞれ個別ページを用意して説明するようにしましょう。
具体的な数字を入れる
サービス紹介資料に実例や効果などを盛り込む場合は、具体的な数字を入れて記載しましょう。数字を入れることで、情報に具体性や説得力を持たせられます。
例えば、事例を紹介する際は「当社サービスにより売上がアップしました」だけでは抽象的になってしまうため、「導入によって売上が20%アップしました」などの表現にしましょう。
また数字を使う際は、部分的にフォントのサイズを上げることで、読み手に対して瞬時にインパクトを与えられます。
フォントはメイリオを使用する
サービス紹介資料内のフォントは、基本的にメイリオを使用しましょう。
メイリオは可読性が高いとされているため、使用することで資料の理解度が上がり、情報伝達の効果が高まることが期待できます。
メイリオを使用する場合は、フォントサイズは18pt〜24pt以上とし、強調したい情報には太字を使って目立たせるなどの工夫をしましょう。
配置を左揃えにする
サービス紹介資料を記載する際は、テキストなどの配置を左揃えにすることも重要です。
なぜなら、人の視線は画面の左上から右下に向かって進むからです。目線の動きを意識した資料作りをすることで、情報がより伝わりやすくなります。
なお、要素を中央揃えにしてしまうと文章の改行位置が統一されず読みにくくなるため注意しましょう。
イラストやグラフを入れる

サービス紹介資料には、テキストだけでなくイラストやグラフも入れましょう。テキストの量が多いと、読み手はすべての文字を読まないと内容を理解できないため、負担をかけてしまいます。
視覚情報は文字よりも情報が伝わりやすいため、比較データの表やプロセスフローを表した図なども活用しながら、サービスの魅力をひと目で理解してもらえるような資料にしましょう。
使う色を絞る
サービス紹介の資料内で使う色は、多くなりすぎないようにしましょう。色が多すぎると、視点が散ってしまいどこに注目したらいいのか分かりにくくなってしまいます。
一般的には、全体で4色以内に収め、1枚のスライドでは2色にするのがよいとされています。そのため、配色を決める際は以下の4つで構成しましょう。
- メインカラー
- サブカラー
- 背景色
- 強調色
余白をとる
サービス紹介資料を作る際は、全体のバランスを見ながら余白をとることも重要です。余白のない資料は圧迫感があり、分かりにくい印象を与えてしまいます。
そのため、スライドいっぱいにテキストや写真などを詰めるのではなく、スライドの端にはテキスト2〜3文字分の余白を空けましょう。
また、余白はスライドのページごとに個別で設定するのではなく、全ページに対して共通で同じ余白を持たせるのがおすすめです。
こちらの「PowerPoint作成 伝わるデザインのコツ」では、パワーポイント・Googleスライドでのデザインを見やすくするコツを紹介しています。パワーポイントを作成する際の参考になるため、活用してみてください。
▼ パワポ資料デザインのコツはこちら

【パワーポイント作成】伝わるデザインのコツ
ほんの一手間で驚くほど見やすく変わる!パワーポイントやGoogleスライドなど資料のデザインを見やすく仕上げるコツを解説します。
サービス紹介資料の改善ポイント

サービス紹介資料の改善ポイントには、大きく分けて2つあります。
- 商品・サービス説明のシナリオ・構成を見直す
- デザインを見直す
1つずつ詳しくみていきましょう。
商品・サービス説明のシナリオ・構成を見直す
商品・サービス説明のシナリオ・構成を見直していきます。サービス紹介資料のスライドでは、複数に分けて各スライドで伝えたいことや、順番を整理していきましょう。
実際の商談で、話の流れや時間配分が期待通りにいかなかった場合も出てくる可能性があります。
そのため、各セクションごとの解説ボリュームや説明の流れの見直しが必要です。
見直しが完了したら、社内の方にもフィードバックを求めましょう。
顧客視点を重視しすぎると、顧客に気付きを提供することが少なくなる可能性があります。顧客が求めていることと、自社が伝えたいことをバランスよく作っていくよう心掛けていくといいでしょう。
デザインを見直す
サービス紹介資料のデザインは、企業・サービスへの印象を大きく左右するため、見直すことが大切になってきます。自社の商品・サービスにいい印象を持ってもらうためにも、資料のデザイン・フォントなどの統一感が必要です。
また、資料の印象や分かりやすさによって、企業・サービスへの印象が変わってきます。そのため、プロのデザイナーにデザインを依頼するのがおすすめです。
英語版サービス紹介資料の作り方

サービス紹介資料の作り方を紹介してきました。ここでは、英語版のサービス紹介資料の作り方を紹介していきます。
英語版のサービス紹介資料では、これまでとは異なった視点で作成していくことが必要になります。英語版ならではの、注意点もあるため、1つずつ詳しくみていきましょう。
英語版サービス紹介資料の作り方のコツ
英語版のサービス紹介資料の作り方のコツには、大きく分けて3つあります。
- ビジネス英語に注意する
- 必要なキーワードだけ使用する
- ビジュアルで訴求する
1つずつ詳しくみていきましょう。
ビジネス英語に注意する
日本語では、日常やビジネスの場で使う言葉は違ってきます。英語でも同じように、サービス紹介資料を作成する際は、ビジネスシーンで使われる英語を使用するよう注意が必要です。
ビジネスシーンで使われる場合のものに置き換えることで、プロフェッショナルな資料を作成できます。インターネットや辞書を利用して、ビジネスシーンに合った表現へと置き換えるようにしましょう。
必要なキーワードだけ使用する
スライドを見やすく、分かりやすいものにするためには、必要なキーワードだけを使用するといいでしょう。日本語をそのまま英訳すると、1文が長くなり理解しにくくなってしまいます。
スライドでは、長い文章や過度な情報は見にくくなります。そのため、シンプルな言葉を使い、必要なキーワードだけを使用するようにしましょう。
ビジュアルで訴求する
サービス紹介資料を作成する際は、一目で分かりやすいように、グラフ・チャートを利用するといいでしょう。文章だけのスライドでは、見にくくなり、一目で言いたいことが伝わりにくいです。
そのため、より伝わりやすい資料にするためには、文章を補強するグラフ・チャートを利用しましょう。
また、箇条書きを使ったり、流れを意識した書き方にしたりするだけで、理解度が上がっていきます。
英語版サービス紹介資料の作成方法

英語版のサービス紹介資料を作成するコツを解説してきました。次は、実際に作成していきましょう。
英語版のサービス紹介資料の作成方法は、大きく分けて2つあります。
- 自分で調べながら作成する
- 外注してプロに依頼する
1つずつ詳しくみていきましょう。
自分で調べながら作成する
サービス紹介資料は、自分で調べながら作成することも可能です。普段、英語に慣れ親しんでいない方にとっては、難しく感じるでしょう。しかし、無料で利用できる翻訳ツールを活用することで、自分でも作成できます。
また、ベースを自分で作成した後に、ネイティブ・英語が得意な人に確認してもらうことで、完成度を高めていけます。
外注してプロに依頼する
自分でサービス紹介資料の作成が難しい場合は、外注してプロに依頼する方法もあります。依頼方法も様々で、資料作成をすべて任せる方法や、英訳してもらう部分だけを依頼するやり方があり、柔軟に対応できます。
自分で作成する場合に比べると、コストがかかってしまうデメリットがあります。しかし、失敗できない商談・プレゼン資料の作成をするときだけ、外注するようにして、場面と必要性に応じて活用していくといいでしょう。
サービス紹介資料を作成してみよう

サービス紹介資料は、自社の商品・サービスの特徴や狙うべきターゲットの特徴に合わせて作成すると効果的です。
自社で作成する場合は、今回の記事で紹介した観点を元にサービス紹介資料を作成してみてください。
また、自社の目標をより効率的に達成する方法としては、プロに依頼することも検討することをおすすめします。
ferretを運営する株式会社ベーシックでは制作代行はもちろん、サービス紹介資料の構成作成から自社制作する際のレギュレーション整備といった支援も行っておりますので、サービス資料作成にお困りの方はぜひご相談ください。
▼ サービス資料の制作をプロに依頼したい方はこちら
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- 単価
- 商品1つ、あるサービス1回あたり、それらの最低単位での商品やサービスの値段のことを単価といいます。「このカフェではコーヒー一杯の単価を350円に設定しています」などと使います。現在、一般的には消費税を含めた税込み単価を表示しているお店も少なくありません。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- トップページ
- インターネットのWebサイトの入り口にあたるページのことをトップページといいます。 一般的には、階層構造を持つWebサイトの最上位のWebページをさします。サイト全体の顔としての役割も果たすため、デザインなどで印象を残すことも考えたサイト作りも有効となります。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- セミナー
- セミナーとは、少人数を対象とする講習会のことです。講師からの一方的な説明だけで終わるのではなく、質疑応答が行われるなど講師と受講者のやり取りがある場合が多いようです。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- フォント
- フォントとは、同一の特徴を持った文字の形状を一揃いでデザインしたものです。
- フォント
- フォントとは、同一の特徴を持った文字の形状を一揃いでデザインしたものです。
- フォント
- フォントとは、同一の特徴を持った文字の形状を一揃いでデザインしたものです。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- フォント
- フォントとは、同一の特徴を持った文字の形状を一揃いでデザインしたものです。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他