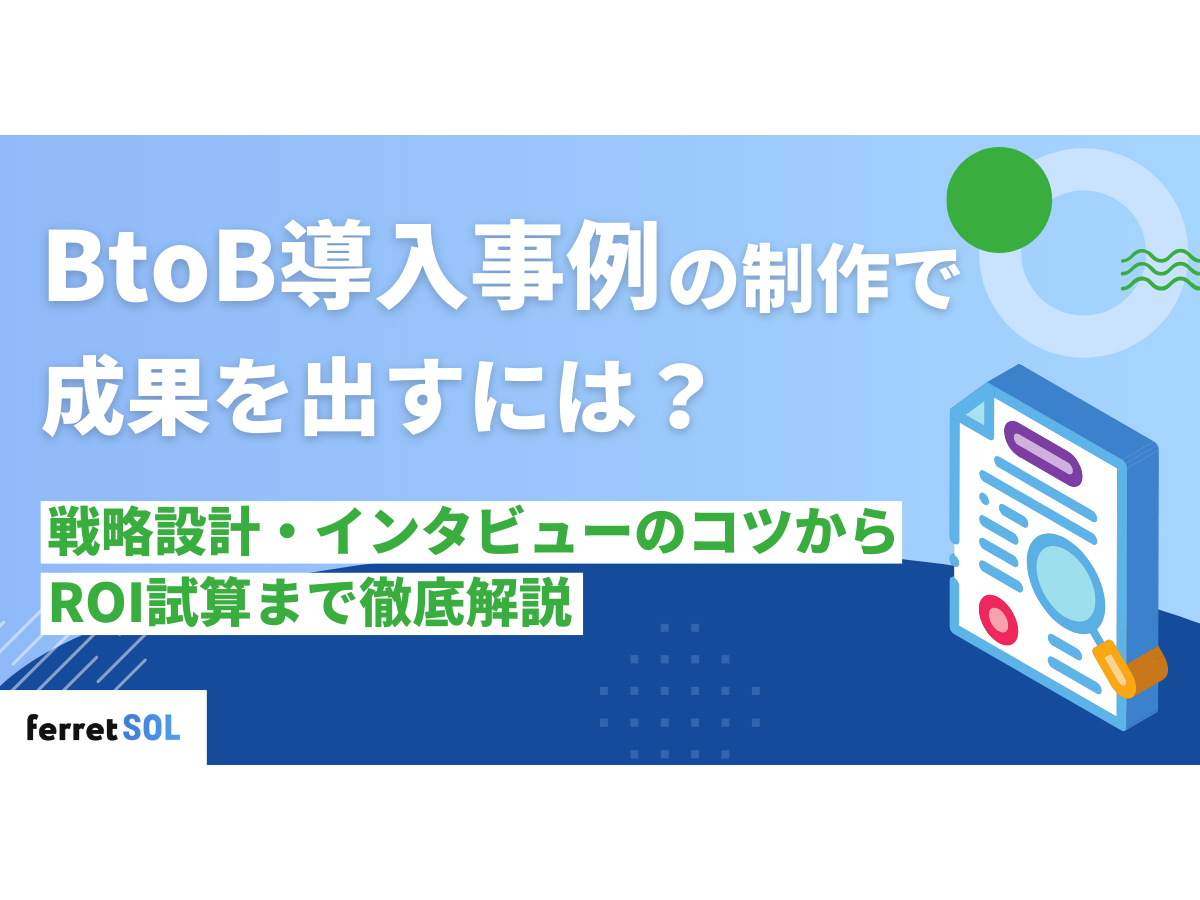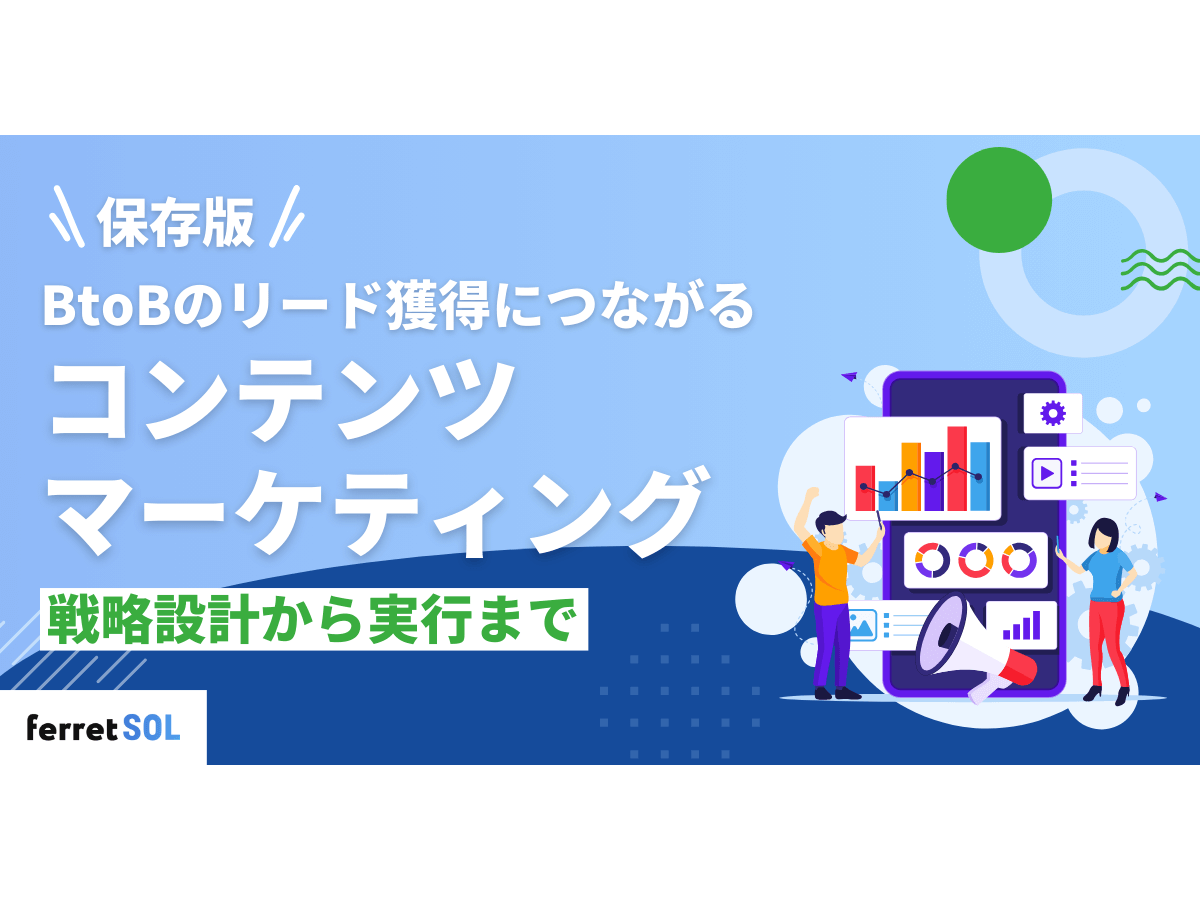【インタビュー】旅行ガイドブック『ことりっぷ』がコンテンツマーケティングで築いたブランド“◯◯らしさ”とは
今回は、人気女性旅行ガイドブック『ことりっぷ』のWeb版・アプリ版を立ち上げた平山氏にWeb媒体へ展開した経緯とコンテンツマーケティングにも通ずるコンテンツ制作におけるお話を伺いしました。
平山氏のプロフィール

平山 高敏
インターネット広告代理店の企画営業を経て、2011年に昭文社へ入社。2013年のことりっぷWEBの開設時からコンテンツ企画、マーケティング戦略、SNS戦略、2B案件支援などWeb事業全般を統括。2015年にはユーザー参加型のアプリの立ち上げに携わり、メディアの枠を越えたコミュニティ戦略全般 を担う。
累計1200万部の大ヒットセラー『ことりっぷ』の作る世界観とは
ferret 飯髙
本日は、よろしくお願い致します。早速ですが、『ことりっぷ』についてお伺いしてもよろしいですか?
平山氏
よろしくお願いします。ことりっぷは2008年に創刊された女性向けの旅行ガイドブックです。メインの読者層は20代~30代の働く女性。創刊から8年が経ち、1200万部を売り上げるヒット商品になりました。
最近ではユーザーがInstagramの投稿で「#ことりっぷ」とハッシュタグを付けて投稿するケースもよく目にするようになりました。
「ことりっぷ」というワードがただの書籍名ではなく、「雰囲気」を表す言葉として定着してきています。つまりはブランド化してきた、ということになると思います。
ことりっぷは、旅先での観光情報として、日本各地の人気観光スポットをはじめ、ご当地のグルメやオシャレなカフェ・スイーツといった女性目線での切り口が人気を呼んでいます。最近では、*“ことりっぷらしさ”*というブランドを活かして旅行とは異なる業界の企業ともタイアップを組んで新たなアプローチも行っているとのことです。
ferret 飯髙
ことりっぷ創刊のキッカケはなんだったのでしょうか?
平山氏
元々は社内の女性社員の声から生まれたものです。その声を落とし込んで具現化したものがことりっぷで、「小冊子のようなサイズ感で持ち運びやすい」「表紙もシンプルで可愛らしい」「誌面にはホワイトスペースを多く設けて読者自身が書き込んだりできる」など徹底的に女性目線での工夫を凝らしました。
書店に並んだ時にも書店員さんが、「こういうのが欲しかったんです!」とおっしゃってくれました。つまり、今まであったガイドブックにない新たな市場を開拓したということです。
『ことりっぷWEB』 立ち上げ当初は問題だらけ

ferret 飯髙
Web版・アプリ版をはじめた理由は何だったのでしょうか?やはりユーザー行動の変化とかでしょうか?
平山氏
いくつか理由はあります。ひとつは仰られたように、ユーザーの行動の変化はあると思います。創刊から5年も経てばターゲットとしているユーザー自身のマインドの変化もありますし、そもそもメディア界隈もがらっと変わっていました。Twitterが流行り始めたのは創刊時の2008年以降ですから、その後5年でSNSが当たり前になってきたこと、まとめサイトの勃興で情報の取得の仕方も変わってきたことなどユーザーを取り巻く環境も変わったと思います。
そういった変化に対してガイドブックとしてどうしていくべきか、というひとつの解の中に必然的にWebの戦略が出てきました。ただ、そういう外的な要因よりも他の要因の方が強かったですね。それは、先ほどお話しした“らしさ”です。2013年当時、ことりっぷは創刊から5年が経っていて、発行部数も1000万部に届くガイドブックに成長していました。「ことりっぷ」の認知が上がるにつれ、広告案件、コラボ案件などが増えてきていた状況だったんです。
つまり、ことりっぷ“らしさ”を活かすようなブランドビジネスの案件が増えてきた時期でもあったんですね。この“らしさ”というのはブランド化する上ではチャンスではあるのですが、一方で危惧もしていました。
そもそも“らしさ”って何だろうと。
話を聞いていると編集部員や営業、更には代理店まで、それぞれにことりっぷ“らしさ”があり、創刊時より幅が広がっていたんです。
理由としては簡単で、創刊から5年が経った当時は、ユーザーの声を聞くことをほとんどしていなかったんですね。だからまずはWebメディアを立ち上げ、ことりっぷが発信し、ユーザーの反響を見る中で本当に求められるものは何かを再検証していくことと、日常的に発信することで潜在層へのアプローチも行っていこうと思ったんです。
さらに、実際にユーザーとコミュニケーションを図る手段として、2015年3月にユーザー投稿型のアプリも立ち上げました。その中で投稿していただいているユーザーさんに直接お会いして定期的にインタビューすることが“らしさ”を見定めるヒントになっています。
2015年3月にリリースしたことりっぷアプリ版は、ことりっぷ編集部が日々発信する旅の魅力を伝える記事に加え、ユーザー自身が旅先の写真を投稿するCGM機能も備えた旅メディア。ことりっぷ内でのインフルエンサーであるスターユーザーや、地域に特化したローカル情報を発信するローカルメディアと連携することでガイドブックには載っていないコアな情報も発信しています。
ferret 飯髙
これまで紙だったところから、Web版・アプリ版を開始するにあたって問題はありましたか?
平山氏
正直、問題だらけでした(笑)。編集部もWebメディアを運営するのは初めてでしたから。どうしても書き方がガイドブックの延長線上になってしまうんです。ガイドブックはスポットの情報などを不足なく説明することがまず第一なのですが、Webメディアは追体験ができないと読んでもらえません。そのあたりの違いを説明するところから始めました。
また開設当初は編集スタッフも紙の編集とかけもちをしていましたので、とにかく1日2本記事を出すことだけで精いっぱいだった気がします。営業の方々に対しても、そもそもWebメディアの広告にはどういうものがあるのか、というところから説明をする必要がありました。
ferret 飯髙
ferretと一緒ですね(笑)。弊社も私が入るまではメディアを立ち上げられる人がいなく、経験ある人間は私一人だったので色々と苦労はありました。
そんな状況からどうやってここまでWeb版を作り上げたのでしょうか?
平山氏
とにかく、いろんな人を巻き込みましたね。編集部員の旅のコンテンツを発信していくことへの熱量はほんとにすごいんですね。僕の知らないことやアイデアなんかもどんどん出てくる。私としてはその熱量をインターネット広告代理店でメディアを見てきた知見から、どういうコンテンツがWebで読んでもらえるのか、それを踏まえてことりっぷではどういう構成にすべきかを一緒に考えていきました。
記事がヒットすればそれを数字とともに共有してましたね。コンテンツがユーザーに届いている実感をもってもらえるようにするためです。そういう積み重ねがあって、Webでもできるのではないか、という意識にも繋がっていったような気がします。営業に関しては定期的な勉強会を重ねていって組織全体のリテラシー向上に努めました。
ferret 飯髙
個人的にも共感するところが多いお話ですね(笑)。
重要なのは型に囚われない広い視点

平山氏によれば、Webメディア開設以降、SNSの反響やアプリの投稿の傾向などを見ていると、必ずしも当初描いていたターゲット層だけが見ているメディアではなくなってきており、もっとボーダーレスな視点も必要になってきているという。
ferret 飯髙
ニーズが多様になってくると編集部でも“ことりっぷらしさ”というブランドを維持するのが大変そうですが、どうしているのでしょうか?
平山氏
とにかく私が編集部に言っているのは、「型に囚われるな」ということです。よく「これはことりっぷじゃない」といった言葉が編集部でも飛び交うのですが、「その根拠は何なのか?」をしっかり問いかけるようにしています。ユーザーの声やSNSでの反響、その他メディアの潮流などを見ているとユーザーの興味関心の揺らぎが見えてくるんです。
半年前なら受けていたコンテンツが急に受けなくなる瞬間が確かにあるんですね。そういう事象をしっかり捉えた上で、では求められる“ことりっぷらしさ”は何だろう、ということを常に考え続けること、それを部内の共通認識にしています。
ferret 飯髙
ことりっぷって、コンテンツマーケティングを意識的にやったというより、ユーザーとしっかり向き合った結果自然とそうなっているイメージです。ちなみに、ことりっぷの指標は何を見てますか?
平山氏
コンテンツマーケティングのことに関しては、まさに仰る通りです。指標に関してはいろいろ見ています。ただ、本来メディアがユーザーに与える最終的な価値はなんだろう、という点が最終的な指標であると思っています。レシピサイトであれば、コンテンツを見て実際に料理をすることですよね。
同じように旅のメディアであれば、実際にユーザーが行動に移ることが最終的な指標になるので「LINEに送る」も重要な観点です。LINEで送るときは、大体友人を誘うときですよね。そう考えると「LINEに送る」は行動に移るタイミングであり、ひとつの指標になると思っています。
ferret 飯髙
PVやセッションといった指標も見ていますか?
平山氏
もちろん、PV・セッションも見ています。つい先日、ネット上では「PV指標論」について議論もありましたが、結局メディアとしてはページを見てもらわなければ広告ビジネスとしては成り立たない部分もあるので必要だと思っています。
ferret 飯髙
仰るとおりですね。メディアをやる以上PVやセッションは切り離せません。ただ、無駄にPVを稼ぐようなことは無意味であって、ユーザーありきで考える必要はあります。ferretでは、新規ユーザーの割合も重要視しています。
本日は、どうもありがとうございました!
平山氏
こちらこそありがとうございます。非常に有意義な時間でした!
まとめ
今回お話を伺った平山氏の言葉からも、紙であろうがWebであろうがユーザーの声に真摯に向き合い、求められていることをコンテンツとして形にしながらも、どう媒体の色をつけてブランド化していくか、がコンテンツを発信するメディアにおいて重要なのではないでしょうか。
その結果が、ことりっぷの築いた“ことりっぷらしさ”というブランドであり、まさに昨今のコンテンツマーケティングブームの前から同社では実践してきたことでもあったのです。
平山氏の言葉を借りるなら、
「型に囚われるな」
これまでの型に囚われない広い視点が、変わりゆくニーズの変化を捉え、コンテンツマーケティングを成功へと導く一つの要因であることは間違いないでしょう。
このニュースを読んだあなたにおすすめ
SEO対策に関するカリキュラム
理解できてる?SEOのよくある間違い6選〜キーワード出現率・被リンク・インデックス数など〜
コンテンツSEOにおける魅力的なコンテンツの作り方
このニュースに関連するカリキュラム

SEO対策に関するカリキュラム
SEO対策に関するカリキュラムを体系立てて学ぶことができます。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- CGM
- CGMとは、インターネットを利用して消費者が情報を生成・発信していくメディアのことです。**Consumer Generated Media**の略です。古くはネット掲示板から始まりブログ、口コミサイトやQAサイトそしてSNSなどがCGMの例です。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- セッション
- Googleアナリティクスは、ホームページに適切に組み込めばアクセス状況を把握できる便利なサービスです。Googleが無料で提供しており、日本でも大手企業や金融機関、政府など、その利用のシェアを広げています。そこで、もっとも基本的な単位がセッションです。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- セッション
- Googleアナリティクスは、ホームページに適切に組み込めばアクセス状況を把握できる便利なサービスです。Googleが無料で提供しており、日本でも大手企業や金融機関、政府など、その利用のシェアを広げています。そこで、もっとも基本的な単位がセッションです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他