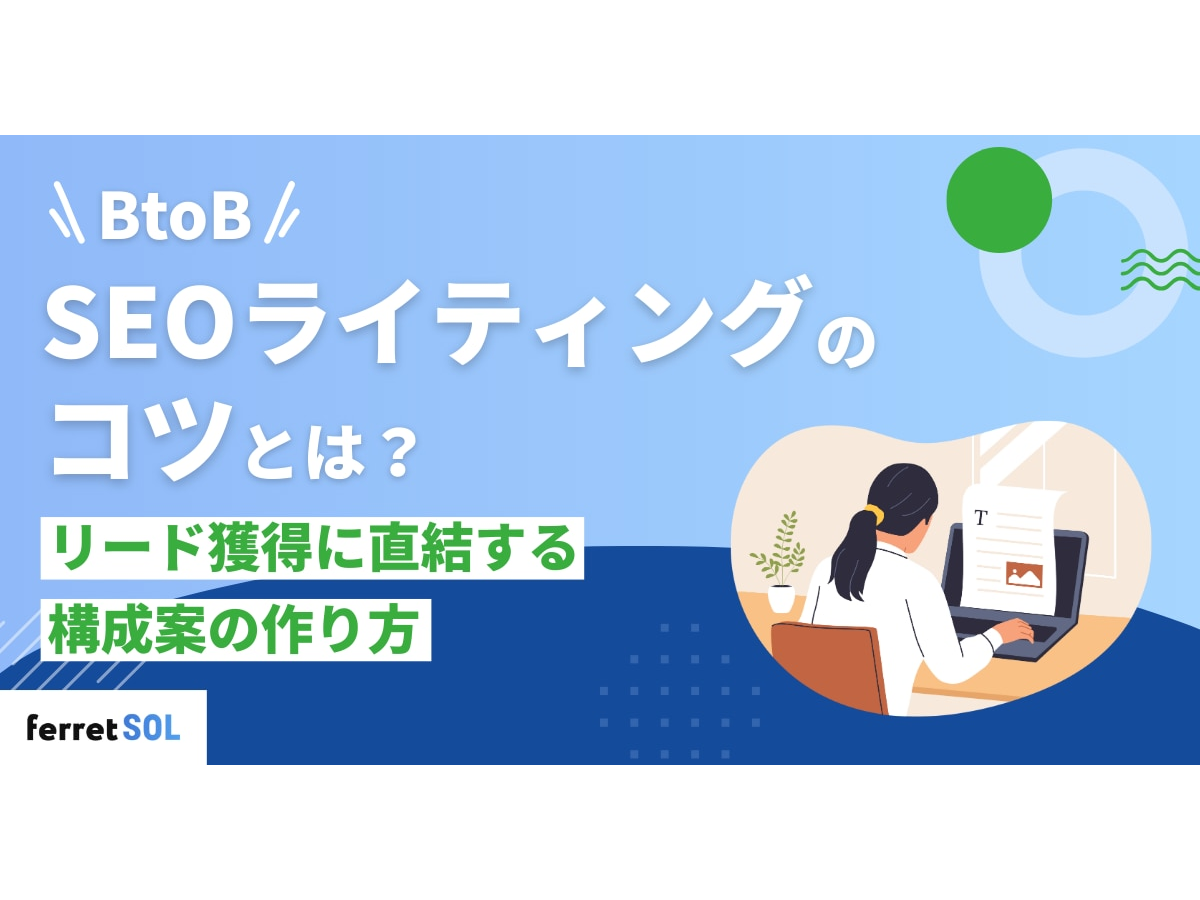コンテンツマーケティングにおける画像・動画・VRの可能性-第3回FOUND Conference in Tokyo-
1月27日、Ginzamarkets株式会社主催「第3回FOUND Conference in Tokyo」が開催されました。
今回で3回目の開催となる本イベントでは、コンテンツマーケティングの最前線で活躍されている企業のマーケティング担当者を集め、今、そしてこれからのコンテンツマーケティングのあり方について議論が交わされました。
今回は、「画像・動画・VRのコンテンツの可能性」をテーマに、それぞれの技術を活用したマーケティングを実践している資生堂・ネクスト・土屋鞄製造所のマーケティング担当者3名によるトークセッションの様子をご紹介します。
登壇者紹介
藤岡 智愛 氏 (資生堂 技術企画部 技術コミュニケーショングループ グループリーダー)

1990年(株)資生堂入社。研究所勤務等を経て、2012年より現職。主にWeb等を通じての資生堂グループの技術PRに関する業務に従事。その一環として、動画を活用した技術情報Webサイト「PICK UP TECHNOLOGY」を運用。
秋山 剛 氏 (ネクスト HOME’S事業本部 リッテルラボラトリーユニット ユニット長)

2008年に株式会社ネクスト入社。不動産・住宅情報サイト『HOME’S』のWEBディレクター、国際事業部門での経験を経て、2014年4月より現職。 『HOME’S』の研究開発(R&D)部門であるリッテルラボラトリーユニットでは、「面白くなければ、技術革進じゃない」というビジョンのもと、最新の技術を積極的に活用し、次世代サービスにつながる新たなプロダクトやサービスの研究開発に取り組む。
沼田 雄二朗 氏 (土屋鞄製造所 お客様コミュニケーション本部 バッグマーケティング室)

土屋鞄製造所 お客様コミュニケーション本部 バッグマーケティング室 沼田 雄二朗 氏
2010年に株式会社土屋鞄製造所入社。「土屋鞄製造所」及び「土屋鞄のランドセル」のEcommerceサイトの企画・開発やソーシャルメディアアカウントの立ち上げ、広告運用に従事。国内外のEcommerce事例のリサーチも行う。
モデレーター: 長田 真 氏(インフォバーン DIGIDAY[日本版]編集長)

株式会社宣伝会議の月刊誌「編集会議」「ブレーン」の制作に携わった後、2004年に株式会社インフォバーン入社。国内有数のブログメディア「ギズモード・ジャパン」「ライフハッカー[日本版]」のプロデューサー・編集長を歴任する。その後、ソリューション事業で大手企業のオウンドメディア立ち上げ・運営を担当。2015年9月よりDIGIDAY[日本版]編集長に就任。
コンテンツマーケティングの手段は「テキスト」だけではない
長田氏:
コンテンツマーケティングというと何をイメージするでしょうか?
大体の人はオウンドメディアや記事広告を思いうかべると思います。
これらの共通項は基本的にテキストと写真をベースにした記事形式ということですね。
これはなぜかというと、コンテンツマーケティングは検索を対象とした集客手段だからなんですね。
しかし、2010年を超えて技術が進化し、様々なコンテンツマーケティングの可能性が出てきました。
そもそもコンテンツって何かというと、「記事」だけではないです。
ユーザーとコミュニケーションをとって楽しませるものがコンテンツだと思います。
技術が発達した今、画像、動画、VRを使ったコンテンツの可能性が出てきています。
これらの項目のフロンテイアとして、登壇頂いている3名をお呼びしています。
まずは私を含め、それぞれ何をされているのかお話ししていただきます。
サービス紹介
長田氏:
私は、簡単にいうと編集者です。元々は雑誌の編集をやっていましたが、2006年からデジタルメディアに進みました。そこから様々な企業様のデジタルソリューションをお手伝いしたりしていました。昨年からは「DIGIDAY」というメディアの編集長をやっています。
デジタルマーケティング戦略情報サイトという説明がついているんですが、一般企業様が、デジタルにおいてどのようにユーザーとコミュニケーションをとっていくのかを論じるメディアです。
藤岡氏:
資生堂からまいりました藤岡と申します。
今日は私どもが運営しているWebサイト「PICK UP TECHNOLOGY」のテクノロジーをご紹介したいと思います。
資生堂は研究開発に力を入れているんですが、あまり世の中に知られていないんですね。そこでそのことをお伝えすべく、2010年にWebサイトを立ち上げてこれまで運営しています。
基本的に動画をメインとしたWebサイトになっているんですが、動画内ではあまり語らず、動画+Webページという構成にしています。
日本語だけでなく、他言語にも対応しており、スマホも対応しています。
これは弊社で行っている脳研究を動画で表現したものです。
なぜ動画なのかというところなんですが、目的が研究開発のご紹介なので、現象などをよりリアルに伝えることができること、また、映像自体がエビデンスになり得る、という点で動画が有効だと考えています。
あとはWebの特性上、動画を出せばニュースサイトに取り上げられやすいというところもあります。
Webで公開していますが、リアルイベントでも活用できますし、言語にあまり依存しないところもメリットかなと思います。
秋山氏:
私はHOME’Sという不動産ポータルサイトを運営しているネクストという会社内に設置されているリッテルラボを運営しています。
HOME’Sはスマートデバイス対応を先駆けて行っていたり比較的テクノロジーに強いんですね。
そのなかで、僕が運営するリッテルラボでは新しい住まい探しの研究を「UXの追求、レコメンデーションの研究」を軸に進めています。
例えば視覚障害者の方でも使いやすいUXの追求をしています。でもそれって、ビジネス的には絶対元はとれない。
それでも顧客満足のためにやるべきだという会社の方針のもとに進めています。
レコメンデーションで言うと、世の中にあるレコメンデーションエンジンは不動産と相性が良くないと僕は思っています。
なので、不動産に特化したエンジンを独自開発しています。
あとはプロダクトも幾つか作っています。
例えば、GRID VRICK(グリッドブリック)というものがあります。
家の間取りをおもちゃのブロックで作ってもらいます。そうするとリアルタイムで3D映像に反映されます。その中をHMDを使ってウォークスルーできるという装置です。
南側のここの部分にこういう窓を作れば西日が入るみたいなところが直感的にわかります。
沼田氏:
土屋鞄では大人向け、子供向けの2つのブランドを持っています。
弊社の場合、機能だけでなく、情緒的な価値を売り込んで、ブランドの世界観に共感してもらうために、主に画像を使って表現しています。
ソーシャルメディアの場合、パーソナルな空間なので、友達が投稿しているような、なるべく一人称的な投稿を心がけています。
紙カタログも年に二回ぐらい発行しています。
こちらはブランドに興味を持たれた方向けに発行しているものです。
メールマガジンも発行しています。
販売促進もやるが、半分ほどは販売には直越関係ないものです。
世界観に共有してもらうことが重要なので、メルマガを通じて自分たちのブランドを表現できるコンテンツを何度も何度も地道に刷り込んでいく感じですね。
長田氏:
今、お話いただいた話を簡単にまとめるとこのようになりますね。

コンテンツマーケティングって最初にも申し上げたんですが「記事」と思われる方が多いかと思います。検索に捕まるのが1番の目的ですが、もう1つ大きなトピックとして「記事なら誰でも作れるんじゃないか」という視点もある。
誰でも作れる「記事」を飛び越えて、敢えて動画やVR、画像を使ってコンテンツマーケティングされている皆様に、もう少し詳しく聞いて行きたいと思います。
なぜその手法を選んだのか?
長田氏:それぞれなぜその手法を選んだのか教えてください。
藤岡氏:
弊社の場合、CM制作の業務フローが社内にありましたので、入りやすかったというのはありました。
ただ始めてみて紆余曲折はありました。
長田氏:CMは代理店におまかせしたりはしないんでしょうか?
藤岡氏:
社内に宣伝部がいるので、そこを中心に動くので、アイデアとか表現の部分は基本的にはインハウスですね。
長田氏:YouTubeが流行ってきて、そういう文化にはすぐに馴染んだんでしょうか?
藤岡氏:
実はサイトを立ち上げたとき、YouTubeには上げてなかったんです。普通にFlashで貼り付けるぐらいでした。
スマホの普及もありますし、世の中の動画を閲覧する流れって変わってきているので、それにできる限り対応しようとしてきたところはあります。
秋山氏:
HOME’Sは最初Web専業だったんですよね。でも僕自身は楽しくなかった。家探しってもっと楽しいものなんじゃないかとずっと思っていました。もっと面白いものを作りたいなと思ったとき、コミュニケーションが大事かなと。
VRを直感的に操作できるようにすることで、お父さん、お母さんだけでなくお子さんも皆で一緒に楽しく家探しできるようにしたいっていうのがありました。
沼田氏:
弊社の場合、機能的なすぐ買うっていう商材ではないので、世界観を伝えるためには画像が一番直感的だし効率的だなと思いました。
あとは、ランドセル買う時って、だいたいお母さんが情報収集したり、展示会に行かれたりすると思うんです。ターゲットとなるお母さん世代は主にスマホを使っていると想定されているので、スマホでコミュニケーションできる媒体ということで、SNSに注力していますね。
ただインスタグラムは、インスタグラマーって言われている方々のレベルが高いので、写真のクオリティだけでは勝てないなと感じています。だから、日々の投稿の中にブランドならではのメッセージを入れていくのが大事かなと思います。
どういう流れで制作しているか、
沼田氏:
ソーシャルメディアの場合、季節性やリアルタイム制が重要なので、毎週チームで話し合って企画を決めています。
各ソーシャルメディアの担当者たちが自分たちでカメラマンになって自由に撮影しています。
藤岡氏:
年間4本程度を目指して制作しています。
研究開発の成果をご紹介するということもあり、題材は論文など社外発表済みの中から、アカデミック上の価値とお客さまが感じられる価値が異なるということを踏まえ、最終的には閲覧者の方々に興味を持ってもらえそうなものを選んでいます。
長田氏:Web動画だと再生回数で評価するんでしょうか?
藤岡氏:
もちろん再生回数は意識しますが、国内外のリアルイベントなどでも活用することもありますので、Web上の数字だけで評価できるものではないと考えています。
長田氏:秋山さんがやられているような、VRをはじめとした色々な企画を実施する時にどのように部下を説得されているんでしょうか?
秋山氏:
部下はこのようなことをやってきたことがない人間が結構いるので、なるべく彼らの成長に繋がるようにしなければいけないかなと思っています。
基本的に課題を見つけるのは僕ですが、部下にも自分事として捉えてもらえるように企画を出させています。
画像・動画・VRだからこそ実現できたことは?
長田氏:画像・動画・VRを利用することによって、どのような反響が起こったか、何が実現できたのか教えてください。
秋山氏:
まず知り合いの会社が変わりましたね。今まではネット専業だったのでネット界隈の企業しか付き合いがなかったんですが、今は全く別ジャンルの企業とつながりができましたね。
長田氏:藤岡さんはいかがでしょう?
藤岡氏:
一般の広告では伝えられないことが伝えられるようになりましたね。プレスリリースを出す時も、テキストだけだったものが、動画コンテンツと連動させることでより具体的に伝えることができます。社内の各部門が連携できるようになってきましたね。
沼田氏:
感覚的な部分ではありますが、ソーシャルをやる以前よりは知っていただく機会が増えたかなと思います。
長田氏:ソーシャル見たよっていうお客様いらっしゃったりするんですか?
沼田氏:
そうですね。SNS見てお店に来られる方は結構います。
反省点は?
長田氏:それぞれの技術を活用する際、反省した点があれば教えてください。沼田さんいかがでしょう。FBだとクレームのようなコメントが来たりすることもあると思いますが…
沼田氏:
クレームのようなコメントをいただいたらできるだけ早く返すようにしていますね。
コメントへの対応について、カスタマーサポートが対応するのか、ソーシャルチームがいいのかで一時期ぼんやりした時期もありましたが、レスポンスの早さが重要だと思われるものはソーシャルチームで、いわゆるお問い合わせに対してはカスタマーサポートへというふうに住み分けしています。
長田氏:クリエイティブなところではどうでしょう?
沼田氏:
コンテンツのリンクをFBに投稿していたが、あまり反応がよくなかったんですよね。宣伝臭を出すと最初のころはスルーされていました。
ですので、「センスの良い友達」のような雰囲気を出して投稿しました。敢えてリンク無しの投稿もしましたね。
藤岡氏:
締め切りがないから難しい部分は多いなと思います。
ある程度のクオリティのものを提供できるとは思いつつ、作りこみに時間をかけすぎているかなと思うところが、反省点というか課題ですね。
長田氏:進行管理を務めるディレクターのような役割の方は?
藤岡氏:
アートディレクターはいますが、いわゆるプロデューサー的な役割はおいてないですね。
長田氏:秋山さんはどうでしょう?
秋山氏:
反省というか…失敗というふうに感じてないんで。
ダメだったらダメで見なおせばいいんです。
課題と今後の展望
沼田氏:
課題というと、情緒を重視した戦略を進めていますが、感情の動きって測れないものだから、そのような感情の揺れを可視化できたらいいなと思っています。
藤岡氏:
今は動画を使っていますが、より五感に訴えかけるような手段を使っていきたいですね。
秋山氏:
研究開発とビジネス、企業とアカデミックがうまく連携できている企業ってなかなかいないんです。
それは多分、お互いをつなぐコーディネーターがいなかったからだと思うんですね。
僕はコーディネーターとしての立場を意識しながら会社をアカデミックな方向に巻き込みながら同時に収益も上げていけるようにしたいですね。
まとめ
長田氏が指摘する通り、現状は検索エンジンでの露出を増やすためにコンテンツマーケティングを実施する企業が多く「コンテンツマーケティング=テキストベースのコンテンツを主軸に行うもの」という認識が主流のようです。
しかし、本来の「コンテンツマーケティング」は、広告だけではアプローチできない、潜在ニーズを持つユーザーに向けて興味・関心を惹くようなコンテンツを提供し、顧客に育てていくための施策を指します。
検索エンジン上の潜在ユーザーを獲得することはもちろん重要ですが、潜在ユーザーを獲得するための手段をテキストコンテンツに限定する必要はありません。
VRや動画などは効果測定が難しいという課題もありますが、まずは自社のユーザーにはどのようなコミュニケーション手段が最適化を考えてみましょう。
このニュースを読んだあなたにおすすめ
マーケティングの基本である市場分析とポジション
ブランディングで集客数はほとんど変わらなくても売上1.3倍
セールスフロー理解の重要性と具体的事例

Web戦略カリキュラム
Webマーケティングを実践するうえで、まずは押さえておくべきWeb戦略の基礎カリキュラムです。Web戦略の基礎は、様々なプロモーション手法やマーケティング活動の基本と言える考え方なので必ず押さえましょう。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- セッション
- Googleアナリティクスは、ホームページに適切に組み込めばアクセス状況を把握できる便利なサービスです。Googleが無料で提供しており、日本でも大手企業や金融機関、政府など、その利用のシェアを広げています。そこで、もっとも基本的な単位がセッションです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- www
- wwwとは、World Wide Webの略称であり、世界中のホームページをインターネットを通じて閲覧することができる仕組みのことです。一般的に Web(ウェブ)とも呼ばれています。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他