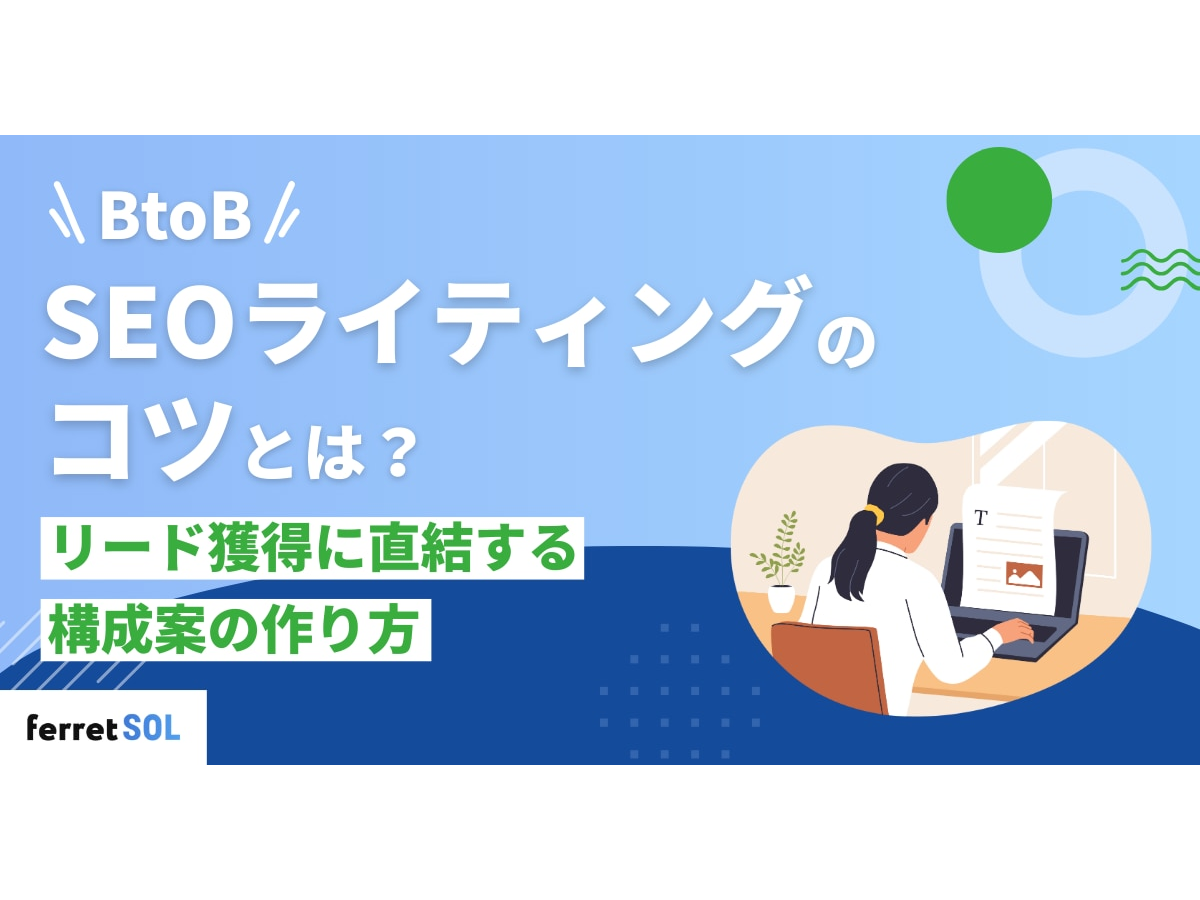【津田大介氏特別インタビュー】あらゆる企業がメディア化する今、情報発信側が見失ってはならないものとは(前編)
SEOやリスティング広告に代表される顕在層向けの集客方法だけでは顧客獲得が難しくなりつつある今、潜在層を獲得するためのコンテンツマーケティングが注目を集めています。
潜在ユーザーとコミュニケーションを図り、顧客へ育成することを目的とするコンテンツマーケティングを実践するため、オウンドメディア構築やソーシャルメディア運用に取り組む企業が増加しています。
情報発信を得意としない企業でもメディア化せざるを得ない状況となった今、発信者として何を意識するべきなのか、何を守るべきなのか、悩まれている企業も多いのではないでしょうか。
そのような企業の悩みに対して1つの答えを提示するため、今回、日本におけるTwitterブームの立役者であり、現在はテレビ、ラジオ、メルマガ、Webサイトなどあらゆるメディアで情報発信を続けるジャーナリスト/メディアアクティビストの津田大介氏にferret編集長の飯高がインタビューを敢行しました。その様子を前後編に分けてお届けします。
前編では、新聞、雑誌、テレビなどのオールドメディアからインターネットメディアまで、あらゆるメディアに触れた学生時代から、パソコン誌ライター、編集プロダクション社長、ITジャーナリスト等様々な職業を渡り歩いた経緯をお聞きし、その中で予見したメディアの未来についてお話しいただきました。
津田大介氏 プロフィール

ジャーナリスト/メディア・アクティビスト。ポリタス編集長。1973年生まれ。東京都出身。早稲田大学社会科学部卒。京都造形芸術大学客員教授。テレ朝チャンネル2「津田大介 日本にプラス+」キャスター。フジテレビ「みんなのニュース」ネットナビゲーター。J-WAVE「JAM THE WORLD」ナビゲーター。一般社団法人インターネットユーザー協会(MIAU)代表理事。株式会社ナターシャCo-Founder。メディア、ジャーナリズム、IT・ネットサービス、コンテンツビジネス、著作権問題などを専門分野に執筆活動を行う。ソーシャルメディアを利用した新しいジャーナリズムをさまざまな形で実践。 世界経済フォーラム(ダボス会議)「ヤング・グローバル・リーダーズ2013」選出。主な著書に『ウェブで政治を動かす!』(朝日新書)、『動員の革命』(中公新書ラクレ)、『情報の呼吸法』(朝日出版社)、『Twitter社会論』(洋泉社新書)、『未来型サバイバル音楽論』(中公新書ラクレ)ほか。2011年9月より週刊有料メールマガジン「メディアの現場」を配信中。
(津田大介公式サイトより引用)
新旧問わずあらゆるメディアにどっぷり浸かった学生時代
**飯髙:**津田さんのこれまでの経歴と、今やられていることを教えてください。

津田氏:
僕は元々オールドメディアが好きでした。テレビっ子だったし、高校時代は新聞部に入っていたので、将来は何かしらメディアに携わりたいなと考えていました。大学入学後、94年頃にインターネットの波が来たんですね。早稲田って実はインターネットインフラが凄く整っていて、96年ごろには24時間インターネットが使える情報センターができたので、そこに入り浸っていましたね。
なので、売るほど時間があった大学時代は新しいメディアと古いメディア両方にどっぷり浸かってました。勉強は全然しませんでした(笑)
世代的にはサイバーエージェントの藤田さんや堀江さんが同世代なんですが、大学時代にネットに触れた世代が起業していて、ネットベンチャー第一世代を形成しているのかなと思います。
大学時代は雑誌もよく読んでいたので、雑誌の編集者になりたいなと思って出版社を受けまくったんですが全滅しました。
作文試験や筆記試験は通るんですが、面接で落とされてましたね。最終面接で「編集以外の職種に興味はあるか?」と聞かれて元気良く「ありません!」と答えたからかなと思ってます。
今なら営業でも全然良いと言えるんですけどね。
その後たまたまライターの仕事を紹介されて、週2ぐらいで働き始めました。
当時はちょうどインターネットが普及し始めた時で、皆インターネットを使い始めたものの、使い方がわからなかったんですよね。本屋に行けば、パソコン関連の雑誌が山ほどありました。
なのでこれは媒体に営業をかければ仕事が来るんじゃないかと思ったんですね。
そんな状況だったので売り込みが功を奏して、いくつかの雑誌で書くことになりました。
そうして決まった仕事のなかに日経BP社があったり、週刊SPA!からも仕事が来ました。
その後、1999年に雑誌などの記事制作を行う編集プロダクション(ネオローグ)を立ち上げました。
ここで、単なるライターから編プロの社長にジョブチェンジしたわけですね。
ナップスターの登場から予見したライターの未来
津田氏:

99年、ナップスターという音楽ファイル共有ソフトが流行りました。
世界中のパソコンを繋げて、お互いの音楽データを自由に交換できることを知ったとき、これは革命だと思いましたね。
音楽業界が変わっていくだろうなと思ったと同時に、ライターの仕事もなくなっていくと予感しました。
音楽ファイルを自由に交換できるようになったのと同じように、ネット上で皆勝手につながって、情報を自由に交換する世界になった時、ライターは食えなくなるなと。
じゃあなんとかしなきゃなという気づきが99年当時ありました。
でもこの動き自体は面白いなと思いました。
音楽業界だけでなく、情報を商売にするあらゆるビジネスで破壊的なイノベーションが起こると思った。であれば、僕がやることは現場の最前線で取材をすることかなと。
そこから3年間ぐらいずっと取材やっているとそれなりに知見がたまってくるんですが、その知見をアウトプットする場所を持っていなかった。
そこで当時ちょうど個人ニュースサイトが流行っていたので、自分でCGIを勉強して2002年に「音楽配信メモ」というサイトを始めました。
ライターからITジャーナリストへ
津田氏:
当時ライターの「上がり」って3つの選択肢しかなかったんですよ。1つは編プロの社長、1つは作家、もう1つはどこかの出版社に就職する。
それは常に意識していました。そんな折、自分が書いていたパソコン系の雑誌がどんどん休刊になって、これからどうしようかなと思っていた時に出版社から単行本を出さないかとお話をいただいたんです。
単行本って、雑誌と違って売れないとお金にはならないんです。でも本を出して自分の名前を売っていくしかないなと思って。
2003年ころから単行本を書き始めて、ITジャーナリストと名乗るようになりました。
こうやって色々試行錯誤していくなかで、うまくいったこともあれば失敗したこともあります。
まず大学留年してるし、就活も全滅していますし(笑)。
雑誌ライターからジャーナリストに変わった時は、収入が激減しました。
創業したナタリーは何度も倒産しかけたし、社会運動を始めると利害関係ができて敵も増える。
いろんな失敗を繰り返しています。
ポリタスも始めましたが、まだマネタイズは十分じゃないですね。
ナタリーもそうでしたが、メディアは最初の2,3年はコストセンターとしてやりながら、どこかのタイミングで収益化を考えなきゃですね。

**飯髙:**ちょうどferretもそのタイミングなんですよ。2014年の9月にリリースして、1年後にマネタイズを始めて、昨年11月にようやく黒字化できました。
**津田氏:**楽しい時期ですよね。
**飯髙:**ただ、編集チームはよい物を作りたい、マネタイズチームはお金を稼ぎたい、どちらが上なんだろうっていうのはいつも考えています。でもやっぱり僕は結果的にはメディア側に立っていますね。
成功するポイントは「得意領域の掛け合わせ」と「反復」
津田氏:
失敗を重ねてきましたが、うまくいって今に繋がっていることもあります。
ナップスターが登場した当時、文化的、音楽的、技術的に解説できるライターがほとんどいなかったんですよ。
僕はインターネット系の雑誌で記事を書いていたものの、トップではなかった。音楽評論家になろうとも思わなかったし、音楽でもネットでも僕より詳しい人はたくさんいた。
だけど、両方を理解して、この事象が起こす未来を語れる人はいなかった。じゃあそこの領域で書き始めればトップになれるなと。そもそもライバルがいないわけですから。
ITジャーナリスとして単行本をいくつか出したんですが、『だからWinMXはやめられない』を書いたことがきっかけで、今はSmartNewsの取締役で、当時ネットイヤーにいた川崎裕一さんに「勉強会で話してもらえませんか」と言われてそこで初めて人前で登壇しました。
2006年に著作権問題を提言するフォーラムを世話人として立ち上げたのですが、それもあってパネルディスカッションの司会を務める機会が増えました。その後テレビやラジオで仕事をするようになり、年間300人くらいにインタビューしたり司会を務めたりしています。結果、今は自分の仕事の中で司会が一番得意になりましたね。
司会をうまくこなすにはいろいろノウハウはありますが、結局数をこなすのが一番です。
人は反復することで得意になるんだろうなと思います。
まとめ
前編では、津田氏の略歴から、仕事との向き合い方やメディア運営の考え方について語っていただきました。
大学時代にインターネット黎明期を体験し、ナップスターを知り、新しいメディアの可能性に気づいたと同時に大きな変化が起きることを予見した津田氏は、恐れることなく大胆な試行錯誤を繰り返し、今のジャーナリスト/メディアアクティビストに繋がる道を切り開いていかれたようです。
後編は、津田氏の更なるキャリア転換のきっかけとなるTwitterとの出会いから、メディアとの関わり方、オウンドメディア運営の際に意識するべき点についてのお話をお届けします。
インタビュー後編はこちら
【津田大介氏特別インタビュー】あらゆる企業がメディア化する今、情報発信側が見失ってはならないものとは(後編)
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- リスティング広告
- リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を、有料で表示するサービスのことです。ユーザーの検索結果に連動した形で広告が表示されるため「キーワード連動型広告」「検索連動型広告」とも呼ばれます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他