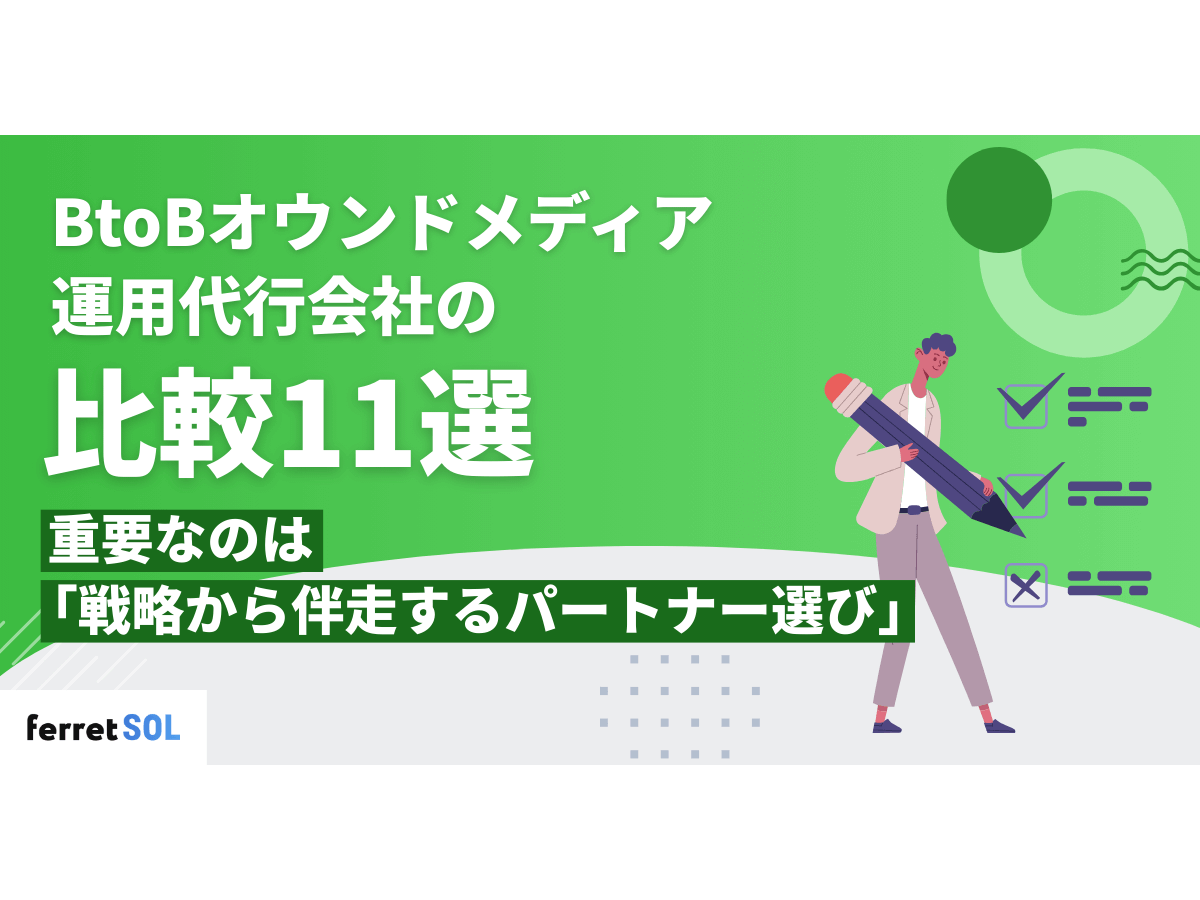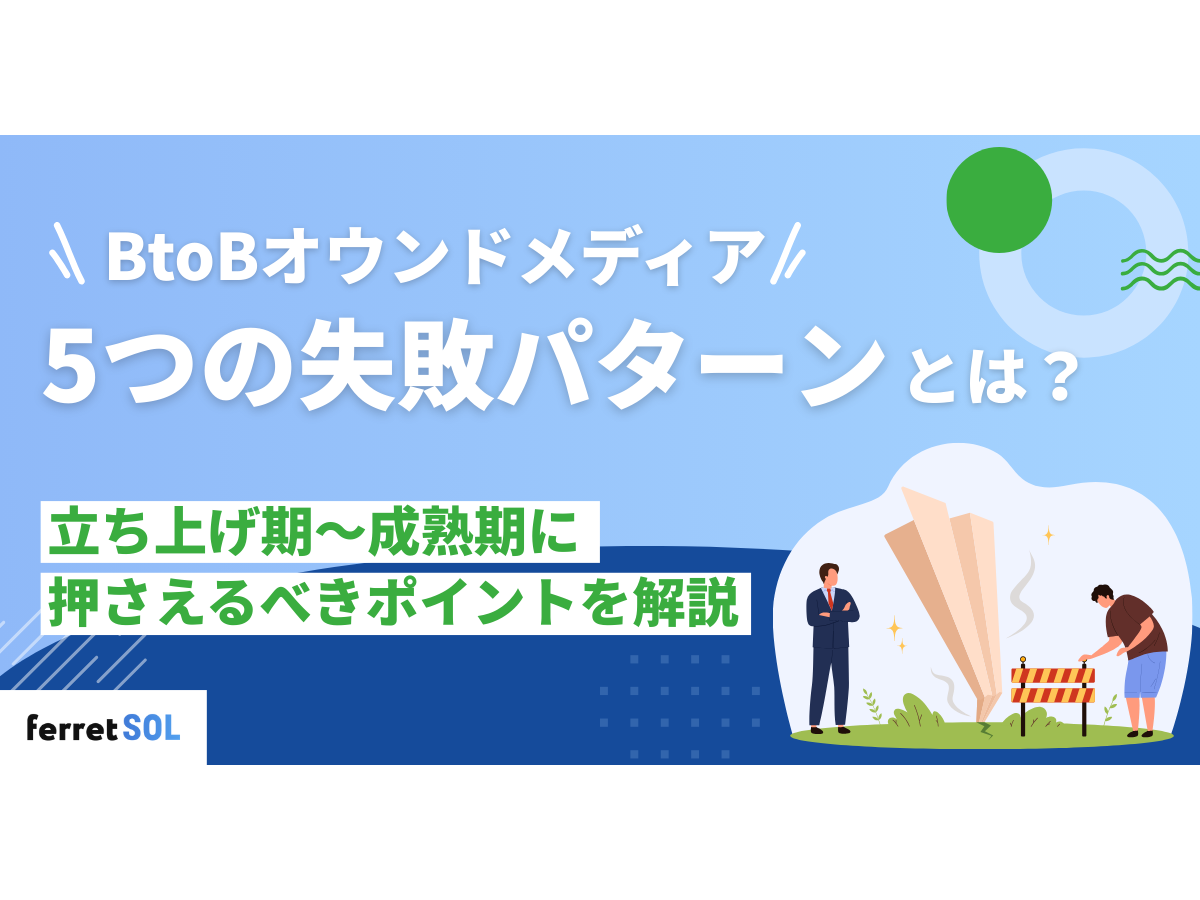【津田大介氏特別インタビュー】あらゆる企業がメディア化する今、情報発信側が見失ってはならないものとは(後編)
津田大介氏インタビュー後編では、企業のオウンドメディア運営を軸に、変容するメディアとの向き合い方やコンテンツの良し悪しの判断、仕事の取り組み方など幅広いテーマについて語っていただきました。
メディアの最前線を走る津田氏は、情報発信するうえで何を最も重要視されているのでしょうか。
インタビュー前編はこちら
【津田大介氏特別インタビュー】あらゆる企業がメディア化する今、情報発信側が見失ってはならないものとは(前編)
Twitterを始めたきっかけ

**飯髙:**津田さんがTwitterを始めたきっかけはなんだったんでしょう?
**津田氏:**始めたのは2007年の4月です。ちょうどナタリー立ち上げ当初で、一緒にナタリーをつくっていた開発者が「ブログはもう古い。これからはTwitterだ」って教えてくれたのがきっかけですね。最初は何が良いのかわからなかったんですが、どんどんおもしろくなってきて、自分が行ったイベントの中継もすぐ始めました。
そしてTwitterがブームになった頃に「Twitter社会論」を発売したらこれが5万部くらい売れて。
本が売れた以上に、イベントに呼ばれたり、テレビからも取材がきたりしました。
**飯髙:**SNS1つとってもいろんなプラットフォームが生まれていると思うんですけど、津田さんが今もTwitterを続けている理由はなんでしょうか。
**津田氏:**フォロワーが60万人を超えて辞めるに辞められないっていうのもありますが(笑)、Twitterの代わりになるものがないというのが一番ですね。
重要な告知媒体であり、新たな論者を知る場所でもある。ゴミこそ増えましたが、本質的な便利さは変わってないと思います。
FacebookやLINEは人間関係が構築できている人と交流を深めることができますが、不特定多数への発信や、思わぬ出会いがあるのはTwitterですね。
ニュースアプリではわからないこともあるし、情報インフラとしてはTwitterに勝るものはないかなと。今Twitterはビジネス的に厳しくなってきていますが、もしなくなったとしても代わりになるものが出てくると思いますよね。
**飯髙:**最近、noteにも注目されてましたよね。
**津田氏:**noteのように、いろんな人がコンテンツを販売できるプラットフォームはこれから大事になってくると思うので、取り組み自体は応援しています。
最近は田端さん・はあちゅう・イケダハヤトあたりが使い始めていますよね。
現状は情報商材販売所みたいになってしまっていて、それは大丈夫かなとは思いますが、それでも注目されるのは良いことかなと思います。
クリエイターがすぐにマネタイズできるプラットフォームがあるのは望ましいと思いますね。
パリ同時多発テロが起こった時、SNSのアイコンをトリコロールにすることに対して賛否両論が巻き起こったわけですが、それに対してTwitterでもFacebookでもなく、ブログを更新する人が多かった。
流れて消えていくSNSではなく、しっかり意見表明できるブログを選ぶ人がたくさん出てきたんですよね。
noteもそうですし、mediumなんかも出てきてますが、ブログ的なメディアの価値が見直されているんじゃないかなと思います。
多様化するコンテンツ

**飯髙:**一方で、テキスト以外のコンテンツも増えていますよね。テキスト不要のコミュニケーションも。
**津田氏:**インスタグラムなんかまさにそうですよね。
多分、皆それぞれ得意な分野で表現していく方になるのかなと。自分が思っていることを表現するのに、言葉、写真、動画などあらゆるメディアの中から選べる時代になりましたよね。
あと最近思うことなんですが、メディアが細かくセグメント分けされたなかで多くの人にメッセージを届ける時、かつてはテレビCMを放映して広告代理店に依頼してキャンペーンを打てばある程度ヒットさせることができたんですよね。
でも今はその方程式が通用しない。通用してもかつてほどの効果が得られなくなった今は、あらゆるメディアで、それぞれに適したかたちでメッセージを伝えなければいけないなと思います。
自分が全てのメディアで仕事しているっていうのは、そういう意味合いもありますね。
もっと仕事を選んでもいいんでしょうが、それだけだと自分が枯れてしまう。
原点に戻れば、僕がやりたいのは「伝える」ことなんです。であれば、全てのメディアに携わらなければいけないかなと。
**飯髙:**津田さんが最近注目されているメディアってありますか?
**津田氏:**朝日新聞の中で特にデジタルに詳しい平さんが運営されている「新聞紙学的」は面白いですね。後は「DIGIDAY」とか。
最近良さに気づいたのが日経新聞のデジタル版ですね。日経のマイニュースという機能があるんですよ。
自分でキーワードや特集を登録すると、ソーシャルメディア的なインターフェイスで話題を追いかけることができます。情報をサッと確認する際に便利ですね。
NewsPicksも利用してます。自分の記事の反響を見るときに使っています。
オウンドメディアは「結果的に宣伝になる」もの

**飯髙:**大手だけでなく、一般企業もオウンドメディアを持ち始めた今、情報発信が得意でない企業が発信力を持つために気をつけるべきことは何でしょうか?
**津田氏:**ソーシャルメディアで一時期、企業アカウントが流行しましたが、成功しているアカウントで、自社の宣伝だけしているところはなかったんですよね。
例えば自動車メーカーだったら、クルマ好きの人に役立つ情報を発信し続けて、その中に自社の宣伝を3割程度含めるのが成功パターンだったと思います。
オウンドメディアの本質も同じです。オウンドメディアをやるんだったら、業界全体に貢献する情報を発信する。
業界そのもののファンを増やすことで、結果自分たちにも還元される。
業界全体の宣伝をするってことはライバル企業にも塩を送ることにもなるけど、中長期的には自分たちにリターンがある。そこができるかどうかじゃないですかね。
企業アカウントの草分け的存在の末広さん(株式会社加ト吉(現テーブルマーク株式会社)公式Twitterアカウントの運用担当者)の決まり文句が象徴的かなと思います。
例えばフォロワーから「今日加ト吉のうどんを食べようと思ったのにラーメンを食べました。ごめんなさい」というツイートが来たら「大丈夫です。麺類皆兄弟ですから」と返すのが定番だったんですけど、これってジョークのように見えて本質を突いた言葉だと思います。そもそも、麺が好きな人であればその人にはアピールできる可能性あるよねって考えられるかどうか。
オウンドメディアを運営する際に重要なのは「結果的に宣伝になる」ところをずらさないことですね。
まずは読者にとって有益な情報は何かを突き詰め、発信して、結果として、自分たちの宣伝になればいい。宣伝のためだけにオウンドメディアをやるんだったら、効率は悪いのでPR会社に丸投げしちゃった方がいいですよ。
コンテンツの質とは「作り手に情熱があるかどうか」
**飯髙:**オウンドメディアやコンテンツマーケティングの文脈で、よく「コンテンツの質」について言及されていると思いますが、津田さんが考える「コンテンツの良し悪しを判断する基準」ってなんでしょうか。
**津田:**やっぱり、作っている人たちの情熱があるか、軸があるかどうかじゃないですかね。そこが全てだと思います。
良い悪いは主観的な判断でしか無いので、それは編集長しか決められないと思います。
メディアは編集長が考えていることを実現するためのものであって、極端に言えば編集部員は編集長の手足となってメディアの持つビジョンを記事というかたちで具現化する。
良いメディアに共通しているのは、コンセプトと軸と情熱があるということですね。
これは音楽でも何でも、全てのコンテンツに共通する普遍的なことかなと。
良い物で売れるものもあれば良くないのに売れるものもある。その相関関係って未知だから、だったら自分たちで納得できるものを試行錯誤しながら作り続けるしかない。
最終的には、出したものが確実に誰かの役に立っているとつくっている側が実感できればそれは「良い」コンテンツなのではないかなと思います。
僕も、自分のコンテンツを読んだユーザーから「面白かった」って言ってもらえるのが原動力になっていますしね。それがあるから辛い徹夜作業も乗り切れる。
人にしかできない仕事とは?

**飯髙:**先ほど、津田さんはナップスターの登場で「ライターは食えなくなる」と予感したと仰ってましたが、先日の津田マガでも「ホワイトカラーの仕事までもAIに奪われる」という下りがありましたよね。
高度な知識を必要とされる職業(弁護士や医師、株式ディーラー等)がAIに取って代わられる、編集領域でも同じで、文章の簡単な要約ならAIでもできると。
人の仕事領域がAIに奪われていく中で、人にしかできないことは残るものなのでしょうか。
**津田氏:**確かにAIはホワイトカラーの仕事を奪うと言われていますが、人にしかできない部分はなくならないと思います。やっぱり人が感動するものとか、感動するきっかけをAIで作り出すのは難しいのではないかなと。
例えばNetflixなんかは賢いなと思うのですが、再生中に一番ブラウザを閉じられなかった俳優がケビン・スペイシーで、一番見られていた監督がデヴィット・フィンチャーだった。だからこの2人を採用したけど、そこから先の制作は全部クリエイターに任せたんですよね。そういうスタンスだったからこそ成功できたんだと思います。
人が何に感動するかって、わからないんですよね。
例えば昔、イカ天という音楽番組がありましたが、そこで「たま」というバンドが絶大な人気を獲得しましたよね。たまってものすごくアングラなバンドなのに大ヒットしたんですよ。
あのバンドがなぜそこまで売れたのか、誰も説明できないんですよね。でもコンテンツってそういうもので、多分そこが本質で。
「売れる」ものはビッグデータでつくれても、本当に人を感動させるものを作ったり、自分が感動したことを伝えたりすることが、、AIに侵されない、人間が持つ最後のサンクチュアリなのかなと。
逆に言えば、クリエイティブ産業で機械に代替されるような仕事をしている人は必要とされなくなっていくでしょうね。
ナップスターが登場した時、僕はほとんどのライターはダメになると感じたと話しましたが、実際多くのライターが消えていきました。
逆に残ったライターは、本当に書けて取材できる人か、この未来を予想して、先回りして動いたライターでしたね。
Webには正解が無いからこそ無限の可能性がある
**津田氏:**飯髙さんは、ferretに入る前は編集の経験はあったんですか?

**飯髙:**僕は編集経験なかったんですよね。2011年に個人ブログを始めて、twitterやFacebookを活用することでトラフィックがとれるようになって。
これはビジネスでも活用できると思い、前々職でオウンドメディアを立ち上げて半年ちょいで100万PVに到達したんですが、編集もライティングも独学でやっていました。
ただ、その後も複数のメディアの立ち上げや企業のオウンドメディアを手伝うことはあったのですが、基本的にはサブ業務といった形でした。
そこで次のステップとして、ferretで本気でやってみようということでジョインしました。
**津田氏:**それで良いと思いますけどね。僕も、誰も教えてくれなかったので原稿の書き方や取材の仕方、編集のやり方は全部独学でした。でも独学だからこそ、いろんな面で応用がきくんだろうなとも思います。新しいジャンルでも自分でやり方を見つけていける。
**飯髙:**そうですね。変に型はできて無いかなと思っています。ある程度ルールがあれば書ける感覚はありますね。
**津田氏:**雑誌の編集だとある程度の「型」はありますが、Webの場合は正解がないですからね。
正解がない分、これからいくらでも新しいことができる。
最近になってオウンドメディアが話題になっていますが、よく考えると全然新しい概念ではないんですよね。紙では昔からやっているし。
それで言うとオウンドメディアの最高峰は資生堂の「花椿」とか博報堂の雑誌「広告」だと思いますね。
質や面白さでいうと、Webのオウンドメディアはまだ紙には勝ててないんじゃないかなと思います。そこまで本気でやっているWebはまだ無い。
でもそれはWebがダメだと言っているんじゃなくて、伸びしろがあるっていうことです。
早く紙を追い越しちゃえよと思っているし、自分もそういうチャレンジを40代はしていきたいなと。
まとめ
オウンドメディアは、自社の利益を上げるためにやるものだと捉えている事業者がほとんどだと思います。
しかし、潜在層を獲得するためのオウンドメディアを運営するのであれば、自社だけでなく業界全体のファン獲得に貢献できてこそ意味があると津田氏は述べています。
「情けは人のためならず」ということわざがありますが、他者への施しは最終的に自分自身に還元されるという考えは、コンテンツマーケティングの根幹を成しています。
オウンドメディアもその思想のもとで設計されるべきで、「ユーザーにとって有益な情報は何なのか」「どのような形式であれば伝わりやすいのか」を考え抜けるかどうかが決め手となります。
特にWebでオウンドメディアを構築する場合、インタビューでの指摘があったとおり決まった型や成功法則がありません。
だからこそ、情報をどのように、どこのプラットフォームでアウトプットすれば自社の潜在顧客に届きやすいのか、常に試行錯誤して改善を重ねる必要があります。
自社のユーザーを思いやる力を軸に置き、あらゆるプラットフォームやコンテンツ形式を試してみましょう。
変化の激しい時代で生き残っていくためには、軸を持ちながら変化を受け入れる姿勢が不可欠です。
インタビュー前編はこちら
【津田大介氏特別インタビュー】あらゆる企業がメディア化する今、情報発信側が見失ってはならないものとは(前編)
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンセプト
- コンセプトとは、作品やサービスなどに一貫して貫かれている考え方をいいます。デザインと機能がバラバラだったり、使い勝手がちぐはぐだったりすると「コンセプトが一貫してないね」などと酷評されてしまいます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ビッグデータ
- ビッグデータとは、一般に、インターネットの普及とITの進化によって生まれた、事業に役立つ知見を導くためのデータのことを指します。「データの多量性」だけでなく、「多様性」があるデータを指します。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他