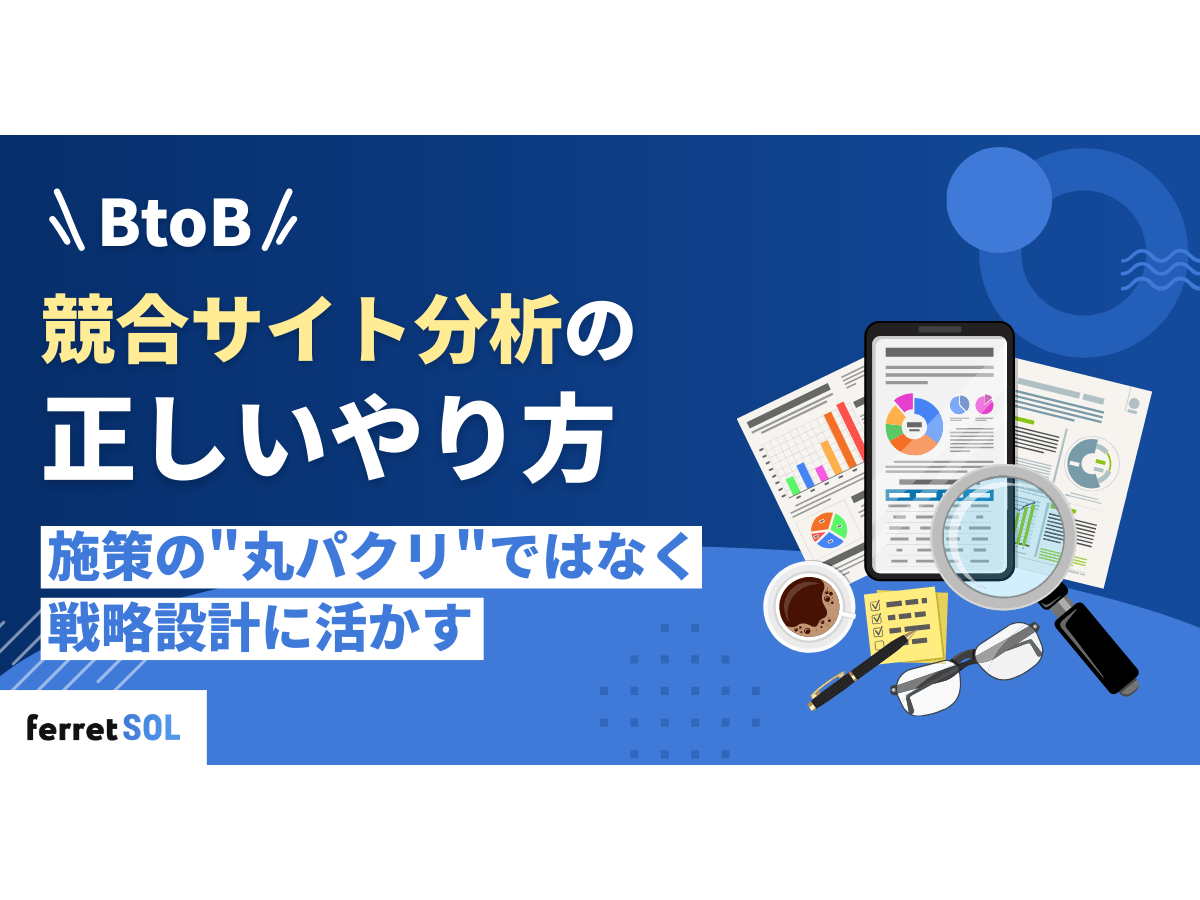【データ公開!】今話題のPtengineのヒートマップを使ってferretを分析してみた(パソコン編)
今回は、最近話題のアクセス解析ツールPtengineを使ってFerret(パソコンでのデータ)の記事がどのように読まれているのかを調べてみました。普段、アクセス解析で見ている情報とは違う視点でユーザー行動が可視化され、なにより分かりやすいことが特徴です。
あまり、数値を見て分析することが苦手という方にはヒートマップがおすすめです。
Ptengineとは

Ptengineとは、株式会社Ptmind社が提供するアクセス解析ツールです。2013年7月にサービスを開始し、日本だけでなく海外にも提供され、累計で10,000サイト以上に導入されています。
Ptengineの特長としては、「直感的で簡単に使えて、リアルタイムに解析が可能」という点です。
これまでのヒートマップでは、解析に必要なデータが一定量取得が必要であったり、測定期間が前日までといった制限などがありました。
Ptengineでは、そういった使い難さが徹底的に排除されています。
主な機能としては、大きく二つです。
1.GoogleAnalyticsと同様のアクセス解析機能
2.ユーザー行動を分かりやすく可視化できるヒートマップ
マルチデバイス対応です。
今回は、Ptengineの最大の特徴ともいえるヒートマップを使い、Ferretの記事がどのように閲覧されているかを分析してみました。
ユーザーがクリックした箇所
こちらはユーザーがクリックした箇所を色分けしております。赤色に近いほど多くクリックされていることを示すよう色分けしています。ユーザーがどのように利用しているか、利用しようとしているかを調べる際に役立ちます。
まずは、クリックされている箇所から見ていきましょう。

読んだ後のSNSボタンより読む前のSNSボタンのほうが押されやすい
現在、Ferretのホームページ内にあるSNSボタンは大きく分けて3箇所です。
「タイトル下(最上部)」「追尾型SNSボタン(ページ左側)」「フッター(最下部)」
このうち、最もクリックされている傾向が、タイトル下(最上部)でした。
【押されやすい順】
1位:タイトル下(最上部)
2位:追尾型SNSボタン(ページ左側)
3位:フッター(最下部)

以下の図では、若干のズレがあるものの、押されている回数の多さを示す赤色がタイトル下のSNSボタン周辺に多いことが分かります。
ここで考えられることとして、
仮説1:読む前にSNSボタンを押す人が多い。
仮説2:下部のボタンまで到達していない、気づいていない。
仮説1は、SNSボタンをどんな時に使うのかによるかと思います。読む前にSNSボタンを押して、あとで読むためのブックマークのような使い方、読んでないけど押しておく、読む前のクセといった事が考えられます。あとはSNS経由から記事を読むにあたりとりあえず拡散しておくなどということもあるかもしれません。
仮説2は、そもそも下部にあることに気付いていないか、ページ左側にある追尾型SNSボタンがフッター(最下部)の役割を担っている。下部に到達する前に追尾型SNSボタンを押しているため、フッターが押されていない可能性が考えられます。
リンクはとにかく押されている
全体的にコンテンツ内のリンクは、とにかく押されていることが分かります。
例えば、3.「trippiece(トリッピース)」の事業計画書の段落にある英語版の資料へのリンクが真っ赤に染まるほどクリックされています。

Ferretは海外からのアクセスは少ないです。
わざわざ英語版を読む必要性を考えても、意図的にリンクをクリックしているというよりは、なにげなくクリックを押しているユーザーが多い。もしくは英語版の資料をどう作成しているのかなど興味本位でクリックしているかもしれません。
一方で、目次部分にクリックが集中していることは、目次部分から抜粋して読みたいユーザーが勘違いしてクリックしていることがうかがえます。
まとめ形式のコンテンツの場合、その中でも必要な情報を取捨選択したいユーザーにとっては、目次が重要な役割を果たすようです。

アテンション(注視している箇所)
こちらは、アテンションと呼ばれる機能で、赤色に近い箇所ほど、よく見られていることが分かります。一般的には、ページ下部にいくにつれ色が薄れていきます。(途中でユーザーが離脱するため)
コンテンツのどこが精読されているか、あるいは、読み飛ばされているかなど、ユーザーの興味・関心を調べる際に役立ちます。

ページの4割は注視して読むが、以降は流し読み
アテンションで、ユーザーがどの箇所をよく見ているかを分析してみると、最初の4割程度までは注視して見ていることが分かりました。
以降になると、赤色の部分は減り、5割まで進むと青色が現れ、飛ばし飛ばし読んでいるか、リンクを辿って離脱しています。
離脱させないための工夫(リンクを減らす、よりニーズに合ったコンテンツを作る)といった改善ポイントがあるようです。

ヒートマップを見ることで改めて感じたこと
パンクズがユーザーの遷移に大きく関わっていることが改めて分かりました。下記を見ていただくとパンクズ部分が赤く染まっていることが一目瞭然です。
定説である、左上のロゴがホームに戻るといった認識以上にパンクズが利用されていることは、ヒートマップを見て気づいたポイントの1つです。

また、記事中には、スライド共有サービスのSlideShareで公開されているスライドが埋め込まれており、ページ内で閲覧することができます。
以下の図を見ていただくと、右側が濃く染まっています。

これは、次のスライドを見るためにユーザーが画面右側をクリックしているからです。
スライド下部には、前後のスライドを見る△ボタンがあるにも関わらず、画面右側(しかも、カーソルを合わせないとスライド出来ると認識しにくい)をクリックするといった認識が多い事が分かります。
昨今のスマホ操作で、指を使ってスライドするといった行為がユーザーの行動心理に影響を与えていることが考えられます。
まとめ
今回使用したPtengineをはじめ、GoogleAnalyticsで数値化できない部分をヒートマップを使えば可視化することが可能になります。
よりコンテンツ内で、ユーザーがどのように行動しているかといった部分を分析したい場合は、ヒートマップを使ってみることをオススメします。
近日スマホでの数字も公開しますのでご興味のある方はぜひお読みください。
このニュースを読んだあなたにおすすめ
LPOカリキュラム
ランディングページ(LP)はファーストビューで興味を惹こう
LPOツール(ヒートマップ)の活用
このニュースに関連するカリキュラム

LPOカリキュラム
LPO(ランディングページ最適化)で最も重要なランディングページの構成をユーザーの心理やノウハウを元に説明します。さらに、LPOの効果を高めるために必要なA/Bテストの方法も併せてどうぞ。
- アクセス解析ツール
- アクセス解析ツールとはホームページに訪れるユーザーがどのような経路で、何に興味を持って訪問しているのかを分析することをアクセス解析と言います。また、アクセス解析においてアクセス情報を収集して、それを解析する手法のことをアクセス解析ツールと言います。様々なアクセス情報を分析することで、ホームページを運用、改善していくことに役立てます。
- ヒートマップ
- ヒートマップとは、Webマーケティングにおけるヒートマップとは、ホームページ内でのユーザーのアクションの大小を、サーモグラフィーのように表示する機能です。ユーザーがどこを一番見ているのか、マウスの動きやスクロールなどから解析し、それを色によって表します。「クリックヒートマップ」「マウスヒートマップ」「スクロールヒートマップ」「ルッキングヒートマップ」などの種類があります。
- アクセス解析ツール
- アクセス解析ツールとはホームページに訪れるユーザーがどのような経路で、何に興味を持って訪問しているのかを分析することをアクセス解析と言います。また、アクセス解析においてアクセス情報を収集して、それを解析する手法のことをアクセス解析ツールと言います。様々なアクセス情報を分析することで、ホームページを運用、改善していくことに役立てます。
- ヒートマップ
- ヒートマップとは、Webマーケティングにおけるヒートマップとは、ホームページ内でのユーザーのアクションの大小を、サーモグラフィーのように表示する機能です。ユーザーがどこを一番見ているのか、マウスの動きやスクロールなどから解析し、それを色によって表します。「クリックヒートマップ」「マウスヒートマップ」「スクロールヒートマップ」「ルッキングヒートマップ」などの種類があります。
- ヒートマップ
- ヒートマップとは、Webマーケティングにおけるヒートマップとは、ホームページ内でのユーザーのアクションの大小を、サーモグラフィーのように表示する機能です。ユーザーがどこを一番見ているのか、マウスの動きやスクロールなどから解析し、それを色によって表します。「クリックヒートマップ」「マウスヒートマップ」「スクロールヒートマップ」「ルッキングヒートマップ」などの種類があります。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ヒートマップ
- ヒートマップとは、Webマーケティングにおけるヒートマップとは、ホームページ内でのユーザーのアクションの大小を、サーモグラフィーのように表示する機能です。ユーザーがどこを一番見ているのか、マウスの動きやスクロールなどから解析し、それを色によって表します。「クリックヒートマップ」「マウスヒートマップ」「スクロールヒートマップ」「ルッキングヒートマップ」などの種類があります。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- ヒートマップ
- ヒートマップとは、Webマーケティングにおけるヒートマップとは、ホームページ内でのユーザーのアクションの大小を、サーモグラフィーのように表示する機能です。ユーザーがどこを一番見ているのか、マウスの動きやスクロールなどから解析し、それを色によって表します。「クリックヒートマップ」「マウスヒートマップ」「スクロールヒートマップ」「ルッキングヒートマップ」などの種類があります。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ヒートマップ
- ヒートマップとは、Webマーケティングにおけるヒートマップとは、ホームページ内でのユーザーのアクションの大小を、サーモグラフィーのように表示する機能です。ユーザーがどこを一番見ているのか、マウスの動きやスクロールなどから解析し、それを色によって表します。「クリックヒートマップ」「マウスヒートマップ」「スクロールヒートマップ」「ルッキングヒートマップ」などの種類があります。
おすすめ記事
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他