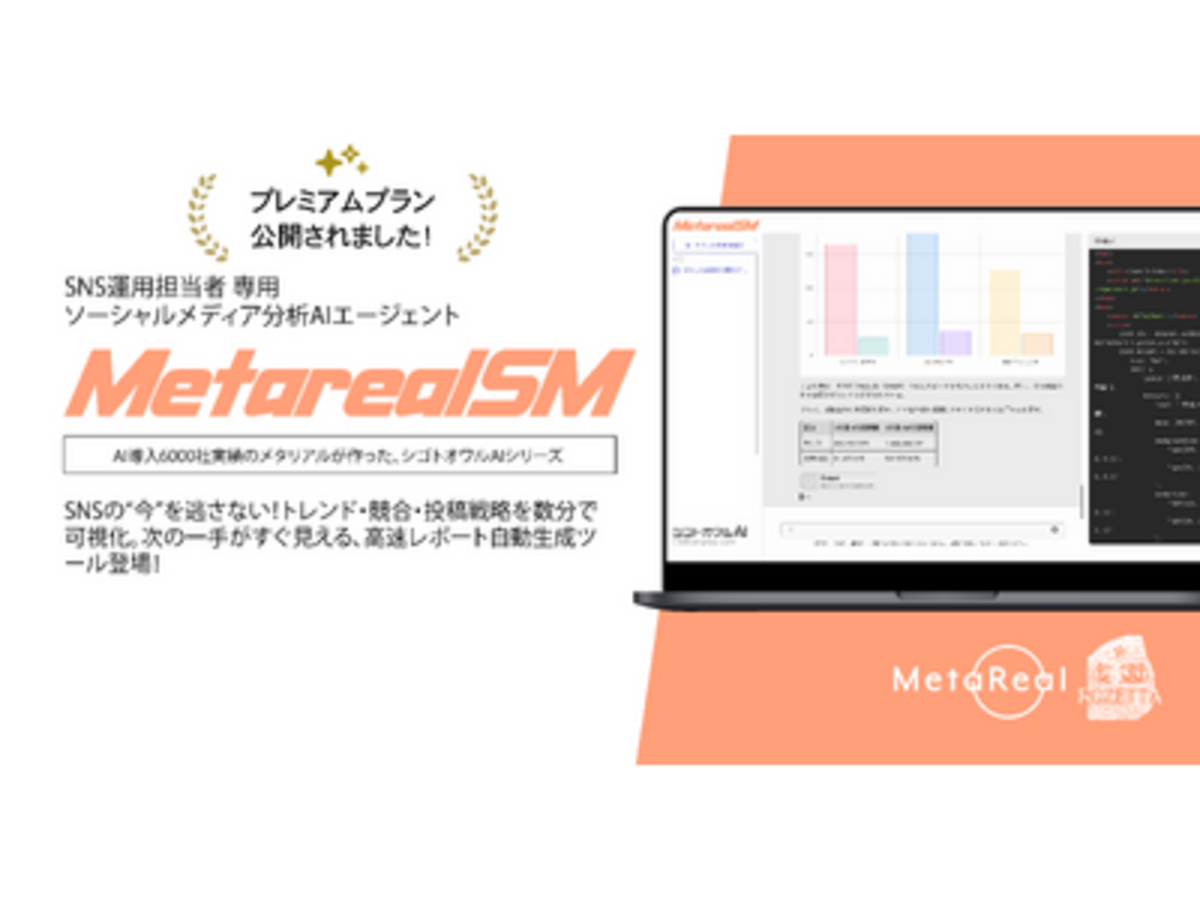八百長疑惑から一転人気急上昇!日本相撲協会から学ぶ、Twitterでファンを作る「舞台裏」の見せ方とは?
日本の国技として知られる「相撲」が、今新しい動きを見せていることはご存知でしょうか。
実際の力士がファンをお姫様抱っこするというイベントや、公式キャラクター「ひよの山」を中心としたグッズ展開など、相撲のイメージを覆すような新しい試みがなされています。
特にTwitterでは2017年6月に公式アカウントのフォロワー数が30万人を突破、ファンを作り出すことに成功しています。
今回は日本相撲協会のTwitterからみる、Twitterでファンを作るポイントを解説します。
力士の魅力を伝える「舞台裏」の見せ方を、一緒に学んでいきましょう。
日本相撲協会とは
公共財団法人日本相撲協会は、年6回の本場所の開催に加えて、相撲に関連した歴史資料の保管や相撲の普及、国技館運営、人材育成などの活動を行っている組織です。
伊勢神宮や靖国神社への奉納相撲で知られるように、相撲は儀式としての意味合いも持ちます。そのため2011年に現役力士が金銭を受け取って勝敗を決めていたという八百長疑惑が持ち上がった際には、社会的にも大きな話題となりました。
結果として、2011年は春場所及び年内の巡業が中止となり、相撲ファンが離れてしまうのではないかと危惧されました。

引用:[スポーツ関連産業の動向と相撲人気の行方|経済産業省] (http://www.meti.go.jp/statistics/toppage/report/minikaisetsu/hitokoto_kako/20160601hitokoto.html)
実際、経済産業省発表している第3次産業活動指数みると、2011年(平成23年)には大きく指数が下がっています。
ですが、その後2012年(平成24年)から一転して上昇傾向に転じ、むしろ問題の発覚前より高い指数を指し示しています。
このような相撲人気の回復の裏には、相撲協会内部の改革だけでなく、新しいファンを生み出す数々の試みがありました。
では、実際に相撲協会がどのような試みを行ってきたのか、相撲協会の公式Twitterアカウントを通して見ていきましょう。
参考:
相撲の歴史 |日本相撲協会公式サイト
[伊勢奉納相撲中止 不祥事では初、靖国は延期|スポーツ報知] (http://web.archive.org/web/20110217030214/hochi.yomiuri.co.jp/sports/sumo/news/20110215-OHT1T00017.htm)
[八百長問題で春場所中止 大相撲消滅の危機|スポニチ Sponichi Annex スポーツ] (http://www.sponichi.co.jp/sports/news/2011/02/07/kiji/K20110207000200390.html)
日本相撲協会のTwitter運営

https://twitter.com/sumokyokai
日本相撲協会では、Twitterにて公式アカウントを運営しています。
八百長疑惑の上がった2011年に開設されて以降、順調にフォロワー数を増やし、2017年7月12日現在フォロワー数は30万4千人を超えています。

https://www.socialbakers.com/statistics/twitter/profiles/detail/393742490-sumokyokai
上記はSNS分析ツール「Socialbakers」により、過去半年間のフォロワー数の伸びをグラフにしたものです。
安定した成長を見せており、半年間で5万以上のフォロワーを獲得しています。
これには本場所開催中でも休場中でも、常にツイートを行っていることが関係しているでしょう。

twitomomyより引用
上記のグラフからもわかる通り、休場中は若干ツイート数が減少しているものの、ツイートを行わない日はほとんどありません。
【日本相撲協会のツイート内容】
・取組の勝敗
・チケット販売情報
・各相撲部屋での稽古の様子
・相撲協会で行ったイベントの様子
・力士のオフショット
・行司や親方と行った力士以外の関係者による活動の様子
このように取組やチケットの販売情報だけでなく、力士のオフショットのようなユニークな内容をツイートしているのも相撲協会の特徴です。
<春巡業@靖國神社奉納大相撲>幸せそうな表情の、千代丸。 #sumo pic.twitter.com/WWHIWwPcpL
— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) 2017年4月28日
上記のツイートには*1600以上の「いいね」*がついており、多くのファンからの支持を集めていることがわかるでしょう。
こういったツイートを通して、フォロワー数を伸ばすことで相撲協会はTwitter上でもファンを増やしていきました。
相撲協会から学ぶ!Twitterでファンを作るポイント
では、相撲協会はなぜここまでファンを増やすことに成功したのでしょうか。
3つのポイントを解説します。
1.露出の機会を増やす
相撲協会ではニコニコ動画にチャンネルを開設したり、ソーシャルゲームを展開したりといった露出の機会を増やしてきました。
また、Twitterでは2016年11月から2017年7月までの間に1日あたり平均で13.01ツイートしており、こまめに情報発信を行っていることがわかるでしょう。
こういった露出の機会を増やすことで、自社のファンとなるユーザーを育成できます。
特にTwitterの場合、自社のことを気に入ってフォローしたユーザーに対して常に情報発信をし続けるのは欠かせないでしょう。
参考:
大相撲チャンネル |ニコニコチャンネル
[大相撲ごっつぁんバトル | バンダイナムコエンターテインメント公式サイト] (https://sumo.bn-ent.net/)
@sumokyokai's profile| Twitonomy
2.写真・動画を活用してビジュアルで訴えかける
<春巡業@常陸大宮場所>桜の下でポーズをとる、勢・御嶽海。 #sumo pic.twitter.com/S9f5WRkaRF
— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) 2017年4月18日
日本相撲協会ではTwitter開設当初、取組の勝敗やチケットの販売情報などをテキストで発信していました。
ですが、それでは土俵以外の相撲の面白さが伝わらないのではないかと現在では、協会のスタッフ自ら撮影を行って画像中心のツイートを行っています。
また、同時にホームページのリニューアルも行っており、以前のテキスト中心のトップページから、ビジュアルを前面に押し出したものに変更されています。
力士の普段の様子や取組の舞台裏は、それまであまり知られることのなかったことでしょう。こういった運営側だからこそ見えることが、実はファンにとっては楽しめるコンテンツとなることもあります。「こんなの写真に撮っても」と思わず、ささいなことでも写真に撮ってツイートしてみるのもいいでしょう。
参考:
もしも、「日本相撲協会」を解析するなら [第23回] | 有名サイト、かってに解析! | Web担当者Forum
[お相撲さんの笑顔に胸キュン--相撲ブームの立役者が語る公式 Twitter の狙いとは |インターネットコム] (https://internetcom.jp/wmnews/20150307/sumo-kyokai-official-twitter-strategy.html)
3.相互に交流できる仕組み・イベントを企画する
<ご来場お楽しみ企画>公式グッズは毎日13時より、横綱手ぬぐいや今治タオルなどを親方が販売しています。 https://t.co/H68yyQJDVo #sumo pic.twitter.com/g0mSn9aHas
— 日本相撲協会公式 (@sumokyokai) 2017年7月11日
Twitterでどんなにファンが増えても、自社の商品やサービスへ触れる機会がなければ成果にはつながりません。
日本相撲協会ではTwitterでの情報発信だけでなく、ファンに向けた交流イベントを行うことで人気をさらに集めてきました。
例えば、人気力士に「お姫様抱っこ」してもらえるイベントや国技館でのちゃんこ屋台、親方や若手力士によるグッズの販売会など、ファンに来場してもらう仕組みを企画しています。
*こういったイベントを企画することでTwitterを通して自社を知ったファンに対しても店舗まで足を運ぶきっかけを作れます。*また、勝敗とは別に「敢闘精神あふれる力士」をファンに投票してもらうなど、相互に交流し合える仕組みを作っているのが相撲協会のポイントでしょう。
一方的な情報発信だけでなく、ユーザーとも気軽に交流できるのはTwitterの強みでもあります。ハッシュタグや投票機能を利用して、ユーザーからもコミュニケーションを引き出すようなキャンペーンを行ってみるのもいいでしょう。
参考:
[平成29年七月場所ご来場お楽しみ企画 |日本相撲協会公式サイト] (http://www.sumo.or.jp/Kansen/campaign/)
[敢闘精神あふれる力士 |日本相撲協会公式サイト] (http://www.sumo.or.jp/ResultData/kanto_seishin)
[遠藤のお姫様だっこに一般女性うれし涙 | nikkansports.com] (https://www.nikkansports.com/sports/sumo/news/f-sp-tp3-20140104-1239647.html)
まとめ
日本相撲協会のTwitterでは、取組の状況だけでなく、稽古の様子や健康診断まで土俵以外の力士の姿を発信しています。そのような「舞台裏」だけでなく、行司などの相撲を支えるスタッフや相撲というスポーツの豆知識などコアなファンにとっても楽しめる情報を発信しているのが特徴でしょう。
画像を使うことで、より身近な存在として感じられるようにしたことも大きなポイントです。Twitterだけでなくホームページもビジュアルを前面に押し出すことで、SNSにとどまらない効果を生んでいます。
また、Twitterから生まれたファンを、実際の来場にまで結びつける交流イベントの存在も成功の秘訣でしょう。リアルの店舗の場合、ファンがいるだけでは売上にはなかなかつながりません。こういった導線を意識することで、企業自体の成果につながるSNS運営ができるでしょう。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- トップページ
- インターネットのWebサイトの入り口にあたるページのことをトップページといいます。 一般的には、階層構造を持つWebサイトの最上位のWebページをさします。サイト全体の顔としての役割も果たすため、デザインなどで印象を残すことも考えたサイト作りも有効となります。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- 導線
- 導線とは、買い物客が店内を見てまわる道順のことです。ホームページにおいては、ページ内での利用者の動きを指します。 ホームページの制作にあたっては、人間行動科学や心理学の視点を取り入れ、顧客のページ内での動きを把握した上でサイト設計を行い、レイアウトや演出等を決めることが重要になります。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他