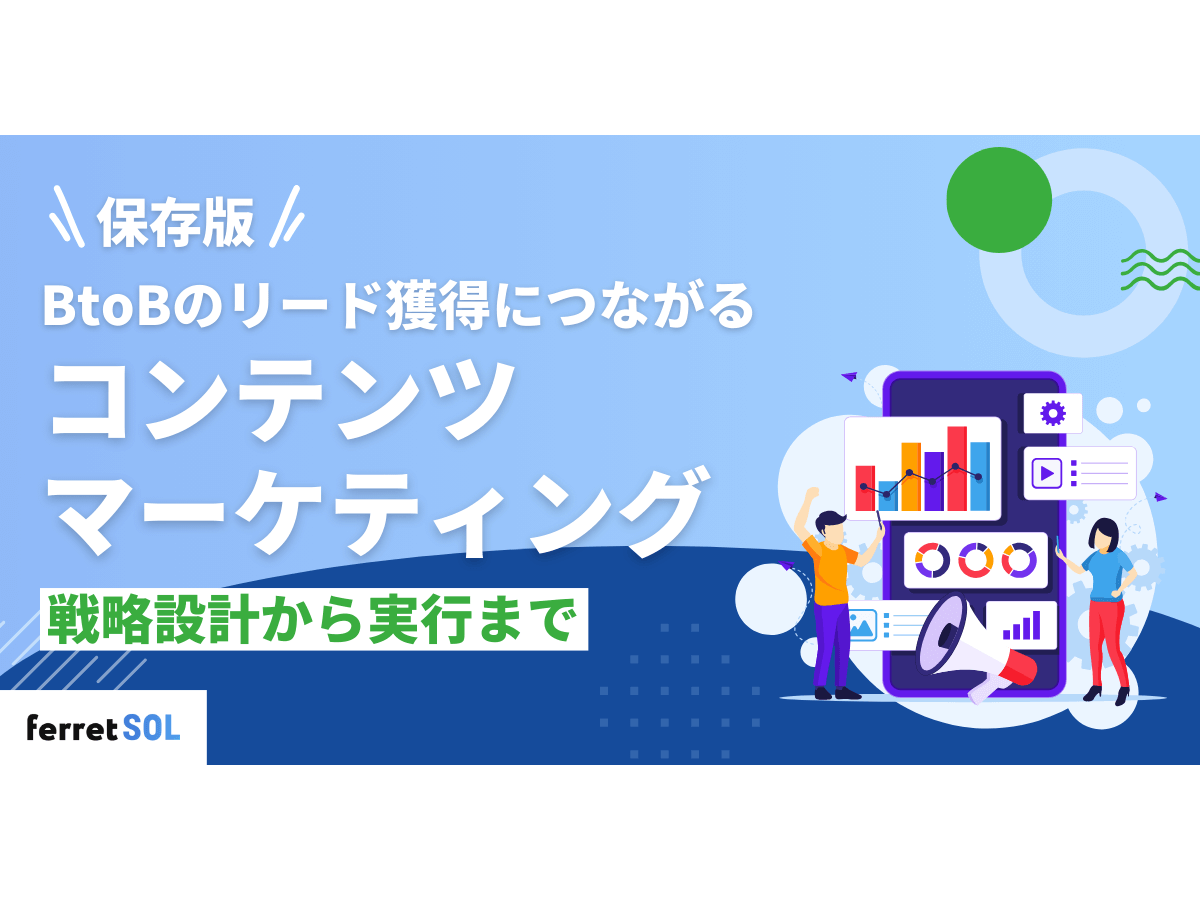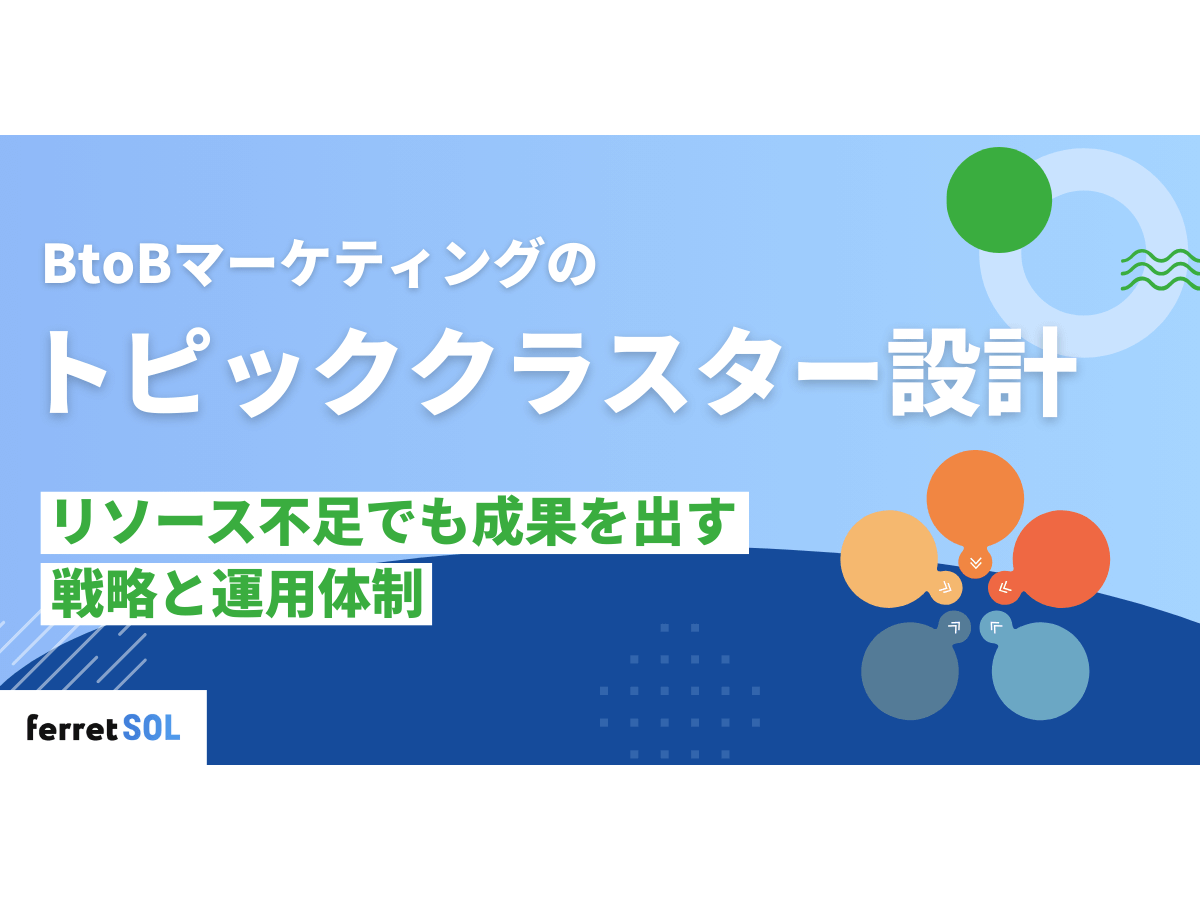「共通デバイスはスマホが最後かも」スマホファーストの先にあるメディアの未来 #FMC2018
Googleのモバイルファーストインデックスからもわかるよう、Webメディアにおいてスマホファーストなサイト設計は欠かせない要素です。
スマートフォンを所持していることが当たり前になった今、メディアはどのように変化しているのでしょうか。
2018年8月24日に株式会社フラー主催のカンファレンス「スマホファーストの次を探そう。」が開催されました。
メディアに携わる4社が「スマホ×メディア Web→ネイティブの次の動きは?」をテーマにセッションした様子をレポートします。
登壇者紹介

(左から)
ナイル株式会社 代表取締役社長 高橋 飛翔 氏
株式会社ベーシック 執行役員/ferret Founding Editor 飯髙 悠太
株式会社JX通信社 代表取締役 報道研究者 米重 克洋 氏
モデレーター:フラー株式会社 App Ape Lab編集長 日影 耕造 氏
個人がメディアになる時代

日影 氏:
スマホファーストが当たり前だからこそ生まれている世界はどのようなものなのでしょうか。
飯髙:
今後5Gが来るという世界の中、スマートフォンでも4Kが見られる世界になるって考えると、まずはテレビである必要がないかもしれないと考えています。テレビと同じものがスマートフォンで見られるかもしれないし、ビックデータの受け渡しも簡単になる。これはすでにそうだが、より情報の速報性もSNSを見た方が早くなる訳で、テレビにしかできないことはなくなる。個人がメディアになるって考え方の方が近いかな。
あとは、多くの人が情報発信している中で、報道も個人が発信したものを拾いに行くような世界によりなって行くかなと思っているのですがどうでしょうか?
米重 氏:
そうですね。事件があればまずは警察や消防に通報します。これが最近だと、通報をする前にSNSに投稿したり、LINEで友人・知人に連絡したりしているんです。そうすると、今までは警察や消防が取材対象だった報道側も、SNSで話を情報を集めていく必要が出てきます。
我々もそこに合わせてAIで情報収集ができる「FASTALERT」というBtoBのSaaSを出していますが、情報が早いということで多くの企業に広がって使ってもらっていますね。
高橋 氏:
「FASTALERT」すごいですよね。管理画面を見ると、Twitterで「火事だ」って動画を撮っている投稿や、事故を撮影した投稿が時系列で並んでわかるようになってるんですよね。それを見て、デスクの方が取材に行くんです。
これは完全に、スマートフォンがないと生まれない世界だと思うんです。スマートフォンが登場してから、カメラの普及台数は爆発的に増えています。1人ひとりがカメラやビデオという情報ソースを持てるようになっ他のは大きな変化ですよね。
米重 氏:
取材の仕方も変わってきていますよね。今までは大手なら2,000人ぐらい記者がいて、事件や事故の取材をやっていました。これは1億人がカメラを持つ時代になると、第一報を伝えることにおいてはSNSの方が早いです。なぜこの事件が起きたのか、どうしてこうなったのかなどの深い部分に関してはまだまだ人の手が必要ですが、情報をかき集めるのであればAIを使った方が早い。
高橋 氏:
車の事業をやっているので車の話をさせてもらうと、自動運転では車のカメラですべての路面情報を収集しながら走ります。この収集したデータが誰に帰属するようになるのかはまだ議論されている最中です。ですがこれがもし個人のものになるとしたら、撮影されたドラレコのデータをユーザーが「FASTALERT」のようなツールに売ることもあるかもしれません。そうすると、ツールが様々なユーザーの走行データを取得していって、より機械学習が進んで事故情報の即時性も上がるかもしれません。
スマートフォンは極論IoTと言えると思います。ですのでスマートフォンのの普及に合わせて、IoTの種類もどんどん増えてきています。それに合わせて、報道、ニュース、情報収集のあり方も変わっていくように思えますね。
スマートフォン1台で生活ができるように

高橋 氏:
これからはスマートフォンにすべてが一元化されるかもしれませんよね。今、ほとんどの車には、キーを持って近づくと扉が自動で開いてエンジンもかけられるスマートキーが導入されています。でもこのスマートキーも、MDプレイヤーとiPodと携帯電話を別々に持っていた時代に、Appleが1つでいいとiPhoneをリリースしたのと同じように、スマートフォン1つでいいって話もあります。実際に、スマートフォンがキーになるという仕組みが採用されつつもあるんです。
もしかしたら今後は、新車からスマートキーすらなくなるかもしれませんよね。スマートフォン経由で人を認証して、扉を開けられるしエンジンもかけられる。個人間のカーシェアリングでもキーの受け渡しがいらなくなるかもしれません。
それでもまだ、パソコンも必要?
飯髙:
スマートフォンが普及したことで、Googleの検索回数が爆発的に増えています。インターネットの使用時間がテレビの視聴時間を抜きそうだし、広告費だってインターネットがテレビを上回るのも、もうすぐそこまできています。これらは、スマートフォンが誕生したことが大きな影響を与えています。
でもBtoB向けのマーケティングメディアの「ferret」は、スマートフォンよりもパソコンユーザーが多いんですよ。割合でいうと7割がパソコンなんですよ。今回はスマホのイベントだけど、実はferretは、パソコンファーストなんです(笑)
高橋 氏:
BtoBのSaaSはパソコン多いですよね。我々もパソコンがメインですが……。
飯髙:
メディアを見ている時に仕事をしているのか、プライベートなのかによってデバイスは変わりますよね。スマホファーストとは言われますが、そこは正しく認識していくべきだとは思います。
高橋 氏:
デバイスシフトが起きているからといって、元デバイスに固執することがダメってことではないですよね。最適なデバイスはどれなんだろうって視点で考えていくといいですね。
飯髙:
マーケティングのツールだと、まだまだすべてスマートフォンで利用するには限界があります。利用目的に合わせてどちらも使っていくようなイメージですね。
Webとアプリの垣根がなくなりつつある

飯髙:
最近だと、Webとアプリの差ってほとんどなくなってきていますよね。例えば、Amazonのレコメンドってめちゃめちゃ優秀じゃないですか。Webで定期購入を促すのがもっと当たり前になっていくと思います。そうなって来ると、Webビューとスマホアプリがほとんど同じ役割を果たすようになって、アプリがダウントレンドになっているという可能性もあると思う。
高橋 氏:
アプリって開発料金とプラットフォーム料金が高すぎる問題があると思います。
漫画が読めるWebサービスで考えるとわかりやすいです。漫画サービスの構造上5割~6割の売り上げが著作料になります。そこからアプリだと、残りの30%ほどをプラットフォームに取られてしまう。結果として利益は少なくなってしまいますよね。Webだったら、この30%は必要ありません。
日影 氏:
アプリだと操作性の最適化や、プッシュ通知を発信できるなどのメリットもありますよね。その辺りはどうでしょうか。
高橋 氏:
それもありますが、PWAが出てきていますよね。
飯髙:
PWAに対応すれば、Webブラウザがアプリのように見られますからね。
日影 氏:
そうやって考えると、Webとアプリの垣根がどんどんなくなってきているとも言えるかもしれません。
報道機関のテクノロジー化は遅れている?

米重 氏:
報道産業はほかのメディアと比べると、特に人間が中心です。労働集約的な業界で、なんでも人間がやります。ある意味産業革命から200年経過している中で、最後まで取り残されているような状態です。
コスト構造は重たいまま、滞在時間は他のものに吸い取られている状態なので、収益はどんどん下がっていきます。新聞広告費も顕著に減少しています。購読者の数も減少していて、高齢者しか読まないと言われるようになっていて……いよいよ方向転換もできない。
そのような中で、スマートフォンの新たなプラットフォームで情報を安く仕入れられると、報道産業の持続性も問われてきます。だからこそ、いかにコストを下げながら、付加価値をあげるかが重要になってきています。
これを実現するには、テクノロジーしかないんですよね。なので僕らは報道の機械化に取り組んでいるんです。
高橋 氏:
実際に日経新聞では、AIが記事書いて機械化に取り組んでいますよね。
米重 氏:
そうですね。日経さんみたいにデジタルを徹底的にやっているところもあるにはあります。スマホファーストという次元ではなく、思い切って切り替えられる会社がクライシスから脱却できるのではないかと思いますね。
報道にも個性が必要
高橋 氏:
報道は各社のユニークネスが大事ですよね。実際に新聞を読んでいて、「読売と毎日って何が違うの?」と聞かれて答えられる人は多くないと思います。でもスポーツ報知との違いはわかりますよね。
インターネットとスマートフォンの普及で、ユーザーがメディアを見る機会は増えていますが、ユニークなものでないと結果としてキュレーションになってしまう。
米重 氏:
報道はまだコンテンツをどうやって読者に見せるのかってところができていません。つまりスマートフォンで読んでもらえる工夫ができていないんです。だからこそ、インターネットのまとめサイトなどに我々が想像する以上に読者がいることもある。
高橋 氏:
新しいデバイスで配信すると何か変わるかもしれない?
米重 氏:
今でもタブレットを配ったりはしていますが……。まずはスマートフォンをやっていかないととは思っていますね。新聞社はスマートフォンに到達しているのかって話もありますし。
飯髙:
情報収集の仕方もどんどん変わってきていますからね。その点ではインターネットも新聞も同じだと思います。何者かの共感を得られないと見られなくなっていると考えると、リアルに感じられるかもしれません。
コアバリューがないメディアもありますが、結局見られなくなりますから。
米重 氏:
そこがはっきりしていたら、読者たちがコミュニティを作って、課金や広告以外のビジネスに繋がることもありますよね。
共通デバイスはスマートフォンが最後になるかもしれない
高橋 氏:
iPhoneが発売されて、その時はまさかスマートフォンが世界を変えるとは一部の人以外は思っていませんでしたよね。けれども、スマートフォンは一気に普及していきました。今では多極分散的にイノベーションが進んでいる感覚があります。VRやXR、自動運転車やスマートスピーカー、どんどん多極化して広がっていっています。
これが何を意味するかというと、全員が当たり前に持っているデバイスは終わりに近づいているってことだと思います。VRやスマートスピーカーはこれからもっと普及すると思いますが、10年後に持っていない人もいるかもしれないということです。
これからは人に合わせてデバイスを選ぶ時代が来る。だからこそ、よりエッジなコンテンツが求められていくと思います。
日影 氏:
みんなが持っているデバイスはスマートフォンが最後かもしれませんね。
高橋 氏:
そうですね。ニーズの細分化に対応したデバイスが、今後は増えていくかもしれません。
飯髙:
スマートフォンは「楽に色々」だけど、好きなものがあればそっちに突き進んでいくということでしょうね。
まとめ:スマートフォンで個々人がメディアになる時代
スマートフォンの普及により、情報収集・発信の方法は変化しています。個人が情報を集め発信する機会が増えている今、もはや1人ひとりがメディアのような存在になっているとも言えるでしょう。
- スマートフォンの普及
- Webとネイティブアプリの垣根が無くなる
- 新しいデバイスの登場
時代の流れに伴い新たなテクノロジーが次々と登場しているなか、Webメディアも新聞も問わずあらゆるメディアに共通して「共感」を得ることが大切です。読まれるメディアとして一貫して考え続ける必要があります。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- インデックス
- インデックスとは、目次あるいは目次として登録されている状態のことをいいます。また、ホームページのトップページや、製品ページの最上層ページなど、ほかのページへアクセスするための起点となるページを指すこともあります。会話や文脈によって意味が異なるので、注意が必要です。
- セッション
- Googleアナリティクスは、ホームページに適切に組み込めばアクセス状況を把握できる便利なサービスです。Googleが無料で提供しており、日本でも大手企業や金融機関、政府など、その利用のシェアを広げています。そこで、もっとも基本的な単位がセッションです。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- SaaS
- SaaSとは、Software as a Serviceの略で、ユーザーにソフトウェアの「機能」をインターネット経由で提供することを言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- SaaS
- SaaSとは、Software as a Serviceの略で、ユーザーにソフトウェアの「機能」をインターネット経由で提供することを言います。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- タブレット
- タブレットとは、元々「板状のもの」「銘板」といった意味の単語です。パソコンの分野で単にタブレットといえば、「ペンタブレット」や「タブレット型端末」などの板状のデバイス全般を指します。ここでは主にタブレット型端末について説明していきます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他