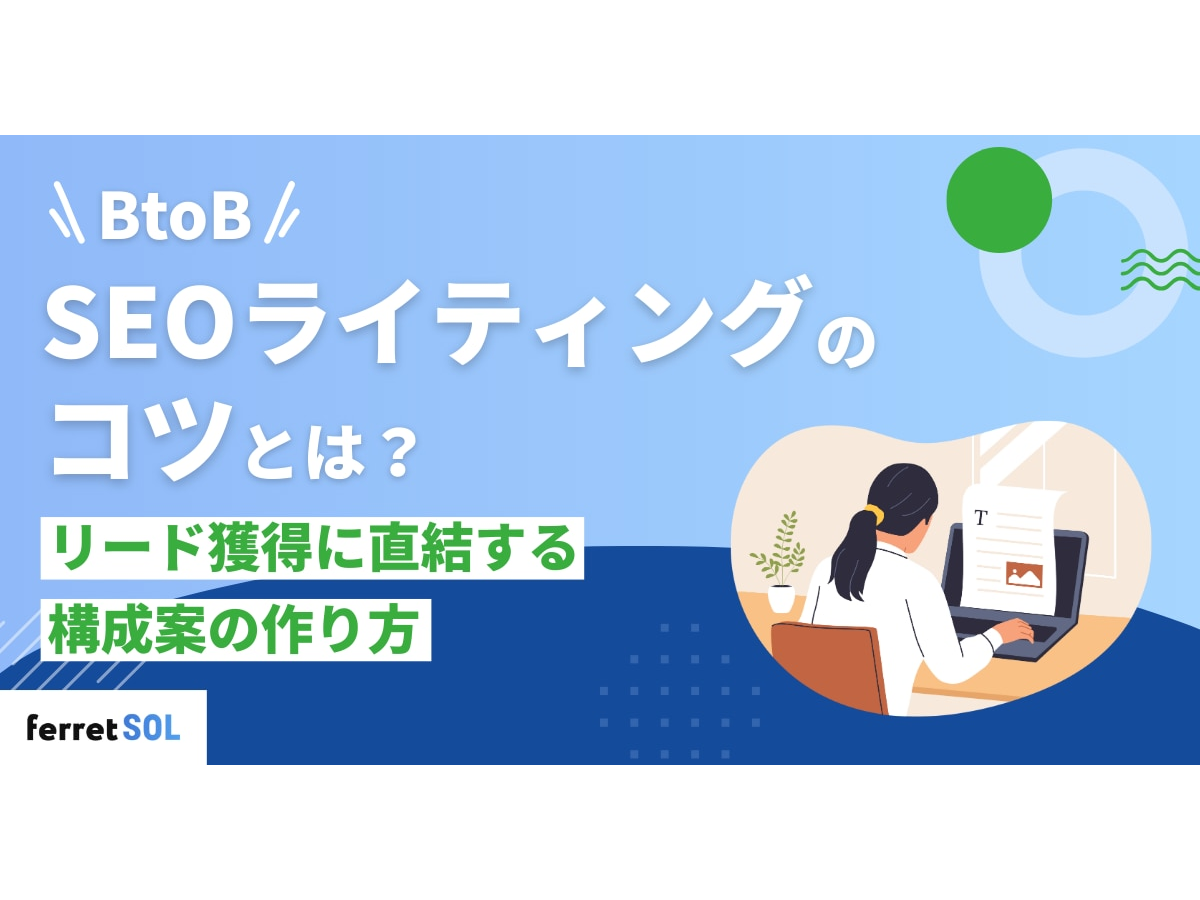コンテンツをターゲットユーザーに届けるための集客手法-第3回FOUND Conference in Tokyo-
1月27日、Ginzamarkets株式会社主催「第3回FOUND Conference in Tokyo」が開催されました。
今回で3回目の開催となる本イベントでは、コンテンツマーケティングの最前線で活躍されている企業のマーケティング担当者を集め、今、そしてこれからのコンテンツマーケティングのあり方について議論が交わされました。
今回は、「コンテンツをターゲットユーザーに届けるための集客手法」をテーマに、異なるプラットフォームでの集客に成功している3社を招いて行なわれたトークセッションの様子をお届けします。
登壇者紹介
亀松 太郎 氏 (弁護士ドットコムニュース 編集長)

1970年、静岡県生まれ。東京大学法学部卒業後、朝日新聞記者になるが、3年で退社。その後、法律事務所リサーチャーやJ-CASTニュース記者などを経て、ニコニコ動画を運営するドワンゴに転職。ニコニコニュース編集長としてニュースサイトの運営や報道・言論番組の制作を統括した。2013年から弁護士ドットコムニュースの編集長として、時事的な話題を法律的な切り口で紹介する新しいタイプのニュースコンテンツを制作し、Yahoo!ニュースなどに配信している。同時に、早稲田大学大学院ジャーナリズムコースの非常勤講師として、ニューズライティングとインターネット放送の講座を担当している。
酒井 亮平 氏(リクルートライフスタイル ネットビジネス本部ネットマーケティングユニット SEOストラテジスト)

1984年生まれ。ネット通販のコンサルティング企業に就職後、大規模サイトのSEOコンサルティングを行う企業に転職。2013年2月、リクルートライフスタイルに入社後は、「ホットペッパービューティー」や「ケイコとマナブ」「じゃらんゴルフ」などのSEOやコンテンツマーケティング業務全般を担当している。
伊藤 新之介 氏(ラフテック 代表取締役)

1988年生まれ、2013年4月、株式会社ラフテックを創業。トラフィックの半分をソーシャルメディアから獲得している月間4000万PV のお笑い特化メディア「CuRAZY」などを運営。
ライター、漫画家、イラストレーター、動画編集者などを内部に抱え、ソーシャルメディアの拡散に特化したコンテンツ制作の統括などを行ってい る。
モデレーター:黒瀬 淳一氏(Ginzamarkets 日本カントリーマネージャー)

筑波大学第三学群社会工学類卒業、神戸大学大学院経済学研究科を終了後、ランディングページ最適化、入力フォーム最適化ソリューションを提供する株式会社アクシイズで取締役を務め、その後、複数企業にて事業開発、営業マネージャーの経験を経て、Ginzamarkets株式会社入社。
自己紹介
黒瀬氏:
「コンテンツを使った集客手法」をテーマに、登壇いただいている3名にディスカッションしていただきます。まずは自己紹介から進めていきます。
私はGinzamarketsの日本カントリーマネージャーを務めています。
当社はアメリカと日本を主な拠点として活動しており、GinzaMetricsというコンテンツマーケティングとSEOのデータ分析ツールを提供しています。
会社として「マーケティングインテリジェンス」をテーマに活動しています。
皆様が、マーケティングを行うにあたり、適切な判断をできるための支援を行っています。
酒井氏:
リクルートライフスタイルの酒井と申します。
弊社は日常消費領域に特化した事業を行っています。ホットペッパービューティーやじゃらんなど、現在35サイト以上を運営しています。私はWebマーケティンググループという部署に所属しており、担当サイトの外部集客を担当しています。
私はコンテンツマーケティングチームのリーダーを担当しています。
リクルートライフスタイルの中でコンテンツマーケティングに携わっているのは10名ほど、その他業務委託で携わっている方も含めると20名、その他外部企業とのやり取りもあります。
弊社のコンテンツメディアは結構たくさんあってですね。現在、ライフスタイルで10サイト以上あります。
基本的にはじゃらんやホットペッパービューティーなど、既存のサービスに紐づくかたちのオウンドメディアを運営しています。
メディアの戦略が一本化されていることはなく、どのようなカスタマーを集めたいのか、どのような目的で行うのかを各サービスの担当者が裁量権を持って、強化する施策を決定して運営しています。
亀松氏:
弁護士ドットコムニュースの編集長をしている亀松と申します。弁護士ドットコムは、依頼者と弁護士をマッチングさせるためのサービスで、弁護士のネットワークを活かしたオンライン相談所を設置しています。
弁護士ドットコムはユーザー層を3つに分けて考えています。
今何か法律が関係するような問題を抱えていて、すぐに弁護士に相談したいという方、裁判というほどではないけど少し法的なトラブルを抱えている方、後は、ほとんどの方がそうだと思いますが、今はトラブルを抱えていないという方の3つです。
今トラブルを抱えていないという方にも弁護士ドットコムを知ってもらいたいということで始まったのが弁護士ドットコムニュースです。
問題を抱えていない方にも興味を持ってもらえるよう、時事的なネタを法律的な目線で掘り下げた内容を配信していて、外部のポータルサイトやキュレーションメディアからの流入が大きいですね。
弁護士ドットコムニュースだけだと、月間訪問者数は400~600万人です。
伊藤氏:
株式会社ラフテックの伊藤と申します。お笑い特化型笑うメディア「CuRASY」を運営しています。現在は月間4000万PVで、SNSからの流入が全体の60%で、バズが得意なお笑いメディアとしてやってます。元々キュレーションメディアの文脈で語られることが多いんですが、僕らはオリジナルコンテンツを作っていたりします。
めざましテレビなどのテレビ番組にデータやオリジナルコンテンツを提供したりしています。
僕らはメディアの人間1人もいなくて、元々エンジニアチームだったんですね。
メディアを運営しなが分散型メディア向けアナリティクスも作ったりしています。
日本語や英語圏のメディアの全記事をクローリングして、シェア数を分析しています。
Netflixがよくやっているんですが、記事にタグ付けをして、トレンド解析を行ったりもしています。
特に力を入れているのが分散型メディアへの移行でして、いわゆる分散型メディアとなると、国内だとPVという指標が大きいんですが、僕らはそこを再定義しようと考えていまう。
例えば最近日本に上陸したBuzzFeed、国内メディアでは月間50億PVって紹介されてるんですが、英語圏では50億CVと書かれてるんですね。
CVというのは「Content Views」の略で、PVに加えて、SNSなどの外部サイト上での動画再生回数や画像クリック数なども含めています。
分散型メディアが進む海外では既にPVからCVに切り替わりつつあります。
それらをまとめて分析できるツールが今無いので、自分たちで独自のアナリティクスを作ったりしています。
なぜこの方法を選んだのか

黒瀬氏:リクルートライフスタイルさんはSEO、弁護士ドットコムさんはニュースからの流入、ラフテックさんはバイラルを通じてSNSからの流入が中心となっていますが、皆様なぜそれぞれその集客手法を選ばれたのか教えてください。
伊藤氏:
僕らは元々マンガ投稿サービスとマンガ制作サービスをやってたんですが、その時からマンガのような娯楽・エンタメコンテツはSEOと相性が悪いなと感じていました。
そこでソーシャルメディアで集客しようと思って、研究していると、どうやらバイラルメディアがトレンドみたいだったので、ソーシャルメディア集客のために実験的にバイラルメディアを始めました。
初月から900万PVいきましたね。
酒井氏:
弊社の場合、メディアごとに戦略が違うので全てSEOを重視しているわけではないんですが、集客戦略として、SEOを重視しているメディアも多いです。。
弊社が運営する主なサービスは、カスタマーとクライアントのマッチングビジネスです。そのため、コンテツメディアのページビューを増やすことは大切ですが、マッチングに繋がらなければ意味がないと考えています。
そう考えた時、SNSで拡散されたり、ニュースサイトに配信することも大切ですが、何かに悩んで検索する人にコンテンツを届けることのほうが大切だったりします。
SEOを重視したコンテンツは、一定の知識があれば検索キーワードを参考に役立つ記事を簡単に制作できるので、取り組みやすいとも思います。
亀松氏:
弁護士ドットコムニュースは僕がいない時から始まっていて、戦略は現社長が決めました。
なぜニュースをやろうとなったのかというと、ニュースの概念がネットの登場で変わってきているからというのが大きいです。
社長がYahoo!ニュースをながめていたら、昔からあるようなマスメディア以外の、今まで聞いたこともないようなメディアの記事が載っている。じゃあ自分の会社でそういうニュースを発信すればヤフトピに載るんじゃないかと。
実際にYahoo!ニュースの担当者に会って、法律の知識を活かしたコンテンツを出したら取り上げてもらえるかときいたら、可能性はあると言われたので始めてみたわけです。そうすると何本かヒットして、再度Yahoo!に相談し、Yahoo!ニュースへの配信を承諾してもらいました。
黒瀬氏:聞いているだけだと簡単そうですが…初めて載るまではどのように進めたんでしょうか。
亀松氏:
ニュースコンテンツで重要なのは、記事を出すスピード感と本数です。社長が編集長を兼務していたときは月10本ぐらいの記事を出して、1本がヤフトピに載るか載らないかぐらいでした。それでもかなり高い掲載率ですが、それぐらいだと効果が少ないので、僕が編集を担当するようになったとき、社長からは「月10本を100本にしてほしい」と言われました。
だいたい半年ぐらいで、月間100本を配信できる体制になりました。
黒瀬氏:一回Yahoo!さんに載るとどれくらいくるものなんですか?
亀松氏:
ヤフトピにのると、記事によってかなり異なりますが、1本あたり、少なくて10万、多いと数百万のPVがあります。これはヤフー側の閲覧数ですが、その1割程度の読者が、配信元である我々のサイトに流れてくるので、かなり影響力があります。サーバーがダウンしたりすることもありました。
プラットフォームにどう対応していくか
黒瀬氏:SEOならGoogle、SNSならTwitter、Facebook、ニュースならYahoo!や配信サイトとそれぞれ利用するプラットフォームがあるかと思いますが、それぞれ日々進化しています。進化するプラットフォームに、皆様どのように対応されているでしょうか?
亀松氏:
最初はYahoo!ニュースを意識していました。
それ以外にもインフォシークやlivedoorといったポータルサイトに記事を配信していきました。さらに、SmartNewsやGunosy、LINEなどのアプリも台頭しているので、それにも対応できるようにしています。
Yahoo!ニュースはかなり厳格にメディアを審査してますが、GunosyやSmartNewsは比較的審査が通りやすいといえますね。
プラットフォームによってユーザー属性が異なるので、それぞれで読まれるニュースは違うかなと思います。
伊藤氏:
FacebookとTwitterに主に施策打ってますね。Facebookページってすごいデリケートなんです。投稿1本滑ると1週間ぐらい響いちゃうんですよ。
コメントシェアされないコンテンツは流してはいけない。それをやってしまうと、そのあとのコンテンツにも大きく響きます。
Twitterに関しては、Twitterトレンド入りするのが一番稼げます。
プラットフォームによってユーザー属性は全然違いますよね。
Twitterは友達と盛り上がる、Facebookはとりあえず褒めるっていう傾向が強いと思います。
黒瀬氏:次に挑戦したいソーシャルメディアプラットフォームはなんでしょうか?
伊藤氏:
やっぱりLINEですね。
実は、10代~20代前半のLINEのタイムラインってアクティブ率ってなかなかすごいんですよ。
個人の投稿に3000シェアついてたりしますしね。
黒瀬氏:最近だと、Twitterが一万文字書けるようになるというニュースが出ていたり、動画が見れるようになったりして、Facebookに近くなっている気がしますが、それでも出し分けは変わらないでしょうか?
伊藤氏:
ユーザーの行動は変わらないと思いますからやはり出し分けは必要でしょうね。
酒井氏:
SEOをやるのであればGoogleの動きを注視するのは基本ですね。
1個1個の事象に一喜一憂するのではなく、Googleがどこに向かっているのかを理解することが大事です。
理解するにあたって、ヘルプや検索エンジンガイドラインを読んで、どのようにコンテンツを作っていくか、コンテンツを作るにあたってどのようなプラットフォームを構築すればいいかを考えています。
黒瀬氏:Googleの仕様変更って激しく変わると思うんですよね。システム部門としっかり連携しないと、Googleとつきあっていくのは難しそうだと思うんですが、そのあたりはどのように対処されているでしょうか。
酒井氏:
そこは、メディアによってバラバラなんですよね。リクルートライフスタイルの中でも、コンテンツマーケティングをどれだけ重視は事業ごとに異なりますし、当然予算の付き方も違ってきます。
ここ1,2年での変化も大きかったですね。モバイルフレンドリーアップデートが出る前は、PC版のコンテンツだけ作っていればよかったのですが、今はスマホ対応しないと、検索順位が低くなってしまうと言われています。
こういった歴史を考えますと、限られた人的リソースとコストの中で、Googleの仕様変更に対応していく体制づくりが大切だと考えます。たとえば、CMSの運用を外部に委託する、もしくは内部でやってしまうとか。
具体的な方法
黒瀬氏:皆さんは、コンテンツを制作する際にどのように企画・制作・分析されているでしょうか?
伊藤氏:
まずフォーマットを決めます。
例えば「◯◯10選」とか。そういったフォーマットにのせて配信するのは効果的ですね。
タイトルもフォーマットの形式がわかりやすいようなものにします。
亀松氏:
うちは毎朝1時間ほど、編集会議をやっています。
専属の編集部員は6人ぐらいいるんですけど、この朝の会議でネタを提案してもらいます。
こういうネタにしようとか、こういう切り口にしようというのをみんなで考えます。
その後、お題を考えて、この人に解説してもらおうという弁護士に電話して、依頼します。OKをもらったら、メールで解説コメントを送ってもらうんですが、そのままでは一般の読者にとって難解な内容ので、我々でわかりやすく編集して、その内容を再度弁護士さんに確認してもらって、記事を公開します。
作成時間は記事によってバラバラです。朝ネタを出して夕方には完成しているものもあれば、2週間以上かかるものもあります。
黒瀬氏:記事のタイトルをつける際のテクニックはありますか?
亀松氏:
やはり、クリックしたくなるタイトルかどうか、ということですね。
Yahoo!って一日4000本の記事が流れてくるんですが、タイトルが悪かったら、編集部の人や読者にまったく読んでもらえない可能性がありますから。
黒瀬氏:面白いコンテンツを出すためのトレーニングは何かやってるでしょうか?伊藤さんどうでしょう。
伊藤氏:
よくやってるのは、国内外のバズった記事をピックアップして、シェア数を隠してどのくらいシェアされたかをあててみたりしてます。それを繰り返していると感覚が身についていく。
酒井氏:
SEOを意識したコンテンツは、まず上位表示したい検索キーワードを選びます。Googleが提供しているキーワードプランナーなどでターゲットユーザーが使いそうな検索キーワードを収集していきます。
収集した検索キーワードは、検索回数や順位データを加味して、選抜していきます。検索されてないキーワードでコンテンツを作っても意味がないですし、コンテンツメディアが上位表示しづらい検索キーワードもありますので、実際の検索結果を見ることも大切です。
黒瀬氏:一定の品質を保つためになにか工夫されていますか?
酒井氏:
弊社はもともと紙から始めているので、そこのノウハウを取り入れています。
紙はウェブのように、簡単に編集することができないので、品質管理の基準が高いレベルで作りこまれています。こういったノウハウをコンテンツメディアに取り入れることで、コンテンツの品質を担保するようにしています。
また、SEO観点では、検索エンジンに取り上げられるための、言語化しにくいノウハウが存在します。そのノウハウを伝えるための方法として、記事の執筆工程を3~5段階に分けて、ライターの方に、フィードバックをするケースもあります。
伊藤氏:
弁護士ドットコムニュースの場合、ヤフトピにはどういう記事があがりやすいんでしょうか?
亀松氏:
オリジナル性が高いものですね。同じ内容のニュースを、新聞系のマスメディアも出したときは、そちらが優先されるんですよね。媒体の信頼性が違うので。なので、弁護士ドットコムニュースでは、我々にしかできない記事を出そうと、常に考えています。
伊藤氏:
直近の例だとSMAP騒動だとどのような記事を出しました?
亀松氏:
SMAP騒動をブラック企業の観点から分析した記事を公開しました。
SMAPの謝罪会見に対して、ネット上では「あれはパワハラだ」という声があがってたんですね。
そこで、労働問題を専門に扱ってる弁護士さんに聞いてみたら、独立しようとする人の退職を拒むような企業の姿勢はおかしいということだったので、そのような内容の記事を出したら、多くの人に読まれましたね。
参考
SMAP謝罪中継「ブラック企業の退職妨害と通じる面がある」労働弁護士が批判|弁護士ドットコム
ニュース
まとめ
企業がWeb上で新規ユーザーを集客する際は、従来であれば検索エンジンかWeb広告の利用がメインでした。しかし今は様々なプラットフォームが台頭し、選択肢が広がっています。
TwitterやFacebookなどのSNSは既に集客手段の1つという認識が浸透しており、ニュースアプリやキュレーションサイトの普及によって、これまでマスメディアのものだと思っていた「ニュース」というカテゴリも、コンテンツを流通させるための1つの手段として利用できるようになってきています。
どの集客手段を選ぶかは、自社ユーザーの属性を見て判断すればいいでしょう。
今回登壇された3名も、揃って「プラットフォームごとのユーザー属性を理解する」ことの重要性を語られています。
自社のユーザーは何を求めているのか、どのような情報が欲しくてどのようなプラットフォームを利用しているのか。
ニーズが件坂していないユーザーを対象とするコンテンツマーケティングは、目的やゴールが曖昧になりがちです。だからこそ、ターゲットユーザーを明確にして企業側でユーザー視点を持てるようにならなければいけません。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ターゲットユーザー
- ターゲットユーザーとは、自社の商品やサービスを利用するユーザー、または、運営するホームページの閲覧を増やしたいユーザーを、性別、年代、職業など、様々な観点から具体的に定めることを指します。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- セッション
- Googleアナリティクスは、ホームページに適切に組み込めばアクセス状況を把握できる便利なサービスです。Googleが無料で提供しており、日本でも大手企業や金融機関、政府など、その利用のシェアを広げています。そこで、もっとも基本的な単位がセッションです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ランディングページ
- ランディングページ(landing page)とは、ユーザーが検索エンジンあるいは広告などから最初にアクセスしたページのことです。「LP」とも呼ばれています。ただしWebマーケティングにおいては、商品を売るために作られた1枚で完結するWebページをランディングページと呼びます。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ターゲットユーザー
- ターゲットユーザーとは、自社の商品やサービスを利用するユーザー、または、運営するホームページの閲覧を増やしたいユーザーを、性別、年代、職業など、様々な観点から具体的に定めることを指します。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他