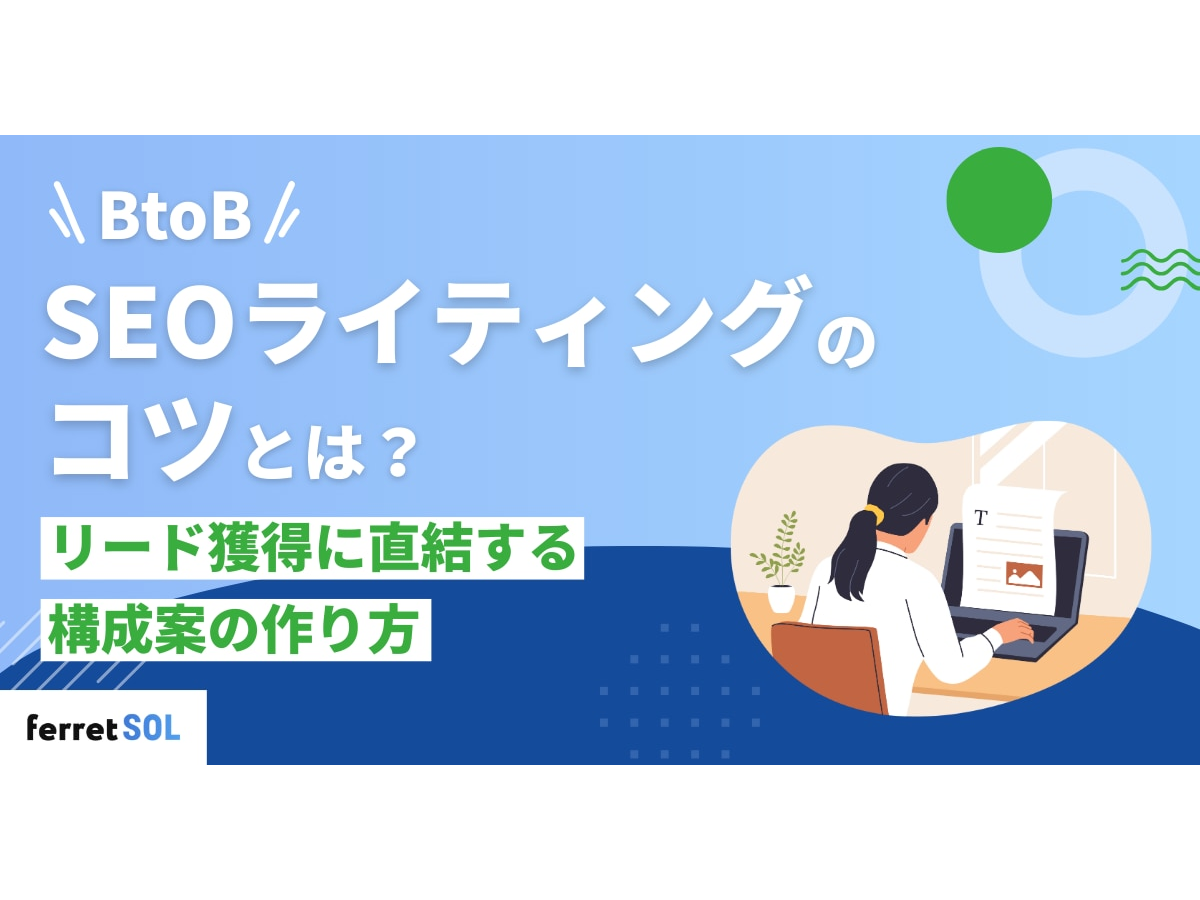「プラットフォームに依存しないダイレクト流入をふやすべき」-これからのWeb集客を考える(okinawa.io 金城氏、おきなわLikes上根氏、ferret飯高)
現在、オウンドメディアやFacebook、Twitter、インスタグラムなど情報発信ツールは無数に存在します。
Webで集客を行うと一言で言っても、何から始めればいいのか、何が重要なポイントなのか、迷ってしまうことが多いのではないでしょうか。
今回は、2016年12月10日に沖縄市コザで開催されたトークイベント「Webマーケティングの本質を読み解くー月250万PVを誇るferret編集長が考えるオウンドメディアの作り方ー」の様子をお伝えします。
東京と地方、それぞれでのファン獲得方法やチャネルに合わせたコンテンツ作成方法など実践的な内容が満載ですので、メディアやSNSなどでWeb集客を行っている方はぜひ読んでみることをオススメします。
登壇者紹介
金城 辰一郎(きんじょう しんいちろう)氏

1987年沖縄県糸満市生まれ。
Webマーケティングを専門領域とし2011年からフリーランスとしてNHKなどを相手にソーシャルメディア運用、コンテンツ企画、イベント等のサポートを行なう。
2013年に起ち上げ間もないBASEに入社し、様々な施策を通してBASEの成長に貢献する。
2016年に独立し、沖縄におけるデジタルマーケティングエージェンシーとしてオキナワアイオー株式会社を設立。
10月に初の著書「チャットボット AIとロボットの進化が変革する未来」をソーテック社より出版。
okinawa.io
上根 麻子(うえね あさこ)氏

琉球インタラクティブ デジタルプランニング局 メディアグループ マネージャー
沖縄県うるま市出身。
高校を卒業後、幼い頃から憧れていた美容業界の道へ進み、エステティシャンとして活動。
その後、Uターンで県内に戻り、2013年4月琉球インタラクティブ株式会社へ入社。
ローンチ間もない「おきなわLikes」のメディアプランナーとして、メディア運営やSNSを駆使したプロモーション等に従事し、沖縄最大級のFacebookページへと成長させる。
分散型メディアへ移行の際は、リーダーとしてチームを牽引。
現在はマネージャーとして、各SNSにおけるコンテンツの工夫やクオリティコントロールを一手に担い、その更なる成長加速に拍車をかけると同時に、若手メンバーの育成にも従事している。
おきなわLikes
飯高 悠太

株式会社 ベーシック ferret Founding Editor/Marketer
広告代理店、ソーシャルメディアコンサルタント、サービス立ち上げを経て、ferretに参画。
これまでに複数のサービス、メディアの立ち上げを経験。ライターとして複数のメディアで寄稿。
Webマーケティングポータル「ferret」の立ち上げからJOINし、1年半で業界No1のメディアに成長。
月間200万PV以上の「働く人を励ます、Webマガジン BookS&Apps」のMarketer。
第1部:オウンドメディアの作り方とは

第1部では、ferret編集長の飯高が「オウンドメディアの作り方」について、約1時間の講演を行いました。
なぜ今「コンテンツマーケティング」がブームなのか
飯高:
なぜ今「コンテンツマーケティング」がブームなのか。
それは、潜在層に向けたアプローチにマーケティングがシフトしてきているからです。
リスティング広告などの顕在層に向けたアプローチは今飽和状態にあります。
その次の段階であるアドネットワークやリマーケティング広告も同じように飽和状態になってきています。
また、少子高齢化により売上が伸びてこないという問題も起きています。
そのため、例えば30代の女性をターゲットとしたオウンドメディアでも、20代のうちからメディアに接触させ、30代になったときにそこからのコンバージョンを狙う、というように「潜在的なユーザーを育てる」ことがポイントとなっています。
顕在層向けのアプローチは今後も獲得効率が良いことは間違いないので引き続き行う必要はありますが、これまであまり注目されなかった潜在層向けの施策も必須事項になったということです。
コンテンツマーケティングを実施することで、企業自身がユーザーの成長を促せるようになりました。
Web集客のメインとなるSEOについても、「コンテンツマーケティングをしっかりやることでキーワードも取れるようになる」と飯高氏は語ります。
多くの企業がオウンドメディアを失敗している
飯高:
現在、オウンドメディアを立ち上げ「失敗」しているという企業が多々あります。
なぜ「失敗」してしまうかというと、部分最適をしているからです。
リスティング・SEO・イベント・メルマガ・記事広告・オウンドメディアなど、各チャネルで部分最適はしているものの、横断的なつながりに欠けています。
オウンドメディアは、そこからすぐコンバージョンすることはあまりありません。
記事を読んでいてすぐ購入に至るわけではなく、まず比較検討をすることから始まり、調べた上で購入する、というのが通常の流れです。
「オウンドメディアを立ち上げたのに一向に成果が出ない」と感じている担当者は少なくないのではないでしょうか。
オウンドメディアに対し、リスティング広告のような直接コンバージョンを期待すること自体が間違いで「間接的なコンバージョンへの貢献度」が評価ポイントとなります。
正しい評価ポイントを理解しなければ、ほとんどのオウンドメディアが「失敗」と見なされてしまうでしょう。
オウンドメディアを成功させるための重要な7つのポイント
飯高:
マーケティングやオウンドメディアなどには、ウルトラCはありません。
重要なことを、当たり前にやり続けることが大事です。
特に意識してほしいのが以下の7つです。
・「誰の何をどのように」を明確にする
・目指すべきゴールとフェーズ
・ペルソナ設計
・カスタマージャーニーマップの作成
・コンテンツ設計
・コンテンツのアウトライン作り
・編集レギュレーションの設定
この7つを徹底してやり続けることで、どのタイミングで効果が出たのか、反対になぜ効果がないのかを見つけやすくなったり、ライターによって記事のレベルに大きな差が出てしまうことを防げたりします。
良いコンテンツを作るために意識するべきこと
飯高:
「良いコンテンツ」を作るために最低限意識してほしいことは以下の5つです。
1.訴求ポイントを探る
2.フックを得たら内容を掘り下げる
3.訴求する際には、具体例と根拠をあげる
4.知らない、お得な、新情報の3つを意識する
5.SUCCEs(シンプル、意外、具体的、信頼できる、情熱に訴えかける、ストーリー性)のあるコンテンツに仕上げる(※引用:アイデアのちから)
この5つのポイントを意識するだけで、ユーザーにとっていいコンテンツに仕上げやすくなります。
コンテンツを発信する際のしくみ
飯高:
オウンドメディアで情報を発信するだけでは、認知度は高まらず多くの人の呼んでもらうことはできません。
新しいコンテンツを出したときにまず最初に拡散のトリガーとなるのが、社内でのシェアです。
社内の一人一人がSNSでシェアすることで、社外の人の目に触れやすくなります。
そして、社外の人がツイートしてくれたら、公式アカウントでリツイートやいいねをして、公式アカウントの認知度もあげていく、というのが大きな流れになります。
一番最初のエンジンとなるのは、まず社内でのアクションなんです。
そのために、社内の個人アカウントを育てていくことも重要なポイントとなります。
拡散が生まれるのはフォロワーを多数抱える著名人がSNSでシェアするのがきっかけになるというイメージが強いかもしれません。
なので自分自身のアカウントのフォロワー数が少ないと、「自分1人がツイートしたところで何も変わらないだろう」と考える方も少なくないでしょう。
しかし、コンテンツを1人でも多くの人に届けるためには、社内のメンバーによる拡散が不可欠です。
自分のツイートを1人でもシェアしてくれれば、そこからさらにインプレッションを獲得できます。
「たいして効果が無い」とあきらめず、地道にSNS発信を行いましょう。
まとめ
今回の講演では、一貫して「ユーザーと向き合い続けること」が重要だと語られました。
ユーザー目線を考えていても、実際は考えている「つもり」で終わってしまっているケースも少なくありません。
ユーザーが何を考え、どのような課題を持っているのかを、ペルソナやカスタマージャーニーマップの設計を通じて明確にしておく必要があるでしょう。
第2部:東京と地方それぞれからのやりかた学ぶ、これからのWeb集客の在り方とは


続いて第2部では、金城氏がモデレーターとなり、上根氏・飯高のトークセッションが行われました。
おきなわLikes・ferretではどのようにWeb集客を行っているのかについてさまざまなテーマでトークが繰り広げられています。
ダイレクト流入を増やせばプラットフォームに依存しない
金城氏:
ferretの一番強い集客チャネルってなんですか?
飯高:
今は検索が強いですね。オーガニック、メルマガ、SNS、リファラルの順です。
金城氏:
網羅的なコンテンツを作っていけばいくほどSEOが起動にのると思うのですが、最初は大変だったんじゃないですか。
飯高:
そうですね、最初はSNSから始めて、1年くらいしてダイレクトかな。
主要なプラットフォームの変化が頻繁にある中で、唯一プラットフォームに依存しないのが「ダイレクト」です。
なので、現在はダイレクト流入を大事にしています。
SNS運用の鍵は「ユーザーの目に触れること」と「コミュニケーション」
金城氏:
おきなわLikesさんは、フォロワーを増やすための施策で具体的に行っていることはありますか。
上根氏:
インスタグラムでは、最初、フォローされたらフォローを返す、写真と相違がないハッシュタグを使う、カメラレンズの設定や撮り方を文章内に記載するということを行いました。
最近は英語でのコメントも多いことや、Twitterでライブ配信したときに海外のコメントもあったことから、各SNSを横断的に見てもらえるようにしています。
昔はFacebookのいいねを獲得しやすかったり、広告が比較的安価だったりしたので、最初は広告を出してました。
金城氏:
最初は広告を使ってファンを獲得し、そこから良質なコンテンツを出すという流れですね。
インスタグラムでのハッシュタグは若者の検索エンジンみたいにもなっていますよね。
沖縄は観光地ということもあって、ハッシュタグで国内外の人が検索していますし。
金城氏:
ferretではどのようにSNSを使われているんでしょうか。
飯高:
基本的には記事を公開したと同時に配信するようにしていて、合間合間に過去の人気記事も投稿しています。
Twitterだと1日約30ツイートですね。
Twitterはツイートする数がそのままタイムラインに出現する数になるので、朝から夜にかけて1時間に1回はTwitter上に現れてユーザーの目に触れるようにしています。
金城氏:
おきなわLikesだと、Facebookなどはどう活用されているのでしょうか。
上根氏:
Facebookはアルゴリズムが変わったり新しい手法が出てきたりしていますよね。
そのため、新しい手法はまず使ってみると反応がよかったりします。
また、ファンとのコミュニケーションを意識的にとりながら、ファンの思いをくみとった投稿をしています。
例えば、沖縄のどこの風景が見たいか事前にアンケートを取り、人気の高かった地域の映像を配信するなどです。
ファンを自分たちのコンテンツにどれくらい巻き込めるかが重要だと考えています。
金城氏:
沖縄ならではのコンテンツですね。今後の手法についてはどのようにお考えですか。
上根氏:
今後の展開としては、SNS内で番組をつくれたりしたらいいなと思っています。
記事コンテンツを安定して生産するためには?
金城氏:
ferretでは1日にどれくらい記事を出してますか?
飯高:
オリジナルが5本、PR TIMESから配信されるものが6本、併せて11本ですね。
金城氏:
外部ライターはどれくらいいますか。
飯高:
3人です。
金城氏:
毎日記事を出すために工夫していることはありますか。
飯高:
内製している記事はコントロールできているため、基本的には記事数が落ちることはありません。
金城氏:
記事のネタはどのように決めているのでしょう。
飯高:
毎週月曜に編集会議をして、キーワードなどからネタを決定しています。
外部ライターとも同様の打ち合わせを行っています。
金城氏:
キーワードの洗い出しはどうしていますか。
飯高:
基本的にとりたいキーワードがデータ化されていて、コンテンツとしては一段落したところです。
Webの流れは早いため、去年のコンテンツが今年変わってたりすることも多く、古い情報は更新するようにしていますね。
分散型メディアは実際どう運用されている?
金城氏:
ユーザーが普段どういった検索をしているのかをしっかり分析してなにを書いていくのかを決めていくのが基本的なコンテンツ作りなのかなというところですね。
分散型メディア(Webサイトを持たず、複数のSNS上で情報発信をしているメディア)の形式をとっているおきなわLikesはどうでしょう。
上根氏:
基本的にインスタグラム、Facebook、Twitterを中心に情報を配信しています。
金城氏:
毎日SNSページは更新されていますか。
上根氏:
1日に1、2回は更新できるようにしています。
金城氏:
予定を組みつつ出しているのでしょうか。
上根氏:
そうですね、PR記事などは先に投稿日を決めて逆算で企画などを検討しています。
オリジナルコンテンツについては、ファンがどういうものを欲しているのかを考えつつ、自分たちも楽しめればいいかなと考えています。
金城氏:
やはり最初は自分のテンションあがる投稿がフックになりますよね。
最近特に当たった投稿ってありますか。
上根氏:
最近だと、360度動画は数字が良かったですね。
また、みなさんが自分ごととして考えられるようなことをキーワードにしつつ、見たユーザーに誤った勘違いを与えないように注釈などもつけた動画も爆発的に人気が出ました。
文章はわたしが考えて、写真はカメラマンが別でいます。
各SNS、日々の投稿がばらばらだし、投稿頻度も違うので、例えばインスタグラムで出てる情報がFacebookでは出てない、ということは普通にあります。
金城氏:
分散型メディアでは各チャネルでファンを獲得していくことが重要ですね。おきなわLikesはWebページがないと思うのですが、ここはどう考えていますか。
上根氏:
Webサイトは不要かな、というところです。
金城氏:
そのメリット、デメリットはなんでしょう。
上根氏:
メリットは、時間とコストがかからないというところです。
あとは商品などは持っていないので誘導先は必要ないかなと。
デメリットは、ストック先がないことです。
記事をためておくことができないので、日々アウトプットしていかないとすぐにリーチが落ちてしまうことはあります。
メディアの付加価値をマネタイズに繋げるためには
金城氏:
基本的にはferretのビジネスモデルでいうとferret oneの販売がメインですよね。
飯高:
そうですね、ただferretとしてもメンバーがちゃんと働けるくらいは稼いでます。
記事広告やメルマガの販売に加え、外部とパートナーを組んでツールやサービスを開発しています。
また、他企業と同時にメディア運営をしていたり、他企業とメディアコンサルをしていたりしますね。
金城氏:
バナー広告を貼らないで、そういうところで稼いでいるんですね。
飯高:
メディアって、ユーザーのことを考えると儲からないんですよ。
メディアに記事広告を入れまくるとユーザーには優しくないですからね。
なので別の部分でマネタイズできたらいいかなと。
金城氏:
おきなわLikesさんはどうでしょう。
上根氏:
おきなわLikesはスポンサー制度を取り、企業さんのプロモーションのお手伝いをしています。
自分たちで持っているファン以上の人に自社の情報を届けるという部分で、サポート役として選んでもらっています。
ただやっぱり記事広告の出しすぎはよくないですし、メンバーも3人なので、月に1企業、2本程度でやってます。
飯高:
リーチ数って保証していますか?
上根氏:
していないですね。
数値はお金に変わるものじゃないことを説明してから、賛同してもらった企業のみ取り上げているので特に問題はないです。
結果報告は毎月だしています。
広告についても、広告を出した方がよさそうな時は出していますが、この判断はこちらでやっています。
基本的には、より魅力的にご紹介しますっていうのがメインにあります。
飯高:
東京だとインプレッションを保証するところが多くて。
ferretはしてないんですけど、さっきもご説明したように記事を読んでそのまま直接コンバージョンはあまりなくて、ferretを読んでその後間接的にコンバージョンしてくれた数を出しています。
おもしろいのが、ferretを読んで、そのあと比較検討して、最後ブランド名を検索してリスティングでコンバージョンしている人が多いことですね。
金城氏:
単に記事を読んでもらうだけじゃなくて成果に貢献しているところに価値があるんですね。
総括
オウンドメディアと分散型メディア、形式は違えど「ユーザーのことを第一に考え続ける」ことが重要なポイントであることには変わりません。
インターネットがこれだけ普及した現在、東京だから情報発信ができる、地方だから情報発信ができないということはありません。
地方だからこそ発信できるコンテンツも豊富にありますので、コンテンツ制作者が実際に触れた、現地だからこそ発信できる情報をあげていくことが重要でしょう。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- リスティング広告
- リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を、有料で表示するサービスのことです。ユーザーの検索結果に連動した形で広告が表示されるため「キーワード連動型広告」「検索連動型広告」とも呼ばれます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- シェア
- シェアとは、インターネット上で自分が見つけて気に入ったホームページやブログ、あるいは、Facebookなど自分自身が会員登録しているSNSで自分以外の友達が投稿した写真、動画、リンクなどのコンテンツを自分の友達にも共有して広めたいという目的をもって、SNSで自分自身の投稿としてコンテンツを引用し、拡散していくことをいいます。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- セッション
- Googleアナリティクスは、ホームページに適切に組み込めばアクセス状況を把握できる便利なサービスです。Googleが無料で提供しており、日本でも大手企業や金融機関、政府など、その利用のシェアを広げています。そこで、もっとも基本的な単位がセッションです。
- オーガニック
- オーガニックとは、検索結果ページに表示されるリストのうち、広告以外のものを指します。「オーガニック検索」、「自然検索」、「ナチュラル検索」などとも言われます。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- バナー
- バナーとは、ホームページ上で他のホームページを紹介する役割を持つ画像ファイルです。画像にリンクを貼り、クリックするとジャンプできるような仕組みになっています。画像サイズの規定はありませんが、88×31ピクセルや234×60ピクセルが一般的です。また、静止画像だけでなく、アニメーションを用いたバナーもあります。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他