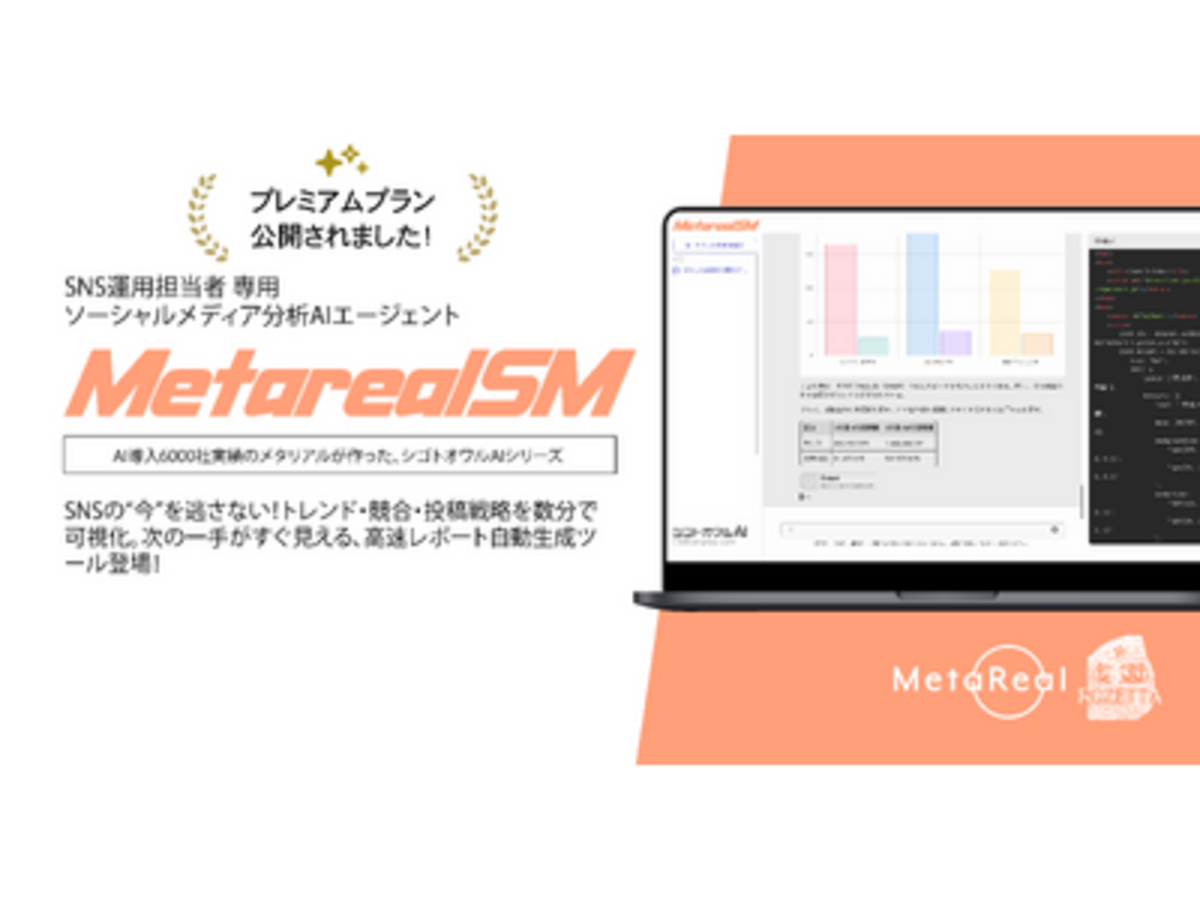SNSとビジネスの相関性!ハロウィン×バレンタイン事例から理解を深める
こんにちは、株式会社ブレインパッドでソーシャルメディア分析を担当している福江です。前回の記事ではナイトプールの事例をもとにソーシャルリスニングの基本的な見方をご紹介しました。
今回はもう一歩踏み込んで、ソーシャルメディアデータとほかのデータを掛け合わせて「SNSとビジネスの相関性」についてご説明します。
参考:
2017年話題の#ナイトプールで学ぶ!ソーシャルリスニングでできること|ferret
ハロウィンとバレンタインの比較からSNS投稿数と市場規模の相関性をみる
2017年も10月に入り、ハロウィンの季節がやってきました。日本でもすっかり定着したハロウィンですが、数年前までは日本でハロウィンをイベントとして楽しむ文化は一般的ではありませんでした。
では、ハロウィンがどのような盛り上がりの推移を辿ったのか、過去のソーシャルデータから見ていきましょう。
2012年まで遡ってSNS投稿を分析
まずハロウィン関連のSNS投稿数を、2012年まで遡ります。また、比較対象としてバレンタイン関連のSNS投稿数も併せて分析します。
ハロウィンとバレンタインは、どちらも日本由来のイベントではなく、企業の販促キャンペーンとして盛り上がったイベントです。実は定着した経緯が類似しており、わかりやすい比較対象として分析します。

※対象メディア :Twitter、Instagram(インスタグラム)
※対象キーワード:ハロウィン、バレンタインのキーワードやハッシュタグ
※対象範囲 :イベント月の投稿数(ハロウィンは10月、バレンタインは2月)
Twitterは2012年以降の全量データ、インスタグラムは2014年以降
※除外投稿 :リツイート、リンク付き投稿
図1を見てわかるとおり、2014年まではバレンタインの投稿数が伸びていたのに対し、2015年からはハロウィンがバレンタインを大きく上回り、2016年にはさらにその差が広がっています。
また、ハロウィンの投稿数は常に右肩上がりなのに対し、バレンタインは2014年から横ばいとなっています。
Twitter、インスタグラムともに日本でのMAU(月間アクティブ ユーザー数)が増加し続けているのに鑑みると、投稿数が横ばいということは投稿に占める割合では減少しているとも言えます。
ハロウィンとバレンタインの市場規模の推移
次に、ハロウィンとバレンタインの市場規模の推移を見ていきましょう。市場規模は関連業界や商品などの総売上を元に推計された金額です。

※日本記念日協会調べのデータを元に筆者がグラフを作成
両イベントの市場規模を比較すると、2016年に初めてハロウィンの市場規模がバレンタインを上回りました。なお、2014年はハロウィンがわずかに上回っていますが、バレンタインの当週に大雪によって物流や交通がマヒし、イベント中止などが相次いたため、イレギュラーとしてカウントします。
先程のSNS投稿数推移のグラフと並べてみると、市場規模はSNSの投稿数の1年遅れでハロウィンがバレンタインを逆転したのがわかります。
余談ですが、2016年ハロウィンの1,345億円という金額は日本記念日協会が推計を行っている記念日の中で「クリスマス」に次いで2番目に大きい金額です。
ソーシャルメディアデータと、そのほかの定量・定性データを組み合わせることにより、市場の「傾向」を見極めることにつながります。
ソーシャルデータも取り入れた統合プラットフォームの構築
もちろん、市場動向は単純なものではなくSNSの投稿数の推移だけで簡単に把握できるものではありません。
ソーシャルデータに絞ってみても、投稿の数(定量データ)のほか、投稿の中身(定性データ)も見る必要があります。
例として、単純にポジティブ、ネガティブといった感情の分類以外に、さらに踏み込んだ要因の部分まで見ることによってその精度は高まります。
ソーシャルデータのような外部データだけではなく、自社で抱えている内部データなどを掛け合わせることによって、今後の”施策”に活用することができます。
以下はデータの掛け合わせのイメージ図です。

※統合プラットフォームの一例
小売系企業なら購買データや顧客データ、スマートフォンアプリをリリースしている企業なら自社アプリのトラッキングデータなど保有しているはずです。過去にイベントやキャンペーンを行ったことがある企業なら、来場者数の記録やアンケートで収集したデータがあるのではないでしょうか。
データ収集を積極的に行っていない企業でも、自社のコーポレートサイトがあれば、Google Analyticsの収集データはあるはずです。
プラットフォームの構築と聞くと敷居が高く感じるかもしれませんが、自社が抱えている内部データとSNSのような外部データを掛け合わせて可視化するだけでも、市場や施策について新たな視点を持つことができます。
SNSはスマートフォンの普及とともに、一部の偏った人々が使うツールではなく、多くの人が利用し、世の中の声や動きをつぶさに把握できるものになりました。企業のマーケティング活動にとっても、重要なデータソースの1つとして”必須”となってきています。
2017年のハロウィンの盛り上がりはどうなる?
最後に2017年のハロウィンの盛り上がりを見てみましょう。(執筆時点では10月初旬のため)9月の投稿数を過去と比較します。

※図4 Twitter、インスタグラムを対象にハロウィン関連のキーワードやハッシュタグを対象に分析。Twitterは2011年から全量、インスタグラムは2014年からの投稿が対象 リツイート、リンク付き投稿は除外
図4を見るとわかるとおり、9月のハロウィン関連の投稿数は2016年から2017年にかけて最も伸びています。すっかり定着したハロウィンの文化ですが、その盛り上がりは留まるどころか、さらに勢いを増しているようです。
まとめ
近年、多くの企業が顧客データの分析やメール配信の最適化など、ビッグデータの活用に力を入れています。
メール配信に比べSNSは歴史が浅く、ソーシャルメディア分析はビッグデータ分析の中でも新しい分野です。そのため、活用事例も少なくどのように自社のビジネスに活かせば良いのかイメージが湧きにくいかもしれません。しかし、SNSは人々の生活に密着した情報をリアルタイムで把握できる貴重な情報源です。
誰もが知りたい市場のトレンドは、ソーシャルリスニングによって捉えることができます。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- コーポレート
- コーポレートとは、日本語の「企業」のことです。インターネット上で「コーポレートサイト」という場合は、企業のホームページであることを表します。また、コーポレートは接頭語として使われることが多く、「コーポレートガバナンス(企業内統制)」などのように、他の単語と組み合わせて使うことが多いようです。会社そのものを指すことが多い「カンパニー」とは使い方が異なります。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- ビッグデータ
- ビッグデータとは、一般に、インターネットの普及とITの進化によって生まれた、事業に役立つ知見を導くためのデータのことを指します。「データの多量性」だけでなく、「多様性」があるデータを指します。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ビッグデータ
- ビッグデータとは、一般に、インターネットの普及とITの進化によって生まれた、事業に役立つ知見を導くためのデータのことを指します。「データの多量性」だけでなく、「多様性」があるデータを指します。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他