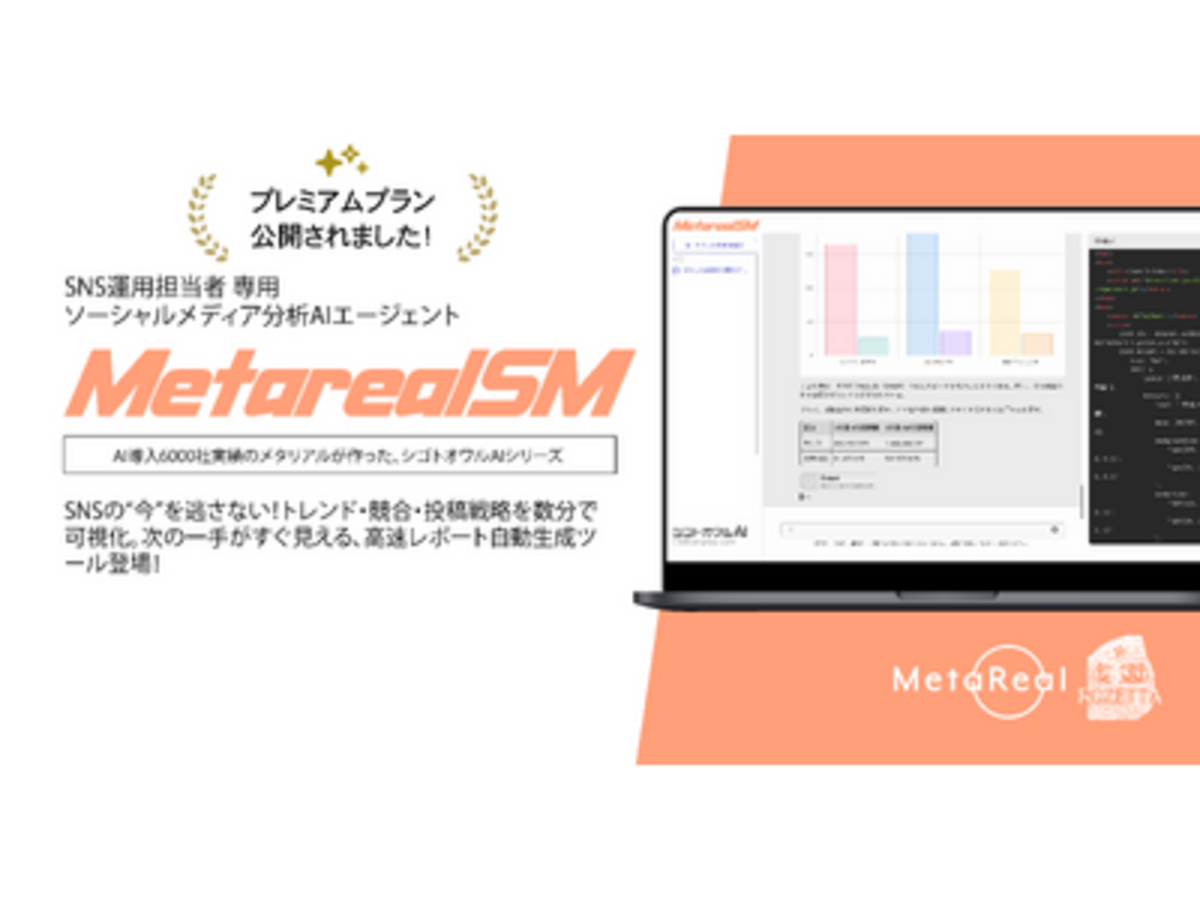情報発信が支援者とのつながりを生む。NPOに有用なツールとは
NPOの活動がメディアを通じて紹介されることは、決して多くはありませんでした。メディアに取り上げられなければ、活動の認知は広がらず、支援者を集めるのも一苦労です。
時代は変化し、インターネットやスマートフォン、ソーシャルメディアが登場しています。メディアに取り上げられずとも、自ら情報発信ができる時代になりました。
NPOも自ら情報を発信し、活動を広げて社会課題の解決をより進めやすくなっているはず。一方で、ツールやサービスを十全につかいこなせているNPOは多くはありません。
今回は、NPOが情報発信を行う上で、検討するべきツールや活用している団体の事例を紹介していきます。
ソーシャルメディアで専門性や活動の様子を発信する
NPOが情報発信を行う際、まず考えるべきは代表による発信です。団体のビジョンや思いを最も説得力ある言葉で語れるため共感されやすく、どんな人が運営しているのかも可視化できるため信頼も得やすくなります。
考えを伝えやすいのはテキストでのコミュニケーションを行う、TwitterやFacebookなどのソーシャルメディアです。これらのサービスは日本でもユーザー数が多く、発信を継続することで注目を集められる可能性があります。
Tポイントで1円から寄付ができます!
— 森山誉恵(NPO法人3keys代表理事) (@3keys_takae) 2017年4月28日
児童虐待の対応件数は年間10万件。
昨年度5万人が使った、親などに頼れない10代向けの支援サービス検索サイトの全国版への拡大や、子ども向けに有料広告表示せず継続運営するために活用します!https://t.co/R7gXYUjT56
活動の様子をこまめに発信したり、自らのNPOが取り組む社会課題に関する専門的な発信などを行うのがおすすめです。専門性やテーマのある情報発信は、フォロワーの獲得につながっていきます。
ソーシャルメディアの発信は、リアルタイム性が求められ、流れていってしまう「フロー」な情報発信です。活動の認知を高めていくためには、別の情報発信手段も用意しておいたほうがいいでしょう。
ブログでの発信は、取材や講演依頼にもつながる
そのために欠かせないツールがブログです。ブログの特徴は情報を「ストック」できるアーカイブ性にあります。
ソーシャルメディアなどで発信した情報も、もう少し文章に肉付けをしてブログに掲載しておくと、NPOの活動や代表に関心を持った人が現れた際にブログを訪れた際に読むことができます。ソーシャルメディアから過去の投稿を探すのは一苦労。どこかに蓄積しておくことを意識しましょう。
アーカイブされていると、活動が継続していること、どのような考えにもとづいて活動しているのかが伝わります。丁寧かつ継続的な発信は、「このNPOを支援するかどうか」を判断する上で、重要な材料になるでしょう。
多くのブログサービスは無料で利用でき、様々なテンプレートも用意されているため、手軽に始められます。

たとえば、若年無業者(ニート)やひきこもり状態など、働きたいけれど働けずにいる若者の自立を目指した就労支援に取り組んでいる育て上げネット理事長の工藤啓さんも、ブログで発信をされています。
工藤さんは「アメーバブログ」上で、活動報告やオピニオン記事を発信。執筆した記事を「Yahoo!ニュース 個人」「ハフポスト日本版」「BLOGOS」にも配信しています。ブログを継続して注目されると、他のプラットフォームへと配信する機会が訪れることもあります。
多くの読者を持つプラットフォームに配信することは、団体の存在や対象とする社会課題の認知拡大に、効果的な方法といえるでしょう。ブログで継続的な発信を行うことで、団体の認知拡大につながり、活動に共感してくれる支援者が生まれる可能性が高くなります。
企業が取り組むオウンドメディアをNPOも
代表個人での情報発信の次は、団体としての情報発信について見ていきましょう。その前に、少し企業の情報発信のトレンドを紹介させてください。
近年、企業が自らメディアを立ち上げ、ブランディングをしたり、サービスや商品を紹介したり、ユーザーを獲得するために情報を発信するケースが増えています。こうした企業が運営するウェブマガジンやブログは「オウンドメディア」と呼ばれています。
NPOの中にも「オウンドメディア」の運営に取り組んでいる事例があり、その代表例が、「病児保育」「障害児保育」「小規模保育」「赤ちゃん縁組」などの課題に取り組むNPO法人フローレンスです。
フローレンスは、オウンドメディア「フローレンスNEWS」を立ち上げ、情報を発信しています。
たとえば、「アクション最前線」というコーナーでは、フローレンス代表の駒崎さんと識者による対談や、事業を始めた背景にある社会構造の問題について紹介しています。子どもの貧困問題を解決していくための事業「子ども宅食」に関する記事では、相対的貧困に関する現状がデータを活用しながら丁寧にまとめられており、非常に読み応えのある内容になっています。

記事の文末にはフローレンスへの寄付や求人へのリンクが貼られているため、共感した人がそのままアクションを起こせるような設計がされています。
実施できれば効果が上がる可能性が高いオウンドメディアですが、課題は立ち上げや運営にかかるコストです。サイト設計やコンテンツ制作、データ分析など行うべき業務も多くあり、まとまった資金も必要となるため、立ち上げるためにはクラウドファンディング等を通じた資金集めも検討するべきでしょう。
資金獲得だけではないクラウドファンディング
では、最後は今話に出たクラウドファンディングについて紹介します。クラウドファンディングとは、インターネットを活用して不特定多数の支援者から資金を集めるサービスのことを指します。
海外から始まったクラウドファンディングは、国内でも複数の事業者がサービスを運営しています。「ジャパンギビング」や「Readyfor」、CAMPFIREの「GoodMorning」など、寄付として資金を受け取ることができる「寄付型」のサービスを提供している事業者も存在します。
NPOがクラウドファンディングを活用することで、資金が得られるだけでなく、クラウドファンディングのサービス上でページを開設すること自体がひとつのチャネルとなり、新しいファン層の獲得につながることでしょう。
クラウドファンディングへの挑戦自体が注目され、メディアに取材されることもあります。
通信制高校・定時制高校の高校生に特化し、独自のプログラム「クレッシェンド」やインターシップなどを展開しているNPO法人D×P(ディーピー)は、クラウドファンディングを上手く活用されています。

D×P理事長の今井さんによるクラウドファンディングでは、直接的な団体の取り組みではなく、自身の挑戦と絡めてクラウドファンディングを行うことで、D×Pの認知度拡大につなげています。
これまでに今井さんは、250kmを走る「サハラ砂漠マラソン」と「アタカマ砂漠マラソン」に挑戦するため、CAMPFIRE上でクラウドファンディングを行いました。前者は520万円、後者は764万円の支援を獲得。プロジェクトページでは、個人の挑戦として取り組む意義だけでなく、事業を行う社会的な背景や具体的な取り組みも丁寧に説明されています。
過酷なマラソンに挑戦することで、高校生にその背中を見せるだけでなく、D×Pの認知度拡大や活動資金につなげているのが印象的でした(マラソン参加のための諸経費は100万円前後ですが、残りは「D×Pへの支援として活用する」と記載されています)。
発信することで支援を集めよう
情報発信は、すぐに効果が出るとは限りません。発信のためには数少ないリソースも割かなければいけません。
しかし、情報を発信することで注目され、支援者とのつながりが生まれます。継続した発信は、寄付の獲得やメディアからの取材依頼、仲間の採用などにつながるでしょう。
活用できるツールは数多く生まれています。ぜひ、NPOとしての情報発信に挑戦してみてください。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他