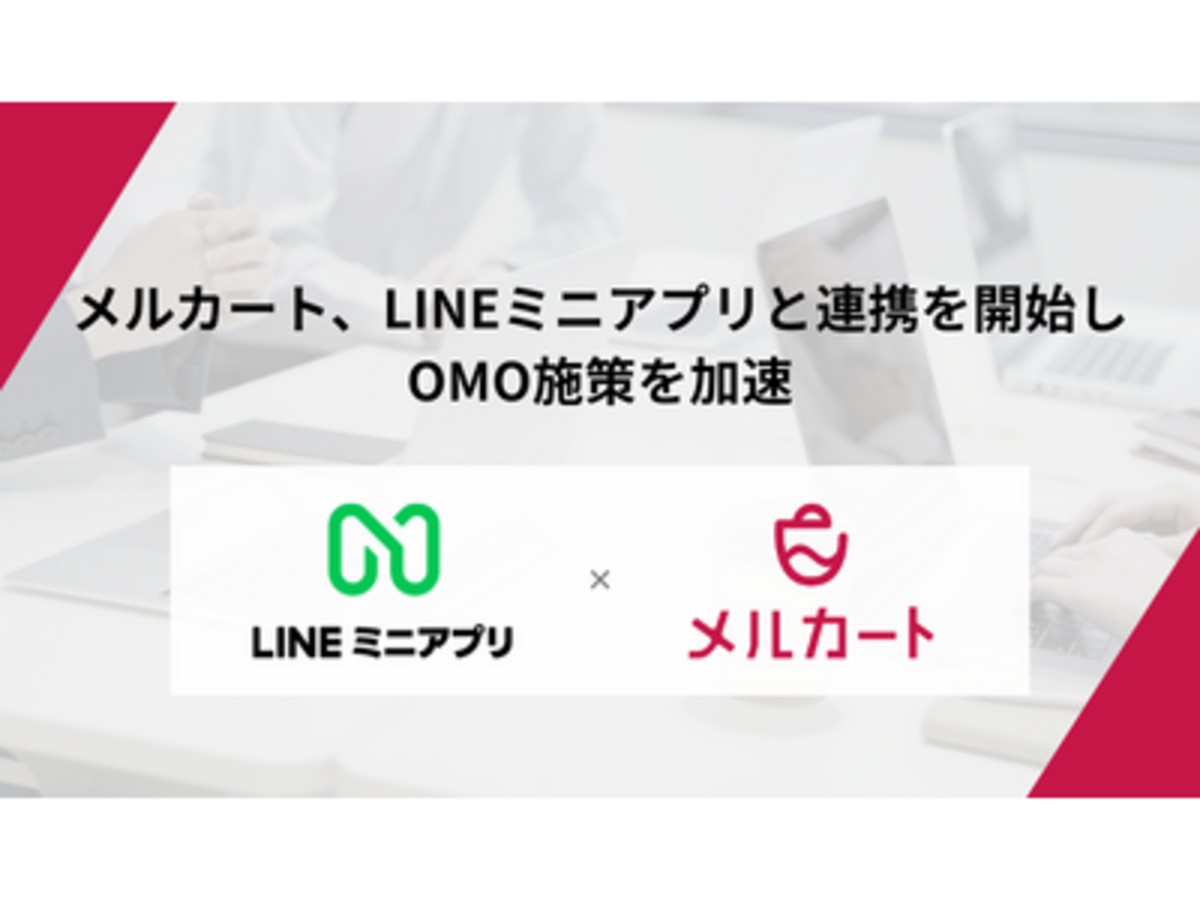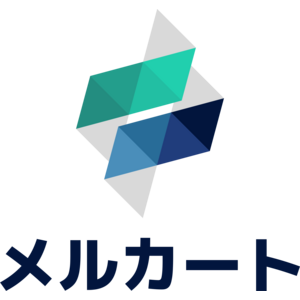ECサイトでは特に重要!サイト運営におけるKGIとKPI
ECサイト運営にあたってやっておきたい事として挙げられるのが、サイトまたは事業自体の「KGI」と「KPI」をしっかり設定することです。サイトの目的が明確でないと運営の仕方もよくわからなくなります。
この記事ではECサイトの担当者向けに、サイト運営における「KGI」と「KPI」の設計について説明します。
KGI、KPIとは
「KGI」、「KPI」という言葉について簡単に説明します。
まずは「KGI」からです。KGI(Key Goal Indicator:重要目標達成指標)とは、あなたの運営するサイトで達成したい目的を、具体的に数字に落とし込んで定量的に表した指標のことを指します。
もう少し具体的に言うと、例えばECサイトなら「売上」だったり、キャンペーンサイトであれば「新商品の認知」といったサイトの目的に対して期間も含めて具体的に数字で設定したものをKGIとするので、
ECサイト→半年後に今の売り上げを2倍にする
キャンペーンサイト→サイトリリースしてから1ヵ月で流入数を10万人にする
といった具合になります。
サイトの目的から、「何を」、「いつまでに」、「どれだけ達成するか」を決定した指標をKGIといいますが、あまりにも無謀な数字ではPDCAも回せないですし、運営していくにあたっての指標としては適切ではありません。KGIは実施施策もふまえ実現可能かをしっかり考慮して設定してみてください。
続いてKPIです。
KPI(Key Performance Indicator:重要業績評価指標)は設定したKGIを達成するために、何をすればよいかを表す具体的な指標のことを指します。
先ほどのECサイトで設定したKGIの例で、KPIを考えてみます。
目標となる売上を達成するために、何をすればよいかを考えるので、売上を構成する要素に分解してみましょう。
・売上=流入数×CVR×購入単価
・売上=新規ユーザー購入金額+リピーター購入金額
例えば上記のような2パターンが考えられますね。
1つ目の場合、流入数、CVR、購入単価をそれぞれ増やせばそれだけ売上は増加させることができるので、KGI達成のための指標として正しそうです。
KPIとしては、流入数とCVRと購入単価のKGIを達成するような具体的な数字となるわけですね。
2つ目については少し違った見方をしています。
売上を構成する要素を、新規ユーザーとリピーターの購入金額という側面で分解しているということです。この時は、新規ユーザーをとにかく流入させたり、リピート率改善を行ったりすることでKGI達成を狙うことになります。
このようにKPIを設定することで、目標に対して具体的にどういった施策をいつまでにどれだけやればいいかが明確になります。
サイト運営にあたって、サイト内のUI向上によるCVRの増加を担う人と、流入を増加させるために広告施策を行う人で担当者が異なる事が多く見受けられ、結局自分は何を達成するためにこの作業をしているのか、目標を見失うこともあります。
そういった時にKPIがしっかり設定されていることで、個々の担当者の意識をKGI達成のためにやっている、と向けることができます。
また、期日と目標数値も決めていて、何をいつまでにやらなければいけないか、が明確なのでサイトの運営効率化にもつなげることができるのです。
ただしKPI設定では気をつけたい点が2つあります。
1つは、KGI達成のために、数字に落とし込めて具体的な施策がわかるものを選ぶこと。
もう1つは、KPIがすべて達成された場合、KGIも達成されるように数値設定を行うことです。
数字での管理をしていくのに定性的な目標となってしまうのはよくありません。
またKGIが売上でKPIを滞在時間の増加にしていては、関係があるかもしれませんが、滞在時間を延ばす施策ばかりやってしまうことになり、売上を達成させることは難しくなってしまうでしょう。
KGIを達成するために、正確な数値設定をする必要があるわけです。
ECでの具体例
ECの場合を例にもう少し具体的に見ていきましょう。ファッション系ECサイトを考えてみます。
A社では前年度10月の売上が2,000万でした。
この時KGを売上前年比120%という目標値を掲げました。
続いてKPIは、
KPI→流入数、CVR、購入単価
KPIとして、この3つに分解できますね。
ここでは、CVR、購入単価は前年度キープで、流入数を前年比120%とさせてKGI達成を狙ってみましょう。
次に考えることは、どうやって流入数を前年比120%にするかなので、ここをさらに分解する必要があります。
サイト流入の仕方としては、検索経由、広告経由、リファラ経由、メルマガ経由など様々です。そうすると、検索を強化するためにページ内コンテンツ量を増やすことに時間を使った方がいいとか、広告はリスティング、アフィリエイト、SNS広告など、どれに費用をかけた方がいいかとか、新規施策として例えばインスタグラムからの流入を狙って、インスタの公式アカウントを開設してみてもいいんじゃないか、など具体的な施策が見えてきます。
そして、具体的な施策ベースまで落とし込めたら、数値の設定をして、何をどれだけ達成すればいいかといったKPIが決定できますね。
このようにKGIからスタートすると、具体的な施策ベースまで分解でき、より効率的に目標値の達成を狙っていくことができます。
また達成できなかった場合も、なぜダメだったか、どこに原因があったか、どれだけ足りなかったかがはっきりわかるので次の施策へ活かしやすいメリットもあります。
時期的な要因や、サイト自体のフェーズによって、都度KGIとKPIは柔軟に変更する必要があります。
例に挙げたファッション系では、毎月売上の最高値を増加、というのはなかなか難しいですし、とにかく新規流入を増やしたいフェーズであればコストがかかるので、利益をKGIには設定しない方がよさそうですよね。
状況に合わせて、的確にKGI、KPIを設計していきましょう。
まとめ:目標値に対して具体的な施策と数値に分解してアプローチしよう
サイトの目的達成のための、KGIとKPIという考え方を説明しました。
言葉自体も混同しやすいので、ぜひ覚えていただきたいですが、大切なのは、目標値に対して具体的な施策と数値に分解してアプローチするという考え方です。
特にECサイトではPDCAサイクルが非常に重要になってきて、何をどう改善すればいいかを適切に判断する必要があるので、しっかりと身につけてサイト改善に役立ててくださいね。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- PDCA
- PDCAとは、事業活動などを継続して改善していくためのマネジメントサイクルの一種で、Plan,Do,Check,Actionの頭文字をとったものです。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- 流入数
- 流入数とは、検索結果の一覧から、もしくは検索連動型広告からなど、特定のリンクを通してホームページにアクセスされた数のことを流入数と言います。流入数が多いとそれだけホームページの内容が多くの人の目に触れているということなので、運営者は流入数が増えるようにマーケティングします。
- CVR
- CVRとはコンバージョンレートの略で、ウェブサイトに訪れた人のうち、最終成果に至った人の割合のことです。たとえば、今まで見込み客であったユーザーが購買客に転換するなど、ユーザーがホームページ運営者側にとって歓迎すべき状態に転換する割合を把握し、ビジネスの精度向上に役立てます。
- 単価
- 商品1つ、あるサービス1回あたり、それらの最低単位での商品やサービスの値段のことを単価といいます。「このカフェではコーヒー一杯の単価を350円に設定しています」などと使います。現在、一般的には消費税を含めた税込み単価を表示しているお店も少なくありません。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- 流入数
- 流入数とは、検索結果の一覧から、もしくは検索連動型広告からなど、特定のリンクを通してホームページにアクセスされた数のことを流入数と言います。流入数が多いとそれだけホームページの内容が多くの人の目に触れているということなので、運営者は流入数が増えるようにマーケティングします。
- CVR
- CVRとはコンバージョンレートの略で、ウェブサイトに訪れた人のうち、最終成果に至った人の割合のことです。たとえば、今まで見込み客であったユーザーが購買客に転換するなど、ユーザーがホームページ運営者側にとって歓迎すべき状態に転換する割合を把握し、ビジネスの精度向上に役立てます。
- 単価
- 商品1つ、あるサービス1回あたり、それらの最低単位での商品やサービスの値段のことを単価といいます。「このカフェではコーヒー一杯の単価を350円に設定しています」などと使います。現在、一般的には消費税を含めた税込み単価を表示しているお店も少なくありません。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- リピーター
- リピーターとは、商品やサービスに愛着を持ち、繰り返し利用してくれるお客様のことです。 リピーターを獲得することは、ホームページを使って売上を上げるためにも重要な指標の一つと言えます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- UI
- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。
- CVR
- CVRとはコンバージョンレートの略で、ウェブサイトに訪れた人のうち、最終成果に至った人の割合のことです。たとえば、今まで見込み客であったユーザーが購買客に転換するなど、ユーザーがホームページ運営者側にとって歓迎すべき状態に転換する割合を把握し、ビジネスの精度向上に役立てます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- CVR
- CVRとはコンバージョンレートの略で、ウェブサイトに訪れた人のうち、最終成果に至った人の割合のことです。たとえば、今まで見込み客であったユーザーが購買客に転換するなど、ユーザーがホームページ運営者側にとって歓迎すべき状態に転換する割合を把握し、ビジネスの精度向上に役立てます。
- 単価
- 商品1つ、あるサービス1回あたり、それらの最低単位での商品やサービスの値段のことを単価といいます。「このカフェではコーヒー一杯の単価を350円に設定しています」などと使います。現在、一般的には消費税を含めた税込み単価を表示しているお店も少なくありません。
- 流入数
- 流入数とは、検索結果の一覧から、もしくは検索連動型広告からなど、特定のリンクを通してホームページにアクセスされた数のことを流入数と言います。流入数が多いとそれだけホームページの内容が多くの人の目に触れているということなので、運営者は流入数が増えるようにマーケティングします。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- 流入数
- 流入数とは、検索結果の一覧から、もしくは検索連動型広告からなど、特定のリンクを通してホームページにアクセスされた数のことを流入数と言います。流入数が多いとそれだけホームページの内容が多くの人の目に触れているということなので、運営者は流入数が増えるようにマーケティングします。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- PDCA
- PDCAとは、事業活動などを継続して改善していくためのマネジメントサイクルの一種で、Plan,Do,Check,Actionの頭文字をとったものです。
- サイクル
- サイクルとは、スタートしてゴール、そしてまたスタートと、グルグルと循環して機能する状態のことを言います。まわりまわって巡っていく、といった循環機構をさすことが多いです。水の循環サイクルというように、実は繰り返しになってしまう使われ方もすることもしばし。また、自転車に関する事柄として、サイクルスポーツなどという使われ方をされることもあります。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他