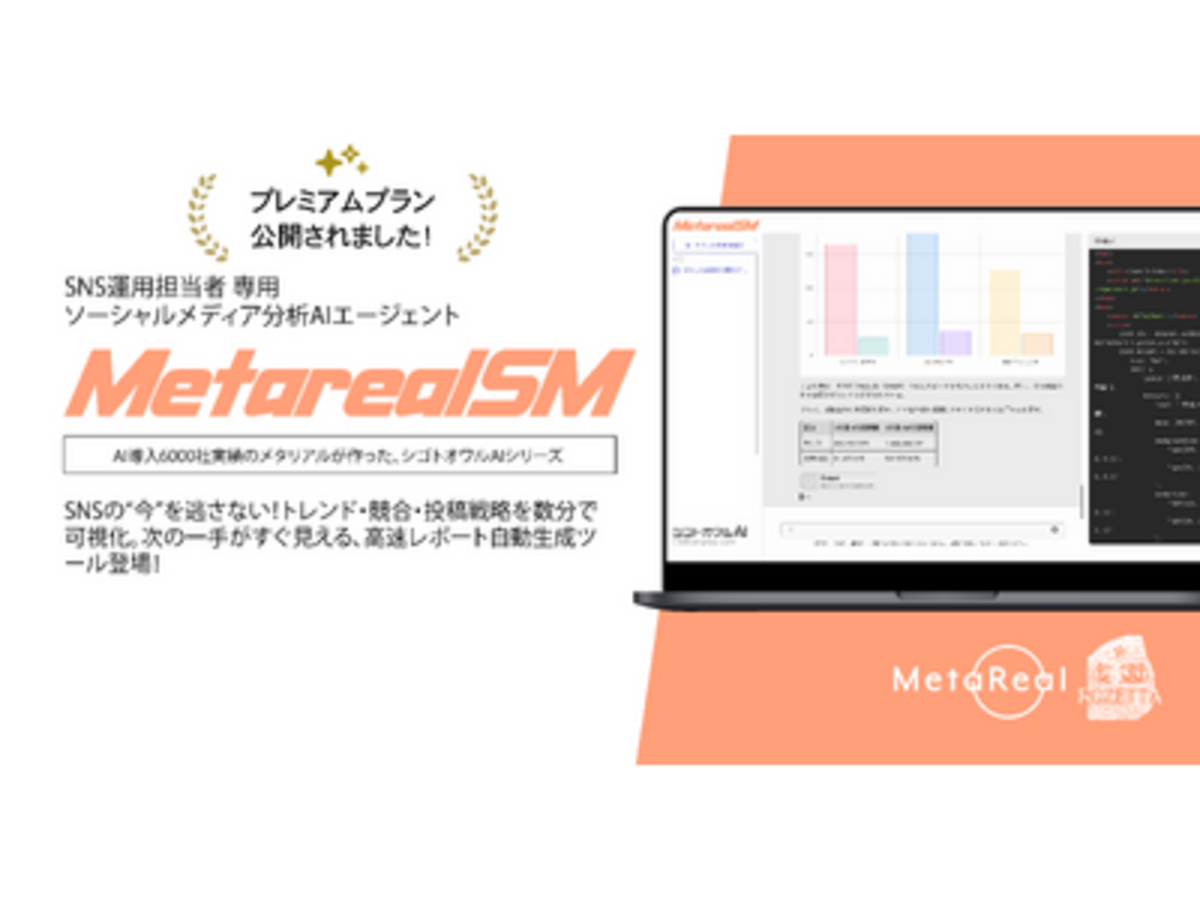Vineがサービス終了に至った3つの理由とは?【衝撃の発表】
2016年10月27日、運営元のTwitter社が、動画共有サービスVine(バイン)の提供を終了することを発表しました。
Vineをご利用くださっている皆さまへ
— TwitterJP (@TwitterJP) 2016年10月27日
日本でも多くの方々にご利用いただいているVineですが、今回の社内改編にともない、数カ月後に提供を終了いたします。現在のご利用もこれまでの作品にも影響はありません。今後、追ってご案内させてください。 https://t.co/AYO1YPaMlZ
Medium上でのVineの声明(Important News about Vine – Medium)

<引用の翻訳>
2013年以降、数百万人の方がVineを使い始め、ループされるVine投稿を楽しんだり、繰り広げられるクリエイティビティに触れるようになりました。本日、我々は数ヶ月のうちにモバイルアプリを終了することを発表いたします。しかし、今日Vineのアプリやウェブサイトにおいて、何か動きが生じることはありません。我々は皆さまと投稿されたVine投稿を大切にしており、正しい方法でサービス終了を進めてまいります。皆さまはVine投稿にアクセスし、ダウンロードすることが今後もできます。我々はこれからもウェブサイトを公開し続けます。なぜなら、我々はこれまで作られてきた全ての素晴らしいVine投稿を今まで通り大切なものであると考えているからです。我々がアプリやウェブサイトに変更を加える前に、皆さまへお知らせを行う予定です。
引用元:Important News about Vine – Medium
かつては企業プロモーションでも積極的に使われていたVineが数カ月以内に終了するという発表を受け、驚いた利用者は少なくないでしょう。
今回は、Vineのこれまでの経緯を振り返り、終了に至った理由を3つに分けて解説します。
そもそもVineとは?
Vineとは、6秒間のショートムービーを制作して共有できるソーシャルメディアです。
アップロードした6秒間の動画が無限ループされる本サービスは、ある時点では2億人のアクティブ・ユーザーを抱えていました。
以下の動画のように、同じ映像が繰り返し自動再生されます。
設立直後にTwitter社が買収、リリース後は1億人以上が利用するSNSに急成長
2012年6月にドム・ホフマンらがサービスを立ち上げ、正式リリース前の2012年10月にTwitterが買収しました。
2013年1月、iOSアプリのリリースを皮切りに、1億人以上が利用するソーシャルメディアへと急成長しました。Facebook など他のSNSとの連携投稿も可能であったため、手軽に情報を拡散できる手軽さがヒットに繋がりました。
以下の記事では企業のVine起用例が紹介されています。サンリオピューロランドやUNIQLOといった名立たる大手企業が、かつてはこぞってVineを使っていました。

アイディアが秀逸!Vineを使った国内企業プロモーション事例5選
今回は、Vineを使った国内企業プロモーション事例5選をご紹介します。 Vineを利用したプロモーションを考えている担当者の方はもちろん、Vine以外の動画配信サービスを利用してプロモーションを行っている担当者の方も、動画作成の参考にしてみることをオススメします。
Vineを利用して拡散する「Viner」
「Viner(バイナー)」とは、Vineを使って動画投稿する人を指します。
6秒という短い時間の中で様々な工夫を凝らした投稿をするユーザーが登場し、1億回以上のループ数を誇るVinerも現れました。
日本でも知名度を得ているのが、大関れいかさんのVineアカウントでしょう。
元々は一般の女子高生であったものの、彼女の投稿は次第に人気を得るようになりました。
これまでに累計9億回以上のループ数を誇っています。
大関さんを始め、Vinerと呼ばれる人は元々一般人だったケースも少なくありません。
知名度に関係なく誰でもインフルエンサーになれる仕組みはVineの成長を促す1つの要因になったと言えるでしょう。Vineの終了が発表された際には、彼女本人もショックであったことを吐露しています。
いやーー!!!!ショックすぎて泣いてる!!w
— 大関れいか (@xtxx_mhz) 2016年10月27日
けどあえて、ありがとう。ほんとvineに出会えてなかったら、やっていなかったら、今の私はないだろうしこんなにたくさんの出会いもなかったなー。愛してるよvine???
Thank you @vine !!
Vineが終了に至ったとされる3つの要因
ここまで順調に成長していたVineが、なぜ突然終了することになったのでしょうか。
大きな要因として考えられるのは以下の3つです。
1.Twitterの身売り交渉の相次ぐ失敗
2.Twitterがアプリ内で動画投稿できるようになったこと
3.インフルエンサーの他媒体への流出
1.Twitterの身売り交渉の相次ぐ失敗
最も大きな理由が、相次ぐTwitter社の身売り交渉失敗とされています。2016年に入ってから、Googleの親会社であるアルファベット、顧客情報管理大手のセールスフォース・ドットコムなどへの売却が相次いで失敗し、Twitter社は経営のスリム化へと迫られていました。
そのため、Vineの終了を発表した日にはTwitter社員へ対する大規模なリストラ計画も発表しました。全社員の約9%が対象とされ、その数は300名近くに及ぶとも言われています。
この余波を受け、Vineのサービス改善へ注力できなくなったのではという憶測も流れています。
2.Twitterがアプリ内で動画投稿できるようになったこと
かつてTwitterで動画をアップロードする際には、YouTubeやVimeo(ヴィメオ)といった外部の動画共有サービスを利用する方法しかありませんでした。そのため、Twitter内で動画コンテンツをスムーズに共有する際には、自社で抱えていたVineへアップロードするのが最も効率が良く、多くのインフルエンサーに重宝されていた背景がありました。
しかし2015年1月からiOS版のTwitterアプリ内にて動画アップロードが可能となり、あえてVineへ投稿する必然性がなくなり始めました。その後Androidアプリやパソコンでの投稿にも対応し、この傾向には拍車がかかったとされています。
また、2016年にはTwitter内でGIF画像の投稿も可能になったことから、Vineアプリの特性であった「短時間のループ再生」に対するニーズとも重なりあってしまいました。Twitterとしては、自社内で似たようなサービスを複数抱えることによるデメリットがあったとも考えられます。
3.インフルエンサーの他媒体への流出
かつては「Viner」と呼ばれる人たちを生み出したものの、ここ数年は情報発信を他のSNSに乗り換える人が少なくありませんでした。事例として紹介した大関れいかさんも、現在はインスタグラムやLINEブログを活用することが増え、Twitterに搭載された動画アップロード機能も頻繁に用いるようになりました。
加えて動画再生回数によって広告収入が得られる「YouTuber」の認知向上や、相次ぐ動画共有サービスの登場により、かつてのVineを取り巻いていたコミュニティへの求心力が弱まるようになりました。
インスタグラムやYouTube、SnapcahtやMixChannelなどといった様々なサービスへの乗り換えが始まり、動画コンテンツの発信者が必ずしもVIneを選ばなくなりました。
Vineスターと運営側との金銭面での対立
2016年3月にBuzzFeed Newsが報じた記事によれば、海外で活躍するVInerを「Vine Stars(Vineスター)」と呼び、Vineの運営チームに対し、彼らから幾つかの提案を行っていたとのことです。
提案内容としては、Vine内にワードフィルター機能(不快なツイートをブロックする機能)を搭載し、Vineスター18人に対してはVineが1人120万ドルずつの支払いを促すものでした。
しかし、VIneスターからの提案は比較的強気なものでした。Vineが受け入れるのであれば週に3本程度の投稿を行うが、もし断るのであれば他の動画配信プラットフォーム(YouTubeやインスタグラム)に移行するという条件を突きつけていたのです。
Vineとしては当初は提案を受け入れる方向ではあったものの、BuzzFeed Newsの報道後に支払いを求めるVineスターが21人に増えたことなどから不信感を示し、支払いに応じることはなかったそうです。また、提案に含まれていたサービスの仕様改善もなかなか行われず、VineスターにとってはVineを使うモチベーションが下がっていきました。
Vineのその後は?
Vineは2016年10月に数ヶ月以内でサービス終了と発表後、2017年1月17日をもって正式にサービス終了となっています。またこれまでは公式サイトにて、過去に投稿された動画のアーカイブにいつでもアクセスできる状態になっていましたが、それも2019年に終了。以降はアカウントごとの固有URLにアクセスするか、Twitterで共有されていた場合のみ、ツイート上で動画を観られる状態になっています。
ユーザーがVineのアカウントページにログインすることもできなくなっているため、実質動画はほぼ観られない状態です。
参考:Vine FAQ|Help Center
身売りの可能性もあった?
Vineのサービス終了が発表されたのちに、運営元のTwitter社には「Vineをサービス単体で買い取りたい」というオファーが相次いでいるとの報道がありました。
Twitter still might save Vine by selling it | TechCrunch
LINEを含む数社が買収に前向きな姿勢を見せていたとのことで、何か動きがあるかもしれないとも予測されていました。しかし、場合によっては買収先でVineがTwitterの競合サービスに変化する可能性も秘めているため、Vineの身売りに関しては一筋縄とはいかないという憶測も流れており、その結果は真意は定かではないものの、サービスは引き継がれず終了に至っています。
Twitterが誰にもVineを助けさせない理由 | TechCrunch Japan
「Vine Camera」への移行に伴い、Vine内でのコミュニティ機能が消失
12月16日、Twitter公式アカウントにて、Vineについての今後の動きが発表されました。
内容としては、Vineのような6秒動画を作成できる「Vine Camera」と、それらの動画をダウンロードできる機能が1月にローンチされるというものでした。
また、今回の発表によってVineはコミュニティ機能を消失し、ソーシャルメディアとしての役割を終えることが、改めて確認できました。その代わり、インスタグラムにおける「Hyperlapse」・「Boomerang」・「Layout」といったサービスのような役割を「Vine Camera」が担い、「Twitterにおける動画作成ツールとしての役割を担い続けるのでは?」という憶測が広がっています。Vineをご利用くださっている皆さんへ:すでにご案内していますように、Vine自体は近い将来サービスを終了しますが、Vineのような6秒動画がつくれるVine Cameraや作品をダウンロードできる機能などを1月にご案内予定です。もう少々お待ちください。 https://t.co/ZnmB2oBjqS
— TwitterJP (@TwitterJP) 2016年12月16日
しかし2020年9月現在、アプリ自体は残っているものの、機能は撮影と編集のみ。ユーザーからは「過去の投稿が観られないなら、Vineである必要はない」という評価に落ち着いています。
参考:Vine-Google Play
VineはVine Cameraに生まれ変わる、Vineコミュニティは消滅 | TechCrunch Japan
ユーザーにとっての利便性を常に追求しなければ生き残れない
かつて企業のプロモーション企画でも重宝されていたVineの存在ですが、隆盛から数年のうちにサービス終了へ至る運びとなりました。Vineを語る上で欠かせないのが、やはりVinerを生み出すコミュニティの存在だと考えられます。
様々な外的要因によってコミュニティが縮小してしまったことから、ユーザーにとって魅力的な場であり続けることができず、Twitterにとっては動画共有手段の1つに成り下がってしまったのかもしれません。
また、Vineはサービスリリース前に会社ごとTwitterへ売ってしまったことから、本発表を受けた創業者が「会社は売るな!」というツイートを投稿する事態にまで至りました。
Don’t sell your company!
— Rus (@rus) 2016年10月27日
確かにTwitterへの売却後、Twitterサービス内への積極的な統合が行われなかった面もあり、ただただサービス終了への道筋を辿るかのように時が過ぎてしまった印象もぬぐえません。
今回の事象から、どんなサービスであってもツールとして止まっているばかりではいけないことが読み取れます。
ユーザーにとって魅力的かつ積極的なコミュニケーションが行われる場であり続けることが、動画共有サービスとしても大切なのかもしれません。
目まぐるしく動き続ける動画共有サービス市場
Vineのサービス終了から読み取れるように、現在の動画共有サービス市場は混沌としています。ひっそりと終わるサービスもあれば、2015年にリリースされた「C Channel」のような新たなサービスもあり、こうした環境の変化に取り残されないよう、最新のトレンドを常に追い続ける必要があります。
ちょっとした仕様変更でも業界としては大きな変化が起こっている可能性もあります。
積極的に情報を収集し、次のトレンドを推測することを心がけましょう。
この記事を読んだ方におすすめ

C Channelから考える、分散型動画メディアを利用したマネタイズ戦略
現在、複数SNSなどのプラットフォームにまたがって情報を配信する、分散型動画メディアの存在感が高まっています。そうした分散型動画メディアをどのようにマネタイズにつなげるか、C Channelの事例を元に考えます。
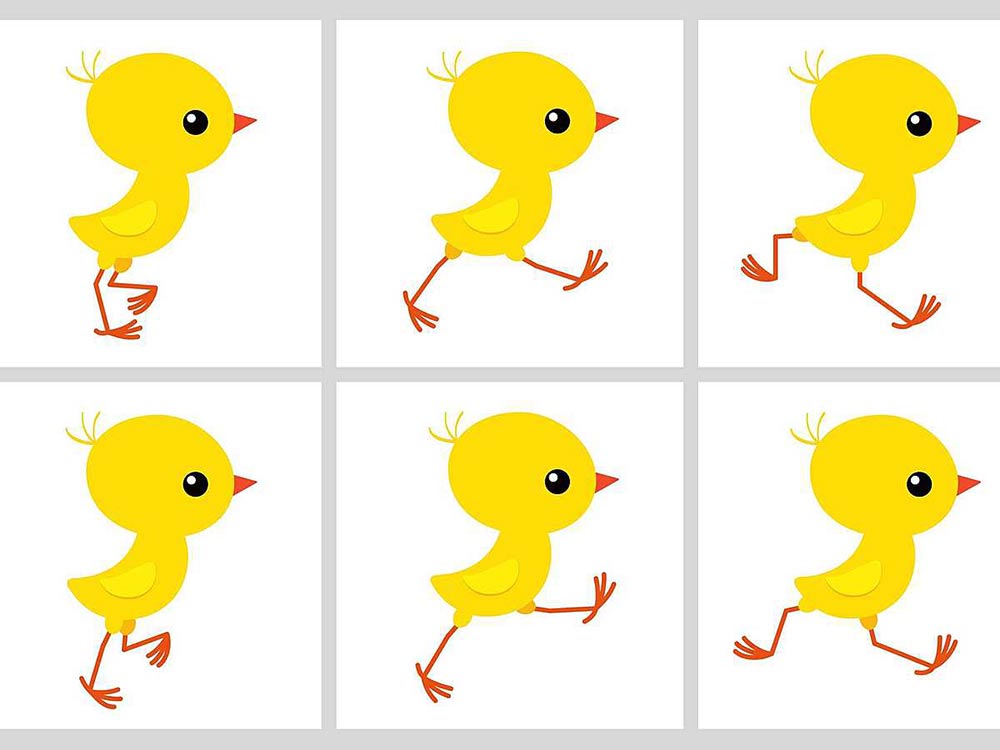
GIF(ジフ)アニメーションの作り方は?無料でGIF作成ができるサービス10選
GIFアニメーションとは、複数の静止画をひとつの動画のようにコマ送りで表示し、動いているように見せる画像のことです。今回は、誰でも簡単にGIFアニメーションを無料で作成することができるソフトやサービスを紹介します。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- Android
- Android OSとはスマートフォン用に開発された基本ソフト(OS)の一種です。米国Google社が中心となり開発されました。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- URL
- URLとは、「Uniform Resource Locator」の略称です。情報がどこにあるのかを示すインターネット上の住所のようなものだと考えるとわかりやすいでしょう。各ページのURLは、インターネットブラウザの上部に文字列として表示されています。日本語では「統一資源位置指定子」という名称がついていますが、実際には日本でもURLという語が使われています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- オファー
- オファーとは、一般的には条件を提案する行為をさします。さらに、ビジネス上では、ある条件を受け入れると、その見返りとして何かが得られる、優遇されるなどの商行為をさすこともあります。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ソーシャルメディア
- ソーシャルメディアとは、インターネット上で不特定多数の人がコミュニケーションを取ることで、情報の共有や情報の拡散が生まれる媒体のことです。FacebookやTwitterなどのほか、ホームページ上の掲示板もこれにあたります。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他