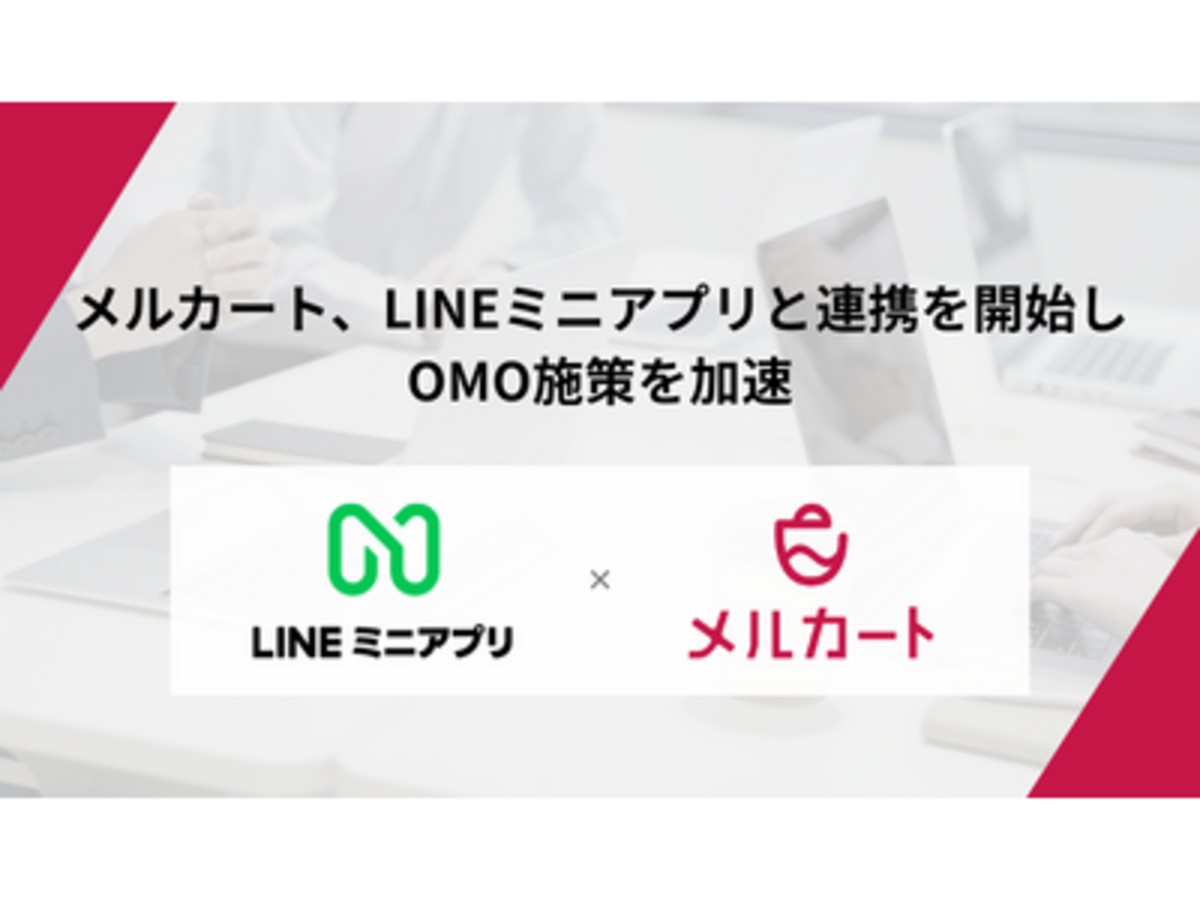ECはスマホ重視に ベテラン担当者が語るECの未来
ECで、スマートフォンを利用するユーザーが増えてきました。2018年3月には、Googleがスマートフォン用ホームページを検索順位の基準とする「モバイルファーストインデックス」の開始を発表し、スマートフォン向けのホームページ作りの重要性がより高まっています。
ECを運営する企業には、パソコンを重視したサイト作りから、スマートフォンを重視したサイト作りが早急に求められていると言えるでしょう。
このような状況を受けて4月12日、株式会社ヤプリ主催の「MOBILE MARKETING UPDATE」で、「モバイルECの現在と未来」をテーマに株式会社ニューバランス、株式会社ケイト・スペード ジャパン、株式会社ディノス・セシール、株式会社ワコールのEC担当者による登壇イベントが開かれました。
紙カタログやパソコンサイトがメインの時代からEC事業に携わってきた4社のEC担当が語る、ECの現状やアプリの活用方法、モバイルECの今後の展開についてレポートします。
参考:
Google ウェブマスター向け公式ブログ モバイルファーストインデックスを開始します
登壇者紹介

左から牧嶋氏、国分氏、石川氏、大藪氏
牧嶋 琢実氏(株式会社ニューバランス ジャパン DTC ECチーム マネージャー)
1971年生まれ。2013年、株式会社ニューバランス ジャパン入社。
DTC Ecommerce Manager。2017年に自社ECサイトをリニューアル以降、ブランドサイトをECサイトに統合。デジタルメディア全般、CRM、リテールを含めたオムニチャネルを推進。
国分 純子氏(株式会社ケイト・スペード ジャパン Eコマース部 アソシエイトディレクター オムニチャネルリーダー)
インポートファッションブランドでの販売職、MD、コンサルティングの経験を経てビジネスを学ぶため渡米、カルフォルニア現地の会社で日本向けEコマースの立ち上げと運営を行い帰国。化粧品やファッションの分野で複数Eコマースサイトの立ち上げに関わり、2013年より株式会社ケイト・スペード ジャパンにてEコマース部を統括。オムニチャネルのプロジェクトなどをリード。
石川 森生氏(株式会社ディノス・セシール CECO EC本部 EC企画部 ゼネラルマネージャー)
SBIホールディングスに入社、SBIナビ(現・ナビプラス)の立ち上げに参画。その後ファッション通販サイト・マガシークでマーケティング部門の責任者として、サイトリニューアルやサイト改善PDCA確立、広告CRM最適化、海外の最先端ソリューション導入を推進。株式会社タイセイのWEB部門を分社化したTUKURUを創業。2016年2月より現職。
大藪 範子氏(株式会社ワコール 通信販売事業部 ウェブストア営業部 ウェブストア営業企画課 課長)
株式会社ワコール入社後商品部、新規事業開発部、全社事業戦略部を経て2000年インターネット推進室を設立。メーカーCRM、Webマーケティングに従事。その後2014年にウェブストア営業部に異動。日々メーカーECのあるべき姿、顧客一人ひとりとのつながりの維持やLTV向上、オムニチャネル推進等で奔走中。
メルマガからSNSへ
少し前までは、ECの流入はメルマガが主流でした。しかしメルマガやホームページは、企業から顧客へ一方向の情報発信しかできません。一方SNSは企業からも個人からも発信ができることから、企業が個人とコミュニケーションを図れ、メルマガに次ぐ手法として導入が進められています。
またSNSといっても、種類は1つではありません。企業にはFacebookやInstagram、Twitter、YouTubeなど様々なチャネルでの発信が求められています。
ニューバランスの牧嶋氏はSNSの取り組みについて、チャネルを分けることでコンバージョンよりもエンゲージメントを強化していると話します。

「ニューバランスではほとんどすべてのSNSを運用しています。TwitterはEC担当者がアクイジションに注力しながら運営し、FacebookやInstagramは各スポーツカテゴリで担当しています。サッカーをする人を応援する取り組みや、その肌感を伝える取り組みなど、ライブ感を大事にするソーシャルネットワークを育てていこうと考えています。そこから顧客がECへ流れてくる恩恵を受けていますが、売りのコンバージョンというよりはエンゲージメントを意識してFacebook、Instagram、YouTubeを使っていますね。」(牧嶋 氏)
SNSを運営している企業の中には、各種SNSを商品のPR手段として積極的に利用することもあるでしょう。
しかし、牧嶋氏はSNSで有益な情報を発信したとしても「これは宣伝だ」と思われてしまうとユーザーが離れてしまうと話します。
「ソーシャルネットワークで役立つ情報があっても、それが物を売るためにやっているという匂いがしただけで嫌われてしまうことがあります。ブランドのファンをいかにして増やすかと考えた時に、真面目に応援している姿を発信していくことが大事だと思っています。」(牧嶋 氏)
LINEは新規顧客よりも既存顧客に有効?
顧客と密にコミュニケーションが取れ、エンゲージメントを高められるツールとして、各企業はLINE公式アカウントやLINE@を利用しています。
LINE公式アカウントを運用しているワコールの大藪氏は、運用当初は新規顧客の獲得ができるのではと考えていたそうです。しかし、実際にはLINEで獲得できた顧客のほとんどが既存ユーザーだったと話します。

「LINEは若い子が利用しているイメージがあったのですが、蓋を開けてみると(ワコールの)ターゲットの年齢と近かったんです。意外と年配の方がたくさんやっていることが判明しました。新規がたくさん取れるだろうと期待を込めていたのですが、LINEを通じて商品を購入した人の半数ぐらいが既存顧客でした。」(大藪 氏)
ディノス・セシールの石川氏も、LINEで新規を取るのは難しかったと話します。
「3月にLINEスタンプを配布して1千万ぐらいファンを集めました。新規の方が反応できるような商品を集めたのですが、新規率は4%でした。」(石川 氏)
ブラウザとアプリの違いは?ECにおけるアプリの価値
パソコン用、スマートフォン用のホームページ以外に、自社のECアプリを導入する企業が増えています。SNSアプリによる集客で既存顧客の購買体験をより便利にすることが求められている中、購入までシームレスにつなぐことが重要となるようです。
セール特価のアプリとテレビショッピングと連動したアプリの2つを導入しているディノス・セシールの石川氏は、ECアプリはブラウザと比べてホーム画面からワンタッチで商品を購入できる点が優秀だと話します。

「僕個人の意見ですが、ただブラウジングするだけのECアプリには価値がないと思っています。セールアプリは在庫をさばくチームがあるので、そこをロイヤリティの高いお客様に対して訴求するツールとして運用しています。テレビショッピングアプリは、テレビを見てブラウザで検索するよりは、ワンタッチで購入してもらう方が良いので作りました。テレビショッピングは、お客様の意欲が高い時に購入してもらった方が良いのでワンタッチで購入できた方がいいんです。」(石川 氏)
アプリはメルマガよりも手軽
また、ECアプリはメルマガよりも手軽にユーザーへ情報を届けられるツールとしても価値があります。メルマガの場合、ユーザーへメールを送るためにはホームページにアクセスしてもらい、メールアドレスを入力してもらう必要があります。しかし、アプリはQRコードを提示しておくだけで、ユーザーが手軽にダウンロードできるのです。
実際にECアプリを導入しているニューバランスの牧嶋氏は、アプリダウンロードの手軽さについて以下のように話しています。

「アプリのダウンロードはメルマガと比べて圧倒的に手軽です。メルマガで会員を集めるのは大変ですから。例えば、アプリならイベントでQRコードを表示するだけでダウンロードしてもらえますよね。ユーザーの手間が圧倒的に少ないんです。(ニューバランスでは)最近アプリ経由の売り上げが向上しています。Googleで検索してからECサイトにアクセスするよりも、ワンタップで立ち上げられるアプリはお客様にとって1番身近な入り口になっているのです。」(牧嶋 氏)
さらに牧嶋氏は、アプリにはロイヤリティの高いユーザーが集まりやすいと話します。ユーザーは、ニューバランスのロイヤリティプログラムをアプリでチェックするため、ニューバランスが好きな人がアクティブにアプリを利用するのです。
ECアプリでスマートフォンの接点が増える
ECアプリの導入は、ユーザーがECサイトにアクセスする機会を増やしてくれます。以前はECとユーザーの接点はメルマガが中心でした。しかし、アプリの導入により、プッシュ通知を利用して直接メッセージが送付できるようになりました。メールに依存していた顧客との接点がアプリのプッシュ通知によって増えているのです。

「アプリによってモバイルの中のタッチポイントが増えたと感じています。今まではメールだけに依存していましたが、アプリにはプッシュ通知の機能があります。プッシュ通知を使って、色々なコンテンツを違う切り口でユーザーへ発信できます。」(国分 氏)
3年後、PCサイトはいらなくなる?
スマートフォンが普及する前までは、ECと言えばパソコン用ホームページがメインでした。今はパソコンよりもスマートフォン用のホームページに重きを置く企業が増え、スマートフォン経由の売り上げが増加しています。
これから、EC事業はどのような動きをみせるのでしょうか。
モバイルECの未来について、「3年後はPCサイトを作らない未来が来るかもしれない」と、ケイト・スペード ジャパンの国分氏は予想します。

「3年経つとモバイルECはもっと大きくなると思います。おそらく3年後のEC事業部で議論しているのは、”PCサイトどうする?”ってことです。今はまだ利用している方がいるので作っていますが、もしかしたらあえて作らないという方向性も出てくるかもしれません。PCサイトはニーズがかなり限定的になってくるのではないかと思いますね。」(国分 氏)
また、ディノス・セシールの石川氏は、データを収集するツールとして、モバイルはさらに活躍していくのではと話します。
「モバイルはデジタルデバイスの中で最も生活の中に入り込んでいるツールです。ただのチャネルではなく、生活者が何を欲しいと思っているかというデータを収集するためのデバイスとして見ていこうと思っています。今までもホームページまで来てもらえればデータは取れましたが、リアルも含めた中で生活者がいつ何をしているのかを可視化できるのがモバイルだと思います。しかし、サービスと引き換えでないとデータはもらえません。我々のサービスを使ってもらって、データをもらう。そのデータから今までにないものを提供したいと思っています。」(石川 氏)
石川氏が期待するように、モバイルによって今までは収集することができなかったデータを収集できるようになっています。例えば、位置情報を使ってリアル店舗の来店履歴がわかり、SNSでの交流からその人の趣味・趣向、友人関係・家族構成などが可視化できるでしょう。
どう対応する? ECの課題
「試着ができない」問題の解決策は模索中
しかし、こうしたデータ活用はECの大きな課題である「試着ができない」という問題の解決策には繋がっていないのが現状のようです。
継続できる施策を考えるべき
ECで注文した商品が届いた時に、「服や靴のサイズが合わない」「思ってたイメージと違った」となった場合、EC側は返品無料として対応します。牧嶋氏、石川氏ともに、これらの問題に対してサスティナビリティの視点を指摘しつつも、返品問題について地道な取り組みが必要と言います。
「試着ができないことは問題ですが、大事なことはサスティナビリティです。返品無料やお試しなどを継続していくのは経済的に難しい。ニューバランスのリアル店舗では3Dスキャナで足の形を数値がする仕組みがあり、その数値をマイページで保存して、それを見ながら電話やWebで接客をして、正しい案内ができるようにしていきたいです。」(牧嶋 氏)

「返品無料にしてお客様に安心してもらいたい気持ちもある一方、リテーラーがそこまで負担するのは難しいと思います。しかも、返品作業はお客様にとっても手間です。サイズデータを保管して、サイズ違いが起きないようにしていきたいですね。」(石川 氏)
スマートフォン前提のホームページ作りを
情報過多により、ユーザーが商品を選ぶのが難しくなっているとも言われています。ZOZOTOWNの「おまかせ定期便」のように、企業側がユーザーに合った商品を選び提供するようなサービスも増えてきています。
「情報がありすぎてどの商品を選べば良いかかわからない」悩みを抱えるユーザーに対して、企業はどのように商品を提案していくべきなのでしょうか。
「お客様が商品点数が多くて選ぶのが億劫と感じる原因として、Webサイトのスマホ化が挙げられます。ケイト・スペード ジャパンの場合、スマホサイトもパソコンサイトも商品点数は変わりません。にもかかわらず、スマホになってから商品が選びにくく、商品点数を多く感じているユーザーがいます。その中で気を使っているのは、どのような商品を販売するのかということです。ECはスマホで購入されることを前提に考えていかなければいけません。A/Bテストを繰り返しながら、サイト開発をしていく必要があります。」(国分 氏)
パソコンで見るホームページとスマートフォンで見るホームページの印象は違います。企業はユーザーがスマートフォンで買い物をしていることを前提に開発し、より買い物をしやすいホームページ作りを心がけていくべきでしょう。
まとめ:ECの主役はスマートフォンへ
ECの主要デバイスはパソコンからスマートフォンに移行しています。それに伴い、企業はSNSやアプリを活用して顧客との新たな接点を持てるようになりました。
SNSは、企業と顧客が密にコミュニケーションを取れる手段として、アプリは手軽に顧客へ情報を発信できる手段として。
これらのツールはうまく活用することで、企業にとって大きな武器になってくれるでしょう。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- インデックス
- インデックスとは、目次あるいは目次として登録されている状態のことをいいます。また、ホームページのトップページや、製品ページの最上層ページなど、ほかのページへアクセスするための起点となるページを指すこともあります。会話や文脈によって意味が異なるので、注意が必要です。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- CRM
- CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、直訳すると顧客関係管理となります。
- オムニチャネル
- オムニチャネルとは、様々な販売チャネルを統合することで、顧客はリアル店舗やオンラインショップなどのチャネルの違いを問わずに買い物をすることができます。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- オムニチャネル
- オムニチャネルとは、様々な販売チャネルを統合することで、顧客はリアル店舗やオンラインショップなどのチャネルの違いを問わずに買い物をすることができます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- PDCA
- PDCAとは、事業活動などを継続して改善していくためのマネジメントサイクルの一種で、Plan,Do,Check,Actionの頭文字をとったものです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- CRM
- CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、直訳すると顧客関係管理となります。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- CRM
- CRMとは、Customer Relationship Managementの略で、直訳すると顧客関係管理となります。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- LTV
- LTVとは、Life Time Value の略で、ある顧客1人または1社が、企業にもたらす価値の総額のことを言います。
- オムニチャネル
- オムニチャネルとは、様々な販売チャネルを統合することで、顧客はリアル店舗やオンラインショップなどのチャネルの違いを問わずに買い物をすることができます。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- エンゲージメント
- エンゲージメントとは、企業や商品、ブランドなどに対してユーザーが「愛着を持っている」状態を指します。わかりやすく言えば、企業とユーザーの「つながりの強さ」を表す用語です。 以前は、人事や組織開発の分野で用いられることが多くありましたが、現在ではソーシャルメディアなどにおける「交流度を図る指標」として改めて注目されています。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- スマホサイト
- スマホサイトとは、スマートフォンからの閲覧に対応したホームページのことです。スマートフォンは、画面サイズや操作方法がパソコンとは異なります。そのため、訪問ユーザーが快適に閲覧できるよう、パソコン用のホームページとは異なるデザインのスマホサイトを用意するホームページが増えています。
- A/Bテスト
- ホームページを作るときや何か商品を売りたいときに掲載する写真、あるいはデザインで迷ったときに、不規則ででたらめな順番でホームページや画像のデザインを変えて表示し、利用者がどちらをより多くクリックしたのか、より多く購入につながったのか、ということを試験できる技術やサービスまたは行為自体をA/Bテストといいます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他