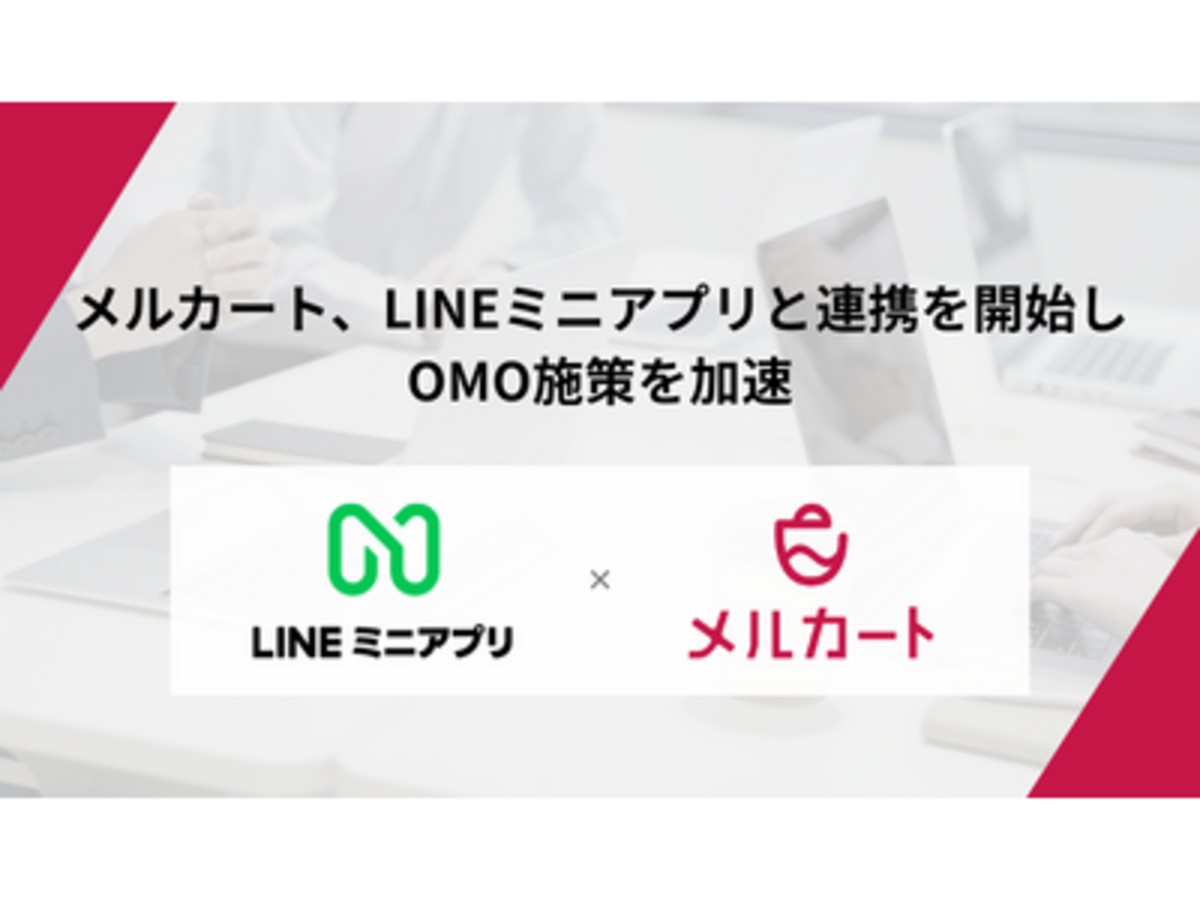未経験から始めるEC運営!売れるECサイトづくりに必要な知識・スキル
ECの市場規模が急速に拡大する中、これからECサイトを立ち上げたいと考えている人も多いのではないでしょうか。
しかし、まったくの未経験だと「まずは何から準備するべき?」「日々のToDoは?」「社内体制はどうやって構築すべき?」など、数多くの疑問が浮かんでくるものです。
そこで本記事では、実際のEC運用で発生するタスクや必要となるスキル、費用、特定の作業を外注し運用体制をうまく構築するためのポイントなどについて解説します。
目次
- 急速に拡大する物販系BtoC-ECの市場規模
- ECサイト運営とは
- EC運営で日々やるべき業務内容は?
- ECサイト運営で必要となるスキル
- ECサイト運営にかかる費用
- 外注すべき作業内容は?
- 社内の説得方法は?
- スキル・知識を身につけて売れるECサイトを立ち上げよう
急速に拡大する物販系BtoC-ECの市場規模
2020年から2021年にかけて、新型コロナウイルス感染症拡大に伴う巣ごもり消費の影響で、物販系分野BtoC-ECの市場規模は大幅に拡大しました。経済産業省も「巣ごもり消費が我が国のEC市場規模を約1.2兆円底上げした」と報告しているほどです。
以下のグラフを見ても分かる通り、コロナ禍以前からの推移を見ても、EC市場規模が年々拡大していることは明白でしょう。
【物販系BtoC-EC市場規模およびEC化率の経年推移】


画像出典:令和3年度デジタル取引環境整備事業(電子商取引に関する市場調査)|経済産業省
実店舗を構える事業者がECに参入した場合、オンライン上に新たな顧客接点が増えることになります。
Web検索をきっかけに自社の存在そのもの、あるいは商品・サービスを知ってもらえる機会が増えるため、遠方の顧客や実店舗とは異なる年代の顧客など、従来リーチできなかったユーザーの獲得も期待できるでしょう。
今後EC化を検討している方は、ぜひそのようなメリットも踏まえてサービス設計を考えてみることをおすすめします。
ECサイト運営とは
ECサイト運営とは、その名の通りインターネット上のショッピングサイトを運営し、商売を行うことです。ECサイト運営に必要な業務は多岐にわたり、大きく以下の2つに分類されます。
| 業務の種類 | 概要 |
|---|---|
| フロント業務 | 商品の企画や仕入れ、サイト制作、プロモーションなど、マーケティングを中心とした業務 |
| バックエンド業務 | 受注処理や在庫管理、出荷・配送など、商品が購入されてから発生する業務 |
フロントでは、ECサイトにユーザーを集めたり購入を促したりといった売上に直結する業務を行います。一方でバックエンド業務は、商品を顧客へスムーズに届けるための事務処理や問い合わせ対応などを行うので、顧客満足度を高めるために欠かせません。
これら2種類の業務を円滑に進めることが、ECサイト運営の成功につながります。
EC運営で日々やるべき業務内容は?
ここからは、実際のEC運営で日々取り組むべき業務内容を解説します。
①販売戦略
販売のための準備・戦略立案です。
●施策立案
目玉商品やセールの投入計画を作成します。年間における繁忙期や売上が落ち込む閑散期、通常期を把握し、人員配置・在庫補充・集客施策など「いつ、何に注力すべきか?」について計画を立てます。
●売れる商品の在庫予測
在庫管理は、ECサイトを成功させるために重要な業務です。例えば、注文が入っても在庫不足による納期遅れを起こすと顧客の不満につながり、問い合わせ・クレーム・キャンセルに追われる事態にもなりかねません。
顧客の満足度を高めるために、注文数が増加してもすぐに届けられるよう、人気商品などの在庫はしっかりと確保しておきましょう。
●売上月報作成
日別・月別の売上実績がいくらだったか実態を常に把握し、数字に基づいて次の打ち手を考えます。
●情報収集
クリスマス・バレンタインといった一般的なイベントや市場のトレンドを把握し、売上につながるきっかけ作りをします。情報収集をする際は、SNSやニュースサイトなどを活用するとよいでしょう。
②ディスプレイ・プレス業務
ブランドイメージを上げる・伝えるための業務です。
●商品撮影
ECサイトに掲載するための商品写真を撮影します。アイテム数が多ければ多いほど膨大な撮影数となるため、商品数に応じた人員を確保しておきましょう。撮影を外注する場合は、サイトイメージに合うような写真を撮影してもらえるよう、トンマナを伝えておくことが重要です。
●バナー・LP作成
集客して商品を売るためのランディングページ作成や、サイト上でユーザーの目を引くためのバナー作成を行います。
●PR会社対応
プレスリリースを出して宣伝活動をする場合、PR会社への対応が必要です。具体的には、PR会社へ商品を送付して撮影や原稿作成、配信などをしてもらうための依頼を行います。
●SNS投稿
昨今、特に若い世代を中心に「SNSがきっかけで商品やお店を知り、ECへ行って買う」という行動が当たり前になりつつあります。そういった層の認知を獲得し集客するために、新商品や人気の商品をSNSで宣伝する業務が欠かせません
SNSにはFacebookや Instagram、Twitter、 LINEなどがあり、それぞれ利用しているユーザー層が異なるため注意しましょう。
▼各SNSのユーザー特性についてはこちら

4大SNSのヘビーユーザーを徹底比較
Facebook, Instagram, LINE, Twitterのユーザー特徴を調査
●サイトの保守・運用
ECサイトを公開した後は、継続的に保守と運用を行う必要があります。保守・運用の具体的な業務の例は、次の通りです。
・商品ページにおける「在庫切れ」「売り切れ」などの表示切替
・サイトや各ページの更新・リニューアル
・障害やエラーの対応
・セキュリティ面のアップデート
保守・運用の体制が不十分だと、サイトに訪れたユーザーに不信感を与えたり、購入意欲を下げてしまったりなどのリスクがあるため注意しましょう。
③集客業務
EC運営において、集客は非常に大事なプロセスです。サイトにアクセスしてもらわないことには何も進められないため、まずはアクセスを集めるための仕掛けを考える必要があります。
●広告
多くのEC事業者は、ランディングページへ集客するためにWeb広告施策を投入しています。ひと口にWeb広告施策と言っても「どこに掲載する?」「どんな言葉・画像・動画でユーザーを引きつける?」など、考えるべきことがたくさんあります。
Web広告については以下の記事で詳しく解説しているため、あわせてご覧ください。
参考記事:Web広告入門ガイド|種類や費用、用語、運用のコツを網羅的に解説
●メディア掲載
雑誌やWebメディアに掲載してもらえると、認知獲得につながりECサイトへのアクセスが増えます。積極的に露出していきましょう。
●企画
「どんな広告を出して集客するか?」「どんな切り口でメディアに売り込んで、取り上げてもらうか?」といった戦略を練ります。
なお、企画次第では、広告・メディア掲載のいずれにも頼らずに集客する策も考えられるでしょう。具体的には「既存商品の工夫(セット化、改良など)」「ECサイト内でキャンペーンを実施する」といったことです。
④販売員業務
購入してもらうまでの、接客作業です。せっかくECサイトにアクセスしてもらっても、上手な接客ができなければ成果に結びつかないため、それぞれのポイントを押さえておくことが重要です。
ECサイトで効果的な接客作業を行うには、Web上で実店舗のように接客をする「Web接客」についての理解を深めておきましょう。Web接客については、以下の記事で解説しています。
参考記事:コロナ禍でECに起きた変化。いま、Web接客ツールが重要視される理由とは?
●商品ページ作成
商品ページを作成する際は、説明文と写真の見せ方が肝心です。以下のようなポイントを考慮しながら、商品の魅力を訴求しましょう。
・サイト全体のデザインになっているか
・ターゲットに合ったデザイン・紹介文になっているか
・競合よりも魅力的な紹介になっているか
場合によっては、1ページ作り込むだけでもかなりの労力と時間がかかるため、外注するという考え方もあります。
●各種分析
ECサイトに訪問した顧客の行動を分析します。以下のような点を分析し、サイト改善や商品開発に活かしましょう。
・購入に至った人はどこから来たのか
・サイト内でどんな行動をとっているか
・サイトを訪問しているのに買わない理由はなにか
●購買導線の見直し・修正
分析によってECサイト内の課題を発見したら、仮説に基づいてサイト内に改善を加えます。
例えば、「購入ボタンの表示場所を変える」「色や大きさを変える」「複数ページ間で遷移する導線を見直す」といったことです。
●モール商品登録・送付
大手ECモールに加盟している場合は、モールへの商品登録や、専用の物流拠点への商品補充も必要です。
●在庫・備品管理
ECサイト運営では、 在庫や備品の管理も欠かせません。
ECサイト上で商品が長らく在庫切れになっていると、買いたいと思っていたユーザーが離脱してしまい機会損失につながります。そのような事態を招かないよう、在庫管理は日々行いましょう。
また、梱包発送用のダンボール、ラッピングなどの備品管理も重要です。管理を怠り不足が生じたりすると、いざ注文が入っても肝心の発送ができません。
●商品の梱包・出荷
注文が入ったら商品の梱包・出荷作業が発生します。顧客満足度を高めるために、サイト上に記載している「注文から○営業日以内に発送」といったポリシーに則って梱包・出荷作業を進めましょう。
また、イベント・セールなどで一時的に梱包・出荷対応が激増するケースもあります。そういった場合でも遅延を招かないよう、社内の体制を整えておきましょう。
ECサイト運営で必要となるスキル
ECサイトを運営する上では、次のようなスキルが必要となります。
- クリエイティブ
- サイト構築・運用
- コピーライティング
- データ分析
- カスタマーサポート
クリエイティブ
ECサイトを運営する際は、クリエイティブスキルが必要です。クリエイティブスキルとは、サイトのデザインや商品画像の加工、バナー・ランディングページ制作などを行うスキルを指します。
いくら良い商品を販売していても、その魅力を十分に伝えられなければ購入にはつながらないでしょう。そのため、魅力的なサイト・商品ページを作成できる人材や、Photoshop・Illustratorといったソフトを扱える人材を確保しておく必要があります。
デザインソフトに精通した人材が社内にいない場合は、初心者でも簡単に操作できるCanvaなどのサービスを活用する方法もあります。
サイト構築・運用
ECサイトを構築・運用するには、HTMLやCSS、PHPといったプログラミング言語の知識が必要です。また、ECサイトでは顧客の個人情報を扱うため、セキュリティ対策に関するスキルも欠かせません。
こういった専門スキルを持った人材がいない場合は、初心者でもサイトを構築できるCMSというツールを活用するのがおすすめです。CMSについては、以下の記事で詳しく解説しています。
参考記事:CMSとは?導入するメリットや種類・特徴を初心者向けに解説
コピーライティング
商品の魅力を効果的に訴求して売上を伸ばすには、コピーライティングのスキルが必要です。コピーライティングとは、文章で読者の購買意欲などを高める技術のことを指します。
コピーライティングのスキルは、商品紹介やSNS投稿、メルマガを活用した販促など様々なシーンで役立つため、ぜひ身につけておきましょう。コピーライティングの基礎知識や押さえるべきポイントについては、以下の記事で紹介しています。
参考記事:心を掴むコピースキルはどうやって身につける?「コピーライティング」の基礎と押さえておきたい2つのポイント
データ分析
ECサイトで継続的に成果を出していくためには、データ分析のスキルも重要です。
サイトのデータを分析する際には、Googleアナリティクスなどのツールを活用します。Googleアナリティクスを使うことで以下のように様々なデータを把握できるため、サイトの課題を発見したり改善したりすることに役立ちます。
- サイト訪問者の属性
- 訪問者の流入元
- サイト内での動向
- 購入に至った経路
- 出稿したWeb広告の効果
Googleアナリティクスについて詳しく知りたい方は、以下の記事もあわせてご覧ください。
参考記事:Googleアナリティクス&Googleサーチコンソール活用法。現状を把握しサイト改善に役立てよう!
カスタマーサポート
カスタマーサポートとは、メールや電話、Webフォーム、各種SNSなどを経由して寄せられたユーザーからの問い合わせに対応することです。
ECサイトを運営していく上では、商品の購入前後の様々なタイミングで顧客とのやり取りが発生します。
顧客の気持ちになって迅速かつ丁寧に対応することで、満足度の向上やリピーターの獲得につながるため、カスタマーサポートスキルも重要です。
参考記事:カスタマーサポートが意識したいお問合わせ対応のポイント
ECサイト運営にかかる費用
ECサイトを運営していくには、立ち上げや運用に様々なコストがかかります。ECサイト運営にかかる費用と、大まかな目安は次の通りです。
ECサイトの立ち上げにかかる費用
● デザイン制作費
ECサイト内のデザインや制作、商品写真の撮影・加工を外注する際の費用(約50~80万円)
● カートシステム構築費:
ショッピングカート機能や決済機能、在庫管理機能などを備えたシステムの実装にかかる費用(5万円~)
カートシステムの構築費は、一から開発する場合は非常に高価となる傾向にありますが、既存のパッケージシステムなどを利用すればリーズナブルに抑えることができます。
ECサイトの運用にかかる費用
| 種類 | 費用 | 概要 |
|---|---|---|
| サーバー・ドメイン費用 | 1,000~5,000円/年 | ECサイトのサーバーや独自ドメインの維持に必要な費用 |
| ECモール・カートシステム利用料 | 売上高やプランにより変動 | モールやシステムにおける月額/年額の利用料 |
| 決済代行費 | 5,000~1万円/月 | クレジットカード決済や後払いなど各種支払い方法の決済代行費用 |
| 配送費 | 地域や商品により変動 | 商品発送にかかる費用 |
| 広告費 | 広告の種類により変動 | 広告を出稿して新規顧客を集客するための費用 |
| 人件費 | 規模や雇用人数により変動 | 社内におけるEC業務担当者の人件費 |
外注すべき作業内容は?
外注は、自社内での負担を減らし、日々の運営を円滑にするために非常に有効な手段です。また、業務効率化以外にも最新ノウハウの提供などを受けられるメリットもあります。
では、何を外注すればよいのでしょうか?ポイントは2つです。
①専門性の高いもの
【例】マーケティング(集客、広告、SNS、コンテンツ運用など)
マーケティングは「何か一つの打ち手を投入して終わり」ではなく、その後の運用(改善〜追加施策投入の繰り返し)によって成果が変わってきます。
特にWeb上の大手プラットフォーマーの変化は激しく、Web広告施策で集客したもののGoogleのルールが大きく変わって広告効果に影響が出るようなことも頻繁に起こります。
そのため、専門知識を毎日追いかけていなければ、全てをキャッチアップすることは難しい領域と言えるでしょう。このように、大きな労力を必要とし専門性の高いものは、外注するのも一案です。
②属人性は低いが、作業負荷が高いもの
【例】商品写真撮影
2つ目は、「この人への依頼でなければダメ!」という作業ではないものの、とにかく作業負荷が高い業務です。
一例として、以下のようなものが挙げられます。
- 商品写真の撮影
- 商品ページ作成
- バナー作成
- 商品登録
- 梱包
ただしこれらは、あくまでも一例で、何を外注すべきかは、会社によってケースバイケースです。自社の強み・弱みを棚卸しして、アウトソーシングによって補完すべきポイントは何かを考える必要があります。
社内の説得方法は?
何らかの作業を外注するには、予算が必要です。その予算を作るには、決裁者を説得して承認を得なければなりません。この時ポイントになるのが「日々の作業負荷をどれだけ客観的に伝えられるか」です。
外注予算を取るための説得例
step1.外注したい作業細目を棚卸しする
例えば、アパレルECで以下の各所に掲載するために、商品撮影が必要だとします。
- 商品詳細ページ
- トップページ
- メルマガ
- 各種SNS
- WEB広告
- ブログ
この作業は、1シーズンに2回、年8回発生します。その作業に対してかかる細かなTODOを、上図のように全て書き出してみましょう。
step2.工数に置き換える
step1.で洗い出したTODOに対し、どれだけ時間がかかるか計算してみます。計算を行う際も、第三者が見ても理解しやすいよう、細かな内訳まで入れておくようにしましょう。
step3.年間に必要な稼働工数を見積もる
「年間でこれだけ工数がかかる」と、数字で表しましょう。その数字を根拠に「社内リソースをこれだけ削減できる」「削減できた分は顧客対応など、より注力すべきことに充て、顧客満足度を向上させられる」など、決裁者目線に合わせて説得に臨むことがポイントです。
スキル・知識を身につけて売れるECサイトを立ち上げよう
ECサイト運営を成功させるためには、マーケティングを中心としたフロント業務と、顧客満足度を高めるためのバックエンド業務を両立することが重要です。
それぞれの業務を円滑に進めるためにも、クリエイティブスキルやデータ分析、カスタマーサポートなどに関する知識を身につけておきましょう。
また、ここまで読んで「自社内だけではリソース的にとても無理……」と思った方は、外部委託やEC運営補助ツールの活用も積極的に検討しましょう。
ECサイト設計・構築からリリース、運用開始後の成長まで伴走してくれるツールについては、以下の資料で確認することができます。これからEC立ち上げに挑む方は、こういったツールについてもぜひ理解を深めておきましょう。
- BtoC
- BtoCとは、Business to Consumerの略で、企業と消費者間の取引のことを言います。
- BtoC
- BtoCとは、Business to Consumerの略で、企業と消費者間の取引のことを言います。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- トンマナ
- トンマナとは、「トーン&マナー」の略で、広告におけるデザインの一貫性を持たせることを指します。また、ブランドのイメージカラーとホームページのデザインカラーを合わせる必要があるなど、「トンマナ」は企業ブランディングにおいても重要です。
- ランディングページ
- ランディングページ(landing page)とは、ユーザーが検索エンジンあるいは広告などから最初にアクセスしたページのことです。「LP」とも呼ばれています。ただしWebマーケティングにおいては、商品を売るために作られた1枚で完結するWebページをランディングページと呼びます。
- バナー
- バナーとは、ホームページ上で他のホームページを紹介する役割を持つ画像ファイルです。画像にリンクを貼り、クリックするとジャンプできるような仕組みになっています。画像サイズの規定はありませんが、88×31ピクセルや234×60ピクセルが一般的です。また、静止画像だけでなく、アニメーションを用いたバナーもあります。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- ランディングページ
- ランディングページ(landing page)とは、ユーザーが検索エンジンあるいは広告などから最初にアクセスしたページのことです。「LP」とも呼ばれています。ただしWebマーケティングにおいては、商品を売るために作られた1枚で完結するWebページをランディングページと呼びます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- 導線
- 導線とは、買い物客が店内を見てまわる道順のことです。ホームページにおいては、ページ内での利用者の動きを指します。 ホームページの制作にあたっては、人間行動科学や心理学の視点を取り入れ、顧客のページ内での動きを把握した上でサイト設計を行い、レイアウトや演出等を決めることが重要になります。
- バナー
- バナーとは、ホームページ上で他のホームページを紹介する役割を持つ画像ファイルです。画像にリンクを貼り、クリックするとジャンプできるような仕組みになっています。画像サイズの規定はありませんが、88×31ピクセルや234×60ピクセルが一般的です。また、静止画像だけでなく、アニメーションを用いたバナーもあります。
- ランディングページ
- ランディングページ(landing page)とは、ユーザーが検索エンジンあるいは広告などから最初にアクセスしたページのことです。「LP」とも呼ばれています。ただしWebマーケティングにおいては、商品を売るために作られた1枚で完結するWebページをランディングページと呼びます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- HTML
- HTMLとは、Webページを記述するための言語です。"HyperText Markup Language "の略です。"<"と">"にはさまれたさまざまな種類の「タグ」によって、文章の構造や表現方法を指定することができます。
- CS
- CSとはCustomer Satisfactionの略称で「顧客満足度」を意味します。顧客との関係維持、サービスの発展に関するマーケティング戦略に関わる用語です。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- リピーター
- リピーターとは、商品やサービスに愛着を持ち、繰り返し利用してくれるお客様のことです。 リピーターを獲得することは、ホームページを使って売上を上げるためにも重要な指標の一つと言えます。
- ドメイン
- ドメインとは、インターネット上で利用可能なホームページやメールなどを識別するときの絶対唯一の綴りを言います。電話番号や自動車ナンバーが同一のものがないのと同様に、インタネットにおいても、2つとして同じドメインは存在できない、といった唯一無二の綴りです。
- ドメイン
- ドメインとは、インターネット上で利用可能なホームページやメールなどを識別するときの絶対唯一の綴りを言います。電話番号や自動車ナンバーが同一のものがないのと同様に、インタネットにおいても、2つとして同じドメインは存在できない、といった唯一無二の綴りです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- バナー
- バナーとは、ホームページ上で他のホームページを紹介する役割を持つ画像ファイルです。画像にリンクを貼り、クリックするとジャンプできるような仕組みになっています。画像サイズの規定はありませんが、88×31ピクセルや234×60ピクセルが一般的です。また、静止画像だけでなく、アニメーションを用いたバナーもあります。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- トップページ
- インターネットのWebサイトの入り口にあたるページのことをトップページといいます。 一般的には、階層構造を持つWebサイトの最上位のWebページをさします。サイト全体の顔としての役割も果たすため、デザインなどで印象を残すことも考えたサイト作りも有効となります。
- メルマガ
- メルマガとは、電子メールにて発信者が、情報を配信する手法の一つで、『メールマガジン』の略です。 一部有料のものもありますが、多くのメルマガは購読も配信も無料で行っています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他