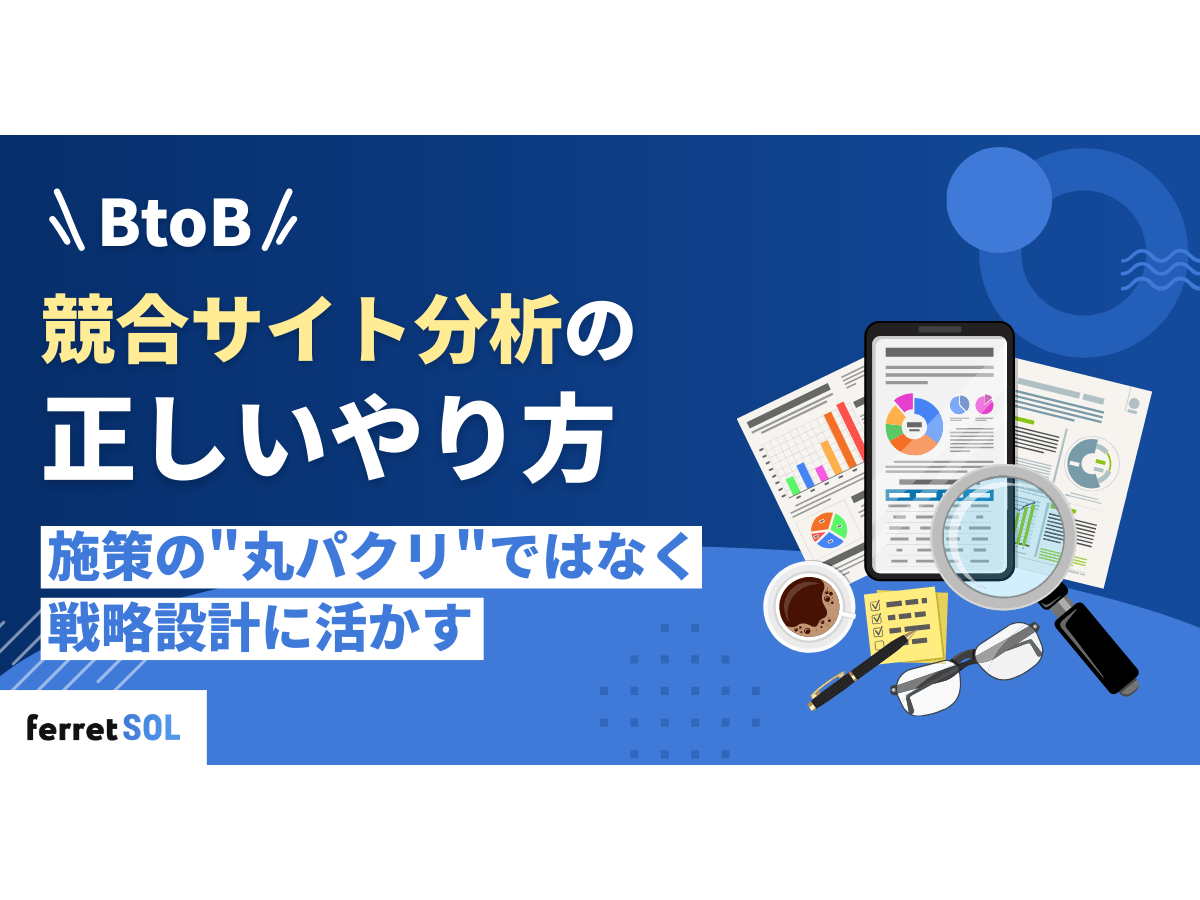ネットリサーチとは?メリットや注意点、進め方、レポート事例を紹介
ネットリサーチとは、インターネット上で行う様々な調査のことです。調査開始から集計、レポートの作成まですべてをWeb上で完結できるため、 企業や組織が必要としている情報を低コストかつスピーディーに集められるのが特徴です。
この記事では、ネットリサーチのメリットや注意点、進め方、レポート事例を紹介します。
目次
▼ネットリサーチのリアルな調査レポートを確認したい方はこちら

ログデータ×アンケートデータによるスマートフォンの通信事業者別ユーザー調査結果レポート
ログデータ×アンケートデータによるスマートフォンの通信事業者別ユーザー調査結果レポートについてご説明します。
ネットリサーチとは?
ネットリサーチとは、回答者にインターネットを通じてアンケートにアクセスしてもらい、Web上で回答してもらう調査手法のことです。Webアンケートやオンラインサーベイとも呼ばれています。
多様な属性から大量の回答データを得やすいため、自社の市場調査にネットリサーチを採用する企業も多くあります。
ネットリサーチは定量調査※1に用いられることが多く、次のような数値データを取得するのに役立ちます。
- 市場実態
- 商品やサービス認知度
- 購入商品や数量、リピート率
- 顧客満足度
では、ネットリサーチによって得られた数値データはどのようなシーンに活用できるのでしょうか。ネットリサーチの調査結果(調査レポート)の活用方法は以下の通りです。
- 商品、サービスの開発
- 新市場開拓戦略
- ブランド認知度の向上
- 顧客満足度、従業員満足度の向上
- プレスリリースの配信
- ホワイトペーパーのダウンロード
ネットリサーチで得られるデータは企業のマーケティングリサーチにおいて欠かせない重要な要素といえます。
企業や組織は数値データの確認に終わらず、調査レポートをどのように活用するのかを明確にしてからネットリサーチに着手することが大切です。
※1 定量調査とは、数値化できるデータを集計して分析する調査方法。
参考記事:インターネットリサーチの変遷 ~ インターネットが大衆化し始めた1990年代後半からスマートフォンが普及した現在まで ~
ネットリサーチのメリットと注意点
ここからは、ネットリサーチのメリットと注意点について詳しく解説していきます。
ネットリサーチのメリット

⚫︎ 短期間でリサーチできる
ネットリサーチでは、調査内容の伝達から回答の回収までを全てネット上で行います。また回答データの分析も回収した回答をそのままデータとして扱うため、紙で行う調査に比べて、人の手で回答結果を入力したり集計したりする手間が省け、調査の開始から完了までをスピーディーに終えられます。
⚫︎ 低コストで使える
ネットリサーチでは回答者の募集・回答の集計はインターネット上で行われます。従来の紙によるリサーチにかかっていた回答用紙の準備・配布、回答データの入力にかかる印刷費・郵送費・人件費といったコストを抑えて調査を実施できます。
⚫︎ 設問の遷移がスムーズで答える側の負荷も軽減
紙での調査と異なり、設問から設問への遷移がスムーズであることもネットリサーチの特徴です。「設問1でAと答えた人は設問3へ進む」といったようなこともネットリサーチなら回答者のアクションを待たず、自動でページ遷移します。
余計な操作をせずともスムーズに調査が進むことで、回答者はストレスや煩わしさを感じることなく回答に集中できるため、正確なデータを集めやすくなるでしょう。
⚫︎ 紙の調査だけでは難しいことも可能になる
ネットリサーチでは、以下に挙げるような、これまで紙の調査ではできなかったことも可能になります。
- エラーの通知機能によって回答のミスや矛盾、無回答を回避できる
- ファイルや画像、動画を使ったアンケートの実施
- 回答とともに回答者の撮影した画像を収集できる
- 条件分岐によって回答者の負担を軽減できる
- 回答者が回答に要した時間を記録できる
こうしたことが行えるネットリサーチなら、紙の調査よりもずっと複雑かつ多様な調査が可能になるでしょう。
⚫︎ たくさんの回答を集められる
ネットリサーチでは、回答者をインターネット経由で募るため、従来に比べかなり多くの回答者を対象にした調査ができます。
紙による調査では回答対象者が多ければ多いほど、調査にかかる費用や手間といったコストが膨らみますが、ネットリサーチでは1,000〜10,000件といった膨大なサンプル数であっても比較的簡単に回答を回収・分析可能です。
インターネットリサーチの基礎知識はこちらの記事でも紹介しています。ぜひ参考にしてください。
参考記事:初心者にオススメ!インターネットリサーチをスムーズに行うための基礎知識
ネットリサーチを実施する際の注意点
⚫︎ 調査対象はインターネット利用者に限られる
ネットリサーチでは居住地・職業・性別に限らず不特定多数の回答者から回答を得られますが、回答者との接触がインターネット経由である以上、ネットを利用していない高齢者などを対象にした調査は難しいでしょう。
郵送・電話調査といったインターネット以外の手段で回答を収集する必要があります。
⚫︎ 複数の回答デバイスへの対応が必要
ネットリサーチはPC・スマホ・タブレットなどあらゆるデバイスに対応した形で行いましょう。若年層の場合、普段はスマホ・タブレットを中心に使っておりPCにはほとんど触れないという人もいます。
そのため回答デバイスを「PCだけ」「スマホだけ」と限定してしまうことで十分な回答数が得られなかったり回答層が偏ってしまう恐れもあります。ネットリサーチではスマホはもちろん、マルチデバイスへの対応が必要です。
⚫︎ 質問項目を増やし過ぎない
ネットリサーチで質問項目が多すぎると、回答者の回答意欲が落ちたり、回答そのものを億劫に感じてしまう恐れがあります。そうなると回答数や回答精度が落ちてしまいます。ネットリサーチを行う際は質問項目や質問内容のボリュームには留意しましょう。
⚫︎ 不正回答のリスクがある
ネットリサーチでは紙での調査と異なり回答者の顔は見えません。そのため、回答者のプロフィールが実際と異なる、虚偽の回答内容、といった可能性もあります。
調査の内容によっては、回答の質を保つために信頼のおけるリサーチ会社に依頼する、回答者の属性を検証する、十分な回答数を集めるといった対策も必要になるでしょう。
▼ネットリサーチを行う際に参考にしたい!店舗とEC利用者の検討行動の違い

店舗とECではどう違う?化粧品購入プロセスを徹底調査
化粧品購入プロセス調査~店舗とEC利用者で検討行動はどう違う?
ネットリサーチの進め方
ネットリサーチは、以下の4ステップで進めます。

それぞれのポイントについて詳しく見ていきましょう。
1. 調査企画を立てる
調査企画はネットリサーチにおいて最も重要です。最初に仮説を立てて、どのような目的でリサーチを実施し、どのようなデータが欲しいのか明確にします。
また、得られた調査結果によってどのような目的が達成できるのか、その後のアクションについても考えることがポイントです。
(例)
- 仮説「商品Aの売上が未達なのは、パッケージのデザインが良くなかったからだ」
- 目的「商品Aのパッケージをリニューアルして売り上げ目標を達成する」
- 欲しいデータ「デザインのどの部分に問題があったのか」
- 調査結果「カラーとキャッチコピーを改善すれば売上がアップする」
調査に必要なサンプル数(アンケート回答者数)や調査対象者の選定も同時に行います。
2. 調査票作成
次に調査票(アンケート内容)を作成します。
調査票は回答率が上がるよう工夫することが大切です。回答者が「答えやすい」と感じるアンケートにするために、以下のポイントを意識してみましょう。
- 簡単な設問項目から並べる
- 設問数は必要最低限にする
- 選択回答形式の設問を増やす
- 専門用語は使わない
- 分岐を設定する
これらを意識することで、質の高い回答を得られるようになります。
3. 実査・集計
調査対象者にアンケートを実施して、回答データを集計します。基本となる集計方法は単純集計とクロス集計です。
単純集計では、設問ごとにどのくらいの人が回答したのか、選択肢ごとの割合はどうなっているのかなどを求めます。クロス集計では、単純集計の数値に性別、年齢、地域などの基本情報を掛け合わせて集計します。
(例)
商品Aを購入したことのある人の中で、週1回以上購入する人は20%。そのうち60%が30〜40代の男性である。
※使用頻度・年代・性別の掛け合わせ
集計を使いこなすことで、全体のデータを見るだけではわからない傾向(トレンド)を見ることができます。
4. 分析・レポート
集計後、調査結果を分析して調査レポートを作成します。調査レポート作成で重要なことは、調査前に立てた仮説と比較することです。
(例)
商品Aは「パッケージデザインの改善点」を得られる結果に設定していたが、実際は「価格」や「形状」に対する回答が多数を占めていた。
仮説が正しければすぐにアクションを起こせますし、仮説が間違っていれば戦略を見直す必要があります。
こちらの記事ではネットリサーチサービスを選ぶ際のポイントについても紹介しています。
参考記事:おすすめネットリサーチサービス9選をタイプ別に徹底比較!失敗しない選び方のポイントも解説
▼生活者アンケートとWeb行動ログを用いた分析例はこちら

2022ヒット商品分析 ライフスタイル編
生活者アンケートとWeb行動ログで見るヒットの理由、ヒットの軌跡 -ライフスタイル編- を解説しています
リサーチツールを活用した調査レポートの事例
自社で定量調査や定性調査※2を実施するには、多くの時間と費用がかかりますが、リサーチツールを活用することで、簡単かつスピーディーにネットリサーチを実施できます。
ここでは、Web行動ログを中心とした分析ツール「Dockpit」の調査レポートを紹介します。
Dockpitは、クレディセゾンのネット会員でモニター登録に同意した国内30万人規模の消費者パネルを活用したマーケティングツールです。インターネット上の行動データからあらゆるサイトへのアクセス状況を分析できます。
※2 定性調査とは、はい・いいえで答えるのが難しい行動の根拠、理由、経緯など変容性のある情報を収集する調査方法。
調査レポートの概要
株式会社ヴァリューズは、Dockpitを使って20歳以上の男女7,920名に「携帯キャリア」に関するアンケート調査を実施しました。
総務省の令和3年版情報通信白書によると、国内のモバイル端末の保有率は9割を超えています。この調査レポートでは、携帯電話会社の実態とユーザーの乗り換え意向などを調査しています。
● 携帯キャリアに関するアンケート調査
| 調査目的 | コロナ禍で携帯キャリアの回線見直しがどの程度行われたのか。 |
| 調査対象 | 「Dockpit(旧eMark+)」のPCパネルの20歳以上の男女。 |
| 調査地域 | 全国 |
| 調査デバイス | PC |
| 調査期間 | 2020年11月5日(木)~11月17日(火) |
| 回収サンプル数 | SCR調査:7,920ssサンプル/本調査:7,687サンプル(携帯所持者) |
● アンケート調査項目
- ユーザープロフィール
- 各携帯電話会社の強み
- 携帯電話会社の乗り換え経験と今後の意向
- 携帯電話会社のチャーンイン/チャーンアウトの実態と今後
- 3大キャリアユーザーの乗り換え先【前⇒現在】
- 3大キャリアユーザーの乗り換え先【現在⇒今後】
- 乗り換え意向者の現利用会社への不満
調査結果のサマリー1. ユーザープロフィール
ユーザープロフィールは「現在契約している携帯電話会社」と「現在使っているOSの種類」を単純集計とクロス集計で表したものです。

MNO※4ユーザーが全体の7割を占めており、MVNO※5ユーザーは男性若年層が多く、Android率が高いという結果が出ています。
※4 MNO(Mobile Network Operator)はdocomo・au・Softbankの3社のこと。
※5 MVNO(Mobile Virtual Network Operator)はMNOから回線の一部を借り、ユーザーに提供している通信事業者のこと。
調査結果のサマリー2. 各携帯電話会社の強み
「なぜ今の携帯電話会社を選んだのか」の回答を、コレスポンデンス分析を用いて表しています。コレスポンデンス分析とは、クロス集計の結果を散布図にして見やすくした分析手法です。

3大キャリアは通信エリアの広さやブランドイメージ、サポートの手厚さ、サブブランド※6、楽天モバイルはキャンペーンやプランによる月額費用の安さで選ばれていることが分かります。
※6 サブブランドとは、MNOが持っている別ブランドのこと。
調査結果のサマリー3. 携帯電話会社の乗り換え経験と今後の意向
過去の乗り換え経験と今後の意向をクロス集計で表した調査レポートです。

約半数に乗り換え経験があり、現在約1割の人が乗り換えを検討しています。MVNOユーザーが特に流動的であることがわかります。
▼市場調査ツールDockpitについて詳しく知りたい方はこちら

市場調査ツールDockpitで3C分析を簡単にする方法とは?
ひとつのツールで3C分析ができる!「Dockpit」を活用したマーケ戦略立案に直結するデータ分析手法についてご説明します。
ネットリサーチをマーケティング戦略に活用しよう
ネットリサーチはマーケティング戦略に欠かせません。ビジネスに絶対はありませんが、精度の高いリサーチによって施策の成功確率を上げることができるでしょう。
自社にデータ分析のノウハウやデータ分析に精通した人材がいない場合は、リサーチツールを活用してみるのもひとつの方法です。リサーチツールを活用することで、誰でも簡単に市場や消費者の声を集められます。
▼ネットリサーチのリアルな調査レポートを確認したい方はこちら

ログデータ×アンケートデータによるスマートフォンの通信事業者別ユーザー調査結果レポート
ログデータ×アンケートデータによるスマートフォンの通信事業者別ユーザー調査結果レポートについてご説明します。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- オンライン
- オンラインとは、通信回線などを使ってネットワークやコンピューターに接続されている状態のことをいいます。対義語は「オフライン」(offline)です。 現在では、オンラインゲームやオンラインショップなどで、インターネットなどのネットワークに接続され、遠隔からサービスや情報などを利用できる状態のことを言う場合が多いです。
- ホワイトペーパー
- ホワイトペーパーは、もともとは政府や公的機関による年次報告書つまり「白書」を意味しました。しかし近年ではマーケティング用語としても用いられており、特定の技術や商品について売り込む目的で、調査と関連付けて利点や長所をアピールする記載がなされることが特徴です。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- タブレット
- タブレットとは、元々「板状のもの」「銘板」といった意味の単語です。パソコンの分野で単にタブレットといえば、「ペンタブレット」や「タブレット型端末」などの板状のデバイス全般を指します。ここでは主にタブレット型端末について説明していきます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- Android
- Android OSとはスマートフォン用に開発された基本ソフト(OS)の一種です。米国Google社が中心となり開発されました。
- キャンペーン
- キャンペーンとは、インターネット上のサイトにおいて、ファン数を増やし、購買行動を促すためにおこなう懸賞キャンペーンなどのマーケティング活動のことです。キャンペーンにはファン数を増やすだけでなく、ファン獲得以上のリアル店舗の来店者数を増やす、資料請求者を増やす、実際の購買を増やすなどの目的があります。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他