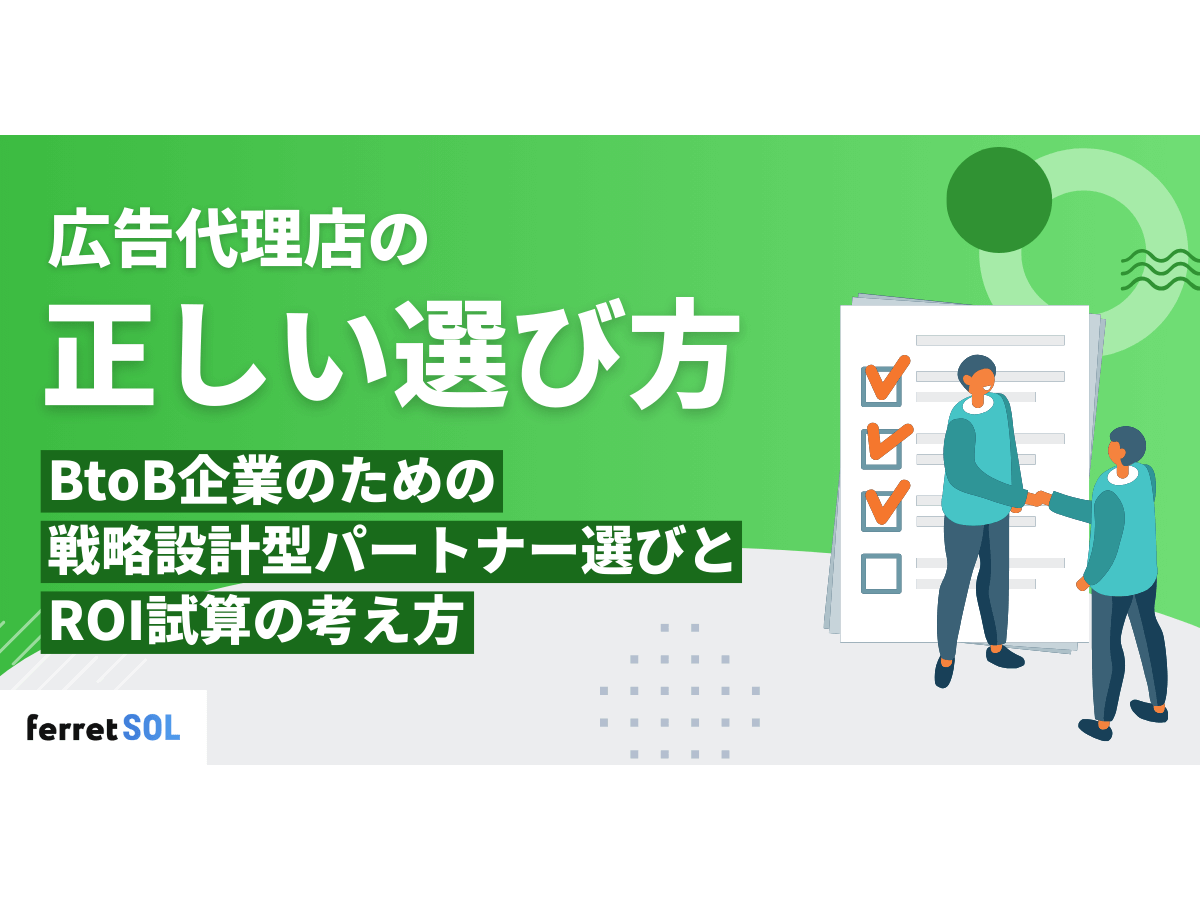データフィードの過去・今・これからを語る-FeedTech2015-(アタラ杉原代表・アタラ岡田氏・アナグラム阿部氏・フィードフォース川田氏)
10月1日、株式会社フィードフォースによる、データフィードをテーマとしたイベント「FeedTech2015」が開催されました。
データフィード広告の最前線で活躍されている4名が一堂に会したパネルディスカッションでは、「今なぜデータフィードがあついのか?」という視点を軸に、データフィードのこれまでの経緯と現状、今後どのように発展していくかまでについて熱い議論が交わされました。
登壇者
パネリスト
杉原 剛氏 アタラ合同会社代表取締役CEO
オーバーチュア、グーグルでの両検索エンジンの広告事業の戦略立案/オペレーション設計に携わる。 2009年にアタラ合同会社を設立。 Web APIを活用したデジタルマーケティングの自動化/効率化/見える化システム開発、リスティング広告、アトリビューション分析コンサルティングを行う。
阿部 圭司氏 アナグラム株式会社代表取締役
アナグラム株式会社 代表取締役。 大手アパレルメーカーを経て運用型広告の世界へ。 現在はCPAの改善だけにとらわれず、ビジネスの最大化を目指す支援を行う。 著書には「新版 リスティング広告 成功の法則」「いちばんやさしいリスティング広告の教本」など多数。
川田 智明氏 株式会社フィードフォースDF PLUS 事業責任者
2012年、株式会社フィードフォース入社。 「オウンドメディアのソーシャル化サービス」の市場調査~セールスを行った後、新規事業として商品データ最適化サービス「DF PLUS」を立ち上げる。 現在は事業責任者・プロデューサーとして、外部企業との事業提携から広告主の集客最大化の提案まで幅広く担当。
モデレーター
岡田 吉弘氏 アタラ合同会社 取締役CC
広告代理店、グーグルにて最大手からベンチャー企業まで幅広くリスティング広告の啓蒙・拡販に従事。2011年よりアタラ合同会社取締役CCO。 検索エンジンマーケティング黎明期から一貫してアカウントマネジメントの現場を主導し、運用型広告の設計運用のみならず、広告運用の研修、自動化/効率化システムのコンサルティング等も実施している。
データフィードのこれまで
キーワードは「フラグメンテーション」
岡田氏:まずはデータフィード広告のこれまでの経緯について、杉原さんお願いします。
杉原氏:
データフィード広告が広まった背景にはフラグメンテーションが大きいかなと思います。
日本語でいうと断片化という意味になるんですが、*「1つだったものがどんどん細かく分かれていく」*さまをフラグメンテーションといいます。
英語圏ではすごくよく使われています。
広告・マーケティングの世界では、*「デバイス×メディア」*と僕は言ってます。
みなさんもいろんなデバイスを使ってますよね。
1人あたまのデバイスの量は増えていますし、情報爆発も今に始まったことではありません。
いろんなメディア・アプリで情報を入手できる状況で、デバイスとメディアの種類をかけ合わせると無数に生まれるわけです。
その中で生活者は分散しています。
例えば、スマホでFacebookを見る方はとても多いと思いますが、一方でパソコンでPVの少ないブログを見る人もいるわけです。
そういう人たちが点在し、分散して、フラグメンテーションを起こすんです。
デバイスの種類って、マーケターとしては意識しなければいけないんです。
デバイスっていろんなものが出てきていますがそれだけでなく、その上に乗っかるOSも、ブラウザも、アプリも、ターゲティングするうえでは意識する必要があります。
なので、*「デバイス×OS×プラウザ×メディア」*となると更にパターンは無数になります。
接触する時間も多様化してますので、そこも施策を考えるうえで考慮しなければいけません。
みなさんはモノを買う時、こういったことを意外と意識せずに色々な情報を見ると思います。
ECで商品を見つけて、比較サイトで商品を比較して、SNSや口コミで評判をチェックしたり、あるいは検索エンジンで能動的に情報を入手したり。
このような情報大爆発時代のなかで、情報を生活者の目にとまらせるのはとても難しくなってきています。
情報大洪水のなかで埋もれないように、適切な網を可能なかぎり張らないとといけない。
そのなかで、企業には色々な課題があります。
メディアは今後減ることはなくて、どんどん増えていきます。
なので網を張る工数も比例して増えていきます。
また、商品点数が多いECさんや物販さんは、何十万、何百万の点数を手動で広告に差し込むのは基本的に難しい。全てをカバーすることは難しい。
売れ筋だけやっても片手落ちになってしまいます。
商品の情報更新性(在庫やリニューアルなど)も高いので更新しきれない。
そこでデータフィードという概念が出てきました。
プラットフォームに効率的にデータを提供することで網を非常に張りやすくなったのがデータフィード広告の仕組みです。
これまで手動で対応していたものが自動で対応できるようになったのが大きなメリットになるのかなと思いますね。
日本のデータフィード広告事情
杉原氏:
米国では2002年ころから取り組まれていました。
最大手級のEC、旅行社などの情報更新性の高い商材を扱っている企業は、検索連動型広告でデータフィードによる自動化を推進していたんですよね。
では日本はどうかというと、2005年頃にオーバーチュアが一部の広告主向けに提供した「カスタムインプリメンテーションサービス」が始まりだったんじゃないかなと思います。
2010年頃から、各社がデータフィード最適化サービスを展開しました。
様々な素晴らしいサービスが出てきたんですが、起爆剤になったのはクリテオの出現だったと思います。
非常に効果が高かったですね。
クリテオの出現がデータフィード元年だったのではないかと思います。
現在はかなり増えましたが100社以上のプレイヤーがいるアメリカにはまだ及びません。
アメリカはメディアの数も多いし、断片化の度合いも違うので、企業としてはデータフィードで一斉配信せざるを得ない状況なので技術が先行しているというのはありますね。
もちろん日本でも、データフィードのプレイヤーは今後増えていくと思いますね。
データフィードの今
岡田氏:背景はおさらいができたので、次にデータフィードの今ですね。
タイトルにもなっている「データフィードはアツい」というところにいきたい思います。
アメリカでは進んでいる現状に対して、日本でも現状本当にアツいのか、というところを実際に広告配信を代理店としてやられている阿部さんから見て、どうなのかを聞いてみたいと思います。
阿部氏:
商材によって、という前提はありますが、影響力が大きくなったというのはあります。
総CVの4割をフィード経由で取ってくるお客様が増えていて、少なくとも2,3割とかなんで無視できない領域になっているのかなと。
アツいなと思うのが、クライアントからオーダーがきたりする時ですね。
岡田氏:今までと逆ですね。これまではこちらから提案しないといけないことだったのが、今は向こうからリクエストが来ると。デリバリーする代理店さんがいて、マスターDBからメディアに届けるまでの間の情報処理をしているのがフィードフォースさんなんですが、現場感としてどうでしょう?
川田氏:
弊社が事業として立ち上げたのは約3年前で、当時はこちらから働きかけてそもそもデータフィードってなんだというところから定義してたんですが、今は問い合わせを頂いたり、お客様の総CVの3割ぐらいがフィード経由になってきているかなと思います。
お客様が抱えている問題は根深くてですね。
情報システム部門とマーケティング部門との連携が難しい、できていないというのは、3年前から大きく変わっていないのかなということも、個人的には感じていますね。
杉原氏:
よくシステム部門からは、「セキュリティ大丈夫?」とか、「効果あるの?」という質問がきたり、いろんなハードルがあると思うんですが、それ対してマーケターはどうアプローチしていけばいいでしょう?
川田氏:
まさにシステムとマーケティングの橋渡しをするのが弊社の役割かなと思っていて。
そのためには役割というか、思想を理解することも重要かなと。
例えばGoogleのPLAでいうと、弊社のお客様で1年運用してご予算が倍以上になっていたりとか。
そもそもPLAがどういう特徴があるのかというところ、データフィードで半自動化することで、特定の商品にCVが偏るのではなく、テールのものまで捉えられるということを説明すると、マーケティング部門の方もシステム部門の方も連携して取り組んでいただけるという状況にはなってきていますね。
岡田氏:
では、雪解けは始まっているというイメージでしょうか。アツいと。
ちなみにそういう話でいくと、今既にCVの4割ぐらいがフィード経由だったりとか、フィードマネジメントを使う企業さんがどんどん増えていくなかで、結局マーケティングなので、出ていくデータ量が増えていくことで、広告効果として返ってくるものも増えていきますよね。
あと、Googleの発表でもあったんですが、自動車業界とかホテル業界とか、情報量が多い分野でデータフィードが活用されていくのかなと。
あとは動画ですね。TrueViewであれば動画の中に広告を組み込めたりするし、それぞれのジャンルと融合していっているのがデータフィードがアツいと言われる所以なのかなと思います。
データフィードのこれから
日本のDFOも第一世代から進化
杉原氏:
以下の図は僕の勝手な解釈になるんですが、オレンジで書いているところが第一世代ですね。
フィードフォースさんがやられているようなデータ変換のところを担っているんですが、「GoDataFeed」という、総合在庫管理と言われているところなんですが、横断的な在庫管理ができるのと、商品ごとのアナリティクスが見れたり、コスト管理ができたりっていうところが第二世代になるのかなと。
川田氏:
弊社が目指すのもこういうところに近いなのかなと思います。
国内のデータフィードでいうと、各広告媒体のフォーマットを最適化するのが第一ステップで、次のステップとしては、チャネルが増えていくなかで、一元管理できる仕組みも必要なのかなと。
在庫の統合管理が第二世代になると思うんですが、ECだけでなく、実店舗の在庫情報とかPOSデータとの連携も必要なのかなと思います。
なぜかというとGoogleさんが「ローカル在庫広告」というのをリリースしていて、Web上の商品リスト広告、今はECの在庫状況が出てくるんですが、例えば六本木の店舗の在庫状況が表示されて、そこに誘導するというようなサービスもUSではローンチされているのでそこも捉えていく必要があるかなと。
岡田氏:じゃらんさんとか楽天トラベルさんとか、それぞれの空き部屋(=在庫)の予約管理とかもリアルタイムで管理していかないとダブルブッキングしちゃうんで、必ず必要になりますよね。
杉原氏:
それをプラットフォーム側が担うのが、フィードフォースさんのような中間企業が担っていくのか、しのぎを削るんでしょうね。
岡田氏:リアルタイム性が生命線になるところもある一方で、中規模以下の企業さんではそこまでリアルタイム性は重要ではなかったりしてプライオリティが違うのかなと。
そうなると中間管理の方が実は現実的だったりするんでしょうか。
川田氏:
そうですね。各媒体をどういう理由で選択するのかとか、各集客チャネルのポートフォリオを組む必要があるのかなと思っています。
そこは弊社や代理店さんとの連携が必要になるのかなと思います。
近未来のデータフィード
岡田氏:それ以外だと、動画・IoT・VRあたりが入ってくるんじゃないかなと。
杉原氏:
動画は確実に入ってくるでしょうね。
岡田氏:動画自体がデータですしね。
IoTとデータフィードの関係性
杉原氏:
IoTでできることって、今までインターネットに繋がってないデバイスを繋げていくことなんですよね。
家にある炊飯器や街中の自動販売機も。
それらが使われた時のデータが取れるので、この人にはこういう情報を出すというような戦略を取ることができます。
イメージとしては、映画の「マイノリティ・リポート」のあの有名なシーンです。
トム・クルーズ扮するジョン・アンダートンがビルを通り過ぎる時、壁の広告がジョンに「新しい車はどうか」「奥さんにブルガリはいかが」と、動画が話しけてくるシーンがありますが、これはデータフィード広告だと僕は思ってます。
ちょっとフューチャリスティックな話ですが、こういう世界は絶対来るかなと思っています。
岡田氏:良い世界なのか、…ちょっとディストピア感もありますが(笑)ただ技術的にはできるという話ですが、実現していない。
そこでいくつか話さないといけないイシューがあるかなと思います。よくITでは「人、技術、その間のプロセス」という三角形について語られますよね。
この3つによってシステムは動いていていると。
今日話してないのは人とプロセスのところだと思うんですけど、人のスキルやキャリアをどう考えていったらいいのかというところを、企業を経営されている阿部さんはどのように対応されているんでしょうか?
データフィード運用に適した組織体制は?

阿部氏:
今までは縦割りで、ヒエラルキーでできてる組織が多いと思うんですが、ぼくらフラットまではいかないんですが、案件ごとにチームを作って柔軟に対応できるようにしています。
そのチームごとに問題を解決するような体制にしています。
岡田氏:企業だとソーシャルの人、リスティングの人って分けがちですがそうではないと。
阿部氏:
それも悪くはないと思うんですが、さっきの情報システムとマーケティングのように縦割りの問題もあったりするので、現場で意思決定しちゃうような形をいま作っています。
岡田氏:データや人は横断しているわけだから、縦に割っちゃうと不都合が多いと。
川田さんにもお聞きしたいんですが、マーケティングとITの部分で壁にぶつかることが多いなかで、今後どのように市場を開拓していくか、そのなかで組織をどういう風にしていこうというのはありますか?
川田氏:
システムとマーケティングが分断されていて、ただそこに気づいていち早く気づいて取り組んでいる企業さんもいて、どうしているかというと、例えばデータフィードやタグ周りなど、システムを理解しているひとが先陣きってやっていたりとかするんですね。
なので、システム部門を理解している人が、先導きってやっていくのが必要になってくるかなと思います。
杉原氏:
むずかしいところですよね。どういう形がいいのか、専門部隊がいればそりゃ楽だけど、現場の人たちがデータフィードってどうやらなければいけないかを考えなければならないから、そこを丸投げするのは厳しいかなと。*
データフィードって難しいと思われていて、苦手意識持たれてる方が多いんですが、言ってしまえばテキストと画像のやり取りなんで、そこに苦手意識を持たず、丸投げせず自分たちでもやってみてもいいのではないかなと思います。
データフィードが持つ可能性
岡田氏:データフィードの軸で、会社として、個人としてチャレンジしたいことはなんでしょう?
阿部氏:
データフィードという軸で言うと、選択肢は無くて、やるしかないと思います。
仕組みとルールを知れば、自分でできる必要はないと思います。最終的には詳しい人に任せてもいいかなと。
ただルールを知らないと何もできないので、最低限の理解は必要かなと思います。
あと、データフィードってデータ有りきの部分でやっていく、というところがすごく強いと思います。
取り入れてないとこがいれれば、それだけですごく効果があると思います。
そこで空いたリソースを必ず投資に回していかないといけないと思います。
次のフェーズを拾っていくことが重要なので、そういった組織を作っていきたいなと考えています。
川田氏:
会社としても個人としても、インフラになりたいと思ってます。
徐々にデータフィードにスポットライトが集まっているなかで、マーケターやシステムの方がディスカッションするためのダッシュボードのようなものが必要になるのかなと思っているので、それを作っていきたいですね。
杉原氏:
一番良い商品データベースは、中間処理をしないデータなんです。
中間処理って意外と面倒なんで、無いのが一番。
理想形でいうと、大元の商品データを柔軟に、すぐ追加できる方がいい。
でもなかなかそこまでいくことができないわけです。それができた会社は強いですよね。
そこを担うのは、フィードフォースさんかもしれないし、代理店さんかもしれない。
この辺をどうしていくのかが課題かなと思っています。
まとめ
データフィード広告とは、その名の通り「データを供給する」広告のことで、リスティング広告、Facebook広告、DSP、SSPなどのアドテク全般がデータフィード広告の枠組みに入ります
。
データフィードが注目されるようになった大きな要因として、「フラグメンテーション」が挙げられていますが、生活サイクルや趣味嗜好が今後更に多様化していくなかで、日本も欧米並みの個別最適化が求められるようになるでしょう。
パソコンでメディアを見るユーザー、スマホのブラウザで検索を行うユーザー、アプリを起動するユーザーと無数のセグメントが存在し、今後ウェアラブルデバイスが普及すれば更に多くのセグメントが生まれます。
各セグメントごとに、最適な広告配信を自動的に行えるのがデータフィード広告の強みですが、杉原氏が述べられたとおり、代理店に任せきりになるのではなく、まずはマーケター自身が自分で理解してやってみるのがいいのかもしれません。
このニュースを読んだあなたにおすすめ
マーケティングの基本である市場分析とポジション
ブランディングで集客数はほとんど変わらなくても売上1.3倍
セールスフロー理解の重要性と具体的事例

Web戦略カリキュラム
Webマーケティングを実践するうえで、まずは押さえておくべきWeb戦略の基礎カリキュラムです。Web戦略の基礎は、様々なプロモーション手法やマーケティング活動の基本と言える考え方なので必ず押さえましょう。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- リスティング広告
- リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を、有料で表示するサービスのことです。ユーザーの検索結果に連動した形で広告が表示されるため「キーワード連動型広告」「検索連動型広告」とも呼ばれます。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- リスティング広告
- リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を、有料で表示するサービスのことです。ユーザーの検索結果に連動した形で広告が表示されるため「キーワード連動型広告」「検索連動型広告」とも呼ばれます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- リスティング広告
- リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を、有料で表示するサービスのことです。ユーザーの検索結果に連動した形で広告が表示されるため「キーワード連動型広告」「検索連動型広告」とも呼ばれます。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- アカウント
- アカウントとは、コンピューターやある会員システムなどサービスを使うときに、その人を認識する最低必要な情報として、パスワードと対をなして使う、任意で決めるつづりです。ユーザー、ID、などとも言います。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- ブログ
- ブログとは、ホームページの一種です。運営者はブログシステムに登録し、利用開始をすることで、ホームページ制作のプログラム技術を修得する必要なく、本文のみを投稿しつづければ、公開・表示はおろかページの整理や分類なども効率的に行えるシステムを言います。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- 口コミ
- 「口頭でのコミュニケーション」の略で、消費者の間で製品やサービスの評価が伝達されることです。 一方で、不特定多数の人々に情報が伝達されることをマスコミと使われます。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- デバイス
- デバイスとは「特定の機能を持つ道具」を表す語で、転じてパソコンを構成するさまざまな機器や装置、パーツを指すようになりました。基本的に、コンピューターの内部装置や周辺機器などは、すべて「デバイス」と呼ばれます。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- データベース
- データベースとは、複数のアプリケーションまたはユーザーによって共有されるデータの集合体のことです。特定のテーマに沿ったデータを集めて管理され、検索や抽出が簡単にできるようになっているものを指します。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- リスティング広告
- リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を、有料で表示するサービスのことです。ユーザーの検索結果に連動した形で広告が表示されるため「キーワード連動型広告」「検索連動型広告」とも呼ばれます。
- サイクル
- サイクルとは、スタートしてゴール、そしてまたスタートと、グルグルと循環して機能する状態のことを言います。まわりまわって巡っていく、といった循環機構をさすことが多いです。水の循環サイクルというように、実は繰り返しになってしまう使われ方もすることもしばし。また、自転車に関する事柄として、サイクルスポーツなどという使われ方をされることもあります。
- アプリ
- アプリとは、アプリケーション・ソフトの略で、もとはパソコンの(エクセル・ワード等)作業に必要なソフトウェア全般を指す言葉でした。 スマートフォンの普及により、スマートフォン上に表示されているアイコン(メール・ゲーム・カレンダー等)のことをアプリと呼ぶことが主流になりました。
- ウェアラブルデバイス
- ウェアラブルデバイスとは、手首や腕、頭など体の一部に装着して使用するコンピュータデバイスのことを指します。Googleの開発しているGoogleGlassやサムスンのGalaxyGear、AppleのAppleWatchなどがあります。メガネや腕時計のような形で身に付けることができ、スマートフォンにかわる端末として注目されています。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他