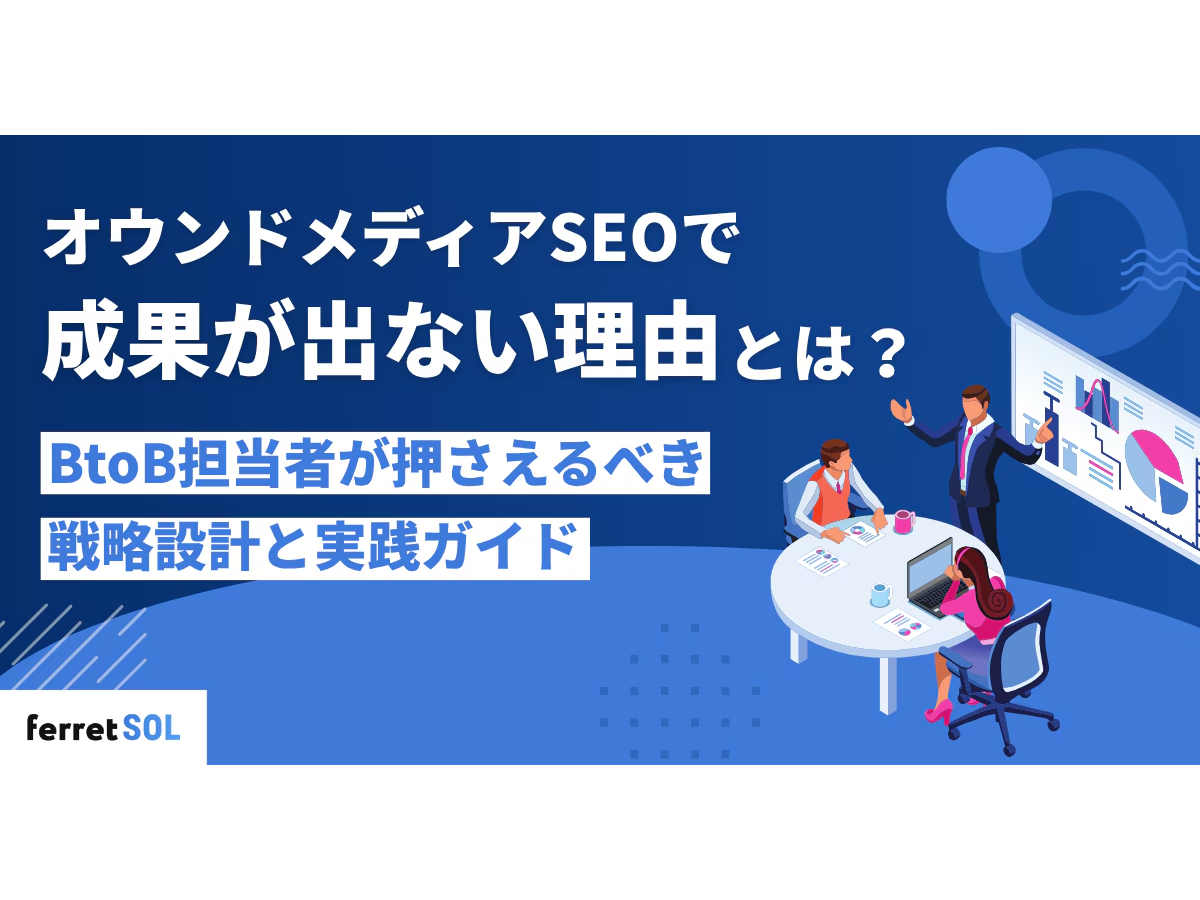Webサイト制作の方法と流れを詳しく解説!BtoBの注意点も紹介
デザインやWeb制作のディレクション経験がない場合、自社のWebサイトはどのようにして制作すればいいのか戸惑う方も多いのではないでしょうか。
そこで今回は、Webサイトを制作する方法を3つ紹介するとともに、制作の流れやスケジュールの目安、注意点などを解説します。ビジネス目的のWebサイトを制作するおすすめの方法も紹介していますので、ぜひご覧ください。
目次
- Webサイトを制作する方法は3つ
- Webサイト制作を外注する際に必須の要件定義と提案依頼書(RFP)とは?
- Webサイト制作におけるスケジュールの目安
- Webサイトを制作する前の準備
- Webサイトの見た目を作る方法
- Webサイトを作成・公開する時のポイント
- BtoBのWebサイト制作の注意点
- Webサイトを公開した後にすべきこと
- ビジネス目的のWebサイト制作にはCMSがおすすめ
- 自社に合った方法でWebサイトを制作しよう
▼これからのWebサイト制作はCMSがおすすめ

圧倒的に使いやすい!見たまま編集のCMS|ferret One
サービスサイト・ランディングページの制作・更新を自分で簡単に行えるCMSに加え、アクセス解析、メール配信などWebサイトの運営に必要な機能が全て揃っています。
Webサイトを制作する方法は3つ
Webサイトを制作する方法は大きく分けて以下の3つがあります。それぞれのメリットデメリットについて解説します。
- CMSを使って自社で制作する
- Webサイト制作会社に外注する
- 自社のエンジニアに依頼する
①CMSを使って自社で制作する
CMSとは、プログラミングやサーバーなどの専門知識がなくてもWebサイトを制作・更新できるシステムのことです。
プログラミングの知識がない人でも、用意されているテンプレートを選択したりテキストを変更したりするだけで、簡単に自社のWebサイトが作れます。
● メリット
CMSを使ってサイトを制作するメリットは、以下の通りです。
・ページの作成・変更・更新が容易
・サイト運営業務を分業できる
・統一感のあるWebサイトが作れる
・SEO対策ができる
CMS利用の最大のメリットは、HTMLやCSSなどの知識がなくともコンテンツの更新やデザイン変更が容易な点でしょう。クリックやドラッグ&ドロップなどの操作で簡単にサイトを制作できます。
また、CMSを使えばデザイン・編集・コンテンツ作成など、サイト運営業務を複数の担当者で分担できます。
さらに、CMSのWebサイト制作ではサイトのどのページにも同じデザインテーマが適用されるためデザインに統一感を出せます。全てのページのデザインを一括で変更できるので、ページそれぞれでデザインが異なりサイト全体の印象が不自然になってしまうことを防げます。
加えて、CMSで作成したページは検索エンジンに評価されやすい構成になっているため、特別なことをしなくてもSEO対策につながります。
● デメリット
CMSを使ってサイトを制作する場合に考えられるデメリットは以下の通りです。
・基本操作の習得は必要
・イレギュラーなデザインのページには対応できない
・無料のCMSはセキュリティのリスクも
CMSでサイトを作るには、まずツールの使い方を覚えなければなりません。ひと言でCMSといってもサービスによって操作性の難易度には差があります。使いやすさに考慮して作られたCMSを選びましょう。
また、CMSでは用意されたテンプレートに沿ってコンテンツを作成していくため、特殊なデザインのサイトは基本的に作れません。
さらに、無料のCMSを使う場合はセキュリティ面のリスクがある点も考慮しておきましょう。セキュリティ対策が不十分なCMSを選んでしまうと、情報漏えいなどのトラブルにつながる恐れがあるため、十分な対策がなされているツールを選ぶのがおすすめです。
参考記事:【無料・有料20選】CMSを徹底比較!導入のメリットや選ぶポイントを解説
▼セキュリティ・SEO対策も安心のCMSはこちら

圧倒的に使いやすい!見たまま編集のCMS|ferret One
サービスサイト・ランディングページの制作・更新を自分で簡単に行えるCMSに加え、アクセス解析、メール配信などWebサイトの運営に必要な機能が全て揃っています。
②Webサイト制作会社に外注する
Webサイトの制作を専門とする会社に外注し、自社のWebサイトを作ってもらう方法です。プロのデザイナー・エンジニアにデザインや構成、サイト構築、セキュリティ対策を任せられるので、クオリティの高いWebサイト制作が期待できます。
● メリット
制作会社に外注するメリットは以下の通りです。
・クオリティの高い自社Webサイトを制作できる
・コア業務にリソースを集中できる
・運用や作成に関する提案・コンサルティングを受けられる場合もある
Webサイト制作のプロに依頼することで、高品質の自社Webサイトを持つことができます。また、企画や要件さえ決定すれば、あとは制作会社の方で作業をしてくれるため、必要な業務に人員や時間といったリソースを傾けられます。
また、制作されたWebサイトへのセキュリティ対策はもちろん、会社によってはプロの視点からWebサイト運用に関する提案や、コンサルティングといったサービスを受けられることもあります。
● デメリット
Webサイト制作会社を利用するデメリットは以下の通りです。
・Webサイトの編集・更新作業がすぐにできない
・多額の外注費がかかる
・社内にノウハウを蓄積できない
Webサイト制作会社といった外部スタッフに制作を依頼している場合、デザインの変更やコンテンツの追加など、Webサイトの一部に変更の必要が生じたときに、すぐ対応できない場合があります。
編集の都度、見積もりや打ち合わせが必要になり「変更したい」と思ったその時にスピーディーな対応ができなくなってしまいます。
また、きちんとしたページを作るとなると、Webサイトの規模にもよりますが依頼には数十万〜数百万円の費用がかかります。企業ブランディングやコンサルティングの費用も含めるともっと多額になることもあるでしょう。
さらに、Webサイト制作会社に外注することで、社内にWebサイト制作・運営のノウハウを蓄積できないことも難点の一つです。
専門スキルや知識を持つ担当者が自社で育たないため、制作や運営をWebサイト制作会社に頼り続けざるを得ないことになります。
参考記事:Webサイト制作会社を選ぶときの6つのチェックポイント。制作会社の種類や契約時の注意点を解説
③自社のエンジニアに依頼する
コーディングやプログラミングなどの専門知識・スキルを持つ自社のエンジニアに、Webサイト制作を依頼する方法です。
設計段階から自社で行い、知識を持つ人材が運用するため、制作費・運営費・維持管理費などのコストをほとんどかけずに済みます。
● メリット
自社で制作するメリットは以下の通りです。
・外注するコストを抑えられる
・自由にカスタマイズできる
・管理・メンテナンスが容易
最大のメリットは、外注するよりもWebサイトの制作・運用におけるコストを抑えられるという点でしょう。外注すると数十万〜数百万円ほどの費用がかかりますが、自社のエンジニアに依頼する場合は、人件費のみで外注費は必要ありません。
また、デザインなどにおける制限がないため、サイトを自由にカスタマイズできます。自社で一からWebサイトを構築しているため、ちょっとしたデザインやコンテンツの修正・変更も簡単です。
● デメリット
デメリットは以下の通りです。
・デザインや機能面で見劣りする恐れがある
・大量のコンテンツを掲載するメディアなどには不向き
・エンジニアが退職すると管理できる人材がいなくなる
エンジニアはコーディングの知識がある人材とはいえ、やはりWebサイト制作を専門としているプロと比べると、どうしてもそのクオリティには不安が残ります。
また、HTML/CSSなどのコーディングでページを作成するため、記事やコンテンツを大量に生産し掲載していくオウンドメディアのようなページには不向きな方法です。この場合は、手軽にコンテンツを作成・管理できるCMSのほうが向いているでしょう。
さらに、Webサイトの制作・運営を担当していたエンジニアが退職してしまうことで、Webサイトの更新・保守ができなくなるといったリスクもあります。
社内の誰も対応できず、削除することもできないまま古いサイトが放置されてしまうといったことにもなりかねないため注意が必要です。
Webサイト制作を外注する際に必須の要件定義と提案依頼書(RFP)とは?
Webサイト制作を外注する場合に必要となるのが要件定義書・提案依頼書(RFP)です。
・要件定義書:サイトの仕様や必要な機能、スケジュールなど、Webサイト制作の基本となる情報をまとめた文書
・提案依頼書:RFP(Request for Proposal)とも呼ばれ、依頼者が制作会社に提出する書類。会社の現状の課題や発注したい内容、要望などを伝えるための文書
また、それぞれの書類には大まかに以下のような違いがあります。
| 要件定義書 | 提案依頼書 | |
|---|---|---|
| 目的 | Webサイトの仕様や機能を明確にする | ・認識のすり合わせ ・自社が抱える課題の明確化 ・相見積もりをする際の参考 |
| 作成者 | 制作会社 | 発注側の企業 |
ここからは、要件定義が行われる流れや提案依頼書に記載すべき内容について解説します。
要件定義の3ステップ
Webサイト制作を外注する場合、要件定義書は制作会社が作成しますが、発注側も要件定義の流れを把握しておくことで、スムーズに進行できるでしょう。ここでは、要件定義の流れを3ステップで紹介します。
1.ヒアリングと課題整理
Webサイト制作の要件定義では、まず制作会社からのヒアリングや課題整理が行われます。このステップがWebサイト制作における土台となるでしょう。
ヒアリングでは、主に以下のような情報について聞かれることが多いため、これらの情報を用意しておくのがおすすめです。
- ターゲットユーザー
- Webサイトで解決したい課題
- 目的・目標
- 予算
- 納期
ヒアリングが終了したら、制作会社が収集した情報をもとにWebサイトの方向性や目的を達成するための施策などを検討します。
2.打ち合わせ・合意形成
制作会社が方向性などを決定したら、再び発注者と制作会社の間で打ち合わせ・すり合わせをした上で、合意形成を行います。
合意形成をした後は要件定義書やサイトの制作が進行してしまうため、上長はもちろんサイト制作に関わる部署の合意も得ておきましょう。
Webサイトのコンセプトや具体的なイメージを共有することで、認識のズレや要件を再検討するといったトラブルを防ぐことができます。
3.要件定義書の作成
課題やWebサイトの方向性・施策・イメージなどが確定したら、制作会社にて要件定義書が作成されます。
一般的にWordやExcel、PowerPointなどの書式で作られるケースがほとんどであるため、希望の書式がある場合は事前に伝えておきましょう。
要件定義書をもとに、より詳細なサイトの設計や費用・スケジュールの見積もりなどが行われます。
提案依頼書に記載すべき項目
ここでは、提案依頼書に記載すべき項目を紹介します。提案依頼書には決まったフォーマットがあるわけではありませんが、以下に挙げる項目を網羅していれば、自社の課題や要望を制作会社へ適切に伝えられるでしょう。ぜひ参考にしてみてください。
● Webサイト制作の目的・ターゲット
提案依頼書には、どのような目的で、どんな層をターゲットにしたWebサイトを制作したいのかをできるだけ具体的に記載しましょう。自社側でここをしっかりと決めておかないと、制作会社からの提案が的外れになってしまう可能性があります。
記載しておきたいのは具体的に以下のような項目です。
- Webサイトの目的(認知度アップ・ブランド力強化・集客・問い合わせ数アップなど)
- 事業やWebサイトのメインターゲット(ユーザー像・顧客層・ペルソナなど)
- 競合・参考サイト(競合会社と比べた自社の立ち位置や強みを明確にしておく)
● 目標(KPI)・課題
Webサイト制作を行う以上、達成すべき目標や解決すべき課題を設定しておかなくてはいけません。目標・課題は具体的な指標や数値に落とし込み、定量的に評価できるようにしておきましょう。
記載しておきたいのは具体的に以下のような項目です。
- 現状の課題(認知度が低い、事業を拡大したい、集客力が乏しいなど)
- 目標(KGI/KPI)(問い合わせ数〇件アップ・集客数〇件を目指すなど)
● 委託したい内容(要望)
Webサイトの制作において委託したい内容はなにか、どこまでどのような機能を必要とするのかを決めておきます。委託する業務の範囲や、行うべき作業の範囲をあらかじめ決めておかないと、制作プロセスが際限なく増えてしまう恐れがあります。
記載しておきたいのは具体的に以下のような項目です。
- 概算ページ数(どのようなページがどのくらい必要か?を概算で)
- 必要な機能(問い合わせ機能・面談予約機能・チャット機能など)
- 希望するデザイン(デザインの方向性・使用するロゴなど)
- テキスト・画像素材(会社で用意するのか、商用素材を利用するのかなど)
- 公開後に運用を行いたいページ(お知らせやコラムページなど後で情報更新を行いたい箇所)
● 提案に入れてほしい内容
最後に、制作会社から提案してほしい内容を記載しましょう。提案してもらうべき内容の例は、以下の通りです。
- 全体のスケジュール
- 予算の見積もり
- 著作権の取り扱いや保証期間
- サイトマップの構成
上記の他に、知りたいことや聞きたいことなどを盛り込むのも良いでしょう。提案依頼書については、以下の記事でも詳しく解説しています。
参考記事:RFP(提案依頼書)とは|ホームページ制作時における役割と活用方法
Webサイト制作におけるスケジュールの目安
Webサイト制作のスケジュールはサイトの規模によって異なります。それぞれの規模に応じたスケジュールの目安は以下の通りです。
| サイト規模 | 目安 |
|---|---|
| 小規模サイト(~20ページ程度) | 2~3ヶ月 |
| 中規模サイト(30~100ページ程度) | 6~8ヶ月 |
| 大規模サイト(100ページ以上) | 8~12ヶ月 |
シンプルな構造の小規模サイトであれば、2〜3ヶ月ほどで制作できます。ただ、小規模であっても採用サイトや新商品の告知サイトのような特別なページは素材や写真・動画などの準備に時間がかかります。
中小企業のサイトや、コンテンツの多い採用サイトなどが中規模サイトにあたります。どのような情報を盛り込むかによってスケジュールが変動するため、ある程度余裕を持たせておきましょう。
大企業のコーポレートサイトやオウンドメディアのような大規模サイトには、長くて1年ほどの期間がかかります。企業情報やお知らせのほか、製品・サービスに関するページやお問い合わせフォームの設置など、様々なコンテンツがあるため、制作作業だけでなくテストにもかなりの時間を要するためです。
関連記事Webサイト制作の見積もり基準から費用相場、注意ポイントを解説
Webサイトを制作する前の準備
自社でWebサイトを制作する場合は、まず以下の準備を行ってから制作に移りましょう。
ターゲットやペルソナ、ゴールを設定する
最初に、自社サイトで集客や告知を行う際に見てもらいたい「ターゲット」を設定していきます。ターゲットを設定することで、訴求力が強まり、集客効果や広告効果にもプラスに影響します。
ターゲットでは対象となる読者の年齢層や役職などを設定しますが、そこからさらに踏み込んで「ペルソナ」を設定することもあります。ペルソナを設定する際は、以下のように実在している人物像を描き出しましょう。
【ペルソナの例】
20代前半の大手企業に3年間勤めるOLで、休日には友達と原宿や表参道でショッピングを楽しむ、ファッション好きのAさん
そして、Webサイト制作にあたっては、以下のようなゴールも設定しましょう。
- 商品PRや販売促進
- 集客を加速させたい
- 問い合わせを増やしたい
ゴールが設定されていないと、制作にかかわるデザイナーやマネジャーも、一体どこを目指しているのかが分からなくなります。
コンセプトを決定する
ターゲットやゴールを設定した後は、具体的なコンセプトを決めていきます。コンセプトが決まっていないと、制作にかかわるメンバーとの間で、齟齬が生まれるからです。
一例として、美容室のサイトのデザインコンセプトを挙げてみましょう。
- どこよりも低価格でオシャレなヘアスタイルを提供する美容室として知ってもらいたい。
- 20代だけでなく、30代~40代のミドルの女性層にも手軽に利用してほしい。
- 予約の取りやすさは都内トップクラス。切りたいときにいつでも気軽に寄れる、便利な店であることを知ってほしい。
抽象的な言葉を具体的に定義することで、サイト制作にかかわる多くの人との共通認識を作ることができます。曖昧なイメージのまま制作を進めてしまうと、誰のためのサイトなのかがわからなくなり、伝えたい内容が読者に届かなくなります。
さらに、どこに何の情報があるのか、ユーザビリティの観点からも使いづらいサイトになってしまいます。コンセプトがはっきりしていれば、情報も選別され、誰が見てもわかりやすいサイトになるでしょう。
サイトのタイトルやキャッチコピーを決める
大まかなコンセプトが決定したら、サイトのタイトルを決めていきます。
すでにお店や会社を運営している場合は、お店や会社の名前がそのままタイトルになる場合が多いと思いますが、新たにWebメディアや新規コンテンツとして立ち上げる場合には、ユニークで覚えやすい名前をつけるとよいでしょう。
サイトのタイトルが決まったら、キャッチコピーを決めていきます。キャッチコピーは必須というわけではありませんが、キャッチコピーがあると、そのサイトが何のために存在しているのかがわかります。
サイトのキャッチコピーを付けるコツは、「一言で何なのかが分かる」コピーをつけるということです。
いくつか例を挙げてみましょう。

現地のホストのお家に宿泊して、191か国以上で暮らすように旅しよう
画像出典・引用元:Airbnb

写真を1枚選ぶだけ
画像出典・引用元:レター

みんなで遊べば、地球は楽しい
画像出典・引用元:trippiece
このように、優れたキャッチコピーはそれだけで、どんなサイトなのか、どんなサービスなのか、イメージが湧いてきます。
逆に言えば、ターゲットやゴールが鮮明でないと、優れたキャッチコピーは生まれません。誰のための、どんなことをしてくれるものなのかが、短いキャッチコピーに宿っているからです。
キャッチコピーを決める上で、一点だけ注意したいことがあります。それは、サービス内容をキャッチコピーに当てはめることです。
「無料でサイトが作れる」「動画が毎月一定額で見放題」といったサービス名を冠したキャッチコピーは、競合となるサイトにも同じことが言えます。キャッチコピーは、単なる説明ではなく、サイトのブランディングにもなります。
プライスレスと聞いたらMasterCard、というように、キャッチコピーを聞いたらこのブランドだ、というつながりを意識的に作っていきましょう。
ポリシーを決める
サイトを作成する際には、制作ポリシーを決めておく必要があります。制作ポリシーとは、「このような方針でサイトを作っていきます」というルールのようなものです。
例えば、「デスクトップ用とモバイル用でWebサイトをわけるか、レスポンシブ・デザインにするか」「対応ブラウザをどこまでに設定するか」「WordPressなどのCMSを使うか」などです。
初めに制作ポリシーを決めておかないと、デザイナーやコーダーが複数いる場合、それぞれ独断でデザインやコーディングを行うことになり、のちの統合やメンテナンスに手間がかかってしまいます。全体的な制作ポリシーだけでなく、デザインポリシーやコーディングポリシーも決めておくとよいでしょう。
また、サイト上で個人情報を取得する場合には、プライバシーポリシー(個人情報保護方針)や利用規約など、防御的情報を準備しておきましょう。
プライバシーポリシーや利用規約を始めから作るのが面倒な場合には、インターネット上で検索すればテンプレート(ひな形)が配布されていますので、利用してもよいでしょう。
サーバー・ドメインを取得する
最終的に作成したサイトをインターネット上に公開する場合は、サーバーやドメインを手配する必要があります。
大規模なWebサービスを作るのであれば、自社でサーバーを組み立てるのも一つの方法ですが、メンテナンス時間やメンテナンスにかかる人件費、電気代など、大きなランニングコストがかかってしまいます。
100円台から契約できるレンタルサーバー業者もあるので、アフターケアや月々の費用、セキュリティ対策などを考慮して最適なプランを選びましょう。
ドメインはタイトルと同じく、サイトの顔となる部分です。記憶に残りやすい、シンプルでユニークなドメインを取得しましょう。
関連記事【初心者向け】サイト作成の手順から準備・方法まで詳しく解説
費用・予算を決める
Webサイトの制作に入る前には、予算を決めておきましょう。自社でかけられる予算を事前に決めておかなくては、制作するWebサイトの規模や形態が定まらず作業にとりかかれません。
以下に、Webサイトの一般的な制作費用の相場を紹介します。
- シングルページ(1ページ)サイト・・・約20万円~30万円
- 小規模~中規模の企業サイト・・・約50万円~300万円
- 大規模な企業サイトやオウンドメディアなど・・・約300万円~
- ECサイトの制作・・・約50万円~100万円
なるべく費用をかけずにサイトを制作したい場合は、外注ではなくCMSなどを使って自社で作る方法がおすすめです。
参考記事:ホームページ制作の相場はいくら?依頼先や種類別の相場と制作にかかる費用
Webサイトの見た目を作る方法
Webサイトを制作する前の準備が整ったら、実際にサイトを作成していきましょう。ここからは、サイトの見た目の部分を作る方法について解説します。
サイトマップを作る
まずは、サイトの設計図となるサイトマップを作っていきます。サイト全体の完成図を想定しておかないと、どこを目指せばいいのかわからなくなるからです。
必要となるページを洗い出したうえで、どのような構造にするのかを決めていきましょう。サイトマップには、前半で見てきたターゲットや目的について考えたことも反映させていきます。
サイトマップの作り方は、以下の記事で解説しています。
参考記事:サイトマップとは?基礎知識とWebサイトにおける役割、SEOへの効果
ページのレイアウトを決める
次に、トップページや商品紹介のページ、会社概要のページなど、様々なページのレイアウトを決めていきます。この具体的なページの設計図のことを、ワイヤーフレームと呼ぶことがあります。
サイトを見ている人は、デスクトップ画面では「左から右・上から下」、モバイル画面だと「上から下」に視線を動かします。優先順位が高いほど上に配置して目立たせる必要があります。また、見せたいものを意識してレイアウトを組んでいきます。
ページの設計図は、一昔前はスケッチで済ませてしまう人もいましたが、最近ではプロトタイピングツールと呼ばれるデザイン・マネジメントツールも増えてきました。プロトタイピングツールを使うことで、クリックやタップで次の画面に移動し、実際に作動しているように見えます。
UI・UXを意識して設計する
Webサイト制作では、UI・UXを意識して設計することが重要です。
・UI(ユーザーインターフェース):使いやすさ、分かりやすさ
・UX(ユーザーエクスペリエンス):ユーザーがWebサイトを通じて得られる体験
Webサイトはデザインや操作性などにおいて、顧客にとって快適なもの、また顧客のニーズを満たすものでなくてはいけません。
顧客が必要な情報にスムーズにアクセスできるよう導線を設計することや、コンテンツ・ボタンを配置すること、分かりやすく見やすいデザインや素材を採用することなどが、UI・UX施策にあたります。
デザイン・トーン・フォント・文体を統一する
Webサイト全体のデザイン・フォントなどは、ガイドラインを策定しブレのないようにしましょう。Webサイト全体のデザインや文体に一貫性がないと、ページを閲覧したユーザーが違和感を覚えてしまうからです。
文章の書き方についても、トーンや表記ルールを決めておく必要があります。
もちろん、採用するデザイン・文体などは訴求すべきターゲットに合わせたものにしましょう。
Webサイトを作成・公開する時のポイント
Webサイトの見た目を作ったら、実際にサイトの中身を制作していきます。
CMSやコーディングでサイトを作る
自社でサイトを作る場合は、CMSまたはエンジニアによるコーディングという2つの方法があります。CMSを使うと、テンプレートを選んでテキスト入力やドラッグ&ドロップなどの操作をするだけで、簡単にサイトを制作できます。
コーディングでWebサイトを制作する場合、ホームページビルダーやBiNDなどのシステムで編集する方法もありますが、こうしたツールを使うにはHTML/CSSなどの知識が必要となり、余計なコードが挿入されることもあります。
以下の状況に当てはまる場合は、CMSを利用して作るのがおすすめです。
- 手間をかけず簡単にWebサイトを作りたい
- 担当者にコーディングやデザインの専門知識がない
- 自社にエンジニアがいない
- 面倒な設定などはしたくない
▼セキュリティ・SEO対策も安心の国産CMSはこちら

圧倒的に使いやすい!見たまま編集のCMS|ferret One
サービスサイト・ランディングページの制作・更新を自分で簡単に行えるCMSに加え、アクセス解析、メール配信などWebサイトの運営に必要な機能が全て揃っています。
SEO対策を考慮する
Webサイトを制作しコンテンツを充実させても、閲覧者が増えなくてはターゲットへの訴求や成約にはつながりません。そのため、Webサイトを構築する際はSEO対策もしておきましょう。
サイト制作時に行うべきSEO対策の例は、以下の通りです。
- titleやdescription、h1タグの最適化
- HTML構造の最適化
- 404エラーページの作成
- XMLサイトマップの送信
- レスポンシブ対応
なお、あらかじめSEO対策がなされているCMSを使えば、上記のような作業を簡略化できます。SEO対策の具体的な方法については、以下の記事で解説しています。
参考記事:サイトリニューアル時に行う10のSEO対策。アクセス減少した失敗例や注意すること
ロゴやバナーを作成する
コーダーのほかにグラフィックデザイナーがいる場合は、コーディングと同時進行でサイトの顔となるロゴやバナーなどのクリエイティブの作成を行います。事前に設計図で打ち合わせたサイズでデザインを行います。
忘れがちなのが、ファビコンの作成です。ファビコンとは、Webサイトをブックマークした際に横に表示されるアイコンです。
最近では、ブラウザのブックマーク用のファビコンだけでなく、iOSやAndroidでホーム画面にサイトのブックマークを単独で作成できるので、忘れずに設定しておきましょう。
ブラウザチェックを行う
ブラウザチェックとは、色々なブラウザでサイトを確認し、レイアウトが崩れていたり、表示のおかしいところがないかを確認する作業です。
世の中にはたくさんのブラウザがありますが、Microsoft Edge、Google Chrome、Mozilla Firefox、Safariは多くの人が使っているので、最低限チェックしておきたいところです。また、スマートフォンやタブレットでも想定どおりに表示されるか確認しておきましょう。
テストサーバーで確認する
ローカル開発環境で開発した場合は、自分自身や自社のメンバーしかアクセスできない状態になっています。インターネット上で誰でも閲覧できるようにするためには、サーバーにアップロードして動作を確認する必要があります。
いきなり本番環境で公開して動かなかったり、リンクが切れていたり、リンクをクリックしたらまったく別の場所に飛んでしまうこともあるので、まずはテスト環境のサーバーで動作を確認します。問題がなければ、本番環境で公開をします。
CMSを使ってサイトを作る場合は、ツールのプレビュー画面などで表示や動作を確認し、公開を行いましょう。
保守管理・更新
Webサイトは作成・公開すればそこで終わりというものではありません。公開後も適宜、メンテナンスや更新を行う必要があります。保守管理・更新で行う作業は以下の通りです。
- 古くなった情報を更新する
- 新たなコンテンツを追加する
- PV数やCV率の分析を行い、改善する
- SEO対策を強化する
保守管理・更新のポイントは定期的に行うことです。目標とするPV数やCV率を達成できない場合は、マーケティング会社などにサポートを依頼してみましょう。
BtoB向けのWebサイト制作の注意点
ここでは、BtoB向けのWebサイトを制作するにあたって注意したいポイントを紹介します。
ターゲットやニーズを明確にする
Webサイトにアクセスするターゲットのイメージや、Webサイトを制作することによってユーザーのどのようなニーズを満たしたいのかを明確にしましょう。
いくらクオリティの高いWebサイトを作れたとしても、自社の顧客やユーザー像と合っていなければ十分な効果を発揮できません。
ただ、ターゲット層を広げすぎたり抽象的なユーザー像を設定して制作を進めると、誰にも刺さらないWebサイトになってしまうため注意が必要です。自社の顧客情報などをもとに、ターゲットやニーズはできるだけ具体的かつ明確に決めておきましょう。
競合サイトを分析し、自社の強みを知る
BtoBのWebサイト制作においては、自社のポジション設定が重要です。どのような業界でも、同業他社は複数存在しWebサイトで認知度アップや集客を図る企業は数多くあります。
そのため、Webサイトを制作するにあたって他社との差別化ができていなくては、せっかく作った自社のWebサイトが埋もれてしまうでしょう。競合サイトを分析し、他社にない自社の特徴や強みは何か、それをどうアピールしていくかを考えなくてはいけません。
サイト設計は分かりやすさを意識する
BtoBのWebサイトにおいては、分かりやすいサイト設計にすることが重要です。
Webサイトを閲覧する側は、限られた時間の中で必要な情報を収集することを目的にしています。凝ったデザインや複雑なサイト構造では「見づらい」「分かりにくい」と感じてしまい、必要な情報にたどり着けないままページを離脱してしまう恐れがあります。
そのため、サイト構造はできるだけシンプルにし、ユーザーが必要とするコンテンツをスムーズに見つけられるような構造にしておく必要があるでしょう。
BtoBのサイトの場合、サービス紹介のページや問い合わせフォームへのリンクを目立たせて分かりやすくしておくといった対策が有効です。
デザインはユーザーの信頼・好感度を重視
サイトのデザインは奇をてらったものにするのではなく、ユーザーが信頼できる見た目や好感を感じるデザインを優先しましょう。必要以上の奇抜さや派手さのあるデザインだと、かえって会社のイメージを損ねてしまう恐れがあります。
また、BtoB事業はユーザーの検討期間が長く複数人の意思決定者がいるため、信頼を損ねてしまうと購買につながらない可能性が高まります。そのため、以下のような点に注意しながら信頼・好感を持ってもらえるデザインにしましょう。
- 無料で公開されている写真素材だけでなくオリジナルの写真も使用する
- 赤や黄色といった警戒色ではなく、青や緑、紫などの落ち着いた色を選ぶ
- 会社の情報を記載する
質の高いコンテンツを提供する
BtoBのWebサイトにおいてはコンテンツの量よりも質を重視しましょう。
網羅性のある記事や信頼性のある情報、ユーザーの役に立つ情報が、サイト全体の信頼性・企業イメージの向上にもつながります。逆にコンテンツの不備や稚拙な記事、真偽不明の情報の掲載などはユーザーの信頼を失う恐れがあります。
また、自社で扱う商品やサービスの情報を載せる場合は、その概要や特長が具体的に分かるようにしておきましょう。
参考記事:BtoBマーケティングの第一歩。勝つための「サイト制作」の基本
▼BtoBに特化したサイト制作ならferret One

サイト制作・初期戦略から相談できます|ferret One
サービスサイト・ランディングページの制作・更新を自分で簡単に行えるCMSに加え、アクセス解析、メール配信などWebサイトの運営に必要な機能が全て揃っています。
Webサイトを公開した後にすべきこと
ここでは、Webサイトを制作・公開した後にすべきことを2つ紹介します。
検索エンジンに公開を知らせる
サイトを公開したら、Web上のサイトや文書、画像などを収集し、検索データベースに保管するプログラムである「クローラー」に、自社サイトを見つけてもらえるよう対策をしましょう。
Googleやbingの提供するWebマスターツールに登録をすると、クローラーが自動的にサイトを巡回してくれるだけでなく、SEOに必要な様々な機能を提供してくれるので、非常に便利です。
以下の記事では、代表的な検索エンジンであるGoogleにページの存在を伝え、クロールしてもらう方法を解説していますので、あわせてご覧ください。
参考記事:クローラーって何!? SEOに絶対必要!サイトの情報を取得させ、検索結果に表示させよう
SNSやリスティング、プレスリリースで発信する
サイトを公開した段階では、検索流入が頼みの綱となります。一方で、TwitterやFacebook、InstagramなどのSNSを活用すれば、こちらから戦略的に存在を認知させることができます。
また、ある程度まとまった予算があれば、リスティング広告を打ったりプレスリリースを出すことで、自分のサイトを宣伝することもできます。
SEOだけに頼ってしまうと、Googleの検索ポリシーが急に変更されて検索結果が落ちた時に、アクセスが急激に落ちてしまうことがあります。できるだけ入り口となる媒体を分散して多く持っておくことで、そうしたリスクを回避することもできます。
ビジネス目的のWebサイト制作にはCMSがおすすめ
近年、サイト制作にCMSを活用する企業が増えています。ビジネス目的のWebサイトの場合、その後の運用・改善のしやすさが重要だからです。
そして、ビジネス向けのサイトを制作するなら、当メディア「ferret」を運用する株式会社ベーシックが提供している「ferret One」がおすすめです。
ferret Oneには、BtoBマーケティングに役立つ機能が一通り揃っているので、サイト制作だけではなくマーケティング活動も効率化できます。
❶ 圧倒的に使いやすい「見たまま編集」のCMS
WordPressと違い「見たまま編集」のCMSなので、HTMLやサーバの知識のない方でもサイト作成ができます。やりたい施策がすぐ実行できてPDCAがスピーディーに回せるのはもちろん、サイト運用の属人化を防ぐことができます。
❷ サイト経由のお問い合わせを増やせる機能
CTAボタンやお問い合わせフォームも、パーツを配置するだけで簡単に設置できます。自動返信メールや、ナーチャリングのメール配信をできる機能も充実しています。
❸ SEOやコンテンツマーケティング機能
ツール自体がSEOに強い仕組みとなっていることに加え、記事・ホワイトペーパー・動画などコンテンツマーケティング施策に必要な機能が一通りそろっています。
▼これからのサイト制作は|ferret One

サイト制作・初期戦略から相談できます|ferret One
サービスサイト・ランディングページの制作・更新を自分で簡単に行えるCMSに加え、アクセス解析、メール配信などWebサイトの運営に必要な機能が全て揃っています。
自社に合った方法でWebサイトを制作しよう
Webサイトの制作および公開後における一連の流れを解説しました。制作メンバーの人数やサイトの規模によっても変わってきますが、基本的な制作や制作時の注意点は文中でお伝えした通りです。
最近では、一部もしくは全体の作業をクラウドソーシングで業務委託することも珍しくなくなってきました。しかし、外部に委託する場合でも、こうした制作の流れを知らないと、思ったとおりのデザインにならないこともあります。
また、シングルページや小規模のサイト制作であれば、外注やコーディングではなくCMSを活用し自社で行ったほうが人員や費用のコストを低く抑えられる場合もあります。制作したいWebサイトの規模や方向性に適した方法を選びましょう。
この記事を読んだ方におすすめ

Webサイト作成に役立つCMS。そのメリット・デメリットを解説!
CMSとは、コンテンツ・マネジメント・システム(コンテンツ管理システム)の略称で、Webの専門知識を持たない初心者でも、簡単にWebサイトの運営ができる管理システムのことです。今回はCMSのメリット・デメリットに加え、導入前に知っておきたいポイントもまとめました。

CMSとは?基礎知識や導入するメリット・デメリットを紹介!
サイトの制作や運用時に、よく「CMS」という言葉が使われますが、実際のところ「CMSって何?」「他のシステムとの違いは?」とイマイチ内容を理解していない方も多いのではないでしょか?今回は、CMSとは何かという基本的な情報やメリット・デメリットについて紹介します!CMSサービスの比較一覧表もありますので、ぜひ最後までご覧ください。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- HTML
- HTMLとは、Webページを記述するための言語です。"HyperText Markup Language "の略です。"<"と">"にはさまれたさまざまな種類の「タグ」によって、文章の構造や表現方法を指定することができます。
- CS
- CSとはCustomer Satisfactionの略称で「顧客満足度」を意味します。顧客との関係維持、サービスの発展に関するマーケティング戦略に関わる用語です。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- コンサルティング
- ビジネスはより高度化し専門的になっています。そこで、事業者のみならず専門家を呼び、彼らからアドバイスを受けながら、日々の活動を確認したり、長期の戦略を考えたりします。その諸々のアドバイスをする行為自体をコンサルティングといい、それを行う人をコンサルタントと言います。特別な資格は必要ありませんが、実績が問われる業種です。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- HTML
- HTMLとは、Webページを記述するための言語です。"HyperText Markup Language "の略です。"<"と">"にはさまれたさまざまな種類の「タグ」によって、文章の構造や表現方法を指定することができます。
- CS
- CSとはCustomer Satisfactionの略称で「顧客満足度」を意味します。顧客との関係維持、サービスの発展に関するマーケティング戦略に関わる用語です。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ターゲットユーザー
- ターゲットユーザーとは、自社の商品やサービスを利用するユーザー、または、運営するホームページの閲覧を増やしたいユーザーを、性別、年代、職業など、様々な観点から具体的に定めることを指します。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- コンセプト
- コンセプトとは、作品やサービスなどに一貫して貫かれている考え方をいいます。デザインと機能がバラバラだったり、使い勝手がちぐはぐだったりすると「コンセプトが一貫してないね」などと酷評されてしまいます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- KGI
- KGIとは、重要目標達成指標のことで、Key Goal Indicatorの略です。プロジェクトや組織などにおいて設定する、数値で計測可能な目標のことをさします。
- KPI
- KPIとは、目標に対して施策がどの程度達成されているか、を定量的に表す指標のことをKPI(重要業績評価指標)といいます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- サイトマップ
- サイトマップとは、ホームページの中にあるページ構成を一目見て分かるようにした、目次のような案内ページのことを指します。ホームページ内にある全てのページへのリンクが一覧になっていることが多いです。はじめて訪問した人でも、どこに何があるのかがすぐに分かるようにすることを目的として作成されます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コーポレート
- コーポレートとは、日本語の「企業」のことです。インターネット上で「コーポレートサイト」という場合は、企業のホームページであることを表します。また、コーポレートは接頭語として使われることが多く、「コーポレートガバナンス(企業内統制)」などのように、他の単語と組み合わせて使うことが多いようです。会社そのものを指すことが多い「カンパニー」とは使い方が異なります。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- 広告
- 広告とは販売のための告知活動を指します。ただし、広告を掲載するための媒体、メッセージがあること、広告を出している広告主が明示されているなどの3要素を含む場合を指すことが多いようです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- コンセプト
- コンセプトとは、作品やサービスなどに一貫して貫かれている考え方をいいます。デザインと機能がバラバラだったり、使い勝手がちぐはぐだったりすると「コンセプトが一貫してないね」などと酷評されてしまいます。
- コンセプト
- コンセプトとは、作品やサービスなどに一貫して貫かれている考え方をいいます。デザインと機能がバラバラだったり、使い勝手がちぐはぐだったりすると「コンセプトが一貫してないね」などと酷評されてしまいます。
- ユーザビリティ
- ユーザビリティとは、ホームページの使いやすさのことです。万人にとって使いやすいホームページは存在しませんが、運営者はターゲットとするユーザーに便利に使ってもらうために、優先させることや割り切ることを検討し改善する必要があります。
- コンセプト
- コンセプトとは、作品やサービスなどに一貫して貫かれている考え方をいいます。デザインと機能がバラバラだったり、使い勝手がちぐはぐだったりすると「コンセプトが一貫してないね」などと酷評されてしまいます。
- コンセプト
- コンセプトとは、作品やサービスなどに一貫して貫かれている考え方をいいます。デザインと機能がバラバラだったり、使い勝手がちぐはぐだったりすると「コンセプトが一貫してないね」などと酷評されてしまいます。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- キャッチコピー
- キャッチコピーとは、商品などの宣伝の際に使用される文章のことです。 宣伝をする対象のイメージや特徴を簡潔にまとめつつ、見た人の印象に残る必要があります。一言で完結するものから数行になる文章など、実際の長さはバラつきがあります。 キャッチコピーの制作を職業とする人のことを、「コピーライター」と言います。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- WordPress
- WordPressとは、CMS(コンテンツマネジメントシステム)の1種で、ホームページ管理システムのことです。ブログ感覚で記事の修正・追加が行えるうえ、通常のホームページ並みのデザインを作成することができます。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- ドメイン
- ドメインとは、インターネット上で利用可能なホームページやメールなどを識別するときの絶対唯一の綴りを言います。電話番号や自動車ナンバーが同一のものがないのと同様に、インタネットにおいても、2つとして同じドメインは存在できない、といった唯一無二の綴りです。
- ドメイン
- ドメインとは、インターネット上で利用可能なホームページやメールなどを識別するときの絶対唯一の綴りを言います。電話番号や自動車ナンバーが同一のものがないのと同様に、インタネットにおいても、2つとして同じドメインは存在できない、といった唯一無二の綴りです。
- タイトル
- ホームページのソースに設定するタイトル(title)とは、ユーザーと検索エンジンにホームページの内容を伝えるためのものです。これを検索エンジンが認識し検索結果ページで表示されたり、ユーザーがお気に入りに保存したときに名称として使われたりするため、非常に重要なものだと考えられています。「タイトルタグ」ともいわれます。
- ドメイン
- ドメインとは、インターネット上で利用可能なホームページやメールなどを識別するときの絶対唯一の綴りを言います。電話番号や自動車ナンバーが同一のものがないのと同様に、インタネットにおいても、2つとして同じドメインは存在できない、といった唯一無二の綴りです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- サイトマップ
- サイトマップとは、ホームページの中にあるページ構成を一目見て分かるようにした、目次のような案内ページのことを指します。ホームページ内にある全てのページへのリンクが一覧になっていることが多いです。はじめて訪問した人でも、どこに何があるのかがすぐに分かるようにすることを目的として作成されます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- サイトマップ
- サイトマップとは、ホームページの中にあるページ構成を一目見て分かるようにした、目次のような案内ページのことを指します。ホームページ内にある全てのページへのリンクが一覧になっていることが多いです。はじめて訪問した人でも、どこに何があるのかがすぐに分かるようにすることを目的として作成されます。
- サイトマップ
- サイトマップとは、ホームページの中にあるページ構成を一目見て分かるようにした、目次のような案内ページのことを指します。ホームページ内にある全てのページへのリンクが一覧になっていることが多いです。はじめて訪問した人でも、どこに何があるのかがすぐに分かるようにすることを目的として作成されます。
- トップページ
- インターネットのWebサイトの入り口にあたるページのことをトップページといいます。 一般的には、階層構造を持つWebサイトの最上位のWebページをさします。サイト全体の顔としての役割も果たすため、デザインなどで印象を残すことも考えたサイト作りも有効となります。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- レイアウト
- レイアウトとは、もともと「配置」や「配列」を指す語です。ここでは、「ホームページレイアウト(ウェブレイアウト)」と呼ばれる、ホームページにおけるレイアウトについて説明します。
- レイアウト
- レイアウトとは、もともと「配置」や「配列」を指す語です。ここでは、「ホームページレイアウト(ウェブレイアウト)」と呼ばれる、ホームページにおけるレイアウトについて説明します。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- UI
- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。
- UX
- UXとは、ユーザーエクスペリエンス(User Experience)の略で、ユーザーが製品・サービスを通じて得られる体験を意味します。似たような言葉に、UI(ユーザーインターフェイス、User Interface)がありますが、こちらはユーザーと製品・サービスの接触面を指した言葉です。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- 導線
- 導線とは、買い物客が店内を見てまわる道順のことです。ホームページにおいては、ページ内での利用者の動きを指します。 ホームページの制作にあたっては、人間行動科学や心理学の視点を取り入れ、顧客のページ内での動きを把握した上でサイト設計を行い、レイアウトや演出等を決めることが重要になります。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- UI
- UIとは、ユーザーインターフェイス(User Interface)の略で、ユーザー(使い手)とデバイスとのインターフェイス(接点)のことを意味します。
- UX
- UXとは、ユーザーエクスペリエンス(User Experience)の略で、ユーザーが製品・サービスを通じて得られる体験を意味します。似たような言葉に、UI(ユーザーインターフェイス、User Interface)がありますが、こちらはユーザーと製品・サービスの接触面を指した言葉です。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- フォント
- フォントとは、同一の特徴を持った文字の形状を一揃いでデザインしたものです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- テキスト
- テキストとは、純粋に文字のみで構成されるデータのことをいいます。 太字や斜線などの修飾情報や、埋め込まれた画像などの文字以外のデータが表現することはできませんが、テキストのみで構成されたテキストファイルであれば、どのような機種のコンピューターでも共通して利用することができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- HTML
- HTMLとは、Webページを記述するための言語です。"HyperText Markup Language "の略です。"<"と">"にはさまれたさまざまな種類の「タグ」によって、文章の構造や表現方法を指定することができます。
- CS
- CSとはCustomer Satisfactionの略称で「顧客満足度」を意味します。顧客との関係維持、サービスの発展に関するマーケティング戦略に関わる用語です。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- タグ
- タグとは、原義では「モノを分類するために付ける小さな札」のことです。英語の「tag」を意味するものであり、荷札、付箋といった意味を持っています。特にインターネットに関する用語としてのタグは、本文以外の情報を付与するときに用いられます。
- HTML
- HTMLとは、Webページを記述するための言語です。"HyperText Markup Language "の略です。"<"と">"にはさまれたさまざまな種類の「タグ」によって、文章の構造や表現方法を指定することができます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- サイトマップ
- サイトマップとは、ホームページの中にあるページ構成を一目見て分かるようにした、目次のような案内ページのことを指します。ホームページ内にある全てのページへのリンクが一覧になっていることが多いです。はじめて訪問した人でも、どこに何があるのかがすぐに分かるようにすることを目的として作成されます。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- バナー
- バナーとは、ホームページ上で他のホームページを紹介する役割を持つ画像ファイルです。画像にリンクを貼り、クリックするとジャンプできるような仕組みになっています。画像サイズの規定はありませんが、88×31ピクセルや234×60ピクセルが一般的です。また、静止画像だけでなく、アニメーションを用いたバナーもあります。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- OS
- OSとはOperation Systemの略称です。パソコンやスマートフォンで操作した内容をアプリケーションに伝える役目を担っています。パソコン用ではwindowsやMac OS、スマートフォンではiOSやAndroidが有名です。
- Android
- Android OSとはスマートフォン用に開発された基本ソフト(OS)の一種です。米国Google社が中心となり開発されました。
- レイアウト
- レイアウトとは、もともと「配置」や「配列」を指す語です。ここでは、「ホームページレイアウト(ウェブレイアウト)」と呼ばれる、ホームページにおけるレイアウトについて説明します。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- タブレット
- タブレットとは、元々「板状のもの」「銘板」といった意味の単語です。パソコンの分野で単にタブレットといえば、「ペンタブレット」や「タブレット型端末」などの板状のデバイス全般を指します。ここでは主にタブレット型端末について説明していきます。
- インターネット
- インターネットとは、通信プロトコル(規約、手順)TCP/IPを用いて、全世界のネットワークを相互につなぎ、世界中の無数のコンピュータが接続した巨大なコンピュータネットワークです。インターネットの起源は、米国防総省が始めた分散型コンピュータネットワークの研究プロジェクトARPAnetです。現在、インターネット上で様々なサービスが利用できます。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- PV
- ページビューとは、ホームページにおいて閲覧者が実際に見たページのページ数を言います。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- リンク
- リンクとは、インターネット上では、あるページの中に記された、他のページの所在を表す情報のことを「ハイパーリンク」と呼び、これを略した言葉です。リンクのある場所をクリックすると、他のページにジャンプするようになっています。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- データベース
- データベースとは、複数のアプリケーションまたはユーザーによって共有されるデータの集合体のことです。特定のテーマに沿ったデータを集めて管理され、検索や抽出が簡単にできるようになっているものを指します。
- クローラー
- クローラーとは、検索エンジンへのインデックス作業のために、インターネット上に存在する様々なページの情報を集めデータベースに登録するプログラムのことです。クローラーが動くことをクローリングといいます。クローラーがページを巡回する際、ページに埋め込まれているリンクを辿って、ページ構造やキーワードなどに関する情報を収集します。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- クローラー
- クローラーとは、検索エンジンへのインデックス作業のために、インターネット上に存在する様々なページの情報を集めデータベースに登録するプログラムのことです。クローラーが動くことをクローリングといいます。クローラーがページを巡回する際、ページに埋め込まれているリンクを辿って、ページ構造やキーワードなどに関する情報を収集します。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- 検索エンジン
- 検索エンジンとは、インターネット上に無数に存在するホームページのデータを集め、ユーザーにそれらを探しやすくしてくれるサービスのことです。「検索サイト」とも呼ばれます。代表的な検索エンジンとしては、Yahoo! JAPANやGoogleなどがあります。また、大手検索エンジンは、スマートフォン向けのアプリも提供しており、これらは「検索アプリ」と呼ばれています。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- クロール
- クロールとは、検索エンジン内のシステムであるクローラ(ロボット)が一つ一つのサイトを巡回し、サイトの情報を収集することを指します。
- Twitterとは140文字以内の短文でコミュニケーションを取り合うコミュニティサービスです。そもそもTwitterとは、「小鳥のさえずり」を意味する単語ですが、同時に「ぺちゃくちゃと喋る」、「口数多く早口で話す」などの意味もあります。この意味のように、Twitterは利用者が思いついたことをたくさん話すことのできるサービスです。
- リスティング広告
- リスティング広告とは、検索エンジンの検索結果ページに、ユーザーが検索したキーワードに関連した広告を、有料で表示するサービスのことです。ユーザーの検索結果に連動した形で広告が表示されるため「キーワード連動型広告」「検索連動型広告」とも呼ばれます。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- Googleとは、世界最大の検索エンジンであるGoogleを展開する米国の企業です。1998年に創業され急激に成長しました。その検索エンジンであるGoogleは、現在日本でも展開していて、日本のYahoo!Japanにも検索結果のデータを提供するなど、検索市場において圧倒的な地位を築いています。
- 検索結果
- 検索結果とは、GoogleやYahoo!などの検索エンジンで検索したときに表示される情報のことです。「Search Engine Result Page」の頭文字から「SERP」と呼ばれることもあります。 検索結果には、検索エンジンの機能に関する情報と、検索キーワードに関連する情報を持つページが表示されます。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- BtoB
- BtoBとは、Business to Businessの略で、企業間での取引のことをいいます。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- WordPress
- WordPressとは、CMS(コンテンツマネジメントシステム)の1種で、ホームページ管理システムのことです。ブログ感覚で記事の修正・追加が行えるうえ、通常のホームページ並みのデザインを作成することができます。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- HTML
- HTMLとは、Webページを記述するための言語です。"HyperText Markup Language "の略です。"<"と">"にはさまれたさまざまな種類の「タグ」によって、文章の構造や表現方法を指定することができます。
- PDCA
- PDCAとは、事業活動などを継続して改善していくためのマネジメントサイクルの一種で、Plan,Do,Check,Actionの頭文字をとったものです。
- フォーム
- フォームとは、もともと「形」「書式」「伝票」などの意味を持つ英単語です。インターネットの分野では、パソコンの操作画面におけるユーザーからの入力を受け付ける部分を指します。企業のホームページでは、入力フォームが設置されていることが多いようです。
- SEO
- SEO(Search Engine Optimization)とは、GoogleやYahoo!などのサーチエンジン(検索エンジン)で、特定キーワードで検索が実行されたとき、ホームページが表示される順位を上げるためのさまざまな施策のことです。
- ホワイトペーパー
- ホワイトペーパーは、もともとは政府や公的機関による年次報告書つまり「白書」を意味しました。しかし近年ではマーケティング用語としても用いられており、特定の技術や商品について売り込む目的で、調査と関連付けて利点や長所をアピールする記載がなされることが特徴です。
- コンテンツ
- コンテンツ(content)とは、日本語に直訳すると「中身」のことです。インターネットでは、ホームページ内の文章や画像、動画や音声などを指します。ホームページがメディアとして重要視されている現在、その内容やクオリティは非常に重要だと言えるでしょう。 なお、かつてはCD-ROMなどのディスクメディアに記録する内容をコンテンツと呼んでいました。
- マーケティング
- マーケティングとは、ビジネスの仕組みや手法を駆使し商品展開や販売戦略などを展開することによって、売上が成立する市場を作ることです。駆使する媒体や技術、仕組みや規則性などと組み合わせて「XXマーケティング」などと使います。たとえば、電話を使った「テレマーケティング」やインターネットを使った「ネットマーケティング」などがあります。また、専門的でマニアックな市場でビジネス展開をしていくことを「ニッチマーケティング」と呼びます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
- クラウドソーシング
- クラウドソーシング(Crowdsourcing)とはcrowd(群衆)とsourcing(業務委託)を組み合わせた造語であり、webサービス上のやり取りで不特定多数の人々に仕事を依頼する新しい雇用形態の一種です。
- ページ
- 印刷物のカタログやパンフレットは、通常複数のページから成り立っています。インターネットのホームページもまったく同じで、テーマや内容ごとにそれぞれの画面が作られています。この画面のことを、インターネットでも「ページ」と呼んでいます。ホームページは、多くの場合、複数ページから成り立っています。
- CMS
- ホームページを作成するための様々な作業を、一元的に管理できるシステムのことをCMS(コンテンツ マネージメント システム)と言います。ホームページを作成するには文章や画像などのコンテンツの作成からHTML、CSSを使った構成・装飾の記述、リンクの設定などが必要ですが、CMSを使用すればこれらの作業を自動的に行なうことができます。
- Webサイト
- Webサイトとは、インターネットの標準的な情報提供システムであるWWW(ワールドワイドウェブ)で公開される、Webページ(インターネット上にある1ページ1ページ)の集まりのことです。
おすすめ記事
関連ツール・サービス
おすすめエントリー
同じカテゴリから記事を探す
カテゴリから記事をさがす
●Webマーケティング手法
- SEO(検索エンジン最適化)
- Web広告・広告効果測定
- SNSマーケティング
- 動画マーケティング
- メールマーケティング
- コンテンツマーケティング
- BtoBマーケティング
- リサーチ・市場調査
- 広報・PR
- アフィリエイト広告・ASP
●ステップ
●ツール・素材
- CMS・サイト制作
- フォーム作成
- LP制作・LPO
- ABテスト・EFO・CRO
- Web接客・チャットボット
- 動画・映像制作
- アクセス解析
- マーケティングオートメーション(MA)
- メールマーケティング
- データ分析・BI
- CRM(顧客管理)
- SFA(商談管理)
- Web会議
- 営業支援
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
- フォント
- 素材サイト
●目的・施策
- Google広告
- Facebook広告
- Twitter広告
- Instagram広告
- LINE運用
- LINE広告
- YouTube運用
- YouTube広告
- TikTok広告
- テレビCM
- サイト制作・サイトリニューアル
- LP制作・LPO
- UI
- UX
- オウンドメディア運営
- 記事制作・ライティング
- コピーライティング
- ホワイトペーパー制作
- デザイン
- セミナー・展示会
- 動画・映像制作
- データ分析・BI
- EC・通販・ネットショップ
- 口コミ分析・ソーシャルリスニング
●課題
●その他